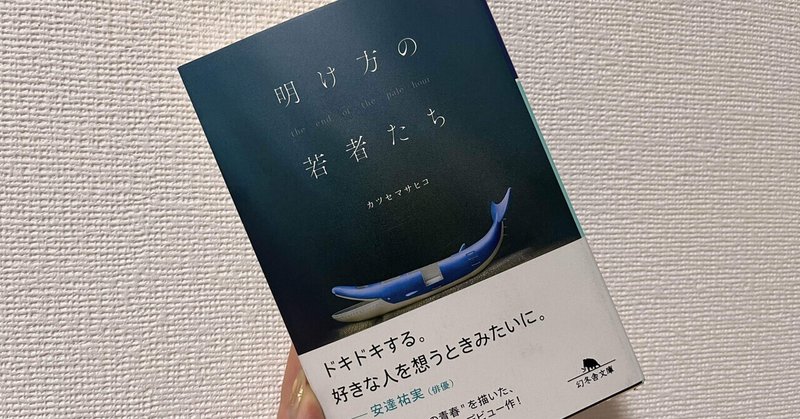
【読書記録】「明け方の若者たち」/カツセマサヒコ
※このnoteは、「明け方の若者たち」のネタバレを含みます。
「恋人と別れて一番つらいのは、相手が次にどんな人と付き合っても、文句を言えないことだよ。現にお前は、あの子の夫に対して何もいう権利がないだろ」
「いや、本人にあったら、言ったとおもうよ。たぶん、殴ってるよ」
「よく言うわ。実際お前は、一歩も家から出ずに大ダメージじゃねえか」
ぐうの音も出なくて、また紅茶に口を付ける。もう甘さに慣れてきている。
「二番目は、相手の好きなものを見つけても、もう伝えられないこと。彼女が好きだったマンガの復刊、彼女と観た映画の続編、全て伝えられなくなる。それが現実」
「それ、キツイ。めっちゃ浮かぶ」
「三番目につらいのは、相手がつらそうなときにも、もう優しい言葉をかけてはいけないこと。フラれた分際のお前が、手を差し伸べていいわけがない」
この本を手に取ったのは、ほんの偶然だった。予定の時間までまだ余裕があったからと本屋に立ち寄って、話題の本の中で一際目を引いた。
物語の始まりは、「勝ち組飲み」。大手に内定が決まった明大生が、俺たちは何かを成し遂げるんだ、すごいんだという根拠のない自信だけを持ってマウントを取るような飲み会をしている。
冒頭から、身につまされる思いだった。
大学4年、春のうちから内定をもらっている子たちは確かに勝ち組だった。私は夏まで内定がもらえなかった負け組なので、その余裕綽々な同級生の顔を嫉妬に狂った顔で見ていた。自分の能力と運の無さを嘆くこともなく、ただ、第一希望の業種からはことごとくお祈りされた。
本書において、「僕」は春に内定をもらった勝ち組であり、入社後に希望の部署に配属されず仕事の意義を見出せないまま働く負け組でもある。一方で、大好きな彼女と同期の親友との時間をキラキラと楽しんでいる。よくいる、サラリーマンの姿にまたちくりと胸が痛んだ。
恋愛と仕事をメインに書き進められる物語は、ドラマチックでもロマンチックでもなく、ただ本当にありそうな日常だ。「僕」と「彼女」の交際には大きな問題が横たわっている。
私がこの物語を読み終わって一番に感じたのは「ああ、きっと私も主人公と同じ道を辿っていたかもしれない」という虚しさと、そうならなかった安堵だった。
好きな人に好きな人がいる。自分は二番目であることを自覚している、そんな感情を私は以前の恋人たちに持たせていたかもしれない。私は「彼女」の側であり「僕」の側にもなり得た存在だ。
物語の中盤で「彼女」が既婚者であることが明かされる。「僕」が1番になれない理由も、それでも「彼女」を愛していたことも、愛されたかったことも、期限付きの恋愛だったことも、離別のあと狂ったことも、全て生々しかった。
昔、彼女がいる人を好きになって、その人の弟を好きな人の代わりにして付き合ったことがある。私の恋愛において、私が一番罪深かった時期だ。奇しくも、この頃の私も就活の真っ最中で、二番目であることを感じとった恋人に狂ったように懸想されていた。
私は既婚者ではなかったし、恋人のことを本当に好きだったかと言われれば「いいえ」と答える。でも「横顔が似ているから」と言った「彼女」に私はきっと何も言えない。それでも、元彼のことは好いてはいた。恋愛感情ではなく愛されることに満足していたに近いし、彼よりも私は私自身が好きだった。まるで、「彼女」だと自嘲しそうになる。
読み進めるほどに、心がぎゅっと締めつけられる。どこにでもある恋だ。きっとそう、どこにでもいる人の、どうにもならない人生の一片で、いっそハッピーエンドだったらいいのにと願わずにいられなかった。
ハッピーエンドで終わらないのも、「僕」がしっかり「彼女」を引きずっているのも、別れてからの「彼女」の気持ちが全く見えないのも、よくある話で。
引き寄せられるように手に取って、出会うべき一冊にあった気がした。今、過去の恋愛を振り返ったばかりの私に、こうなるなよと告げているようだ。
タイミング、悪すぎ。それでも好きな作品だなと、あとがきまで読んでから本棚にそっと刺した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
