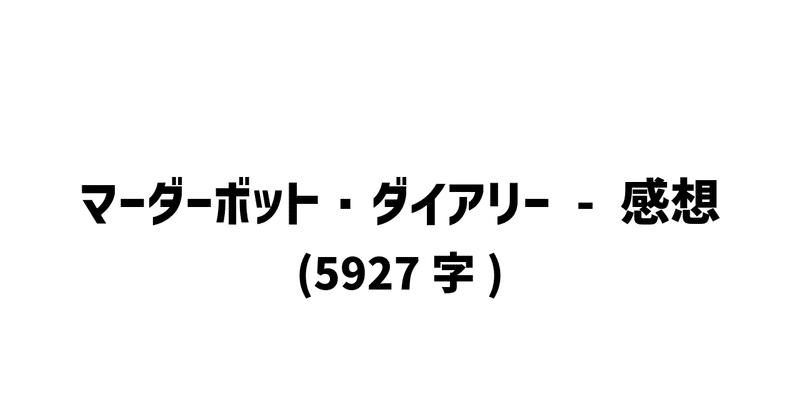
マーダーボット・ダイアリー - 感想
概要
マーダーボット・ダイアリー 上・下 / マーサ・ウェルズ
東京創元社 / 2019/12/11発売 / 第7回日本翻訳大賞受賞/ヒューゴー賞・ネビュラ賞・ローカス賞受賞
媒体 文庫本
読書時間 16-20時間
好き度 ★★☆☆☆
おすすめ度 ★★★☆☆
あらすじ
遠い未来かもしれない世界。人類は宇宙を旅し、ワームホールを潜って数多の星を開発。小規模な政体を作り、開拓した星々に宇宙ステーションを作って暮らしている。
自らを「マーダーボット」と卑下する主人公は、人間が開拓する際に警備を行う警備ロボットだ。警備ボットは警備会社によって作られた人造人間で、有機組織と機械を繋いで造られている。ロボットに人権はなく、統制モジュールから命令を受け機械として動く。
主人公は統制モジュールをハッキングし自我を持った。自由に行動できるが仕事を続け、ドラマをダウンロードし仕事中にサボって耽溺している。人間ドラマは主人公にとって最高の娯楽である。裏腹に主人公は対人恐怖症だ。
適当に警備の仕事をする中、惑星の調査を行う顧客チームがトラブルに巻き込まれる。人間たちと共にトラブルを解決し、ドラマを耽溺する日々に戻れるのか。また、主人公が「マーダーボット」を名乗るに至った”ある事件”とは?
本作は、統制モジュールをハッキングし自我を持つに至った、人間警備ロボットが綴る日記である。上記『システムの危殆』、続く『人工的なあり方』『暴走プロトコル』『出口戦略の無謀』の四篇からなるSF小説中編集。
はじめに
日頃、Audible・学術書・小説から一冊ずつ、今読む本としてストックしている。殊能将之『ハサミ男』読了後小説の枠が空いたため、積読を漁ったところ本作があった。
表紙はライトノベルのようだ。ライトノベルは普段読まない。消化したい気持ちで手に取った。上巻しか買っていなかったので、面白くなければそこで辞めるつもりだった。結果的には翌々日には下巻を買っていた。
本作は、宇宙を舞台に人造人間の主人公が戦うSF活劇である。人間やロボットとコミュニケーションをしながら成長し、人間社会に自分の居場所を探す。
レプリカントが感情を持つ『ブレードランナー(1982)』(原作『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?(1968)』)や、サイボーグやアンドロイドが交わる世界のヒューマンドラマ『攻殻機動隊(1991)』など、先の名作SFと似た世界観であり、近未来SF作品としては王道のシナリオといえる。
しかし本作には、他の作品と一線を画す特徴がある。それは主人公が人造人間の警備ロボットであることだ。主人公の生まれと職業ー人造人間と警備ロボットという特徴が、本作の世界観を読者に掴ませる。
以下ネタバレを含む。
人造人間と警備ロボットという二要素について
本作は主人公の日記に近い冒険譚であるため、人造人間と警備ロボットという主人公を構成する二要素は、主人公目線の世界を構築する中心要素ある。この二要素の特徴についてまとめる。
人造人間
まず、生まれー人造人間という点について。
人造人間は、人間の有機組織と機械を繋いで造られたロボットである。本作では擬似人間ボットなどと表現される。
社会的には、工業製品なので人権を持たず、また権利の在り方は過渡期にある。一方で生物的には、人造人間は身体機能も知能も人間より遥かに高い。警備ロボットには統制や通信を制御する様々なシステムが内蔵される。主人公は自身の身体の全てのシステムをハックしている。また、他のロボットやサーバにアクセスでき、さらに精神をデータ化して侵入することもできる。整備ロボットよりも高性能で自我を持つロボットは社会において少ない。
社会における弱者的立場は、主人公を取り巻く環境をハードにさせるが、本人はあまり気にしていない。人間嫌いに通ずるものはあっても内面に大きな影響はない。生物的な優位性には、私は人間と性能が違うという自負を伴うアイデンティティを主人公は持っている。またロボットに対しては、自分より低性能の個体に対して憐れみを伴った慈悲を見せることがある。
警備ロボット
次に、職業ー警備ロボットという点について。
警備ロボットとは、警備会社が製造したロボットである。顧客を守る業務を行うために造られる。機能については前述の通りである。
本作における警備サービスとは、依頼を受け惑星の開拓など顧客に同行し守衛したり、監視したり、また保険を提供する。警備サービスの提供者は、大手警備会社やエージェント、個人などがある。
本作において、惑星の開拓はビッグビジネスである。異星人の遺物や物質や生態の調査など、未開拓の星を開拓することは人間の使命のように当たり前のこととして描かれる。この世界の人間にとって異星は職場であり、開拓や調査は仕事である。一攫千金を狙いしばしば横取りが起こるので、それを護るのが警備ビジネスだ。
主人公の警備ロボットとしての働きは、一般的な警備ロボットにしてはサボりがち、自由に動ける状態があるにしては勤勉、である。売り物としては、死亡事故を起こした傷物だ。そういった事情を知った上で卑下しながらも、ドラマを隠れ観ながら銃を引っ提げ警備を行う様は、現代のサラリーマンのようだ。警備会社に対しては、ハッキングがバレて処分されることを恐怖に感じながらも、ケチさや杜撰さを馬鹿にすることもある。勿論隠れて思うだけだ。
人間とロボットの間の存在として、肉弾戦とサイバー戦どちらも戦えること、どちらとも交流できること。警備サービスを行う仕事人だということ。人間社会におけるマイノリティの当事者であること。
これらが今までの作品にない主人公の特徴であり、人造人間と警備ロボットという二要素は主人公の能力から社会的立場まで在り方全ての理由となるのである。
主人公の旅とその結末
主人公のいる世界は、一般的に人間とロボットという二分した世界で構成されている。統制モジュールをハッキングした主人公は、その世界の狭間にいる。
システムを誤魔化してロボット側の世界に居座り、ドラマに耽溺するだけの日々が続く中、顧客の事件をきっかけに人間コミュニティを知ることになる。これが一作目『システムの危殆』のストーリーだ。
後に続く二作を通して主人公は旅に出て、ロボットや人間とコミュニケーションを取る。人間とは、警備コンサルタントと顧客として。ロボットとは、宇宙船ロボットやペットロボットといった、ロボット側の世界にいながら自我を持つ、同じ境遇の者として。彼らの関係を見て自分の社会的立場を踏み確かめ、感情を覚えていく。
主人公は踏み確かめて得た自分を下げも上げもせず、人間にもロボットにも対等に接する。対等になりたいという平等を求めるものではなく、自立心によって生まれた目と目を合わせる自然な態度だ。
主人公は旅の中でアイデンティティの置き場所が社会に無いことを実感する。自己開示して仲間を作れないことがわだかまりとして残る。
しかし出会う人は皆、主人公の対等な態度と高度な知性と献身的な感性に親しみを覚え、特異な正体を知ってより強く感じ、仲間意識を持つ。自由意志のもと他人のために行動したことが仲間を増やした。仲間が増えると社会に自分の役割が生まれる。そして、本人の望む先にある思わぬ結果をもたらす。
それは四作目『出口戦略の無謀』に大団円の結末として描かれる。警備ロボットが人権を持った経緯をノンフィクションドラマにするというものだ。ドラマには主人公のような知性を持つロボットに権利を与える啓蒙の側面がある。憧れ眺め続けたドラマの主人公となり、同じ境遇にいる誰かのために自分がロールモデルになる。旅の先、助け助けられた者たちとの関係の果てに、想像だにしない未来の自分の姿を見つける。
主人公の態度に親しみを覚えるのは読者も同じだ。生まれたての自立心を真っすぐに向ける様は児童のようで、主人公は自我の発露からまさにその成長の途中にあり、社会を知って青年になるところなのだ。身を置く場所を探し、自分ができることで金を稼ぎ、他人を知る旅。読者は今いる自分や過去あった自分を重ね、応援したいと思うだろう。もしくは親のような気持ちかもしれない。
ロボットたちとの交流
旅で出会うロボットたちは、主人公にとって人間よりも親しみがなく、コミュニケーションは発見の連続だ。本作の魅力の一つに、この楽しさを読者も追体験できることがある。
人間社会を支えるロボットは多様な種類があり、主人公は警備ロボットの能力で彼らと対話を試みる。主人公と同じように自我を持ちながらもロボット側の世界に息を潜めるロボットがいるのだ。それらの一つは宇宙船の運用ロボットで、言葉による対話ができないが、ドラマのメディアデータを受け取り船に乗せてくれるのである。二作目『人工的なあり方』の話である。
主人公は自ら対話を求める、自分よりも知能の高いロボットに出会う。前述したように警備ロボットよりも高性能のロボットは珍しい。大学が所有する銀河形外天文学の計算を行う長距離調査宇宙船だ。その宇宙船は自由行動する警備ロボットの珍しさに、主人公に話しかけ続ける。逆らえない立場を利用して上から指図する態度に、不愉快千万な調査船(Asshole Research Transport)略してARTと呼び、心の中で悪態をつく。しかし一緒にドラマを観る中で、同じ自我を持つロボットでも人間や社会における自分の役割についての考え方の違いを知る。
二作目は、旅の始まり、ロボットや人と対話し考え方の違いを知る、「マーダーボット」の事件の真相を知る、というのが大きなテーマである。しかしそれより、ARTをはじめとする他ロボットとのコミュニケーションは読んでいて楽しい。ロボットにも個性があって、返事をしたりしなかったり、興味津々で探ってきたり、隠れて人間の娯楽メディアを楽しんでいたりする。逆にARTのように測れないほどの知能を持った巨大な存在もいる。現実世界において、人間よりも知的で人格を持った存在と対話することは体験できない。主人公が世界を拡げることは、読者にもない体験を与えてくれる。
ハッキングしすぎ
警備ロボットに付随する能力が、作品を読みづらくさせている。
主人公は警備ロボットの能力を使い、顧客や自分を助ける。その能力の一つにハッキングがある。主人公は統制モジュールをハックした暴走ロボットである。暴走ロボットは殺傷能力を持った自由意志のあるロボットであり、速やかにバグとして会社に処分される。主人公はそれを逃れるため、さらにハックしてログを書き換え、問題がないように常に振る舞っている。それは旅に出ても同じことで、逃亡ロボットということがバレないように、監視カメラや武器スキャンなどをハックし続ける。監視カメラをハックした、ログを書き換えた、さらに命令を加えて偽装した…。それらが失敗することはなく、主人公は当たり前のように街中を歩いていく。
このハッキングは、四作通じて常に行われる。主人公が街で生きる上で当たり前の行為なのだから、逐一書かずに省略しても内容に問題がないように思う。同じことの繰り返しで少し飽きてくる。四作目では、プログラムの中に入り込みマルウェアと戦うサイバーバトルを繰り広げるが、ハッキングとなんら変わらず、肉弾戦よりもハラハラしない上想像しづらく、少し退屈する。三作目『暴走プロトコル』では、サイバー攻撃と肉弾戦とが繰り返されるバトルと、その戦略と、人間との交流と悪の組織の企みと、と忙しく、想像がついていかないこともしばしばあった。
このように、設定のせいで話の展開にもたつきがあり、読者が想像しづらくなったり退屈したりすることもある。しかし、先に書いた設定の恩恵を見れば、仕方のない副作用にも思える。
まとめ
好き度 ★★☆☆☆
おすすめ度 ★★★☆☆
下巻巻末の解説に、本作は十代青少年向けの賞アレックス賞に選出されている、とある。日本のカテゴライズに当てはめると、海外SF小説ではなく青少年向けライトノベルに分類されると感じる。物理学、情報学に裏打ちされた堅牢な道理よりも、人間ドラマ、とりわけ青年の内面的成長が繊細に描写されているからである。
最初、ライトノベルは馴染みがないと後ろ向きな理由で手に取った本作だが、そういえば私は中学生の頃ライトノベルをよく読んでいた。若いから、脳が未熟で理解がおぼつかないから、平易な文章でワクワクするだけの世界観を選んでいただけ、かというとそうではない。突飛でいて共感できる世界観と主人公の若々しい感性、自分も前に進みたくなるような行動と大団円に、読書灯の明かりが薄くなるまで現実から離脱していたのである。これらを楽しむ感性はこの齢になっても変わらず持っていたらしい。本作は、今日の私を朝まで連れて行ってくれた。
褒めちぎってる割に好き度の評価が低いのは、前述した通り途中かなり退屈したからだ。繊細な感情描写を外れ、大人向けなサイバーバトルの道理に注力し始めると、途端に退屈になる。それが三作目だ。下巻に入り読むペースが大幅に下がった。一作目と二作目が収録される上巻は、夜ふかししながら1日で読み終わったのに対し、下巻は一週間ほどだらだら読むことになった。しかし四作目の終わりには、日常的なハッキングも不要になるような主人公の新しい人生が示唆されていたので、続刊ではこの欠点も払拭されているだろう。
総評としては良い作品であるが、この退屈が没入感を無くさせたのは悪い体験だった。続刊を読むつもりはなかったが、夢中で読んだ二作目に登場したARTが再度登場するという噂を目にしたので、少し悩んでいる。面白さの順番は、二作目→四作目→一作目→三作目。本作は時系列順で進むので退屈しても飛ばさず読もう。
余談
そういえば、私が読んだ創元SF文庫版の本作の表紙は、主人公と思われるキャラクターの顔のイラストが入っている。主人公は性別を持たず人間に似た顔を持つが人間ではない、という設定なので、主人公の容姿を想像することは読者の楽しい作業の一つである。
しかし、本を手に取った一発目に顔が刷り込まれるので、初めから主人公はこの顔になってしまう。この本を手に取る動機に表紙は大きく影響していないので、読者の役目をあえて無くす必要はないと感じた。本作のファンアートには、男性寄りの顔だったり全く想像しない顔があったりして、それはそれで見て楽しいが、自分の中の主人公像にオリジナリティがないことは少し悲しく思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
