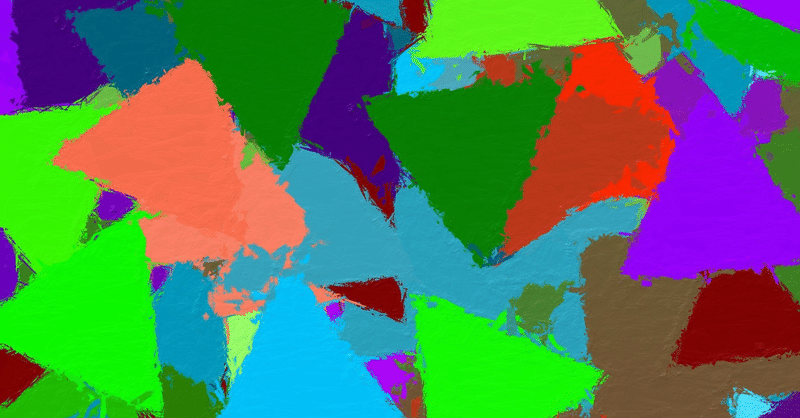
【読書感想】十二国記ひとまとめ
大学入ったとき、周りの友だちがみんな十二国記読んでたのは嬉しいカルチャーショックだったと懐かしく思い出した。歌舞伎と同じで語り口を楽しむ物語なので、ネタバレとか心配せずに語り合いましょう。私は『魔性の子』以外は一通り読みました。ファンタジーとして淡々と読んだ作品もあれば、国際政治、地方行政や民俗学のテキストとして関心深く読んだ作品もあり。一覧にしてまとめておきます。
月の影 影の海
十二国記始まりの物語、少女マンガテイストの強い成長物語。
楽俊ありがとうという感想。
あと身体的に指令の能力を借りて剣を振るううちに、主人公の精神性が変化する側面もあった。
風の海 迷宮の岸
『風の万里 黎明の空』のドンパチ&エモシーンの畳み掛けに比べるとお上品な話である。麒麟の生態にスポットを当てたオープニング。ちょうど『白銀の墟 玄の月』が刊行された頃だったので、「戴国関係の話だけキュレーションしてくれ」と頼むと、忽ちに所持巻を持参してくれた父(NHKアニメに造詣が深い)に感謝。この作品の時点で、十二国記シリーズ全体を貫くテーマが「正統性」とは何か、であると、読めば読むほど感じます。
東の海神 西の滄海
子どもの頃、アニメ版が訳分からなくて観るのをやめた記憶があったが、この歳になってから読むとめちゃめちゃ面白い。
中央集権と地方分権の均衡みたいな話から説き起こしていくのだが、立憲君主制の萌芽として「王の纏う権威は治世の実権と分離が可能ではないか」という思考実験を導入している。このファンタジー世界では仙という不老不死の階級による徳治が前提とされているので、麒麟の「失道の病」という、昏世が革るシステムを内在させることを極めて重要視する。そもそも民主という概念を標榜しながら、民の意思を侮り、それを統治に反映させるプロセスが未発達であるという矛盾を、暗愚の王の退場手続きを「民意を」「代弁する」麒麟という獣に一元化させることで解消させようとしているのである。
そうしたシステム上の不備に、実際に現場で民の意思を目の当たりにする州官たちが切実な問題意識を持つというシナリオになっている。「ここに獣がいる-この獣の不可思議な習性を珍重した先人が、ありがたがって世の理に押し上げた」というセリフは上記のような問題意識を端的に表現しており、お見事。神格"化"という語彙が端的に示すように、権威は他からの眼差しによって成り立つ。麒麟の物語とはつまり「物語」なのであって、この獣は必要に駆られて権威構造における位置取りを与えられたに過ぎないにもかかわらず、やがてそうした始原が忘れられていったのだ、とデファクトに成立している権威構造に疑いを持った時、既成秩序の有識者たちは誰も明確にその疑いに向き合ってくれない。そこに現場サイドが孤独を抱き、対話に絶望することでついには実力行使へと傾斜してしまうのが非常にリアリティがある。
しかし、更夜と六太の関係が、かろうじて対話を成し遂げている。上記のような問題意識に対する六太の回答は、「民主」とはどこまで行ってもフィクションであり、「民意」を悉く拾う万能のシステムは存在しないのだから、事実上合意されて成立したシステムを騙し騙し運用する方が社会的コストは最小となる。「民主」「民意」とは魂のあり方の問題だ、とする趣旨である。もう少し構図化すると「理性の及ぶ範囲で、より良いシステムを追求すべきだ」とするエスタブリッシュ層の斡由と、「神ならぬ人間がつくったシステムである以上、脆弱性を孕み、避けがたく私たちの実存を何らかの形で毀損するものだ」と突き放す、被支配者層の哀しみを知る六太の視点の違いが導入されているということ。
進歩主義者の現代人は斡由を応援したくなるのだが、六太の諦念を等閑視しないのがファンタジーの醍醐味。捨て子によって「崖」に流れ着き、獣に育てられた更夜が、群れからはぐれる孤独を語り、生物個体として弱いが故に群れずにいられない、組織化を避けられない人間の性質を六太に説く。
だからこの物語は、被支配者の論理から抜け出せない六太の成長物語なんだな。「民意」の装置として、麒麟たる自己が存在する、というアンビバレントに彼は悩む訳だが、彼の選んだ王である尚隆も、平気でプロパガンダを使って民意は操作できるものと捉えており、マスとしての命に責任を持つ支配者層の論理を、囚われの身となることで目を逸らさずに見届けることとなる。
で、後半で斡由が実は「謝ったら死ぬ病のインフルエンサー」で更夜が「サロンの崩壊を忖度で留めようとして却って悪化させる信者」だという構図で、エスタブリッシュは前進局面では威勢が良くても、後退局面で凛と在れない浅薄さを描写すると分析される。
それを村上水軍との衝突により滅んだ小松氏の最期にあって、尚隆がノーブレスオブリージュを貫徹したのと対照し、やはり「王の器は違う」という結末へと持っていく。ただし、驪媚の犠牲は、王の地位への信仰と尚隆の人格への傾倒が不分明にみえて、説得力に欠ける。
「言葉ではなく行動で見てくれ」と更夜と約束し、実際にそれを示す。という形で六太が「目を瞑る」ことでクライマックスにする。そうした「行動」の積み重ねこそが500年繁栄する雁国の今に続く動態であると読者は知っているが、麒麟が目の前の命を重視する慈悲と、王が民の幸福の総和を高めようとする功利主義は、そうした時間軸の概念の導入によって両立を図るほかないとも言える。
風の万里 黎明の空
本作だけは4〜5回は読んでて、アニメも何回も見ている、ファンタジーとしては最高傑作だと思う。何回読んでも適切に涙と興奮を供給してくれる名作。あと楽俊ありがとう。
図南の翼
供王珠晶といえばノーブレスオブリージュの生き字引、というかそれを祥瓊と対比する狂言回しとしてのキャラクターで、珠晶の叱咤と楽俊の激励が相まって頑なな祥瓊を溶かしていくのが『風の万里 黎明の空』の数ある見どころのうちの一つでした。
さてその珠晶の人格形成過程に迫る。最初から最後まで黄海の冒険と艱難辛苦を描いた番外編は、胎果の王が蓬莱で訳も分からず誓約を受ける図式(慶)とも、蓬山で昇山を待ち受ける図式(戴)とも違う、報われるとも知れない努力に、人格の尊さを保ちながら取り組んでいく十二国の正攻法に挑んだ場合のやり方を読者に供給してくれる。
「玉座は血で贖うもの」と妖魔の跋扈する黄海で群れを為して「隣の者が犠牲になる間に自分を守ることができる」という論理を身につける。「弱者を守るだけの力を得なければ、包摂の理想を振りかざすことに意味がない」とも。しかしそうした現実を超えて、見捨てられた人々を救いに戻る少女は、なんだかんだ王道ファンタジー少女である。
また、黄朱の頑丘を、自己完結して生きる者のモデルとして描く。危険に満ちた黄海を知識と腕力によって生き延びる強者は「国家による保護など必要ない」と主張する。「王を求めるのは依存である」と。この問いに対する少女の回答は「私は王を求めるのではなく、王になりたいのだ」であると。かっこいいね。
既に利広が指摘するように「王を守り、多数を守るために、少数の犠牲はやむなし」とするのは臣下の論理であると。では王の論理とは?「それでも全ての者の境遇に想像力を馳せ」「例え王がいなくとも臣下が安寧を実現し、またそれを信奉できるシステムを構成しておく」という程の決意が語られる。
「王にだって戸籍がない」ってのもいいね。黄朱にも、騎商にも、王にもなれる。どの未来の可能性も等価だと、十二歳の少女という造形が説得力を持って見える。それでいてやはり王になるのだと、無頼の頑丘すらも図南の翼を幻視して無意識に理解する。いつでも、肇国の曙光に立ち会うのは楽しい。
黄昏の岸 暁の天
十二国記げに国際政治の教材やな!
上巻で凄いのは情実人事で宮中を埋める慶王朝との類似を充分意識しながら戴王朝の急進的な武断改革に対する文官の違和感と不安を丁寧に炙り出していることで、その役割に外様ながら抜擢された女秋官長の花影を当てる。
李斎と花影のダイアログで進展する第二章はシスターフッドとしても良いが、強力なリーダーシップのもと武断新政に革新を期待する民衆に対し、それでも普遍的価値に基づいたシビリアンコントロールを効かせなければならない文官が、その役割ゆえに批判の依り代として見出されがちだという構造に向き合う。
もう一つは泰麒をいとけない幼児ではなく民意の具現として理解する王驍宗の統治指針で、麒麟の体現する価値が普遍であると無前提に信じ、呪術的な要素を内在的に埋め込んだ統治の在り方は、泰麒の内心というアルゴリズムを本人すら言語化して解説できない局面では、正統性の補強に悪利用されかねない。
それってまさに現代のAIを万能視し、AIの託宣を絶対視する”信仰”世界のアナロジーなんだが、6年経って「少年が成長することで」そこのシステム脆弱性が克服され、正統な統治が見出されていく、というセカイ系的な物語の進展はなかなかアツイな。しかも正統性は天や他国の承認ではなく、国民によってのみ付与されると。まだ雌伏の章。
下巻は荒廃した他国に介入する際のロジックが見どころで、"普遍的価値"を押し付けることには謙抑的であるべきという前提で見ると陽子はまだ若い。むしろ延王の「難民流入による自国秩序への影響」といった合理的な視座の方が理解し易いだろう。虚海が防壁となって難民流入を抑制することが延王に積極策を取らせないという地政学と、集団安全保障は国家間の危機に対して適用するもので、内政干渉はその範疇ではないとする理論の方が読者には理解し易いのではないかな。当然少女マンガファンタジーでそんなのは許されないが(笑)「私が倒れた時、他国が助けてくれる先例」というのもよく分かるが、それは国家間の互恵的関係を信奉できるほどに普遍性を確信している自我の決断に過ぎない。
一方で、ここにこそ「故事を引くこと」を責務とする三師のような役職を内在させていることの意義を説明することもできる。覿面の罪を始めとする天の条理については、宗教的権威が与える正統性担保のためのプロトコルを、政治的・社会的要請に応じて法解釈者(ここでは玉葉)が何らかの「理屈が立ってさえいれば」と柔軟に解釈する動態が歴史(たとえばオスマン朝では、社会秩序のデファクトに合わせてコーランのドグマを柔軟に解釈し、兄弟殺しの廃止、利子の設定、非ムスリムの平等などが宗教的権威を乗り越えて認められるようになった)と馴染む。
華胥の幽夢
▷冬栄
泰麒が漣を訪問する話。「見守っている目があるからこそ、できることがある」ってのは皇室っぽくていいね。
▷乗月
初読だが弑逆を選んでも簒奪は望まない芳の月渓の悩む話。桓魋おまえ詩人やんけ。祥瓊の変化に影響されて仮朝を決意する仕掛け。
▷書簡
楽俊と陽子のやりとり。アニメで観たな。
▷華胥
表題作で、才国のエピソードゼロ。「責難は成事にあらず」が多くの読者に訓戒を与える模様。
▷帰山
利広と風漢が柳視察ですれ違い、奏の「世界の保安官」ぶりがややパタナリスティックに描かれている。
丕緒の鳥
厳しい時代にあって職掌に実存を捧げる下級官僚に注目した4短編。そういう話に共感する年齢と時代になってきた。毎年夏になると、戦争モノの、悲惨な民間人の戦争体験がクローズアップされる映像作品が多く発表されますが、必要以上に平和の大切さとか戦争の無意味さを訴えるのではなく、ただ戦争という状況下で最善を尽くす職業人が描かれる作品の方が好ましく感じるのと似ています。(80年たった僕らは、もう少し冷静な視点でアノセンソウを見たがっていると思う。)
刊行時に読んだ時には、他のシリーズ作品との連関を意識していなかったので浅い感想しか持たなかったが、通読するとテーマが見えてくる。『華胥の幽夢』は王たちの物語、『白銀の墟 玄の月』は民セクターの中間団体に目を向けた描写に多くの紙幅を割いていました、と。そう対置すると、『丕緒の鳥』は下級官僚を描く、というのは一本筋が通っていると理解。著者の「民主とは観念ではなく実際の暮らしの情景だ」とする強い関心を感じ取れる。
『青条の蘭』における興慶は、そういう視線を代表している。彼のセリフである「役人、と一絡げにできるほど、役人を知るわけではない」は分かりやすい。「俺たちには俺たちの約束事がある」と背面の広がりを匂わせる猟木師という黄朱は、”木地師”を連想させるが、単に専門技術を取り上げるだけでなく、もう少し秩序との接続を描きたいように見える。
秩序から切り離されたように見える流浪の民が実は、下級官僚という毛細血管を通じて秩序の側に影響を及ぼすとか、王や麒麟の有り様に客観的な視点を導入するといった相互作用への関心というか。『図南の翼』の頑丘や、『白銀の墟 玄の月』の耶利は、そうした立場を代表しているようにも感じられる。
で、まあその全てが連関して「民」という言葉に包摂される、と言ってしまえば陳腐かも知れないが、それを分解して悉皆的に描いて行こうという丹念な作業を繰り返すうち、おそらく誰もが、どこかしら、共感できる箇所を得てファンタジーに鼓舞される体験をするということなのだと思います。
白銀の墟 玄の月
さて貴種流離譚。血統や呪術性による権威ではなく「奇蹟ではない現実的な何か」によって人格そのものへの敬意を勝ち取り、それを権威の淵源とすることが肇国の不安定に対する一つの解答だってヒストリアも言ってたよな。

泰麒がこういう意識を持つに至るのは、能力的制約に基づいたものであるとともに、『魔性の子』で描写されるような(読んでないのですが)身分制から切り離され、人格に対する迫害を受けてきた出自と成長過程を背景とした切実なものとして整合する。またその傍らに、天というフィクションに疑念を持ち、人の繋がりに活路を見出そうという李斎の眼差しがある。
文州の現場視点で民の物質的困窮に接し、「驍宗はどうしているのか」のミステリを捜査する李斎に対し、鴻基に殴り込みに行く泰麒を通して描かれるのは霧がかかったように組織体の一員である自覚を持てず、「阿選はどうしちゃったのか」に戸惑う官吏たちの精神的困惑である。実はこの「前に進んでいる気がしない」停滞感こそが「国が乱れる」ことの徴し(果)であり兆し(因)でもあると、現代日本に引き付けるなら、大きな物語を喪った国家が、まず組織体の足元から分断を始めていき、その過程で縋れるような物語を各員が独善的に編み出し、占有しようとし出す。正統性の奪い合いが、過度に矮小化され、多極化した状況で起こるということ。張運、阿選、琅燦すら親密圏の泡の中に安住しようとするように見えるがどうか。その反射として、傀儡というガジェットは「低賃金で過労死ラインまで働かされ自我による思想哲学を喪失した組織構成員」を想起する。
物語の奪い合いでは、九章で琅燦が天の摂理を読み解こうとする場面、読者は泰麒の思惑を知ったつもりで牽強付会さを面白がっていたら、実は「構造的には正しい」と気づき始める。ただ物語を展開させるために無理筋の解釈を置いているとも見えるのだが、一方で、天の意を人格に擬えて語る中で、泰麒の人格がどのようなアルゴリズムで動いているのかは、李斎や他の随従たちと必ずしも同じとは限らないというヒントでもある。そこまで考えて、「あれ、ここまで泰麒の一人称あったっけ?」と気づく。すげえ筋だ。すぐに項梁もそのことに気づく。
また、あるいは張運のセリフ「本当に麒麟なのか」が表わすように、第四の壁の向こう側に居る登場人物たちにとっては、泰麒のアイデンティフィケーション自体もまた問題視されるという、重層的な構成になっている。
正統性がいくつものフィルターを通して供給されることによるブラックボックスがあって、しかもその個々のフィルターが正統性を損なっていないこともまた証明されなければならない・・・という堂々巡りがすでに萌芽している。
とはいえ、ここで泰麒の思惑がわからないのは読者も同じであると気づかされるのは見事。こうした解釈多様性が物語の外にも開かれていて「どう評価するのは人による」と会話文に入れ込む表現が重なる。例えば「大軍だった」ではなく「多いとも少ないとも言える」と留保する。こうした留保が今作の特徴のような気がする。地の文で決めつけない。解釈を広げるインタラクティブな作品世界の拡がりを企図する。
泰麒の言動から推測できる麒麟の行動原理は「戦う民主政」に近いのかな。ではそこで標榜される普遍的価値は? 一義的には「民の安寧」だが、その判断の根拠は?
功利主義世界に住んでいる私たちはどうしても死傷者数とか貧困率といったKPIに依拠しがちではある。前作、『黄昏の岸 暁の天』でも、他国が介入姿勢をとる基準が一つの議論の対象ではあった。ここで結果として、Wikipediaの「人道的介入」の記事を読むと、国際介入の不作為が国境なき医師団などのNGOを発達させたとあるように、社会的不安定に対して中間団体が果たす役割が大きくなる、という形で「民」セクターが成熟していく。
そうした描写が、李斎視点で執拗になされている。単なる「民の荒廃」を描くためだけの民俗学フリークだと思ってたらちゃんと繋がっています。道観、新農、そして土匪までも、貧困に対抗する中間団体の理論を内包して、アプローチは様々ながら実践に至っている。こうして成熟していく「民」の意を体した麒麟、という絆が繋がれば説得力にはなるだろうか。
後半では、李斎が「天に実体がある」と認識しているのが明言される。自然科学的な観察眼で天のシステムを捉える琅燦を対置しつつ、『黄昏の岸 暁の天』で蓬莱山の深奥を体験した李斎は、社会学的な天のダイナミズムに、それでも「人格によって割り切れない淵源がある」とは、もはや信じていない。王権は神授されるのではなく、神授されるというフィクションを都合よく操る人々がいるだけ、という前提で議論に臨んでいる。と、思ってたら、中間団体としての顔しか見せて来なかった道観が、遂に卓央山への巡礼路にまで捜索を拡げるに至り、信仰団体の顔を顕わして来る。天についての議論を斜に構えていた李斎が、「信じる客体」ではなく「生かす主体」として捉える価値観に触れる。ここは読み飛ばしてしまいそうだが良いシーンだった。
耶利は黄朱(黄海の住人)で、驍宗の呪術性を彩っていた鴻慈が、黄海の植生の根分けという実に合理的な代物に過ぎなかったと明かすシーンに興奮する。次々に呪術性を解体し、同時に解脱していく王と麒麟。ファンタジーが脱構築されていき、歴史のステージが進むのを目の当たりにしている興奮である。よく似ているのは、真田氏が四阿山の歩き巫女と協力してたみたいな、例えば情報収集、毒や薬による生死のコントロールといった「呪術的と他に感覚されるもの」の要因が、「秩序化された空間」の外にある「人・物の機能」で説明されていくことへの興奮であるが、それは逆に言えば合理的なものを「呪術的と感覚する」社会の通念への関心でもある。
そう考えると、魂魄を吸う次蟾は、妖魔というガジェットではあるが、要するに『銃・病原菌・鉄』において描写されるように、西欧のもたらした病原菌が南米の現地文明を滅ぼしたみたいなもので、自然環境因子の持つ「機能」のみを積極的/消極的に社会へと受容していくことで変化が訪れる、その解釈を人間が後付けで行う、という順序を意識しているように見える。
3巻ラストでようやく驍宗視点。「地の底で拾った沙包(おてだま)」は、信仰であり恩義であるものが水の流れに乗って穴蔵の王を回復させる逸話で、呪術性と合理性を接続する。なお古来、穴蔵は回復を象徴する舞台装置なので実はこの展開は王道である。洞窟は再生・復活の聖地として信仰された。その土壌には、①海上から洞を潜って内部へ進入する動態を禊ぎの原型ととることができる、②洞窟の天井から垂れる水滴を「乳の水」として、生命の根源と把握した、③里芋の種芋を穴籠めする習俗、④クマの穴篭もりが翌年の誕生をもたらす、等があるようだ。
墨幟に対する王師の精神的敗北は、土匪を使い捨てるか、助けるか、という点にあった。自らを危機に陥れても民を守るという姿勢を示すことによる正統性が、戴国がずっと探し求めていた問いへの答えだったのかもしれない。それは「餓えぬだけの食糧」や「冬を越せる住居」という中間団体と重なる部門ではなく端的に「安全保障」という恩恵だということ。
しかしクライマックスはそうかぁ…呪術性の超克はやっぱり難しかった。舞台装置が「声が通らない」と断ぜられてるし、獣形の麒麟の視覚的説得力は風の万里で実証済みだもんな。王と麒麟が揃う絵面という段階に、まだ止まらざるを得ない。鴻基に集った群衆は置き去りの客体だったのが残念。
その中で、去思と項梁のダイアログは一つの成果ではあったかな。王の在位が天によって一意に定まるものではなく、顔の見える同輩たちの犠牲や意志を基盤として成立したという体験を経て、生業に注力することがそれだけで国家・国力に同じ地平で繋がっているという自覚を得た民、そういう民が増えていくプロセス。明治維新かよ。
琅燦が自身の設計した社会実験をどのように評価したのかは是非知りたいところ。「化け物だ」という言葉は、泰麒が「麒麟」の埒を超える人格を証明したという新境地への高揚とも、泰麒という「麒麟」の所与の前提を外れる人格に頼ってまで天意が追認されていく落胆とも読める。
これはでも後者っぽくない? 琅燦は後者で、耶利が前者。自分はそれでなんとなく納得した。如何でしょう。しかし江州に琅燦も呼んで、李斎とダイアログして欲しかったな。今回の実験結果で、琅燦も天を有機物とみなし始めただろうし。
解説、だいたい自分と同じような視点で書かれてて頷きながら読んだが、①泰麒が模索した「民と接続した権威」ってのと、②琅燦の社会実験の話だけは消化不良でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
