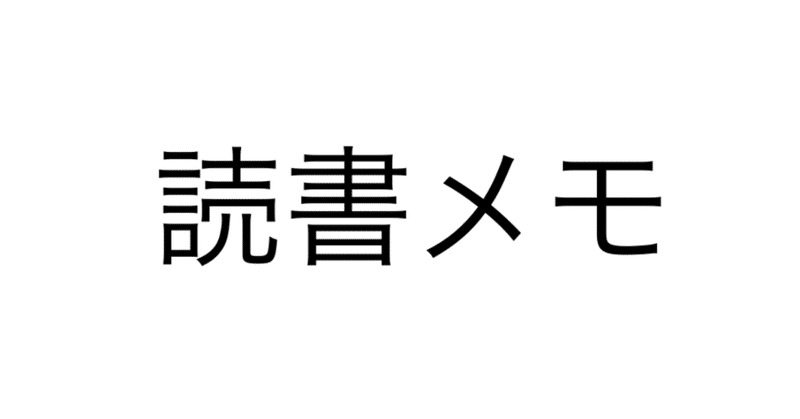
【読書メモ】人口で語る世界史
約10億人から70億人と7倍に増えた直近の200年の人口の変化から世界史を読み解きます。何だかだいぶ時間がかかった。
ざっくりまとめ
・人口増加の原動力は(乳児)死亡率と出生率と移民
・死亡率の低下と出生率の低下と平均寿命が伸びなどが順々に起きていくことで人口転換が起き、人が国から流出し始める。それが世界各所で起きている
・平均寿命が低い国は高齢化問題はないものの安心できる社会とは言えず、平均寿命が高い国は社会的に安定ではあるが高齢化問題に当たる
・移民による人口移動は人種問題や宗教、地政学への影響が大きい
・特殊合計出産率と人口置換水準
メモ
人口と直結するものとしては軍事力と経済力がある。
出生率が低下すると社会全体の平均年齢が上昇する。平均年齢が高い=若年人口が少ない国は裕福な傾向がある(これは今の日本にも言える?)。近代化=出生率低下と平均寿命の伸び=人口転換が起こる。
ある土地で生産される農作物で養える以上に人口が増えると食糧不足となり過剰な人口増加が抑えられる(マルサスの罠)。しかし、輸送機関の発達や公衆衛生環境の向上によって変わってきた。
アメリカが経済大国なのは国民の数が多いから。という理論が通るならば今後中国やインドが経済大国になるのは間違いない。またナイジェリアの人口増加も凄まじく注目しておきたい国でもある。
ドイツの人口増加はイギリスが辿った道(工業化や都市化に加えて高い出生率と急低下する死亡率)と似ていてたがフランスは異なり出生率が低く外国へ移住する人も少なかった。
ロシアの人口増加も19世紀の間に4倍になり、第一次世界大戦が始まる頃には年間1.5%くらいの割合で増加していた(出生率自体は下がり始めていたが、死亡率が下がってきたため相対的に増えていた)。しかし成人男性の平均寿命が1960年代からほとんど変わっていないためヨーロッパのような高齢化の問題はないが、それは決して安心できる社会ではない。
日本は非ヨーロッパ人国家で初めて人口転換を迎えた国。人口転換がヨーロッパやアメリカよりも遅かったにもかかわらず、高齢化のスピードは凄まじい。ロシアと違って平均寿命の高さによって人口減少は遅れているが、社会が老いていっているとも言える。日本は人口減少の先駆者となっているので、世界から注目されている。
実はメキシコからアメリカへの移民よりもアメリカからメキシコへの移民の方が増えている。これはメキシコの経済が成長してきたことと合計特殊出生率が低下したことによる変化。
安価なテクノロジーと私的公的な慈善活動のおかげで人口転換が経済を先回りすることがある(モロッコなどは一人あたりの収入がアメリカの1/5〜1/6であるにもかかわらず平均寿命にほとんど差がない)。
輸送手段の質的技術的向上が人口増加速度を超えればサステナビリティが向上して、人口が減り始めたところから自然が取り戻されてくる。今世紀の終わりまでには人口増加は止まる可能性が高い。
最後まで読んでいただきありがとうございます! いただいたサポートは僕が読みたい書籍代に使います!!
