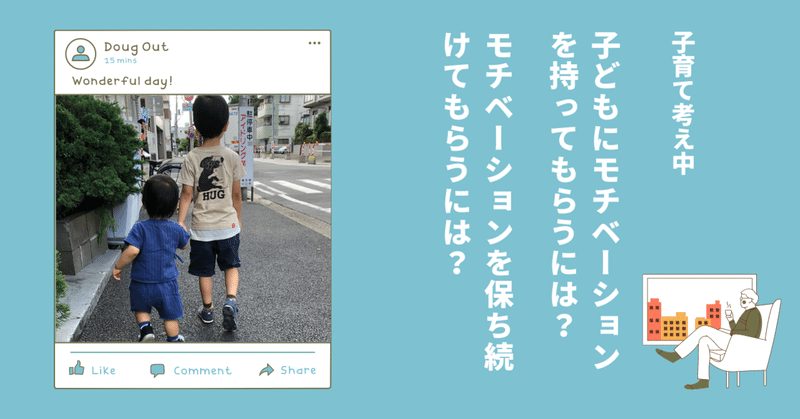
子どもにモチベーションを持ってもらうには?モチベーションを保ち続けてもらうには?
先日、ある教育イベントの講演動画を視聴していた際に、自分の子どもとの向き合い方の方向性を決めさせてくれた言葉に出会いました。
教育とは子どもの内発を促す外発である。
「子どもの『やりたい』『やり続けたい』を促すために、外部からのきっかけを与えることが教育である。(子どもの内なるモチベーションを発生させる仕掛けづくりである)」と私なりに解釈しました。
私自身、二人の子どもを持つ親であり、仕事でも多く後輩たちがいる立場でもあります。これは私のエゴかもしれませんが、子どもたちにも、会社の後輩たちにも、楽しく仕事をしながら、より多くの成長をしてもらいたいと日頃から思っています。
しかし、どのように向き合っていくことが親として、先輩として正しい姿なのかがわからないまま、目の前に対処しなければならない事態がやってきていました。
よりよい教育をしてあげたい。しかし、その方向性が定まらない。そのモヤモヤが、過去に「強引な手法」、時には「感情的な表現」としてあらわれることもありました。
子どもたちや後輩たちのことを思っていた行動でも「これだったらやらない方がマシだった」ということも多くあったように思います。
彼ら・彼女らからすれば本当に迷惑な話です。
「教育とは子どもの内発を促す外発である」という言葉に出会ってから自分がやるべきことや、自らがあるべき態度と冷静に向き合えるようになり少しずつ自らの心にも余裕が生まれてくるようになりました。
今回は、私の頭の整理もかねていますが、同じように悩んでいらっしゃる方の考えるきっかけとなればと思い、まとめてみることにしました。
1.「やりたい」「やり続けたい」を促すための準備
では、子どもたちの内なるモチベーションを促すために外部から与える仕掛けの設計をどのように行っていけば良いのでしょうか。
今回の講演者曰く、まず大前提としての環境を整えてあげる必要があるとおっしゃっていました。
それは、「居場所」と「出番」です。
居場所 = 失敗しても何も不利益を被らない安心した場づくり
出番 = 子どもが主役になる瞬間
失敗することを恐れず取り組み、自らが主役になれる瞬間が多く訪れると自己肯定感を養うことができるようになります。内なるモチベーションを高める際にはこの環境づくりを徹底することが重要であるとのことです。
環境を整えた上でおこなうのが子どもたちが「自分で自分を振り返り改善していく機会(内省)」を促していくことになります。
「やりたい」と思わせるだけでなく「やり続けたい」と思ってもらうためには、「内省を促すための仕掛けづくり」が不可欠です。
最初は、改善のためのちょっとしたヒントを与えたり、振り返りのサポートをしてあげたりということが大事ですが、徐々に手法を学んで一人でできるようになっていきます。
すると、決して楽な作業でなくとも、徐々に子どもたちは探究心を養い、勝手に楽しむようになります。まさに「楽しんどい」状態となるわけです。
この理想系を実現するために、我々は「内省を促すための仕掛けづくり=外発的アプローチ」をより良いものにしなければなりません。
実は、親や教育者も「外発的アプローチ」をより良いものにするために「内省」をおこなう必要があると考えています。
つまり、我々も仕掛けづくりのための探究が必要だということになります。
私が教育の方向性で迷わなくなったのは、日頃から準備をしていけば良いのだと思えるようになったからです。今までは結局いきあたりばったりで子どもたちと向き合っていたのです。
とはいえ、いきなり仕掛けづくりといっても、アプローチ方法はなかなか難しいものです。
現在、私は「内省」やり方についての情報を集めつつ、つい人がやりたくなる仕掛けについての情報を積極的に集めるようにしています。
その中で大変参考になる一冊があったのでご紹介しておきます。
「あの任天堂のゲームはここまで考えられて作られていたのか」と驚くと同時に、仕掛けづくり=課題設定方法の参考になりました。
「ついやってしまう」体験のつくりかた 人を動かす「直感・驚き・物語」のしくみ
2.突然、縄跳びができるようになった息子〜たまには諦める〜
私には小学校一年生の息子がいますが、この記事を執筆している1ヶ月前には「縄跳びができない」という問題に直面していました。
あれこれ指導はしてみているのですが、全く上達しない・・・。
理屈で教えてしまうので、頭で考えてしまい、体が動かなくなり、よりできないという負のループ。
息子もできないのでだんだん練習しなくなり、お手上げ状態でした。
するとその2週間後に急に縄跳びができている息子がいたのです。
どうも小学校で朝の時間に友達と練習して、ちょっと先生にアドバイスをもらってできるようになってきたようです。
「そのアドバイス俺もしたよ・・・。」と思いながら息子の話を聞いていましたが、それと同時に学校という環境の偉大さを感じました。
自分が息子をなんとかしようとしなくても、学校の先生という教育者がいて、友達がいるという環境が解決してくれることもあるのだと肌で感じました。
子どもの内なるモチベーションを高め、維持するための仕掛けづくりへの探究は継続しつつも、親(自分)が100%解決しようとしなくても良いと少し気持ちが楽になりました。
とは言え、授業時数の関係などで学校で解決できない場合もあるのですから
見極めは大事ですね。
「逆上がり」が直近の課題です…。もう学校ではやってくれないらしいので…。
3.モチベーション維持に報酬は危険
親であれば誰でも、子どもが興味ありそうなことを見つけ、夢中になってくれるような状況を作り出そうとしたことがあると思います。ですが、こちらの思った通りにならないことがほとんどです。
だからこそ、手を変え、品を変え、アメやムチを使いながら子どもたちの行動を促そうとします。実はこれは会社の後輩にもやってきたことです。
私がここにあれこれ書かなくとも、すでに内発を促すための工夫をしている人はほとんどだと思います。
実は、この仕掛けづくりにおいて1つだけ気をつけなければならいことがあるようです。
それは、何らかの行動の交換条件として「報酬を与える」という行為です。つまり、アメとムチを使った仕掛けづくりは注意が必要ということです。
報酬を与えることは、一時的なモチベーションを高めるシチュエーションであれば効果を発揮するのですが、継続的に子どもたちに行動を起こさせる手段としてはあまりうまくないようです。
我々はその場限りの教育をしたいわけでないはずです。
エドワード・デシという人が行ったパズルの研究によると、報酬を与えてパズルに取り組ませたグループは、報酬がなくなるとパズルに取り組む時間が少なくなったにもかかわらず、報酬を与えずにパズルを取り組ませ続けたグループは徐々に取り組む時間が長くなっていったと言います。
今まで楽しんで活動していたにも関わらず、「報酬が遊びを仕事にしてしまう」のです。報酬が設定された瞬間に途端にやらされている感が生まれてしまい、活動のモチベーションが失われてしまいます。このような現象、もしくはその逆の現象をトム・ソーヤーのエピソードになぞらえて『ソーヤー効果』というそうです。
言われてみればなんとなく当たり前のように思えますが、自分の行動を振り返ってみると、手っ取り早く子どもたちの行動を促すためにご褒美で釣るという手法をとっていること気がつきました。
例えば、家庭内でありがちなのが、お手伝いをやったら、お小遣いをあげるという仕掛けは要注意です。
また、地味にやりがちなのは「抱っこ」の要求に対して「●●したら抱っこしてあげる」という愛情が報酬になっているパターンです。
自らの成長にも時間はかかりそうなのですが、挫けずに考え続けられるように私も内省し続けながら探究し、子育てを楽しんでいこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
