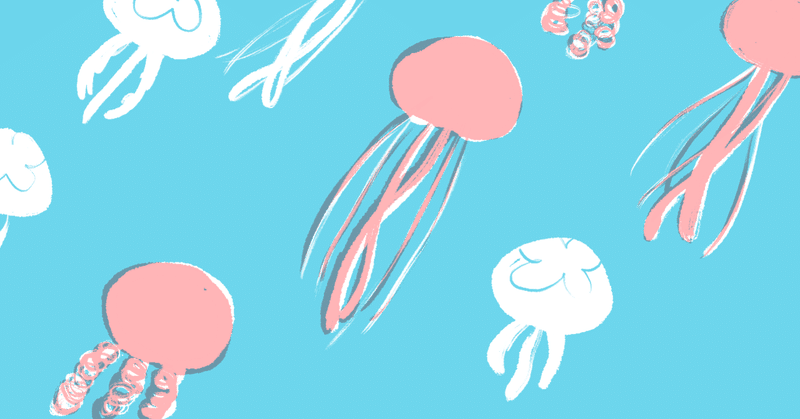
SNS時代の、お酒のブランディング試論#1
日本酒業界に限らず、どこの業界においても入手困難になるような人気の商品もあれば、どうにも売れ行きの遅い商品もあります。
人気・不人気の差の大きい部分は、いわゆるブランド力の有無、ということになると思うのですが、ひとくちにブランドと言っても様々。
エリアでブランディングされる場合(国産和牛、魚沼産コシヒカリ)や、メーカーでブランディングされる場合(PRADA、TOYOTA)も、販売側でブランディングされる場合(TOPVALU、セブンプレミアム)、なんなら購入者によるブランディング(皇室御用達、あの○○さんも愛用!)なんてのもありますね。
こう見てみるとブランド=専門家(権威)によるお墨付き、ハズれない・恥をかかない信用・安心感…ってところでしょうか。
もっと噛み砕いていうと、消費者の皆様の…
「そんな専門的な細かいこと言われてもわからないよ、どれが【良いやつ】なのか、ざくっとまとめて把握させてよ」という思いに応えるお墨付き
さて、先日こんな記事を書きまして…
上の記事の概要はというと、美味しいお酒の選択は、どんな用途なのか、どんな環境で、何を食べながら、どんな人達と…といった試合場とルールで大きく変わる。ムエタイとキックボクサーがロープを張ったリングの上で戦うなら最高に盛り上がるが、実力派柔術家を国技館に呼んで土俵の上で相撲とらせても、かなり厳しいのと似ている…という話。
であれば、多種多様な味の幅に加えて、食との相性、更には季節性まであるお酒のブランドは本来、メーカー型のブランド(他社にない特許がある、デザインが優れている)ではなく、セレクトショップ型のブランド(一定以上の品質基準をバイヤーが保証、情報やアドバイスで誘導)の方がしっくりくると思うのですが、あんまりそうなってない気がします。
でも「だから今の○☓はだめだ」なんて言う気はさらさらないんですよw誤解なきよう。一般の消費者だって、「今この銘柄が熱い!」ってTVや雑誌で読めば飲みたくなるし、卸店も酒屋も飲み屋も、売れる酒置けば売上あがるわ、在庫ぐるぐる回転するわ、劣化させるリスク少ないわ、いいことづくめ。最終的にはビジネスなんで。売れなきゃ潰れちゃう。
では、どうやったら「今この銘柄が熱い!」状態になるのか。酒屋を8年やってて思うんですが、例えば「新酒鑑評会で金賞を取りました」とか「○○セレクションで最高賞を受賞しました」とかの喜ばしいニュースが出ても、それをSNSで拡散したりしても…、売上…あんまり変化ないんですよね(遠い目)
そのくせ「TVのちょっと有名なコメンテーターが、○○(有名銘柄)よりも圧倒的に美味いと言った」とかで入荷が不安定になるくらい売れちゃうw地酒業界はニッチで小さい業界ですから、TVで起きたさざ波は、酒屋にとっては津波になっちゃう。
では、現時点であまり有名でなく、どうやって売れていこうかと日々苦心している中小の酒蔵がブレイクするには、マスメディアに運良く取り上げられるか、お金払って取り上げてもらうか、マスコミの中の人と人的コネクションでも無い限りは、「今この銘柄が熱い!」状態にはならないのか?…といえば、そうでもない気がするんです。(気がするだけですが)
かなり思わせぶりな終わり方になってしまうんですがwまだまだ書くこといっぱいあるのに、もう既にだいぶ長くなってしまったので、次回以降、【SNS時代の、お酒のブランディング試論#2】に引き継ごうと思います。乞うご期待!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
