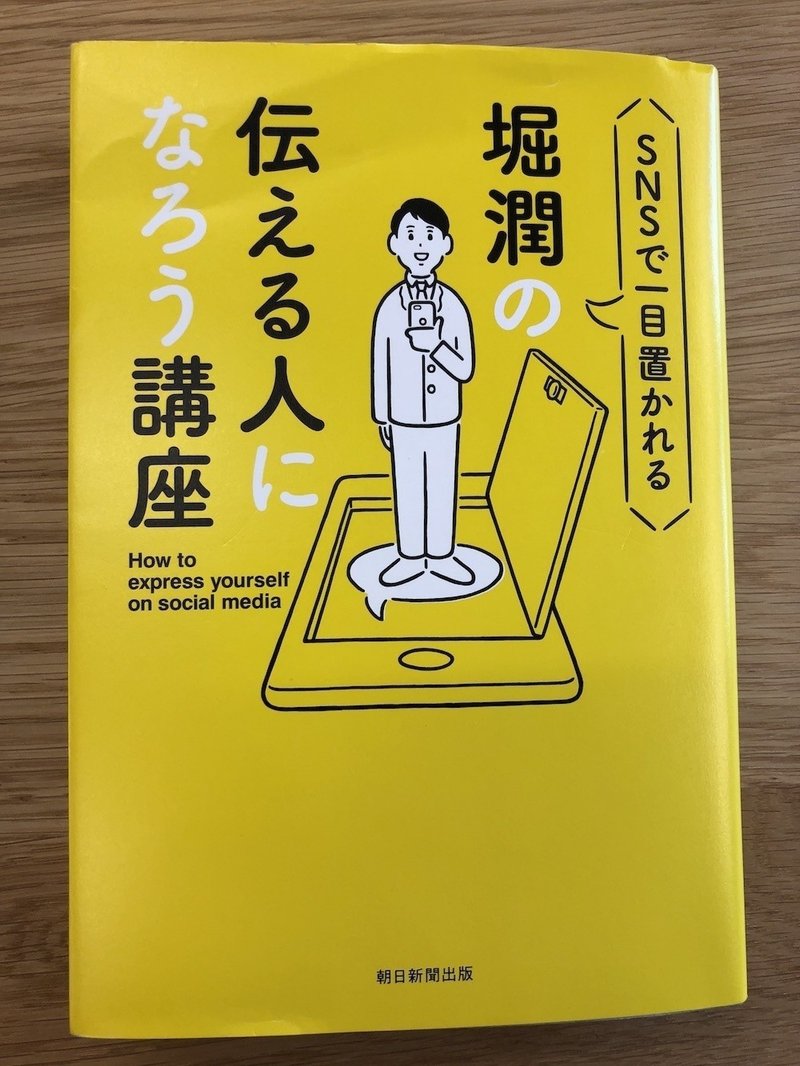「堀潤の伝える人になろう講座 」を読んで。
フリーアナウンサーの堀潤さんが昔から好きなんですけど、この本を読んでなぜ好きなのかがよくわかったような気がしました。
タイトルの通り、「みんなも伝える人になろう!そのやり方を教えるよ」といった内容の本。
様々なメディアの読み方(見方)から、実際に何をどのように発信していけば良いのか、そしてその発信方法は?というところをとても丁寧に説明していて、とてもわかりやすく、読んでいてやる気をもらえる本でした。
堀潤さんを知ったきっかけについて
・私が堀潤さんを知ったのは、多分NHK退職の少し前だったと思います。
(正直その時は知っただけなので特に何も思わなかった)
・堀潤さんをよく見るようになったのは、毎朝東京MXでやっていたモーニングクロス。
・見ていた当時(2014年頃)は家入さんやはあちゅうさん、駒崎さんなど、ネットではよく見るけど実際に動いているところを見たことがない人がたくさん出ていました。
・そういう好奇心から見ていたのだが、番組の面白さと、堀潤さんの司会の丁寧さから毎日見るようになった。
・黒田さんが担当していた「エンタメCROSS」の時だけ自由にやる堀潤さんも面白かった。(黒田さんがしっかりしていたから自由にできたのかと思う)
・長野県松本市に移住してからはめっきり見なくなってしまったが(Mキャスでは見れるが、気楽に見れないと見なくなってしまう不思議)、未だにtwitterとかで内容(#クロス)追っているので、不思議と懐かしい気はそんなにしない番組。
この本についての要約と感想
第1章:メディアをどういう風に見るべきか
・メディアってどういう風に見たら良いのか?に対する説明の章。そもそもメディアなんてものは嘘をはらんでいるものであると行っている。
・なので、様々なソースから情報を得て、自分で考えることが大切。情報を得るということは、どうしても偏ってしまうので、とりあえずは「常に情報を疑う目を持とう」
・情報発信の際は、大きな主語よりも小さな主語が大事
・大きな主語というのは「長野の人は〇〇だよね」「A型だから几帳面だね。」
×「長野県の人達ははうどんよりそばが好きだ」
○「昨日会ったAさんは、うどんよりそばが好きだ」
・堀潤さんが高校生に「中立とは何か?」と問いかけた際に、「中立とは、極論を知って議論を続けることだと思います。」という解答があったらしいですが、この言葉は本当にすごいと思います。
・伝える人になるということは、考え続けることだということを感じました。
第2章:個人のメディアの作り方を例を参考に説明
・熊本地震の時の個人の発信の例や、恵比寿新聞、東京電力福島第一原発の内部告発など、様々な具体的な事例を紹介し、個人のメディアの作り方を説明してくれます。
・「オピニオン」より「ファクト」重視
(オピニオン20%、ファクト80%とのこと)
・これはWeb制作やマーケティングでも大事なんじゃないかなと思いました。ファクト100%よりは、ある程度作り手の思い(オピニオン)があった方がよくなる気がします。。。
第3章:伝えるスキル 基本編
・第2章までを読んで、「よし、発信が大事なのはわかった、でも何を発信すれば良いのやら。。。」と思っている方、たくさんいると思いますが、この本ではこの章以降で具体的にどういったことを発信していけば良いのか、というのをステップごとに紹介しています。
・「step1:テーマ あなたは何の当事者ですか?」では、あなたが発信できそうな情報を見つける作業です。
・知識のある人は、もっと知識がある人を知っているので「私なんかが発信しても役に立たないんじゃ。。。」と思っている方がいると思うのですが、そういった方々には下記のペイジの枌谷 力さんのブログを読んでいただきたいです。
以下引用
例えばAという分野について、10段階でレベル10の人がいるとする。この人が発信する情報は確かにAに関わる人すべてが参考にできるだろう。ではレベル5の人の情報はどうだろうか。レベル6以上の人には役立たないかも知れないが、レベル5未満の人には有益な情報になりえる。ではレベル2の人はどうだろうか。レベル3以上の人には役立たなくとも、レベル2になるまでの方法は教えられる。業界分布がレベル8以上が一握りで、レベル2未満が多くを占める構造なら、多くの人から喜ばれるだろう。
私はこのブログを読んでから、積極的に情報発信をするようになりました。すべてのレベル2の人々に向けて書いているつもりで。
・なので、どんどん好きなものを見つけて情報発信することが重要だと思います。
・そして、ここでももちろんファクト重視!好きなものだとオピニオンをどうしても書いてしまいがちですが、なるべくファクト80%で書くように心がけると良いと思います。
・「step2:ゴール 何のためにそれを伝えるか」では、「伝えることで何を達成したいか」というゴール設定をします。
・そのゴールを達成するためには「取材」「分析」「発信」「行動」「再分析」が必要。何度も粘り強くこの5つを行っていくことが大事。
・「step3:対象 あなたは誰に伝えますか?」では、誰に伝えるか、というところの想像力を働かせます。伝える相手を想像しながら、書く。ここでも小さい主語に向けて書くのが良いかもしれません。
・「松本市のみんな」ではなく「長野県松本市に移住しようと思っているけどなかなか決断できない、東京の中野区に住んでいる30際独身の田中さん」みたいな。
・文章を書くときには起承転結の「転」が実はめっちゃ重要。「転」することで、話に躍動感が出る。
第4章:伝えるスキル 応用編
・「情報は動画で伝えるのがおすすめ」とのことで、第4章の応用編ではまず最初に動画で伝える方法を説明しています。
・P.146〜186で動画の撮影方法を説明してくれているのですが、これから動画撮りたい方必見だと思います。
・P.187〜201では、文章で伝える方法、伝わりやすい文章の書き方を説明しています。私のように文章を書くのが苦手な人は必見。実際に文章の例を出して、どうしたらもっと良くなるか説明してくれます。タイトルのつけ方もヤフトピの例を挙げて説明してくれるのでわかりやすい。
・P199〜は情報を売り込む方法、SNSの利用方法の説明。どのSNSで発信するのが良いか、どのブログサービスを使うのが良いか、迷っている方は参考になると思います。
第5章:メディアの多様性が社会を豊かにする
・5章では堀潤さんがどうしてここまで情報発信を続けてこれたのか、理由を説明してくれています。
・また、情報発信をしていると、どうしても反対意見や批判も出てきてしまいます。その時の対処法が目からウロコだったのですが、反対意見を「批判」ではなく「新しい発見」とみるそうです。反対意見は一見イラッとする要素だったりしますが、確かに落ち着いて向き合うと結構大事だったりしますので、今後取り入れたいなと思いました。
(もちろんヘイト等は論外だけども)
思ったことなど
・普段から発信しておくことが大事。信頼性が上がるかなと思います。
・私も松本市の方々にインタビューをしたりするのですが、その際は小さい主語(例えば、松本市の〇〇町で喫茶店を営むAさん)を重要にしていきたいです。
・挿絵のイラストがかわいい

山内 庸資さんというイラストレーターの方のようです。
本で紹介されていたサイト
最後に
今は個の時代と言われているし、何かしら発信していきたい、でも何をしたら良いかわからないという方にとってこの本は、背中をグッと押すというよりは、そっと肩に手を置いて寄り添ってくれるものになると思います。
おすすめです。
読んでいただきありがとうございます。