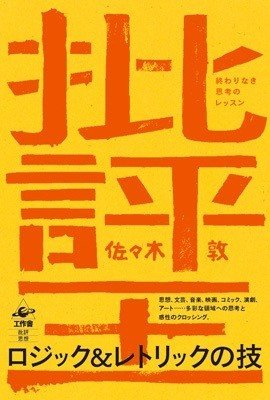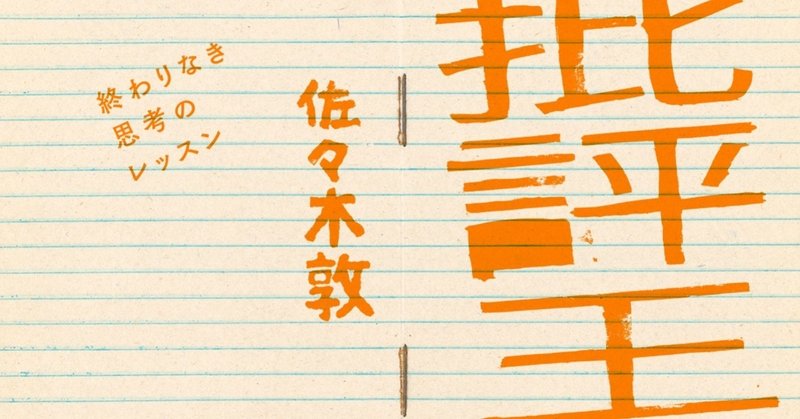
佐々木敦さんが語る:第3回 反射神経で書く
2020年8月26日発売予定の『批評王——終わりなき思考のレッスン』を刊行を記念して、著者・佐々木敦さんへのロングインタビューを連載形式でお送りします。(第2回はこちら)
■章立ての妙
『批評王』では、まず収録したい原稿をすべて石原さんに預けました。膨大な量なので、章立てをして構成を考えてみようという話になりました。アンソロジー本の場合、ジャンル別に章立てするのか、年代順に並べるのか、そのどちらかの方針になることが多いと思うんです。でも、どちらも違うだろうとふたりの意見が一致したものの、僕の大学での仕事などが忙しくなって、そのままいったん止まってしまったんですね。
だいぶ経ってから、石原さんから原稿を厳選して、批評のスタイルに則してグループ分けした章立ての提案がありました。そのときに、人から見るとこの文章とあの文章は同じグループになるんだ、という気づきがありましたが、コンセプトが硬い印象だったんです。その後グループ分けの試行錯誤を繰り返し、テクストもいくつか入れ替えました。まずは構成をつくらないと本づくりはスタートしないので、自分でもここはがんばらないと、と力を込めてやりました。
新聞書評を収録した第6章「批評の反射神経」以外は、最終的に5つの章に落ち着きました。原稿をほぼ同じぐらいの量にして5つの章に分けること、そして各章であまりジャンルが偏らないようにすることなどを心がけました。この本は、とにかくジャンルも時間軸もバラバラな本にする、でも、バラバラだけれども批評の様態というカテゴライズで分かれている本にする、というコンセンサスが石原さんとの間にできていました。
各章の大まかなコンセプトはありましたが、「批評の絶体絶命」「批評の丁々発止」などの章タイトルが最初からあったわけではありません。
通常は収録されているテクストの内容から章タイトルが決まっていくものですが、これが難しかった。テクストのグループ分けや並びの順番はおおよそ決まったものの、ここから読者にわかりやすい「くくり」をどう提示すればよいのか。そこで、いわばキャッチフレーズのようなテイストの章タイトルを考えてみることにしました。

■「批評の絶体絶命」が思いつくと……
寝ているときに頭の中でつらつら考えていて、ふと「批評の絶体絶命」というフレーズが思い浮かんだんです。僕は過去十年ほど、批評という営み/試みの価値と意義を人に知らせたいと思って色々と活動してきましたが、それはそもそも批評が危機にあるという意識があったからです。自分は批評家を名乗って活動してきたけれど、批評ってけっこう絶体絶命だよな、と。批評家養成ギブスや批評再生塾をやったのも、そういう危機感があったからだと思います。
特に第1章の冒頭には自分の批評のマニフェスト的なテクストを置こうと考えていましたから、「絶体絶命」がふさわしいよな、と。じゃあ他の章も4文字言葉にしたらいいんじゃないかと思い立ち、そこから「丁々発止」「虚々実々」「右往左往」「荒唐無稽」が出てきました。
僕は「レビューを書くときに重要なのは反射神経だ」とずっと言ってきたので、しかも4文字だから、第6章は「批評の反射神経」でいこうと。最初に「絶体絶命」を思いついたら、次々と浮かんできて、シメたと思いました。
それぞれの章のはじめに、その章の解説的な短文を書き下ろしました。4文字言葉を思いついたときに、解説の内容まで考えていたわけではありません。たとえば「批評の絶体絶命」というお題ならどんなことを書こうかと、まさに反射神経でスイスイと書いていったんです。
中身を吟味して考えて考えて書いていく人もいらっしゃると思いますが、僕は基本的に反射神経で書くタイプなんです。たくさん仕事を抱えていた時代が長かったこともありますが、もう一方では、反射神経で書いたものでも、時間をかけて書いたものでも、読む人の反応はあんまり変わらないんだなと思う経験が少なくなかったんですね。それなら、ぱっと思いついて書いたほうがいいんじゃないか、とだんだん考えるようになりました。
本当に今回もすぐに書けてしまった。そういう頭になっているんだと思います。でも思いつきだけでやってるわけではなくて、むしろ書いてないときも四六時中ずっと何かを考えているんです。だが書くとなったら考えたことを書くのではなく考えながら一気呵成に書いてゆく。それが自分には合っていると思っている。

■書くことの身体性
文章を書くという行為の身体性とでも言うんでしょうか。あるお題を出されたときに、どういう答えをすぐさま返せるかという批評家としての身体性。一冊の本になるような長い文章を書き継いでいくときでも、それは重要だと思っています。これも自分ならではの特性のひとつだと思います。『批評王』の初校ゲラでも、ほとんど文意は修正しませんでした。基本的に雑誌の原稿もゲラ段階ではほぼ直しません。書くときにはすでに完成しているんですね。書き直すくらいだったら、もう1本書くよ、という気持ちが強い。書いているときは書いているときで、とにかく早く書き終わりたくて仕方がない(笑)。それが思考と執筆のベクトル感覚というか推進力になっているのだと思います。
長い原稿を書くときも、事前にメモ書きをするとか、ノートをとるとかは僕は全くしない。ある作家や作品に関して8千字とか1万字の文章を書くときには、頭の中に漠然と「自分はこの人についてこんなことを思っているだろうな」というのは頭の中では考えています。というか、考えているときにすでに文章になっているんです。頭の中で考えているより書いたほうが早いから、それでもう書き始めちゃう。
だから僕は書き出しの1行目にこだわっています。1行目と最後の1文はすごく重要だと思っている。1行目さえ思いつけば、あとは流れに任せて書いていって、終わりを綺麗に締められれば良い。書きながら自分が何を考えているのかがわかってくるんです。俺はどうやらここに向かっていくんだなというのが、半分くらい書き進めるとようやくわかってきて、そうすると終わりが見えてくる。そこに至るまでは自分が最終的に何を結論とするのかさえ、わかってないことが多いんです。
でも書きあぐねてそうなっているのでも、行き当たりばったりに出鱈目にやっているのでもなくて、ある確信を持ちながらノリノリで書いているわけですよ。ノリノリで書いているのに五里霧中でもある。ずっとそうやってきました。だからたくさん文章が書けるんです。(第4回に続く)

佐々木 敦(ささき・あつし)
文筆家。1964年、愛知県名古屋市生まれ。ミニシアター勤務を経て、映画・音楽関連媒体への寄稿を開始。1995年、「HEADZ」を立ち上げ、CDリリース、音楽家招聘、コンサート、イベントなどの企画制作、雑誌刊行を手掛ける一方、映画、音楽、文芸、演劇、アート他、諸ジャンルを貫通する批評活動を行う。2001年以降、慶應義塾大学、武蔵野美術大学、東京藝術大学などの非常勤講師を務め、早稲田大学文学学術院客員教授やゲンロン「批評再生塾」主任講師などを歴任。2020年、小説『半睡』を発表。同年、文学ムック『ことばと』編集長に就任。批評関連著作は、『この映画を視ているのは誰か?』(作品社、2019)、『私は小説である』(幻戯書房、2019)、『アートートロジー:「芸術」の同語反復』(フィルムアート社、2019)、『小さな演劇の大きさについて』(Pヴァイン ele-king books、2020)、『これは小説ではない』(新潮社、2020)他多数。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?