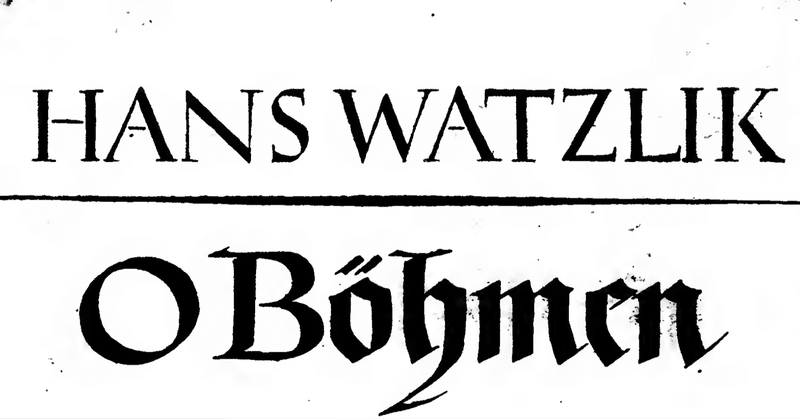
【プラハのドイツ語B級文学 読書ノート】ハンス・ヴァツリク『おぉボヘミア!』
ハンス・ヴァツリク『おぉボヘミア!』
今回紹介するのはハンス・ヴァツリクHans Watzlik (1879-1948)の『おぉボヘミア O Böhmen』(1917)。まずは日本ではほぼ知られていない作家ハンス・ヴァツリークについて簡単に紹介する。
ハンス・ヴァツリク

ヴァツリクは1879年にシュマヴァの森(ボヘミアの森)南東部にあるドルニー・ドヴォジシュチェDolní Dvořistěに生まれる。チェスケー・ブヂェヨヴィツェČeské Budějoviceとプラハで教育学を修める。教師としてシュマヴァの森の北西部にある村を転々とした後、ニールスコNýrskoの男子校で1924年まで教員を務める。
その後はフリーの作家として活動を始める。彼の作品はチェコ人の間でも評価が高く、1931年にはドイツ語作家分野でチェコスロヴァキア功労賞も受賞している。
一方1920年代半ばには、ヴァツリクは反チェコ的作家と見做され始めており、1930年代にはズデーテンドイツ党(チェコスロヴァキア共和国内に多く居住するドイツ人の権利や利益の保護を主張した政党。後に、ナチスがチェコスロヴァキアを分割統治するきっかけを与えた)に入党している。1938年にミュンヘン協定が締結され、ナチスがチェコスロヴァキアを占領すると、ヴァツリクはドイツへ移住し、ナチ党にも入党している。第二次世界大戦中はドイツで非常に評価の高い作家と見做されていたが、戦後は収監され、チェコスロヴァキアから追放される。1948年レーゲンスブルク近郊のトレンメルハウゼンTremmelhausenで死去。
あらすじ
主人公プラインファルクはチロルで地質学を修め、故郷ボヘミアの都プラハで、熱狂的なドイツ民族主義者のマルクヴァルト、田舎からプラハに出てきた苦学生ヴェルフェル、チェコ人の父とドイツ人の母を持つ学生ヴルクという旧友たちと祝杯をあげていた。そこに美しい女性が本を持って近くにやって来る。彼女はカシャという名のヴルクの知り合いで熱狂的なチェコ民族主義者だった。プラインファルクの提案で彼らはカシャを自分たちのテーブルに呼ぶ。するとカシャは彼らの前でチェコ語の詩を朗読しはじめる。彼女はこれを「ニーベルンゲンの唄」より昔に書かれたチェコ語の詩だと信じているが、実際は「クラーロヴェー手稿」という、既に学術的に偽書だと証明された詩だった(※)。マルクヴァルトがカシャに突っかかったために彼らの間に気まずい雰囲気が流れるが、なんとか二人を仲直りさせて会はお開きとなる。
数日後、プラインファルクが街を散歩していると、カシャに出会う。連れ立って歩いていると突然雨が降り出したので、二人は聖ヴィート教会の中で雨宿りする。雨が止むと、二人はフラチャヌィの丘を歩いてゆく。当初はドイツ人のプラインファルクに反抗していたカシャだが、チェコ民族に理解を示すプラインファルクに心を開き、二人の仲は次第に縮まってゆく。 プラインファルクは、ヴェルフェルとマルクヴァルトの三人で居酒屋に行く。居酒屋で飲んでいると、あるチェコ人の男が酔っぱらって騒ぎ出した。驚いたことに、それはヴルクの父だという。ヴルクは父の騒ぎを聞きつけて居酒屋にやって来て、父を家に連れて帰る。チェコ民族主義者の父は、ヴルクがドイツ人アイデンティティを持つことを苦痛に思っており、絶えず問題を引き起こすのだという。 プラインファルクとカシャは逢瀬を重ねるが、カシャは会う度にプラインファルクに対してチェコ民族の偉大さを強調する。ある時、プラインファルクはカシャの家を訪問することになった。プラインファルクは、帰宅したカシャの叔父クラールと言葉を交わして、彼が「クラーロヴェー手稿」の研究に生涯をささげてきた研究者だということを知る。また、プラインファルクは、熱狂的なチェコ民族主義者であるカシャの兄モイミールと激論を交わす。モイミールが去った後、カシャに結婚してドイツ人になってくれるよう望むプラインファルクに、カシャは、ドイツ人になるくらいなら死んだほうがましだと答える。プラインファルクは意気消沈してカシャの家を立ち去る。その帰り道に彼は、あるドイツ人女性が自分の故郷の訛りで喋っているのを耳にして、彼女に愛着を抱く。 以来プラインファルクはカシャを避けて山々に調査に出かけていたが、カシャのことが気になって調査に集中できず、結局カシャに謝ってよりを戻すことになる。
その年の夏、プラインファルクはカシャと共にカシャの故郷の村へ出かける。モイミールが村のネポムツキー教会でフス戦争の英雄ジシュカの骸骨を発見したことで村はお祭り騒ぎになる。カシャたちのチェコ民族主義的言動にずっと目をつぶってきたプラインファルクは、これに耐えかねてひとりプラハに帰り、長らく帰っていなかった自分の故郷へ足を運ぶことにする。故郷へ向かう乗合馬車で、プラインファルクは偶然、カシャとケンカした日の帰り道に見かけた、自分の故郷の訛りで話すドイツ人女性ゲルトラウトと同席する。彼女は弟の葬式のために家に帰るということだった。プラインファルクは彼女を家まで送っていく。
プラインファルクはそこから歩いて祖父の故郷に向かった。その村はもともとはドイツ人が多く住む村だったが、今では完全にチェコ化している。プラインファルクの祖父はその村で最後のドイツ人として葬られた。プラインファルクは、さらにそこから歩いて自分の生まれ故郷に足を延ばした。しかし、驚いたことに村は完全にチェコ化しており、自分が住んでいた家は、チェコ人が経営する宿屋になっていた。プラインファルクは村を離れ、子どもの頃に親しんだ森の中へと向かう。そこで彼は唯一ドイツ語を話す木こりの男性と出会い、家に招待される。家に着いてみると、それはプラインファルクの古い知り合いの女性の一家であることが分かる。彼らはたくさんの子どもを抱えているが、チェコ人に仕事を奪われ、貧しい生活を余儀なくされている。プラインファルクは危機感を覚えると共に、カシャとの関係が心配になり、プラハに戻ることにする。
しかし、プラインファルクはプラハに戻った後もカシャを訪ねるのを長らくためらっていた。ある時彼は、街でカシャの叔父クラールに出会う。クラールは、手稿論争で自分の考えがほとんど支持されなかったことを残念に思いつつも、プラインファルクやドイツ人に好意を示し、珍しいものを見せてやると言って彼を自宅に呼ぶ。なんとクラールは「クラーロヴェー手稿」の原本を手にしていた。プラインファルクが驚いているところにカシャがやって来る。二人の間にはたちまち愛情が燃え上がるが、そこにモイミールが現れ、民族主義的な論争が始まる。カシャがドイツ民族やドイツ語に対して敵対心をむき出しにするのを見て、プラインファルクはカシャの家を立ち去る。
プラインファルクはヴルタヴァ河畔で自殺をも考えたが、かつてプラハ城の聖ヴィート教会を建立したペーテル・パルラーに「生きるとは行動することだ」励まされ、自殺を思いとどまる。さらにプラインファルクは、ゲルトラウトへの思いを自覚しはじめる。
その後プラインファルクは研究に身を捧げていたが、その間にプラハでは、チェコ人とドイツ人の対立が暴力沙汰にまで発展していた。ある日久しぶりに街に出てきたプラインファルクは、混乱の最中にあるプラハでヴェルフェルとヴルクに出会う。暴動に巻き込まれた三人のうちプラインファルクとヴェルフェルはドイツ協会に逃げ込むことに成功するが、ヴルクはチェコ人に反撃を仕掛けたせいで大けがを負う。チェコ人の父を持つことを引け目に感じていた彼は、そうすることで自分のドイツ人性を示そうとしたのである。
その後プラインファルクはボヘミアの森にあるドイツ人の村を訪ね歩く。そしてゲルトラウトの実家に赴き、彼女や彼女の家族と関係を深め、婚約する。自分の故郷にドイツ人教師がやってきたこともあり、プラインファルクは、故郷のドイツ人を守り抜く意思を固める。そこにちょうど、ウィーンでドイツ民族主義者の仲間たちと活動していたマルクヴァルトがボヘミアの森にやってきた。プラインファルクはマルクヴァルトたちと行動を共にする。
森で一週間ほど過ごした頃、彼らの傍をチェコ人の集団が通りかかる。そこに馬車が走ってきて集団に突っ込む。マルクヴァルトは危うく馬車に轢かれそうになったチェコ人の女を助けるが、この女はカシャだった。カシャは結婚し子どももできていた。プラインファルクはカシャから、サラエヴォ事件が起こったことを知らされる。
翌日、プラインファルクはゲルトラウトと結婚式を挙げる。マルクヴァルトが来るべき戦争のことで憂鬱になっていた以外は式は無事に終わる。次の日プラインファルクはゲルトラウトと、自分の故郷に暮らす木こりの一家を訪ねるが、その明くる日に第一次世界大戦が勃発。二人はその日のうちに別荘を発ち、プラインファルクは軍隊に入るためプラハへ、ゲルトラウトは両親のいる故郷へと戻る。
プラインファルクは中尉として、チェコ人が大半を占める部隊に配属され、カルパチアでロシア人と戦うことになる。同じく東部戦線で、マルクヴァルトが中尉として戦死する。戦争は長引き、ゲルトラウトの最後の弟までもが徴兵される。プラインファルクの故郷に暮らす木こりの一家では、戦争中に母親が死んだ。負傷して戦争から帰還した父親はそれを知って精神状態を崩し、精神病院に送られる。ゲルトラウトは残された子どもたちを実家で引き取って育てることにする。しかし、息子たちを失ったゲルトラウトの母は、嘆き悲しんだ末に死ぬ。ヴェルフェルはモンテネグロへ送られ、そこで夢にまで見た憧れの海を始めて見る。しかし彼は、同地で行われた戦闘で戦死する。イゾンツォに送られたプラインファルクは、戦地で、当初怪我で出兵できなかったヴルクに出会い、カシャの兄がロシア軍に降伏した後、ロシアでチェコ人向けの新聞を発行していると聞く。
五月に息子が生まれたという知らせを貰ったプラインファルクは、戦地からボヘミアへ向かう。プラハにはチェコ人によってフス像が建てられていた。しかし故郷に戻ると、ゲルトラウトがプラインファルクの実家を買い戻してそこで暮らしていることが分かった。ドイツ人の司祭もやってきて、村は徐々に再びドイツ化しはじめていた。やはり故郷と人々を引き裂くことはできないのだという胸を熱くするプラインファルクの喜びの言葉で物語は締めくくられる。
※ ボヘミアでは、1817年に、13世紀から14世紀に書かれたと推定される手稿ドゥヴール・クラーロヴェー手稿が、1824年には、8世紀から10世紀に書かれたと推定されるゼレノホルスキー手稿が相次いで発見された。この発見はチェコ文学史を塗り替える大事件として同時代のチェコ民族復興運動に大きな影響をた一方で、その真偽は疑問視されていた。その後様々な研究が行われ、1880年代には同手稿が偽書であることはほぼ通説となっていた。
感想
この作品はまさにB級文学、完全なる駄作だと思う。なぜヴァツリクが1931年にチェコスロヴァキア功労賞を受賞できたのか理解に苦しむ。この作品が発表されたのは1916年だが、既にヴァツリクの思想が反チェコ民族主義とドイツ愛国主義に偏っているのは明らかだ。バイオグラフィーから考えると、その後の著作でバランスが取れたとも考え難い。
主人公のプラインファルクは最初こそチェコ民族を自民族と分け隔てなく見ようとしているが(ただしこの時点でもチェコ人を下に見ている態度が透けて見える)、故郷がチェコ化したのが明らかになってからは、ドイツ人の生活を脅かすチェコ人への大いなる嫌悪感に取りつかれてしまうし、カシャとモイミールも、まるでカルト信者のように頑なで愚かに描かれているように見える。ちょっと極端すぎる。実際にはクラーロヴェー手稿が偽書であると主張した研究者の中にはチェコ人だって含まれていたのだ。一般人だってこれほど頑なに信じ続けていた人は多くないだろう。
なにより展開があまりにご都合主義的だ。プラインファルクがカシャからゲルトラウトに心移りするのも分かりやすすぎる。というか、ゲルトラウトという登場人物があまりに物語にとって都合がいい存在だ。せっかくカシャという異なる民族の女性との恋愛を描き始めたのだから、そこにこだわって彼らなりの出口を見つけてほしかった。
あと、プラインファルクが第一次世界大戦に出兵して翌年五月に帰郷するまで十カ月だが、その間に住民のほとんどがチェコ人だった村がドイツ化し始めているというのは、ちょっと展開が早すぎるのではないだろうか? 住民ってそう簡単に入れ替わるものなのだろうか? 戦争中だから? 小さい村ならそういうものなのか? チェコ人もドイツ人も住む村として残っていくことはできなかったのか?
そして最後のプラインファルクの喜びの言葉の数々は、第一次世界大戦でオーストリアが敗北し、チェコスロヴァキア共和国が独立したことを思うとかなり説得力に欠ける(一応作中にはフス像の建立を暗澹たる思いで見つめる描写も付されているが)。もちろん第一次世界大戦後もチェコスロヴァキア共和国内にドイツ人は多く住み続けたが、彼らの立場はどんどん厳しくなって、結果的にズデーテンドイツ党など新ナチス的政党が発生することになる。また、第二次世界大戦後はチェコスロヴァキアに住んでいたドイツ人の多くは国外に追放された。プラインファルクが喜びの声をあげた30年後には、多くの人々が故郷から暴力的に引き裂かれたのである。
文体は、前に挙げた二人の作家と比べてかなり技巧的。ところどころで詩が引用されていたり、詩的な表現、古風な表現が多く使われている。その点では文体は純文学的な感じがする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
