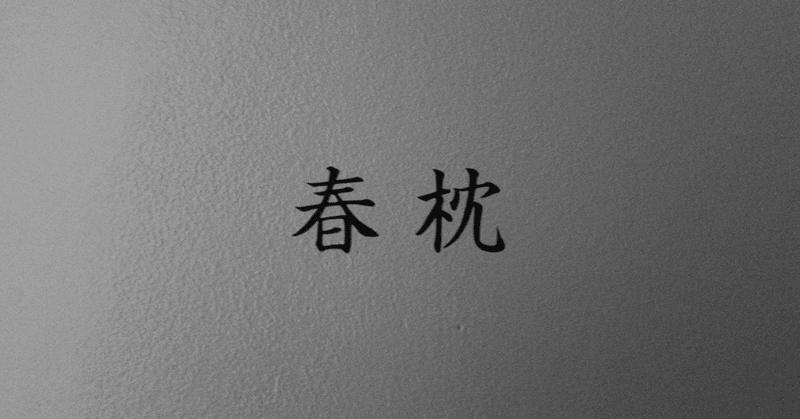
小説「春枕」第一章〜春ごとに花の盛りはありなめど(2)〜
(つづき)
わたしの頭の中で、満開に咲き溢れた桜の木が風に揺られている。
「美咲ちゃん、また会えたね」
桜が歌うようにささやく。
わたしは思わず、声をあげた。
「あ!わたし、この桜を知っているわ。わたしが産まれたばかりの時に、この桜を見たことがある」
わたしが産まれて間も無くしたころ、母の里帰りに吉野へ行った。母はこよなく和歌を愛した人で、満開の桜の木の下でわたしにそっとささやいたのだった。
「『春ごとに花の盛りはありなめど会ひ見むことは命なりけり』ね、美咲ちゃん。
毎年春が来るたびにお花は最盛期を迎えるけれど、それを見ることができるのは命があるからなのよ」
どうやらわたしの脳裏に浮かんだイメージは、桜の使いである春花さんにも見えたらしい。春花さんは、まるで花がほころんだような笑顔で言った。
「美咲さん、わたしも実は、この桜の木に初めて出会ったときに『あ!』って思ったんです。なんだかとても懐かしい感じがして…。
それからというものの、わたしはこの木に仕えているんです。お客さまを癒したいという、桜の木の願いを叶えるために。」
わたしは、産まれたばかりのわたしを抱き上げて、優しく微笑みかけてくれた母のぬくもりを思い出した。
そうだ、そういえば、春花さんはどこか母に似ている。上品で優しくて、それでいて凛とした芯の強さを感じさせるところが。春花さんは続けてこう言った。
「わたしたちは辛く厳しい冬を乗り越えて、ようやく暖かい春を迎えます。満開に咲いた桜を目の前にして『今年も生きて桜が見れたんだなぁ…』と、感慨深く思いますよね。
毎年桜が見られることはちっとも当たり前なんかじゃないんです。桜の命を美しいと感じるわたしたちの命がまた、何よりも尊く、美しいのです。」
母はわたしを抱きしめながら、こうも呟いたのだった。
「美咲ちゃん、産まれてきてくれてありがとう。あなたとこうして桜を見られて幸せよ。どうか来年も元気で生きて、桜が見られますように。ずっとずっと、毎年お祈りするからね」
思わず、涙がこぼれてきた。わたしは紛れもなく、母に愛されていた。そして、この世に生を受けたことをこの桜の木に祝福されていた。
しずかに涙を流すわたしを見つめ、春花さんが優しくささやく。
「わたしはこのお店で、お客さまの人生の節目に立ち会いたいのです。もちろんお祝いごとや、大切な人と過ごす時間にうちのお店を使ってくれてもいい。でも、人生は色々なことがありますよね。突然悲しい出来事がやって来たとしても、うちでゆっくりしてほしい。
わたしは、いえ、この桜の木は、お客さまのすべてを包み込み、癒したいのです。そして、少しでも元気になって帰ってほしい」
わたしは涙を拭った。
「母は花が好きな人でしたが、生前、桜が一番好きだと言っていました。それでわざわざ里帰りして、産まれたばかりのわたしにこの桜の木を見せてくれたのでしょう。
ずっと忘れていたのに、この木はわたしのことを覚えていてくれた。ありがとう。なんだか不思議。母を亡くした痛みがやわらいだ気がします。」
春花さんはいたずらっ子のように笑って、わたしの手のひらに、陶器でできた桜の花びらを一枚握らせた。
「最後に美咲さんに魔法をかけます。きっと、いいことがありますよ」
🌸
わたしはその晩、夢を見た。
あの桜の木が満開に花を咲かせる下でビニールシートを敷いて、母とわたしの2人で春花さんのお茶をいただいている夢だ。
母は微笑んで、わたしにこう言った。
「寂しくなったら、いつでもこの桜の木を思い出して。そうすれば、何度だって会えるから。そして、忘れないで。わたしがあなたを愛していたことを」
「わかったわ、お母さん」
わたしは母の手をギュッと握りしめた。
夢からさめたわたしの手は、母の手の温もりを確かに覚えていた。
「もう、大丈夫。わたしは、愛されている。それだけで、何もかも信じられるような気持ちがするわ」
もうすぐ夜が明けて、朝がやってくる。わたしは部屋の窓を開けて、まるで生まれ変わったような気持ちで大きく呼吸した。
(第一章おわり)
「春ごとに花の盛りはありなめど会ひ見むことは命なりけり」
『古今和歌集』よみ人しらず

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
