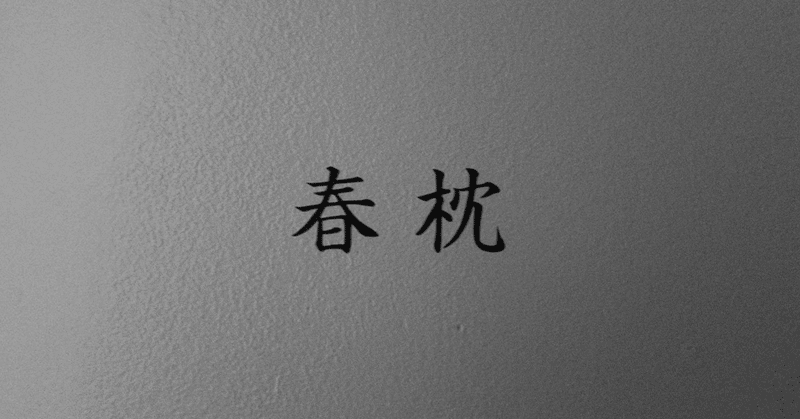
小説「春枕」第四章〜世の中よ道こそなけれ(2)〜
(つづき)
「悲しみや痛みはネガティブなものとして嫌われがちですが、無理やりにポジティブになる必要はない。この歌も、ただ嘆いているだけじゃなく、そんな自分を少し離れたところから見て、その思いをしみじみと味わっているようにわたしには感じられます。
和歌ってね、そういうものなんですよ。歌に、そっと自分の思いを託すんです。そして、歌を読んでくれた別の誰かに、その気持ちを共有するんです。
悲しい痛いと泣いたって、苦しい辛いってもがいてもいいじゃありませんか。そういうものなんですよ、生きるって。
それに、人間はみな孤独な生き物だと知っているからこそ、誰かと悲しみや痛みを分かち合って生きていくことができるのではないかしら。
孤独であっても、決して一人じゃない。」
春花さんはそう言って、桜の木をそっと撫でた。この木が俺を呼んだのだとしたら、いったい何を伝えたかったんだろう。
「この桜の木の机はね、あえて矯正していないんです。だから、日によってしなる。傷もひび割れもそのままにしてあります。人間だって、そう。むしろ、不完全だからこそ、美しいのです。
生きることは確かに苦しい。みんなが弱さや痛みを抱えて生きている。わたしと桜の木は、うちにいらっしゃるお客さまを、丸ごと受け止めたいと願っています。うちに来れば大丈夫、一人じゃない。そう思っていただけるように。
だからこそ、順司さんは桜の木に呼ばれたのだと思いますよ。」
じっと黙る俺を見て、春花さんはそっと絆創膏を手渡した。
「その指のささくれ、痛いでしょう。もう我慢、しなくていいんですよ」
そうだ、俺は手がいくら荒れても、クリームひとつ塗ることすらしなかった。もちろん絆創膏だって。
かつて俺の手を握りしめてくれた女がいた。情の厚い女だった。俺の酒癖と女癖の悪さで泣かせてすぐに逃げられてしまったけれど、やけに温かい手をした女だった。ずっと忘れていたのに、アイツの顔が浮かんでくる。アイツもよく、こんなふうに世話を焼いてくれたっけ。
俺は、自分をかえりみることもなく、人に頼ることもなく、ずっと一人で生きてきた。一生そうやって生きてゆくものだと思ってきた。でも、それはなんて傲慢な思いだったのだろう。
ほんとうの俺は、ずっと寂しかった。痛みや弱さを吐き出して受け止めてくれる人が欲しかった。俺は孤独だった。でも、一人じゃなかった。そのことに、ようやく気がついた。今、目の前にもこんなふうにして優しく手を差し伸べてくれる人がいる。
「春花さん、ありがとな」
情けないことに男泣きする俺の目の前で、春花さんは、優しく言った。
「順司さんにお出ししたお茶はね、ゲンノショウコと言います。自分の弱さや痛みを受け止められる人こそが、ほんとうの強さを持っている。そのことに順司さんが気付いてくださる様に、願いを込めました。
いつでもこの場所に帰ってきてくださいね。わたしと桜の木は、順司さんの居場所になりますから。」
春花さんの慈愛に満ちた微笑みはまるで、夢の中で見た満開の桜の木の化身のように美しかった。
(第四章おわり)
「世の中よ道こそなけれ
思ひ入る山の奥にぞ鹿ぞ鳴くなる」
皇太后宮大夫俊成
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
