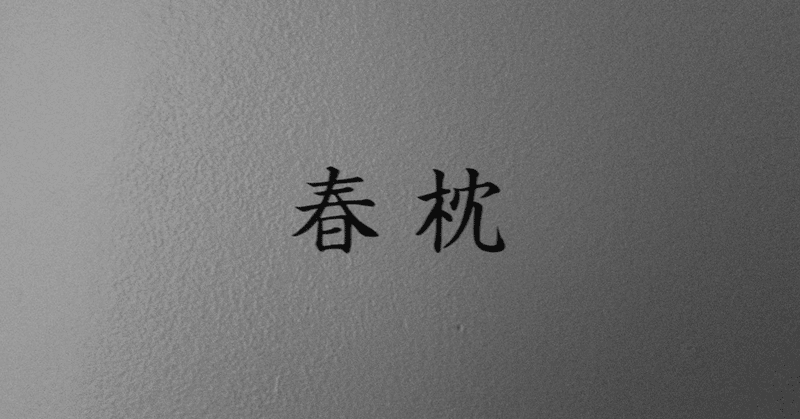
小説「春枕」第一章〜春ごとに花の盛りはありなめど(1)〜
春。
百花繚乱の美しい季節のはじまり。
「あ、さくら」
東京•銀座駅の出口に立ったわたし、二条美咲の目の前に、ひとひらの花びらが舞い降りてきた。
思わず花びらを手を伸ばして受け止めると、それはなんと発光している。
光る花なんて、見たことがない。
あっけにとられていると、花びらはわたしの手のひらを離れ、きらきら輝きながら風に流されていった。
不思議なことに、「こっちへ来て」とまるでわたしを誘うような声がする。
もしかして、これはさくらの声…?
「待って!」
わたしは慌ててさくらを追いかけたのだった。
🌸
不思議なさくらの花びらは、つづらおりの階段を登った上にあるお店の、白い扉の前にはらりと落ちた。
「ここまで来たら、勇気を出すしかないわね」
思い切って扉を開けると、仄暗いお店の中から優しい声がした。
「いらっしゃいませ」
楚々とした美しい女性が、ゆらゆら揺れる蝋燭の灯りに照らされて微笑んでいる。
「ふだんは招待制で知り合いしか来ないお店なんですけれど、お客さまはどうやら桜の精に呼ばれたようですね」と言った。
「たしかに桜の花びらを追いかけてやってきましたが、このお店のどちらに桜の木があるのかしら?」
「こちらですよ、お客さまの目の前にあるこちらの机は、奈良県吉野の山桜の木で出来ているのです。この木は本当に気が強くて、一筋縄ではいかないの。だから人を選ぶのですが、お客さまのことはほうっておけなかったんでしょうね」
そう言って、戸惑う私に彼女は微笑んだ。
「さあ、おかけ下さい。わたしはこの桜の木の使いです。名前は、春花と申します。ご縁があって出会った大切なお客さま。さっそくお茶をお出ししますね」
すすめられるままに白い椅子に腰を下ろす。銀座の街の真ん中とは思えないほど静か。ゆらめく蝋燭の炎を見つめていたら、春花さんが野草で入れたお茶を出してくれた。
「うちは薬草茶でお客様をおもてなしするお店なんですよ。今日は、ドクダミとスギナをブレンドしてみました。どうぞ」
ドクダミもスギナも、厄介な雑草だ。その上ドクダミは、独特のにおいがする。しかし、その2つが合わさったお茶は、意外と苦味はない。そして、森のような香りがする。なんて、爽やかな風味。
わたしはひと息ついた。ほんとうに久しぶりに、こんな風に深く呼吸した気がする。まるで、森の中にいるようだ。桜の木の机をそうっと撫でてみると、そのぬくもりが伝わってくる。なんだか気持ちを吐き出したくなって、思わず言ってしまう。
「実は、大好きだった母が亡くなってしまって…。もういっそのこと、後を追って死んでしまいたいと、何度も思うんです。
こんなに辛い思いをするのなら、何にも感じなくなってしまえればいいのに…心なんてなくなってしまえばいいのに…。」
春花さんはじっと黙って、桜の木の机を愛おしそうに撫でて言った。
「この桜は、樹齢100年か120年といわれています。それこそ、良いことも目をそらしたくなることも見続けてきたのでしょうね。
桜を見上げる人びとが、笑ったり泣いたりしながら懸命に生きて、そして死んでゆくさまをじっと見守ってきた。桜の木からしたらちっぽけに思えるような、わたしたち人間の生涯を、まるで愛おしむように。
桜の花にできることは、春が来たら美しい花を咲かせることだけ。ほんのわずかでも憂いを忘れて、桜の美しさに魅入られるひと時があれば、人は生きてゆける。どんなに辛いことがあっても、美しいものを見て『美しい』と思えるうちは大丈夫だと思える。それが、人間が持つ命のパワーなのでしょう。そのことをきっと、桜は知っている。
こうして机の形に姿を変えて花を咲かせることがなくなっても、お客さまのことを励ましたくて、桜の精があらわれたのだと思いますよ。」
ふとわたしの脳裏に、一本の桜の木の姿が浮かんできた。
(つづく)
※この物語は、フィクションです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
