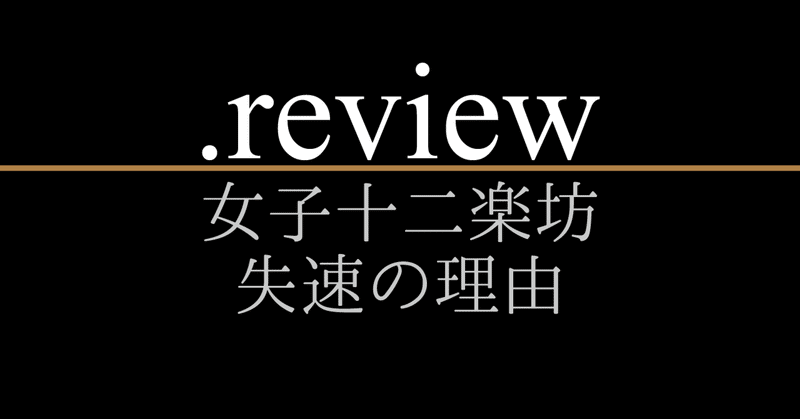
アーティストのプロモーション戦略論2~女子十二楽坊はなぜ失速したのか/おニャン子・ハロプロ・AKB48、そして少女時代 vs. KARAの戦略比較~
「アーティストのプロモーション戦略論2~女子十二楽坊はなぜ失速したのか/おニャン子・ハロプロ・AKB48、そして少女時代 vs. KARAの戦略比較~/松永英明(#co_article031)」は、プロジェクト「.review」に投稿され、2011年1月24日に公開された論考である。
アーティストのプロモーション戦略論2~女子十二楽坊はなぜ失速したのか/おニャン子・ハロプロ・AKB48、そして少女時代 vs. KARAの戦略比較~
2010/11/15 ver. 1.1
本論考は「女子十二楽坊はなぜ売れたのか」の内容に引き続き、アーティストのマーケティング/プロモーション戦略について論ずる。
前回の論考「女子十二楽坊はなぜ売れたのか」は、女子十二楽坊の結成ならびにそのヒットの秘密を探った。メンバーの実力もさることながら、王暁京や塔本一馬らによる優れたマーケティング戦略と骨のあるコンセプトが存在したことが明らかになったと思う。
今回はその論考を踏まえつつ、続編として、それほどの優れた戦略の上でヒットを放った女子十二楽坊が、なぜ売り上げを維持できなかったのかということをテーマとして論じていきたい。特に以下の点について考察する。
(1)コスト面における制約と誤算
(2)複雑な権利関係による活動の制約
(3)ファン囲い込みの遅れ
(4)個別メンバーを売り出さない「アーティスト戦略」の問題点
(5)ライト層向け戦略によるディープファン層の離脱
(6)日本国内でのメディア露出の途絶
これらの条件を踏まえ、最近の事例として韓国の女性アーティストグループ「少女時代」と「KARA」のプロモーション方法の違いの実例を分析する。最後に補記として、現在の女子十二楽坊の動向について簡単に書き添える。
■承前
2003年7月24日、アルバム「女子十二楽坊 Beautiful Energy」で日本デビューした女子十二楽坊。そのヒットの理由について、前回の論考「女子十二楽坊はなぜ売れたのか」では、北京のプロデューサー王暁京(ワン・シャオジン)が生み出したコンセプト、作曲・編曲の梁剣峰(リャオ・ジェンフォン)のアレンジ方法、そして日本でのマーケティングに独特の才能を発揮した塔本一馬という三人のキーパーソンが浮かび上がってきた。
しかし、女子十二楽坊の名前を知らない日本人はいないとはいえ、その勢いは一年も経たないうちに急速に落ちていった感がある。なぜ女子十二楽坊は失速したのか。全国的な知名度をなぜ維持できなかったのか。その原因を、当時の楽坊を取り巻く複雑な環境とともに読み解いていきたい。もちろん、この論考は戦犯探しでもなければ、誰かを批判するためのものでもない。ただ、成功の要素とともに失敗の要素を知ることは、「次」の成功につなげるために必要なことだと考える。
なお、本論考では、前回の論考をお読みであることを前提に論を進めていくことをご了承いただきたい。筆者の立場については前回の論考にも述べたとおり、女子十二楽坊の最大のファンサイト・掲示板「女子十二楽坊資料館」の運営者としてオフィシャルサイドにも協力してきたものであり、運営に関わることはないがその実情を垣間見る立場にはあったことを念頭にお読みいただければ幸いである。
■女子十二楽坊の活動区分年表
ここで改めて、女子十二楽坊の活動時期を区切って、それぞれの時期の特徴を見ていきたいと思う。
○第一期:結成期
2001年5月18日の結成から、日本デビュー以前、すなわち中国での活動を主体としていた時期。この時期の集大成が2003年1月に北京で開かれた「奇跡」というタイトルの単独コンサートといえる(その模様は日本でもライブ盤「奇跡」に収められている)。
○第二期:日本デビュー&ヒット期
2003年7月24日の日本デビューから2004年1月2日武道館コンサート前後まで。ファーストアルバム「Beautiful Energy」ならびにライブ盤「奇跡」、紅白歌合戦への出演など。日本ではプラティア・エンタテインメントがレコード発売権を有していた。
2003.7.24. 女子十二楽坊~Beautiful Energy~(日本オリジナル1st)
2003.11.6. 奇跡(中国ライブ盤)
○第三期:プラティア・エンタテインメント後期
2004年から2005年9月まで、すなわち日本セカンドアルバム「輝煌」、2004全国ツアー、オフィシャルファンクラブ(OFC)結成、「Eastern Energy」での全米デビュー、薬師寺音舞台、サードアルバム「敦煌」、2005全国ツアーまで。
2004.3.3. 輝煌~Shining Energy~(オリジナル2nd)
2004.8.17. Eastern Energy (12 Girls Band、全米デビューアルバム)
2005.1.26. 敦煌~Romantic Energy~(オリジナル3rd)
2005.7.27. 女子十二楽坊~THE BEST OF COVERS~
○第四期:ミューチャー・コミュニケーションズ期
このころプラティア・エンタテインメント社は負債を抱えており、その負債を親会社プラティアが肩代わりすることで独立、2005年9月にミューチャーコミュニケーションズとして再出発することとなった。小女子十二楽坊のデビュー(EMIミュージックジャパン)、2007年7月のミューチャー破産まで。同時にOFCも解散となる。
2005.11.2. Merry Christmas To You
2006.4.12. 女子十二楽坊Best
2006.6.21. 世界名曲劇場~序曲~
2006.11.22. 世界名曲劇場 ~第一幕 中国民謡集~
○第五期:停滞期
2007年半ばから2009年いっぱいぐらいまでの時期。公式ネットファンクラブ(NFC)が新たに結成され、中国での活動中心。日本国内での固定的な所属レコードレーベルはない。
2007.8.22. 上海(EMIミュージック・ジャパンより)
2008.7.30. 四季のソナタ(ユニバーサルミュージック/MILESTONE CROWDSより)
○第六期:新生女子十二楽坊
2010年~。メンバーの大量引き抜き、ソロや新ユニットの誕生、新生女子十二楽坊の活動開始。
2010.10.13. 元女子十二楽坊のメンバー3人によるユニット「Alive2」のアルバム「Alive2 ~Again~」
おそらく、一般的な日本人であれば、女子十二楽坊といえば第二期の記憶しかないかもしれない。ただ、第三期には「僕らの音楽」などへの出演もあり、楽坊を「お茶の間で見る」機会はそこそこあったといえる。しかし、第四期以降についてはまったく知らない人が大多数だろうと思われる。
では、失速の原因は第四期にあるのか。いや、そうではない。オリコン1位や武道館チケット10分で完売などの華々しい成果を上げていた「絶頂期」ともいえる第二期において、すでに「その後」につなげるための準備が整わず、結果として「失速」していった、と私は見る。
■(1)コスト面における制約と誤算
女子十二楽坊は、その成功要因が同時に難問ともなっていた。つまり、「十三名という大所帯」の「中国人アーティスト」によるグループであるということである。これは新鮮さをもたらし、インパクトを与える要因であった一方で、実務的レベルにおいては大きな障害ともなったのである。以下、この前提を踏まえた上で、問題点を記していこう。
◎採算が取れない
一般ニュース報道では「合計いくらを売り上げた」といった表現が多い。もちろん売上高は重要であるが、それ以上に大事なのは「利益がいくらなのか」ということである。いくら売り上げが高くても、経費がそれ以上にかかれば赤字であるし、売り上げが低くても経費が抑えられていれば大もうけかもしれない。
では、女子十二楽坊の「収益」はどうだったのか。
日本ファーストアルバムを合計でダブルミリオン200万枚売り上げ、武道館公演チケットも11分で売り切れ、2004年日本全国ツアーも完売御礼だった女子十二楽坊の「売上高」が大きかったことは言うまでもない。しかし、実際には利益は大きくなかった。
当初、ファーストアルバムの価格は「CD+DVDの2枚組で2980円」であった。低下が低く抑えられた上にDVDつきなのだから、これをお得と言わずして何というかという低価格戦略である。この時点では、アルバムにも収録された代表曲のPVとメンバー自己紹介が入っているだけだった。宣伝費を考えると採算ラインは20万枚。ただ、それは大幅に上回ることができた。
しかし、セカンドアルバム「輝煌」は、ニューアルバムに加えて、武道館公演のDVDが収められた。これが失敗の一因だったと後に塔本一馬自身が振り返っている。2007年7月25日付夕刊フジの記事「破産した女子十二楽坊仕掛人が内情激白「経営者失格」」での塔本発言を引用しよう。
「武道館公演を全部収録してニーキュッパ(2980円)で売り出した。よく売れました。ところが、著作権料の読みを間違った。CD、DVDそれぞれに支払うと16%にもなった。こんなの日本だけですよ。50万枚売っても製作費などで赤字になっちゃった」
CDだけで15曲、さらに武道館公演は13曲。重複は「リバーダンスよりリール・アラウンド・ザ・サン」のみなので合計27曲となる。「読売ADリポート ojo」の2004年4月の記事によれば、このセカンドアルバムの採算ラインは40万部に跳ね上がっていた。ファーストアルバムの利益分はすっかり飛んでしまったのである。
さらに、コンサートでは赤字だった。「コンサートは満杯で、どこもソールドアウト。でも舞台に金を掛けすぎて、いつも赤字だった。クオリティーを下げたくなかった。愛情があるからね。夢を追いかけすぎたのかな…」(夕刊フジ記事より)という状況だった。
◎人数の多さと「アゴ・アシ・マクラ」
女子十二楽坊のメンバーは13人。この人数の多さはステージの華やかさを生む効果がある一方で、単純に経費をふくれあがらせることとなる。いわゆる「アゴ・アシ・マクラ」代、すなわち食費・交通費・宿泊費が膨大なものとなるのである。単純計算でソロシンガーの13倍(少なくとも食費・交通費は単純増)。3人組のPerfumeと比べても4倍になる計算だ。
実際にはコンサートツアーには北京スターディスクの王暁京社長、孫毅剛副社長も同行することが多く(作曲編曲の梁剣峰が同行することもあった)、それだけで15~16名の大所帯である。それが海を越えてやってくるのである。北京・成田間だけでも大きな費用が発生する。さらに、会場間の移動も大きな負担となってのしかかる。
2009年に新生EXILEが14名ユニットとして誕生したとき、他人事ながら真っ先に心配になったのは「アゴ・アシ・マクラ」が倍増するということだった。もちろん、事務所側としてはそのデメリットよりも、14名に増えることでその分ファン層を広げることが目的だろうと思われるが、かかる経費は大きかったはずだ。
AKB48ともなれば「女子十二楽坊」の4倍以上ということになるが、実際の運用上、意外と経費は抑えられているように見受けられる。AKBの公演は普段、秋葉原のAKB48劇場という固定された劇場で開催されているので、そこに移動費は発生しない。
例外的な場合、たとえば2010年の全国ツアーを調べてみたところ、6都市15公演をチームA・K・Bの3チームで分担している(広島・仙台はチームAのみ、福岡・北海道はチームKのみ、大阪はAとB、名古屋はKとB)。つまり、48人×15箇所を回るのではなく、実際の移動総数はかなり小さく抑える工夫がなされているのである。
AKB48は海外公演でも1チーム16人前後のみが渡航している。2007年9月北京公演はチームBの16名。2009年7月パリ公演は例外的に多く、AKBから19人、SKEから3人の合計22人(それでも48人の半分以下)が渡航したが、現地で16歳未満のメンバー6人が出演できないことが判明し、結果的に出演は16名となった。同年9月ニューヨーク公演は16名、同年10月カンヌ公演は12名。2010年7月のロサンゼルス公演も16名の選抜メンバーである。
AKBでも、さすがに48人が揃って海外公演のために渡航した例はない。実質的に十数名くらいが限界ということであろう。
大人数グループでは、このように移動の問題は非常に大きい。しかも、国内での移動だけではなく、中国から海を渡ってくる女子十二楽坊の場合、アゴ・アシ・マクラ代に加えて事前にビザを申請せねばならないという、大きな負担がのしかかることとなった。
このように、本来収益が望めるはずのCDでも2作目以降の意外な費用発生と売れ行きの伸び悩みがあり、移動の問題などを含めてコンサートでも利益が上げられなかったという実情があった。つまり、売上高は高いが収益は低かったのである。
■(2)複雑な権利関係による活動の制約
◎マネージメントの複雑な関係
日本のアーティストの場合、一般的には「所属事務所」と「レコード会社」の役割が分かれているのが普通である。ここに、コンサート制作を行なう「イベントプロモーター」などが関わってくる。アーティスト・マネージメントやファンクラブの運営などは多くの場合が所属事務所のやることであり、レコード会社はCDの発売のみ、イベントプロモーターは(たいていの場合所属事務所と組んで)コンサートを運営する。
たとえば、中川翔子の場合、所属事務所はワタナベエンターテインメントで、ファンクラブ「ギザピンク」の運営も同社である。CDはSony Musicから出ており、 コンサートはワタナベエンターテインメントがDISK GARAGEと連携している。Perfumeの場合であれば、所属事務所はアミューズ、CDレーベルは徳間ジャパン、ワンマンのコンサートはホットスタッフ・プロモーションが制作する。エイベックスのようにレコード会社が事務所を兼ねる例もあるがそれは例外で、基本的にはこの三つの役割で分担されている。
しかし、女子十二楽坊の場合は変則的なスタイルとなっていた。
まず、そもそもの所属事務所は王暁京率いる北京スターディスクである。すべてはスターディスクとの契約にもとづいて運営される。
しかし、日本でのCD制作・発売ならびにコンサート開催の権利を契約したのが、塔本一馬率いるプラティア・エンタテインメント(後にミューチャー・コミュニケーションズ)であった。プラティア・エンタテインメントは、通常のレコード会社としてだけではなく、日本におけるマネージメント部分も担当することとなった。そのため、通常は所属事務所が担当するコンサート企画も国内分については同社が担当することとなった。
つまり、日本国内では、エイベックスと同様にレコード会社が事務所も兼ねているという状態に近い。しかし、エイベックスと違うのは「日本国内での権利のみ」しか持たないというところであった。日本(ならびにアメリカ・ヨーロッパ)を除く他の地域、たとえば中国国内や台湾、東南アジアでの活動について、プラティアは一切権利を持っていなかった。
さらに、北京スターディスクの日本の代理店として創設されたのが、シンホァーミュージック(世紀星華文化公司)であった。音楽プロデューサーでかつておニャン子クラブにも関わっていた稲葉瀧文社長、ファーストアルバムの音楽ディレクター本多計廣がその中心メンバーである。「女子十二楽坊」と扇型のマークの日本における登録商標はシンホァーミュージックが有していた(現在はPROMAXに権利移行)。女子十二楽坊グッズの販売権もこのシンホァーに所属していた。
コンサートに関してはPROMAXが担当であったが、企画・制作にプラティア・エンタテインメントが大きく関わっていた。
レコード会社がアーティスト・マネージメントの部分も兼ねることには、メリットとデメリットがある。楽坊の場合は日本での宣伝方法を日本人の敏腕仕掛け人に任せきるという意味ではプラスに働いたが、一方で手が回りきらない部分が出たこと、また日本国内でのやり方についてプラティア・エンタテインメントが全権を握り、日本国外での全権を握るスターディスク/シンホァーとの間で必ずしも情報が共有されない場面があるなどの問題が存在した。
たとえばこんなことがあった。私のウェブサイト「女子十二楽坊資料館」は非公式で勝手にやっていたもので、当初プラティア側からはあまり快く思われていなかったようだ。しかし、中国で報道があったりするとさっさと訳して載せたりするので、やがて「プラティア関係者が資料館サイトで最新情報を手に入れ、サイトを印刷したものを会議で使う」という逆転現象が起こるようになった。裏を返せば、北京サイドが中国メディアに発表する内容が東京にきちんと伝わっていなかったということでもある。
また、こういう経験もある。某CD店での店頭プロモーションに楽坊メンバーが実際に訪れることになり、北京の王社長からシンホァーミュージック経由で「それを資料館サイト内掲示板で告知してほしい」と要請されたことがあった。ところが、直接そのCD店とやりとりをしていたプラティア側では一般告知はしない約束になっていたらしく、プラティアの方からすぐに取り下げるように依頼があった。
実質上、北京と東京に二つの所属事務所があり、必ずしも情報共有されていない状況があり、それによってスムーズな運営や意思統一が行なわれない場面は多々あったように思われる。
■(3)ファン囲い込みの遅れ
◎ファンクラブ立ち上げの遅れ
女子十二楽坊公式ファンクラブ(通称OFC)が始動したのは、2004年半ばのこと。サイトのプレオープンが4月15日、会報誌第1号の発送が7月中旬である。つまり、日本デビューから1年が過ぎており、2004年全国ツアーも終了した後のことだった。先に挙げた年表ではすでに第3期に入ってしまっている。
このファンクラブの始動の遅れがファンを逃した可能性は高いと思われる。
実は、2004年1月2日の武道館コンサートの会場で最初の公式ファンクラブ募集のチラシが配布され、実際に会員募集が行なわれた。これはシンホァーミュージックによって運営されることになっていた。しかし、会員が思ったように集まらず、このときのファンクラブは結局、お流れになってしまったのである。これに関しては全額返金、さらにお詫びとして特製キーホルダーが送られた。
その後、ファンクラブ運営をプラティア・エンターテインメントが行なうこととなり、急遽会員募集が行なわれた。これは2004年全国ツアーに会員募集が間に合ったため、今度はファンクラブ設立が可能となった。通称「OFC(オフィシャル・ファンクラブ)」の始まりである。だが、200万枚売り上げたユニットにしては規模は大きくなかった。
振り返ってみれば、日本デビュー直後の第2期の膨大な「女子十二楽坊に興味を持った人たち」を第3期以降につなげられなかった一因として、やはりファンクラブの出遅れがあるのではないかと思われる。
もし仮に、デビューアルバムの時点で同時にファンクラブ会員募集が開始され、CDにも募集が明記されていたとすればどうなっていただろうか。当時、CD購入者限定招待で開催された恵比寿ガーデンプレイスでのプレミアムコンサートには応募が殺到していた。千組二千名の募集に4万件以上の応募があり、3回の予定のところを急遽4回に増やしたほどだった。この時点でファンクラブへの入会を募集していれば、入会者が1万人の大台に迫る規模になったことは想像に難くない。
ファンクラブ入会動機として最も多いのは、ほぼ間違いなく「コンサートチケットのファンクラブ会員優先販売、優良席の確保」である。もちろん、コンサート主催とファンクラブ運営が異なる場合に、まれにこの連携がうまくいかず、その結果として会員も集まらない、コンサートへの固定ファンを確保できない、といった悪循環に陥る例も見受けられるのだが、女子十二楽坊の場合は(シンホァー主導であれ、プラティア主導であれ)チケットと連携させることにまったく問題はなかった。翌年春の全国コンサートツアーチケットの優先販売をうたうことができていれば、事情は大きく異なっていたはずだ。
女子十二楽坊の場合、ファンクラブへの集客に必要な条件は揃っていた。もちろん、ファンクラブの運営というのは人手もかかるし、利益も薄い。会員数がよほど多くなければ、年二回の会報の発行とその送料だけでも赤字になりかねない。そこで会員限定グッズや会員限定特別イベントなどで利益を出していく必要が出てくる。また、継続して提供するだけの情報や素材があるかどうかという点も問題になる。しかし、ファンクラブ内部だけで収支を計算すれば非採算部門になるとしても、そこでファンをつなぎ止め、CD販売やコンサート・イベントへの動員へと結びつける存在として、ファンクラブの果たす役割は大きい。ファンクラブ会員は自ら口コミで宣伝してくれる存在でもある。
このファンクラブの募集が2004年にずれ込んだことで、集められたはずのファンを囲い込みきれず、非常に濃いファンのみのファンクラブとなったことが、後々のCD売り上げやコンサート集客に影響を与えたことは見逃せない。
先日、Puffyが「期間限定ファンクラブ」を開設することになったが、このように時限設定で募集しておき、必要に応じて期間を延長するという方法も有効だろう。少なくとも時期を逃してしまうくらいならば、会員数が集まらない危険を冒してでも、とりあえずファンクラブを作っておく方がよいのではないかと思われる。
■(4)個別メンバーを売り出さない「アーティスト戦略」の問題点
◎あくまでもユニット単位、個々のメンバーの印象の薄さ
女子十二楽坊には、塔本一馬や稲葉瀧文という、かつておニャン子クラブに関わった有能な人たちが関わっていた。おニャン子クラブ、モーニング娘。をはじめとするハロープロジェクト、AKB48系グループ、さらにはキャンパスナイターズといった「女性多人数ユニット」と比較することは、その意味では外れていまい。
しかし、楽坊と他のユニットには大きな違いがあった。「アイドルではなく、あくまでも本格派アーティスト」――これはもちろん大きなウリであると同時に、呪縛でもあったと思われる。
女子十二楽坊はあくまでもアーティスト、古典楽器演奏家によるユニットなのだ。そこで、プラティア・エンターテインメントは「個々のメンバー」の個性を出さない方向性で売り出した。公式サイトでも小さな顔写真とプロフィールのみ。熱心なファンの間でも、メンバーの区別がきちんとつくようになったのはデビュー後半年近く経った時期であった。当初は簡単な日本語が話せるということでクロースアップされた「丸顔の琵琶担当の人」ジャン・シュアン(張爽)がなんとか識別された程度で、個々のメンバーをピックアップして個々にファンをつけるという方向性ではまったくなかった。
それどころか、「メンバーは全員で十三人いて、そのうち十二人が番組やステージに立つ」という編成であったことが明らかにされたのは、十三人が初めて舞台上で勢揃いした2004年1月2日武道館コンサートを報じるスポーツ新聞紙上においてだった。
あくまでも「女子十二楽坊というユニット」単位での売り出しだったのである。それは日本デビュー期においては非常に有効な戦略であったが、ファンをつなぎ止めるという観点からはマイナスに働いた部分もあったと思われる。
◎ツヨシ十二楽坊
この女子十二楽坊「非個性化」戦略は、パロディのされ方でもわかる。たとえば2003年末に草彅剛がSMAP×SMAPで披露した「ツヨシ十二楽坊」は、草彅が多少髪型を変えながら12人の役をやったものを同時に重ねて、PV風に仕立てたものであった。楽坊メンバー自身も怒るどころか大爆笑したというこのパロディは、実際には12人のメンバーそれぞれの髪型や表情などまで実に細かく再現していたのだが、当時の熱心なファンでもそこまでは見分けられていなかった。ただ12人分の役をツヨシがやった、というところに笑いのポイントがあった。
また、当時作られたアダルトビデオ「女子十二尺棒」は、メンバーのルックスとは似ても似つかない女性が十二人、単に赤い服を着てPVっぽく撮影しただけのもの。
つまり、個々のメンバーの特徴は二の次、「赤い服を着た美女が十二人」というのが女子十二楽坊の受け入れられ方であったことがわかる。
女子十二楽坊個々のメンバーのプロフィールが初めて詳しく掲載されたのは、中国情報を扱う雑誌「CHAI」2004年1月号(2003年12月発売)であった。この取材は大連で行なわれており、CHAI編集部が、プラティア・エンターテインメントではなく北京事務所に対して取材を申し込んだものと思われる。当時、メンバー情報に餓えていたファンは、このマイナーな雑誌に飛びついた。
その後、翌年になって講談社から出た写真集で、ようやく公式プロフィールが詳細に紹介されることになるのである。ドキュメンタリー番組で個々のメンバーをピックアップしたものが出てくるのも、やはり2004年以降のことであった。
◎他の大人数プロジェクトは個性化戦略
この「非個性化戦略」はプロデューサーの意向として徹底され、メンバーには協調が叩き込まれていた。映像では13人のメンバーの写る時間ができるだけ均等になるように配慮されていた。与えられたプロジェクトを完璧に「再現」することが求められ、そこには当然きわめて高い技能が求められたが、彼女たち個々の持つ才能を魅せていくという方向性には進まなかった。それこそが成功要因でもあり、同時に将来の発展の阻害要因でもあったと思われる。
「会員番号の歌」まであったおニャン子クラブや、「総選挙」を行なうAKB48は、個々のメンバーをクローズアップし、それぞれのメンバーに対して濃いファンをつけていくことを目指している。ハロプロでのシャッフルユニットも、小グループ化することで個々のメンバーの個性を強調する努力の現われと考えられる。ハロプロやAKBのファンの間では、自分が専門的に応援するメンバーを指す「押しメン」という言葉がある。
楽坊のファンの場合、資料館掲示板などでそれぞれのメンバーのファンが集まることもあったが、あくまでもかなり濃いファンによる自発的な動きであって、その存在をプラティア/ミューチャーサイドが認識はしていたものの、利用することはほとんどなかった。
女子十二楽坊にとっては、メンバーブログなど個々のメンバーによるプロモーションも想定できないことだった。それは、メンバー自身がアイドルあるいはポップスでいう「アーティスト」という意識ではなく、まさに「芸術家」という本来の意味での「アーティスト」という意識が強かったという要素も大きかったが、一方でプロデューサーによるイメージ戦略の影響も大きかったといえる。
女子十二楽坊の場合、個々のメンバーの特徴付け(「キャラを立たせる」行為)はファンの手によって行なわれた。メンバーの特徴をつかんだイラストやニックネーム等もファンから自発的に与えられたが、それらが公式に採用されることはないままに終わった。それはライトファン層をディープファン層に変える原動力を欠いたということではないだろうか。
■(5)ライト層向け戦略によるディープファン層の離脱
◎ターゲットを狙ったカバー戦略
女子十二楽坊のアルバムは、カバー曲が目立つ。代表曲「自由」「奇跡」をはじめとするオリジナル曲も多いのだが、特に第三期から第四期に入るにつれてオリジナル曲は減っていき、『世界名曲劇場』シリーズでは完全にカバーのみとなった。
カバー曲を採用するのは、時間的なメリットが大きい。商品として耐えうる曲をコンスタントに、またアルバムに必要な曲数だけ揃えていくには、作曲家の負担が大きくなる。だが、カバー曲採用によって曲数を増やすことが可能だ。
また、すでに評価の固まっている知名度の高い曲を盛り込むことで、購入意欲を高めることができる。ファーストアルバムではSMAP「世界に一つだけの花」、美空ひばり「川の流れのように」、小田和正「ラブストーリーは突然に」、中島みゆき「地上の星」が収録されているが、男女それぞれの幅広い年齢層に対応する選曲であることが理解されよう。
セカンドアルバム『輝煌』ではI WiSH「明日への扉」、谷村新司「いい日旅立ち」、テレサ・テン「時の流れに身をまかせ」という、わかりやすい若年・中年・高年向け選曲に加え、当時まさに旬だったリバーダンスのカバーも含んでいる。
全米デビューアルバム『Eastern Energy』では、アメリカ市場を睨んでCOLDPLAYの「Clocks」を収録した。さらに、サードアルバム『敦煌』は、久保田早紀「異邦人」のほか、「冬のソナタ」のテーマ「最初から今まで」を収録していた。
その後はほぼすべてがカバー曲のみとなっていく。オープニング曲に採用された「ドラえもんのテーマ」は別としても、その後はカバーアルバムまたはベスト盤のみとなる。『Merry Christmas to You』はタイトル通りクリスマス曲集、『世界名曲劇場~序曲~』は映画テーマ曲中心(ただし、フィギュアスケート荒川静香の演技曲で有名になった「誰も寝てはならぬ」もちゃっかりと収録)。
ミューチャーでの最後のアルバムとなった『世界名曲劇場~第1幕 中国民謡集~』だけは以上と流れが違い、中国西部の民謡を再現した作曲家・王洛賓の曲を西洋音楽的アレンジしたもので、これは北京の王暁京の構想による。
◎カバー戦略へのファンの批判
カバー曲を収録することについて、ファンの中でも異論は多く見られた。特に熱心なファンの間では「カバー曲は要らない」という声も強かった。
その中でも、楽坊的な独自アレンジ色が強い曲は好評だった。「世界に一つだけの花」楽坊アレンジなどは好感をもって迎えられた。しかし、原曲を忠実に再現しすぎていて、楽坊による演奏である必要が感じられない、と評価されたカバー曲もあった。たとえばエンヤの「オンリータイム」やCOLDPLAYの「Clocks」、あるいは「白鳥の湖」は「楽坊らしさがない」と評された。
また、アルバムのコンセプトから外れると思われるカバー曲は不評だった。特に『敦煌』という西域をイメージしたアルバムに冬のソナタのカバー曲が収録されたのは、売れ筋に走りすぎてコンセプトを壊したという見方が強かった。
熱心なファンにとっては第二、第三アルバムのオリジナル曲の評価が高かったが、残念ながら、「自由」「奇跡」を超えて一般にアピールするオリジナル曲はついに生まれなかった。徐々に資金的にも苦しくなっていく制作サイドとしてはカバー曲で制作していくしかなかったが、それがオリジナル曲を好む熱心なファンが離れていく要因の一つとなってしまったのだった。
そして、楽坊を知らなかった人たちにも理解してもらえるはずのカバー曲が、狙ったほどの効果を上げなかったのも、残念ながら事実であった。
女子十二楽坊のディープファン層は、大きく分けて、個々のメンバーの熱心なファン(アイドル的視点)と音楽性にこだわるファンがおり、それが重なりあっていた。個々のメンバーのキャラクターを立たせないことでアイドル的嗜好のファン層は増えず、一方で音楽性を求めるファン層がカバー曲続きで少しずつ離れていったことは、熱心なファンの絶対数そのものの減少へとつながっていった。
■(6)日本国内でのメディア露出の途絶
◎外国に住む外国人であるということ
女子十二楽坊が「外国に住む外国人」のグループであることも制約要因となった。外国人であることだけでは今の時代、決してマイナス要因ではない。ここでまず注目したいのは「ふだん日本に住んでいない」ということなのである。CDの収録、コンサートツアーやイベント参加のために来日するとき以外は日本国内にいない。ファーストアルバム収録時にはウィークリーマンションを借り切っての合宿状態で都内に滞在していたが、それが終われば帰国する。
常に日本にいないというのは、プロモーション面において非常に大きなデメリットとなる。CMだけでも押えておけば、お茶の間でテレビ画面に映り続けることになるが、音楽番組やバラエティ番組などで露出を「続ける」ことは難しくなる。
例外はあるものの、基本的に人気を持続するためには、テレビを筆頭とするマスメディアに露出し続けることが必要である。逆にいえば、デビュー時の楽坊は塔本一馬の戦略により、特定のセグメントをターゲットとして集中的に情報を投下することで、その時点でのメディア露出作戦は完璧であった。それは年末にかけても持続し、クライマックスが紅白歌合戦と武道館コンサートであったといえる(武道館の模様はスポーツ紙等で大きく取り上げられた)。
しかし、2004年に入ってからはテレビ出演やCM出演が減り、彼女たちが中国へと帰国してしまうと途端に情報が途切れてしまった感があった。日本の多くの人にとって、情報源はテレビである。「テレビに出なくなる」=「最近見ない」=「過去の人」という等号で結ばれてしまうのが実情だ。
◎ファンの年齢層の高さとネットの弱さ
女子十二楽坊のファンの年齢層は高い。ファンクラブの平均年齢が40代後半から50代。当時すでに30代後半だった筆者でかなり若い方だった。武道館でも、その後の全国ツアーでも「観客の茶髪率」は非常に低く、NHKホールの入り口で観客を見渡していた塔本一馬が筆者に「年齢層高いよねえ」とつぶやいたこともあったほどだった。
若年層が着うたやダウンロード販売で済ませてしまう傾向がある中で、CD購入に慣れ親しんできた高年齢層をターゲットにしたこと自体は、決して間違っていなかった。今もCDという形のあるものを売りたければ、ダウンロードで買うことに物足りなさを感じるレコード・CD世代を狙うべきだろう。
しかし、この年齢層の高さは、イコール、ネットとの親和性の低さも意味していた。つまり、女子十二楽坊ファンブログやファンサイトがほとんど立ち上がらなかったのだ。逆に言えばそれだからこそ、筆者が情報不足を感じて立ち上げた「女子十二楽坊資料館」があっという間に最大の楽坊ファンサイトになり得たわけである。しかし、その後もファンサイトはまさに片手で数えられるほどしか登場しなかった。
一方、同時期にハロプロファンのブログはまさに数え切れないほど存在した。はてなダイアリーだけでも「ハロプロオタブログ」が1ジャンルとなりえるほどだった。ネットでの盛り上がりとリアルでの活動は決して比例するわけではないが、それでも、これだけ多くのブログが常にハロプロのことを話題にしている状態、というのは、テレビ出演などとは別に一般の人たちに対して存在感をアピールする要因となりえる。
女子十二楽坊は、テレビにも時々しか出ない、ネットでも情報がない、という状態になってしまっていた。それはすなわち「過去の人」として認識されることと同義であろう。大多数の人に向けた宣伝においては「今、何がホットな話題なのか」が常に求められている。話題性を集めること自体が大変な作業ではあるが、その後はいかにそれを持続するかという観点に切り替えていかねばならないのである。しかし、すでに述べたとおり、来日するだけで多額の費用が発生する楽坊の場合、それは非常に難しいことだった。
■まとめ
以上の6項目をもう一度振り返ろう。
(1)コスト面における制約と誤算
(2)複雑な権利関係による活動の制約
(3)ファン囲い込みの遅れ
(4)個別メンバーを売り出さない「アーティスト戦略」の問題点
(5)ライト層向け戦略によるディープファン層の離脱
(6)日本国内でのメディア露出の途絶
(1)と(2)はすなわち「プロデュース側(レコード会社等)の自由な動きを制約する要因」となったものである。費用的にも権利的にも、次第に動きが取れなくなっていった。ファーストアルバムの利益は大きかったが、それが次につなげられなかったことが悔やまれる。
(3)~(6)は売り出し方における問題点である。もちろん、これらの問題点は前稿で述べた巧妙な宣伝戦略を前提として踏まえた上で、それを持続する上でマイナスとなったと思われる要因を書き出したものである。
■検証・少女時代 vs KARA
では、以上の問題点を踏まえて、日本上陸した韓国女性アーティストグループ「少女時代」と「KARA」を見てみよう。
これまでの「韓流」ブームを非常におおざっぱにまとめると、「冬ソナ」ペ・ヨンジュンなど韓流ドラマブーム(中高年女性層中心)、東方神起からビッグバンにつながる流れ(ジャニーズファンと重なる若年・中年女性層中心)に続く第3の流れとして、2010年夏から、韓国ガールズユニットが相次いで上陸しようとしている。その代表とも言える2グループが「少女時代」と「KARA」である。
少女時代は2007年8月デビューの9人組ユニットで、韓国のみならずアジア圏で人気を博している。2010年8月にこれまでのPVの総集編DVD『少女時代到来~来日記念盤~』で日本上陸、DVD購入者を招待したショーケースは2万2000人を集めたという。所属プロダクションは韓国の「SMエンタテインメント」。韓国でS.E.S.、BOA、東方神起などを輩出した大企業で、日本法人も有している。また、日本でのレコード会社としては、ユニバーサル・ミュージックのレーベル「ナユタウェイブレコーズ」に所属する(山崎まさよしやBENI、バブルガムブラザーズ、ゴダイゴ、海援隊などと同じレーベルとなる)。
一方のKARAは2007年3月デビューの5人組ユニット(当初は4人)。所属事務所は韓国のDSPエンターテイメントで、SMエンタテインメントと並ぶ韓国二大事務所の一方の雄である。日本では少女時代と同じくユニバーサル系列だが別レーベルの「ユニバーサルシグマ」に所属する(中森明菜、松田聖子、布施明、ムック、織田裕二などと同じレーベルとなる)。日本デビューシングルは2010年8月。少女時代とほぼ同時期の上陸であるが、シングルとしてはオリコン初登場で2位という快挙を成し遂げ、10月のアルバムも好調である。
日本では同じユニバーサル系になるのだが、少なくとも公式サイトなどの露出傾向を比較してみると、この論考的にはKARAに軍配を上げざるを得ない。
最大の違いは日本公式ファンクラブの有無である。KARAは日本公式ファンクラブがすでに始動しており、ウェブサイトでの紹介も非常に充実している。一方、少女時代は韓国公式ファンクラブは存在するが、日本ファンクラブは(2010年10月時点で)まったく存在もしなければ設立予定のアナウンスもない。
また、そのプロフィールの扱いもまったく違う。KARA日本公式ファンクラブサイトのプロフィール欄では、一人ずつの顔の特徴がわかる写真が2枚ずつ掲載されている。一方、少女時代の公式サイト(ユニバーサルミュージック内)では、「美脚グループ」を謳いたいためか膝から上の全身写真が小さく載っているのみで、顔の違いまで見分けられる写真はない。つまり、個々のメンバーを取り上げてのアピールではなく、あくまでも「美脚9人」というユニットとしての売り出し(つまり女子十二楽坊スタイル)になっている。
PVなどでちょっと気になるメンバーを見つけたとき、ファンクラブサイトや公式サイトを開いて「あ、この娘だ」と判別がつくか否かは、非常に大きな問題なのである。つまり、そこでさらに興味を持ってファンになるか、興味を失うか、という分岐点になり得る。
もちろん、今後の継続的な露出が可能になれば結果は大きく変わってくると思われるが、少女時代が一度は2万2000人を集めたものの、そこでファンクラブの入会告知ができなかったことをどうカバーするかは大きな課題になるように思われる。
あらためて6項目に当てはめて整理してみるならば、以下のようになるだろう。
(1)コスト面における制約と誤算……韓国は近いとはいえ、5人、9人が頻繁に揃って来日するとすれば(韓国内での活動も考えれば)移動コストは問題となる。ただし、現在の音楽界では一般に「初回限定版DVD付き版」を限定販売することが多く、収録曲もCDと同じ場合が大半なので、DVD著作権が本体を圧迫することは少なくなっているように思われる。
(2)複雑な権利関係による活動の制約……BOAの場合は「アーティストマネージメントも兼ねる」エイベックス所属でファンクラブもエイベックス主催のために複雑な部分もあると思われるが、少女時代・KARAにはその点の問題はなさそうだ。
(3)ファン囲い込みの遅れ……上述のとおり、KARAはOKだが、少女時代は完全に出遅れている。
(4)個別メンバーを売り出さない「アーティスト戦略」の問題点……上述のとおり、KARAはOKだが、少女時代は今後の課題となりそうだ。
(5)ライト層向け戦略によるディープファン層の離脱……楽坊での「ライト向けカバー曲/ディープ向けオリジナル曲」は、KARAと少女時代では「ライト向け日本語曲/ディープ向け韓国語原曲」という対立になりそうだ。いかに日本語詞版のクオリティを落とさないかが課題になりうる。
(6)日本国内でのメディア露出の途絶……これは今後の課題。コストとの兼ね合いもあるが、定期的に来日して音楽番組や芸能情報番組、あるいはバラエティ番組などに出続けることが必須である。
楽坊と比較しても有利な面は多々見られるため、健闘してほしいと思う。
■最後に:その後の女子十二楽坊
.reviewのアブストラクトの時点で「その後の女子十二楽坊」についてのリクエストがあった。おおざっぱな流れは冒頭の年表に記したとおりだが、第六期(つまり現在)の状況について簡単に記しておこう。
ミューチャーコミュニケーションズ倒産後は日本への進出の足がかりを失った状態だったが、元ミューチャー社員でアーティストマネージメントを担当していた庄磊が事前に独立して設立していた海日エンターテインメントが日本公式ネットファンクラブを設立、現在は「The 12 Girls」ファンクラブとして、楽坊ならびに元メンバーの合同ファンクラブとなっている。
その間、楽坊の活動は停滞し、2006年の時点で活動休止していたリーダー格のジャン・シュアン(琵琶)を始め、数名のメンバーが事実上楽坊から離れることとなった。その欠けを埋めるために北京スターディスクでは妹分のユニット「小女子十二楽坊」や「半打玫瑰(Six Roses)」からメンバーを補填することもあったが、2009年、メンバー9人が引き抜かれて合計12人のユニット「V12」が結成されるという事態に至った。V12は演劇プロジェクトの音楽部門という触れ込みであったが、プロジェクト自体が頓挫、その後「Viva Girls」と名前を変えての展開を狙ったが、こちらも現在活動はストップしている。
一方、北京では旧楽坊に残された3人のメンバー(チョン・バオ:琵琶、リャオ・ビンチュイ:竹笛、シー・ジュエン:琵琶)を中心に、現役女子大生の新メンバーを加えた新生「女子十二楽坊」が生まれた(一部、V12から戻ったメンバーもいる)。新生楽坊は中国大手のオンラインゲーム会社テンセント(騰訊)のゲーム主題曲を担当したり、アジア圏でのライブを実現したりしているが、新アルバムなどの展開は未定のままだ。
そのような状況の中で、2010年10月13日には、元女子十二楽坊メンバー3名によるネオ・インストルメンタル・ユニット「Alive2」の復活アルバム「Alive2 ~Again~」が発売された。メンバーはジャン・シュアン(琵琶)、ジャン・リーチュン(二胡)、マー・ジンジン(揚琴)で、いずれも各楽器パートの首席奏者だった。カバー曲として名曲「また君に恋してる」が収録されているほか、半分以上が新しいオリジナル曲で、代表曲「ファイア - Fire」はテクノ風である。女子十二楽坊時代の制約を離れ、独自性を追求するサウンドを目指すとうたわれている。
また、これとは別にイン・イエン(二胡)がソロ活動を開始している。
女子十二楽坊から生まれた潮流は、いよいよ次のステージに入ろうとしているようである。
【関連リンク】
○読売ADリポート ojo:プラティア・エンタテインメント「女子十二楽坊」が売れる理由
http://adv.yomiuri.co.jp/ojo/02number/200404/04kigyo.html
○ZAKZAK:破産した女子十二楽坊仕掛人が内情激白「経営者失格」「夢を追いかけすぎた」
http://www.zakzak.co.jp/gei/2007_07/g2007072514.html
○ツヨシ十二楽坊映像
http://www.pandora.tv/my.maraika/33400421
○KARA日本公式ファンクラブサイト
○少女時代公式サイト
関連論考
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
