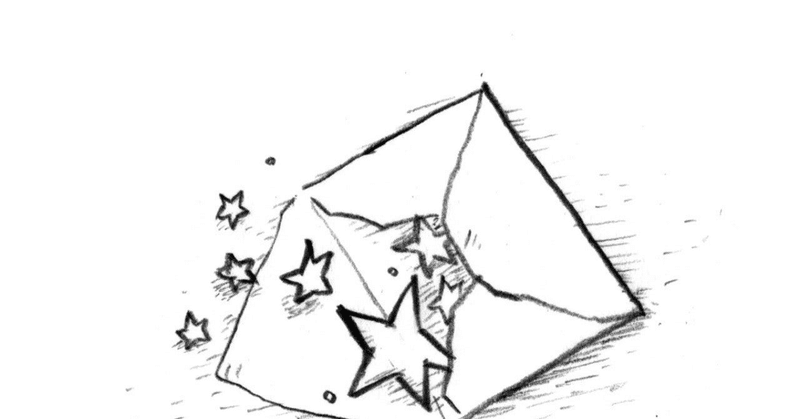
<ネタにできる古典(18)>手紙の話(源氏物語、十訓抄、徒然草)
不用意な文言が炎上を招くのは現代に限ったことではないのかも知れません。建長四年(1252)頃に成立したとみられている『十訓抄』には次のような記事があります。
すべて文はいつもけなるまじきなり。あやしく見苦しきことなども書きたる文の、思ひがけぬ反古の中より出でたるにも、見ぬ世の人の心際は見ゆるものぞかし。ただいまさしあたりて、はづかしからぬ人と思へども、落ち散りぬれば、必ずあいなきこともあれば、よく心得べきことなり。
(現代語訳)
手紙というものは全て、どんな場合であっても普段のままであってはいけないのだ。思いがけない書き損じの中から出てきた、非常識で見苦しいことが書いてある手紙によっても、見たこともない人の心の中がわかってしまうものだ。今現在のところは特に立派でもない人だと思っていても、(出した後になって)手紙が拡散してしまえば、かならず思いがけない嫌なことも起こるので、よく分かっておいた方が良いのである。
「落ち散りぬれば」のあたりがゾッとしますね。若い頃のヤンチャな発言のせいで、大物になった数十年後に炎上するようなものでしょう。こういう文言が残されている鎌倉時代にはどのような炎上沙汰があったのか想像すると、なかなか楽しくなります。
この十訓抄の話の影響も指摘されている話が徒然草にあります。
しづかに思へば、よろづに過ぎにしかたの恋しさのみぞせんたかたなき。
人しづまりて後、長き夜のすさびに、なにとなき具足とりしたため、残し置かじと思ふ反古など破りすつる中に、亡き人の手習ひ、絵かきすさびたる見出でたるこそ、ただその折の心地すれ。このごろある人の文だに、久しくなりて、いかなる折、いつの年なりけんと思ふは、あはれなるぞかし。手なれし具足なども、心もなくて変わらず久しき、いと悲し。
(現代語訳)
静かに物思いに沈んでいると、何事につけ、過去への恋しさばかりで胸がいっぱいになる。
家人が寝静まってから、長い夜のてすさびに、気の向くままに道具などを片付け、いらない古紙などを破り捨てている時に、故人が練習で書いた文字や遊びで描いた絵を見つけると、在りし日に戻ったような気がする。今も生きている人の手紙でさえずいぶん時間が経って、どんなことがあった時のものだろう、どの年のものだったろうなどと思うと、しみじみ感慨深い。使い慣れた道具なども、使うこちらは変わるのにずっと無心に昔のままで、実に悲しい。
こちらはひたすらにノスタルジー。それでも反古を「破りすつる」という言葉には後に残すまいという意思も感じられます。亡き人の手紙を見て当時を思い出している所などは源氏物語・幻巻の
落ちとまりてかたはなるべき人の御文ども、「破れば惜し」と思されけるにや、すこしづつ残したまへりけるを、もののついでにご覧じつけて、破らせたあひなどするに、かの須磨のころほひ、所どころより奉りたまひけるもある中に、かの御手なるは、ことに結ひあはせてぞありける。みづからしおきたまひける事なれど、久しうなりにける世の事と思すに、ただ今のやうなる墨つきなど、げに千年の形見にしつべかりけるを、見ずなりぬべきよ、と思せば、かひなくて、疎からぬ人々二、三人ばかり、御前にて破らせたまふ。
を彷彿とさせます。あるいは兼好法師、自らを老いた光源氏に重ねていたのかもしれません。もっともこの構造は無名草子やそれに影響したとおぼしい能因本の枕草子にも見られますので、具体的な影響関係は詰めようもないのですけれど。
それにしても他の作品の手紙に関する記事と比べて読んでみると、徒然草の最後にある「手慣れし具足なども、心もなくて変わらず久しき、いと悲し」は印象的です。モノを見てノスタルジーに浸っていた自分を急に相対化する、心無き具足たち。こういう切れ味もまた徒然草の味わいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
