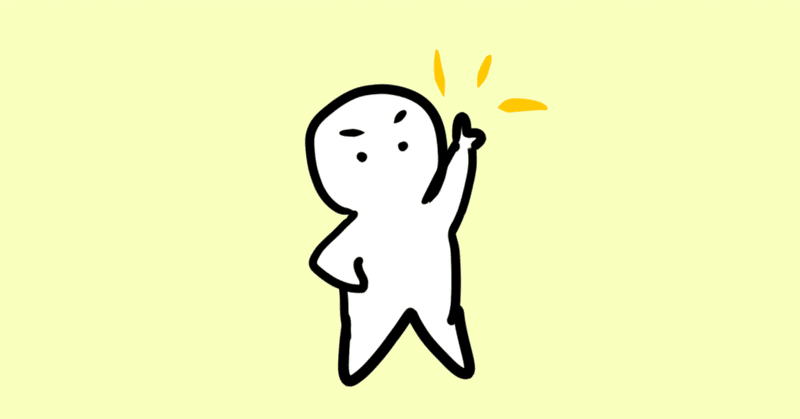
ボドゲのゲームメカニクス分類『目標に関するメカニクス』(スケジュールによる分類)
<はじめに>
はじめまして、古瀬と申します。今回の記事は私が行っているゲームメカニクスの分類の一部です。
今回の範囲はゲーム中にプレーヤーの指針となる目標を作るためのメカニクスとなります。分類自体の目的、方針に関しては目的と方針を、(まだ、大部分が執筆中ですが)目次に関しては暫定的な目次をご覧ください。
ここは違うんじゃないか? とか こういう種類もあるのではないか等のご意見ありましたら@Biblio_Gamesまでお願いいたします。
<序文>
”ゲームには選択肢が必要”とよく言われますが 目標がなければ、その選択肢を選ぶ基準がありません。ではプレーヤーの目標とはどのように作ればよいのでしょうか?
目標はより分解すると
①スケジュール(いつまでに) ②課題内容(どのような課題を) ③どれぐらい 達成するのか? に分解する事ができます。
それを達成(未達成)する事で与えられる④賞罰(報酬/罰点)と組み合わせてプレーヤーに⑤わかりやすく提示し、
・何をすればいいかはわかるが 最適な選択とその順序はわからない
・”目先の目標”が適度に変わりつつも、全体を通した大目標がある事
という状態を作る事がゲームデザイナーのするべきこととなります
③どれぐらいに関してはただの数値、④に関してはゲーム特有の部分が多いためこれらは省きます。①スケジュール、②課題内容、そして⑤課題の提示方法について順に記述していく予定をしております。
今回の記事では①スケジュールの部分を列挙し、その特徴について掘り下げていきます。
2章-1スケジュール(SCH)
SCH1”特定期限”までのスケジュール
前述のとおりゲームにおける目標は
条件1:何をやればいいかは理解できるが
条件2:最適な計画の立案をは難しい
条件3:毎ラウンド考える事(≒体験)はある程度変わる
といった状態になる事が望ましい。
これを達成するための第一歩は”締め切りのタイミングを最終ラウンドのみにしない事です。
ばらばらの締め切りがある複数の課題は
・マイルストーンとしてプレーヤーの理解を促す。
・今、注力して考えなければいけない事と余裕があれば考えるべき事を提示し、広いレベルのプレーヤーに対応する
・別の魅力(危機)として人を誘惑し、悩ませる
といった作用を持ち得ます。
優先して考える”目標”切り替わる事で考える事が切り替わる事はゲームにおいては重要です。
ゲームの流れは【1-2 進行(現在下書き中)】にも記載した通り、フェーズやターンといった区切りを繰り返していくことで進んでいきますが、ゲーム体験(≒感情)は繰り返しにならないようにしましょう。幸いなことにこれは慣れればそこまで難しい事ではありません。
ゲーム終了時以外のタイミングが無いことは正直あまりお勧めしません。
ゲーム時間が30分以下で、核となるアイディアにインパクトがあればぎりぎり可能かとは思います。しかし、それ以上となると(最初に設定した、あるいは与えられた)目標に向かって淡々と歩を進めるだけの体験になってしまっているものが多いように感じます。
SCH1-1 ゲーム終了時までに
(定義)
ゲームの終了時までにやればよい課題です。アクションやタイルについている単純な得点や ゲーム終了時にしか得点化しない大目標がこのカテゴリーに属します。
(特徴)
最も単純な締め切り。ゲーム終了時までに達成すれば良い目標。そのタイミング上、与えられる賞罰は勝利点(加点、減点)か勝敗(勝利、敗北)のいずれかとなります。
得られる報酬は大きく分けて3つに分類できます。
①単純な得点
※別のリソースに変換できたり、不労所得や新たなアクションの実行の条件となる場合、これに含みません
※後述する【SCH2-1】早取りや【SCH3-2】縮小に含まれるものは含みません
このタイプの資源変換の完全な終点であり、特別面白さは生みません。
ただ、わかりやすいため、「どの目標を達成するか」の基準にはなりえます。
②ゲームを通しての大目標
【SCH1-2 ラウンド終了時までに】と共通している部分も多いですが、
非公開の情報による得点や多様な得点計算など、誰が勝っているかを曖昧にする効果はこちらの方が大きいです。
③最終ターンの細かな点数
例えば、資源5個で1点、使わなかったカード1枚1点等という細かな点数。
「最終ターンで得点する方法がないためやる事が無い」という状態を防ぐ程度のものです。正直、勝敗にはほぼ関与しません。
得点幅が小さい場合等は無理に点数をつけず、タイブレークの条件にしたり、何もせず勝利を分かち合うようにしましょう
(ゲーム例)
無数にあるうえ、基本的な項目のため省略します。
SCH1-2 (とある)ラウンド終了までに
(定義)
中間決算あるいはラウンド終了時の決算での賞罰がこれにあたります。ゲーム終了時にも同じ条件での賞罰がある場合、【SCH1-1 ゲーム終了時までに】には含めず、こちらに属するものとします。
(特徴)
【SCH1-1ゲーム終了までに】に比べ、ある程度短いスパンでできるためプレーヤーが感覚をつかみやすいのが特徴です。
状況により役割や特徴が違うため分けて記載します。
<同じ目標を繰り返す場合>
最終ラウンドと同じ得点計算を前もってする事でゲームの内容、流れを掴ませる事ができます。
<違う目標を繰り返す場合>
ゲームの大枠を変えず、毎ラウンドの体験をばらつかせることができます。大抵は毎試合、各ラウンドの目標を変えられるように実装するため試合ごとに変化をもたらすポイントとしても機能します。
<毎回ではないラウンド終了時の決算>
判定が毎ラウンドではない場合、各ラウンドの優先順位に波を作る事ができます。
例えば農業や会社経営、蛮族からの都市の防衛をテーマに含むゲームにはXラウンドに1回、資源を払えなければ失点というルールが存在し得ます。(それぞれ食料供給、給料支払い、侵略への対処という世界観的にあった意味を伴って実装されます。)このようなゲームでは支払いのあるラウンドと無いラウンドで該当する”資源の獲得”に関する切迫度合いを変える事ができます。
<資源が揮発性がある場合等>
以下のどちらかに当てはまるような場合についてです。
資源や権利が揮発性(つまりラウンド終了時に消えてしまう)
資源を保存しておく倉庫、手札に非常に低い上限があり、その判定がラウンド終了時に行われる
このような場合「ボトルネックを見つけ、それを解消できる奴は偉い」という価値観の元、プレーヤーを競わせることができます。
例えば、「食料がたくさん収穫できるが機械が足りずないため加工できずに腐らせてしまう食品加工工場」や「営業が全然仕事を取ってこないためにエンジニアの開発力が活かせない会社」にならないように経営するようなテーマのゲームです。プレーヤーは毎ラウンドの結果を見て、次のラウンドに足りなかったもの(”機械”や”営業”)を見極めて強化する事になります。不適切な改善(既に過剰な”食料”や”開発力”を更に強化するなど)すると得点が伸び悩むか下手すると大きな減点となります。
(ゲーム例)
事例:コンスタンティノーブル
上記<資源に揮発性がある場合等>の例。このゲームでは以下の3つの揮発性の資源、権利をふんだんに使い、ボトルネックとなる箇所を多く用意しています。
契約書。達成する事でお金(非揮発性の資源)や勝利点を得るための目標が記載されたカード。達成には記載されているのと同じ数同じ種類の組み合わせで消費し、船を出航させる必要がある。毎ターンランダムで入手するが、得られる枚数を増やすことができる。次のラウンドへ持ち越せるのは初期状態では1枚だがお金があれば増やす事はできる。
商品(5種類)。上記の契約書や(特定の資源を勝利点に変える権利を得る)商業施設で勝利点やお金に変換するのが主な使い道。お金で生産施設を建てて生産するか、お金で買う事で入手する。ただし前者は建設した次のラウンドからしか生産されず、後者は毎ラウンド購入できる品の種類や購入可能な個数が変わる。基本的に毎ラウンド1つしか次ラウンドに持ち越せない。特殊な建物「倉庫」を建設する事でその数を増やすこともできるが、倉庫は全プレーヤー合計で1個しか建てられない
船の(出航)。船自体は航海しても消費しないが、戻ってくるのは次ラウンド以降となる。上記契約書を解決するために使う。お金を払って入手する。(余談だが積載量、値段、戻ってくるまでの時間が違う3種の船が存在する)
1つのボトルネックを解決する手段も複数用意されており、それぞれに一長一短があるのがポイントです。例えば「資源が余ってもったいない状態」の場合、以下のような解決策が存在します。
契約書を大量に引き、達成する:得られる金額は多いし得点も手に入る。ただし、内容はランダムの上、契約書は次ラウンドに1枚しか持ち越せない。(説明は省くが船の種類や契約を手に入れる方法も複数ある。)
3つセットで得点化:毎ラウンド売れるのは3種のみでランダムだが、1ラウンド前から内容は提示されている。得られる勝利点は高いが、同じ種類を3つ揃えなければいけない上、お金は得られない(=自分の場を拡大できない)。ゲーム中盤以降の選択肢。
生産施設を建てる:「1ラウンドに一度特定の種類の商品を払って得点を得る権利」を得る。内容が固定のため計画しやすい。しかし得点や金額への変換レートは低い
倉庫を建てる:次のラウンドに持ち越せる量が4つになる。コストも低く、上記3つと違い、どんな種類の商品が余っても対応できる。しかし、得点が増えるわけではない。また、倉庫は1つしかないため先着1名のみ(=早くしないと取られるかもしれないが、序盤は生産資源を増やしたい)
このように「ボトルネックを認識しているか?」、「その上で最適な手段を選択したか?」の2段階でプレーヤーを評価する内容になっています。
SCH1-3 不労所得の増加(なる早で)
(定義)
各ラウンド開始時、あるいは終了時の不労所得(アクションを消費しない資源の算出)の増加がこれにあたります
(特徴)
上記2つと違い、”いつ”というタイミングがゲームからは指示されていません。しかし、例えば『ラウンド開始時小麦が一個もらえる』という効果を持つ建物は”できる限り早くこの建物を建てよ”というスケジュール感の提示にほかなりません。
大抵の場合、他の不労所得(場合によっては、1回限りの資源獲得や勝利点)と並べられ、どれをどの順番で獲得するかを判断させる形をとります。
(ゲーム例)
多数あるため省略
(SCH1-2/SCH1-3)の亜種 とあるラウンドの後に
(定義)
とあるラウンドより後に目標の達成をするべきという課題です。純粋に遅い方が良いというルールは極めて稀で大抵は【SCH1-2 とあるラウンドまでに】や【SCH1-3 不労所得の増加】の亜種として実装されます。比較的よくある例をあげるならば、建物のグレードアップがあるゲームにおいて『中間決算時に低レベルの建物を多く持っているほど得点』等があります。
(特徴)
よりよい状態にする方法が2つある事が特徴です。上記の例『低レベルの建物を多く持っているほど得点』で言えば、
【SCH1-2 とあるラウンドまでに】と捉えて新しく低レベルの建物を建てる。
【op-SCH1-2 とあるラウンドの後に】と捉えて低レベルの建物をグレードアップさせるのを次ラウンド以降に延期する。
のいずれかでより多くの得点を得る事が出来ます。後者の方法は「何もしなくていい」点で前者より効率はいいですが、アップグレード後の建物によって生み出される(大抵はより価値の高い資源の)不労所得を諦める事になります。
(ゲーム例)
事例:ガイアプロジェクト
このゲームでは資源を払って、建物をグレードアップしていきます。
(ゲーム開始時から公開されている)各ラウンドのボーナスによっては後のラウンドになってから建物のアップグレードをした方が良いこともあります。
また、このゲームでは建物をアップグレードする事で不労所得(資源の獲得)は改善していく傾向にあるのですが、「資源Aの産出は増えるが、資源B(資源Aより価値は高いが上位互換ではない)の産出が減る」という事が起こりえます。
SCH2 ”相手”依存のスケジュール
仕事でも趣味でも、一人ですべてをコントロールできず、他人の進捗に依存する場合、スケジュール管理の難易度は高くなります。その他人が協力的でなく、自分のスケジュール予定を共有してくれない場合は猶更です。
対戦相手という(少なくとも1位を目指すという点では)”利害の一致しない人物”をスケジュールに介入させる事は計画遂行の速度や(先を越された後の)再計画の重要度をあげます。また、対戦相手と部分的に”勝負”を行うことで勝ち負けの説得力を上げてくれることでしょう
SCH2-1 早取り(相手より早く)
(定義)
いわゆる早取りといわれる仕組みです。最もきつい条件の場合、最も早く目標を達成した者だけが恩恵を受ける事ができます。
2人目以降に目標の達成を許す場合、コストが高くなったり、効果(勝利点)が低くなったりします。
(特徴)
非常に多くのゲームで採用されています。このような目標が並列にいくつか並べられている場合、『他人の行動をよく見て欲しいものが被らない状況を作れると偉い』という指針を与えることができます。(徒競走が苦手でも参加者が1人ならただ完走するだけで1位になれますから)
また、インタラクションが減少している200X年代後半以降、局所的に他人と争うポイントを作る事で、ソロプレイ感を下げる役割が与えれれているように思えます。特に201X年代以降の紙ペンゲームにおいてはこの傾向は非常に強い状態です。プレイ人数を広く取りたい紙ペンゲームにおいて、他の目標に比べ、得点の大きさを変化させなくてもある程度機能する点が評価されての事と思います。(※筆者は他人の行動を見れるタイミングが限られている紙ペンでの早取り採用に疑問を持っています。しかし、明らかに少数派のためこのような言い回しとなっています。)
(注意点)
両立しづらい早取りの目標を複数並べる場合、並べる目標の数はプレーヤー人数とずらした方が良い場合が多いです。
(例えば「赤い建物をを4つ建てる」と「青い建物を4つ建てる」等の複数の目標を同時に進める事ができる手段のない目標の場合、)人数と同じだと単に1個ずつ1人が取って終わる展開になりがちです。
また、先手有利にならないように気を付ける必要があります。具体的には①初期資源に傾斜をつけて対応する、②同じラウンド、ターンで達成すれば同時とみなすといった方法があります。
(ゲーム例)
多数あるため省略
(関係するメカニクス)
川、ワーカープレースメント(狭義) etc
SCH3 順番依存
ゲーム中の選択とは『何をするか?』だけではありません。極端な話、「カードを1枚使って1枚引く。山札が切れても手札がなくなるまでゲームを行う」というタイプのゲームの場合、何をするか?は引き運によって決まってしまうことも多いです。
多くのゲームの場合、「どの順番でアクションを行うか?」に意味を持たせる という意識はゲームを組み立てるうえで非常に重要なものとなります
SCH3-1 アクション拡張
(定義)
〇〇をする前に××を行っておくと〇〇のアクションの効果やコストが改善するというメカニクスです。
一つ例を挙げれば『工場を建設してから生産を行うと生み出される商品数が増える』といったものです。
(特徴)
このメカニズムを使うことでプレーヤーに アクションの順番を考えさせることができます。前述の例で言えば、工場を建設してから生産を行いたいのであって生産をしてから工場を作りたいのではないのです。
このメカニズムを使う上での注意点はゲーム全体を通しての良い順番を自明にしすぎない事です。
その具体的な方法の1つ目は一本道にせず円環を描くように設計する事です。わかりやすさを重視して、最終的な大きな勝利点(及び最終得点計算の要素)は終端となっている事はむしろ好ましいですが、それ以外に関しては
アクションA⇒アクションB
アクションB⇒アクションC
アクションC⇒アクションA
のようにどのアクションにも それよりも先にやりたいもの とそれより後にやりたいものが少なくとも1つ存在するようにするとよいでしょう。
チェックポイントとして
・アクションの順序を結果が同じになってしまっていないか?
・アクションの順番が確定になってしまっていないか?
の2つが満たされているか確認すると良いでしょう。
(ゲーム例)
多数あるため省略
SCH3-2 アクション縮小(できれば使い切った後に)
(定義)
【SCH3-1 アクション拡張】や【SCH4-1手番圧縮】の逆。
ゲーム中に手に入れたアクション効率やアクションの権利等を放棄する事で報酬を得るという目標。
(特徴)
その特性上、終盤に使う事が多いため、大抵得られる報酬は勝利点や大きな勝利点を獲得するのに必要なもの(マジョリティーで点数が得られるところに駒を置く権利等)になる傾向にあります。
単純に実装してしまうとできる限り遅くすれば良い(≒得られるものが勝利点である場合、最終ラウンドにすればよい)事になってしまうため他の条件と組み合わせる事が必須といえます。
具体的には 1ラウンドにできるアクションの回数が限られているようにするか、 【SCH2-1 相手より早く】と組み合わせる事となります。
ゲーム例
事例 レイクホルト
野菜を育てるのに必要な畑を捨てる事で広義の得点トラックを進めるアクションがあります。
ワーカープレースメントであるこのゲームでは、このタイプの効果は1ラウンドに1度しか使えないため残っているターンがあってもこのアクションを実行する意味はあります。(大抵行った方が良いです)
また、このアクションがある事で、畑を新たに獲得する選択肢の存在意義が比較的終盤まで残っています。
事例 ナヴェガドール(恩恵アクション)
このゲームのアクションの一つ”恩恵”では(工場、造船所等の要素一個当たり等の)基礎点を挙げるトークンを得る事ができます。得点のシステム上この取得は勝つために必須となっています。しかし、そのコストとして代わりに貴重な資源である労働者を返さなければなりません。労働者は後述する【SCH4手番圧縮】の要であるため、できる事ならば後でこのアクションを実行したいこととなります。
しかし、このタイルは種類ごとに限られた数しかありません。同じ種類のトークンを欲しがっている他のプレーヤーよりは早くこのアクションを実行する必要があります。
SCH4 手番圧縮
多くのボードゲームでは、皆が同じターン数を行って誰が最も高い点数を取得するかを競います。従って他人が2ターンかけてやっている事を1ターンで行うことができればその分勝負を大きく有利に進める事ができます。所謂手番圧縮という考え方です。
SCH4-1 手番圧縮(まとめて一気に)
(定義)
資源を多く用意してからアクションをすることにより手番(や資源)を節約できる という目標設定です。
簡単に言えば
手順A
①資源獲得⇒②資源の変換(1回分)⇒③資源獲得⇒④資源の変換(1回分)
だと4手番かかってしまいますが
手順B
①資源獲得⇒②資源獲得⇒③資源の変換(2回分)
なら3手番で行うことができます。この節約した1手番を使って得点をしたり相手を攻撃したりして、勝利に繋げるという工夫点をゲームに付与する事ができます。
手順Bを目指す事をプレーヤーに推奨するメカニクスです
(特徴)
このスケジュールを使う場合に注意しなければならない点は
何も工夫無く使うと”できる限りためてからまとめて変換する”が最適解になってしまう点である。
この問題を解決するにはどうすればよいでしょうか?
最も一般的だと思われる対応は上で説明した”SCH2相手より早く”と組み合わせる事です。
上の手順Aと手順Bをもう一度見比べてみてください。前述のとおり、手順Bは確かに3手番で2回分の資源変換を終わらせており、最終的な効率では手順Aを上回ります。
しかし、手順Aは2手目に最初の資源変換を終えており、これは手順Bより1手早いものとなります。資源を払って手に入れるものが後ほど価値が低くなる(あるいはコストが増える、あるいは多くの種類1枚しかないカードの中から早いもの順で選ぶ)場合この1手番の遅さが仇となる可能性を作者は仕込むことができます。
また、あまりに強力な手番圧縮が起こらないように保持できる資源に上限をつける例もよく見られます。
(ゲーム例)
事例 ブラス
ブラスの紡績所は同時にいくつも出荷する事で手番を圧縮する事ができます
ただし、紡績業には需要があり、それを超えるとそもそも出荷ができなくなる(可能性がある)事がプレーヤーに提示されています。
つまり紡績業に力を入れるプレーヤーはできる限り溜めて①手番を圧縮したいが、②競合他社となったプレーヤーよりは早く売りぬけたいという感情を持つ事となります。
また、
・出荷をせずに資金を手に入れないことは資金面で厳しい(そのために借金をすることに手番や未来の収入を失うことになる)
・【SCH1-2中間】 ゲーム前半が終わるまでに出荷しなければ得点の機会を損失することになる
という事も考える事になります。
事例:ナヴェガドール
多くの労働者を雇う事でアクション(植民地の獲得、建物の建設)を複数回実行する事ができます。
ただし、
・植民地や建物は早く買うほど安い。
・労働者を増やすには大抵資金が必要
・労働者を失うことで手に入れる恩寵タイルは勝つうえで必須
事例:センチュリー:スパイスロード
典型的な『資源の上限』を用いている例。
このゲームでは、カードを使って資源(スパイス)の変換を行うが材料となる宝石を2セット以上持っていると効率よく資源を増やしたり、ランクアップさせることができる。ただし、スパイスを持てる量の上限が決まっているため、カードごとの相性や順序を考える事となります。
改変履歴
2021.12.23 公開
2022.8.25 加筆修正
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
