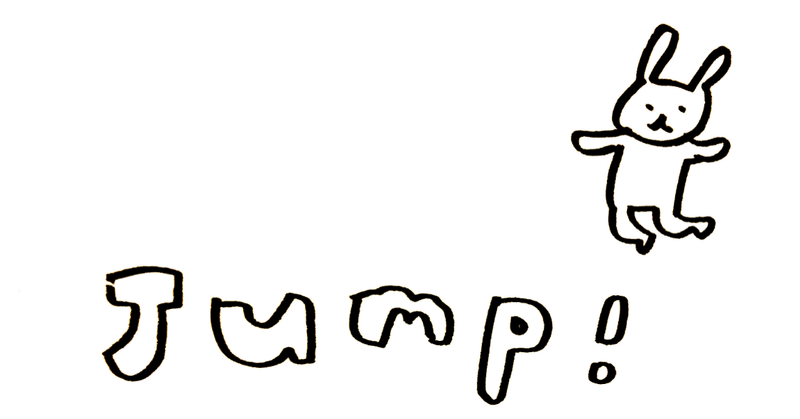
うさじの話
国際空港からミシシッピ川を越えて、ひたすらに東にまっすぐに伸びるインターステート(州間国道)のハイウェイを走ると、左右には真っ平にコーン畑が広がるようになる。
風景が単調になり、まっすぐすぎて眠気を誘われころに、その小さな町はあった。
州立大学がある以外に、特にこれといった見どころもなく、住民のほとんどが、農業、あとは大学に関わる職業についているこぢんまりとした町。
そこで、私は1年間日本語を教えていた。
♢
バブル経済がはじけたあとも、日本の政府は、日本文化や日本語の海外普及を狙って、外郭団体を通じて、アメリカの国際交流機関や、現地の学校などへ日本語教師の派遣プログラムを行っていた。
そのひとりとして、私が派遣先を志望するときに選んだのは、高校時代から慣れしたんだ「アメリカの家族」が住む州から、ミシシッピ川をはさんだお隣。
なぜかといえば、ちょうどこのプログラムと同じタイミングで合格通知をもらっていた、言語学とくに日本語学で有名な大学がその州にあったから。
せっかくなら、その州の日本語教育界に関わっておいたほうが、その後有利だろうと思ったのだ。
♢
日本語教師だとかっこよく書いてみたが、実際のところ、それは現地で日本語を教えているメンター教師とペアを組んで働くというプログラムで、私が組んだ相手は、当時の私から10歳くらい年上、40前の白人男性だった。
彼は、米軍在籍時代に日本に駐留していて、そのとき日本語を習得したので、その後、教師になることにしたという。
希望の派遣州にいけたことは嬉しかったが、私は当初からあまりこのペア相手の先生とはうまがあわなかった。
まるで日本の昭和の父親のような彼はとても内向的で無口。
社交家を自認する私だが、派遣前の交流イベントでも、あまり打ち解けることができなかった。
そして、九月。新学期が始まり、教室の中で一緒に教えるようになると、その溝はますます大きく広がるように感じた。
「あなたは正しい発音をデモンストレーションするのためのアシスタントなんだから、黙ってこの単語リストを読みあげるだけでいい」
高校時代から憧れてきたはずの、アメリカで日本語を教える夢。
でもそれは、こんな先生のことばからスタートし、グレーな予感を含んでいた。
ある時、生徒の質問に対する彼の説明が、文法的に正しくなかった。
横にいた私は、無意識に、表情を変えてしまった。なにも口には出さなかったが、おそらく生徒も、そしてその生徒たちの反応から、先生自身も間違ったことに気づいたのだろう。
「私が文法の説明で間違っても、生徒の前では正さないでくれ。生徒からの尊敬が損なわれる」
彼は怒りに任せて、教室の机を私に向かって激しく押し出した。
机にぶつかったお腹の痛みより、いろんなものを日本に残し、はるばるアメリカまで、こんな時間を過ごすために来たんだろうかという心の痛みの方が強かった。
彼はそのまま教室を去った。
その後、教員室のコピー機で翌日用のプリントを刷りながら、私は涙を流した。
会社の営業部門でチームリーダーとして事務の女性たちをまとめてきた私のようなタイプは、彼が求める「黙って頼んだことだけをする慎ましい日本人女性」とは大きく違う。
彼にとっては使いづらい存在だったに違いない。
けれど、そういう「日本的な女性観」から抜け出したくて、ようやくアメリカに来れたと思っていた私にとって、アメリカ人からのこの要求は、日本の会社で上司に突きつけられるよりも期待が多かった分失望感をもたらすものだった。
♢
そんな中にも、希望の光は射すものだ。
その年は、初めて高校のシニア(最終学年)の生徒が、選択科目である日本語をドロップせず継続希望したため、Japanese Level 4の授業が必要になっていた。
先生は
「レベルも上がるし、過去の教案もないので、ゼロからやらなくてはならない。あなたに任せます。自由に授業を組んでください」
と、男子学生三人、女子学生一人からなるこのクラスを私にまかせた。
これはお互いにとって一番いいアプローチだった。
私は引きつづき中学校の初歩クラスと、高校で行う彼のJapanese1-3でアシスタントを務め、全ての宿題プリントとテストの採点もしたけれど、Japanese4については彼の確認も許可もなく、学ぶ文法や単語を決め、教案を作り、テストや教材を用意することができた。
ここでようやく、自分が大学で学んだ日本語教授法を活かし、アメリカで教えている、という実感を持つことができた。
♢
アメリカの高校では、大学のように学年に関係なく希望する科目を選択してカリキュラムを組み立てて行くので、シニアの生徒がJapanese 1や2にいることはめずらしくない。
その男子学生もそうだった。
名前を憶えていないのだが、仮にジェームスとしよう。
ジェームスはシニアのとても背の高い生徒で、なかなかのおしゃれさんでもあった。おとなしくて教室の中で目立つわけではなかったが、熱心にひらがな、カタカナ、そして初歩の漢字を練習していた。
けれど、ある日を境に、ぱったりとジェームスが授業に来なくなった。ドロップアウトはめずらしいことではないので、ジェームスもそのひとりかと思っていたところ、放課後、私がひとり教室に残り、Japanese4の準備をしているところに、ひょっこりジェームスがすがたをあらわした。
「コンニチハ!」
引っ越しなどいろいろな変化が重なり、授業に出られなかったこと。
けれど、日本語は楽しかったので、また戻りたいが、ギャップを埋めることができるか心配なこと…。
ジェームスの話をきいていて、こうやって日本語に興味を持ち続けてくれる生徒が増えることが嬉しかった。
「じゃあ、週に二日くらい、追いつくための補習をしましょうか」
私は提案した。
ジェームスはきっと頼みごとが切り出せないでいるんだと思ったから。
彼はJapanese 4にいるタカシ(母親が日本人のハーフ)と仲が良かった。
試しに頼んでみろとタカシにアドバイスでもされたのだろう。
先生に許可をもらい、こうして、放課後の補習授業が始まった。
♢
「うさーじ!」
へ?一瞬なんのことか、まったくわからなかった。
ジェームスの手元をみると、丁寧にかかれたそのひらがなは「うさぎ」。
「サのひらがなと、ジのひらがなはとても間違いやすいですね」
と、いうジェームスに、私はあわてて黒板にひらがなを書き、
「Usagi、は う、さ、ぎ ですよ」
と発音した。どうもGIとアルファベットで書かれた音をジと読むと思い込んでいたらしい。繰り返し「うさぎ」をノートに書きつつ、ジェームスはうさーぎ、うさーぎとブツブツ唱えていた。
「でも、ぜったいウサージのほうがかわいいですよ。ラビットのイメージにあってます」
スタスタと歩いて来たジェームズは、私の書いた「うさぎ」の横に、可愛らしいうさぎの絵をチョークで描いた。
「Giveのギ、ですよ。ギ!」
絵の上手さに感心しながら私はギ、ギ、ギと繰り返した。
♢
補習の甲斐もあったのか、やがてジェームズは授業の内容に追いついて、問題なくついていけるようになった。
でも、なんせ、高校最後のシニアイヤーなのだ。やりたいこともあるだろうに、どうして補習を止めたいといいださないのか。
そう不思議に思い始めた頃、ジェームズが問わず語りに自分の家族について話しはじめた。
「実は、僕の両親は数年前に離婚していて。で、少し前、父親がぼくとあまり歳の変わらない女性を連れてきたんです。
彼女は妊娠していて、『喜べ、新しい妹がくるんだぞ』といわれました」
最近その妹が産まれ、父親も継母もその赤ちゃんに夢中なのだという。
赤ちゃんのためのスペースがある家にと引っ越しもし、すべてが赤ちゃんを中心に回りはじめた。
そんな家には帰りたくない、けれど表立って波風はたてたくないし、友人たちと遊び歩くような気にもなれない。
「だから、この夕方の教室はぼくの居場所なんです。センセイ、アリガトウゴザイマス」
俯いていたジェームズは、最後に顔をあげて、日本語でニコリとお礼をいった。
♢
親だって人間だ。自分の幸せを追いかけるのは悪いことではない。
ただ、この西日さす放課後の教室が私の心に鮮烈に焼きつけたものは、ティーンエイジャーたちが、そういったオトナの陰で、みんなの幸せを考え、ことばを呑み込んでいることだった。
「でもね、センセイ。ぼく、そろそろ家にちゃんと帰って、妹の面倒見るのを手伝おうと思います。そしてね、赤ちゃんにウサージって日本語を教えてあげるんだ」
分かってますよ、と、ウインクしながら、ジェームズがいった。
♢
日本語を教える、なんて偉そうに思って教室に立っていたけれど、これは私が人間として学ぶ時間だった。
先生との関係も、ほかの先生方との時間も、そしてなによりも生徒たちとの「日本語を教える、学ぶ」以上の交流も。
本当に大きなものを学ぶ時間だった。
♢
もし、あなたがどこかで「ウサージ」とうさぎのことを日本語で間違って云うアメリカ人女性にであったら。
それは、もしかして、ジェームズセンセイの熱心な日本語教育の成果かもしれない。
そう想像しただけで、なんだか私は嬉しくなってしまう。
あの時17歳だった彼らは、今ごろ40前のいいオトナになっている。
そして赤ちゃんはもう成人している頃だ。
みんなどこかで。
元気に、笑顔で暮らしているといいな。
いただいたサポートは、ロンドンの保護猫活動に寄付させていただきます。ときどき我が家の猫にマグロを食べさせます。
