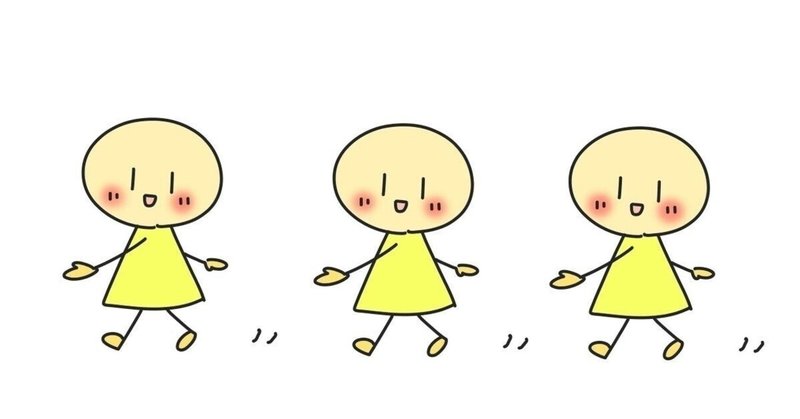
私と「妹」たち
末っ子の私には、「双子の妹」がいる。
♢
初めてアメリカ本土にいったのは17歳の夏だった。
それまで体験した外国は、小学校一年生で行った香港、三年生だったグアムそして高学年以降いっていたシンガポールくらい。
だからずっと憧れていた「ザ・アメリカ!」へ足を踏み入れる興奮と喜びで、ロサンゼルス空港に到着した時は浮き足立っていた。
前にも書いたが、この初めてのアメリカ上陸とは、ある留学団体が主催する夏休みの交換プログラムだった。
一年間の交換留学を父親にどうしても許してもらえなかった私にとって、この夏季短期留学はなんとか得られた最大のチャンス。
しかも、自分のバイト代とお年玉貯金をすべて注ぎ込み、足りない分は成人式の着物を返上する約束で出してもらったから、とにかく投資を回収しなくてはいけないという思いでいっぱいだった。
アメリカ本土の土を踏んだ時、私は、「時間を絶対に無駄にせず、たくさん英語を話し、たくさん友達をつくるんだ」という意気込みに満ちていた。
♢
けれど。
そう、たいていこういう話は「けれど」と続く。
3週間の語学学校と寮生活で、なんだか私の「がんばろう」は枯渇していった。
最初は積極的にスペイン人の輪に入り込んだり、ヴェネズエラ人やプエルトリコ人の友達を作ったりした。
しかし、日本語で考えたことを英語に翻訳し続けるのはとても疲れる作業だったし、パーティーの仕方やらハグなどの距離感やら、いろんなカルチャーギャップに翻弄されることも多かった。
結局、寮生活も中盤をすぎると、やっぱりスペインや南米の学生たちはみんなスペイン語圏で仲良くなっていき、トルコやモロッコの学生たちは連帯していたし、私も英語を話すことになんとなく疲れたなと思い始めていた。
♢
そんななか、いよいよ後半のホームステイが始まった。
日本人が同じ空間にいた寮生活とは違い、ホームステイがはじまると、これまでの日本語のおしゃべりという逃げ場はなくなった。
朝起きた時の「おはよう」から「おやすみ」まで英語に変換するには、脳みそをフル回転しなくてはいけないということだ。
当時はインターネットなどないから、メールも、ネット検索もない。
こっそり日本語思考で息抜きできるのは、日本に宛てて手紙を書くときだけだった。
家族と食事し、どこかへ出かけ、テレビをみたり、他愛ない会話をする。
そのどれも、全部が英語。
だから、きっと、オーバーヒートした脳みそが休息をもとめていたに違いない。私は朝寝坊し、昼寝し、夜はとっととベッドに入り、とにかく眠ってばかりいた。
♢
「今日、バスケットの練習に行くけど、いく?」
ホームステイが始まってすぐ、ジャネルがそう訊いてきた。
私のホストシスターはジェニーとジャネルという双子の姉妹。しかも、私とちょうど一つ歳下。
そう、私たちは3人同じ誕生日だった。
ジェニーは容姿端麗、成績もよくチアリーダーのメンバーで、ミスコンテストの常連。
もう一人のジャネルは運動神経抜群でバスケットの選手、かつ、頭脳明晰の生徒会メンバーという、まるで少女マンガにでてきそうな二人。
かといって、それを鼻にかけることもなく、双子たちはゆっくりとした英語しかついていけない私を、それでも諦めずに自分たちのクラブや友達との活動に誘ってくれていた。
バスケへの招待もそんな彼女たちの配慮のひとつだったろう。でも、ちょうど英語環境もえつき症候群にかかってしまっていた私は、あっさりとこたえた。
「やめとく。バスケ、好き、じゃない」
いかんせん語学力の不足というのは、潤滑油になるはずの説明をまったくもってすっ飛ばしてしまう。
本当だったら「誘ってくれて嬉しいんだけど、あんまりバスケは好きなほうじゃないから、今日はやめておくね」といいたいけれど、語彙は不足しているし、微妙なニュアンスを伝える表現力もない。
だから、実際に口にするのは「No. I don't like basketball.」 というめちゃくちゃ愛想のない返事だ。
なんせ、英語に疲れた脳みそは、もう限界をこえている。
だから、そのぶしつけさに気が回らない。
♢
幸運にも、私はその家にやってきた四人目の海外留学生で、家族はみんな外国人留学生というものに慣れていた。
しかも前夏に滞在した日本人高校生は、とても内気で、毎日ほとんど口をきかず、折り紙だけしていたらしい。
おかげで、双子たちは「日本人って、これまで受け入れたドイツや南米の学生に比べると、英語があまりできないし、シャイ」と思っていた。
だから、私がその日本人高校生とは対照的に、カタコト英語ながらも行きたいところにはいきたがり、やりたくないことにはきっぱり嫌だというのは意思があってよろしいと好意的に思われていたようだ。
お母さんが、外国移民の子供たちむけの英語の先生(外国語としての英語教育は母国語としてのカリキュラムとはまったく異なる)だったということも、ラッキーだった。
お母さんはいつも、簡単なことばを選び、ゆっくりと話してくれたし、私がけげんな表情をするとすぐに読み取って、わかるまで丁寧に説明をしてくれた。
♢
当時高校三年生だった私の、学校での英語の成績は悪くなかった。
メニューや看板といった「文字」の英語を読み下すのはまったく問題なかったし、聴き取りも、かなりの割合で理解できた。
理解できるからこそ、自分が「いいたいこと」もたくさん頭に浮かんでくる。
ただ。
その「いいたいこと」を「タイミングよく、さくさくと英語に変換して外に出す」というのはどうやらまったく脳みその違う部分を使うものらしい。
日本語で浮かんだ「いいたいこと」を英語に変換している間に、目の前の会話のはどんどん別の話題に移ってしまう。
ようやく英語の文章が組み立て終わった時には、その文章の行き場はどこにもない。
表面的には、私のことを「何ひとついわずウンウンとうなずくだけ」あるいは「不愛想にイエスノーしかいわない」と誤解しているだろうと思うと、なんだか悔しい。
ストレスは日々つのっていくばかりだった。
♢
とはいえ、英語しか話せない環境の効果というのはすごい。
だんだんと言いたいことを英語に変換するスピードは速くなり。
思いやりのある家族だったおかげで、「どうやらコイツは何かを言いたいみたいだぞ」と、私の表情から感じ取り、会話を待ってくれるようになったので、やがてコミュニケーションは格段によくなっていった。
私と双子たちの「言葉のテニス」は、私の空振りや、ボール拾いばかりだったものが、だんだん返球できるようになり。
双子たちが私が取れるところにボールを返してくれるおかげで、ラリーもできるようになっていった。
♢
ブラスバンドの演奏会、夜中のドライブ、友達の家の地下の巨大スクリーンで観る映画…。
やり取りができるようになるに従い、双子たちとの時間の楽しさは大きくなり、一緒にでかけても心地よく過ごせるようになっていった。
近所の家でパーティーをしたあと、電灯のない真っ黒なコーン畑の真ん中の道を、ヘッドライトの明かりだけを頼りに走りながら、大音量でカーステレオを鳴らして帰ったこと。
私が唯一ついていけるテレビ番組だった「セサミストリート」を、ひやかすことなしに一緒に観てくれて、キャラクターのSnuffleupagusの名前の発音をゲラゲラ笑いながら練習したこと。
二人のバイト先のレストランに、内緒でお父さんお母さんと三人で食べにいって、ニヤニヤしながらステーキを食べて、大いに嫌がられたこと。
どれも楽しい記憶だ。
♢
そんななか、いちばん強く印象に残る思い出は、お父さん側の親族が一堂にあつまって湖畔の別荘でBBQをする「ファミリーリユニオン」。
お父さんは自身も朝鮮戦争に出兵していた経験があるし、親族の男性たちも同じように戦争経験があると事前にいわれていた。
けれど、いちばん年長の伯父さんが、
「真珠湾攻撃のことをどう思う?広島は当然だったと思うか?」
と、訊ねてきたとき、私は完全に無防備で、言葉を失ってしまった。
いまの自分だったら、上手に反応ができる。
その後の海外生活で、戦争の歴史が話題になることはたくさんあった。自分はどう思うのか、そしてそれをほかの国のひとにどう伝えればわかってもらえるか、なんども経験してきたから。
「え、えっと。せ、戦争の歴史は…」
けれど、この時の私は、日本人として何も答えないわけにはいかないと焦る気持ちと、自分の意見を取りまとめなきゃというパニックと、そしてそれを英語に変換する作業がオーバーヒートしてしまった。
たどだどしく英単語を並べはじめたとき、後ろから「妹」の声が重なった。
「伯父さん、確かに彼女は日本から来たわ。でも、彼女はあきらかに、戦争の時には生まれてなかったじゃない。それなのに、そんな質問を彼女にぶつけるの?いま、彼女は家族の一員としてここにいるのよ」
ジャネルは毅然とした姿で、私を守ってくれた。
「ジョン伯父さんって、いつもあの調子なのよ。去年、別の日本人の留学生のときにもそうだったから、やめてねってみんなで言っておいたはずだったのに」
帰りの車の中で、双子たちは声をそろえていった。
「そもそもね、去年の時から伯父さんたちは『なんで日本人の留学生なんて受け入れるんだ』って猛反対だったんだって。だけどお父さんは『だからこそ受けれるんじゃないか』って押し切ったらしいの。ま、お父さんらしいわよね。ジョン伯父さんは年に一回BBQの時しか会わないし、この先あんな目にあうことはないと思うから、心配しなくていいわよ」
失礼極まりないわよね。
ジェニーもジャネルも、私の側にたってくれている。
それが、ほんとうに嬉しかった。
♢
思えば、一つ年下の、「妹」のはずの二人は、いつも私を守ってくれていたように思う。
ホームステイも中盤を越えたある日、一緒にショッピングモールのコーヒー屋さんに立ち寄った時のこと。
ジェニーがまず注文し、ジャネルがそれに続いた。
家族との会話はだいぶスムーズになっていたけれど、私はそれでも、初めて会う人に英語で話すのは、怖かった。
だから、ドキドキしながら
「ブ、ブ、ブ、ブラック、コーヒー、プ、プ、プリーズ」
と、言葉をはきだした。
「ハァ?」
店員さんは、まったく意味が分からないという顔をして、鼻から息をだし、肩をすくめた。
その、あからさまな拒絶反応が、かえって私のパニックを呼び、ただ「black coffee please」の三語で終わるはずの注文のことばは、頭からぶっ飛んでしまった。
「あ、えっと、えっと、えっと」
と、少し離れたところでコーヒーが出来上がるのを待っていたジェニーとジャネルが私の様子に気づいた。
「なに、なに?どうしたの?注文はなに?」
「ブラックコーヒー」
双子相手にはちゃんと言葉がでてきた。そして、その言葉を受けて、ジャネルが店員さんを見上げて
「聞こえた?」
といった。
店員さんは、フンガッとさらに鼻息をあらくしてレジを打ち、顎で代金を指ししめした。
支払いを終えて、コーヒー受け取り口で二人に合流した私に、憤慨しながらジャネルがいった。
「私にはちゃんとブラックコーヒーって聞こえてたし、わかったんだからね。なんなのよ、あの態度。がっかりだわ。大丈夫。ちゃんと英語でいえてるからね。自分のせいだなんて思っちゃダメよ。私たちにわかったんだから、わからないあっちが悪いのよ」
♢
英語だけの環境で汗をかいた3週間は長いようで短かった。
そして、出発の日は、偶然にも私たち3人の誕生日だった。
「またね。ここはもうあなたの家だから、いつだって帰っていらっしゃい」
お母さんは目を赤くして、そういってくれた。
Facetimeどころか電子メールすらなかった時代。国際電話が一分360円、飛行機代は15万円だったから、これが「アメリカの家族」の顔をみる最後かもしれないと私には思えた。
終わるとなってみると、途中、疲れたからと投げやりになって英語をがんばらなかった時間がもったいなくてたまらない。
不完全燃焼の不愉快さと、英語ができると思い上がっていた自分の現場での英会話力のなさに、悔しさをかみしめていた。
「はい、ぜったい、また遊びにきます」
お父さんのキスとお母さんのハグにそう応え、双子たちにブンブンと手を振った。
♢
その次の夏。
私は、一年間家庭教師のバイトで貯めたお金でふたたび「アメリカの家族」を訪ねた。
でもそこにはジェニーの姿しかなかった。
なぜなら、「私も逆の立場になってみる」と、ジャネルはドイツの田舎町へ夏休みホームステイ体験に行っていたからだ。
そして、日本に戻ってきた私のもとに、ドイツからの手紙が届いていた。
ーーー去年、あんなにゆっくり話さないといけないことや、昼寝や居眠りばかりしていることを茶化していたことをあやまりたくて、書いています。
本当にごめんなさい。
ドイツにやってきて、私はセサミストリートのドイツ版みたいなテレビを、この家の5歳の男の子と二人で観ています。
私の話し相手は、その子と、おばあちゃんばかりです。なぜなら、他の大人や若者の話すスピードにはとてもついていけないからです。
午後にはもう脳みそを使いすぎて、神経を張り詰めすぎて、昼寝ばかりしてる自分に、ああ、こういうことだったんだとようやくわかりました。
外国語の世界にいることが、こんなに厳しいことだなんて。
また、アメリカに来てね。
その時には、もっと、ちゃんと言葉を選んで、ゆっくり話すようにするから。約束します。
ジャネル
♢
それから、もう30年ちかく時間が流れた。
ジャネルのドイツホームステイの翌年、今度はジェニーが長野にホームステイしにやってきた。
やがて20代後半になり、私が日本語教師としてアメリカで暮らすようになったとき、ジャネルは英語教師としてナミビアでボランティアをしていた。
私よりもっと過酷な環境で集団生活しながら英語を教える彼女からの手紙は、大いに励みとなった。
医師としてもうすでに緊急治療室で働いていたジェニーは、休みになるとビールや美味しいものを車に積んで、ミシシッピ川を越えて遊びに来てくれた。
その後、ジャネルがアメリカに戻りスタンフォード大学の法学部に行くことを決めたとき、私はジェニーがすむ街の大学のMBAコースに進学することにした。
貧乏大学院生となってピザやポテトばかり食べていた私を、ジェニーは「私が食べたいからディナーにいこう」といって誘い、中西部ではまだめずらしく、高級だった和食レストランでよくご馳走してくれた。
さらに時が流れ、私がロンドンに転勤になると、法廷弁護士になっていたジャネルはサンフランシスコから、そして三人の子供たちの母をしつつ赤十字の緊急治療室で働いていたジェニーはミネアポリスから、引越し祝いをスーツケースにいっぱい詰めて遊びに来てくれた。
ある年の秋には、ミュンヘンのオクトーバーフェストにいってみんなでドイツの民族衣装を着て大いにビールを楽しみ、私がピッツバーグ出張になったから、休暇をとってお父さんとお母さんを訪ねる予定だといえば、二人も予定を調整して一緒に帰省した。
場所も時間も違うところにちらばって暮らし、それぞれ忙しくしているけれど、携帯で簡単に連絡が取れるようになった今では、Whatsappのグループチャットで毎日のように冗談をやりとりしている。
♢
旅行先で、いい歳をして、軽口をたたきあい、ふざけあう私たちの様子に、「どういったご関係なんですか?」と訊かれることがある。
私たちは「ええ、3人誕生日が同じ、姉妹なんです」と笑ってこたえる。
私は末っ子だけれど、アメリカに二人、とても素晴らしい妹たちがいるのだ。
いただいたサポートは、ロンドンの保護猫活動に寄付させていただきます。ときどき我が家の猫にマグロを食べさせます。
