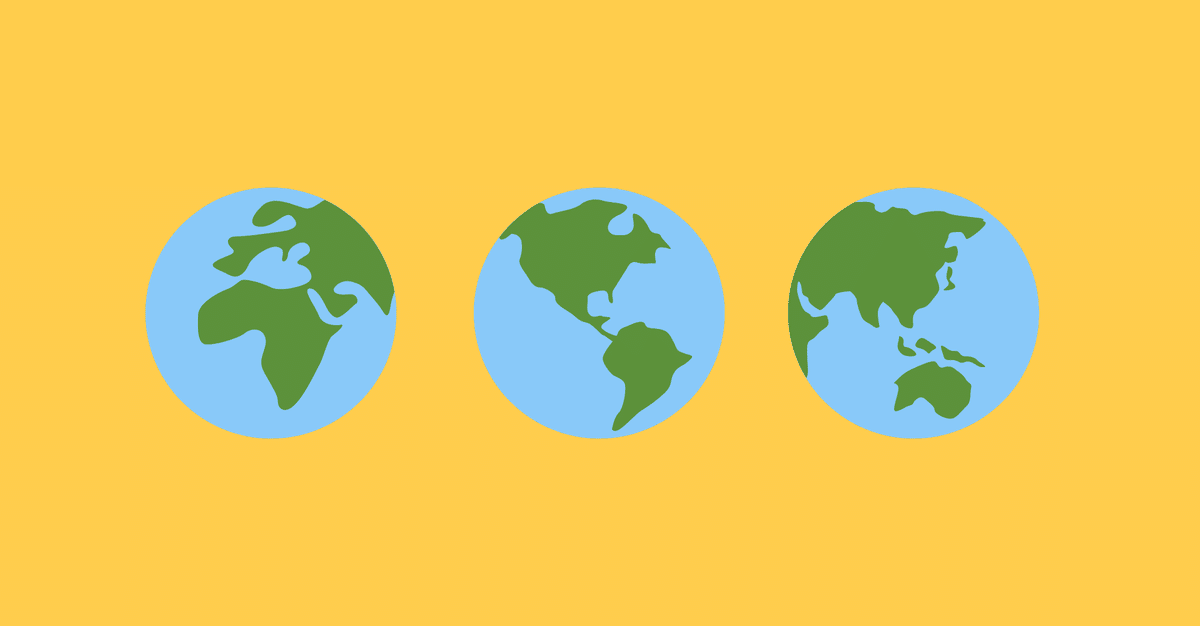
Photo by
shimakoneko
異国で、知らない季節に身を置きたい!
再読の部屋 No. 4 岡本かの子作「河明り」 昭和14年(1939年)発表
「旅に出たい」、とせがむ心をなだめるため、岡本かの子の「河明り」を開きました。
「河明り」は、岡本かの子を彷彿とさせる、女性作家が主人公。彼女は、執筆中の小説の想を得るため、川辺にある、貿易商の店の部屋を借ります。やがて、貿易商の娘が、心を寄せる男の気持ちがわからず、悩んでいると知り、気になって仕事に手がつかなくなります。
自分が執筆に集中するためには、「娘に男の気持ちを確認させればよい」。そう考えた作家は、船上の男と会うため、娘を連れてシンガポールへ行きます。その行動力が、とても気持ちいい。
そして、二人の旅をバックアップしてくれた、作家の叔母さまが、また、素敵。若い頃、藩侯夫人の秘書役として仕えた彼女は、藩侯夫妻が公使として欧州に赴任した際に伴われ、その帰国の途上で世界の国々を廻ってきたという人です。
「あんたも一遍そのくらいのところに行っていらっしゃい。すると世間も広くなって、もっと私と話が合うようになりますから」
そう言って、旅券だの船だの信用状の手配をして。二人を神戸まで見送ってくれました。
ー・ー・ー・ー・ー・ー
そして訪れたシンガポール。ラッフルズ・ホテルで寛いでいた作家の目に、異国の熱い空気と眩しい光の世界が、次のように映っていました。
すべてが噎(む)せるようである。また漲(みなぎ)るようである。ここで、蒼穹は高い空間ではなく、色彩と密度と重量をもって、すぐ皮膚に圧触してくる濃い液体である。叢林は大地を肉体として、そこから迸出(へいしゅつ)する鮮血である。くれない極まって緑礬(りょくばん)の輝きを閃かしている。物の表は永劫の真昼に白み亘り、物陰は常闇世界の烏羽玉いろを鏤(ちりば)めている。土は陽炎を立たさぬまでに熟燃している。空気は焙り、光線は刺す―――
私と娘は、いま新嘉坡(シンガポール)のラフルス・ホテルの食堂で昼食を摂り、すぐ床続きのヴェランダの籐椅子から眺め渡すのであった。芝生の花壇で尾籠なほど生の色の赤い花、黄色の花、紺の花、赭(あかつち)の花が、花弁を犬の口のように開いて、戯れ、嚙み合っている。
岡本かの子の時代の海外旅行は、現代と比べて、時間と手間とお金が何倍も掛かるものだったと察せられます。その始まりから終わりまで、驚きに溢れ、見聞きした物事からの印象も濃厚な気がします。
「河明り」を読みながら、ほんの一時、当時の旅の雰囲気に浸ることができた気がしました。それにしても、旅に出たい!
お立ち寄り頂き、ありがとうございました。
*岡本かの子作「河明り」の過去記事です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
