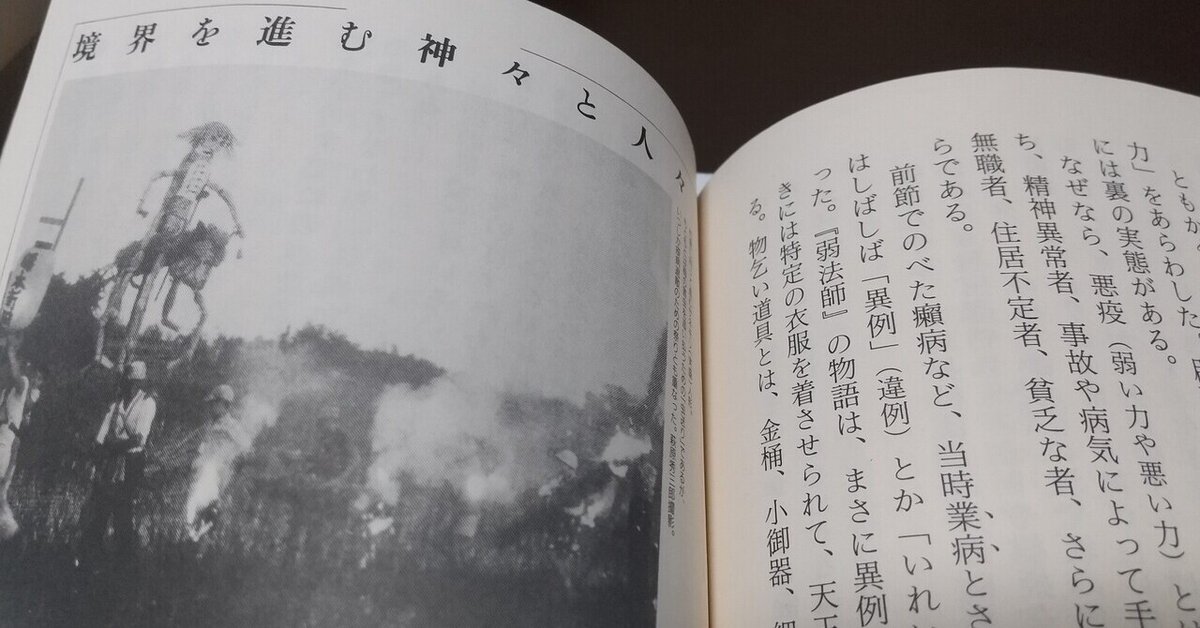
「フラジャイル 弱さからの出発」読書メモ11
以下、第5章「異例の伝説」第2節「境界をまたぐ」の抜粋と、そこから感じたことや考えたことである。
この節では、「境界」にまつわる話が様々な角度から様々な事例を織り交ぜてなされていて、その中には差別の話も含まれる。
私たちが生きる2021年現在の世界の雰囲気は、「境界をなくそう」「差別をなくそう」「インクルーシブな社会を」「まぜこぜ社会を」といったスローガンに溢れていて、それを良しとする方向に進んでいる一方で、その方向に対する強烈なアレルギーを示す人も実は多くいるというのが私の皮膚感覚である。この現代社会を生きる私たちにとって、この節や、次の節「隠れた統率者」(まだ精読していない)等は重要なテーマ・ヒントとなりそうな気がしている。
そもそも「裸になる王」や「欠けた王」の儀式を民衆レベルでもどいたのは、境い目の芸能だった。もともと芸能はその多くを境い目で生んでいた。(p.297)
私たちの日常生活は、実は劇場なのかもしれない。服を着て、化粧をして、かっこつけながら、何者かを演じながら日々を生きざるをえないのではないのだろうか。それが垢ぬけた人間の業なのだと思いこませながら生きている。それが善いこととか悪いこととか一概に言えなくて、もちろん息苦しさはあるけれど、やはり演じてしまうというのが人間の性ではないか。それが私たちの日常の場の風景なのではないか。
しかし、繰り返すが、それは息苦しいことで、人によっては死にたくなるほど苦しい振舞なのである。だからこそ「自然体」とか、「ありのままで」と歌うことが流行る。そして境界の話。境い目で裸になるという習俗が王権の交代にもかならずといってよいほどあらわれる、などといった話の後の上の文章である。人間は何故か境い目を設けたがる。国境とか、性別とか、言葉とか。何かと線を引く。縄張りをつくっておきたい。そこには我欲が含まれているのかもしれない。或いは、実は大した深い意味もないテキトーな線なのかもしれない。
芸能は境い目で生んでいたという話だが、それはそうかもしれない。ある一部の層にだけウケる内輪っぽい芸というのは素人感が漂う。遍く全ての層の心を鷲づかみにしてこそ、スターなのだろうし、芸能のプロなのだろうと思う。もっとも、現代の日本の芸能界、特にお笑い関係の芸能人の振舞は、どこか内輪っぽさが漂っているように感じる・・・が、これは私のお笑いについての理解力の低さによるものなのだろうか・・・。
行逢裁目(ゆきあいさいめ)(p.298)
境い目は、厳密なものというより、決めたくて決まったもの、と書かれている。そのいきさつをふくんだ昔話として、この言葉が各地にいろいろ残っているそうだ。行逢は行き逢うこと、裁目は柳田国男によると境い目が語源だそうだ。このように、境い目というのは、なかなかいいかげんに決まるものだが、一度決まってしまえば、現実的には結構重要な意味をもちはじめ、「ここ」と「むこう」を区別する機能を発揮するとのことだ。
次に、私たちにとって非常に身近な話題、「運動会の綱引き」の話題である。この綱引き、実は境い目をめぐる大きな意味をもった行事だったそうだ。知らなかったが、こうして言われてみれば、まさに「縄張り争い」という言葉がぴったりの行為だなとは思う。
たとえば、こんなものまでもがとおもわれる今日なお運動会にみられる綱引きも、しらべてみると、もとは満月の夜の村境でチガヤを綯って雄綱と雌綱を引きあう行事であったことが知られてくる。(p.300)
綱引の起源が中国豊穣儀礼としてかなり古くからあり、東西アジア一帯でも天父地母の聖婚儀礼や雨乞い儀礼の再現に深く結びついていることを知った。そうしたときには綱引とも変じたチガヤを飾りながら、そこに各種の境い目の芸能が生まれていったのである。(p.300)
境い目をめぐる縄張り争いと豊穣儀礼が重なり、神聖な儀式として「綱引」は存在していたようだ。人間が精いっぱいお互いに力を出し合い縄張り争いするところに、豊穣の神が生まれるということか?この仮説は今勝手に私が思いついただけのものである。
芸能の多くは「辻」と「道」と「門」とで発達してきたという説がある。(p.301)
辻とは、十字路や交差点のことを指すようだ。要するに家の外ということなのかなと思ったのだが、それではあまりにもざっくりとした解釈過ぎるのか。家の外である以上、やはり芸能は内輪っぽくてはだめで、仮に内輪っぽさを活用したとしても、それが何か全体への発展性につながるようでなくてはだめなんじゃないかと思う。
小笠原恭子は芸能の場は夜を暗示する冥府との接点をもっていなければならないとさえ言った。(p.302)
冥府とは死後の世界のことだそうだ。生と死をまたぐ。これは究極の境い目だなと思う。その境い目の雰囲気を漂わせなければ、芸能の場とはいえない、ということか。
そもそも芝居小屋自体が「ここ」と「むこう」の境い目の象徴なのである。(p.302)
舞台の話である。最近は、いろいろなところで「舞台裏」「プロセス」を「公開」する傾向が流行っている。神秘性より親近感が優先される世の中になってきた。それだけ、人々の心が不安になってきているということなのかもしれない。
しかしここで重要なのは、そのような芝居小屋にはつねにいくつもの境界が仮設定されていたということである。(p.304)
芝居小屋というものは、特に境界を意識したつくりになっているのだな。
芸能は境い目を好む。では、芸能が境い目に発生したのはなぜなのか。境い目は弱いものたちが集うところであったからである。では、なぜ、境い目には弱いものたちが集うのか。それは、境い目に強い神をおいたからである。(p.304)
上の文章では、弱いとか強いとか区別された書き方をしているが、弱さと強さは実は表裏一体ではないかと思う。だいたい、芸能人とか有名人になる人とというのは、不遇の生育環境で育ってきたというエピソードが非常に多い。そしてハングリー精神で強くなって有名になるという物語は非常にありがちである。その過程そのものが、まさに「境い目をまたぐ」生き様だと思う。「境い目をまたぐ」経験こそが、芸能の場において、大きな力になるのかもしれない。だから、平凡で、居場所の確保された、最初から恵まれたような人は、芸能の場に向いていないのかもしれない。
ヘカテ―(p.304)
古代ギリシアの境い目に立つ強い神らしい。ヘカテーがわからないとギリシア経由のヨーロッパ最古の民間神話の構造はほとんどわからない、とまで書かれている。グレートマザーとか、冥界神とかとも書かれている。重要そうなので、メモとして書き残しておいた。
そのほか多くの弱者の兆候をもった者たちを追放し排除するための祭祀が境界神の祭祀の裏で進行した。節分として知られる追儺の行事にもそんなしくみが隠れていた。(p.308)
綱引きの話に続き、私たちにとって身近な行事である節分も、境界にまつわる行事だそうだ。「節分」という言葉自体がいかにも境界とリンクしているので、綱引きの話のほどのインパクトはないが、日本各地に、こうした文化は根付いているのだなと。
ちなみに、私は、今はわりと日本が好きなのだが、子ども時代は「日本的なもの」を忌み嫌っていた感覚があって、西洋に憧れ、世界史の授業のフランス革命の話などで気持ちが高まるようなところがあった。「日本的なもの」の何を嫌っていたかと今考えると、こういう「村八分」的な文化の雰囲気が嫌だったんだろうなと思う。日本文化の排他的な雰囲気、排除する側はきっと快適なんだろうが、自分は排除される側の人間だなという自覚があったため、忌み嫌っていたんだと思う。しかし、じゃあ西洋はそんなにすべての人に開かれた平等な文化なのかといえば、知れば知るほど、優越感に満ちた植民地支配の文化が根っこにありそうだし、どいつもこいつも大して変わらないと知ってしまうと、日本文化嫌いの気持ちは弱まっていった。現代社会を嘆き、昭和をやたらと輝かしい時代であるかのように回顧する人は多いが、全く私は共感できない。昭和の時代を大人として生きていたら、私は相当生きづらかったような気がすると直感する。今はわりと生きやすい。いろいろな物事の境界が曖昧になっていることで、境い目付近にいる人間にとっては生きやすい世の中になっていると思う。ただ、これまでマジョリティだった人にとっては、生きづらい世の中になってきているだろうし、その息苦しさが、人数が多いだけに世界中を覆っていて、世界全体が苦しそうな印象はある。何か突破口をみつけられたらいいなと思う。
多くの境界神がしばしば杖をもっていることが気になる。(p.311)
この文章を読んで頭に浮かんだのは、映画「DESTINY 鎌倉ものがたり」に登場する、安藤サクラが演じていた死神である。この映画は、珍しく映画館で鑑賞した。ちょうど境界のところに死神が立っていて、杖も持っていた記憶がある。2017年の映画でクリアに覚えているくらいだから、よほど印象的だったのだろう。
男鹿半島のナマハゲが木製の刃物をもってあらわれるのも夕刻で、その声はたいそう呪文めいている。(p.312)
境界をまたぐタイミングはトワイライトな夕刻と決まっているそうだ。夕方という時間帯自体が、昼と夜の境界だからかな。ナマハゲの由来も気になる。
おびただしい事例を駆使したうえでの赤坂の結論は、境界が生んだ境の民にとって杖はスティグマであり、現世と異界を分けるシンボルであり、その杖の本来はもともとは柱や樹だったというものである。(p.313)
赤坂憲雄『境界の発生』(1989)の「杖と境界をめぐる風景」に書かれた内容を受けての、上の文章である。またしても登場した「スティグマ」という言葉。やはりピンとこないなあ。この言葉、すごくモヤモヤする。まあ、とにかく現世と異界を分ける象徴として杖があるとのことだ。
杖は特権の標識でもある。(p.313)
たしかに、子どもとか、大人でも、平社員には杖は似合わない。ある程度年を重ねた人でないと似合わない。杖があることはある意味、弱さの標識でもあると思うのだが、「弱さを表に出すことを許される特権」、という感じなのだろうか・・・?
「弱者の特権」(p.314)
弱法師たちのもつ杖、すなわち「よろめく神」のもつ杖こそは、どんな社会の強さ にも勝る象徴力を、ある場面にかぎっては、いっとき発揮することができたのである。(p.314)
現代社会の重要な裏テーマのような気がする。女性、障害者、子ども、etc...弱い立場に立つ人たちを「守ろう」とする社会的な動きは今加速していて、それに対するアレルギー反応も実は水面下で起こっている。
弱さを弱さとしてだけ見るのではなく、人間は「育つ」ということ、生かし方次第で、これまでとは違った人間の輝き方があるかもしれないという「潜在性」「可能性」(深さ・豊かさ)といった側面からアプローチすることが大切な気がする。
では、このような杖をふるう者はどんな日々の実態をもっていたのだろうか。それを見るには、そうした人々の生きかたのギリギリの境界、すなわち差別と非差別のギリギリの境界をまたいでみなければならないようだ。(p.314)
次の節の話も面白そうだ。楽しみに読みたいと思う。
サポートして頂いたお金は、ライターとしての深化・発展のために大切に使わせていただきます。
