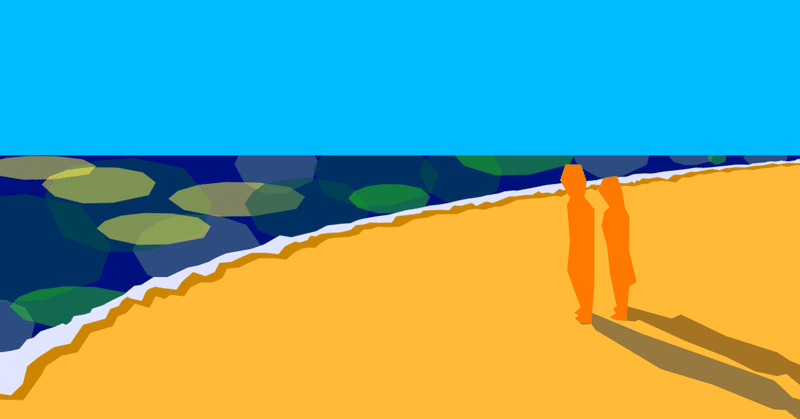
人は、目に見えない当たり前が過ぎ去った後に見える当たり前を幸せと呼ぶ。
<『毎日2分で人生に役立つ気づきが得られる小説』気づいた時から動き出すあなたの人生>
今ある幸せって何なのでしょうか。
蛇口をひねったらきれいな水が出てくること。
好きな時に好きな動画を見れること。
隣に大好きな人がいること。
今、ここにあると信じている幸せが僕にどれだけの価値をもたらしてくれているのか、高校生の時の僕は気づいていませんでした。
祖父が亡くなったのは、高校2年の冬休み前、期末テスト前日でした。
祖父は病気がちでここのところ入院と退院を繰り返していました。
僕が小学生の時の元気な姿と比べるとだいぶ痩せ細り、口数も少なくなっていました。
僕は小さい頃から家族とあまり話さない大人しい子供でした。
いや、大人しいというのはいい表現であり、本当は遠慮していました。
家庭の事情で父方の祖父母と一緒に生活を始めた2歳の頃から、僕にとって家庭とは居心地のいいものではない場所でした。
なので、祖父の体が弱くなり始めた時も、僕は高校生になったというのにも関わらず、どう接していいか分かりませんでした。
期末テストの前日、僕は教室で英語の授業を受けていました。
実はその日の放課後、入院している祖父のところへ行って顔を見せようと思っていました。
僕なりの接し方を考えていて、祖父にとって最後の孫である僕のちゃんとした姿を見せようと、そういう思いがあったからです。
以前にも何度かお見舞いに行っていましたが、祖父の様子は日に日に悪くなっている一方でした。
驚くほど早めに出てくる夕飯もあまり手をつけず、「味はどう?」と聞いたら「まずい。」と看護師さんが目の前にいるのに言ってしまうほど気も使えなくなってしまったのかと、がっかりもしました。
それでも「母親の代わりだよ」と言って僕のわがままを受け入れてくれた 祖父に感謝の気持ちは持っていました。
だからこうやって病院に来ているんだろうな、とも。
「もう、帰るね。」
そう言って寝ている祖父の近くに寄ると祖父は点滴がついている右手を僕の方に差し出して、「じゃあな。勉強頑張れよ。」と言いました。
僕は一瞬拍子抜けしましたが、祖父の目を見つめ直して右手を差し出しました。
強く握った祖父の手のひらは昔と変わらずシワシワで、少し冷たかったです。
僕の手の温かさがそのまま跳ね返ってきて、心が少し、冷たくなりました。
それが僕と祖父の最後の会話でした。
学校の帰り、兄から電話がかかってきた時、僕の心の中から、初めての感情が沸き上がってきました。
ジトジトしていて、暗くて、重い。
僕の体にのしかかったそれは一瞬のうちに僕の心を支配しました。
そして、それは涙として溢れてきました。
分からなかった。
何もかも。
理解できなかった。
何もかも。
信じたくなかった。
何もかも。
僕にとっての祖父はいつも当たり前のようにそこに座って新聞を読み、当たり前のように畑仕事をし、当たり前のように将棋の相手をしてくれる当たり前の存在でした。
しかし、今までの僕にはそれが見えていませんでした。
当たり前だったからです。
当たり前に会話を適当に済ませ、当たり前に目を逸らし、当たり前に恨んだりもしました。
そんな良いことも悪いことも含めた当たり前を僕は祖父と共有したかった。
ちゃんと当たり前が当たり前に僕の前にあることを確認したかった。
それが僕にとって一番大きな後悔でした。
今でもその残り香は僕の鼻の奥でくすぶっていて、たまに思い出してはゾワゾワした気持ちにさせます。
そしてその度に、祖父が与えてくれた当たり前を誰かに与えられるように、また僕が受け取れるようになりたいと願うのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
