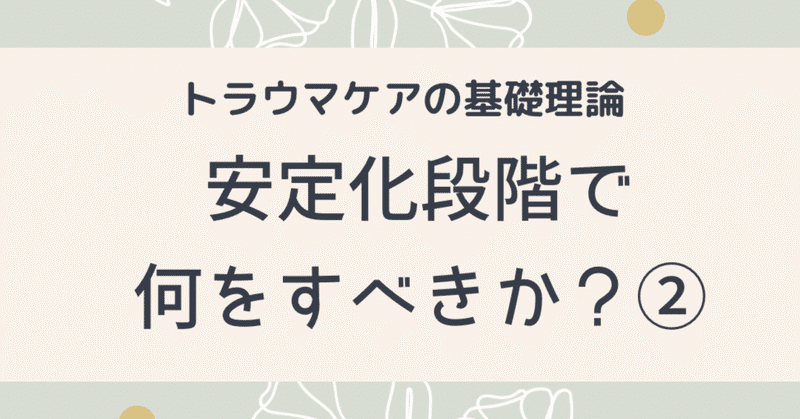
トラウマケアの基礎理論⑩ 安定化段階でなにをしていくべきか?② (トラウマケア EMDR 臨床心理士)
こんにちは、
うるま心理相談室ココロンの臨床心理士、とねがわです。
安定化についてのPart.2になります。
前回記事では、
・安定化はなぜ大切な事なのにほとんど知られていないのか
・EMDRでの行き詰まりサイン
・安定化とは、基礎づくりである
という内容について書きました。
↓↓↓↓
基礎が十分あるから、EMDRの処理が安全裡に進められるのですね。
今回はその基礎って何なのか?と言うことと、
実際に安定化段階でできることについて、
もう少し掘り下げて考えてみたいと思います。
※ちなみに今回の内容はあくまで私の考える「安定化」であり、
お読みの皆さんの背景まではわからないので、
絶対視せず、ヒントの一つとしてご覧ください。
すでに治療中の方は、ご自身のセラピストとの治療計画を優先してください。
主に参考にした文献はこちら。



EMDRから見た複雑性トラウマの治療の現在
EMDRは「トラウマ記憶の処理」を可能にする道を切り拓いた意味で、画期的でした。
その経緯はnoteで書いた通りです。
一方、EMDRが後世に残した課題として、
1,脳の情報処理に行き詰まりが起きるとき、その要因はなにか?
2,安定化でどんな準備性を高めておけば、それを回避できるか?
という論点が残されました。
そのひとつのキーワードとして「リソース」がありました。
前回書いたような、EMDRにおける
・安全のイメージが作れない
・堂々巡り
は、特に複雑性PTSDの治療で頻発する事象であり、
それはまさに何らかのリソースの不足があることを示しています。
しかし一方それらは、成育歴をたどれば無理もないことでもあります。
なぜなら複雑性トラウマを抱える人ほど、
・親子の関係性で苦しんでいた背景
・安心や安全を感じる機会などそもそもない状況だった
・苦痛や痛みを封印し、パーツを適応させることで生き延びてきた
・恥や罪悪感があって、自分をいたわる術を学ぶことが難しかった
・そもそも自分に何が起きているのかすらわからず、自分を責めるしかなかった
などといった背景があるからです。
ここを補強するために、安定化があります。
つまり処理に入る前に、
・安心感とは何かを掴む
・治療の見通しをもつ
・感情コントロールの仕方を身につける
機会を、セラピストとの間でつくる必要があるのです。
※ある程度、社会の中で健康度を保って過ごせている方にとっては、安定化段階は比較的早く済むことがあります。
とはいえ、人生で傷を持たない人はいないので、健康な人でもいくつか上記に重なる点がある場合は、手早く安定化作業を行います。
その作業を進めていく上で、
実際のカウンセリングでよく大切になるチェックポイントをまとめてみました。
今回、扱おうと思っているトピックは、
<目次>
1、治療同盟
2、心理教育
3、感情のアップダウンを静める
4、解離が阻むもの
5、身体の感覚が分からない
6、セルフケア 〜自分をいたわること
7、記憶に触れるのが怖い
8、愛着テーマ
9、その他
と多岐に渡ります。(今回は、1〜3までを書きます。)
1、治療同盟 〜その治療関係は安心か?
まず第一に、安心・安全の治療関係があるかどうか?です。
すべてはここに始まりここに終わる、といっても過言ではありません。
回復という共通の目的に向かって、
話し合いを続けていくための関係性を、
カウンセリングでは「治療同盟」と呼んでいます。
すごーく簡単にいえば、
「何でも言い合うことができて、話し合える関係」
のことです。
人間どうしのことなので、
治療同盟は初めからあるわけではありません。
カウンセリング全体を通して、一緒にコラボしてつくっていくところがあります。
複雑性PTSDの症状のひとつには、
「対人関係の構築の困難」があるため、ここをちゃんと安心できるものにしていくことはとても重要なポイントです。
まず、相談しようと思えたことがすごいのです。
コミュニケーションを重ねて、
風通しの良い関係をつくっていくことは、
トラウマ処理をしていく上での大切な足場になります。
2、心理教育
・「自分に何が起きているのか、わからない」状態に向けて
多くの方にとって、トラウマ反応はそうと言われるまで、自分でも気づいていないことが多いです。
脳による自動的な反応だからです。
・まるでジェットコースターに乗っているような気分の上下のアップダウン
・突然蘇ってくる過去の感覚や記憶(フラッシュバック)
・理由もなく泣きたくなったり、イライラがとまらないとき
・そういう自分への自己嫌悪
は、実は過去のトラウマ状況への「対処の名残り」であり、
生き延びるために必要な反応だった、
ということを、情報としてまず伝えることを「心理教育」と呼びます。
ただ知るだけでも、それまで自分を苦しめてきた症状の正体・仕組みがわかるだけで、
ぐっと楽になる方が多いです。
拙著のトラウマケアの基礎理論シリーズは心理教育の目的で書いています。
・認知再構成
自分を苦しめてきた反応ひとつひとつが、それは実は必要な反応だった、
と意味づけを転換していく作業を、認知行動療法では
「認知再構成」と呼びます。
認識が変わると、それに対する私たちの構えが変わり、
行動を選択し、選べるようになります。
「過覚醒で頑張り続けることが、自己価値を保つためにどうしても必要だ」
という認識を持つ人に対して、
いきなりリラクゼーションを入れても逆に不安を高めたりするのは、
この認知のテーマが絡んでいるから、ともいえます
3、感情のアップダウンを静める
トラウマが背景にある方の場合、
不快な感情や記憶が出てくるのを防ぐため、
あえて忙しくすることで、気を紛らわせて適応している人もいます。
しかし限界ラインを越えると、その後電池が切れたように、
動けなくなってしまうため、
こうした気分のアップダウンに苦しんでいる人も少なくありません。
ここで重要な安定化のテーマは、
複雑性PTSDの症状の一つでもある、「感情調節の問題」です。
・生活タスクを減らす試み
凪の状態をつくることが、EMDRに入る上で必要不可欠です。
そのため、ケースによっては
具体的な生活上のタスク・負荷を減らすための
話し合いをもつことも必要でしょう。
意識の覚醒度合いを上げるために、カフェインや炭酸水などを好む人もいます。
そうした外の刺激量をコントロールして、
気分の波の振幅を穏やかなものにしていきます。
・耐性の窓
そこで大切になる視点は、「耐性の窓」です。
意識の覚醒度を3段階に分け、
真ん中のほどよい凪の状態=「耐性領域」
にいれる時間を長くします。

・上のゾーンが過覚醒で、警戒し、気を張って過ごしている状態。
・真ん中が安心している状態
・下のゾーンが低覚醒で、シャットダウンし、動けない、抑うつの状態
です。
こういう方がけっこう多いので、
↓↓↓↓

なるべくこういう状態を目指します。
↓↓↓↓

実はこんな感じをしている。
ただ、あくまで「なるべく」なので、多少の上下は仕方ないと思います。
①自分で気づけること、
②上下に振れても、戻ってこれるスキルがあること、
が、あくまで大切です。
その他の気分の波のパターンについては、私のインスタ記事もご覧ください。
(横にスワイプするとその画面のまま読めます)
また、「適応的防衛」といって、
・高止まりしている方が、(主観的には)安定している感じがする
・低覚醒で推移する、低空飛行がメインのため、上げるのは逆にきつい
という人もいます。
安心(まんなか)を体験したことがないためです。
体験したことのないものを、無理に作ろうとしても、むりです。
なのでこの場合は、無理には推し進めません。
また、ここにはいわゆる「パーツ」が関与していることが多いため、
パーツワークを用いながら、パーツにとって納得できる範囲で、
調整可能な方法を探します。
(無理にやるとパーツが反発するので、ほんとにむりしない)
依存症・嗜癖という対処
ちなみにですが、依存や嗜癖行動は、この防衛的適応に関連しています。
気分を高い状態で維持するために、カフェインなどの刺激物に依存するのは、真ん中に戻らないようにする意味で、本人にとっては必要な対処です。
また、睡眠に入る前に、高すぎる覚醒状態を下げないといけないため、
アルコールを用いることも、本人にとっては必要な対処です。
低覚醒に入ったときに襲ってくるフラッシュバックに対して、覚醒度合いを上げて現実感を取り戻すために、
・リストカットをする
・薬物や性、ギャンブル
・過食をする
など直接刺激を身体に入れて、覚醒度を取り戻す試みも、本人の立場に立てば必要な対処と言えます。
ただ長い目で見ると、身体に負荷をかけていってしまうため、
どこかでちょうどいいコントロール方法を探していくことが望ましいと言えます。
それも、安定化で行う大切な作業です。
安定化はなかなかに奥が深い
ひとつひとつ解説していくと、非常に紙幅を使うことがわかったので
一旦ここで区切って、③に記事を分けます。
次回は、皆様にとって悩みのタネと思われる
「解離」「身体感覚」などのテーマから始めます。
続きをどうぞお待ちください。
お読みくださり、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
