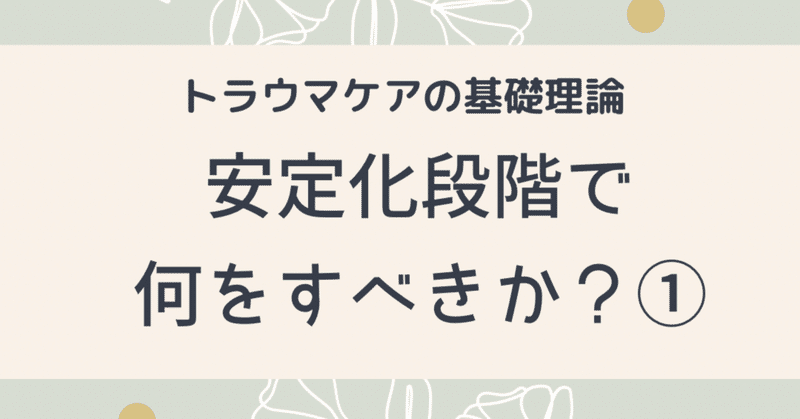
トラウマケアの基礎理論⑨ 安定化段階でなにをしておくべきか① (トラウマ治療 カウンセリング)
こんにちは。
うるま心理相談室 ココロンの臨床心理士、とねがわです。
昨今、話題になっているトラウマケア。
そのトラウマ治療には、いくつかのステップがあります。
トラウマ治療の3段階については、私のnoteでも以前に紹介しました。
復習をかねて、ざっと書くと
ステップ1、安定化
ステップ2、トラウマ記憶の処理
ステップ3、再統合
の3ステップ。
ちなみに上記提唱者のジュディス・ハーマンの新著では、
ステップ4:「(社会的)正義」
があるのではないかと論じられています。

トラウマ治療の方法は、近年爆発的に増加しており、喧伝のされ方もさまざまです。
ただトラウマ治療を受けようと考えている方に、事前に知っておいていただきたいのは、
ステップ2の治療法には、その効果に、いわばある「但し書き」がある、ということです。
それは、
「クライエントに十分な安定化がなされていることを前提とする」
という(暗黙の)一文です。
「安定化とはなにか?」について、
一般人の方で答えられる方はおそらくほとんどいないはずです。
「安定化」とはなんなのでしょうか?
「何の」安定のことなのでしょうか?
何がどう安定すれば、適切な効果が得られるのでしょうか?
それを、書いていこうと思います。
なぜ安定化は知られていないのか?
なぜ安定化という概念は知られていないのでしょうか。
そのわけの一つとして、安定化という発想は
主にトラウマ治療の専門的なトレーニングを積んでいる心理士にしか知る機会がないことが挙げられます。
したがって、こころの専門家である臨床心理士の中でも、
安定化についてはまだ浸透しきってはいません。
むしろ、もしかしたら知らない人の方が多いかもしれません。
臨床心理系大学院のトレーニングで、安定化は教わらないのです。
というか、基本的に通常の大学院において
・トラウマ治療のやり方や
・愛着トラウマ、
・発達性トラウマ
・解離の対応
については教わりません。
実際に仕事をし始めてから、知るのです。
お金をかけて勉強をします。
ちなみに私がどこで知ったかというと、
・最初はEMDRのトレーニングで、
・その後実際にクライエントとEMDRを試みた中で
です。
また、もう一つの理由として挙げられるのは、
「各種の治療方法だけが一人歩きしていて、トラウマ治療全体についてのエッセンスが周知されていない」
こともあります。
これは私たち専門家にも責任があるかもしれません。
万能なものへの憧れは、人間誰しもあるものですが、
誰にも100%効く、万能な心理療法というのはありません。
今日の安定化がなぜ必要かという話は、その辺りとも関連してきます。
トラウマ治療に関わって初めてわかる「安定化」の意味の重さ
私はトラウマケアについてはEMDRを基本としているので、その文脈から書きます。
EMDRを実施していく中で、安定化が必要とわかるケース例とそのサインをみてみましょう。
サイン1:安全なイメージ
EMDRでは実際のトラウマ治療に入る前、ある練習を行います。
それは「安全な場所のワーク」です。
眼球運動を用いて、安心のネットワークにアクセスしていく作業です。
これはトレーニングの中でも、実施することが強く推奨されています。
これをやっているとあることに気づきます。
・安全のイメージにスッと入れる人 と、
・安全なイメージがそもそも思い浮かばなかったり、あっても入れない人
の2種類です。
後者の場合、思い浮かばないのみならず
逆にトラウマ記憶のイメージが侵入してくる時すらあります。
実は、これが「安定化」が必要なサインの代表例その1です。
この場合、EMDRの実施をとりあえず見送り、
例の「安定化」作業に入ります。
サイン2:堂々めぐり
色々ありつつも安全な場所のワークが終わり、無事EMDRに入ったケース。
いよいよトラウマ記憶に入っていったそのとき…問題が発生します。
「EMDRで眼球運動をして記憶処理に入ったんだけど、しんどい場面からなかなか抜けられません」
「考えがずっとループしてしまって、特に変わりがありません」
「なかなか楽になりません」
…これがもう一つの代表的なサイン、「堂々めぐり」です。
この場合、そのままEMDRを続けても、
トラウマが十分な解消に至らない可能性が高いため、安定化を見据えた、EMDRの応用が必要になります。
何が起きていたのか?
サインを示した2つの状況で足りなかったもの。
それは、「リソース」です。
「リソース」とは、その人が困難を乗り越える際、心理的に活用可能な、
ポジティブな材料・資源のことを指します。
具体的には、
・人生におけるプラスの体験・記憶
・安心の神経回路
などです。
EMDRは脳の情報処理を加速させる技法ですが、
脳が自然処理として、出来事を過去として終わらせられないでいるのには、
それなりの理由があります。
それが、このリソースの不足によると考えられる、
脳処理の「スタック(行き詰まり)」状況です。
この行き詰まりを解消するために、トラウマセラピストたちは日夜勉強をし、必要があればその他の技法も学んで補いながら、治療にあたっているのです。
EMDRの必要十分条件
したがって、EMDRを行うまず必要十分条件は、
・この安心の神経回路や記憶・イメージに脅かされることなく
アクセスできること、
・その上に立って、ターゲットとなるトラウマ記憶から
距離をとって眺められること
だと言えます。
=安全な「いま・ここ」の土台に立ちながら、片足だけ過去につっこんでいること。
この状態をEMDRでは、「二重注意」の状態と呼びます。
「いま・ここ」が安心である状況において初めて、
脳は情報処理のスタートラインに立つことができます。
「いま・ここ」が過去に脅かされ不安定である状況のままでは、
クラウチングスタートする時の、スタートの姿勢が大きく崩れて始まってしまっているのです。
ふりかえると、
先の2つのサイン例「安全なイメージが作れない」「堂々めぐり」
で示したようなケースの要因は、いくつか考えられます。
・安心の神経回路を刺激することが、逆に不安のトリガーになっている
・ネガティブ感情に持ち堪える対処スキルが不足している(=過去に呑まれる、情緒的に揺れやすい)
・トラウマ状況を乗り越えるための、必要な経験・視点が足りない
・愛着テーマが解消されていない
・解離があるため、処理がブロックされている
などです。
どれも専門的な表現でむずかしいと思います。
すべて理解はできなくとも大丈夫です。
これをすべて解消してからでないとEMDRできないのか?と問われれば、
「それはケースとその流れによる」としか言いようがないのですが、
(フロイトの喩えを用いれば、
「チェスの盤面の進み方はいつも一つには限らない」ように)
少なくとも、EMDRが成功裡に終わるには、
これらの条件が自ずと順番は違えど解消されているからと考えられます。
(強いていうなら、解離に対する対応と知識は必須であると思います)
安定化は「基礎づくり」の作業
安定化とは何かといえば、人によって不安定化している箇所は違うため明言が難しいですが、
安定化はいわば「基礎づくり」にあたります。
強い苦痛にさらされてもなんとか保っていられるための基礎です。
一方、専門家側のテーマとして考えてみれば、
「セラピスト自身の、人と人生を診てとる力、そして支える力」の成熟
が必要ではないかと、この文章を書いていて私は感じました。
EMDRやその他トラウマ治療の手段は、あくまで無意識のテーマを開く「キー(鍵)」であり、
そのキーを使って扉を開けるとき、細心の注意が求められます。
その扉の在り処と注意を示す役割と、後ろから勇気づけ支える役割が、私たちセラピストです。
扉を開けること自体はクライエントであるあなた自身にしかできません。
焦らず、じっくり安全なペースで進めてください。
皆様がよいセラピストと出会えることを、心から望んでいます。
さて、安定化のコンセプトを掴んでもらうための文章は、
このくらいで大丈夫かとは思います。
次回は、安定化で実際にどんなことをするのが考えられるかを、
私なりに書いてみたいと思います。
どうぞお楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
