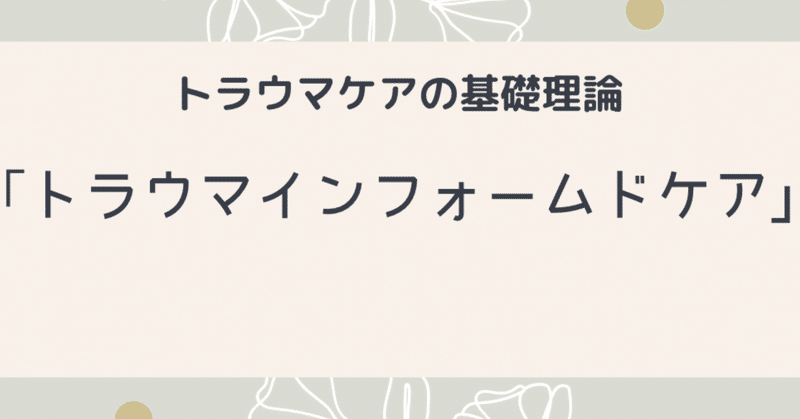
トラウマケアの基礎理論④ トラウマインフォームドケアについて
このシリーズでは、トラウマケアについての昨今の知見を紹介しています。
さて、ここまでシリーズ①〜③で、こころ傷つきが現在に及ぼす影響はどんな形を取ってくるのか?について書いてきました。
それは現象を拾ってみると「複雑性PTSD」というグループでくくることができるかもしれない、ということでした。(もちろんこれが全てではないのですが…)
前回の投稿についてはこちらを参照↓
が、そろそろ「じゃあ実際どうすればいいんだ?」という声が聞こえてきそうです。
そこで今回は対応面についても少し触れて行きたいと思います。
これはどちらかというと、当事者向けというより、その方の周りにいる、家族や学校の先生、支援者、友人知人の方々に向けての情報になるかもしれません。
まず、トラウマに対応する際、我々に必要になる大切な視点があります。
それは、「トラウマインフォームドケア」です。
トラウマインフォームドケアとは
トラウマインフォームドケアについては、下記の著書が詳しいです。
改めて目を通すと、非常にいい本でした。
対人援助職に関わる方はぜひ目を通されて損はないと思います。
トラウマインフォームドケアは、1990年代後半から米国で用いられるようになった考え方です。
主にACEs研究(小児期逆境体験の研究)と、フェミニズム運動による女性のトラウマサバイバーに関する研究をもとに、精神疾患やアディクション(依存症)へと、知見が応用されてきた発展の背景があります。
一言でいうと、「日々の対応の中にトラウマによる影響という視点を織り込んで関わっていくこと」と言えるでしょうか。
ざっと要点をかいつまむと、
トラウマインフォームドケア(TIC)は,対象者の言動をトラウマの「メガネ」で見ることから始めるアプローチです。
暴言や暴力,怠惰や無気力,嘘やごまかしなどを“問題行動"と捉えると,支援者は相手を叱責したり,拘束したり,追い立てたり,非難したりしてしまいます。支援者自身も,傷つけられたり,裏切られたと感じたりして,無力感を抱きやすくなります。
しかし,そうした言動が表れた状況を探っていくと,何らかのきっかけ(リマインダー)によるトラウマ反応である可能性が見えてくるかもしれません。
(中略)
臨床現場で新たな傷つきが生じることを防ぐために,すべての対人援助職が身に着けておくべき公衆衛生的アプローチがTICです。
ということです。(引用って便利。)
本書に沿って、中身にちょっと触れましょう。
野坂さんによると、トラウマを抱えている人に私たちが接したとき、その対応は大きく分けて3つのレベルに区分けできます。

Informedが「全体の入り口」
Responsiveが「より個別的な対応」
Specificが「専門家レベルのケア」、
と言えそうです。
それぞれのレベルの対象と、対応の中身は下記になります。

このように、レベルによって、できることとやれることは異なります。
それぞれにできることをやっていければいいのだと思います。
予防、という観点で見ると、以下のように分けられます。

トラウマによる影響は、
「知っていないと対応できない」し、
「知らないと見えない」
ところがミソです。
したがって啓蒙が必要です。
(その目的で私も記事を書いています)
3つのレベルでできることと、簡単なポイントを、書いてみます。
1、一般的なトラウマの理解と基本的対応(Informedレベル)
トラウマインフォームドケア(略してTIC)は、ケア全体の基盤に位置付けられる。トラウマの知識を踏まえた理解や対応を行うものであり、支援者はもとより、本人、そして社会全体にトラウマの基本情報が周知されている状態が目指される。
トラウマはいわば「こころのケガ」であり、
例えるなら「からだのケガ」をした人に向けて社会がバリアフリーにデザインされるように、トラウマのある人の心理的障壁をなくすために、相談しやすい環境や体制を作っておくこと、と言えます。
一般的に、こころの傷つきの深い人ほど、感情調整や対人接触に困難を抱えやすく、
生きづらさを感じており、一方で周囲からは理解しづらいために、
「手のかかる人」
「問題児」
「かまってほしい人」
「対応の難しい人」
とみなされ、無理解にさらされやすい傾向があります。
逆に、全く手のかからないように、痛みを人に見せないことで適応している人もいます。(その方が気づかれにくい)
ご本人にとっても今の状態がトラウマによる影響だと知らないことも大半で、
・内容を触れられること自体をご本人が恐れていたり、
・人に話して蓋を開けると出てきたものを引きずってしまうので話したくなかったり
・人に話して否定された体験が残っている(=再受傷)
そのために誰にも相談しない、ということが起こります。
ご本人も触れられないものを他者が気づくことはできません。
なので、周囲には余計に訳が分からず、気づいた頃にはご本人がダウンしていたり、相談できる人がいない、誰もお手上げの状態に陥ることも珍しくはないと思います。
この時、背後で働いていやすいものが、「回避」や「侵入症状」「否定的認知」などなのです。
だから、その時「何が起こっているのか?」「なぜご本人は誰にも話そうとしないのか?」を周囲が知っておくことが大切なのです。
それを知っていることで、
・「もしかしたらこれは回避が今出ていて、今はまだ内容に直接触れるタイミングではないのかもしれない」
・「相手が安心を感じられるアプローチから入ろう」
と対応が変わっていきます。
第1段階の目的は、まず周囲が「気づく」こと。そして「安心してつながれる関係になる」ということでしょう。
2、トラウマに対応したケア
第1段階のTICによる対応をする中で、こころのケガの影響がある人がいたならば、次の段階のトラウマレスポンシブケアに繋げて行く。レスポンシブとは、その人自身のトラウマの内容に合わせて対応するという意味である
ここでは、さらに個別の事情やトラウマに特化した、知識の提供(心理教育と呼びます)や、対処スキルを教えていきます。
具体的には、
・トラウマ反応のメカニズムを伝える
・リラクゼーションの方法を探す(呼吸法、タッピングなど)
・グラウンディング(現在に意識を戻す方法)
・ノーマライズ
・感情調整の必要性の理解
・現実生活で過覚醒⇄低覚醒を行き過ぎないようなタスクや仕事量を減らすなどの調整
を行います。
第2段階の主要な目的は、「トラウマの影響を最小限に抑えること」です。
そのためには、
①自分の状態を理解し、
②トラウマ反応をマネジメント(管理・調整)し、
③ご本人の回復力(レジリエンス)を高めるよう促すこと
が、焦点になります。
3、トラウマに特化したケア
トラウマの第3段階は、明確に分かれているわけではない。トラウマレスポンシブケアやスペシフィックケアにおいても、TICのアプローチが基盤となっており、それぞれの段階で取り組まれる課題も重複している。それぞれを別のステップと捉えるというよりも、TICを基礎としながら、より特化した専門的な介入を積み上げていくのである。
そのため、TICの基本的な取り組みをせずに、最終段階のトラウマスペシフィックケアだけ実施しようとしてもうまくいかないことが多い。いきなりトラウマ記憶を扱う心理療法を行おうとすれば、本人は抵抗を示し、一緒に取り組んでいく支援者たちもどんなふうにサポートすれば良いかわからず、トラウマ治療を回避してしまうことがある
上記のように、3段階目は専門家が伴走していく段階ではありますが、内容は第2段階目もかなり含んでいます。
私自身も、カウンセリングの最初は第2段階のケアから入ることがほとんどです。
そうして安心・安定感を増していく取り組みを経て、ご本人とセラピストの間で合意ができた時に初めて過去の記憶の処理を目指していきます。
トラウマ記憶の治療法は研究が進んで、いくつかあります。
代表的なものを挙げると、国際トラウマティック・ストレス学会がガイドラインで推奨する治療法には3つあります。これらは治療効果を示す科学的な根拠があるものです。
1、トラウマ焦点型認知行動療法(TF-CBT)
2、PE(持続的エクスポージャー)
3、EMDR(眼球運動による脱感作と再処理)
上記の3つはたとえ心理士でも、指定されたトレーニングを受けないと実施することができないもので、全ての心理士、精神科医が行えるものではないですが、いずれかのトレーニングを受けた人はトラウマについて基礎的な知識を持っている支援者なので、こういった方から探されるといいと思います。
それぞれの学会HPには治療者リストが挙げられているものもありますので、ご参照ください。(※ココロンの臨床心理士は、EMDRの治療者リストに登録されています)
それ以外にも、エビデンスレベルが上記3つまではいかないにしても、トラウマケアの治療法は沢山あり、いずれもそれぞれ長所と短所があります。
それはまた追って案内しましょう。
まとめ(私見含む)
あなたの目の前にいる人に、どんな対応が必要なのかは、どんなトラウマを受けたのかも、その程度も、ケースバイケースのため、最初からはわかりません。
第2段階である、「その人の事情に立った個別的なケアの方法」がわかるためには、「ご本人が相談につながる」必要があるのですが、トラウマを生き延びてきた人の場合、そもそも人とつながるためのスキルや、人と対面する自信を持てなかったりするために、その相談につながるまでの間に長い道のりが必要です。
だからそのために「第1段階」があります。
周囲にいる人が「トラウマインフォームドのメガネをかける」ことで、トラウマを可視化し、存在に気づいていることで、まず「トラウマがあることはお互い知っているけど、無理に蓋を開けられることもない、無理のない安心できる関係」をつくることができれば、自然なタイミングで、「一緒に相談に行ってみよう」と声をかけれます。
信頼できる人の探してくれた相談機関や、その人が信頼できると判断した人物ならば、「少しくらいなら会ってみてもいいかな」と思えるかもしません。
あるいは、その人が一緒に付いてきてくれたら、怖さは軽減するかもしれません。
今はまだだな、と相手が思ったなら、どこらへんに怖さがあったのかな、と信頼できる人と話し合うことができます。
あるいは、ご本人が繋がるまでの間、ご家族や友人が、代わりに先に相談につながることもできるでしょう。
そうしてトラウマインフォームドな関わりが何かを周りが知り、個別の事情に合わせたオーダーメイドな対応をご本人へ実践することができれば、ご本人の生活は楽になるはずです。(これはもう既に第1→第2段階に足を踏み入れています。)
そうしてご本人にとっての安心を増やし、回復に向かっていくプロセスを、本人のペースで共有し、寄り添ってほしいのです。
いきなり専門機関に引っ張っていかなくともいいです。「あなたとの信頼」が、「いつか誰かとの信頼」に橋渡しされる日が必ず来ます。
トラウマインフォームドケアとはそういうことなのかな、と今回記事をまとめていて思った次第です。
(野坂先生の「トラウマインフォームドケア」の本は、非常に広い射程を持った本でよかったので、また次回取り上げたいと思います)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
