
トラウマケアの基礎理論(12) 安定化段階でなにをしていくべきか?③ (トラウマケア EMDR 臨床心理士)
トラウマ治療における
安定化について、Part.3になります。
タイトルが(12)なんだか、③なんだか、いい具合にとっちらかってきましたが
一応、シリーズものです。笑
Part.1・2はこちらから。
Part.1
Part.2
※今回の内容もあくまで私の考える「安定化」であり、
お読みの皆さんの背景まではわからないので、絶対視せず、ヒントの一つとしてご覧ください。
すでに治療中の方は、ご自身のセラピストとの治療計画を優先してください。
・安定化記事のシリーズ全体の目次
<目次>
1、治療同盟
2、心理教育
3、感情のアップダウンを静める
4、解離が阻むもの
5、身体の感覚が分からない
6、セルフケア 〜自分をいたわること
7、記憶に触れるのが怖い
8、愛着テーマ
9、その他
今回は
・「4、解離が阻むもの」
・「5、身体感覚がわからない」を扱います。
4、解離が阻むもの
前回記事で、「解離とは何か?」について説明しました。
そこでの要点をまとめると、
解離には、
1、「だれの」経験か? (所有感覚)
2、「いつの」経験か? (時間感覚)
の2つがわからなくなる。
という特徴があり、
分離された体験は、
まるでジグソーパズルの絵の中で「ピースの欠けがある」=穴が空いているような状態にも喩えられる、ということです。
端的にいって、
解離によってEMDRの処理が妨げられる理由は、
体験の「時間感覚」と「所有感覚」の混乱があるために、
脳の「統合」の作業が阻まれているからだと思われます。
(なんだか壮大な話ですね。)
「解離」の反対は、「統合」なのです。
この点を踏まえ、安定化段階で解離に向けて必要な準備は3点に絞れます。
(1) 現在化の促進
(2) グラウンディングスキルの構築
(3) パーツマッピング
(1) 現在化の促進
EMDRで大事なのは「二重注意」を維持できること、でした。
それは、「いま・ここ」に留まりながら、
「それは過去だったよね」
「いまは終わっているよね」
と(ドキドキはするけど)冷静に眺められる視点のことです。
先に述べた「耐性の窓」をヒントに考えると、

現在化とは、
「真ん中のほどよいリラックス状態にいれること」です。
カウンセリング内で言えば、
考えながら、(感情を)感じることが同時にできる、という状態です。
耐性領域の外に(上と下)はみだす時のサインとしては、
・感情が氾濫して涙が止まらなくなる
・過去の出来事に、ことばで触れるだけで動揺する
・記憶に圧倒される(ひきずる)
であり、
こういうときは、もう少し現在化のスキルを安定させる必要があります。
そこで役立つのが、
次に述べる「グラウンディング・スキル」です。
(2) グラウンディング・スキルの構築
まだ記憶や感情に圧倒される時があるーーーー
そこでなるべく意識を真ん中に戻す作業が必要なので、
そこで一般的に行われるのがグラウンディングです。
グラウンディングとは、
直訳したら「地に足がついている」という意味で、
要は「いま・ここ」にいる感覚のことです。
例として、
もしあなたが今、椅子に座っているか、
ベッドに寝ながらこの記事を読んでいらっしゃるとしたら、
・「足の裏や、背中が、地面や背もたれに接地している」感覚
に意識を向けます。
ただそれに気づきます。
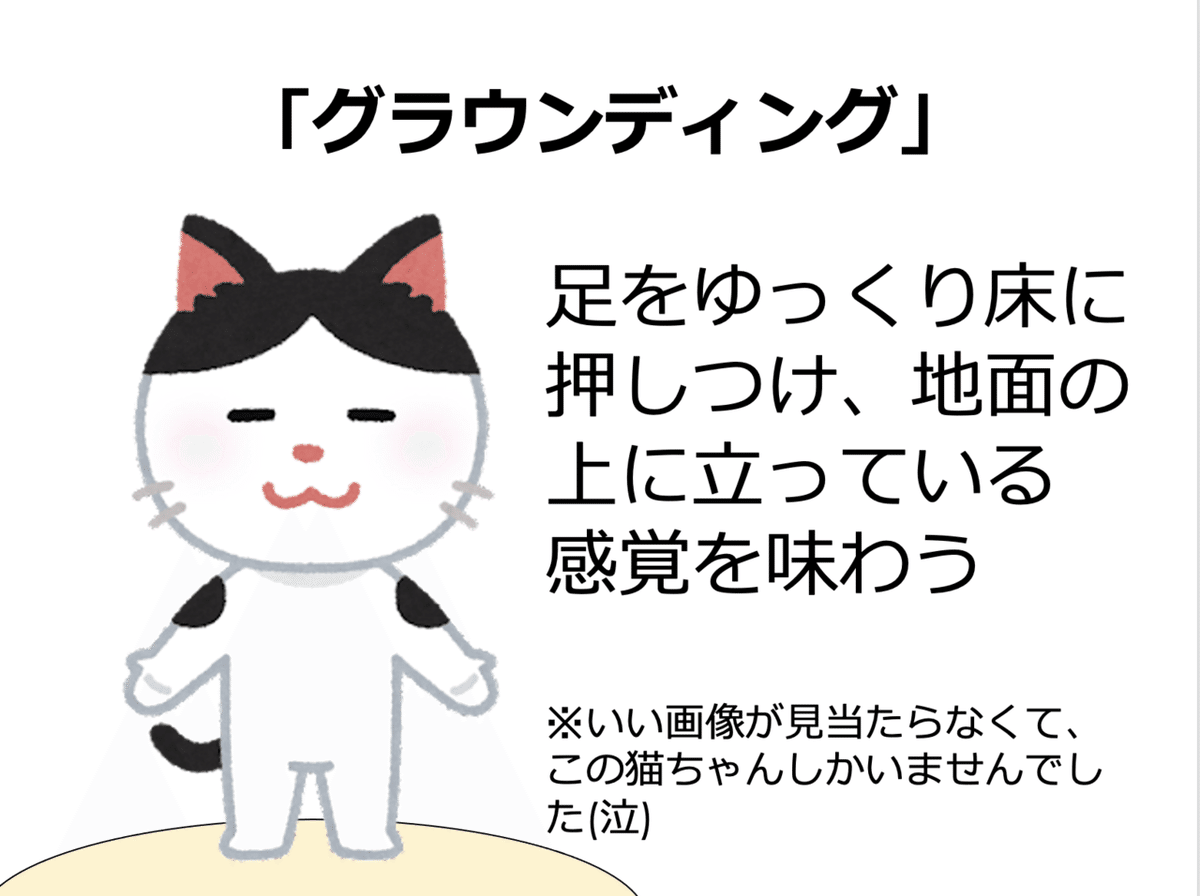

あったのであった
そこで、ちゃんと意識がここにあるな、という感覚に気づきます。
※水を飲むでも、何か食べる・youtubeをみるでも
我に帰ることができればなんでもOK!
以前にインスタでまとめた現在化の方法も貼っておきます。
・フラッシュバックの終わらせ方
現在化の方法は、実はフラッシュバックの対処そのものでもあります。
なぜなら、フラッシュバックとは、
まさに時間感覚の混乱で、脳が過去に飛んでしまっているような状態だからです。
ここでもキーワードは「現在化」です。
グラウンディングを試してみて、
意識が現在に戻ってきたかどうか?の確認としては、
BHS(バックヘッドスケール)というものさしが使えます。

フラッシュバック/低覚醒時に、
意識が過去に行ってしまっているときは、
・ぼーっとしている感じ
・意識が少ーし頭の後ろの方にあるような感じ
・いま、ここにいない感覚
としてわかります。
「あっ!これはフラッシュバックだ!まずい!」
とまずは気づいて、
グラウンディングをしてみて、
ちゃんと意識が「0」=いまここ、に近づいているかを確かめます。
(そしてくりかえします)
原理として、
過去から現在にある安心に意識を戻すことができると、
フラッシュバックは収まります。
フラッシュバック(背側迷走神経)自体が遅発的なところがあるので、
収まるのに時間がかかるかもしれませんが、
「現在」の安心をONにするのが大事です。
詳しくは、こちらの記事の中盤にも書いてあります。
(3) パーツマッピング
次に解離の対処として、「3、パーツマッピング」です。
パーツってなに?についても、過去の記事で説明しています。
▪︎解離とはなにか
要は人格の断片化(=所有感覚の喪失)が、
もうひとつの解離の特徴でした。
これはジグソーパズルの全体から分離してしまったピースのことです。

EMDRに入る前に(あるいはやっている途中に)、
それぞれのパーツが人生のいつの時点で立ち往生しているか?
を大体でいいのでマッピングして、把握しておきます。
必要があれば、立ち往生しているパーツにアクセスし、話を聞きます。
これが「時間の定位」です。
また、EMDRを行っていいかどうか自体を、
パーツ達に確認することもあります。
納得できていないパーツがいれば、
そのパーツの気持ちに寄り添うことを優先します。
その時もEMDRを中断します。
・パーツは意味があって存在している
代表的なイメージとして、
・自責のパーツ
・過食や自傷をするパーツ
・過活動で頑張ろうとするパーツ
などがあります。
彼らは必要があって存在しており、
過去を生き延びるのに役立った対処を、今も試み続けています。
また、パーツなりの必要性があって、
「痛み」や「恥」に触れることから、
「私」を必死に遠ざけようと努力していたりします。
それがEMDRにおける処理をストップさせることがあります。
「守ってくれている」のですから、
無理に手放させようとするのではなく、理解と共感を持って
迎えていくことが肝要です。
パーツワークは特に専門性が求められるところなので、
解離性障害のトレーニング(パーツワークの訓練)
を受けていない人は、くれぐれもやらないでください。
・それでも処理中に解離が起きることもある
それでもEMDR中に、強い衝撃が想い起こされると、
解離で意識を飛ばすことで対応する人もいます。
これは別にまずいことではありません。
解離があるかないか?ではなく、
どうやって戻ってこれるか、が重要です。
そのためにグラウンディング・スキルの習得を
きちんとやっておきたいところです。
5、身体の感覚がわからない
最後に、もうひとつEMDRの準備段階でよくあるサインがあります。
それが、「身体の感覚がわからない」です。

(1) 身体とつながることで、初めて自分の中で起きていることがわかる
最近、「マインドフルネス」というのが流行っていますね。
自分の内側に目を向ける、という意味でEMDRにおいても
「マインドフル」であるスキルは重要です。
なぜなら、いわゆる、
「トラウマは身体に記憶される」からで、
身体も記憶とつながるひとつの「窓」だからです。
・身体の痛みを無視できる(あるいは敏感に感じすぎて苦痛)
・まるで感情を感じないようにできている
といった方もいますが、
これも一種の「切り離し」に近く、
本質的には解離と関連しているように感じる時があります。
理想的には、
身体の感覚とつながることで、初めて自分の感情にもアクセスできます。
ただ、身体の感覚をシャットアウトするのにも、
それ相応の理由があると考えるべきでしょう。
したがって解離の対応と同様、
ここも無理にマインドフルネスを推し進めるのではなく、
「パーツ的な」発想が必要と私は思います。
(身体症状も、自律神経の調整不全であると同時に、
「パーツが身体を使って伝えようとしているメッセージ」
ということもあります。)
(2) 人間が動物と違ってトラウマ化しやすい理由
ところで、
そもそもなぜ人間が他の動物と違ってトラウマを感じやすいのか?
というときにひとつ面白い視点があります。それは
「ふるい落とし がないから」
というものです。
ふるい落としとは、
動物が危機に瀕して、「凍りつき」(=死んだふり)に入り、
仮死状態になるとします。
そこから戻った時に、
身体をブルブルッ!と震わせて、凍りつきを払ってから、
平常モードに戻っていく直前の動作のことを
「ふるい落とし」と呼ぶそうです。

人にはトラウマにあった後に身体としての
「ふるい落とし」がない、からではないか?という視点です。
実際、EMDRでトラウマのエネルギーが解放される時に、
・身体の震え、痺れ、ピリピリ
・深い呼吸が入る
などの動作が見られることがあります。
これはふるい落としに相当しているのかもしれません。
(3) 身体の安心を確保する
閑話休題。
ともあれ、身体へのアプローチで重要なのは、
身体の「安心・安全」を確立することです。
EMDRの処理においては、
認知・記憶のテーマがひととおり終わった後に、
身体のテーマが残っていることがあります。
私は身体についてはマインドフルネス含めたボディワークとパーツワーク、
そしてブレインスポッティングで対応しています。
安定化である程度、
身体の感覚を拾うことの意識づけができておくといいですね。
さて、今回は
「解離」と「身体感覚」の2つの安定化について書きました。
大体主要なところはここまでで書けてきていると思うので、
あとは愛着テーマや、その他の確認事項です。
あと一息。
今回もお読みいただきありがとうございました。
ココロンでは専門家によるオンラインのトラウマ治療を行っています。
予約状況の照会はこちらからどうぞ。↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
