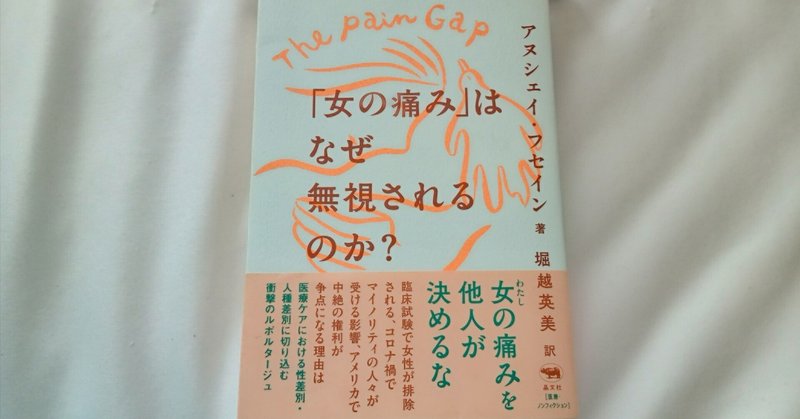
感想『「女の痛み」はなぜ無視されるのか?』
アヌシェイ・フセイン 堀越英美(訳) 2022 晶文社
入院のかたわらで読んだ本です。
内容がとても素晴らしく、これは心理職の方にもおすすめしたい点がいくつもありました。
というのも、心理職の中には医療に関わる方が多くて無縁ではないということ、女性が多いという点で無縁ではないということ、そして男性にとってこれが男性にも同じことが起きますか?という問いを味わってもらうために、読んでもらえたらよいなぁと思いました。
著者はバングラデシュ出身の女性です。
80年代にバングラデシュに育ち、バージニア大学に進学したことを機に、アメリカで生活し、アメリカで出産し、死にそうになる経験を経ました。
その経験から出発して、なぜか医療は女性の痛みの訴えをきちんと聞かない、その女性が有色人種だともっと聞かない、そのことをデータと事例を上げながら説明していきます。
感情論ではありません。そこにはデータがあり、事例があります。声を上げる女性たちの多くは高学歴であったり、社会的な地位があったり、自らの特権があることを踏まえて、責任感を持って、行動している人たちです。
そのような特権を有していても、女性だったり、有色人種だったりすると、医療では訴えを聞いてもらえず、死にかけたり、死んでしまうことがある。そのことを顕著に見えるようにしたのがコロナであったことを、この本は教えてくれるのです。
この本に出てくる統計を少し挙げてみましょう。
2012年に過去20年間の米国発表の研究を分析したところ、痛みを訴えるアフリカ系アメリカ人患者は、医師から鎮痛剤を投与される確率が白人男性より22%低かったそうです。(p.59)
黒人の母親の妊娠関連死亡率は白人の母親の三倍(243%)高いそうです。これは、黒人女性は低所得で学が無く、自分をまおるための主張ができないという誤解を招く原因となっています。(p.73)しかし、その反証として、テニススプレイヤーのセリーナ・ウィリアムズを始め、医師であっても、研究者であっても、政治的なポジションがあったとしても、妊娠時に死にかけたり、死んでしまった例を、著者は次々と示していきます。黒人の妊娠関連死亡率は大卒の女性のほうが高く、大卒の黒人女性は同等の教育を受けた白人女性に比べて妊娠関連の合併症が志望する確率が5.2倍も高いのだそうです。(p.74)
なぜかならば、訴えれば訴えるほど、ヒステリーだ、クレーマーだと扱われて、無視されてしまうから。
更に、私が驚いたのは、女性の健康に関する臨床試験や情報が欠如しているという指摘です。
私の普段の職場が医療現場であることから、医療に関する多くのデータは身体の性別に依拠していることから、性自認にのみ依拠して医療を行うことになるとデータが使えなくなる危険性について考えさせられたことはあります。
しかし、そもそも、実験や臨床試験から女性が除外されていたとしたら。それも、男性の方がホルモン系が単純であるため、研究費用が安くつくという理由で。
たとえば、慢性疼痛の患者の70%が女性であるにも関わらず、疼痛研究の80%は男性やオスのマウスを対象として行われているそうです。(p.107)それで、そのデータはどれだけ女性に当てはめて考えてよいものなのでしょう。
研究助成金の交付にあたり、被験者に女性を含めることが義務付けられたのは、2016年のこと。つい最近ですね。
そこに、民族の多様性までカバーするには、まだまだ時間が必要そうです。アメリカであっても。
後半は、コロナのパンデミックが更に状況を悪化させ、数字となってミソジニーとレイシズムが医療現場に跋扈していることが描き出されていきます。
ジェンダーと人種が交差することで、特に有色人種の女性の命が危険にさらされること。特に、出産の現場で。
と同時に、その章は、コロナが激しく流行していく初期の段階において、医療現場がどれだけすり減るような思いをしたか、感染症に対してハイリスクな1人としてどれだけビクビクして毎日を過ごしたか、強烈に思い出さされるものでした。
今だってまったく安心できるわけではありませんが、それでも、ワクチンも何もなくて、ロックアウトされた環境で、自分の行動の1つで死ぬかもしれない、誰かを殺すかもしれないヒリヒリとした空気は、とてもトラウマティックな体験でした。
先進国の中で最も妊産婦死亡率が高いアメリカでは、そこで、病院で出産する他に、自宅出産という選択肢が脚光を浴びたのだそうです。
それに伴い、助産師やドゥーラという職業が紹介されていました。日本とは状況が違うので、一概にそれが解決策というわけにはいきませんが、ドゥーラという専門職は、私にとっては初耳でした。
ドゥーラというのは、有色人種、中でも黒人女性が利用することが多い専門職だそうで、産前産後の妊産婦のケアをする人であり、通院や出産につきそい、時に代弁者となり、妊産婦を支援するエッセンシャルワーカーです。
日本にも、この職業は是非ともあってほしいなぁと思いながら読みました。
すると、枕元に置いていたこの本に目を留めた看護師さんと話す機会があり、この人はドゥーラという言葉を当然のようにご存知で、日本でもマイ助産師という形で一緒ではないが取り入れて実現しようとする流れがあることを教えてくださいました。
さすが、婦人科。
この本を読んでいて驚くこともいっぱいありました。
何人もの女性たちが、リーダーシップを発揮して、グループを作り、支援活動をしたり、政治活動をしたり、普及活動をしたり、アクションを起こしていることが、ただただすごいなぁ、素晴らしいなぁと、圧倒される思いになりました。
彼女たちは、彼女たちにはある種の特権があることを自覚しています。そこがまた、興味深いものに思えました。
日本での特権の感覚やイメージは、未熟な万能感のようなものです。
そうではなくて、それは万能ではなく、罪悪感を伴うものでもなくて、責任と自信を伴う権能として発揮されるものであるのです。
その感覚がとってもアメリカらしくて、私は好きだなぁと思うと同時に、私も自分の身につけてきたものに対して卑屈にならずに、それを活かすことを考えていきたいように励まされました。
ロビー活動のようなことは苦手ですし、病身でできることは限られてしまいますが、それでも、自分がしたいこと、できることを探していきたいような気持ちになって、この本を閉じました。
どうか、よければ、手にとってください。
そして、女性の声に耳を傾けてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
