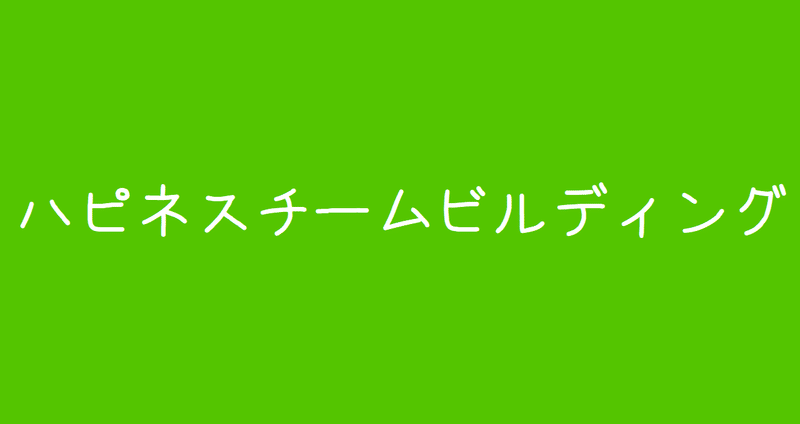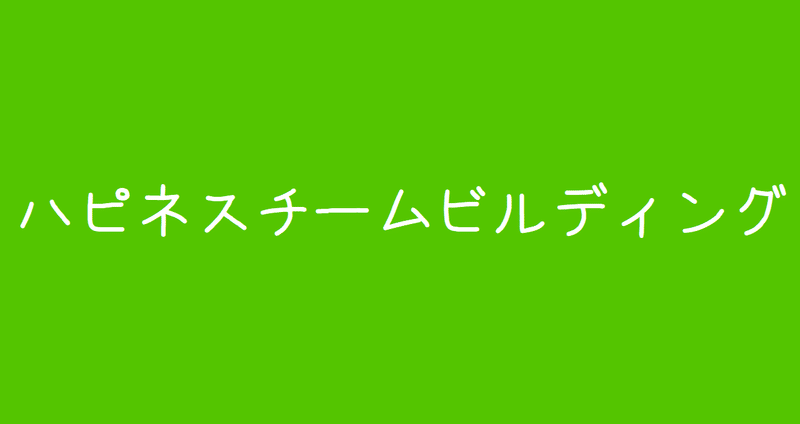コミュニティに参加して楽しみながら成長する(#25)
この記事の初出は、Software Design 2024年4月号です。
コミュニティに参加してからの変化数年前の筆者は、技術記事の投稿経験なし、社外での勉強会の参加経験なしの状態でした。
それが社外のコミュニティに参加したことがきっかけで、価値観が劇的に変わりました。
現在は、記事を書いたり、社外で勉強会を開催したりなどを楽しく行っています。
楽しいチーム開発をするためには、まず自分のエンジニア人生が楽しくあることが大切ですので、今回はコミュニティに参加することで楽しみな