
日本酒ってなあに?4 なぜ人は酒を造るのか
文化と風習
私は「人はなぜ酒を作るのか、なぜ人は酒を飲むのか」という答えを求めて酒造りをしています。
なぜならば、人間が酒を造り飲む理由を理解できれば、誰にとっても最高の酒を造ることが出来るからです。
私が杜氏になってからの天穏をずっと見ていってくださった方はご存知だと思いますがおさらい。
小島の取り組み
27BY 天穏 齋香…生酛吟醸で御神酒の再現、山廃仕込の復活
28BY 無窮天穏・無窮天穏 齋香…新ブランド無窮天穏の立ち上げ
29BY 無窮天穏 天頂・齋蔵・天啓…生酛純米大吟醸、山陰吟醸造りの追求
30BY 無窮天穏 天雲 3日麹…余韻の追求
1BY 全量純米化、無窮天穏SAGA、蔵人の責任醸造…継承、リキュール・その他の醸造酒免許の取得
2BY そやし水もと、KODANE雑穀どぶろく…生命を生む酒
これらの取り組みは全て「人はなぜ酒を作るのか、なぜ人は酒を飲むのか」の答えを求め、その答えを検証していく過程で生まれたものです。
さらに先に進むためにも、日本酒ってなあに?1~3では日本酒とは何か、自分なりの定義を明確化しようと考えてみました。
日本酒の定義
1.税法上の酒としての日本酒(米、米こうじ、水を原料として発酵させて濾したもの)
2.日本酒とは、日本人を祖先にもち、日本の伝統文化と風習を有する人たちの酒。
3.日本とはイネの水耕栽培が始まってからの日本国のことを指す。
日本酒とは、米、米こうじ、水を原料として発酵させて濾したものであり、日本の伝統文化と風習にそった酒である。
こういうことだろうと思います。はっきりとしてきました。
今回はなぜ人は酒をつくるのかを見ていきます。
まずは文化と風習。
稲作カレンダーとお祭り
文化風習というものは、一瞬の出来事ではなく、長い時間をかけて生まれるものですね。
まずは日本酒にとって大切な原料である米を作る稲作のサイクルを見てみましょう。

イメージ通りですね、4月に播種、5月に田植え、8月中旬から米が実り、9月後半には稲刈り。
このサイクルを弥生時代から2500年以上やってきたのが日本ですね。
そして田植えの行事と密接に関係しているものがお祭りです。
田植えの春祭り、米が実る夏祭り、収穫後の秋祭りと、稲作行事の重要な節目にはお祭りが行われます。
このことは現代人の私たちにも十分に想像できるでしょう。

お祭りとは神事を行う日のことですね。
神事とは人が神様に対して祈りを捧げる事を言います。
「神様、これから大事な稲作行事をするのでどうぞよろしくお願いします」と。
その神様とは、日本の場合、自然(八百万の神)とご先祖様のことを指します。
お祭り、神事とは、神社にお供え物をして、稲作の成功による五穀豊穣と子孫繁栄を願うこと言うのです。

私は稲作行事とお祭りが日本の伝統文化と風習を担っていたように感じています。
日本では飛鳥時代以降から考えても約1400年間、稲作とお祭りを永続的に行ってきました。小さな集落、村から国単位まで全国各地で行われてきました。
これを文化風習と言わない理由がありませんね。
このような民族の文化風習のことを民俗と呼びます。
ここからは稲作とお祭りの民俗を見ていきたいと思います。
ただし、民俗には証拠がありません。地方によってバラバラで、数値化できるものではありません。
各々の原風景と照らし合わせて納得する事が重要となってきます。
ぜひ検証してみて下さい。
予備知識
1,人間はすべてホモ・サピエンスである。

私たちは日本人である以前に、大型哺乳類ヒト属ホモサピエンスです。
現代人も、弥生人も、縄文人も、私もあなたも、みんなホモサピエンスです。
そのホモサピエンス、ものすごい特殊能力を持っていることをご存知でしょうか。それは想像する力です。
そして想像したものを概念として捉えて、言語や文字で他者と共有できるという特殊能力を持っています。

概念とは空想上の物事です。
例えば、神様です。物理的に存在していないのに、私たちは共通認識としてその存在を共有しています。
国も概念です。日本は物理的には存在していないのに私たちは自分を日本人だと言っています。
お金もそう。
それ自体は価値のない紙切れなのに、その概念を共有するすることで相互に価値のあるものだと仮定して、物の売買に使用していますね。
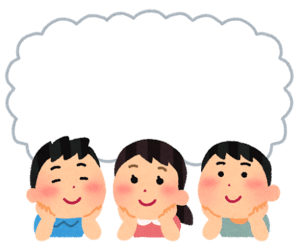
加えて、自分の想像していることと、相手が想像していることが、もし一致していたら、相手に親近感を持ってしまうという点も見逃せません。
好きな歌手が一緒だった時、出身地が同じだった時、好きな食べ物が一緒だった時には仲良くなってしまいますよね。
なぜ仲良くなるかと言うと、仲良くなったほうが、自分の生存確率が上がるからです。
だから人は無理矢理にでも他人と共通する概念を見つけて誰かと仲間になろうとする本能があります。
これを類推(るいすい)と呼びます。
プロレスを見たら興奮した、悲しいドラマを見たら涙が出た、エロ動画を見たらああなった、怪我をしている人を見たら自分も痛い気持ちになる。
誰か1人が泣いたら連鎖して泣いてしまう子どもたち。
これらは全部、自分には起こっていない事象なのに、自分にも同じ事象が起こっていると思ってしまう。
これは類推しているのです。
そうすることで自分と他者は喜びや悲しみを共有する仲間となり、後の生存確率が上がるということを、私たちは本能で分かっているのです。

ホモサピエンスは、同時期に種の戦いをしていたネアンデルタール人よりも、知能も筋力も劣っていたとされています。
しかしホモサピエンスは勝利し現代でも繁栄を続け、ネアンデルタール人は約4万年前に絶滅しています。
ホモサピエンスは上記のように群れになる力に長けていたのです。
ホモサピエンスは想像と共感による群れの力で現代まで生き延びてきたんですね。
まとめ
人は概念を共有することで群れとなり、生存確率を上げている。
2,日本人はもともと狩猟採集民(縄文人)であった。

旧石器~縄文時代のホモサピエンスは狩猟採集により食べ物を調達して生きていきました。
彼らはその過程で生と死という概念を知ります。
物事には精霊(神)が宿り、全ては大地から生まれ、大地に帰っていくという概念です。
これは精霊信仰、アニミズムと言われ、やがて人々は儀式や祭事をするようになっていきます。
精霊と繋がる人をシャーマン、巫女、魔女と呼ぶ姿は世界中で見られ人々を先導しました。
卑弥呼(ひみこ)は個人名ではなく姫巫女・日巫女(ひめみこ)といわれるシャーマンで、個人名ではなく役職である、だからヒミコは多数存在したという説もありますね。
これらは縄文思想とも呼ばれ、生まれるためには死ななければいけない。貰ったら返さなければならない。そうしないと次もまた貰えないという考え方です。

「貰ったものを返せば次も貰える」と思えれば、未来を見通せて楽ですよね。
貰えることがわかっていれば子孫も増やせます。
この思想は狩猟採集を生業としている彼らにとってはごくごく自然な考えだったようです。
取り過ぎてしまったら食糧危機になって絶滅しますからね。
アイヌやマタギのように、獲物の一部は神に捧げる(返す)といった行動は世界中の民族でみられる行動です。
現代人の私たちでも、他者から何かを貰ったらお返ししなければいけないと考えますす。
それを続けることで関係性を続けている、仲間を保持している面がありますよね。
この、もらったら返さないと行けないと思う心理を、「返報性の原理」といいます。
古代人の思想が今の私たちにも習性として刻まれている可能性があります。
また、生と死の実例として、弥生時代から古墳時代では死んだ有力者の骨を山に埋めて、再生を願う儀式が行われています。
そこは岩座、祠、聖地といわれる場所で、時代が進むと四方突出古墳になっていますね。これらのほとんどは山に設置されています。
そしてこの時代から、神様の中に御先祖様がメンバー入りします。
山の神様、精霊と同じ場所に先祖の骨を埋めていますから、神と御先祖様が一体となるのです。

時代が進むと日本人の神様感の中には仏様が新たに加わって、
日本人の神様の概念=自然+ご先祖様+仏様となります。
自然神(精霊・八百万の神)や七福神を見て分かる通り、日本の神様はなんでもありです。
他国に比べて日本は狩猟採集期間が長かったせいか、環境的にハードモードだったのか、神様の概念が実に多彩で複雑です。またもらえる保証、未投資の良い未来があるのならば子孫繁栄できますね。
予備知識としてのホモサピエンス(ヒト)の習性まとめ
1,人は概念を共有することで他者と群れになる。
2,貰ったものを返すとまた貰える。返報性の原理を持っている。
3,1と2ができていれば生存および子孫繁栄ができる。
私たちホモサピエンスは、群れとなって生存するための習性が、本能として備わっているということですね。
なぜ人は酒を造るのか
説明が大変なので図解します。




結論
酒は神から米をもらったことに対する感謝の祈りを捧げるために造られる。その酒は御神酒と呼ばれる。御神酒を神との接点である神社や岩座にお供えして五穀の豊穣とそれに伴う子孫繁栄を祈る。
1,米は山の恵み

あ古代の人々はもともと山で生きていた狩猟採集民ですから、里でつくる米は山からもたらされる実りであると考えていました。
現実的にサトは山の延長線であるし、田んぼに張る水は山から注がれるものです。田んぼやサトは先祖が開墾したものですからね。
米一粒に神が宿る、お盆(米の実る時期)にご先祖様が帰ってくるという話があります。
この言葉から神(自然+ご先祖様)が山から里に降りて米を実らせてくれると昔の人は考えました。
山にいる神様が里に田植えの時期を知らせる花がサクラだった。田植えを知らせる人物を翁と言って、その様子を伝える田楽が伝統芸能の能になったりしていますね。花咲かじいさんの元ネタも田植えの時期を知らせる翁でしょう。
2,貰ったら返えす

田植えをして、無事に米が実り、収穫ができた。
神からお米をもらったのだから、ちゃんとお返しをしないとと、次からお米をもらえなくなってしまうかもしれません。
貰った米をそっくりそのままお返しする訳には行きません。
本音はもっとほしいんだから。お米をより良くして返さなくてはいけませんね。
昔の人は手間を掛けてお米をお酒にしてからお返えしすれば、感謝の気持ちが伝わって、次はもっと米をくれるかもしれないと考えました。
お酒は、神様に対して、返報性の原理を果たすために造られました。
当時の人は発酵のメカニズムがわかりません。酵母によるアルコール発酵など知る由もありません。
彼らは、米が酒になるという奇跡は、神様がもたらす奇跡だと考えていたようです。
アルコールを飲めば元気になったり熱くなりますから、神の力が身に宿ったと錯覚させるには十分だったはずです。
昔は栄養ドリンクもエナジードリンクも無いですからね(大麻はある)。アルコールの作用は抜群だったでしょう。
3,お供え
酒ができたら、それを神にお供えしなくてはいけません。
しかし神様ってどこにいるの?答えは山の中。
山の中ってどこ?それは先祖の骨が埋まっているところだよ。

先祖の骨を植えた場所は山の中の巨石や巨木の下です。
理由は定かではありません。巨石や巨木には生命力を感じたのでしょう。
この先祖の骨を埋めた場所を磐座や聖地と呼びました。
巨木のヒノキも霊の木と呼ぶそうですよ。
歴史が進むと、そのふもとに神社を建てるようになりました。
サトからでもヤマを拝めるように。この時代になると十分な国になっていますね。
ヤマ(神→先祖の骨→巨石・巨木=聖地)→神社→サト(ヒト)
ということで、神にお酒をお供えする場所は聖地か神社です。
一緒にお餅や食料も添えて感謝の気持ちを表現します。
古代だとおばばというかシャーマンや巫女と言われる人がお供えして踊ったりしてますね。
神社になってからは神主さんが神事といって、なにやら難しい物言いで五穀豊穣と子孫繁栄の祈りを捧げています。


神様から貰ったお米を、人の手で祈りを込めて酒にして、それをお供えする。
そのことでお酒は御神酒(おみき)へと変化します。
御神酒とは神にお供えした酒、神の力が宿った酒です。完全に気持ちの問題ですが、古代人にエビデンスは必要ありません。十分通用します。
まとめ
米をつくり、米をもらい、酒にして、神に返す。
また米をつくり、また米をもらい、また酒にして、神に返す。
またまた米をつくり、またまた米をもらい、またまた酒にして、神に返す。
この米に関わる人と神の返報性を少なくとも1400年、稲の水耕栽培が伝わってからだと約3000年続けてきたのが日本人です。
だから米から造るこの酒を、日本酒と呼んでいるのでしょう。
この営みを続けてきたから人は生存と子孫繁栄ができて、今の私たちがいるんですね。
なぜ人は酒を作るのか?
神様からもらったお米をお酒にして、神にお供えするため。
そうすることで、また米をもらい、生存と子孫繁栄につなげる。
いままでの日本酒の定義まとめ
1.税法上の酒としての日本酒(米、米こうじ、水を原料として発酵させて濾したもの)
2.日本酒とは、日本人を祖先にもち、日本の伝統文化と風習を有する人たちの酒。
3.日本とはイネの水耕栽培が始まってからの日本国のことを指す。
4,日本酒の伝統文化とは、神様(自然・先祖)からもらったお米をお酒にして、神様にお供えすること。
2022年追記
このときは酒は人と神との返報性のツールといっていました。
現在、わたしは酒とは人と神の贈与関係のツールだと言っています。
神が人間に米を贈与する
巫女が米に命を贈与する
巫女は神に酒を贈与する
この永遠の繰り返しが日本酒の伝統文化です。
神⇔巫女⇔人間
このように巫女は神と人間を繋ぐ両義的存在として君臨します。巫女とは人間界で最も価値のある存在である子供の埋める女性のことです(当時の話で現代の話ではありません)。
巫女は米を噛むことで、米に命を贈与して酒にします。
酒=神+人
ここでこの図式が成り立ちます。
巫女は酒を神に贈与し、お告げと酒を獲得し、神の使いとなった。
酒と占いで神と人を操る巫女、シャーマンの誕生です。
これはそのまま私たちの卑弥呼のイメージですね。
卑弥呼は数多くいて、人と神の秩序を保っていました。
男系国家になって影響力のある巫女は姿を消してしまいますが、現代でも巫女の影響は残っています。10代の女性がいろいろな意味で無敵な理由がココにありますね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
