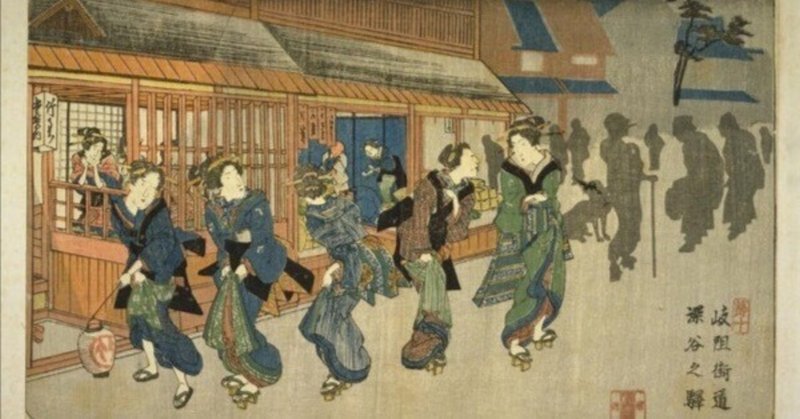
日本語を「教える」ことの70−80%は話題という「桶」に言葉遣いという「水」を溜めること
今はほとんど見られなくなりましたが、夏の打ち水というのをご存じでしょうか。下の写真のように、夏の昼間の暑さをやわらげるために日が陰ってから家の前の道に水をまくことです。で、日本語の習得をこの打ち水に譬えたいと思います。

1.表現活動の日本語教育あるいは自己表現の日本語教育
文型・文法を中心として適宜に語彙も加えながら教えていくというやり方ではなかなか日本語が上達していかないというのは、日本語の先生の多くが共有している認識だと思います。筆者は、そうした方法の代替案として表現活動の日本語教育を提案しています(西口, 2020)。表現活動の日本語教育あるいはその基礎段階の自己表現の日本語教育では、話題を中心としてユニットが設定され、各ユニットではその話題で3人の登場人物が自分の話をします。それをナラティブ(語り)と呼んでいます。ナラティブは簡単に言うとその話題での話し方の例示です。
*ナラティブのサンプルとそれを含む教材は、http://nej.9640.jp/sample_honsatsu.htmlで見ることができます。
各ユニットでは、学生(学習者)は、(1)ナラティブを学習(理解)し、(2)ナラティブを「なぞり語り」し、(3)ナラティブから言葉遣いを「盗み取っ」て我が物(摂取)にし、(4)さまざまな言葉遣いの蓄えを形成します。そして、そのように形成した言葉遣いの蓄えをリソースとして、その話題について話し始め、さらに話し方を洗練していくというステップで日本語の習得を進めます。そして、教師の役割は、この4つのステップを援助し支援し、学習者が話し方を洗練するのを促進することとなります。
従来の日本語の学習と習得支援(教育)のアプローチでは、文型・文法や語彙が注目されてきました。自己表現の日本語教育では、その代わりに言葉遣いに注目します。自己表現の日本語教育は、話題を柱として 話題を運営するさまざまな言葉遣いの蓄えを形成して、話題の言語技量を育成する方法だと言うことができます。
2.自己表現の日本語教育の学習指導として重要なこと
さて、さまざまな言葉遣いの蓄えを形成するとはどういうことでしょう。それは、話題という「桶」に「水」を溜めるようなものです。
打ち水をするときには、桶に水を溜めなければなりません。桶に水がまだ3センチしか溜まっていない状態で、杓(しゃく)で水を撒こうとしてもうまく撒くことができません。水が十分に溜まっていないからです。
それと同じように、学生がさまざまな言葉遣いの蓄えを十分に形成していない状態で話させても、うまく話すことはできません。当然です。言葉遣いという「水」が十分に溜まっていないわけですから。話題という「桶」に、話題を運営する言葉遣いという「水」をしっかりと蓄えないと、話せませんし、相手が話すことを理解することもできません。つまり、言葉遣いの蓄えがないと、言語活動に従事することができません。
3.なけなしの水を撒く? なけなしの言葉を話す?
多くの先生は、ユニット学習の早い時期から「学生に話させる」ということをします。学生に話させるというのは、「溜まった言葉遣いを組み合わせてあなたの表現意図を日本語にしてください」ということです。ですから、「溜まった言葉遣い」がかなりあることが前提です。言葉遣いの蓄えが形成されていない状態で話させるというのは、「桶」にわずかにあるなけなしの水を何とか撒こうとしているようなものです。それは、無理なことです。
*「学生に話させる」ではなく、先生の先導(モデル)に従って言わせるというの(模倣活動やショドーイングなど)は、適切だと思います。それは、言葉遣い摂取のための活動となります。
4.必要なのは「桶」に「水」を溜めること
表題にありますように、日本語を「教える」ことの70−80%は話題という「桶」に言葉遣いという「水」を溜めることだと思います。日本語の先生たちは、だれも「桶」に「水」を溜めるということをしないで、みなさん「なけなしの水を撒く」ことばかりしているように見えます。そして、学生たちが話せないのを見て、さらに話す練習(「なけなしの水を撒く」練習)をします! 一体、誰がいつ「桶」に「水」を蓄えてくれるのでしょう。「桶」に「水」を溜めることこそが日本語を「教える」ことの重要部分なのに…。
文献
西口光一(2020)『新次元の日本語教育の理論と企画と実践 — 第二言語教育学と表現活動中心のアプローチ』くろしお出版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
