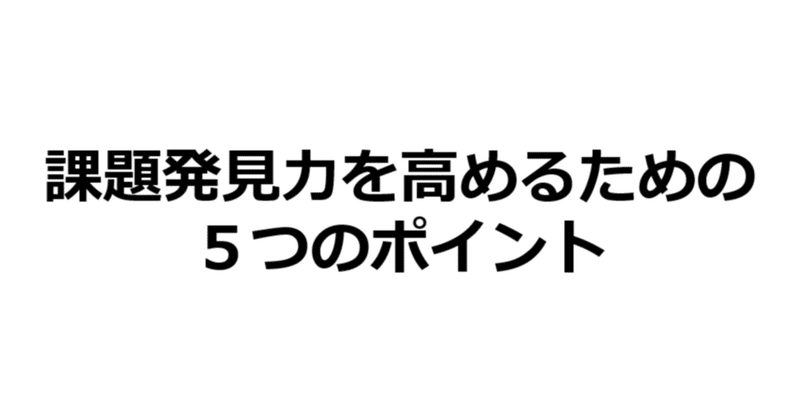
課題発見力を高めるための5つのポイント
こんにちは!
ビジネス・ブレークスルーの高松です。
自らを進化させるためには、学び方も進化させなければいけない。そう思って、「研修進化論」と題してnoteを書いています。
さて、今日は、課題発見力を高めるための5つのポイントをご紹介します。私自身、年間100日くらい研修講師をしたり、個別添削も数えてみたら年間1,000名以上させていただいています。
日々、多くの方の課題発見・問題解決のお手伝いをさせてもらっています。
でも、ぶっちゃけ、一人一人状況は違うわけです。
なので、研修の中で、こんな風に考えてください!とお伝えしても、やっぱりそこには無理がある。つまり、研修で学んだことをそのまま使おうということではなく、それぞれ「アレンジする力」が必要になるわけです。(当たり前のことを言うなと怒られそうですが・・・)

その一方で、どういった分析をするのか、どれくらいの視野を持つべきかは、当たり前ですが、人それぞれ、問題それぞれ違うわけです。
ただ、これまでのこういった研修やビジネス書では、「プロセス論」を強調しすぎてしまい、個別最適に考えることから遠ざけてしまっているのではないかと思っています。
つまり、プロセスは共通だけど、やり方は人それぞれ違うので、みんな工夫しようという話なんです。自分なりに、やりかたを工夫してアレンジすることができなければ課題は発見できないし、問題解決はできない。
今回は、課題発見するためにアレンジすべきポイントをまとめてみようと思っています。そのポイントも大きく言えば5つくらいにまとめられると思っています。
まずは、課題発見の流れからご紹介します。
人それぞれ違う状況に対応できる「課題発見プロセス」はこのようになります。

第1ステップ 問題認識
どういう問題に取り組むのか、問題を定義します。現状とあるべき姿(ありたい姿)のギャップを認識して、何を解決したいのかを明らかにします。なんとなく始めてはダメ!
第2ステップ スコープの設定(問題解決の地図を持つ!)
その問題に取り組むにあたって、どれくらいの視野(スコープ)で考えるべきなのか設定します。それが、私が推奨する「問題解決の地図」です。
第3ステップ 問題の分解
目の前にある問題は、どういう問題なのか?問題を分解します。問題を分解することで、「どこ」で問題が起きているか特定します。どこどこ分析と言ったり、Whereのプロセス言ったりもします。
第4ステップ 原因仮説出し
特定された問題がなぜ起きているのか、仮説だしを行います。その問題は、なぜ起きているのか?思い付きだけでなく、網羅的かつ精度の高い仮説を出す(筋の良い仮説と呼んでいます)。
第5ステップ 課題のまとめ
情報収集した事実から課題を抽出します。何が一番悪いところなのか、どこを直すと効果が一番あるのか。本質的課題を明らかにします。これが課題発見のプロセスです。
ここからが、今回のポイントです!
課題発見力を高める5つのポイントがこちら。
実務で活用するためには、この5つのポイントに気を付けてほしいです。

ポイント① 問題認識の際には、状況に合わせて時間軸を設定をしよう!
どこまでの未来を見て問題解決に取り組むのか。ここの認識は組織、個人として明確にする必要があります。いまここにある問題をすぐに解決したいのか?1年後、2年後のちょっと先を考えるのか。それとも、5年後、10年後を見据えるのか。どこまでの未来を見るかはカッチリと設定する必要があります。
ポイント② スコープ設定の際には、自分の役割に合わせた視点を持とう!(それが問題解決の地図!)
組織の中では、自分自身の役割があります。その役割に合わせて、見るべき範囲(スコープ)が変わってきます。問題の具体的な検討を始める前に、自分がどこまでの事を見なければいけないのか俯瞰図を持ちましょう(これが、問題解決の地図)です。ただし、どんな地図を持つべきかは、人に異なってきます。現場スタッフ、営業マネージャー、事業部長、経営者それぞれに違った地図を持つべきなのです。
ポイント③ 問題分解の際には、問題の種類に合わせて問題を分析しよう
目の前にある問題の種類によって分析の仕方は違います。研修だと売上や利益などをテーマにすることが多いですが、それ以外にも色々なテーマがあります。例えば、業務ミス。メールの誤送信をしてしまった。その場合には、どんな分析をするのか。問題の種類に合わせて分析する必要があります。
ポイント④ 問題の種類に応じて、筋の良い仮説を創る!
問題を特定した後は、仮説を創ります。その際も、その問題の種類に合わせて、筋の良い仮説を創りたいところ。目の前にある問題は、なぜ起きてしまったのか?でも、それは、なるべくしてそうなってしまっている。問題の種類を認識し、さらに、問題と原因の典型的パターンを知ることによって筋の良い仮説も出せるようになります。
ポイント⑤ 問題の種類に応じた課題の抽出
実は、課題のまとめ方は問題の種類によって違います。これは、たぶん誰も言っていない気がします!(たぶん!)でも、とても大切!業績アップのための課題発見と業務ミスをなくすための課題発見では、実は課題の抽出方法が違います。その辺りを認識でできていないと、混乱する。この違いは、また書きます。
まず、知ってほしいのは、適当に問題解決に取り組むと現場は混乱します。
だから、しっかりと課題発見の方法を学ぶことが大切!
世の中に存在する問題が、どんどん複雑になってきている。だから、問題解決トレーニングも進化していきますよー。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自分自身を進化させるために、一緒に学んでいきましょう。
課題発見力を高めて、進化したいという方はぜひ、ビジネスアウトプットGYMをご受講ください。
さらに、法人向けの公開講座も開講予定です。
本はこちらです。
また書きまーす。
もし宜しければ、イイね!ボタンお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
