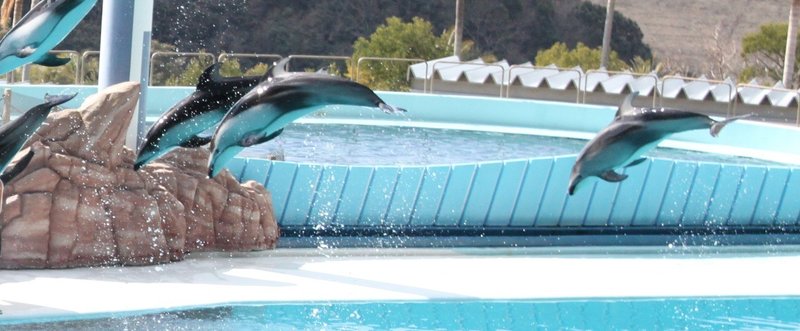
「体験中心」が意味すること
2017年2月14日
(火曜日は「教えること/研究すること」のトピックで書いています)
これからのビジネスは顧客にどのような「体験」をさせるのかが鍵を握っているといわれています。
たとえばコーヒーショップでは、コーヒーという商品そのものをどのようなソファで飲んでもらうかという体験が売りになります。確かに同じコーヒーを飲むのであれば、眺めがいいところや、落ち着くところ、座り心地がいいところで飲みたいと思います。これがライバルとの差別化につながるというわけです。
書店でも、本という商品そのものを座って試し読みできるという体験を提供するようになっています。オンラインでも本を試し読みできるという体験を提供するケースが多くなっています。考えてみれば、本を買うのは本そのものを買うのではなくて、本を読むという体験を買うのですから、その体験を試してもらうのはお店のサービスの重要な部分になります。
そう考えていくと、授業や研修もまた体験中心という考え方が重要なことがわかります。授業や研修でお金が払われるとしたら、それは参加者がなにがしかの知識やスキルが「使えるようになること」という可能性に支払われるわけです。
授業をする教員や研修講師が持っている知識とスキルそのものにお金を払うわけではないのですね。そのことを多くの教員と講師は誤解している。先生が知識とスキルを持っているのは「前提条件」です。それがなければ教えられませんから。その条件の上でお金が支払われるのは、それを使って、参加者に知識とスキルが身につくようにできたかどうか「だけ」によるのです。
参加者が「今日の先生はすごい人らしいけど、なんだかよくわからなかったわ」という感想を漏らしたらお金は払われないでしょう。
授業や研修では体験中心の流れがやってくるでしょう。それは参加者が知識とスキルを自分のものとして使えるようになることを目指す限り、その方向性しかないのです。
教員や研修はまず参加者に体験させる機会をデザインします。その上で、中心となる理論や原理をそれに結びつけます。なぜかというと、それが自分の体験を展開・応用するために必要だからです。体験は理論として自分のものとしたときにはじめて生きてきます。それが理解ということです。
ここから先は
ご愛読ありがとうございます。もしお気に召しましたらマガジン「ちはるのファーストコンタクト」をご購読ください(月500円)。また、メンバーシップではマガジン購読に加え、掲示板に短い記事を投稿していますのでお得です(月300円)。記事は一週間は全文無料公開しています。

