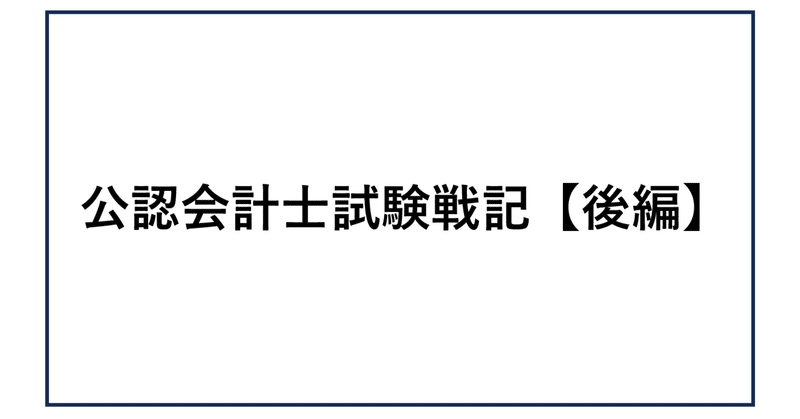
公認会計士試験戦記【後編】
はじめに
今回のnoteでは、私の公認会計士受験生時代を振り返りながら、合格するまでの道のりをお話しする後編として、公認会計士試験に合格するまでのお話しができればと考えています。
なお、前編、中編をまだ読んでない方は先に前編、中編から読んでいただくことをおすすめします。
それでは早速いきましょう。
夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だ。
合格までのラストスパート
半独学で再スタート
二度目の短答に落ちてから、予備校にも所属しない中での新たなスタートを切ります。在学中に論文式試験を受けることはできなくなったのですが、大学卒業前の2018年12月に短答式試験が控えていたので、次はこれに向かって進めることになりました。
二度目の短答式試験を受けた頃からは、周囲も私の勉強に対する姿勢を見て期待をしてくれるようになっていて、公認会計士試験合格という私一人の目標が、いつの間にかみんなの目標に変わっていることに気づきます。
しかし、みんなが期待してくれるようになったことと反対に、予備校に所属せず半独学で勉強をすることになっていたため、通常であれば予備校が組んでくれる合格までのスケジュールなどがないといった状況でした。
そのため、仕方なく自分で合格までのスケジュールを組み、勉強方法を考えることになりました。
振り返ると、このときに自分で足りないところをどう補うかなど様々な検討をしたため、普通に予備校に所属して合格するよりも得るものは大きかったと感じます。
このような形でとりあえず再スタート。
勉強方法は、アウトプット教材は過去問に切り替え、過去10回の短答式試験を10回転ほど回し、理論対策として、基本書の読み込みを行いました。
大学4年の頃は授業もほとんどなかったので、朝9時に図書館で勉強をスタートさせ、途中空き教室を挟みまた図書館に戻るといったことを繰り返し、19時ぐらいまで大学で勉強をするといった生活を送っていました。そして、家に帰ってももちろん勉強し、起きている間はずっと試験のことだけを考えていました。
遂に短答合格
2018年の7月ごろから半独学での勉強に切り替えて、半年弱が経った12月。遂に短答式試験当日を迎えます。
短答式試験はこれで三回目。正直合格以外の選択肢はなかったです。
ちなみに、この短答式試験の前にTACと東京CPAとクレアールの3校の公開模試を解いていて、TACとクレアールではA判定、東京CPAではC判定と全てボーダーラインはクリアしているといった状況でした。
さらにTACの模試では、1,125人中76位となかなかの上位だったので結構な自信を持って本試験に挑みます。
こんな自信満々の試験当日、管理会計論で事件が起きます。問題が難しすぎて全然解けた気がせず。公認会計士試験では各科目で40点に満たない科目があった場合は足切りになるのですが、管理会計論が終わってすぐの感想は「足切りかも」でした。
試験当日は予備校が解答速報というものを出していて、試験が終わると一、二時間ほどで解答を出してくれます。本来であれば、他の科目に集中するために当日すべての試験が終わるまでは解答を見ないということが受験のセオリーなのですが、管理会計論でこのような状況だったため、まだ別の科目が残っているにもかかわらず、自己採点をしました。
すると、40点。ギリギリ足切りセーフといった感じでした。
結局この採点おかげで、再度試験に集中することができ、最後までやり遂げることができました。
試験が終わると、ちょうど父親が地方から来ていたので、父親と弟と居酒屋に行きました。
私はもともとお酒を飲まないタイプのため、居酒屋でご飯を食べていると、ちょうど全ての解答速報が予備校から出ます。
居酒屋にもかかわらず、試験結果が気になりすぎてその場で自己採点をしました。
父親と弟は「俺たちの前でやるなよ」というような感じだったのですが、私にとっては人生を賭けている大勝負だったので構わず採点をし、結果、正答率65.8%。あの管理会計論の出来をなんとか他の科目でカバーし、なんとか合格ラインに乗るような点数に持っていくことができました。
その日の夜は全く寝れず、ずっと予備校の試験の講評を視聴していました。
その中で、今回の管理会計論の難易度をどの予備校も語っていて、相当難しかったんだなということを実感し、少し安心することができました。
それから一ヶ月ほどが経った合格発表当日。多分受かっているだろうということで、合格番号の貼り出しが行われる霞ヶ関の金融庁まで直接確認に行きます。
結果は、合格!
短答式三度目の正直でした。その日は本当に嬉しく、合格を確認してそのままお祝いとして豊洲に海鮮丼を食べにいきました。
この短答合格では、両親をはじめ家族や親戚など、様々な方が喜んでくれて、自分は本当にたくさんの人たちに支えられているということを改めて実感する貴重な経験となりました。
ちなみに、短答合格の少し前に、日商簿記1級も合格しています。もちろん嬉しかったですが、短答の喜びの方が何倍も大きかったので補足的に書くことにしました。
予備校に再入学
短答に受かると、次は8月の論文試験に向けて勉強することになります。
私は、過去に一度論文の勉強を少しだけ進めていましたが、そのときは短答に後1%で落ち結局論文には進めなかったため、次の短答に受かるまでは短答の勉強だけに切り替えていました。
したがって、論文試験特有の科目や論点をもう一度基礎から勉強する必要があると考えていて、そのためには予備校に入ることが必須であると考えていました。
ただ、このときは貯金ももちろんないため、両親に予備校代を出してもらう形になり、以前入ってた予備校と同じ予備校であるクレアールの論文対策講座を選択することにします。当時は東京CPAに入ることも考えましたが、クレアールで一回勉強していたということが大きく影響し、クレアールという選択になりました。
あいかわらずクレアールの予備校代は他校に比べて安く、論文対策講座も他校に比べると格段に安かったと記憶しています。
正直、この安さがなければ今頃私は別の人生になっていた可能性もあるので、クレアールには大変感謝しております。
浪人突入
短答に合格し予備校に再入学して少し経った頃の2019年3月、大学を卒業しました。
大学院に行くか、公認会計士受験浪人をするかで悩んでいたのですが、大学院に行きたい理由を掘り下げて考えたところ、公認会計士試験の一部科目免除に引かれている自分に気づきます。
大学院の学費はただでさえ高額なのに、勉強するためではなく免除のために行くということはどうなのかと考え結局行かない選択をしました。
また、運良く短答式試験も合格したので、免除を使う機会がなくなったことも大学院を選択しなかった大きな理由の一つです。
そのため、卒業後は浪人という形になりました。
浪人生活がスタートしてからも、普段の生活に変化はなく、ひたすら勉強の日々です。論文の勉強は記述が多く、苦手な暗記にも積極的に取り組みました。
特に、財務会計論の理論と企業法はクレアールの理論対策集を全部覚えるぐらいの勢いでした。
このように勉強面では特に変化はない日々でした。
一方で、金銭面やメンタル面は結構辛い時期となりました。
特に金銭面は厳しかったです。
実家に戻らず弟と二人暮らしをしていましたが、大学を卒業していたため仕送りなどはなく、生活費は自分で賄う必要がありました。
ただ、バイトもしていなかったので、家族や親戚からもらった大学卒業のお祝い金を取り崩し、なんとか8月の論文試験まで持つように節約生活を送っていました。
そんな生活を送っていたある日、友達の結婚式に出席するということで地元に戻る機会が訪れます。
結婚式に参加し、その後久しぶりに家族や親戚と会い、他愛もない会話などをしながら、次の受験の手応えなども話し有意義な時間を過ごしました。
私の家庭は、私が小さい頃から母の姉の家族と距離が近く家族同然の関係なのですが、他愛もない会話をしている中で、伯母と伯父から、生活はどのようにしているのかと尋ねられます。
そのときは大学卒業祝いで貰ったお金を取り崩しながら一日600円〜700円ぐらいで生活していたので、そのように話すと、私たちが生活費をサポートすると言ってくれました。試験までは残り3ヶ月だったので、1日1,000円は使えるようにと、90,000円の現金と、伯父がギターを買うために貯金していたという500mlのペットボトルに100円玉が詰め込まれた貯金箱を貰いました。
当時は本当に資金繰りが辛かったので、本当に嬉しかったです。伯父や伯母も決してお金に余裕があるわけでないにもかかわらず、こうして私のためにお小遣いを捻出してくれてたので、今回一発で絶対に受かると決意も強くなりました。
そして、さらにギアを上げて論文まで勉強に励みました。
論文の勉強
このように金銭的なストレスから少し解放されて勉強を進めることができるようになったのですが、論文の勉強は、試行錯誤の連続となります。
当時、Twitterなどでは「短答受かれば論文余裕」というワードが流れたりしていて、論文は意外と苦労せずにいけるかもと思ったりしていました。
しかし現実は、薔薇色な論文生活は訪れませんでした。
個人的には短答より論文の方が大変だったので、受験生の方がこのnoteを読んで下さっていたら、油断せず最後まで走り抜いて欲しいです。
論文の勉強に話を戻すと、クレアールに申し込み勉強を進めましたが、一部の科目でクレアールの教材に論文用の問題集がないことに気づきます。そのため、その科目たちは必然的に答練ベースのアウトプットというスタイルになりました。
そんな中、答練ではテキストに載ってない問題もバンバン出たのでこの勉強法は自分に合わないと思い、合わない科目は東京CPAと市販の問題集を活用しながら勉強を進めることにしました。
活用した教材は、東京CPAの教材は、財務会計と租税法の計算コンプリートトレーニング、経営学の論文対策講座、管理会計理論対策集。市販の問題集は論文式試験対策新トレーニング管理会計論、公認会計士試験「論文式」監査論セレクト30題。と、結構な教材を活用しながら勉強を進めることになりました。
クレアールの教材から離れたことで少し不安も残ったのですが、過去問を解きながらこの勉強方法で問題ないということを確認したりしながら進めていました。
この勉強方法も正直受験生にはおすすめできないですが、当時は合わない勉強方法を続ける方がリスクだと考えていたので、この自分で選択した問題集たちを完璧にして落ちたら仕方ないという気持ちで勉強をするといった状況でした。
遂に論文式試験
論文の勉強を始めて最初の方は勉強方法で苦戦をすることもあったのですが、その後なんとか自分なりの勉強方法を確立し、1日8時間ほどの勉強をコツコツ続けながら日常を過ごしていました。
途中、他校の公開模試なども受けながら、自分の位置を確認したりもしましたが、公開模試の結果はC判定で、合格ボーダーラインギリギリしかでませんでした。
ただ、ボーダーラインギリギリということで、他の受験生と勝負できる位置にはいると考えることができたため落ち込むことなく、かといって慢心が生じることもなく、いい緊張感のまま勉強を続けられる要因にもなっているといった状況でした。
このような感じで勉強を続けていると、本試験一ヶ月前くらいから受験が待ち遠しくなってきました。試験が終わればとりあえず受験生のストレスからは解消されるだろうと考えていたのです。
そして2019年8月、遂に論文式試験を迎えます。
論文式試験は公認会計士試験の総本山のため、とても気合を入れてnoteを書きたいのですが、正直試験のことはほとんど覚えていません。
当時は問題を解くことに全てのエネルギーを使っていて、その出来事を記憶することまでできなかったのだと思います。
ただ、一つだけ覚えているのは、財務会計論で資産除去債務の問題が出たのですが、答案用紙に書いた漢字が間違えていることに残り2分で気付いたことです。
私は、資産除却債務と書いていたので、それを直す必要がありました。しかも資産除却債務というワードを4回ぐらい使っていて、全てを直す必要があります。
本来なら2分あれば余裕で直せるはずですが、修正テープを引いてボールペンに持ち替えたところで手の震えが止まらなくなり、結局直せない箇所が出てしまいました。
試験監督から「止め」の合図が告げられたときは、全ての文字を直せなかったので頭の中が真っ白になり机にうつ伏せになりながら、「また来年も受けないといけないのか」と涙が出そうになりました。
正直、今振り返ると漢字ミスの一つや二つぐらいで合否に影響することはほとんどないと思いますが、当時は本当に余裕がなく、絶望状態でした。
そんな記憶しか残ってない論文式試験ですが、終わってから帰路に着くときは、開放感でいっぱいでした。
合格発表
このように紆余曲折がありながらなんとか論文試験も無事終えることができました。
論文試験の合格発表は11月で、試験が終わってから3ヶ月弱ほど期間があったため、その間は地元に帰ったり、ビジネス書や自己啓発本を読んだりとこれまで出来なかったことを思う存分楽しみました。
ただ、もし落ちたときのためにということで1日に2、3時間は公認会計士試験の勉強をしながら、実力が落ちないように維持するための勉強は続けていました。
そんな中、とうとう合格発表の日が訪れます。短答式試験のときは張り紙を直接確認することで合格を確認しましたが、論文式試験では手応えが五分五分でどちらに転んでもおかしくないと思っていたので、一人で自宅からネットで確認することにしました。
受験番号が書かれたページで自分の番号を探していると、自分の番号に近くなればなるほど緊張してきます。
とうとう次が自分だと思って画面をスクロールすると、自分の番号が飛んで自分より後の番号になっていました。
この瞬間不合格ということで「そんな甘くなかったか」という気持ちになりました。
ただ、もう一回見てみようと思い見返すと、なんと、自分の番号がありました!
本来は横から順に見るところを、縦に見ていたため誤って不合格と思い込んでいたのですが、改めて見ると自分の番号があったということで、その瞬間大量の涙がこぼれてきました。
そして、家族や親戚などこれまでお世話になった方々に合格の連絡をしました。
みんな自分のことのように喜んでくれて本当に最後まで諦めないでよかったと思いました。
それと同時に、今度は自分が社会人になってみんなを支えられるように頑張ろうと思うことができました。
合格をネットで確認してからは、短答の時と同じく、霞ヶ関まで行き、自分の名前が書かれた張り紙を確認することにします。
自分の名前が書かれた張り紙を指差しながら写真を撮ったりと、達成感と喜びでいっぱいでした。
その日は本当に嬉しくこれまでの人生で一番の興奮を感じた日でもあったと思います。
簿記を始めてから4年、公認会計士試験を目指すと決め予備校に入学してから2年半、長かった受験生活に終止符を打つことができた瞬間でもありました。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
前編、中編、後編に渡って私の公認会計士試験を振り返ってみましたが、いかがでしたでしょうか。
まとめる中で、改めて充実した日々であったことを実感しました。もちろん受験生時代は、充実していると感じることもないぐらい毎日が必死で、受からないかもしれないという現実と向き合いながら、その不安をかき消すように勉強していたと記憶しています。
私は、日商簿記2級に一回落ち、日商簿記1級に二回落ち、全経簿記上級に二回落ち、公認会計士短答式試験に二回落ちといった形で、合計7回も不合格になっています。
ただ、途中で諦めなかったことが功を奏し合格することができました。
私の合格の秘訣は「諦めずに続けることができた」に尽きると思います。
もともと勉強エリートではなかった私の話ですが、こういう人でも合格することができるということで、少しでも誰かの役に立ってくれたら嬉しいです。
今後、また5年後ぐらいにこのような形で大きな挑戦の記録を綴れるようにこれからの人生も様々な挑戦を続けていきたいと考えています。
改めて、最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
