
第8回 神戸・新開地「『楠木新』が生まれるまで②」
行き詰まりの中で休職
2000年のこと、45歳で大手保険会社の支社長だった私は、保険の内容確認や調査を行う関連会社の人事担当部長に出向になった 。
この会社の役員は主に本社で部長クラスだった人たちが常務や専務で転籍していた。みなさん気のいい人たちで、職場の雰囲気は悪くなかったが、自分の将来を考えた時には納得がいかなかった。
毎日毎日、受け身の仕事をして、新しいことにチャンレンジする雰囲気も感じられなかった。
「自分の10年先はこういう姿か」と違和感が膨らんだ。
一方で、どのように対応すればよいのかについてのアイデアは何も持ち合わせていなかった。それが後日の休職の引き金になった。

青龍寺空海記念碑(陝西省西安)の前で
2002年3月の47歳の時に、今度は関連会社から本社の販売管理を統括する役職者への転勤辞令が出た。
周囲から見れば栄転に映ったかもしれないが、私の中では「仕事をやり抜いてさらに昇進していこう」という気持ちと、「もうそろそろ本当に好きなことをやりたい」という思いがぶつかり合って、ちょうどアクセルとブレーキを同時に踏んだような状態に陥った。
仕事も忙しくなるので、前年に始めた関西大学での非常勤講師を転勤後も続けることができるかという不安も抱えていた。
この転勤から1か月もしないうちに、身体中のエネルギーが一気に失われて力が入らなくなった。
夜も熟睡できずに、朝早く目が覚める日々が続く。身体が鉛のように重くて出勤するのがやっとの状態だった。
20数年間、風邪ですら休んだこともない私が未体験の体調不良に陥った。ただ当初は病気だという自覚はなくて、妻に勧められて土曜日に病院に行くと「うつ状態」という診断が出て休職することになった。大学の非常勤講師も途中で代わってもらった。

当時は迷いの気分を紛らわすために、アジアの一人旅や 国内の聖地と言われる場所を巡ったりした
一度目は3か月ほど休職して職場を変わると体調は戻ったが、翌年度の4月に役職に復帰すると、また調子が悪くなった。このように復職と休職を繰り返した。
休職期間はそれほど長くなかったが、体調不良の期間は2年半ほど続いた。
最後の休職の時には自分でも「もうダメかな。会社を辞めよう」と覚悟したくらいの状態だった。
自分が生まれ育った街が頭に浮かぶ
休んだ直後の極悪な状態が治まるにつれて、休職中は家でどう過ごしてよいのか分からなかった。仕事の息抜きで見るテレビは楽しむことができたが、いざ多くの時間ができても面白いと思える番組はなかった。
外出はできる状況だったが、行けるところは書店か図書館、スーパー銭湯くらいしかない日々だった。
土曜、日曜日になると、少しほっとしている自分があった。やはり会社を休むことに対する罪悪感が残っていたのだろう。
その頃に私の頭に浮かんできたのは、なぜか自分が生まれ育った街だった。私は子どもの頃を当時は神戸一の歓楽街だった新開地・福原界隈で過ごした。色街にも近く、「東の浅草、西の新開地」と並び称されたこともある賑やかな街だった。
そこでは、映画評論家の淀川長治も通っていた映画館や、いつもワクワクさせてくれたお笑いの神戸松竹座をはじめとして多くの飲食店も軒を連ねていた。
実家は薬局で、へんこつ(頑固)な父と話し好きの母と妹の四人で暮らしていた。
周りの友達も酒屋、八百屋、自転車屋など「屋」のつく家の子どもばかりで、銀行や役人の子はいなかった。

母とは子どもの頃の楽しかったことや昔の思い出話も出た。
母はすでに70歳を越えていて、息子の私も50歳に近づいていたのだが、二人で話す時は昔の母と息子に戻っていた。
会話の中心は、当時の近所にいた個性のあるおっちゃん達の話だった。
この連載の第2回でも紹介した、「車検の時はタイヤに傷さえつけておけば、後でうまくごねれば車検代はただになるのや」などと詐欺まがいのことばかり言っている他称「詐欺師のオジサン」。彼は事情で親がいなかった近所の姉弟に金銭的な援助をしていた。
私たち中学生に語りかけてくる「ヒモ」と自称していたおっちゃん。
いつも淡々としていて何ものにも動じなかった隣の古本屋のおじいさんも話題に上った。
自身が営んでいる小さな旅館の前に椅子をおいて、終日座ったままで通りを行き交う人たちをずっと眺めていたオジサンは、働く姿を一度も見たことがなかった。
でも息子の受験にはとても一生懸命だった。
夢にも現れた彼ら=オジサンたち
家のすぐ近くに住んでいた元親分であるSさんは、大学の法学部に入学したことを知ると、「絶対すぐに弁護士になったらアカンぞ。まずは検事になって名前を売ってから弁護士になれよ」と顔を見るたびに何度も私に繰り返した。
最近話題の「ヤメ検」になれと勧めていたのだ。
小学生の時には、子どもたちは集団で登校していたが、集合場所は雨が降るとぬかるむ砂利道だった。
自治会長がSさんに「子どもたちの服や靴も汚れるので、アスファルトにしてもらうように市役所に頼んでもらえないか」と依頼すると、2〜3日してすぐに市役所の工事担当者が来て、一気に道が舗装された。
真偽は定かではないが、「戦後の混乱期に役所が土地の区画整理などでSさんたちの手を借りたので、ステテコ姿で助役室に出入りできるらしい」と自治会長は話していた。
母はSさんの妻と気が合ったためか、「受験勉強の時に使え」とSさんから軽くて暖かい超高級品のガウンをもらった。ただガウンについていた強い香水のにおいには辟易しながら勉強していた。
Sさんの妻は、「ウチのおっさんと、この薬局の主人(私の父)が、サラリーマンやったら、絶対部下にバットで頭をカチ割られるでぇ」と私の店の前でぼやいて爆笑の渦を作ってくれた。
Sさんの息子たちは私よりも年下で、彼らには自分の刺青を見せないように気を配っていた。
後日談になるが、大学時代に同じクラスだったF君が、インフラ系の会社の神戸支店に新入社員として配属された。F君は私の友達だと言うとSさんとも話し合える関係になった。その会社内でもSさんは持ち上げられる顧問のような存在だったので、F君は社内でも一目(いちもく)置かれるようになったそうだ。
F君にSさんは私のことを何か言っていたかと聞くと、『すぐに弁護士にならずに、まずは検事になってから弁護士になれと言ったのに」と繰り返したらしい。やっぱり懲りない人だったと思ったものだ。
でも私はそういうSさんにとても愛着を感じていたのである。
また、毎日新開地で映画ばかり見て一向に働いている様子がなかった酒屋のお兄さん、彼は私に映画館や神戸松竹座の入場券をよく譲ってくれた。
近所には、どこで働いてお金を稼いでいるのかわからないオジサンもいた。歓楽街はお金が回っているのでそういう人たちも暮らせたのかもしれない。
騒がしいまでのにぎわいのあった庶民の街で、「人間の素(す)」を出しながら生きてきた新開地のオジサン、オバサン、友達とその家族の姿が蘇った。
母の涙、友達の笑顔、小学校からの帰り道の夕焼け、串カツのかおり、パチンコ屋の騒音、野球グロ―ブの皮革の臭い、銭湯の映画のポスターなど、頭の中で記憶を辿ったレベルではなくて、まるで身体全身で何かを取り戻そうとしていた。
以前にも述べたが、新開地界隈のオジサンたちは私の周りのビジネスマンより圧倒的に良い顔をしていた。収入や財産は少なく、将来の保障もなかったのにだ。
人の表情が輝いたり魅力的になるのは、収入を増加させたり合理的な思考を高めることから生まれるものではないのだろう。
休職中に彼らが何度か夢の中に登場した。大企業の組織論理の中では、どうにもならない自分の課題解決を、会社員とは対極にある彼らのエネルギーに求めていたのだろう。
「原因―結果」の因果関係よりも心の中の葛藤
会社に復帰すると、周囲は私の休職の原因を上司との確執であると結論付けていた。
たしかに私と相性がいいタイプとはいえなかったが、それが主要な理由ではなかった。
直接的な原因は、大きな環境変化(所属異動、未経験の仕事、新たなメンバーとの仕事、組織再編のドタバタなど)による心理的な疲れだったのだろう。
でもそれだけでは私を納得させる理由にはならない。
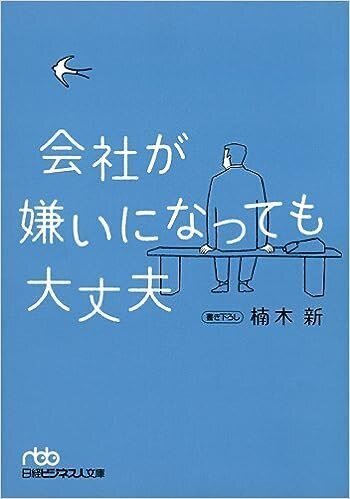
管理職の立場になって自分が働いた手応えを実感できにくくなっていたことも遠因の一つだ。
加えて年齢的なものも関係していた気がするのである。
若い時だったら乗り切れたようなことでも、柔軟に対応できなかったこと。もうひとつは、中年以降になって残り少ない人生なのに、自分がやりたくもないことを繰り返すのはもういやだという気持ちが徐々に強くなっていた。
後者のストレスがすべてを後ろ向きにした。内面のジレンマが大きかったのである。一方で、周囲は、上司との関係が原因だと結論付けることによって安心したかったのだろう。
「会社に入ってからの楠木の経歴や働きぶりを考えると、君が仕事を投げ出す理由がわからない。会社に入るまでの生い立ちにでも関係しているとしか思えない」という同期入社T君の発言を「結構本質を突いているかなぁ」と興味をもって耳を傾けたことを覚えている。
こどもの頃の原体験は私を強く規定していたのかもしれない。
大切なものを捨てなければ、価値のあるものは手に入らない
結果的には50歳の時に体調は戻った。
回復した理由は特に思い当たらなかったが、「もう病院や医師や薬に頼っても無理だ、どうにもならないんだ」と諦めかけたことが次のステップにつながった気がするのである。

当時、産業医が私に語った「葛藤の場面では、捨てる作業が必要だ」という言葉がその時頭に浮かんだ。「捨てる」というのは「居直る」ことでもある。
医師などの専門家が取り組む対症療法的アプローチでは、マイナスからゼロの世界(元の状態)に戻すことが第一目標とされる。
また当の本人も悪い状況から脱して元の状態に戻ることを強く望んでいる。しかし今までの自分の働き方やライフスタイルがメンタル不全を呼び込んだケースでは(私の場合はそうである)、単に元の状態に戻るだけでは同じ繰り返しになる恐れがある。
私が会社に復職後に再び休職したのは、本来の解決には至っていなかったからだ。本当の回復は、元に戻ることではなく、「自分の心構えを何らかの形で切り変えること」「今までとは違う新しい生き方を探すこと」だというのが実感である。
体調が戻ったときには、それまでの20数年間で築いていた会社での役職や立場を失うことを割り切れた感じがあった。
逆に言えば、私たちが変わることをためらうのは過去に手に入れたものを手放すのが怖いからだ。
会社員という人生を送っていると、自分が属する組織との関係で大切なものをあきらめるタイミングが必ずやってくる。
会社の破たんやリストラ、左遷による場合もあれば、定年退職、役職定年、病気や思いもよらない事故に遭遇したことがきっかけになるケースもあるだろう。
いずれにせよ、このあきらめるというか捨てる作業がないとなかなか新しい道が見えない。
後ろのドアを閉めなければ前のドアは開かない。一方的に貯め込む姿勢ではなかなかうまくいかない。
私が長く取り組んできた「転身」についての取材でも感じるのは、その捨てる作業を後押しするのは、自身の生い立ちや子どもの頃の体験、病気にかかる、家族関係の見直し、故郷への思いなどが影響している場合が少なくないのである。
50歳から会社に復職して、これからは本当に自分のやりたいことをやろうと決意した。しかし簡単にはいかなかった。新たなステップにいくには一定の試行錯誤や人との出会いが必要だったからだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
