
だしに過ぎない 平野啓一郎の『三島由紀夫論』を読む40
『春の雪』第三十八章、思い通りに聡子に会えない清顕はこんなことを思ってみる。
大切なのは心ではなく状況だつた。清顕の、疲れた、危険な、血走つた目は、二人のためにするこの世の秩序の崩壊を夢見てゐた。
「大地震が起こればいいのだ。さうすれば僕はあの人を助けに行くだらう。大戦争が起こればいいのだ。さうすれば、……さうだ、それよりも、国の大本が揺らぐやうな出来事が起こればいいのだ」
清顕の考えは深沢七郎の『風流夢譚』そのものだ。あるいは第三巻のドイツ文学者のような考え方ではあるまいか。
打撃と言えば、昭和三十六年二月一日に発生した嶋中事件の影響も大きい。嶋中事件とは、「中央公論」(昭35.12)に掲載された深沢七郎の「風流夢譚」(夢の中で起こった革命において天皇や皇族が処刑される話を戯画的に描いた小説)に憤慨した右翼少年が、浅沼社会党委員長刺殺事件(昭35.10.12)に刺激されて、中央公論社の嶋中鵬二社長宅を襲って夫人に重傷を負わせ、家政婦を刺殺した事件である。その際、「風流夢譚」を「中央公論」に推薦したのは三島だという風聞が流れ、三島は右翼から脅迫され、約二ヶ月間、警察に護衛されることになる。実際には、三島は「風流夢譚」の雑誌掲載を推薦したわけではなかったが、事前にその原稿を読んでいたのは事実で、この作品の扱いは難しいので自作の「憂国」と併載して毒を相殺したらどうかということを、「小説中央公論」編集部の井出孫六に伝えていた。従って、三島は「風流夢譚」の掲載と全く無関係というわけではなく、その結果として、実際に人が殺され、三島自身も生命を脅かされるというのは、やはり只事ではなかったのである。
三島の、清顕の言い分は天皇を弑すとまでは言っておらず、具体性を欠くことから事件にはならない。それは『風流夢譚』だけではなく『宴のあと』によっても学んだ教訓があるからで、具体的な実在の人物に刃を向けることはできない。しかし方向性はまさに謀反である。
それにそれに対して童貞の‼ 本多は、
「貴様がやればいいぢやないか」
と指嗾する。平野啓一郎はここで指嗾と言うべきであった。この童貞男は世界の秩序の崩壊を自らの手によって行うことを清顕にそそのかしている。
この後、白っぽい土竜の死体が出てきて、清顕と本多は黒い犬の死体を思い出す。つまり何かしら意識の中では黒い犬の死体と土竜の死体が因縁づけがされる。清顕はその土竜の死骸の尻尾を摘まんで掌に横たえ、また尻尾を摘まんで池に放る。
土竜の尻尾は鼠ほど長くはない。腹の白い土竜というものにも思い当たらない。
ただそういうものが出てくる。これは何を意味するのか。
これが「無力な一個人」のアレゴリーなら、とてもこの先を読む気がしないなと、平野啓一郎でも思うだろう。この土竜はただの土竜で何の寓意も持たない。そうでなければ平野はこの土竜について触れなければならなかったはずである。
平野は金閣寺を天皇だと見做した。では土竜は何故天皇ではないのか。
わざわざ拾い上げて放り出す。この行為そのものがアレゴリーに対する拒絶であろう。しかし本多はここに清顕の心の荒廃を読む。
それなら何十年先に、貴様が貴様の一等軽蔑する連中と一緒くたに扱われるところを想像してごらん。あんな連中の粗雑な頭や、感傷的な魂や、文弱という言葉で人を罵るせまい心や、下級生の制裁や、乃木将軍へのきちがいじみた崇拝や、毎朝明治天皇の御手植の榊のまわりを掃除することにえもいわれぬ喜びを感じる神経や、……ああいうものと貴様の感情生活とが、大ざっぱに引っくるめて扱われるんだ。(中略)そうしてその『真実』というやつは、百年後には、まるっきりまちがった考えだということがわかって来、俺たちはある時代のあるまちがった考えの人々として総括されるんだ。(中略)その時代をあとから定義するものの基準は、われわれと剣道部の連中との無意識な共通性、つまりわれわれのもっとも通俗的一般的な信仰なんだ。時代というものは、いつでも一つの愚神信仰の下に総括されるんだよ。
この時代というものに反発を感じていたのはそもそも本多の方であった。清顕は雅びにそめられた薫育によりそういうものを体質的に受け入れずにいただけで、明確に言語化して批判していたのは確かに本多だった。ところがその立場が入れ替わった。
清顕は反時代的な批判精神を持っていない。確かに私的な言い分で、秩序の崩壊による混乱を求めているだけだ。
物語としては三十九章で「拒まれた清顕」というものかはっきりと描かれる。夜聡子の家の前まで行って、その明かりが消えるのを眺め、むなしく帰るさまを見ると、勇ましい、小生意気な、自分が聡子に惚れられていることに自信満々の清顕がもう懐かしい。
荒ぶる神の仄めかしももうどこかへ消えている。なるほどそんなものは単なる夢だとしか思えなくなる。
清顕は松枝侯爵に撞球室へと呼びだされ、蓼科の書置きを突き付けられる。その「御姫様懐妊も内輪のことだから」と言うレトリックで、そこに清顕の名がなくとも、これは清顕がしたことだろうと詰められる。
たかが人間如きに。
あとは清顕の意志とは関係ないところで話が進んでいく。聡子の妊娠を知ってしまった松枝侯爵は清顕を打ち据え、聡子を堕胎させる計画を練る。清顕には謹慎が命じられる。ここでバカ親父とバカ息子が出来上がった形にはなる。
無論ここは火掻き棒で殴られる本多とビリヤードのキューで殴られる清顕の対を見なくてはならないところであるが、例によって平野にはその視点はない。「23 清顕の美と死」で「世俗的失墜」と書きながら、そして「57 「道徳要請」としての現実世界」において、本多の罰を、
それは、徹底して世俗的な評価であり、
と捉えているのに対として論じない。平野は『春の雪』を『仮面の告白』のシンメトリーと見做すことで、『天人五衰』との比較をことさら避けているように見える。
この世の秩序の崩壊を夢見てゐた清顕の前で清顕の起こした小さな渦巻はたちまち何事もなかったように納められようとしていく。第四十章、ただ決めかねて先延ばしにすることしかできなかった綾倉伯爵は、実に優雅であった。
あらゆる解決には、趣味のよさに於て欠ける点があつたから、誰かがその趣味の悪さを引受けてくれるのを待ったほうがよい。
この優雅さは松枝侯爵の母、清顕の祖母のいかつい豪胆さと対をなすものだ。
宮様の許嫁を孕ましたとは天晴だね。
綾倉家の雅びは、そういう世界を知らない私には調子っぱずれなものに見えるが、本物の貴族の世界を知っている三島由紀夫の言い分の方が正しいのであろう。又薩摩の女はこのようにあけすけに豪胆なのであろう。ここに北一輝の禁書を絡めると三島由紀夫の狙いが透けて見えるような気が……。
しないな。
よくよく考えてみると童貞本多は禁書によって少なくとも「万世一系の天皇」などというものが出鱈目であること、天皇の権威というのは仮に薩長の君主が担ぎ出したものでありながら未熟なもので、社会的に作り出していかねばならないものだというような考え方もあることを知っていたのである。
ところが北一輝の本が禁書とされていることから、清顕はまだ万世一系などという神話を信じているかもしれない。乃木大将は崇拝しないけれども、形式的には春日宮妃殿下の御裾持ちにうっとりすることによって、清顕は天皇という創られた権威には気がついていないのだ。
この天皇観のずれは答え合わせがされないので顕在化しない。しかし綾倉家と松枝家の対応の中には、少なくとも宮家に対する考え方のずれがあり、そこはうっすらと付け合わせされていないであろうか。
平野は清顕の罪が死とは結び付かないと繰り返し指摘している。それはあくまで聡子が宮家の一人の許嫁に過ぎず、聡子を孕ませることは天皇の権威を犯すことには繋がらないという指摘であろう。では宮家の一人の権威とはどのようなものであるか。
まずわかりやすいのは松枝侯爵家の考え方である。何事もなかったようにことを進めようと判断するのに躊躇がない。
これは殆どサラリーマン社会における上司と部下、或いは取引先との関係、つまりあくまでもビジネスライク、正義や道徳ではなく損得の関係に近い。ミスは隠してごまかせばいい。つまり宮様が自分の息子のお手付きのしかも堕胎までさせられたお古を妃として迎えねばならないこと自体は問題ではないのだ。ビジネスなので自分の利益で動く。忠義心はない。
綾倉伯爵家においては宮様に対する敬意というものはそもそも問題にもならなかったように見える。綾倉伯爵家の雅びには、損得などと卑しい考えが入り込む余地がない。こちらも忠義心はない。ただ雅びである。
いや全然雅びではなかった。すっかり忘れていた。第四十一章には、自殺未遂の見舞いに来た伯爵と蓼科の対峙が描かれる。蓼科は八年前に殿さまから伺った話は秘密にして死ぬつもりでいた、と脅す。
八年前の綾倉伯爵が春画を見ている様子が描かれ、春画には身丈と同じ大ききの男根が描かれ、それらは皆奪い取られてしまう。「男根を満載した一艘の船」に伯爵は何とも言えない陰気な気分になる。八年前のことである。この時とさらに十四年前との二回、蓼科に伯爵のお手がついた。
この八年前の日、伯爵は蓼科に松枝侯爵から受けた屈辱を明かし、復讐の企てを命じていたのだ。松枝侯爵から受けた屈辱とは聡子の婿を自分が探してきて嫁入り道具の行列を拵えてやるという宣言だった。そこに「綾倉家の代々から一度も出たことのないやうな長い長い豪勢な行列をね」と加えたことで、伯爵夫人は眉をひそめたが、伯爵は柔和に笑っていた。
しかし新興貴族の金持ち自慢がどうしても許せなかった伯爵は蓼科にこう命じたのである。
松枝の言いなりになって縁組が進められたら、誰でもいいのでその時聡子が気に入っている男と添臥=させてくれと。聡子を生娘のまま松枝の世話する婿にやってはならないと。そしてこんなことも言う。生娘でないものと寝た男に生娘と思わせ、逆に生娘と寝た男に生娘でないと思わせられるかと。
ここで例の「支え」が蓼科の教えであり、清顕の行動がやはり蓼科に操れたものであり、綾倉伯爵の復讐が松枝侯爵親子をバカ親父とバカ息子にしてしまったことに気がつく算段である。
確かに言われてみれば「聡子の手が、やさしく下りてきてそれを支へた」というのはまるで玄人の仕事である。それに蓼科は本気で絶対に止めようとすれば止められたはずであり、こうして結果的にすべてが伯爵の依頼であったと明かすことにより、伯爵をやり込めてしまう。
綾倉伯爵の雅びもまた、指嗾であった。自らは手を下さず、伯爵は松枝侯爵に復讐を果たすことになった。形式的には宮家は復讐のだしに使われたことになり、綾倉伯爵はあとは侯爵が何とかするだろいうわけで「すべては人まかせの段階に入つたのだ」とまで考える。これが本物の雅びなのか?
ここには恋とは凡そ呼びえない、むき出しの性がある。それはまさに春画のような淫靡な世界だ。
伯爵が見舞いに来ると知らされて蓼科は化粧をした。八年前に既に五十路半ばの蓼科が六十三四になってまた女として伯爵を迎えたのだ。「男根を満載した一艘の船」、化粧した蓼科、そして清顕のホワイトアスパラガスを支える聡子の小さな手……。
清顕はそれが蓼科の教えであることに永遠に気がつかないだろう。清顕は天皇の正体も、天皇の病気も、そしてこんな皇太子も知らずに死ぬのだ。
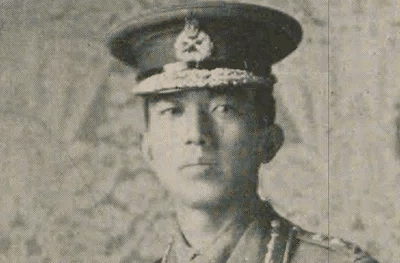
清顕の恋、或いは行動は、綾倉伯爵の復讐のシナリオの現実化でもあった。清顕の感情は蓼科に巧妙にコントロールされて、聡子を孕ませた。綾倉伯爵は何度もセックスさせなさいとは命じていない。清顕は一回だけで終わりにできなかったから目的のないセックスを続けさせられていただけだ。清顕もまた蓼科の復讐のだしに過ぎない。これが恋の話に見える人は眼科に行っても無駄である。
[余談]
読み直してみるとかなり細部は忘れている。複雑すぎて仕掛けが全部拾えない。
(堕胎) 第212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕 胎したときは、1年以下の懲役に処する。
こんなことも調べたはずなのに忘れていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
