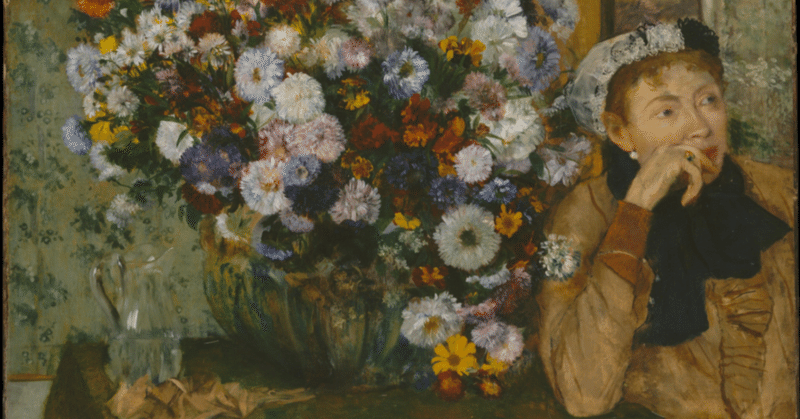
カメラ残しの術 芥川龍之介の『西郷隆盛』をどう読むか③
芥川が「シナリオもの」においてかなり先進的なカメラワークを遊んでいることは既に述べた。『誘惑』しかり、
それから『浅草公園』しかり、
そして「シナリオもの」とは言えないが、やはり映画を意識した『影』のカメラワークはすごい。
しかもそれは飽くまで言われてみればの話で、芥川の文章は圧搾の美で上手いとは言われるけれどカメラワークという点ではあまり言われてこなかったのではなかろうか。そして寧ろ自然と言葉に意識が操られて理解してしまい、その構図の斬新さに気がついていない人も多いのではなかろうか。そのカメラワークは大正六年の時点でかなり遊ばれていた。
「同じ汽車に乗っているのだから、君さえ見ようと云えば、今でも見られます。もっとも南洲先生はもう眠ねむってしまったかも知れないが、なにこの一つ前の一等室だから、無駄足をしても大した損ではない。」
老紳士はこう云うと、瀬戸物のパイプをポケットへしまいながら、眼で本間さんに「来給え」と云う合図あいずをして、大儀そうに立ち上った。こうなっては、本間さんもとにかく一しょに、立たざるを得ない。そこでM・C・Cを銜えたまま、両手をズボンのポケットに入れて、不承不承に席を離れた。そうして蹌踉たる老紳士の後うしろから、二列に並んでいるテエブルの間を、大股に戸口の方へ歩いて行った。後にはただ、白葡萄酒のコップとウイスキイのコップとが、白いテエブル・クロオスの上へ、うすい半透明な影を落して、列車を襲いかかる雨の音の中に、寂しくその影をふるわせている。
実際カメラで撮影していればなんということはない画である。しかしこれはまだ映画なりフイルムなりというものが一般的ではない時代、ましてや動画撮影経験など皆無であろう若者が、さも動画撮影をしているかのように忍法カメラ残しをやってしまった瞬間である。
大正四年の『羅生門』に既に引きの画からの寄り、カメラのスイッチというものは見られたのだが、カメラ残しも大正六年の『西郷隆盛』で自然に滑り込ませていた。
大正七年の『地獄変』ではカメラを左右に振っている。
あるいは芥川はやろうと思えば全然できるのに、当時の読者には到底理解されまいと遠慮して、極端にアクロバティックなカメラワークは『誘惑』までは抑えていたのではあるまいかと思えてきた。
ところが乗って見ると、二等列車の中は身動きも出来ないほどこんでいる。ボオイが心配してくれたので、やっと腰を下す空地が見つかったが、それではどうも眠れそうもない。そうかと云って寝台は、勿論皆売切れている。本間さんはしばらく、腰の広さ十囲いに余る酒臭い陸軍将校と、眠りながら歯ぎしりをするどこかの令夫人との間にはさまって、出来るだけ肩をすぼめながら、青年らしい、とりとめのない空想に耽っていた。が、その中に追々空想も種切れになってしまう。それから強隣の圧迫も、次第に甚しくなって来るらしい。そこで本間さんは已むを得ず、立った後の空地へ制帽を置いて、一つ前に連結してある食堂車の中へ避難した。
これは説明であり、描写にしていない。ここを「そこで本間さんは已むを得ず、一つ前に連結してある食堂車の中へ避難した。立った後の空地は制帽か置かれていた」と書くと忍法カメラ残しの気配にはなる。しかしここは敢えてやらない。
で忍法カメラ残しのその後がまたすごい。
それから十分ばかりたった後の事である。白葡萄酒のコップとウイスキイのコップとは、再び無愛想なウェエタアの手で、琥珀色の液体がその中に充みたされた。いや、そればかりではない。二つのコップを囲んでは、鼻眼鏡をかけた老紳士と、大学の制服を着た本間さんとが、また前のように腰を下している。その一つ向うのテエブルには、さっき二人と入れちがいにはいって来た、着流しの肥った男と、芸者らしい女とが、これは海老えびのフライか何かを突つっついてでもいるらしい。滑らかな上方弁の会話が、纏綿として進行する間に、かちゃかちゃ云うフォオクの音が、しきりなく耳にはいって来た。
が、幸い本間さんには、少しもそれが気にならない。
コップにフォーカス。まだ本間さんと老紳士はアングルに入れない。少しカメラを引いて本間さんと老紳士をアングルに入れる。その一つ向こうのテーブルもアングルに……いやこれは、「さっき二人と入れちがいにはいって来た、着流しの肥った男と、芸者らしい女とが」と書かれていなかった過去のシーンが追加され、あとは音になっている。「らしい」と書かれているのでカメラでフォーカスされていない。絵にしてみればピンボケの着流しの肥った男と、芸者らしい女が背景には見えなくもないが、聞こえているのは音で、老紳士は悪戯の手ごたえを味わうように無言で本間さんの困惑の表情をじっと眺めていたことになる。「滑らかな上方弁の会話が、纏綿として進行する間に、かちゃかちゃ云うフォオクの音」にガンマイクが向けられてる。
凄いな。
トーキーが始まるのが昭和初期。これは大正六年の作。
それで音をこんな風に操るのか。
何故かと云うと、本間さんの頭には、今見て来た驚くべき光景が、一ぱいになって拡がっている。一等室の鶯茶がかった腰掛と、同じ色の窓帷と、そうしてその間に居睡りをしている、山のような白頭の肥大漢と、――ああその堂々たる相貌に、南洲先生の風骨を認めたのは果して自分の見ちがいであったろうか。あすこの電燈は、気のせいか、ここよりも明くない。が、あの特色のある眼もとや口もとは、側へ寄るまでもなくよく見えた。そうしてそれはどうしても、子供の時から見慣れている西郷隆盛の顔であった。……
そしてこれが本間さん目線のカメラでの回想シーン。
まだ黙っている。
まだ黙らせている。
しかし「滑らかな上方弁の会話が、纏綿として進行する間に、かちゃかちゃ云うフォオクの音」は気にならないので、本間さんの回想シーンがはじまると同時に音はミュートされる格好だ。
なんたる構成。
なんたる演出。
もうあほくさいよって屁こいて寝たろ。
[附記]
「らしい」と「気にならない」でこんな芸当ができる人間が外にいるだろうか。いないなあ、たぶん。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
