
マイナンバー制度の問題点⑦
「高額っていくらのことなんですか?」と聞いてみたら、年齢や使徒によるってはぐらかされちゃった。 pic.twitter.com/bNxZEVlZXY
— 小林 敬明|PDFへの書き込みはAxelaNote (@takobaya391076) December 29, 2022
マイナンバー制度の最大の問題はリーガルとテックの両利きの人材不足、そこから生じる情報不足だと書きました。そして現在、最も遅れているのは法改正論議です。この点に関して既に、
まず必要なことは法律概念の整理・統合です。その前に文語体と口語体と旧字体と新字体が一つの法律の中で継ぎはぎにされている問題こそ検討されるべきなのです。
現にマイナンバーの主な利用目的である「税」と「社会保障」の間で、同じ呼び名のものが別の意味で使われていること、そのことが問題視されないことが一番の問題でしょう。
あるいは同じ社会保障の枠組みでも健康保険と年金では「お給料」のことを「報酬」と呼び、労働保険では「賃金」と呼びます。そして呼び名だけではなく「報酬」と「賃金」は全く異なる法律概念なのです。税法では「報酬」とは弁護士などに支払われる外注費です。さらに言えば労働法の中でも法律ごとに「賃金」の概念が異なります。こうした問題を無視して、制度設計が進められています。
このように書きましたが、もう少し具体的書くとこういうことです。

つまりこれではバックヤード連携もワンストップも本来はあり得ないわけです。
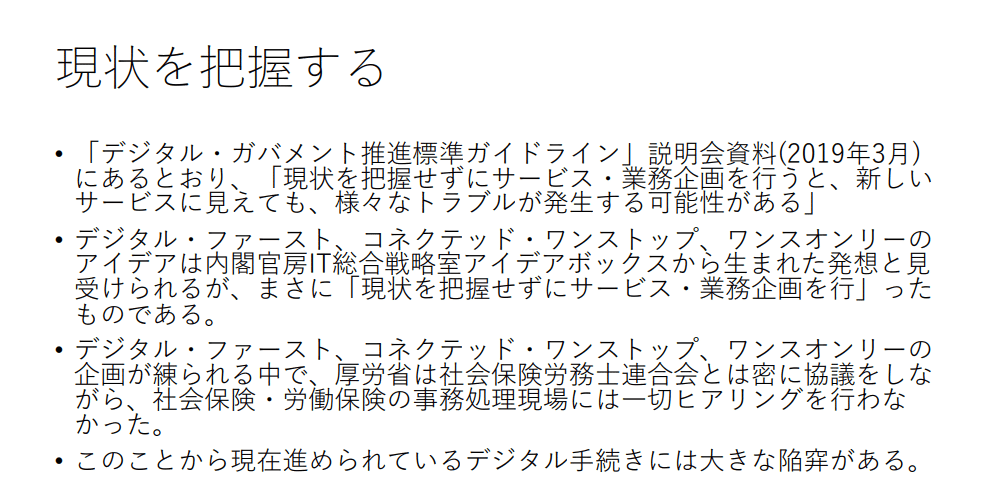
しかしよくよく考えてみれば、そもそもこんなばらつきは誰にも見えていないわけです。それはまさに「リーガルとテックの両利きの人材不足」から来ることで、なかなか議論になりません。
それでもこれまでのIT総合戦略室の構成員にそうした問題意識が皆無であったわけではありません。元内閣官房 森田勝弘氏はあくまで個人的な見解としながら『日本の電子政府政策の歩みと問題提起』という論文をJ-STAGEで公開し、その中ではっきりと「法律用語の不統一」を指摘し、その解決策の提案をしています。しかし2014年に提案された「論理プロセスリポジトリ」は、まだ存在しません。
またその後、この問題が繰り返し議論されている形跡は見当たらず、デジタル庁にも「法律用語の不統一」を検討している気配はありません。

特に法令の使っている用語も、文脈で意味が決まるというのはおっしゃるとおり多数あるというところでございます。例えば記号の意味を事前に固定するのではなくて、それが意味の幅を持ち、それ以上は文脈で決まるといったモデル化も考える必要があるなと思っていまして、その辺りを専門家の先生方にご意見をいただきながら、議論させていただきながらつくるのがいいのかなと思っております。
これが令和4年11月9日における事務局の認識です。つまり「モデル化も考える必要があるな」という認識であり、「論理プロセスリポジトリ」の提案がまるでなかったもののように議論されているということです。
稲谷作業部会構成員: 私も実は今まさに同じことを言おうかなと思っていたところでして、アノテーションに当たるところが最終的に残らないと、人が解釈を行っていく上で、しんどいところが出てくる可能性があるというのはそのとおりだと思うのですね。
ただ、そのときの視点を誰にするかというのは大事な問題かなと思っています。要するに、解釈権限とか概念設計というのを最後にやるのは、我が国の制度的には裁判所だと思うのですね。
つまり、法の作り方においては、裁判所が、どういう概念がどういう形で出てきていて、だから今回の事案に関してどうなのだという概念形成や概念内容の範囲決定をすることを念頭においてきた、日本の法解釈学は基本的に裁判所における法解釈を精緻化するという観点から出てきたところもあって、それが改め文に対する愛ともきっと関係しているのだろうなと思います。そうすると、この種の法創造に関わる人たちから見ても問題ない形式を整えておくことが、結果的にスムーズに新しいやり方に移行していく上で重要な意味を持つのだろうと。
さらに令和4年3月16日時点ではまだ法律を「人」に解釈させようとしています。これでは所謂法律のデジタル化というものは成立しないわけで、あれかこれかというバイナリーな法律というものは目指さないとも解釈できます。
ところで現実的には国は例えば非課税世帯を対象に、給付金を支給する訳です。
商船三井から配当が来ていました。 pic.twitter.com/xzM1bjMODa
— あば (@ei_washington) November 29, 2022
仮にこの人に他に収入がなく、独身で、源泉控除のみで処理をしていた場合、この人も非課税世帯ということになり、給付金が支給されます。私はそのことが悪いとは思いません。そういう法律の仕組みなので。
しかし「非課税世帯」という法律用語に、国会議員さんたちが勝手に「貧困世帯」→「生活困窮世帯」という解釈を与えていることは確かですよね。私が指摘したいのはむしろそうした人間側の勝手な思い込みの問題です。これは税制や社会保障を論じる為政者が税制や社会保障の仕組みを理解していないという問題ですらない。
むしろそこではないのだ。
勿論もらうべきではない人が給付金を貰っているのが駄目だなんていう程度の低い話でも無い。
むしろ問題の質は、
こうした近代文学の根源的な陥穽に似ている。
この「非課税世帯」の問題にはツイッターで荘司雅彦氏(サイバー大学客員教授 弁護士)にも絡んだのですが、あまりピンと来なかった様子です。この肩書の人に絡んで無駄なら、後は誰に絡めばいいんですかね?
自分はマイナンバーに関しては完璧だという人はぜひ名乗り出て欲しいものです。
実は法律そのものが選択と解釈で個人の属性を様々に捉えてしまっている、という事が云えます。この問題そのものを問題として認識できる人が現れるまでは、マイナンバーでデジタル社会が実現されるなんてことはありません。
Q.日本人は物事を白黒つけるのが下手だと思いますか?
— 一目置かれる雑学 (@trivia_hour) December 29, 2022
・思う 21%
・思わない 7%
・どちらともいえない 72%
M Kodak Gray Scale Kodak, 2007 TM: Kodak 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19 inches cm 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kodak Color Control Patches Blue Cyan Green Yellow Red 3 4 10 6 15 7 11 12 13 14 16 17 18 19〓Kodak, 2007 TM: Kodak 3/Color Black Magenta White 299 SOTST229741200 662-155
888
尾崎那陶洵盛著寶雲磁小考舍藏版
尾崎那陶洵盛著寶磁雲舍小考藏版
縣地虎龍遂昌圖全境縣泉龍13リト后昔ハ可赤七イ床褥管山政石浦城縣界處上春田文源氏新薔上映下東五都竹曲白歩菴苦縣界慶元汎根荒村景〓縣界벼村竹森蝶順汎梅小縣界慶元(載所志縣泉龍藏庫文洋東)圖地縣泉龍
(藏氏尾押花立)片破瓷靑取採岸海倉鎌
(藏館物博室帝京東)鉢瓷靑窯泉龍
(藏館物博室帝京東)皿繪赤州吳
(藏氏作茂町反)枕陶(麗高繪)窯洲磁
(藏氏輔民河橫)鉢窯
662-155序本書は昭和七、八兩年間に東洋陶磁〓究所より發行する雜誌「陶磁」に投ぜる拙稿數篇を集めたものだ。本來とくに故紙となつて埋もるべき運命にありしものが計らずも寶雲舍の爲めに拾ひ上げられ一册に輯めて美々しく裝幀されて再び世に出ることになつた。これ所謂枯木に花が咲き埋れ木の世に出ると云ふ僥倖であつて余の全く豫期せざりしところ眞に感謝に堪へざる次第だ。さて併し乍らかく外觀の立派な本になつてみると其の內容の蕪雜さが一入目立つ、然し今更書き直す譯にもゆかぬから只數ヶ所に少しばかりの補訂を行ひたるまゝに止めた。讀者幸に取捨し讀者幸に取捨して可なり。按ずるに支那古陶磁の學は今日尙ほ未解決の大問
題が餘りにも多い。さりとて支那の現狀では重要なる古窯址の學術的調査と云ふ樣なことは痴人夢を說くに等しい。而かも之れが行はれざる限り是等諸問題の徹底的解決は期待出來ない場合が多いのであるから支那古陶磁學が首尾一貫せる完全なる學問の體系を具ふる樣になるのは前途尙ほ遼遠と云はねばならぬ。併し乍ら文献の方面を省ると從來東西磁學家によりて殆んど資料は漁り盡されたかの觀あるも余の經驗の寡陋を以てするも猶ほ時に網に洩れたるものを發見せること之れなきにあらず。若し夫れ既知の文献の考察に至りては從來磁學家の行ひ來りたるところは可なり遺憾の點が少くない樣だ。卒直に云へば是等旣知の文献は再檢討を行ふべき必要が大いに之ありと信ずる。今本書の數篇の如き此の方面に向つて及ばず乍ら出來るだけ努力せる積りだ。固より廣汎なる斯學から見れば極めて些々たる部分的の〓究に過ぎず且つ余の微力なる其の成果は敢て見るに足らざるも、之れによりて若し多少なりとも斯學に貢献するところあらば望外の幸である。此の機會に於て余の〓究につき多大の便宜を與へられたる東洋文庫、貴重なる名品の寫眞撮影を許可せられたる東京帝室博物館、橫川民輔博士、反町茂作氏、及び立花押尾國手、本書出版に就き快諾を與へられたる東洋陶磁研究所同人並に裝幀につき雅麗なる意匠を凝らされたる小野賢一郞氏等の諸賢に對して深甚なる謝意を表する。是等諸方面の同情及び援助なくしては本書は到底生れ得ざりしであらう。昭和九年五月一日尾崎洵盛識
又於韋處乞大邑瓷盌杜甫大邑燒瓷輕且堅扣如哀玉錦城傳-(4)-君家白盌勝霜雪急送茅齋也可憐
定窯紅瓷につきて哥窯の香爐其の他亡羊寐語圖磁州窯漫筆吳須赤序(三)〓波雜誌に記せるもの(二)文潞公の紅瓷(四)苧麻灰淋汁、芝麻楷淋汁(三)芝麻醬(二)芝麻花(一)椶龍泉窯趾の調査報〓につきて龍泉窯靑瓷鉢龍泉縣地圖(龍泉縣志所載) (一)磁州窯(繪高麗)陶枕吳州赤繪皿鎌倉海岸採取靑瓷破片哥窯鉢(四)蔣祈陶略に見ゆるもの張貴妃の紅瓷版支那陶磁小考眼繪目次(古西) (一〇一) (六二) (五三) (四五〓一〓
支那陶磁小考尾崎洵盛著
龍泉窯址の調査報告につきて支那古窯址の夥しき數に上るべきは今更言ふまでもない事であつて、文献に見ゆる古窯の所在地丈けでも決して少い數では無いが、是等の多數の古窯址の內で學術的發掘調査を行ひたるものの如きは恐らく現在までの處絕無と云ふも不可なき有樣であると思ふ。而して其漸く實地調査に着手せられたるもの二三之なきにあらざるも、是等は大抵人を僦ひて現場に派遣し、其拾ひ集めて持歸りたる破片を檢討する位の程度であるのは殘念ではあるが、現在支那の事情から見て、萬止むを得ざる次第であろう。顧るに過去數十年に亙りて東西の瓷學家と稱する輩は只管文献のみに倚りて支那古陶磁に關する臆說を立て、甲論乙駁、恰かも衆訟の如く斯學の〓究も旣に迷路に彷徨して殆ん文献に見ゆる古窯而し現場に派遣し、
ど一步も進むこと能はざる底の今日に方りては、須らく文献上のみの議論は姑らく之を中止し、假令學術的の發掘調査にあらざる不完全なる調査にせよ、實地現場の踏査の結果に一應耳を傾くるのが至當であると云はねばならぬ。而して其踏査の結果は頗る有益なるものがあつて、よしんば學術的確實性は之を他日の用意周到なる發掘檢討に之を讓らねばならぬにせよ、從來行はれた臆說迷夢を打破一掃して古窯乃至古陶磁の〓究に頗る偉功を奏すべきことは、數年來大谷光瑞師が行はれた河南省の諸窯址、並に南宋官窯址等の調査に徵して明白である。今此に紹介せんとする陳萬里君の龍泉窯址に關する實地調査報〓の如きも亦た其一例であつて支那古陶磁の〓究に關して確かに劃期的の一調査であると思ふ。尤も同君は自ら斷つて居る通り瓷學家にあらず、又考古學者にもあらず、加ふるに政務調査と云ふ用務を帶びて居たのであるから、其餘暇極めて短時間の間に、只同地方に出張した機會を捕へて、數ケ處の窯址を見て廻り且同地方の人々につきて種々質ねて獲たる結果を報告せる程度に過ぎないのであるけれども、龍泉窯が宋元以來數百年間頗る有名であつて、其產出せる靑瓷が品質から云ふも、又數量から云ふも世界に冠絕して居るにも拘はらず、未だ曾て實地現場を踏査して報告せる者あるを聞かざりし事情に鑑み、又現在是等の窯址が如何なる狀態になつて居るかを知るのに頗る興味ある參考資料であると思ふから、旣に四年前の調査報告であるけれども此に紹介する次第である。殊に同君の報〓は惟だ人を俄ひて現場に赴かしめ自分は坐して其話を聞いたのとは事違ひ、自ら親しく其地方に赴き且其若干は自ら現場を見て廻り破片を採收したのであるから其報告は潑刺として生氣に滿ちて居るし又其價値に於て前者とは格段の相違があることは言ふまでも無い。而して親歷せる部分と、訪聞即ち聞き書きによつて得た資料とを區別して記述せる如き頗る同君の眞摯なる態度を覗ふに足るものと思ふ。聞く處によればかつて陳萬里君は西域〓究を專攻し燕京大學の史學科を〓へ、著書西行日記があり、今上海にあつて醫者をしてゐるとのことだ。陳君が龍泉窯の古址を踏査したのは民國十七年即ち西暦一九二八年の六月であつたが、同君這回の旅行は、前記の如く龍泉の窯址を探るのが主要の目的ではなくて、舊處州府所屬の各縣地方の政務を視察するのが目的であつて且同君は元來磁學家ではないし、又考古學者でもないけれども、此の旅行の序を以て龍泉の古窯址を調査したものだと云ふことであ著書西行
る。そこで旅行に先ちて豫め參考書中から龍泉靑瓷に關する個條を拔萃して之を行李に收め、龍泉に至るに及びて、該地の人等が古墓を發掘して時に得たる器物を以て之を實證したが、中には靑瓷以外往々洛陽方面の塚墓中に發見する所の唐瓷に類するものもあるが、彼の龍虎瓶とか五嘴瓶の如きは從來瓷學家の說述せざる所のものである。而して是等は其價格が暴騰して、往々諸外國へ流出し彼地博物館等に羅致せられてしまひ、國人が之を一見したく思ふも容易に見ることが出來ない、そこで狼狽して〓究を叫ばうと云ふのが今日の有樣である。此外靑瓷の出土するもの十中の九は商人の得る所となり、轉じて上海に運ばれ、高價を以て外國人に賣渡される。最近舊瓷碎片の箱詰にされて外國へ運び出されるものが夥しき數に上つてゐる。夫れ〓朝の初期旣に「李唐の越器人間に無し、趙宋の官窯晨星を看る」の歎があつたのであるが、運命の至る所、廼はち今日の發見ある次第である。顧るに、如何に出土の器物が豊富であつでも、國人が只だ茫然と手を束ねて視て居る計りで其貴むべき所以を知らないと云ふのが我邦の現狀である。此によりて發憤し視察の餘暇を以て勘查に從事する所があつたが、勘查の後其大要を記述して國民の注意を喚起せんと思ふ。是れ自ら講陋を問ふに暇なき故である。宋代靑瓷の內で龍泉窯と稱するは文献によれば即ち弟窯のことであつて、章生一の主どる所のものは之を生二のものと區別する爲に遂に哥窯と稱するに至つたと云ふことであるが、然し今日現在の龍泉に於ける呼稱を按ずるに、則はち哥窯弟窯の所在地は、〓ね只だ大窯と呼んで居るのみである。此外宋代龍泉の瓷窯にして予の實地知る所のものに、尙ほ木岱の一個處がある。而して明代に燒いた靑瓷窯址の龍泉縣治區域にあるものは這回短時間內に調査した結果によれば、磁湖溪、孫坑、胡邊月等の數ヶ處があるし、慶元縣內には竹口新窯(?)、麗水縣內には寳定がある。凡そ此等の地址は從來皆文献に載せてないものであつて、明代に顧仕成の主つた窯の竹口にあるもの、(顧仕成については後に述べる機會があると思ふ)及び從前只だ明代の仿龍泉の窯にして處州府に移りたりと云はれ、而して其地點を詳にせざるものゝ如きも、今則ち留むる所の遺跡、確鑿として考證することが出來る。古籍に記載せられてある所の僅かに傳聞に憑つて輾轉抄錄せられたる者を知る上に於て、苟くも之に加ふるに證驗を以てせんと欲すれば實際の調査にあらざれば功を爲さぬ。而して之と同時に實地經驗の結果、往々意想の外に出る者があることは之を今回の調査に徵して益信ずる者である。今度の親歷せし所及び訪問せる所によりて、各地につき一
一其の大要を述べ樣と思ふ。甲、親歷せる部分是は實地調査せる諸地點である。(一)大窯(宋代の章生一、章生二の窯址)之は大梅に在る。此地は龍泉縣治を距ること八十五里(之は勿論支那里だ、以下做之)、西方は小梅鎭を、又西北は査田市を距ること各十五里。大梅村は溪北に在りて、石榴の木が一本溪上に横斜して生へて居る。溪の南岸に沿ふて行くこと約數十步すれば、即ち曾て發掘せられた洞穴が數ケ所あるのを見る。更に進めば則ち右を見ても左を見ても、土阜穽陷、觸地皆是である。而して舊瓷の碎片、及び窯を燒いた時に用ひた器托、即ち匣鉢等が滿地に狼藉たる有樣だ。其地域を計るに約廣さ十餘畝もあらうか。溪北即ち對岸にも亦た道に沿ふて碎片が澤山落ちて居る。土人の言ふ所によれば、此邊の周圍一帶に窯址が散布して居つて、其數約十ヶ所以上もあるが、然し只だ、何處の窯が哥窯で、何處の窯が弟窯であるかは區別することが出來ない。此處は民國二三年頃に始めて發掘し五六年の頃には〓人の此處に在つて古器を發掘する者が每日數百人位あつた(是れは土地の人の詞だと斷つてある)。此故に靑瓷の出土する者も亦た、此時期を以て最も夥しと爲す。又前年佛國人某が松陽縣の天主〓會の紹介によりて此地に來り、多數の碎片を採收し去つたと云ふ。(二)竹ロ(明の顧仕成及其他)之は慶元縣治域內であるが、北方小梅鎭を距ること三十五里、南方慶元縣治を距ること六十里、龍泉から慶元に至る交通の要路に當つて居る。窯址は市鎭の後街、一帶の山麓の段地にある。土地の人の言によれば、窯址は約十餘ヶ所あつて、後窯許家、後窯陳家の如き均しく其窯址を考ふべき也とある。唯だ顧仕成の窯は何處に在りやと探究するも確切に指明すること能はず。然るに余は後窯許家の處で一ヶ所の窯址を覓め得たが、此邊一面に舊瓷の碎片が散布して居つて、其狀恰かも前記大窯の如くである。所謂後窯なる者は、大窯と云ふ宋代の窯に對して後に起つた窯と言ふ呼稱であるかとも思はれる。(三)胡邊月(明代)龍泉、八都鎭の西南約二里許。(八都は龍泉縣治を距ること六十里)此處の窯址は山坡に靠近してゐて、現在民家の菜圃であるが碎片は餘り多くない。盖し窯址全部が尙ほ未だ發掘せられ居ない未着手であるがらだ。
(四)寳定(宋代?明代?不明)大港頭鎭の對岸に在り。麗水縣治內である。東の方碧湖を距ること十五里、縣治へは六十里である。市鎭の附近に錯落散布せる高阜甚だ多く、土人は窯山と之を名けて居る。實は即ち窯址である。窯を燒いた時に用ひた器托が四圍に散在し、且舊瓷の碎片が夥しく、俯して拾へば即ち是と云ふ有樣だ。此の如き情形の窯山約二十三ヶ處あり、獨逸人某、曾て前年此地に來り地を購ひて發掘せんことを要求せるも、未だ實現する能はずと云ふことだ。て、訪聞せる部分是は實地踏査せざるも土地の人等に種々質問して得た資料即ち所謂聞き書きである。(一)木岱村(宋代)木岱口を距ること五里、東の方八都を距ること二十里。(二)溪湖(明代)龍泉の南、縣治を距ること三十五里、龍泉から慶元へ往くには必らず通過するところだ。東の方八都を距ること二十里。龍泉から慶元へ往くには必らず通過するところ(四)孫坑(明代)査田の西南十五里、龍泉縣治を距ること八十五里、此處は宋代の靑瓷を仿造せるものが澤山出る。土人は之を「孫坑貨」と稱して居る。又此處には現在土窯ありて、專ぱら粗器を燒造して居る。(五)新窯(?)竹口の南方十五里、慶元縣治を距ること四十五里の地點にある。(六)上羊頭(〓代)八都の西方十五里、之は果して靑瓷を仿造する窯であるか、夫れとも亦た尋常の土窯であるか詳かならず。龍泉靑瓷の胎土は細膩にして潔白、識者は景德鎭の土に勝れりと謂ふて居るが、吾人試みに大窯々址から出土せる碎片につきて之を檢査するに、所謂土細質白と云ふは洵とに虛語にあらざるを知つた。寳定、竹口、胡邊月、等の出土品は則はち〓で灰色を帶びて居る、固より大窯に遜ること遠し矣。其然る所以は是等諸窯が胎土を採收せる場所が各異るからである。大窯は果して何處から土を取たか余は得て知らざる所であるが、胡邊月は則慶元縣治を距ること四十五里の地點にある。之は果して靑瓷を仿造する窯であるか、夫れとも亦た尋常の土窯で
今瓷泥を產出した地域を簡略ち沈屋の土を用ひ、木岱窯は則はち之を木岱本村に取つた。に記述すれば左の如くである。(一)木岱村、此地點の距離は前記した。る。現在此處に土窯數ケ所ある。(二)東元坑、此處は孫坑、半邊月、土窯等が瓷泥を取つた處であつて、位の處にある。(三)沈屋、此處は八都を距ること十里。(四)麻洋、此處は八都を距る二十一里。此處の瓷泥は沈屋に比すれば品質稍や劣る。(五)源底、現在の貴溪口にある土窯は則ち此處の瓷泥を用ひて居る。(六)寳鑑、本村には現在土窯が十餘ケ處ある。(七)溪頭、八都の北方十里に在る、本村には現に土窯が十餘ケ處ある。(八)河碟排山、現在開源村の土窯は即はち此處の瓷泥を用ひて居る。(九)東音口、本村にも現に土窯が一ケ處ある。(十)五都垟、木岱口鎭の南五里。此地にも現在土窯がある。此地の土は龍泉所產の瓷泥中最も佳なる者であ土窯等が瓷泥を取つた處であつて、孫坑を距る約五里(十一)車孟黄金澤、本村にも現在土窯が一ヶ處ある。(十二)坑口、本村にも現に土窯が數ケ處ある。(十三)塘上太平下、木岱村の北方約二里。(十四)嶺上、現在埠頭の土窯は即はち此處の瓷泥を用ゆる。(十五)大坦村大塘灣山、木岱口鎭の東方五里。本村にも現に土窯が一ケ處ある。龍泉、慶元附近、及び麗水、寳定、等に蘊藏せらるゝ靑瓷は、其完整にして商人の手を經て買求むる外に策なき者を除きても、地面上に殘存する碎片の豊富なること已に前述の如くであつて、實に從來宋·元·明·〓の靑瓷を〓究する者等の夢想だも到らざる如き意想外の實情である。余が自ら親しく目驗したる所、及び聞きたる處により、一時の感想を日記に筆錄したが、其內から數則を摘錄記述すれば左の如きものがある。(一)今まで諸人の發掘せる方法を見るに、或は側面の方から掘進する者もあり、或は中を掘り去りて一大穹窿を圍成する者もあり、毫も科學的の方法を講ずる者なし。之が爲に折角地中に於て完好に保存せられてあつたものも、右の如き無茶な發掘の爲に必ず大部分破損して了るものが十中八九である。現に余は幾多の碎片にして原來の形狀の內一部分のみ
を留存せるものを見たのである。(二)何の窯趾が果して哥窯であるか、未だ毫も知ることを得ないのであるが、必ずや是は合理的の發掘によりて、磁片上から之を證明する必要があらう。現在に於ては碎片が無茶苦茶に紛亂して仕まい、是によりて鑑別せんとするも、亦た頗る困難を感ずる。(三)此種の碎片は、現在誰一人として過ぎて問ふ者もなき有樣であるけれども、余は考古學上此碎片の〓究は甚だ意議あるものと考ふるものである。此處に得らる瓷片は其種類頗る多く色彩、形狀等種々であるから必ずや其比較研究によりて系統的の說明を立て得るものと思ふ。〓究上此の如く豊富なる標本の陳列してある處は、何處へ行つてもあるまい。品物の完整であると否とは、是れ賞鑑家の玩藝に供せらるや否やの問題に過ぎない、實際考古學上から云へば全然沒交渉の問題である。可惜、余は考古學の專門家にあらず、且又時間も促迫して、萬、余をして多少の光陰を費して是等碎片を檢理する爲に工夫を用ゆるを許す能はず、亦た祗だ短促の時間內に於て見當り次第檢拾したと云ふに過ぎざりき。(以上、民國十七年、六月一日、大窯に在りて記す) (四)這種甚だ得難き物件(龍虎瓶を指す)は中國(政府)自ら應に之が保存に當るべきものだ否らざれば則ち〓究せんと欲する人ありとも容易に國內で見ることを得ざるべし。何ぞ況してや國內の所謂一般賞鑑家及び收藏家の如き偶々一二點の比較的良好なる品を有して居ても仲々人に之を看せしめず、其狀恰かも是れ深窓の娘姐が人に姿を寫されるのを怕るゝに彷彿して居る。說き來りて眞に是れ歎ずべし。(一七年、六月六日、査田市に在り) (五)余か現在拾ひ有して居る碎片は、竹口、大窯、八都の三ケ處で、其他の地方は人に依賴して採收せしめ樣と思つて居る。但だ是れ別人なるが爲に余の用意の存する處を十分呑み込めないであらうし、從つて十分討檢して採拾恰當を得るやは分らない、是れ然し如何とも爲し難き處である。(一七年、六月七日、八都に在り) (六)余は得たる所の碎片の標本を出して寥君に示して看せた。同君曰く「惜むべし、大窯の碎片は數年前已に外國人が人に依賴して箱に詰め、荷造りして運び出して仕舞つた。今は已に極好の碎片は覓め得易からず」と。余の檢拾した大窯の碎片十餘種の內祇だ一片だけ最も好きものがあるが、是れとても大窯の極めて上手の色釉では無い。寥君又曰く「吾國人にして龍泉に至りて碎片を集拾せるは、君が最初だ」と唯だ慙ずる所は、余は瓷器に關して〓究した事が無く、龍泉窯の器物を見たのは祇だ北京の古物陳列所にある物を
見たのみであるから、更に〓究などと云ふことは出來ない。今回の採收の如きも是れ何人と雖も應に思ひ付き得べき事柄であつて、自分は敢て賞鑑家の眞似する譯でなし、又收藏家の仲間入りをする考もないのだ。唯希望する所は手に任かせて些々たる碎片を檢拾して將來〓究の用に備へやうとするに在るのみだ。而して此地は如上多數の古窯址のあることは是れ全然疑を容れざる事實であるが、何の一ヶ處の品物もが決して他處の品物と混合して居らぬと云ふ事が極めて純粹な〓究を行ふに便宜妥當の條件である。然らざれば單に一個の品物を取つて其窯名を判斷せんとする如きことは云ふまでも無く困難な事である。此理由により極めて多數の窯址を跋涉せんと願ふたが、僅々十餘箱の破片を搜し得たのみであつた。願はくば更に大規模の收集を行ひ、省の政府が專門の委員を派遣して其事に當らしめ、收集を了りたる後、各個窯址より收集せるものを把りて其重複を去り、分類陳列して龍泉窯〓究家等の參攻に供せんことを。(七)現在上等の龍虎瓶は大〓米國へ送られて仕舞ひ、日本も亦た一對の牡丹瓶を買取つた、都て是は上海の商人の手を經て賣られたものである。又碎片の箱詰にされて佛國へ送られたものも少くない。幾年前佛國人が松陽縣の天主〓會の紹介により、龍泉に來り碎片を搜集せる者があつた。(八)龍泉の監獄の外面にある泥墻の上に塗り込められて居る二個の破片を寥君が見付けてあつたのを剝がしたが、是は確かに大窯の上等の釉色のものであつて、余の採集せるものに較べれば勝つて居る。之によりても龍泉地方に採取すべき材料の如何に豊富なるかを知るべきである。(以上、一七年六月八日、龍泉に在り) (九)此種の土阜が合計三十餘ヶ處あるが、此地の土人は都て窯山と呼んで居る。而して彼等が發掘したものも自然に地表に露出したものも、都て之を「窯山貨」と呼んで居る。余等は一個の窯山に赴き、山の側面なる泥土の裏から少なからざる燒窯時の坯託を發見したが、同時に多數の碎片をも檢收した。是等は以て比較〓究の材料となすべきである。(以上一七年、六月十六日、寳定に在り)龍泉靑瓷の歷史上の價値旣に彼の如きものがある、而して今回僅々短時日內の調査に得たる所の結果は其窯址に關する者及蘊藏露顯の材料復た此の如くである。之を搜尋し、之を採集し、之を整理するには今や實に多く得べからざる機會であるから、允に宜しく專門家を遂派し、各該地に馳赴し、切實に進行せしめば、成績必ず觀るべきあらん。爰に知る
所に就き、率ね臆見を貢すこと左の如し。(一)切實に調査を要すは麗水、龍泉、慶元、三縣境內の宋代及以後の仿宋靑瓷各窯址の地點區域にして、從來文献に載せず、或は闕略して詳かならざる者に對し充分の勘誤證明及記錄を行ふこと。(二)各該地蒐集の成蹟によりて相互に比較〓究の資料を供給すること。(三)蒐集し得たものを分類陳列して、從來收羅せられたる靑瓷未だ之あらざる大觀を爲すこと。(四)豫め將來整理の結果に備へて、專集を出版し、靑瓷〓究家唯一の參考書を爲ること。(右國立中山大學語言歷史學研究所週刊第四集第四十八期一九二八年九月二十六日發行による)陳萬里君の龍泉窯址調査報〓は大要前記の如くであるが、勿論陳君自身も斷つて居る通り、專門家の專門的調査でなく、只だ同地方通過の序を以て多數ある窯址の一部につき單に若干の表面採收を爲したのに過ぎぬ樣である。而して其採收した一破片をだに見ることを得ないのは如何にも殘念であるが、今之を奈何ともしやうがないから、以下此有益なる報告に關して、二三の管見を述べてみやう。(一)順序として陶說卷二より左の記事を擧げる。宋哥窰の項に本龍泉琉田窰、處州人章生一、生二、兄弟於龍泉之窰各主其一、生一以兄故其所陶者日哥窰、而して次に宋龍泉窯と云ふ項の下に、弟窯即ち生二の窯のことを記述して居る。陳君の報告によれば、所謂大窯なるものが右の哥窯、及び弟窯の窯址であると云ふことであるが、其所在地は大梅であつて琉田とは云はぬ樣である。大梅は果して昔の琉田の地に該當するのであるか、陳君は之に關して何等報告して居らぬが一應査竅の要がある樣に思ふ。琉田は明代には劉田とも書いたらしいのであるが、(後述菽園雜記の記事參照)、龍泉縣志、處州府志、等に揭ぐる當該地方の地圖を見ても琉田、劉田共に見當らない。而して大梅も小さな部落であると見えて、これまた見當らない。因に龍泉縣志は數種あるが、宋志は嘉定二年、邑人何澹の著。明志は、一は嘉靖乙酉、生一以兄故其所陶者日明志は、一は嘉靖乙酉、
八邑人葉溥溪槎人民間で輯。一は萬曆戊戌邑令夏舜臣編。〓朝の縣志も二種ありて、一は順治乙未、邑令徐可先修。一は乾隆の新輯であつて、予の見ることを得たるものは此乾隆志である。宋嘉定の舊志は簡略に過ぎて叙說明鬯を缺くと謂はれ、明嘉靖志は繁に過ぎて添蛇續鳧にして漫衍無家と稱せらる。然し乍ら是等二志は旣に闕佚して幾んど傳はらず。而して明萬曆の夏舜臣編する所の舊志は分類、簡繁、節無く、前後宜しきを失ふ。順治初年に成つた徐志は仍ほ多く明制の舊によりて、食貨の一門の如き頗る繁冗を覺ゆとあるから、相當詳細に叙述せられてあると思はれる。然るに乾隆志は之を節略して仕舞ふたと云ふから、瓷窯の一條の如きも舊志を見ることを得るならば、恐らく其詳を知ることを得るかとも思はれるが、今之を見ることを得ない。さて、順序として少しく重複の嫌ひあるが、乾隆版龍泉縣志の記述を擧ぐるとする。同志卷之一、輿地、古蹟の條には左の如く記述してある。生二章靑器。章姓生二名不知何時人甞主琉田窰凡磁器之出於生二窰者極其靑瑩純粹無瑕如美玉然今人家亦鮮有者或一〓一鉢動博十數金厥兄名章生一所主之窰其器皆淺白斷文號百坂碎亦冠絕當世今人家藏者尤爲難得世人稱其兄之器曰歌々窰其弟之器曰生二章云同以上の記事は從來傳へられて居る所と大差なく、別に珍らしいことはない。然るに同志卷之三、物產の條には左の如くある。靑瓷窯一都琉田瓷窰昔屬劍川自析〓立慶元縣窰地遂屬慶元去龍邑幾二百里明正統時顧仕成所製者已不及生二章遠甚化治以後質麤色惡難充雅玩矣右によれば、琉田は慶元縣に屬し、龍邑即ち龍泉縣を去ること幾んど二百里と云ふのである。若し此記事が眞であらば、琉田と大梅即ち大窰なるものとは全然別所であらねばならぬ。何となれば、一は慶元縣に屬し、龍邑を去ること二百里もあると云ふのてあるし、一は龍泉縣內に在りて縣治を去ること八十五里と云ふのであるから、此二所は到底同一の所だとは考へられないからである。然るに同じ龍泉縣志卷之二、都圖の條には左の如くある。延慶〓在縣西南都六圖二十九一都統圖八都在琉田大梅等處距縣八十里尙ほ又卷之一輿地山水の條には左の通り記してある。別に珍らしいことはない。然るに同志
琉華山在南一都距縣七十里亦名仙山々頂有仙人遺蹟鐵香爐在焉山下即琉田居民業陶是等の記事が事實であるとすれば琉田の所在地は、龍泉縣治を去ること二百里もある慶元縣內に在りと云ふのは誤りであつて、龍泉縣の西南部、延慶〓に在りて、琉華山の麓、龍泉縣治を去ること七八十里程の處であらねばならぬ。之れは孰れが眞實であろうか?。予は後說即ち龍泉縣延慶〓內に在りて龍邑を去る七八十里內外と云ふのが事實であろうと思ふのである。且これならば陳君の謂ふ所の大窰なるものゝ所在地に略ぼ該當する譯である。此事實を更に裏書きするのは明陸容の著、菽園雜記であつて、之には靑瓷初出於劉田去縣六十里と云ふて居る。劉田は云ふまでも無く琉田であつて、劉琉二字、同音相通ずるのである。尙ほ他に一の傍證とも云ふべきは、陳君の記述せる顧仕成の窯址は慶元縣內の竹口であると云ふ事實であつて、由是觀之、前記龍泉縣志卷之三、物產の條下の記事は、琉田と顧仕成の燒いた竹口とを混淆した爲に起つた間違であろうと思はれる。前記縣志卷之二によると琉田は琉華山の麓に在ることが分るが、此琉華山と云ふのは處州府志卷三に左の如く出て居て、此地方に在りては相當に著名の山の如くであるが、不完全なる地圖上に之を求め難し。琉華山亦名仙山凡登者自朝至暮乃達巓際上有長湖深不可測水委蛇數十里始出大溪下爲琉田有靑器窯久廢然るに同志に大梅嶺を說明して、山勢如蛟龍伸舒狀臺湖立前琉華障後極爲峻拔とあつて、而して臺湖の位置は地圖にも縣の西南慶元縣境に記されてあるし、大梅と云ふ地名も亦た地圖にこそ見當らないが、琉田と共に前記縣の西南方延慶〓に記述せられてあるから琉華山、從つて琉田の所在地も略ぼ此近くにあること丈けは推測出來る。右によりて陳君の所謂大窯なるものは、古來文献に記せられた處の琉田の古窯址と認めても恐らく差支無いものゝ如くであるが、猶ほ多少の疑が無い譯ではないから、愈々事實之れが昔の琉田であるか、否かと云ふことを次回に調査の機會に明白に確かめて貰ひたいと思ふ。(二)次に前記縣志、物產の項に記してある顧仕成のことであるが、陳君の記述によれば顧氏が明の正統頃に燒造したのは慶元縣治域內の竹口であるとのことであることは旣に述べ
た。而して龍泉縣志に琉田となつて居るのは種々理由によりて竹口の誤であると思はれることも前述した。然し乍ら尙ほ一步つき込んで疑問を起して見れば、龍泉縣志に記する處の「正統時顧仕成所製者己不及生二章遠甚云々」とある記述の仕方から考ふるときは、顧氏の製品は當時即ち明の正統頃には、其窯の所在地が琉田であつたにせよ、又は竹口であつたにせよ、兎に角此地方で最も優れたる品であつたことは事實であらう。若し然らずして二流品、三流品と云ふことであらば決して右の如き記述はしないだろうと思はれる。又同じ琉田で燒いたのでなければ章氏の作品と比較することは、妥當を缺いて居る樣である。而して後述すべき菽園雜記の記事を見ると、少し時代は下るが明の中頃最良の靑磁を產したのは矢張り琉田であつたのは事實の樣である。況んや之に加ふるに後述の如く顧仕成は龍泉縣治に接近して居る南隅の人であるから、自分の〓里に近く琉田とか、木岱とか、金村とか云ふ立派な土を產する地があるのに、ワザ、ワザ遠い隣縣まで出かけて窯を起すと云ふのは一寸不自然の樣に考へられる。是等の諸點を綜合すると顧氏が燒いたのは竹口であつて琉田で無いと云ふことは少し疑を抱かぬ譯にゆかない樣であるが、是は將來の學術的調査の結果によりて疑問を解決する外に途はあるまいと思ふ。因に縣志によると、此顧仕成なる者は孝子として有名であつて、卷之十人物、孝友の部に左の通り出て居る。顧仕成父歿事繼母李氏孝謹凡母嗜好率如所欲母疾供侍湯藥衣不解帶及歿哀毀旣葬盧墓三年有白免紫芝之祥有司以孝聞景泰壬申立孝子坊以旌之と云ふのである。尙ほ同志卷之二よると、顧仕成孝子之門南隅人事繼母孝謹母病疽吮血而愈及歿盧墓三年明景泰年旌とあるが、此人物は其生榮した時代が景泰頃であつて略ぼ同時代であるし、姓名も同一であるから、明正統時靑磁を製した顧仕成と同一人と考へて差支無い樣に思ふ。而して此顧氏は單に一陶工であつたろうかと云ふに、前記縣志の記述の仕方から考へると、後に述べる章氏兄弟の場合と同じく、其地の窯業を主宰して居た相當又は相當以上の企業家と見る方が至當であろう。何しろ此時分は龍泉靑磁の名が海外にも鳴り響いて居た頃であるし、其需用最も旺盛であつた頃であるから顧氏の窯業も恐らく相當大規模のもので盛んに大量生產を行ひつゝあつたかと推測せられる。而して現今時々顧又は顧氏等の文字のある靑磁卷之十人物、孝友の部
器を見るのは此當時顧仕成の製せるものか、左もなければ其後顧氏の名聲を利用せんとする者が附したる記號であると見るのが寧ろ至當であろう。(大谷光瑞氏の近著、支那古陶瓷の內に顧と云ふ字のある靑磁の鉢の圖ありて、同氏は之を以て恐らく顧と云ふ人の祭婚の用に供すべく註文製作されたものと想像すると說明を附して居られるが、此說は如何かと思ふ。)尙ほ正統の頃顧仕成の作品は旣に章氏の製品に遜ること遠く、成化、弘治以後益粗惡となつたとあるが、此事實と其各時代に於ける品質低下の程度等は無論、將來窯址及びガラ場等の發掘によりて確實精細に學術的調査を遂げらるべき問題である。之は敢て云ふまでもなく獨り此窯址のみでなく、他の總ての窯址に通して行はるべきものであることは言を俟たない。(三)次に問題となるのは章氏兄弟のことである。此兄弟が主宰した窯が果して陳氏の所謂大窯であつたとすれば將來大窯の學術的調査によりて章氏の作品、其時代、窰式、構造、變遷等々一切の事情が明々白々となる日が來ることは疑なく、單に時日の問題であると信ずるが、然し章氏兄弟の素性等に關しては新しき文献資料の發見せられざる限り、矢張り依然として神祕的の雲に閉さるゝを免れないのである。龍泉縣志には前述の通り、章姓生二名不知何時人甞主琉田窯云々とあるが、明朗英著七修續稿には左の如く記載せられてある。(七修續稿は嘉請四十五年の著述である)。哥窯與龍泉窯皆出處州龍泉縣南宋時有章生一生二弟兄各主一窯(中略)龍泉窯至今溫處人稱爲章窯聞國初先正章溢乃其裔云(卷六)右によると章生一及生二等開窯の時を以て南宋と爲すもので、且彼等は章溢なる者の祖先だと云ふ說を傳へて居るのである(陶說によれば稗史類編にも南宋時有章生一弟二弟兄とあるが此書の方が晩出であると思ふ、其考證は之を略す)。朗英の七修類稿につきては四庫全書總目提要の評は褒貶相半ばし、其理由が例を擧げて說明してあるが、其繁を厭ひて今之を略す。要するに此書は他の諸書に見えない有益なる記事があつて、從來文献の缺漏を補ふに足ると云ふ樣な美點もある代りに、亦た牽强杜撰の議を受くべき缺點も少なからずあると云ふことだ。而して即今當面の問題である章氏開窯の時代、及び其素性に關する
記事が果して文献の缺漏を補ふに足る有益なる記事であるか、又は出鱈目であるかは、今之を判別するに足る何等の資料も無いのであるが、章溢と云ふ人物は元末明初頃龍泉地方に於て著名なる人物であつたらしく、其傳記は諸書にも散見して居るやうだ。今手近にある人名辭書より簡單なる傳を左に錄して置く。章溢、明浙江龍泉人。字三益。天性孝友。元末統〓兵屢平劇盜。授浙東都元師。辭不受。隱匡山。太祖以幣聘之。累拜御史中丞。時廷臣伺帝意多苛。溢獨務大體。後喪母。以毀卒。福王時謚莊敏。龍泉縣志には勿論此人の詳傳が出て居るし、又御史中丞章溢の墓誌銘なるものは國史編修官宋濂(此人は御史中丞、知制詰となつた人で、章溢よりも此人の方が有名の樣だ)が撰して居る。而して更に此地方出身の學者王褘の撰になる章氏祠堂記と云ふのがあつて、其前段に章氏祖先のことが、可なり詳しく出て居るが、窯業に關係したことも、生一生二と云ふ樣な名も、少しも書いては無い。然し祖先が窯業に關係し又は之によりて產を爲したと云ふが如き事歷は、支那に於て、殊に儒〓の見地から恐らく自家の素性を飾る記述とは認められず、反て面白くない事實かと思はれる故、假令斯る事實があつても、祠堂記と云ふ祖先の美點や事歷を潤飾して書く樣な場合には、憚つて之を書かないであらう。果して然らば祠堂記に書いて無いからと云ふて、直ちに其事實が無いと否定も出來ない。今此祠堂記によると、章氏の祖先は五代から宋初にかけて福建省浦城の人で、章太傅諱仔鈞なる者が頗る名望家であり、其三世都中官郞諱重なる者が甞て龍泉地方に獵して、(福建省の浦城から山道を經て龍泉地方に出る道路がある)、西寧〓に至り山水明秀なるを愛して因りて家す焉とある。是れが章氏の祖先であつて、代々同地方の豪族であつた樣である。縣志には又章中丞府の舊蹟と云ふのが記してあり、在縣都鼓樓花園廢址尙存として邑人季汝明過章公廢宅詩を載せてある。此章中丞は勿論章溢のことであつて、元末明初の人であるから此人の代、若は其前に縣都に居住するに至りしものであらう。以上は其大略であるが、要之章氏の祖先は略ぼ北宋の中期頃には、旣に龍泉地方に土著し其地方の豪族として頗る繁榮して居たものと見て差支無い樣である。果して然らば、其數十又は數百の子孫後裔の內に南宋の頃に至りて靑器を燒く者がありたりとしても別に不思議は無いと考へる。而して陶說にせよ、縣志にせよ、皆生一生二なる者が琉田の窯を主宰せる樣に記して居るから、勿論單純なる陶工では無くて、恐らく一種の窯業家であつ
二八て、而して其名と作品とが後世に頗る傳稱せられた所からみれば、必ずや相當の規模の事業で獨り技術的のみならず經濟的にも成功して居たものであろう。只だ生一生二と云ふ名稱の如きは工人の名に相應しきものであるから、斯る豪族の子孫とも思はれないとの說も出やうが、然し之は北宋の中期から南宋までの間には前述の通り相當子孫も繁殖して居るだらうし、是等の內には二三の企業家が出たとて不思議はあるまい。又假令章溢なる者が章氏の本家であるとしても、家道の盛衰と云ふこともあるから、其祖先の內には一時窯業に從事した者があつたとて決して不合理ではあるまい。(四〓章氏開窯の時代につきては、目下の處、文獻としては右七修類及稗史類編の記事以外に何等之を否定又は肯定すべき資料はないやうである。然るにこゝに近頃注意すべき一の事實がある。それは近年本邦相州鎌倉の海岸から相當數量の砧手靑瓷の破片が拾取せらるゝことである。予の見たる此種の破片は立花國手が同地に避暑中、海岸で拾ひ集められたもので、石油箱に一杯位あつた。(挿圖參照)是等の破片は果して昔船舶が此種の瓷器を澤山積んで此地に來り難破して、其結果破片となつて波打際に打ち上げらるゝものであるか。夫れとも又は日常使用して居た瓷器が破損すると之を海岸に捨てたり、或は川の上流へ捨てたりしたものが、豪雨氾濫の際に海岸へ洗ひ流され、それが砂中に埋沒して居るものが波浪の爲に打ち上げられるものであるか、明かには分つて居ないが、恐らく後者の場合が事實らしく思はれる。而して立花國手の集められた破片を檢査するに、勿論是等の多數の破片の內には砧手以外の靑瓷、及白靑磁等のものも、可なり澤山混つて居た。其中には今日まで餘り見たことのない、變つた面白きものも少なからずあつたが、直接本問題に關係なき故、今之を說かぬ。又砧手なるものも、種々の沿革から今日は、可なり廣義の意味に用ひられる場合もあつて、決して一〓には云へぬけれども、鎌倉に於て拾はるゝものは大部分は砧靑瓷特有の粉靑色の美麗なる釉を有するものであつて、其中には凸花雙魚の皿、外側に蓮瓣模樣を浮彫りにせる鉢、浮牡丹手の香爐(?)等の破片も混つて居た。而して注意すべきことは、其數量から判斷して鎌倉時代に於て此種の靑瓷が相當多量に本邦に輸入せられ、從つて此時代に於ては左まで珍稀なものではなく、就中、皿鉢の類の如きは、恐らく當時中流の家では一般に使用せられて居たものと思はれることである。即ち換言すれ
ば此種の砧手靑瓷の時代は是によりて先づ我鎌倉時代と推定しても恐らく大過あるまいと考へる。鎌倉時代と云ふても賴朝が此地に幕府を開いたのは建久三年、南宋の三代光宗の紹熙三年、(西紀一一九二年)に當り、而して南宋が厓山の一戰に滅亡したのは、皇朝の弘安二年、(西紀一二七九年)に當つて居るが、此種靑瓷が鎌倉に輸入せられたのは此間八十七年許りの期間である。而して賴朝が幕府を開いたとて直ちに輸入せらた譯でもあるまいし、而して元將伯顏が臨安を陷れたのは景炎元年で(西紀一二七六年)、咸淳の中頃からは旣に天下騒然たる有樣となり、本邦でも文永四年(西紀一二六七年)には蒙古の書が來り其後屢々蒙古の使者を郤けたる末執權時宗が遂に之を斬つたのが建治元年(西紀一二七五年である。斯くの如き有樣であるから南宋末に於ては到底平和的な貿易など行はれなかつたものであらう。即ち假に鎌倉時代の初期十年間位、南宋滅亡前十年間位、合計二十年位を前記の八十七年から除くと、先づ六十七年間位の間に是等の靑瓷は大部分輸入せられたものであらう。南宋に在りては慶元、嘉泰頃から咸淳の中頃迄(大略西紀一二〇〇年より同一二七〇年頃迄)である。右の理由により此種の靑瓷が產出した時代は略ぼ明かとなつた次第だと思ふ。勿論元代に至りては、元寇の國難以來當分は彼我の交通は杜絕して居たし、第一元代に於ては獨り靑瓷のみならず一般に陶磁は粗惡となつたことは諸家の一致する處であるから、砧手の如き優秀なる品を產出、輸出することは不可能である。さて、そこで次に考ふべきは其產地であるが、所謂靑瓷の產地につきては從來種々の臆說が唱へられ、今尙ほ明確でない、然し右鎌倉に於ける多數破片の採收によりて此手のものが宋の官窰であるとの說は先づ成立が困難となつた樣だ。何となれば云ふ迄もなく、官窯が斯くの如く相當多量に本邦に輸入せられて日用品として使用せられたことは考へられないからである。其他の說の內で從來支那骨董商等の間に漫然唱へられて居た、砧靑瓷を宋龍泉窯と呼ぶ名稱は、現在の處、最も眞實性に富んで居る樣である。從來西洋の瓷學家は何等の考索を費さずして、漫然勿論解釋を以て此說を取り上げて少しも怪まぬ樣であるが之れでは假令其說が精確なる學術的調査の結果に符合したりとて、夫れは偶中であつて、子供のあて事と毫も異つた處はない、眞摯なる研究的の熊度ではあるまいと思ふ。而して十數年來斯種の靑磁の疵物が支那に於て多量發掘せられ、歐米及本邦にも續々輸入せられたのは顯著なる事實であるが、(勿論是等發掘品中には少なからざる手變りと稱せらるゝものが混入して居る。是等は異つた時代、又は異つた窯の產品であらう)、從來其出土地につきては骨董商等の傳ふる所は甚だ曖昧であつて、果して何處であるか頗る明瞭でな
い。今陳君の採取した破片の一片をだに見ずして直ちに砧手が大窯の產であると斷定するが如きことは勿論不可能であるが、然し砧手につきては次の諸點は注意に値すると考へる。(一)其時代が南宋であること。此事は旣に前述した。(二)數量が相當多量に上りし事。此事も前述したが即ち之は民窯の所產であることを物語るものである。(三)其品質の優秀なること。(四)釉色が粉靑色であること。右の內(一)及(二)につきては旣に述べた故に再說せぬ。(三)につきては砧靑瓷が靑瓷として最も優秀なる品質を有して居ることは諸家の一致する處で敢て絮說を要せぬが、宋代最も優秀なる靑瓷を產出した民窯は何であるかと云へば、矢張り第一に龍泉窯に指を屈せねばなるまい。龍泉は元明以降頗る粗製濫造の弊に陷つたが宋代には頗る優等の品を產出したことは後に詳述する南宋初期の書である雞肋編に宋初吳越王錢淑が貢進に用ひた祕色靑瓷は龍泉の所產だと書いてあるのでも分ると思ふ。此記述は少くとも南宋初頃迄は龍泉から頗る優秀なる靑瓷を產出したことの一證と認むるに足るであらう。降つて元末明初以下の文獻、例へば輕畊錄、格古要論、遵生八牋、〓秘藏等々に章窯だ哥窯だと八ケましく記述せられて居るのも、又宋以後殊に元明時代に海外に於て廣く高名を博し、餘り需用の劇しき爲に遂に粗製濫造の甚しきに陷つたと云ふ事實も、畢竟恐らく宋時代の優秀なる作品を追求する人情から起つたことと考へる。次に(四)である粉靑色と云ふことは、恰も南宋の中頃開禧二年(實朝が將軍であつた、建永元年、西紀一二〇六年に當る)の著である雲麓漫抄に龍泉窯は粉靑で越窯は艾色であると記述して居るのにより、當時の龍泉窯は粉靑色であつたことが分るが、是れ恰かも砧手靑瓷の釉色に外ならぬ次第である。以上の諸點を考慮して此種の砧手靑瓷を以て南宋の龍泉窯と推定せんとする者である。而して若し果して章氏が南宋時代、龍泉縣琉田又は所謂大窯に於て優秀なる靑瓷を燒造して居たと云ふ事實があるならば、此種の砧手靑瓷は必ずや章窯の產であらねばならぬと考へる。(五)今や愈更に溯りて南宋より前、即ち北宋末以前の龍泉窯につきて多少の考察を費さねばならぬ順序となつた。前顯菽園雜記には後に其記述を引用するが劉田が此地方に於ける最
初の窯のやうに記してあるが、これは或は事實かも知れない、然し乍ら此書は明の中頃の著述であるから如何に信用出來るとて、宋代の事項につきては其まゝ鵜呑にする譯には參らぬ。又此記を直ちに章氏の開窯と結び付けて、初めて此地に於て燒成を試みた者は章氏であると考へることは素より性急狼狽の議を免れまい。換言すれば南宋の章氏以前に旣に龍泉窯が存在して居たかも知れ無いのである。今南宋より前旣に此地に窯があつたと云ふ卑近な一說を擧ぐれば景德鎭陶錄に揭ぐる左の記述である。宋初處州府龍泉縣琉田所燒云々(卷六)然し陶錄は〓朝中期の書だ、漫然宋初と云ふたとて、固より取り上ぐべき筋合では無いことは云ふまでもない。然るに前にも一寸述べた雞肋編を見ると左の如き記述がある。處州龍泉縣(中略)又出靑瓷器謂之秘色錢氏所貢蓋取於此宣和中禁庭製樣須索益加工巧(卷上)此記述によれば、龍泉窯は即ち秘色窯だと云ふのであるから又々議論の種であるが、此問題の詮議は之を他日に讓り、此著述の時代若くは其以前に於て龍泉窯が存在して居つて優秀なる靑瓷を產したこと丈けは疑ふ餘地は無い樣である。此書は莊綽字季裕の著であつて、紹興三年二月五日の自序がある。然し其內容は紹興四年、七年、八年、九年までの記事があるから四庫提要には疑書成之後又續有所增と云ふて居る。だが要するに南宋初期の書であつて紹興三年は、皇朝の長承二年(西紀一一三三年)に當り、藤原時代の末期ではあるが、養和元年(西紀一一八一年)六十四で死んだ平〓盛がまだ十五六歳の頃である。賴朝が鎌倉に幕府を開いた建久三年より五十九年前である。此書は多少の失考はある樣であるが、著者の父は元祐中黃庭堅、蘇軾、米芾等と交遊があり、季裕自身も猶ほ米芾、晁補之等と相識の間であつたから學問頗る淵源あり亦た多く軼聞舊事を識る云々、其書を觀るに後來周密の齊東野語と相埒す、軽畊錄等諸書の及ぶ所にあらざる也と四庫提要にあるから、先づ相當に信用出來る書であると思ふて差支無い樣である。莊季裕の生歿年は諸書に見えないが、其識つて居つたと云ふ米芾(大觀元年又は二年死す、擬年錄彙編による)及晁補之(大觀四年死す、同書による)は皆北宋末期の人であるし、季裕が北宋末大觀-宣和頃の事項につきて記述する所は相當信用出來ると思ふ、例へば前揭宣和中禁庭制樣須索益加工巧と云ふ一條の如き是である。從つて北宋末に於て旣に龍泉窯が存在して居つたことも、又此時代に最も精工なる品を產したことも、先づ確實
であらう。然し夫れより百年も溯りて眞宗の天禧とか乾興とか云ふ時代に果して龍泉窯が存在したか、どうか、と云ふことになると、此書の記述は其まゝ鵜呑に信ずることは六ケしいし、況してや夫れより更に四五十年も溯りたる北宋の初期になると尙更の事である。然し目下の處龍泉窯に關する之より古い文献は見當らない樣である。只だ此處で前に述べた陶錄の記事、宋初處州府龍泉縣琉田所燒と云ふのを顧みると右の雞助編の記事と略ぼ同じ時代のことを述べて居るので、滿更捨て難い樣な氣もするが、然し是は恐らく偶中であらう。是等の事情を考ふるときは南宋に於ける章氏の開窯と云ふことは、餘ほど其意義を注意して考へねばならぬと思ふ。尙ほ章生一の主宰したと傳へらるゝ哥窯と云ふ頗る厄介な問題があるが、此問題の考究は之を他日に讓り、琉田、大窯以外の窯址につき次に述べ樣と思ふ。餘ほど其意義を注意此問題の考究(六)琉田以外の窯址につきては陳君の報告中にあるものにして吾人が初めて其名に接するを得た處のものが頗る多いが、然し乍ら從來文献に見ゆるもので陳君の未だ言及せざるものも亦た少くない。琉田以外の此地方の窯址につきて近代初めて之を指摘せるは恐らく「ヒルト」氏であらら。氏は今を去ること四十餘年旣に其著書中に菽園雜記を引きて金村の名を擧げて居る。一二Hirth, PL. IN Ancient Porcelain:〓Study三Chinese Mediacval Industry EBS Trade. 1888.p. Case然るに此著書の目的は必ずしも窯址の〓究に在らざりし爲か、氏は他の窯址に言及せず、而して爾來他の諸家も亦た唯だ氏の書を引用して金村の名を擧ぐる程度である。是れ實に菽園雜記に溯りて其記事を再び檢討せざるが爲であつて、大に可笑な事であると思ふ。然し乍ら是等の諸家にして若し一度該書を繙くの勞を執るならば左の記事を發見するであらう。靑瓷初出於劉田去縣六十里次則有金村窯與劉田相去五里餘外則白雁梧桐安仁安福綠達等處皆有之然泥油精細模範端巧倶不若劉田(下略)菽園雜記は陸容の著であつて、今獻彙言、續說郛、守山閣叢書、墨海金壺、紀錄彙編等々多くの叢書に收めてあるから、比較的見易き書であることを附言して置く。四庫提要に然し乍ら從來文献に見ゆるもので陳君の未だ言及せざるものCase紀錄彙編等四庫提要に
よれば此書は於明代朝野故實叙述頗詳多可與史相考證旁及談諧雜事皆竝列簡編葢自唐宋以來說部之體如是也中間頗有考辨(中略)王整甞語其門人日本朝紀事之書當以陸文量爲第一即指此書·雖雖無雙之譽奬借過深要其所以取之者必有在矣とあるから、大抵孟浪杜撰の議ある明代雜著の內にありては出群の書として先づ信用すべきものゝ一と云ふて差支ないであらう。而して著者陸容は成化丙成の進士とあるから其生榮した時代も大凡分明である。從つて前記諸窯に關する記事につきて見るも、是等の窯は此時代に活動して居たと見て差支ない樣である。尙ほ乾隆龍泉縣志卷之三には琉田以外の窯につきて左の如く出て居る。烏瓷窯十七都宏山磚瓦窯十八都塘田等處缸鉢窯治南二里劍池湖是等は其名の示すが如く、或は黑色乃至黑褐色の器を燒き、或は磚瓦を燒き、或は缸鉢等の粗器を燒く土窯の類であつて乾隆頃活動して居たものであらう。現在と雖も、粗器雜器を燒く土窯の類が此地方の諸所に存在することは陳君の報告にもある通りである。然し乾隆志には菽園雜記に記せる諸窯は、琉田の外には記載せられて居らぬ。是は恐らく此頃には旣に廢せられて居つた故であらう。然るに光緒勅修の浙江通志を見ると、卷一百〇七、物產七、の處に瓷器の項に左の記事がある。『龍泉縣志』龍泉昔產窯器靑瓷窯在琉田道泰大其垟安福蛤湖因溪坪官田兪溪大浪坑烏瓷窯在宏山陳灣磚窯在大沙塘田里山南坑直衝大口蘆陂沛田缸窯在劍池湖惟瓷器昔屬劍川自析〓立慶元縣窯地遂屬焉近亦窯戶稀絕矣此記事は乾隆志に見當らないから、恐らく順治志、又は萬曆志から引き來りしものであらう。兎に角、右には菽園雜記及乾隆志等に擧げてない窯名もある。例へば靑瓷窯の內、大其洋、蛤湖、因溪垟、官田、兪溪、大浪坑、等又烏瓷窯の內、陳灣、磚窯の內、大沙、里山、南坑、直衝、大口、蘆陂、沛田、等がそれである。而して是等の諸窯は陳君の報告にも洩れて居る樣であるが、內には同一窯で今日名の變つて居るものもあるかも知れない。今以上諸書に見ゆる窯地を集めて、不完全なる地圖の上に其所在地を求むるならば白雁梧桐、安仁、安福、道泰、蛤湖、等は略ぼ龍泉縣治の東又は東北方雲和縣に通ずる大溪の是は恐らく此頃卷一百〇七、物產七、の處に瓷器の項に左の記事
流れの左右に在ることを發見する。(卷頭龍泉縣圖參照)白雁は白岸、道泰は道太、等となつて居るが是は雁岸、泰太、同音相通ずるを以て同一の地であると考へる。其他の地名の如きも縣志により山川、〓里、等の名稱を考ふるときは大凡其所在地點を考定することが出來るものもある。例へば綠達と云ふのは地圖には見當らないが、縣志によれば、又名建德〓龍泉〓在縣東北都五圖六十九の內二十一都統圖十九、綠達楊梅蛤湖吳岱等處距縣五十里二十二都統圖二十一、安仁大舍湯浩門等處距縣六十里二十三都統圖十、都在安福吳墩處距縣六十里更に潭名の條を見れば、太白雁口潭、綠遶潭、安福潭、安仁口潭、以上係東北下水通雲和とあるし、又灘名の條に、梧桐灘、綠遶灘、安福口灘、安仁口灘とある。是等により綠遶なる地は假令圖上に見當らざるも大凡、縣治の東北方六十里內外の地點で、太白雁、梧桐安福、安仁等の近くに在ることが分る。而して安福、安仁等は大溪の本流より各支流泰太、同音相通ずるを以て同一を少許溯上せる點に在りて、其大溪に流入する合流點を各、安仁口、安福口と呼んで居るのであるから、之から推測して綠遶は太白雁、梧桐等の如く恐らく大溪の本流に臨んで居る地であつて、安福、安仁の如く支流に入り込んだ地ではあるまい。それは右に擧げた潭及灘の名によりても推測出來ると思ふ。即ち安仁口潭、同灘、安福口潭、同灘等何れも大溪本流の潭、灘の名であつて綠遶潭、同灘も同じく大溪の潭灘であらねばならず、從つて綠遠も亦た大溪に臨んで居るべき筈であらう。又例へば大其垟、及因溪垟につきては、蛤湖潭(及灘)道泰口潭(及灘)と並んで大箕洋潭(及灘)、及因溪垟潭(及灘)と云ふのが揭げられてあり、右は皆「以上係東北下水通雲和」とあるから、同じく大溪に莅んで居て、蛤湖及道泰の近傍に在ることが分る。又兪溪灘と云ふのがあつて、「係南上水灘至三都查田通慶元」とあるから、之は大溪の上流に在りて慶元縣への通路に當ることが分る。其他金村(天堂山の麓に在る)、大沙(稽聖潭の下にある)宏山、官田等は百萬分一東亞與地圖にさへ其名を發見するし、又他の窯址所在地名につきては、之を考定し得るものもあるかと思はれる。之は大溪の上官田等は百萬分一東亞與之を考定し得るものもあ
尙ほ縣志によれば、龍泉縣內には右の外に瓷窯嶺(同下潭及灘)縣南十、七里黃窯灘、斗窯灘(以上係東北下接雲和)、瓦窯口灘(係西南上水至十五都雙溪口)等の如き窯址と關係ありと思はるゝ地名を發見する。是等琉田以外の諸窯は、琉田の如く有名でなかつたにせよ、矢張り調査を行ふべきものであることは言を俟たない。而して其內で前記縣治の東北方に在る諸窯址は陳君が龍泉から處州府麗水縣寳定へ赴きたる際、當然通過したと思はれる沿道であるにも拘はらず、同君は之に一顧をも與へざりしは遺憾である。尙ほ麗水縣に入る前に通過すべき雲和縣の彊域內にも恐らく窯址が存在して居るのではあるまいか。是等の事情は將來の調査に俟つ外は無いのである。麗水縣內には寳定以外にも窯址が少なからず、諸所に散在して居るのではないかと思はれる。それは縣治(即ち處州府)より程遠からぬ所には磁窯と云ふ地名があるし(孝行〓在縣西南爲都六の內、四都領莊十二の內、縣治より五里)、又縣志によれば西方松陽縣境に近き方面には後窯山と云ふ山があつて、左の如く三十六の古窯址があると云ふのだ。高岡塞縣西五十里 山知県人民間其右巉巌雄峻爲獅子山洪塘之水出焉西爲後窯山日古三十六窯遺址上有白鶴廟下山半有洞深十餘丈爲悟空寺又西白殿山又西爲鳳凰山爲小鳳凰山又西爲鐵壓塞云々是れ丈けの記事があれば、實地に莅めば大凡其窯址の地點は見當がつくと思ふ。尙ほ景德鎭陶錄を見ると左の如く記してある。麗水窯(處窯同)亦宋所燒即處州麗水縣亦曰處窯質粗厚色如龍泉有濃淡工式尤拙(卷七)之が果して右三十六窯址の窯に該當するか否かは勿論精細なる調査の結果に待たねば分らない。然し陳君の報告中に從前只だ明代の仿龍泉窯にして處州府に移りたりと云はれ、而して其地點を詳にせざるものゝ如きも今則ち留むる所の遺跡、確鑿として考證することが出來るとあるのは果して右の諸窯址の內で何處を指すものであらうか?陳君の云ふ處は陶錄卷七に處窯として左の記事があるのを意味して居るのかと思はれる。浙之處州府自明初移章龍泉窯於此地燒造至今遂呼處器云々此記事の意味を考ふるに、恐らく處州府治又は其近郊を指すのではあるまいか。單に處州と云へば勿論處州府の行政區劃內であつて龍泉縣も慶元縣も其中に包含せらるゝことに
なるから、前記の記事は意味を爲さぬことになる。從つて陶錄に處州府と云ふは府治即ち府城のことでなければならぬ。然し府治即ち府城の中に窯があることは考へられぬから恐らく其郊外であらう。例へば處州府治から僅か五里の地にある前記の瓷窯と云ふ地の如きは其窯址ではあるまいか?。此他麗水縣內には土地窯、缸窯、瓦窯、下缸、窯販、陶坑等の地名がある、是等は何れも窯業と關係があるかと思ふ。去つて松陽縣に至れば碗〓、瓦窯田、缸窯なる地名があるし、遂昌縣に至れば缸窯販、瓦窯岡がある。若し夫れ金華縣に至りては、陶錄によれば唐代の姿州窯の故地であるとのことだから、勿論十分精細に調査する必要があらう。瓦窯、下缸、窯販、陶坑等の地名がある、是等は何れ附記小山富士夫氏の談によれば、鎌倉二階堂に住せらるる第一高等學校〓授菅虎雄氏は三十年來、鎌倉に於て古陶磁の破片を採取せられ、之を其住宅の一室の壁に一面に塗り込めてあるそうで、其數、目算七八千に及ぶと云ふ。而して是等の破片の大部分は砧手靑磁であつて、近年立花氏の採取せられたものよりも皆大形の破片であると云ふ。尙ほ是等は只に海岸のみならず、陸上內部にても拾はれたものだとのことである。吳州赤繪吳州赤繪と稱する一種の支那製の燒物につきて余は今まであまり注意して居らず從つて特に〓究したこともないから其產地及時代等につきては殆んど何等知つて居ない。只だ自分の記憶して居る處が正しいならば、從來此種のものの時代につきては漠然として明末から〓朝にかけて出來たものと云はれて居り、其產地につきても亦た漠然として南方支那と云ふ樣に云はれて居た樣である。而して此種のものの產地を福建省漳州府龍溪縣石碼窯に擬定した最初の人(少くも最初の邦人)は恐らく上田ドクトルであつたと思ふ。之に對して一方には從前から廣東說もあつた樣であるが自分には果して孰れが正しいか判斷が出來ない。然し後述する如く石碼產の磁器を廣東に送りて廣東で上繪付を爲したと云ふ事實も
果して然らば其產地の如きも一方にきめて仕舞ふことも出來あつたのではないかと思ふ。果して然らば其產地の如きも一方にきめて仕舞ふことも出來ないのではなかろうか。「ブッシェル」氏の記述によれば石碼窯の作品は多くは日用の雜器であつて厦門を經て遠く印度、南洋諸島、「シヤム」等々南方海外へ輸出せらると云ふ。又同氏は景德鎭の白磁が陸路廣東へ輸送せられ、同地で上繪付をして海外に輸出せられると記して居る。是れ「エス、ウエルズ、ウヰリアムス」氏の所說に基くものらしい。〓Oriental Ceramic Art, Sec- tion 100 Chapters XX DES XX.景德鎭から陸路嵩高で、こわれ易い磁器を遠く廣東へ運ぶことは事實容易なことでは無いから一寸考へると右の所說は頗る疑はれるのであるが、然し地圖を見ると江西省の奧と廣東省の奧とは有名なる大庾嶺を境として相接して居るのであるから、都陽湖から舟で整江を溯りて贛州又は信豊迄持て行き、此所から馬又は人の力で一つ山を越ゆれば所謂嶺表即ち廣東省で、其所には演水と云ふ川が流れて居るから韶州又は其上流で更に舟に積めば一氣に廣東へ達することが出來る譯だ。大庾嶺は昔から有名な山脈で相當高峻であろうけれども是れさえ越ゆれば水路が兩方にあるのだから案外樂かも知れない。一體支那の河川は吾人の想像以上に舟楫の便を通ずる處が多いのではないかと思ふ。彼の有名な三峽の嶮は其一例だが、浙江省の奧の彼の龍泉窯を宋元以降海外に輸出するに當り如何なる經路を取りて搬出せるかにつき嘗て「ヒルト」氏が〓究したことがある其際龍泉地方の山奥の河川は急流で巉岩、瀑湍相次ぐと云ふ有樣だから到底舟によりて處州邊へ搬び下すことは不可能であると斷定し山路福建地方へ送り出したものであろうと推定したかに記してあつた樣だ。然るに龍泉縣志を見ると此「ヒルト」氏の考は少しく早計に失した樣に思はれる。夫れは此地方は古來水怪多しなどと云はれて頗る恐れられ舟の難破するもの少なからざりしことが書いてある、是れ即ちタトへ險阻であつても舟楫の通じて居た一の證據だ、加之縣志には唐時代の縣令某の治水の〓末を記した碑文が載つて居て、此時に岩を破碎したのが何十個所急湍を治したのが數十個所と云ふ風に一々書いてあり之が爲めに舟の難破するものが著しく減じ住民一同大に喜んだと云ふ樣なことが書いてある。されば宋元以降龍泉窯の搬出には無論此水路によつたことは言を俟たぬと思ふ。是は其一例であるが、景德鎭窯が陸路廣東に送られたと云ふことも必しも排斥すべきではあるまい。次に「エス、ウエルズ、ウヰリアムス」、LLD.氏の記する處によれば石碼窯と云ふのウヰリアムス」、LLD.氏の記する處によれば石碼窯と云ふの
は石碼の近くにあるPa-Kwohと云ふ村に在るのであつて其產品中普通品は內地用となり、又は印度、シヤム、南洋等に仕向けられるが、他の一部に染付のもの及び、白地のものあり、兩種共に廣東に送られ廣東で夫れ〓〓好みに應じて上繪付を爲し輸出せせらるると云ふ。次に上繪付の方法、模樣の種類等々につき記述して居る、其價は晩餐用食器十二人前一揃(合計八十九點)で六十二弗乃至九十二弗位、朝食用セツト七十點で一一十弗乃至三十五弗、三十人前の大揃二百七十六點で染付百七十五弗、上繪付三百三十弗、茶器大揃百十二點で染付百四十三弗、上繪付のあるもの百十六弗位の相場であつたと云ふ(以上は廣東に於ける相場だ)當時尙は喜望案を越へて輸出せらるゝもの每年六千世位ありしと云此記述は西曆一千八百五十六年即ち威豊六年の著であるから長髮賊の盛んなりし頃であつて本邦では安政三年だ。乾隆、雍正、康凞と云ふ風に溯つて古いことはよく分らないが十八世紀頃景德鎭から白地の磁器を廣東に送り、廣東で上繪付をして歐洲へ盛んに輸出したことは諸家の說く所であるし、(例、前記「ブツシエル」氏の外、Burton Porcelain, 151 Art CIS) Manufactureマ129又P〓re 2 Entrecollesの第一信(一七一二年即ち康凞五十年)にも厦門に於ける輸出の盛大なるを見て嘗て景德鎭の陶工等が原料を携へて福建地方に移住せるPa-Kwohものあることを記せるより察するに恐らく旣に明末〓初頃から前記の如き生產-輸出の徑路が行はれて居たものであろう。一體支那磁器の海外輸出は遠く唐宋に其端〓を發して居るのであるが其最も盛んとなりしは喜望峯航路の發見後、葡萄牙、西班牙、和蘭、英國が相次ぎて支那及東洋貿易に熱中した頃であつて、喜望峯航路發見當初は支那磁器の歐洲輸入により巨利を博したるが、追追歐洲各國に於て之が模倣を〓究し.其成功につれて支那磁器も追々賣れざるに至りたりと云ふことであるから、石碼窯の產出並に廣東の上繪付の盛衰も先づ之れと其步調を共にしたものと見られるかと思ふ。葡萄牙の船が喜望峯を廻つて初めて廣東に達せしは西紀一五一七年(明の正德十二年)だと云はれて居る、其後九十年許りを經て一六〇二年和蘭東印度會社設立せられ、之と前後して英國の東印度會社も設立せられた、是等は前記の如く巨利を博する爲競ひて支那磁器を歐洲に輸入したものである。其數は蓋し夥しきものありしならん。明末までは歐洲の需用は唯支那磁器其まゝを得るに滿足したるも〓朝となりてより歐洲より種々の好みを注文するに至れりと云ふ。其數量も追々增加して西紀一七〇〇年十月四
日佛國印度會社が「ナント」に於て賣りたる磁器百六十七箱に達せり。又一七五九年中和蘭船により輸入せられたる磁器品目及個數表中には白地に金模樣の珈琲盌二千七百對を初めとしコーヒー道具、茶道具等々各々數千乃至數萬點を算し、同一七六〇年和蘭船三艘の輸入品目中には十四萬九千餘點の珈琲盛、三十萬七千餘點の茶盌を初め、夥しき數量を揭ぐ(詳細はJacquemart et Le Blant: Histoire de ET Porcelaine, Paris, 1862, pp·29-34參照) Telf d Entrecollesの記する所によれば當時の歐洲向輸出磁器は大低靑花なりと云ふ。是れ康凞五十年前後の景德鎭のことなり。是等は恐らく一旦廣東に送り同地にて外人好みの上繪付を爲して輸出せるものか?。又外國船が廣東に滯泊中船長の好みにより其船の繪など皿鉢に畫かしめたるものあること、景德鎭より廣東へ輸送せる白地の磁器の內には其まゝ歐洲へ送られ歐洲にて上繪付せるもの少なからず之が爲め西洋の支那陶瓷蒐集家が屢欺かれて憤慨の種となること、(其數量の少なからざりしことはBurton A General History ofPorce- lain, Vol. 1 T.參照)、歐洲製の支那磁器模造口四が更に支那にて模造せられたること等々西洋瓷學家の齊しく記述する所だ。本邦に於ける吳州赤繪と稱するものの内には西洋船などの描いてあるものも往々見受けるが多くは皆支那固有の模樣が畫かれてある樣だ。勿論是は西洋向の輸出品でなくて、支那內地用乃至日本向南洋向等であるが爲であらう。然し其產地は矢張り西洋向輸出品と同じと見るが至當であらう。然し前記「ウェルズ、ウヰリアムス」氏も記する如く勿論福建省石碼窯のものが悉く白地又は染付のまゝ廣東へ送られ同地で上繪付をした譯ではあるまいから、石碼に於て上繪付せるものも多々之あることであらう。此點は誤解のない樣に附記して置く。廣東の窯業地は一九〇四年出版「ドクトル、ケル」著廣東案內によれば佛山鎭石灣窯にして同名の村の南西七哩にありて、日用雜器乃至裝飾品等各種の製造、燒成及掛釉を行ふと。說瓷には廣窯在石灣(中略)自明時已遷於此宋陽江舊窯今日早已消滅矣〓初頗有良工數人云々とあり、陶錄には始於廣東肇慶府陽江縣所造蓋做洋磁燒者(中略)甚絢彩華麗惟精細雅潤不及瓷器云々とあり。匋雅には廣窯有似景德鎭者(中略)皆白地彩績精細無倫云云とある。是等を綜合すれば略廣窯なるものを察知することが出來る。勿論他所の產品に上繪付を爲すのみならず、亦た自ら白地染付等の燒物を造り、之に上繪付を爲したるものだろう。
さて以上の內果して何れが吳州赤繪に該當するのであるか?石碼、石灣兩窯共に今日でも燒いて居る樣だから現在の此兩窯〓に其製品につきて調査するのも一方法かと思ふ。磁州窯漫筆燕趙悲歌士。相逢劇孟家。寸心言不盡。前路日將斜。磁州は直隷省の西南邊、河南省に境を接するところに在り、春秋戰國時代の趙國の地である。趙の故〓邯鄲東北方約七八邦里に在り、此地方は戰國時代に說客策士の往來頻繁であつたのみならず、秦將白起が大いに趙軍を破り降兵四十萬を悉く坑にし進んで邯鄲を圍み、歲餘、幾んど脫するを得ず。幸にして楚魏諸侯の來援によりて圍を解くことを得たなど云ふこともあつた。然し趙國は名將廉頗、趙奢、名臣藺相如、虞卿、平原君の食客毛遂等が心身を竭せる必死の努力も其甲斐なく終に强秦の爲に併呑せられた。國破山河在、城春草木深。詩人にあらずと雖も誰か感慨なきを得んやである。藺相如の墓は州の西四十里
然し史記には廉頗は壽春に卒した羌村に在り、又廉頗の墓は州の北五十里趙拔庄に在る。然し史記には廉頗は壽春に卒したとあるから未だ此墓の是否を知らずと云ふことだ。因に盧生邯鄲の夢と云ふのは唐の開元年間の邯鄲に於て起つたと云ふ浦島太郞「リツプヴアン、ウヰンクル」と同じ樣な話である。磁州の燒物は州城を去ること西方約五十支里の山間彭城鎭に產出するものであつて、甕缶盆碗罎瓶諸種の雜器を燒く。黃綠翠白黑各色あり。然れども質厚くして粗なり、只だ肆店莊農の用に供すべし。惟に饒の景德、常の宜興に比せざるのみならず、即ち聞の建窯、浙の龍泉、粤東の土瓷も猶ほ此に勝ること萬々なりなどと大に謙遜して居る。尤もこれは宋元の古窯とは事違ひ明、〓時代になつては其產品も劣等となりしことは勿論であらう。然し今日宋代の磁州窯と稱し頗る高價に賣買せられて居るものの內に果して是等の比較的新しき品が混入して居ないであらうか。格古要論などを見ると素者價高於定などと頗る賞美して居るけれど、これなどは果して北宋代の定窯との比較であるか甚だ疑はしいと思ふ。北宋代の定窯が淨瑩愛すべきものであつて南宋の初頃旣に稀少となつたことは周輝の記する所であるから其後定窯と稱せられ來つた宿泗邊の場違ひものと比較したのでは公平ではあるまい(格古要論は明初の書だ)。磁州の西方一帶の山地は石炭の產地であつて、土民は到る處に穴を掘つて採炭して居るとのことである。故に其窯業に使用せられて居ることは勿論だ。然し之は近代のことであつて昔、たとへば宋代と云ふ樣な八百年も前から果して專ら石炭を以て燒いて居たかと云ふに、これは精しく〓究の上ならでは斷言出來ないところの一つの課題であらうと思ふ。石炭は可なり古くから支那人に知られて居て其文獻も稀では無いらしい。殊に例へば宋代に於ても宋史陳堯佐傳に「徒河東路、以地寒民貧、仰石炭以生、奏除其稅」などとある。然し此種の文獻は勿論直ちに取つて或る特定の地に於ける窯業に石炭使用の證左とはならぬ。それはもつと積極的の證據が無ければならぬと思ふ。前述の通り現代に於ては磁州窯は專ぱら廉價なる石炭を用ひて燒造せることは勿論であるが、恐らく明代に於ても彼の天工開物に說かれてある如く煤窯と稱する石炭窯で燒造して居たものであらう。(天工開物は明季の書だ)然し宋代となると左樣に簡單に勿論解釋で片付けて仕舞ふ譯には行かぬ。若し此地方に於て宋代に於ても石炭が多量に採取せられて居たとの證據があり、其上尙ほ此地方に當時旣に伐採すべき樹木が缺乏して居たとふこ
となれば殆んど動かすべからざる決定的の證據とも云へよう。然し之は誰も未だ證明した人は無いやうだ。桑田變じて海となることもあるのだから今日の禿山は數百年の昔は鬱蒼たる森林で掩はれて居たことも無論あり得るのであつて、彼の山東省の有名なる泰山の如きも數百年前には山及其周圍は鬱蒼たる深林と竹籔に掩はれて居たらしく其頃には此地方は虎の生息地として有名であつた然るに此地方は殆んど禿山ばかりで虎など藥にしたくも見る事が出來ないと云ふ話だ。又羅振玉氏だつたかの發見によれば河南省殷墟出土の甲骨文に狩して象を獲たとの記事があつて三代の頃には黄河流域に象が棲息して居たらしいと云ふ。下つて唐から宋初頃には尙ほ今日の浙江省の奧や福建.廣東地方には象が居たらしく吳越王錢淑が馴象を太宗に献じた記事がありて初は之は南方交趾とか暹羅あたりから得來りしものかと思ふたが其後宋人の隨筆を讀んで居ると福建省漳州地方で野象の害に苦んで之を防止する方法など說いて居るから宋初頃には尙ほ此方面には象が棲息して居たのでは無いかと思ふ。(此事につきては其後藤田劍峰博士の遺著東西交渉史の〓究、南海篇を讀むと象と題する一文ありて同博士は他の種々の文献を引いて略同樣な意見を述べられて居ることを發見した。)話が甚だ多岐に亘つたが要するに今日を以て七八百年の昔を推定することは危險であると思ふ。何故に斯ることを冗漫を厭はず述ぶるかと云ふに筆者は窯業技術のことは丸で素人であるが宋代の磁州窯と思はるるものを見ると其釉の色とか調子とか云ふものは後世明〓頃のものとは可なり趣を異にせるものの樣に見受けられる。即ち宋代と思はるるものは釉の色調がどことなく溫潤の樣だ(尤も土中等の爲に變化せるものは別だ。)是は勿論原料の變遷とか技術の退歩とか云ふこともあるかも知れないが他方に於て燃料の變遷と云ふことも當然一應の考究を要すべきではないかと思ふからである。序であるから窯のことも一言する。一時北方の窯の構造はこうだから酸化焰だとか南方の窯の構造はああだから還元熖だとか云ふ說を唱へた人があつて大に世の中を惑はした。我等技術には皆目經驗の無い者は頭から之を信じて居つた然し例へば均窯の釉とか、所謂北方靑瓷であるとか云ふものにつきて胸中の一塊の疑問は之を奈何ともすること能はず大に悶々に堪えなかつた。然るに近年に至り大谷光瑞師の熱心なる〓究と故太田覺眠師?の献身的踏査との賜により河南省の汝州窯の附近から北方靑磁及均窯の燒損じが續々と發見せられ之が爲北方の窯に還元熖なしなど云ふ說は根底から覆された。吾人は之によりて恰かも窓を開いて山を見る思を爲した。蓋しかゝる思を爲せる者は獨り筆者のみであるま
い。均窯につきては今此に說くべき場合にあらざる故之を略すが、右は要するに現在を以て直ちに數百年の昔を推定する危險を如實に示した著しき一例だから此に記して置く。磁州窯の釉藥と化粧掛とは美しき牛乳狀を呈して極めて新鮮で、定窯の釉が「クリーム」狀を爲せると對照して、之が磁州窯に現代人の愛着を禁じがたき主要なる理由の一であると思はれるが、此釉殊に鮮新な白い化粧掛は何處から得來るものであらうか?磁州城の西南六十支里許りの處に白土山と云ふのがあつて白土を產するが胡粉の如くであつて繪の具に用ゆべしとある。之は恐らく白堊、白善土、白土粉、〓粉などの別名を有するものであらう。名醫別錄に邯戰の山谷に生ず、采るに時なしとあり、梁の陶弘景の注に即今〓家用ゆる者甚だ多しとある。磁州窯は手近にかゝる良質の白土があるのであるから其の化粧掛は此白土を用ゆるのではあるまいか。因に白土は珪酸礬土だと云ふことだ。遠く宋元時代のことは分らないが明代に於ては彭城鎭に官窯四十餘座を設けて罈を燒成した。此所で燒成した〓は之を一旦官〓廠に集積して舟運によりて京師に送り光祿寺に納入した。其數量は明の宏治十一年には瓶〓一萬一千九百三十六箇を貢したと云ふ。官罈廠と云ふのは初は州城の南關石橋の東に在つたが後に北方の琉璃村に移り、間もな間もなくまた南關に復し、間もなく又移り、次で再び南關に復すと云ふ樣に兩所の間を反覆移動した樣だ。此官〓廠と云ふのは單に燒成を監督する役所であつて窯の所在地で無いことは前記の通りだ。罈の音t'anで土製の德利だと云ふことだ。勿論此所では燒物であつて土製ではない。罈と云へば恐らく酒罐のことであつて、酒罐と云へば吾人は直ちに紹興の酒罐を想起するが然し明代と現代とは時代も違ふし、而かも南と北とでは氣候風土人情風俗頗る異る。江南の橘、之を江北に植ゑれば枳となると云ふ位であるから今日紹興の酒罐の形を以て直ちに明代磁州の罈と同形だとは云ふ譯にはゆかぬ。磁州窯手の燒物を產出せるは獨り磁州のみならず直隸、河南、山東、山西の諸省內到る處で燒成したものであらう其最も著名なるものは山東の博山、山西の霍州、河南の許州等であると云ふ。嘗て山東省灘縣に於て北宋代の墳墓より出土せる一連の磁器の如きは所謂磁州窯手のものなるも仔細に點檢するに其胎土、作風等に於て稍磁州窯と相違せるを以て恐らく此附近博山邊にて燒成せるものならんと「ラウフア」氏によりて唱へられ爾來之に賛する者多し。此例によりて見るも。また支那各地に於て昔から到る處に土窯雜窯等の窯
が分布散在して居つて日用の雜器を製造せる事實から見ても(之は日本でも昔から同じ樣であつたらしい)現在吾人の見る磁州窯手の燒物を一々前記此方面の諸省の各窯にあてはめて判定することは現代に於ては六かしいと思ふ。今姑らく學者の云ふ所を略述すれば宋代の磁州窯は其胎土淡黃灰色を帶び、其釉は著しく和かき亮釉であつて、下にかけたる白色の化粧掛と相合して溫潤驚くべき美觀を呈して居る。時としては化粧掛を爲さゞるもの、化粧掛の上に描〓して釉を施さゞるもの、釉の上に描〓せるもの等がある。宋代の磁州窯の特徴は右の外尙ほ其作風の丁重なること及び就中描畫の色調並に風格に在りと云ふ。即ち描〓の色調につきて云へば宋代のものは純然たる暗褐色にあらざれば暗紅褐色であつて後代のものは之に反して「スレート」樣の灰色か帶紫褐色なるを常とす。更に瓶罐等の場合に於ては宋代のものは內部に暗褐色の釉を施すを常とするも後代のものは內部は掛釉せず淡灰色の胎を露はすとも云ふ。描〓の風格に就きては宋代のものは筆勢輕快にして力强く大低印象風の圖案を描く。後代のものにも勿論宋代と同じ圖案を反覆せるもの多しと雖も描法粗拙にして宋磁描〓の素朴性と新鮮味とを缺いで居る。尙ほ明代のものには右宋磁の圖案模倣の外に煩細なる圖案を施せるものが多い。是れ他の諸窯と等しく明代圖案の一特徴と云ふべきだ。綠宋瓷と云ふものがある。即ち無色の亮釉の代りに綠色乃至靑翠色の亮釉をかけたものだ。之も磁州の所產として頗る珍重される。洋人は之を以て「ペルシヤ」地方の技法が支那に傳來せるものと爲す。其證據として擧げられるは「ザーレ」及「ヘルツフエルト」兩氏が古代「ペルシヤ」の廢墟就中「メソポタミア」の「ラツカ」に於て同じ技法を施せる「ペルシヤ」陶器の破片を多數發掘せるによる。綠釉靑釉のものは明代に於ても引續き燒成せられ、今日見るものの多くは明代以降のものだと云ふ。此他尙ほ刻花、加彩、Sgraffito technic其他磁州窯手のものにつき行はれて居る技法は仲々種類が多いが筆者は詳しく知らないし、大抵東西諸家の詳說する所だから總て省略する。
六一亡羊寐語「陶磁」第四卷第五號及び第五卷第二卷所載の鹽田氏の「疑問のかずかず」を讀む。小生の如く廿五六年前初めて陶說、陶錄の書に接して以來散々是等の難問題に惱まされ來つた者には一讀感慨無量である。鹽田氏の提示せられたる諸問題の內越州窯以下の諸窯に關するものの如きは何れも大問題であつて東西瓷學家の頗る苦心して居るところであるから之が正確なる解決は固より一朝一夕のことではあるまい。依て夫れ等には今觸れざることとし同氏の提示せられたる疑問の內で比較的鎖細なる二三につき本誌の餘白をかりて潜越ながら管見を述べさして貰ふ。(一)椶眼機は又棕ともかく。櫻は椶欄即ち「シユロ」だ。然し竹泉譯陶說の如き或は「シユロメ」と文字通りに解し(卷三永樂窯の項)或は「シユロスヂ」と譯し、(卷二汝窯の項)甚だしきは機根「シユロノネ」などと寐語す(卷三隆慶萬曆窯の項)洋人も之には大に手を燒きと譯し或はPalm leafなどたりと見え「ブツシエル」氏の如き或はPalm leaf veining spotsと譯す。(因に「ブ」氏の陶說英譯は竹泉和譯陶說と共に同じ誤譯を爲せるは偶合か、或は又何か相倚るところある故か頗る怪むべし。)其他文字通りにPalm eyes. Palmaugenzeichnungenなどと云ふ者もあり(Hobson: Chinese Pottery and Porcelain. Vol. I.P. 53; 7. Embden: Ch. Fr〓h- keramik. ?〓〓〓)。借問す棕梠に眼ありや。また無しや?蓋し彼等は恐らく自ら其意味を了解せざるならん。〓des petits boutons de ET fleur de L-「ジユリアン」は棕梠の花蕾と譯して居るapparence Fabrication de el Porcelaine Chinoise 7.0 195)然し棕梠arbre tsong,棕cm Stanislas Julien: Histoire Gの花蕾の意味が如何にして棕眼から出てくるか何等說明もして無いから全然分らぬ。要す六三Embden: Ch. Fr〓h- keramik.〓des petits boutons de ET fleur de L- apparence de el Porcelaine Chinoise 195)
るに之も棕梠の眼と五十步百步の解釋の樣だ。又之を梭(オサ)の眼だの梨子地紋など云ふは恐らく何等の根據が無いと思ふ。然し乍ら今如上の諸說を觀ると明かに二個の別異の群又は傾向に分類することが出來る。即ち一は之を以て丸きもの。或は點の樣なものと解せんとする者で、「シユロノメ」「花蕾」「梭の目」「梨子地紋」などは此群に屬する。而して他の一類は之を長き線條樣のものと解せんとする者で「シユロスヂ」やpalm leaf veining等は此群に屬する。斯く正反對の二說が成立するは畢竟遵生八機等に「汁中櫻眼隱若蟹爪」とあるより生ずるのだと思ふ。椶眼が丸ければ蟹爪も丸い筈だし、蟹爪紋が長ければ機眼も長い筈だ。然るに、支那人の解釋を見ると之を小さな穴の意味に解して毫も疑を挿んで居らぬ。其例を匋雅及說瓷の二書より左に錄出する。釉汁中凹而縮者日機眼亦曰鬘眼淺大而滋潤者曰橘眼云々(每雅上六六-六七葉、說資上一六同)釉汁中含有水星如小珠歷々可數曰水眼若起泡沫與膜質則不得冒此名矣機眼較巨縮而凹亦謂之變眼(毎雅上七一-七二葉)之で見ると水眼は兎に角として櫻眼は一種の孔穴であること疑ひない、而して又之を變其而して又之を變眼とも云ふとある。此變眼の二字こそ管見によれば此不可解の術語を解釋する鍵であると思ふ。髮は辭源によると租翁切音變東韻。髮亂也。獸之頸上毛也。とある。即ち獸類の頭の後部から背部に至るまでの間、即ち頸の上部に生へて居る毛を云ふのであつて、丁度馬の立て髮に相當するものである。馬の立て髮は駿又は鬃であつて其音韻は等しく租翁切音變東韻又は徂農切音悰とある。而して眼の字には穴の意義がある辭源に「孔穴曰眼、如泉眼、井眼」とあるのがそれだ。さて獸類の立て髪の穴とは何であるか?之は毛を拔去つたアトの穴である而して獸類と云ふても之は豚を指せるに外ならぬ譯だ。即ち支那人の重要家畜の一である豚を屠殺して料理するに方りて先づ其毛を處理せねばならぬ。而して其髮即ち比較的最も硬剛なる頸上部の毛を拔去りたるアトにポツ〓〓と穴があくのを取つて釉に生ずる穴を形容せるものに外ならぬ。斯くの如き解釋は一見甚だ奇々怪々で、棕梠の眼から豚の毛穴が出てくるなどは瓢簞から駒が出で山の芋が鰻に化する以上の珍說で荒唐無稽だと哄笑される向もあるかも知れな此變眼の二字こそ管見によれば此不可解の術語を解釋する鍵であると
いが、然し夫れには相當の理屈があるのであるから一應聞いて貰ひ度い。髮眼と云ふのは實は獨り瓷學上の術語であるばかりでなく、又鑑硯上の術語でもある。吳蘭修の瑞溪硯史卷二に左の如く出て居る。豬鬃眼豬鬃眼凡石見之皆非上品、然甚落墨久而不滑(硯坑志)蘭修按豬鬃眼如拔去豬鬃毛孔石理不凝結故有此病〓は前述せる如く駿即ち馬の立て髪のことであるが此處には變と同義に轉借せるものと見て差支無いであらう。豬は猪であつて、支那では我邦の「ゐのしし」は野猪と云ひ、豚のことを猪と云ふ。即ち豬鬃眼は豚の頸部の上側に生へて居る硬剛なる毛を拔去せるアトの穴を指すもので硯石に之に彷彿せる小孔のあるのを形容せるものであることは吳蘭修の說明せる如くである。瓷學に於ける髪眼即ち櫻眼も亦た此鑑硯上の術語と同義と見て差支無いであらう。而して機は勿論變の假借又は轉訛であらう。硯坑志と云ふは周氏硯坑志と云ふて容易に見ること能はざる珍書で、本邦にも二三將來され之を收藏せる人ある由であるが小生は不幸にして未だ見ることを得ない。然し乍ら右吳蘭修の端溪硯史に援用する處によりて今の場合事足りるであらうと思ふ。端溪硯史は書肆に行けば何時でも求められ得る極めて普通の書である。豚の毛穴を以て形容するなど我等日本人には頗る突飛の樣だけれども支那人の日常生活から見れば是などは尤も俗分りする形容で右に述べ來つた樣な廻りくどい說明などは恐らく反て噴飯の種であらう。從つて此變眼と云ふ語の如きも硯が先か燒物が先かなど云ふ事なく他の種々の場合にも用ひられて居たと思ふ。一體支那人は美術品の鑑賞に方り六ケしく云へば種々の術語、通俗に云へば、あらゆる物象を持來りて之を形容するから、長たらしき說明を要せずして端的に其色なり、形なり乃至其有樣を了解せしむることが出來る。例へば蜜淋釉、鼻涕釉、淚痕、蚯蚓走泥紋、霞片、星點、野雞翅、木紋、葢雪、鐵繡花、蝗股紋、蚱蜢腿、蜻蜓翅等々甚しきは〓疽、麻癩等云ふもあり。又色の如き豇豆紅だ、胭脂水だ、蘋果綠だ、茄皮紫だ、何だ、かだと所謂千〓萬端である。之は至極簡明適切である代りに動もすれば樂屋落ちとなりて他人には全然分らぬことになる。機眼の如きも稍此類と云へよう斯る場合には別種の古美術品の鑑識に用ひられたる術語を一應調ぶるのが可と思ふ。同じ術語を用ひある場合も往々之あり
て照合して發明することもある。例へば猪肝色、羊肝色の如き、後述する芝麻の如き〓法に芝麻麬がある、是等は各明瞭にして彼此照合の必要なきも獨り瓷學上のみならず或は鑑硯上、或は〓法等にも用ひらるる術語である。それから往々にして文字の遍を變へてあることがある本問題のは木遍が實は影である例だが、釣窯が均窯になつたり鏽花が繡花になつたりするのは其例である。是は恐らく音韻相通ずる所あるから初め書き誤りたるものであらう。これにつけて思ひ出さるるは今を去ること約十年前ある人が硯に關する一書を著はした中に雨淋墻靑花と云ふことが書いてあつた。當時誰も其出處につきて知れる者が無かつた。小生の師事して居つた斯道の老大家故某氏の如きは斯樣の名稱の靑花は未だ何の書にも出て居ない、之は著者某が此硯·を支那で買つた時支那人の受取に書いてあつたとか云ふので、自著に記述せるもので、恐らく文字も碌々知らぬ支那骨董屋の付けた名であらうと笑はれた。然るに其後間もなく小生は取調べることがあつて偶然明の汪阿玉の著である汪氏珊瑚網畫法を繙いて居ると麬石法の內に「長斧劈皴許道寧顏輝是也名日雨淋墻頭」とあるのを發見した。依つて小生は直ちに之を老師に報告したところ老師も大に意外とせられた樣であつた。由是觀之雨淋墻靑花と云ふものは恐らく文字も碌々知らぬ支那骨董商の命名ではなくして、支那に於ける相當〓養ある文雅の士で愛硯家の命名であらうと思ふ。此時老師齡旣に七十內外で、硯の〓究に從事せらるること五十年に近いと云ふことであつた。然るに尙ほ且此事ありしは〓究の大切で油斷の出來ないこと、殊に自分の專門に立て籠らずに廣く諸子百家の書に渉る必要あることを示す一例であると思ふ。依て事瓷學と何等關係なきも他山の石として此に掲げて置く。機眼と不可分の關係にあるが如く見ゆるものを蟹爪紋と爲す。是は遵生八牋に初めて「汁中機眼隱若蟹爪」と述べられ次で〓秘藏、博物要覽等に剽刻轉載せられた爲に東西瓷學家頭痛の種となり來つた。然し初めて蟹爪紋を記述せるは恐らく格古要論であつて其當時は櫻眼とは何等關係なかりしものの樣だ。少くとも同書には椶眼のことは書いて無いやうだ。(因に格古要論は洪武廿年の著、遵生八牋は萬曆十九年の著、〓秘藏は恐らく萬曆の中半より溯るまいと思はれる。博物要覽に至りては明季天啓の書だ。)近代に至りて蟹爪紋は一般に開片の一種と考へられ支那及西洋瓷學家等は毫も疑を挿まぬ樣だ。只だ本邦では前記違生八牋以下の記述の爲に之を蟹の脚にあるボツボツと解する
說も有之。我々後學の惱みの種となつて居る。之につきては若干の私案もあるけれど未だ寐語するまでにも纒らないから暫らく宿題として置く。然し三人成虎とか一人傳虛萬人傳實とか云ふことがあるから餘り遵生八牋の記述を過信してはいけないと思ふ要するに此書の記事が源であつて他書は明人の陋習に沿ふて之を剽刻したに過ぎない。遵生も亦た或は他書から剽刻し來りしやも知れないのだ。(二)芝麻花芝麻は即ち胡麻(ゴマ)本草に一名脂麻、俗作芝麻云々とある。花はハナでは無くして云ふまでもなく模樣又は文樣であつて、胡麻の形をした小さな點とも云ふべきである。之は恐らく遵生八牋汝窯の項に「底有芝麻花細小掙釘云々圓底······密排細小掙釘數十又見碟子大小數枚云々足底有細釘」とあるのを最初の記述とするものならん。而して說瓷には「古瓷之底有釘痕者古人思想較拙以鐵籤支皿底入窯而燒燒成則撤去鐵籤故底有釘痕也」(上一六葉)とあり。毎雅には瓷釘有二種有垂々如足者所謂爪者是也又有以竹籤支撑皿底而入窯者追火候圓滿撤去竹籤則亦有釉如釘形即掙釘也(下六二)とある。火候圓滿なるに追んで竹籤を撤去するなどの輕業は到底出來ないし第一竹など灰になつて仕舞ふ。殊に此種の燒物は一個づゝサヤに入れて燒かれるものだ。又鐵籤とするも燒成後鐵籤が無事に殘つて居るかと云ふに是も恐らく疑はしい。是等は皆著者が窯業技術の實際を知らざる爲の妄言であらう。然し要するに恰かも鐵又は竹の釘でも置いて其上に安置して燒いた樣な痕があるのは事實だ。是は無論耐火度の極めて高い石灰、珪石等を主成分とせる土を以て製せる釘の痕であらう。而して均窯の水盤などには此細かい「ゴマ」狀の釘痕が圓形に一列に數十又は數百點も排列せるものあることは往々見る處である。遵生八牋の記述は畢竟此種の釘痕を指せるものであらう。更に詳しく云へば芝麻花細小釘掙は胡麻の樣な形をした細小の支柱の痕と云ふことであらう。然し小生は宋代殊に北宋時代に斯る精巧なる技術が存在せしやにつき多大の疑惑を抱く者である。只此には遵生八棧記述の意義の一解釋を述ぶるのみ悉く書を信ずれば書を讀まざるに如かずとか書なきに如かずとか云ふこともあるから是等の書就中明人の書を讀むるに方りては大に法眼を具するの必要あるを認む。(三)芝麻醬
次に芝麻醬であるが、芝麻は前述の如く胡麻であり而して醬は本邦の味噌のことだ。爲念辭源を見ると食品之用以調和者。麥麵米豆。罨黃加鹽。曝之而成者也。(論語)不得其醬不食。凡食物搗爛如泥者皆曰醬云々とある。即ち芝麻醬は胡麻味噌のことである。之は勿論其塗られた暗褐色の釉の有樣なり色なりが胡麻味噌に酷似するから斯く云ふたもので實物の胡麻や味噌を塗る譯でもなければ、また前述の芝麻花と何等關係ある譯でもあるまい。芝麻醬は大抵均窯手の水盤の外底、及哥窯の模造品の外底又は釉下全體等に塗られてあるもので言ふ迄も無く紫口鐵足の模倣である。紫口鐵足は宋元以來頗る有名になり賞美せられたから其模倣を試むるは勢當然であるが、何分鐵分の含有量豐富である浙江地方の土(夫れも地方や場所及時代によりて異ることは勿論だ)でないと思ふ樣に紫口鐵足にならぬ。そこで手つとり早く普通の胎土の上に鐵分の多い赤土(恐らく大抵人爲的に調合するものであらう)を塗りつけて誤魔化すのだ江西や河南などの模製は皆一手である樣に思ふ。(四〓苧麻灰淋汁、芝麻楷淋汁苧麻灰淋汁、芝麻稽淋汁、之は小生には分らぬ。然し陶錄に此言非也とあるし餘り當てにはならぬと思ふ。尤も苧麻は江西省が支那で最も有名なる產地であるから或は鹽田氏の想像の如く其灰を取つて用ゆる位のことはあるかも知れない。稽は禾莖で稈と同義だとあるから或は麻を取つた後の廢物の稈を燒いて灰を作り之を用ゆる位のことは支那人に非ずとも如何にもやりそうなことである。殊に芝麻醬釉の場合には普通の釉の如く上等品で無くても間に合ふであらう。此場合勿論苧麻稽灰でなければならぬ。而して淋汁とあるから之に水を注ぎて前陳芝麻醬の赤土を捏るのに用ゆるもの乎。芝麻稽淋汁も亦た同樣の想像がつく。以上は元より純然たる臆說だ、然し普通用ゆる釉料の灰は景德鎭から可なり遠い地方(鎭の南百四十支里樂平縣と陶說卷一陶冶圖說にもある)で鳳尾草即ちウラジロに相當するかと思はるる羊齒科の植物を靑白石と共に燒きて之を製し、船で景德鎭に運び來るものを窯業家が買つて之を用ゆるのであるから若し手近に在る廢物の苧麻なり芝麻なりの稈を用ゆれば經濟的にも大に利益ある譯だ。是等の問題は小森氏に鹽田氏から說明を求められたから何れ明快なる解答があると考へるし、景德鎭へ行つたことのない小生が斯る臆說を述ぶるは潜越至極で誠に濟まないが筆の序に寐語さして貰ふ次第である。
哥窯の香爐其他(一)明の成化乃至弘治頃のことである。浙江省嘉興府嘉善縣の富豪に曹瓊と云ふ者があつて好運にも偶然の機會から其頃旣に絕無稀有と云はれた哥窯の香爐を一つ手に入れた。此香爐は高さ約二寸許りの濶さ是に稱ふと云ふ甚だ小形のもので其葢は海東靑(蓋し隼のことであらう)が天鵞を捉へて居る處を美玉で鏤めて拵へてあつた。此頃元末から明初にかけて造られたる哥窯のコツピーは群を成し隊を爲すと云はれゾロ〓〓と澤山あつたけれども眞宋にして精美なるものは實に珍貴で鳳毛麟角にも比すべきものであつたから。曹瓊の滿足は云ふも愚かなりけりで朝夕之を愛撫し、坐右に置きて片時も之を離さないと云ふ執着さであつた。曹氏は五代頃の祖先が仁和から此地に移住して以來巨族として此地方一帶に並ぶ者なく瓊の如きも祖先傳來の威望と殆んど計るべからざる資產とに任かせて若い頃にはずいぶん酒色に沈湎したこともあつたが、歡樂極まつて哀情多しとかや齡不惑に達するころから酒色に飽き〓〓して、弗つり之を思ひ止まつて彼氏の父、祖父、大祖父等々祖先以來代々 の誰しもが爲し來つたやうに書〓骨董の道樂に踏み迷つて來たのだ。曹氏は右の通り一代身上の陶朱猗頓では無くして何十代と續いた豪族であるから酒色から書〓骨董道樂に轉向すると今までは殆んど振り向きもしなかつた倉庫の中の塵にまみれて積んである書〓骨董を出しては鑑賞に日を送る樣な日が續いた。是等の古美術品は曹氏の祖先等が苦心して蒐集せるものであつて、魏晋以來の名蹟、三代の古銅器、古玉、古琴古硯.其他ありとあらゆる古玩寳器が鬱然として山の樣に堆積して居た。かくて五年十年の平和な星霜が流れるに從ひ曹氏の眼識も頗る上達して祖先等の蒐集に高等批評を如ふる樣になり、之に滿足せずして更に前人未踏の境地に邁進せんと志すに至つた。即ち曹氏の坐右に置きて片時も之を離さないと云ふ執着
樣な地位境遇の人が誰しも經驗する樣に彼氏は頗る無いものねだりに浮身をやつした。然し書〓古銅器古玉其他のものは祖先以來略ぼ一流の品がよく蒐集されてあつた。唯だ明初以來起つて來た比較的最も新奇な藝術鑑賞の對象であるところの燒物丈けは未だ十分の蒐集が出來て居なかつた。何しろ此頃は永樂を去ること未だ六七十年內外、宣德を去ること五六十年內外と云ふ時代であるから、永德の脫胎杯の如き曹氏の倉庫の隅から三十も五十も塵にまみれて出て來たし、項墨林の歷代名磁圖譜にある宣窯積紅朱霞映雪魚耳彝爐、宣窯積紅雙柿水注、宣窯靑花龍文小硯、宣窯靑花鵞壺、宣窯靑花象尊、宣窯積紅鳳首壺、宣窯積紅鹵壺、宣窯靑花龍松茶杯、宣窯積紅三魚把杯、同雙桃肥杯、同斗笠杯、同三魚小盞、同三魚宮碗、同龍文宮碟、と云ふ樣な今日吾人が容易に見ることが出來ない結構な品も曹氏の居室、書齋等の飾棚には雜然として排列し相互に凄艶を競つて居た。蓋し是等は殆んど皆曹氏の父より祖父なりが手當り次第に買求めて置いたもので曹瓊氏自ら買つたものとては殆んど一點も無く又斯く時代の若い而かも澤山集めてあるものを更に買ひ求める氣にもなれなかつた。若し夫れ曹氏日常の食卓上の器皿に至りては成化窯の五彩三彩乃至靑花の極めて上手のものを用ひたのは寧ろ當然であつて、後に神宗(即ち萬曆)皇帝の尙食の御前の杯が一雙で其價十萬と云はれた成窯雞缸杯、乃至五彩鵝缸杯、同菊花小杯、同樹根小杯。同蒲桃〓杯等々は上手のものではあるけれども其頃の新製品であるから好事家の曹氏は多數注文して取よせては常用品として妻妾等と共に日々使用して居た。然るに是等は何しろ極めて薄手のデリケートな品であるから十日に一度位はそそうでころれる。別に惜しいとも思はずすぐに新品を補充すると云ふ風であつた。曹氏の晩年には弘治の諸窯も追々用ひらるるに至つたけれども、嘉靖、隆慶、萬曆の如き今日に在りては相當に珍重されて幅を利かして居る品は勿論未だ姿を見せない時代である。さて、かやうに結構づくめの身分の曹氏は右の樣な平々凡々の新品には無論目も吳れず其熱心に集めたものは專ぱら宋元の古窯であつた。而して多年に亘る熱心なる搜査の結果大抵の品は悉皆集まつたが、最後まで手に入れることが出來なかつたのは哥窯であつた。曹氏は仕舞には文字通りに寝食を忘れ血眼になつて四方八方に懸賞付で捜し廻つたから、彼氏の手に流れこんだ哥窯の數は蓋し夥しき數量に上り、皿鉢香爐から古銅器の形を模せるものなど種類も極めて多かつた。然し是等は悉皆所謂元末明初頃のコツピーであつて一
點と雖も曹氏を滿足せしむるものはなかつた。流石の曹氏ももはやあきらめようとして居る所へ、偶然出入の者が持て來たのが此香爐である。これでこのまゝにすんでしまへばそれまでなのであるが、滿つれば欠くる世の習ひであつて今まで足ることのみを知つて此の世の中に苦勞と云ふものを知らなかつた曹氏にとりて容易ならぬ一大事が出來した。それは此地方の太守である麥太監と云ふ宦官上りがあつて彼の愛藏する哥窯の香爐のことを嗅ぎ出した.此時代は宦官の勢力極めて旺盛であつたし、宦官上りのことであるから貪婪飽くことを知らず、殊に他人の愛撫秘藏する物は何でもかでも奪つて自分の物とせねば承知しないと云ふ難物であつたから堪らぬ。早速支那古來斯る場合の慣用手段であるところの最も簡便有効な方法に出でて曹氏を捕へて獄に投じた。そして格別罪科のない曹氏を每日引出しては拷問折檻するので憐むべし此まゝにして置けば曹氏の命數も最早短日月の問題となつた。そして他方には人を倩ふて間接に曹氏の家族に對して例の哥窯の香爐を出せ、あれを出せばすぐ釋放してやると云ふのである。萬已むを得ないから曹氏の子息は哥窯の香爐を麥太監に献上して父の放免を得た。所がよくしたもので所謂佛家の因果應報であらう。麥太監は之を手に入れたけれども長く之を秘藏することは出來なかつた。いくばくもなく此事が段々と上役の方へ洩れ聞えて遂に都に在る其親分である朝廷の司禮監の有力者の耳に入つた。これが麥太監の親分丈けあつて太監に輪をかけた樣な難物であつたから。すぐと太監に此香爐を所望した。麥太監はイヤと云へば勿論直ぐに非道い目に遇ふから献上せざるを得なかつた。是れで宦官の幹部である某有力者(惜しいかな其名は傳はらぬ)から更に皇帝に献上して仕舞へば定石通りであつて何の變哲もないのであるが、そこが浮世の面白い處であつて一夜梁上の君子ありて首尾よく竊み出して蘇州へ走り此所で上海の澱山張信夫と云ふ者に二百金で之を賣つた。これは正德年間のことであると云ふ。張信夫は上海に歸つて更に他の好事家に賣つた。こゝまでは分つて居るが夫れから先此香爐は何所へ行つたか更に行方が分らぬ。例の項墨林の名磁圖譜にも載つて居ない樣であるから、或は恐らく間もなく支那から海外へ流出したのでは無からうか?。正德と云へば本邦にては後柏原天皇の御宇で略ぼ永正年間に當り足利義稙が將軍であつた。此頃から嘉靖頃にかけては例の倭寇が最も猖獗で朝鮮から廣東更に南方に至るまでの沿岸地方は殆んど其慘禍を蒙らざる地とては無く、明が衰滅した重要原因の一には倭寇が
數へられる位である。實際浙江福建其他沿岸地方の方誌などを見ると倭寇は海岸にある都市は勿論のこと時として河川を溯りて二十里も三十里も內地まで襲撃し來り數百名が隊を組んで褌一つの裸體で手に〓〓大刀を振りかざして劫掠を恣にして居るのであつて固より手當り次第財寳を掠奪するのであるから曹氏の哥窯香爐も亦た其內に無かりしとも限らぬ。或は又必しも倭寇によらずとも賣買によりて本邦へ渡來せざりしとも誰か保證出來ようか?太閤秀吉が秘藏し石川五えもんが盜みそこねた千鳥の香爐がそれだらうと言ふた僕の友人もある。然し是は恐らく「眞夏の夜の夢」であらう。(二)明の成化、正德と云ふ頃に旣にかくの如く珍重せられた哥窯であるから今日仲々其「眞宋にして精美」なるものは搜しても見當り難いのは寧ろ當然である。明代に於ても稀少であつた他の一證は項墨林の名磁圖譜に哥窯は只一點硯山が載せられてあるのみなることである。それ故明代鑑賞家の記述も頗る明確でなく從つて之に基く近代諸家の詮索も至難であるのは敢て不思議でない。陶說には妮古錄などを引きて若干の哥窯の器物を擧げて居るが果して眞宋のものであるか、直ちに信用することは出來ない。今西洋諸家の哥窯に關する說を見るに、章窯との關係に關する傳說に拘はらず結局南宋の官窯と同一又は極めて近似のものと見る者が多い樣である。其根據は蓋し(一)遵生八牋、〓秘藏、博物要覽其他の書に南宋の官窯と哥窯とは品格大率相同じとあつたり、又は此兩窯とも杭州鳳凰山の土を取つて燒いたとあるのと、(2)項墨林の名磁圖譜に載せてある前記の硯山と官窯の諸器(官窯は十點許りのせてある)とを比べると殆んど區別がつかぬ等によるものであらうと思はれる。更に近年になると大谷中尾兩氏の如きは杭州の郊壇窯の窯址から出たと云ふ破片なり品物なりによりて哥窯即ち郊壇窯なりとの說を立てて居られる樣だ。郊壇窯も南宋の官窯の一種であるから略ぼ前記諸家の說を裏書きしたものの如くである。尙ほ中尾氏は之に加ふるに哥々とは北人が天子を呼稱する語であるから哥々窯又は哥窯とは天子の窯即ち官窯であるとの說を述べて居られる樣だ。斯く述べ來るときは哥窯は郊壇窯のことであつて別に問題は無いやうであるが、然し哥窯の起原に關する傳說即ち南宋時代に龍泉に章氏兄弟ありて弟窯と區別して哥窯(兄の窯)
と云ふたとの傳說との調和は之を如何にすべきや。之が殘されたる一つの課題であらねばならぬ。「ヒルト」氏の說くが如く單に當時龍泉地方に存在した兩種の窯に附會せる空想的傳說であるや或は歷史的事實であるかゞ第一の問題であり、兄弟のことは空想的傳說であつても「ヒルト」氏の云ふ如く兩種の窯が龍泉地方に存在したと云ふことが事實であるや否やが第二の問題であると思ふ。而して若し龍泉地方に哥窯の本質を具備せるものが產出したと云ふ事實が今後證明せらるるなれば前記の南宋官窯の一種が哥窯なりとの說は否定される譯である。然し是は勿論たゞ將來の可能性を言ふて置く丈けであつて決して其蓋然性を、況んや必然性を唱ふる譯ではない。中尾大谷兩氏の採收せる郊壇窯の燒物につきては兩氏の著書に其寫眞が出て居るし、又曾て中尾氏の好意により破片を三四個見せて貰つたことがあるが仲々面白いもので頗る〓究に値すべきものとは思ふが、然し之を以て直ちに間違なき哥窯なりと斷定するには〓躇せざるを得ぬと思つた(之は數年前見せて貰つたときの感想、今見たら何と思ふかは自分にも分らぬ。)又哥々窯が天子の窯だとの新說につきては確かに前人未唱の說で頗る面白い說であると思ふ。たゞ此說が愈採用せらるるまでには必然簇出すべき種々の問題例へば何故に南方の杭州に於て北人の呼稱を用ゆるに至りしや?何故に獨り郊壇窯のみに限りて哥窯と稱し修內司官窯及北宋汴京の官窯は天子の窯と稱せざりしや?何故に龍泉の如き南方の山間僻地に天子の窯を存在せしむる如き飛んでもなき傳說を生ずるに至りしや?等々を解かねばならぬと思ふ。又北人が天子のことを哥々と稱すると云ふ典據につきても中尾君の開示せられんことを希望する。之を要するに管見によれば如上明代以降諸家の所說にも拘はらず未だ哥窯が龍泉地方に存在して居つたと云ふ傳說を棄つることは出來ないと思ふ。換言すれば此傳說を打破する丈け有力なる壓倒的論據は未だ發見されて居ないと考へるのである。抑も南宋時代龍泉地方に於て章氏兄弟の窯が存在せることを記述せる最初の文献は筆者の知る限りでは郞瑛の七部修類稿であるが此書並に本問題の傳說につきては嘗て陶磁第四卷第二號拙稿龍泉窯址の調査報告中にも少しばかり書いて置いたから再說せぬが決して一〓に空想とか無稽とか云ふて排斥出來ぬと思ふ。此點筆者は尙ほ當時の考を棄てることが出來ない。而し序に云はねばならぬことは遵生八牋などに官窯は鳳凰山の土を取つて燒いた云々、而し
て哥窯は私家で燒いたけれども同じく鳳凰山の土を取つたと云ふ樣なことが書いてある。此說が事實であるとすると哥窯は杭州から餘り隔つて居ない地方に在つたことになる。勿論此近傍は可なり水運の便利な地方ではあるけれども龍泉地方は嘗て本誌拙稿中にも述べた通り山又山の中であつて杭州から土を運ぶなどは一寸考へられないことである。龍泉から燒物を急流に乘じて運び出す場合と異り、土を運び入れるには言ふ迄もなく急流を溯らねばならぬ。是れは先づ六ケしいことだと思ふ。故に遵生八牋の記事を事實だとすれば哥窯の所在地は龍泉に在らずして杭州の近傍か又は少くとも水運の便のある地であらねばならぬ。而して此說によれば哥窯は私家にて造るとあるから官窯にあらざることとなる。此遵生八牋の所說は哥窯が南宋官窯と同等又は類似の品であると云ふことと、章氏兄弟の傳說とを調和することの出來る面白い折衷說である樣に見ゆるが、然し前記の次第により章氏の兄が故〓を去りて杭州又は土を鳳凰山から運ぶに便利な地に移住して燒いたと云ふ事實が立證されなければ成立し得ない。而して此ことは誰も未だ唱へたこともないやうだし、況んや立證せる人あるを聞かぬ。今是等の諸說を暫らく其まゝと爲して他の方面から考へてみるならば、龍泉地方に果し龍泉地方に果して杭州の鳳凰山に劣らざる或はこれよりも勝る土を產出せざりしやと云ふことも一の問題であらねばならぬ。哥窯の重要なる特色の一であるところの鐵胎と云ふ條件は龍泉に產する諸種の靑磁就中砧手と稱せらるるものに於て可なりの程度まで滿たされて居るのであるから之よりも一層鐵の含有量多き土が龍泉地方に產出せざりしと斷言することは無論出來ないのであつて從つて此方面から見れば龍泉地方に哥窯は出なかつたと云ふことは出來ないし、或は砧手靑磁の如き火によりて露胎の處が「チヨコレート」色乃至赤褐色となる土を產する以上一層含鐵量の多き土を產出したと見る方が寧ろ至當とも云へようと思ふ。因に砧手靑磁の露胎の處、例へば葢の裏、足の裏と云ふ樣な場所は傳世品ではすれて剝落して仕舞つて居る場合が多いけれども、近年渡來せる窯址の發掘品と思はるゝものは尙ほ上記の色を十分に存して居るものも少くない。是等を見ると殆んど鐵足と云ふても可なりと思はるる樣な色を呈して居るものもある。勿論砧手の場合には紫口は毫も認められぬ。(三)以上述ぶる如き難物であるところの哥窯と云ふものは果して如何なるものであらうか?
今諸書を參考として少しく此本質の問題に觸れてみようと思ふ。(イ)紫口鐵足哥窯は紫口鐵足であると云ふ。紫口鐵足と云へば哥窯、又哥窯と云へば紫口鐵足、と云ふ風に直ぐに連想させるほどであつて、哥窯と紫口鐵足とは不可分の關係にあることほど左樣に重要なる特色である。然るに世上にはまゝ紫口でないもの又は鐵足でない品ものを持て來て哥窯なりと云ふ人があるのは困る次第である。紫口鐵足と云ふのは言ふまでもなく胎土が鐵の含有量比較的多いから露胎の場所は火の爲に紅褐色乃至暗紅褐色を呈し恰かも鐵で拵へてあるかの外觀を呈するが故に鐵足と云ふのであり、又口緣などは窯內にて熱の爲に釉が熔けるときは半流動體になりし釉が自重によりて器の下方に流れ落ちんとする傾向ある故に口緣などは勢、釉が薄くなるを以て褐色の胎土が薄くかゝれる釉を通して見ゆるを云ふたものである。支那では褐色と紫色との區別が頗る暖昧で普通吾々が褐色と云ふ色を紫と稱することは少しく支那の古美術品就中鑑硯の道を〓究した人などの知る所である。明代以降の諸書をみると何故であるか頗る此紫口鐵足を賞美して居るが其賞美する理由に至りてはよく分らぬ。兎に角世人が之を賞美する結果、哥窯と云ふものは益有名になり從て其模造、僞造が續々と出來るやうになつたのは事實である。此模造乃至僞造品は勿論巧妙なのもあり、又拙劣なるもあり、千差萬別であるが、巧妙なるものは鐵の含有量多き土を見付けて之を用ゆるなり、又は鐵分少き土に鐵錆などを混ぜて之を用ゆるものもあるべく、拙劣なるものは普通の胎土を用ひて器形を造り之に鐵錆を混ぜる粘土を釉と共に塗れると思はるゝものもあり(實際は此手のもの多し)。又紫口鐵足を餘りに世人が賞美するが故に哥窯とは全然異りたる他の燒物に至るまで之を模する者少なからず。例へば均窯の水盤と稱し洋人が數萬金を抛つものの外底に芝麻醬と稱する胡麻味噌色の土又は釉を塗るが如き是である。又〓朝の蕎麥手其他時として靑花磁の足底まで黑色乃至暗褐色の土又は釉を塗れるものあるは人の知る所なるが是等は皆鐵足の模僞に外ならずと思ふ。彼の口紅手と稱する如きも恐らく其淵源は紫口の模僞に出づるものだ。要するに是等は皆紫口鐵足の賞讃に與られんとする爲にわざ〓〓斯かる手數も厭はざるものである。前記均窯水盤の外底の如きは褐色乃至暗紅褐色の釉土を塗るが其他のものは暗褐色、乃至灰黑色、甚しきは黑色の釉土を塗るものが多くして是等は恐らく鐵は黑いものと云ふ頭
から割り出したものであらう。然し眞正の哥窯の鐵足と云ふものは果して斯く黑色又は之に近きものであるか、どうか、と云ふに之は說瓷の著者が云ふ通り「釉のなき所、呈するところの色は其紅なること瓦屑の如し」と云ふのが却て近いのでは無いかと思ふ。勿論紅と云ふ字を文字通りに臙脂の色を解しては困るのであつて、紅褐乃至暗紅褐色で「チヨコレート」色に近いのであらうと思ふ。瓦屑と云ふのは勿論其色のみにつきて云ふたものであつて其土の粗鬆なるを指稱した譯では無い。恐らく砧手靑磁の場合の如く其土は極めて緻密であらうと思はれる。又鐵の含有量が多いとて露胎にあらざる内部まで鐵色を呈して居るものではあるまい。忌憚なく云へば郊壇窯なるものは紫口鐵足の內就中紫口の條件に於て未だ首肯し兼ぬる樣に思ふ。小生の見た郊壇窯の破片は紫口のものは一もなかつた。(一)ノ釉色哥窯の釉色に米色と粉靑との兩種あることは諸家の說く所である。米色と云ふのを文字通りに米(こめ)の色と解しては如何なる色かサツパリ分らぬと思ふ。近代の西洋瓷學家は之をmillet即ち粟(あわ)の色と解して居る即ち黃色の一種である。其基く處は恐らく說文に米字を釋きて粟實也とあるより來るものと思ふ。兎に角洋人の此解釋は蓋し正しいものであると考へる。要するに哥窯の釉色は黄色の系統に屬する一種がある譯だ。粉靑と云ふのは普通pale Thr又はlicht grunなどと譯されて居る樣であるが、小生如き外國語の智識甚だ淺薄の者にはよく分らないが、どうも此pale又はlichtと云ふ字には(1)7と云ふ意味が確然と現はれて居ない樣に思はれて何だか物足りないやうな氣持がする。「粉」は云ふまでもなく其靑色が單に水や油の如き透明なる「メデイアム」を以て薄められたものにあらずして、之に胡粉の如き白粉を混ぜて不透明となされた靑色を云ふものどある。〓家の所謂具入りの靑色である。單に色が薄くなると云ふのではないのだ。右米色にせよ、粉靑にせよ孰れの場合でも哥窯の釉は厚くかゝつて居て、「其釉厚潤にして純粹、千年を歷て而かも瑩澤、新きが如し」とか、「古氣盎然として人の眉宇を撲つ」とか云ふ感じは主として此釉から出てくるものであらう。尙ほ右の黄にせよ靑にせよ、たゞ其色が主調になつて居るのを云ふのであつて純黃純靑など云ふ意味では無論ないのだ。又他の靑磁などと異り哥窯の釉色は單色釉であるけれども單調でなく比較的變化に富み複雜であるのは事實のやうだ。後述する開片と相俟ちて其要するに哥窯の釉色は黄色の系統に屬する一licht
鑑賞價値を高からしむる所以の一は此變化の多い釉色にあるかと思ふ。(ヘ)開片開片も亦た哥窯の最も重要なる特色であることは勿論である。然し開片にも種々ありて其内の如何なる開片が果して哥窯の特色に屬するかと云ふことになると今日に於ては可なり混雜して仕舞つて容易に之を明確にし難き憾みがある。百坂碎とか魚子紋とか云ふ樣な小さな開片までを哥窯だと云ふ樣な說が相當古くから行はれて居るし、洋人の書例へば「リユツケル、エムデン」氏の書などにはずい分時代の遞下するものと思はれるもので小さな開片のある器の圖が哥窯として掲げてある。之れなどは如何なるものかと思ふ。我々が考へて居る哥窯の開片(眞宋即ち宋代の哥窯の眞物の開片)は大體大きな開片であつて決して小さな開片とは思はない。明代の何の書であつたか百坂碎と號すとか云ふ樣な記事があるがあれは所謂元末乃至明初の僞造か何かを見たものであらう。隱紋魚子の如しとか斷紋隱裂魚子の如しとか云ふのは(說瓷)どうも首肯し難い樣だ。匋雅には之に反して「哥窯の瓷胎は大片骨に入り窯を出で風を經て隨時迸裂す」とあるが、骨に入りと云ふは兎に角大片とあるのは正しいやうに思ふ。兎に角比較的大形にして不規則なる開片が思ひ切つて出て居るから比較的變化の多い釉色と相俟ちて男性的な豪宕の感を與ふるのは事實である。古茂と云ひ古雅と稱し、或は又紋片雅觀光色幽沈、尤も輩流を傾倒するに足る蓋し哥々窯也(毎雅)など稱美せらるるは亦た宜なり矣である。飮流齋說瓷を見ると北京の古物保存所に哥磁加彩の器がある而して著者の友人も亦た一を藏して居るが具に確かに宋物たること疑なし、花彩古氣盎然殊に後に加ふる者に類せずとある又同書に「近來宋元の盤盛出土するもの頗る多し云々」とありて「一を哥窯加彩の碗と爲す。彩釉濃厚、色澤深古、決して眞〓假彩の物にあらず。以て宋代彩色の一班を考ふべし焉」と述べてあるが。之は實物を見た上で無ければ何とも云へないが、可なり疑問であると思ふ。要するに哥窯と名のつくからには曲りなりにも如上の諸條件を具備して居なければならぬと思ふ。然し屢說するが如く「眞宋にして精美なるもの」に至りては明代旣に絕無稀有であつたのだから今日仲々見付からぬは當然であらう。匋雅の著者は哥窯の眞なるものは光彩人を照らし式樣亦た最も古雅なり、今世人に輕んぜらるる所以は皆贋作也とか、甚だ
古茂なれども當世に重んぜられざるは盖し仿製較や多く眞なる者は千に一を得ずとか云ふて居る通りであつて他の高名なる美術品と同じく所謂惡道の累を免れざるものと云へよう。魚目眞珠に混ずと云ふことがあるが是は眞珠を魚目の中から撰み出さねばならないのだ。昔學生の頃學んだ韓退之の文章の中に伯樂一たび冀北の野を過ぐれば馬群遂に空しとか何とか云ふことがあつたが眞の哥窯は恰かも之を千里の馬に比すべきであらう。たゞ千里の馬は常にあるけれども伯樂は仲々出て來ないと云ふのが韓文公の主張であつたやうだが哥窯の場合には仲々常にあると云ふことは出來まい。而して伯樂は同じく滅多に出て來ないのであるから、名器名品の世に認められて出ることは眞に千百年にして一度遭遇する僥倖ではあるまいか?誰であつたか、ある支那鑑賞家が哥窯の一名器に對して獨立孤高の品、世を擧げて之を識る者なしと嗟歎したのは良とに故ある哉である。記して此に至りて端なくも小堀遠州と利休に關する逸話を思ひ出す。小堀遠州が盛んなりしころ、ある人が遠州に向ひ御機げんとりの積りで云ふのに「流石にあなた(と云ふたか宗匠と云ふたか)の眼識の御高いのには常に我々の敬服措かざる所であります。あなたさまの御撰定になる掛物なり道具なりはどれもこれも成るほどと我々一同が見て誰も感歎する樣な結構な品計りであります。之に反して利休の眼識につきては吾々は常々疑を抱いて居ります。それと云ふのは利休の撰定されたと云ふものを今日見ますと、我々にはどこがよくてこんなものを撰まれしや頓と合點のゆかぬ品が少くありません。それ故あなたさまの方が利休よりは遙かに高邁なる眼識を具へて居らるることは間違ありませぬ」と。之を聞いた遠州はさぞかし喜ぶだろうと思ひの外反つて悄然と悲しげに答へて「それこそ利休が如何に高邁な眼識を具へて居たか、我々の到底思ひも及ばぬところである事實を最も雄辯に物語つて居るのであつて、自分の撰定する品が悉皆諸君に感心され共鳴されるのは畢竟自分の眼識が諸君と同一水平線上に在つて極めて平々凡々であるところの何よりの證據だ」と云ふたとのことである。(此話は岡倉覺三氏の名著「茶の本」に出て居たのを昔讀んだのを記憶から此に書く。岡倉氏は何の書によられたかは知らない。又何分長い日月を經たから記憶も薄らいだが意味は大體間違なき積りだが詳しくは同書を見られたい。)世の中には多數の人が見て感心して喜ぶものが最も審美的價値多しと爲し。又は鑑定なども多數決で決しようとする人が間々ある。之は審査會とか鑑定會とか云ふ樣な制度組織
としては萬止むを得ない方法であるだらうけれども、其萬止むを得ないところの窮策であると云ふことを忘却し又は閑却して仕舞つて之が最良の方法だと考へて居る人もある樣だ。かくの如きは認識不足と云はうか何と云ふか、甚しき誤謬であると思ふ。多數者が伯樂であり利休で無いかぎり多數決は正當ではあるまい。而して伯樂や利休の如き名人、總じて名の字のつく者は其時代の千萬人に卓越せる者でなければならず、世の中が如何に進步しても同時代に三人も五人もが伯樂であり利休であることは容易に實現出來ない空想であるならば、前記の樣に多數決で良否を决しようと云ふ考の當否は自ら分明であらう。窮餘の制度である審査會鑑定會の審査鑑定などが往々失敗に終る理由は詮ずるところこゝに在るのだ。然し相當分る目利の中に一人分らぬ者が居つても同じ結果になるのであるから皆が皆利休氣取りになつても困るのであるが前述した事實と云はうか眞理と云はうか、之れ丈けは認めて置きたいものである。右の樣な譯であるから哥窯の如き、よく云へば獨立孤高の名品わるく云へば誠に厄介極まる難物が伯樂利休に遭邁して世に出るのは先づ千年に一度と云ふはかなき機會であらう。又董其昌の書いた畫眼に次の如きことが書いてある。是より先、余嘉興を過ぎて項氏所藏の晋卿が瀛山圖を觀、武林に至りて高氏所藏の郭恕先が朝川圖を觀たり。二卷は皆天下に傳誦する北宋の名跡なるも、以て此卷(趙令穰が江〓〓夏卷)に視ぶるに退舍するなからず。蓋し瀛山圖は筆細謹にして澹宕の致なく、朝川は多く数せず唯だ拘染あり、猶ほ是れ南宋人の手迹なり。余京師に在りて懷に往來し夢寐に形はるるに至る。是に及んで披觀再過するを獲たり。始めて知る營平が所言百聞は一見に如かずとは、眞に老將の語なることを。此れ聊か以て畫を論ずるのみ。是に類する者更に何ぞ限らん。人々須らく自から法眼を具すべし、人に隨つて耳食する勿れ。この話なども前記利休の場合と照合して藝術鑑賞と云ふ問題の眞諦を理解する上に於て大に參考になるかと思ふ。要するに衆口鑠金と云ふこともある。市に三虎と云ふこともある。又一盲衆盲を引くとか一犬虚に吠へて萬犬其實を傳ふとも云ふ。其他此種の俚諺鑑戒は吾人の日常生活に多大の貢獻を爲して居るのであるから獨り古美術鑑賞のみが其例外ではあるまい。蓋し門より入るものは家珍にあらず。各自法眼を具すべきであら50
附記本稿を書き了りたる後、亦樂會に於て近頃橫川博士の獲られたる靑磁の大鉢と小石川松治君が先年杭州の萬松嶺附近に於て採收せられたる靑磁の破片とを比較對照するの便宜を得た。小石川君の採收せられたる破片と横川博士の此大鉢とは同一種の靑磁に屬するものであることは殆んど疑を挿む餘地なきものの如くであつた。是れ獨り余の斯く考へたのみならず同じ會合に出席せる數名の諸氏が恐らく悉く認められた處のやうである。前記本文中に記述せる中尾氏の杭州郊壇窯址に於て採收せられたる破片を朧ろげなる記憶から喚起してみると小石川君のものよりは釉色は可なり薄かつた樣だが他の點は極めて酷似して居たと思ふ。殊に露胎の處卽ち高臺の如きは黑色を呈し破面に於ける胎土の色は暗灰色に近く而して釉下に一線鳥黑色の土を見る(之れ特異の黑土を塗れるにあらずして胎土の內比較的外面に近きが故に多く火候及釉の影響を受くる爲黑色に變ぜるならんと云ふ人多し)。要するに中尾氏の郊壇窯の破片と小石川君の破片及び橫川博士の大鉢とは同一窯の所產と認めて可と思はれる然し郊壇窯が哥窯であるか否かにつきては前記の通り未だ疑問であると思ふ。郊壇窯は云ふまでもなく南宋後期の官窯であつて其位置は郊壇の下に在つたことは周知のことであるが「ペリオ」氏は十年前成淳臨安志を引きて靑器窯。在雄武營山上圓壇左右。とある圓壇は天壇の意に外ならず。而して天壇は臨安(杭州)の嘉會門外南方四方の地而して天壇は臨安(杭州)の嘉會門外南方四方の地に在り。之れ輟耕錄に新窯と稱するものに符合すと指摘して居る。(一九二三年通報誌上Paul Pelliot氏のNotes 111 l'histoire de EI C〓ramique Chinoise 7.0 36參照。)咸淳臨安志は道光復刻以前は兎に角、今日に於ては坊間容易に求むることを得る普通の書籍であるし、乾道淳祐の兩志が甚だ不完全なる殘卷であるに比して原本壹百卷の內九十五卷を復し獲て略ぼ完全に近きを以て南宋臨安の地理、地文を知らんと欲する者は何人も先つ此書を繙くものであるから「ペリオ」氏の指摘の如き別に異とするに足らざることであるが然し近代に於て之を指摘せるは同氏を以て嚆矢とするが如し故に之を記して置く。宋史高宗本記によれば紹興十三年臨安に於て圜丘を築くとある。これ蓋し郊丘即ち郊壇であらう。其形狀は四層であつて、上層は縱横共に七丈、第二層は十二丈、第三層は十七丈、第四層は二十二丈、十三陛を分ち、陛七十二級とある。尙ほ其附近には燎壇、端誠便殿、熙成殿、泰種門等附屬の建造物があつたやうだ。今の杭州の地圖と咸淳臨安志の附圖とを對照して見ると南宋時代の杭州即ち臨安は今の杭州よりはもつと南方に延びて居たものの如くである。尤も其延びて居たのは大體行宮即ち大內の境內丈けであつて今の杭州の南門である鳳山門の位置は略ぼ南宋時代の大
内の北門であつた和寧門の位置に近い樣である。南宋時代行宮の南門である嘉會門は鳳風山の右翼で其支山であるところは包家山即ち恐らく今包山と稱する山の裾に在つたとのことだ。郊壇窯が開始せられた時期即ち修內司窯が郊壇附近に移つた時期につきては何人も未だ之を攷究發表せる者あるを聞かぬ。之は早晩何人か篤學の士によりて〓究指摘せらるべき問題であると思ふがそれには特に直接其時期を推定するに足る文献資料の發見せられざる限り先づ順序として修內司窯の位置からして考定してかゝらねばならぬと思ふ。如何となれば窯を移すと云ふ必要から見て舊位地に窯を存續することを不便とする事情が發生したと推定することが至當であり、斯る推定を根據として其時期を定むるには修內司窯の位地からして考定せねばならぬからである。然し乍ら之れあまりに本篇の範圍を逸脫する事柄であり且筆者用意の未熟であるが故に此に擱筆することとする。×××××附記尙ほ右哥窯に關する拙稿の內左の通り少々訂補して置くそれは右の文中小石川君が郊壇窯の破片を萬松嶺に於て授收せられたる由を記載したが、是は小生記憶の誤でありし由にて、當日拜見した破片二個の內一は同君が杭州に於て入手せられたるもの、又他の一は大谷師が多數採收の破片の一であるといふことだ、右は小石川君の注意によりて此に訂正する。尙ほ修內司窯の位置に關しては咸淳臨安卷志十內諸司の內に同文館在孝仁坊內提擧修內司靑平山口とあり而して同志の附圖を見れば〓平山と云ふのは和寧門外に在りて此丘陵に修內司營と二ケ所に亙りて記されてあるから、これが修內司窯の所在地と見るも一見可の樣だ。杭州府志によると元末城を改築し二里を縮入し宋の宮城の北の和寧門によりて以て南門を爲くり卽ち和寧を以て之に名く云々明初名を鳳山と易ゆとある。卽ち後の鳳山門である。近年の杭州の地圖を見るに鳳山門內に〓平巷なる名稱が尙ほ殘つて居る。此近傍に修內司窯が在つたものであらうか。此地萬松嶺から餘り隔つて居らぬが萬松嶺は南宋の時宮禁に密通し紅墻碧瓦高下鱗次し主として宦臣の有力者等か此所に宏壯なる第宅を構へて居たとのことだ。されば此地から修內司窯、郊壇窯、定窯等々種々の破片が出たとて不思議は無い。我鎌倉からさへ龍泉窯の破片が相當に出る位である。而して〓平山が旣に修內司の所在地であるからには一應此所に窯が在つたと見るも不可なき樣である。只然し乍ら同じ成淳臨安志の附圖を見る
と鳳凰山下八蟠嶺と眞聖殿との中間に當りて舊司と云ふのがある。而して其傍に酒庫がある。之れ或は初の修內司では無からうか?何しろ咸淳は南宋末の年號であるから當時の修內司を以て直ちに窯の所在地と斷定すること能はざるは勿論である。況んや舊司なるものが存在するに於ておやである。尙ほ又況んや修內司窯を築いたと傳へらるゝ邵成章は北宋末の天子欽宗の內侍であつて宋室の南渡に方りて高宗に從ひ之に仕へた者である(宋史卷四百六十九に其傳がある)。卽ち咸淳よりも少くも百二三十年も前の人であるに於てをやである。定窯紅瓷につきて定州に紅瓷を產したと云ふ文獻は夙に磁學家の注意する所であるが、定窯紅瓷の如何なるものであるかにつきては今日尙ほ頗る疑問であつて何等定說が無いやうだ。而して又今迄餘り詳細に是等旣知の文献を考察した者も見當らないのは何故であるか、寧ろ不思議である。宋元は兎に角明初以來定窯紅瓷として疑なきものを見た人が無いのであるし、流石に好事家項墨林の歷代名瓷圖譜にも紫定、黑定までは載せてあるが紅定なるものは一點も載せてもなければ記述しても居らぬやうである。されば定州に紅瓷を產したと云ふ事實までも疑ふもののあるのは强ち無理でもない。然し從來定窯紅瓷に關する文獻につきて瓷學家の執つた態度は前陳の如く極めて冷淡てあつて、碌々文獻を考究もしないで居る。是れでは如何なる說を立てゝ見ても、或は其存在を疑つて見ても、夫れは畢竟毫も斯學に資す
る所以ではあるまいと思ふ。之に反して若し是等旣知の文獻につきて出來る丈けの〓究を爲すに於ては、假令〓究の結果が何等成果を齎らさず、依然として從來の說より一步も進むことを得ず、又現在の疑問を解決すること能はざるが如き場合に於ても、それは其執られたる考究方法が不適営であるか、或は其方法は適當であつても考究の過程に於て錯誤に陷れるか、或は又資料不十分によるか等々の缺點の爲めであつて、後來の〓究家に覆轍の戒を與へ更に考究の方向を暗示する丈けでも決して徒勞ではあるまい。學問の進步は畢竟〓究の失敗に基く多數犧牲者の集積の上に結果するものである事實を顧るときは、余の此貧弱なる〓究も所謂一塊の棄石と云ふ意味に於て必しも無意義ではあるまい。されば此拙稿を草するに當り其成果の大小有無等は元より余の顧慮する所にあらず、只將來本問題を考究せんとする人の爲に何等かの參考ともなることを得ば夫れで筆者の勞は酬いられる譯である。さて古文獻の考究に入るに先ち、從來瓷學家就中歐洲の瓷學家が此問題につきて如何なる說を吐いて居るかを一瞥するのも敢て徒爾ではあるまい。「ホブソン」氏は其名著支那陶瓷論に於て紅定なるものは格古要論、〓秘藏の如き古書に〓秘藏の如き古書に記述しあらずと云ふ理由を以て虚僞の一語を以て之に冠し問題とならざる如き態度を執つて居る。(一)〓1 Hobson; Chinese Tottery Cum Porcelain Vol. I,P·〓〓)然し同時に元代の蔣祈の陶略に記せる定州の紅瓷なるものにつきては、是れ白瓷と白瓷との比較の意に解するにあらざれば文意通ぜずと爲し、紅の意味を釉色にあらずして胎土の色と解せり(100. cit.f.n.3)。此解釋は原文の意味を取り違へたる爲に生じたる誤解なること明白にして、後述するが如く此原文の意味は色彩が似て居ると云ふにあらずして饒州產の瓷器が其ロ質質於於定定の紅瓷と拮抗するに足るを說くに過ぎず。是れ「ホブソン」氏が原文を讀解せざるが爲に陷りたる謬說にして邦人の如き恐らく誰も「ホブソン」氏の如き誤解に陷る者之あらざるべし。又原文は到底「ホブソン」氏の如き解釋を容れ難きものなるは議論の餘地なしと思ふ。但し「チンメルマン」氏は右の脚註の意味を顧慮せずして定州より紅瓷を產せる元代の記事を「ホブソン」氏が引用し乍ら他方には格古要論及〓秘藏よりも古き書に紅瓷の記事なしと說くは矛盾なりと難ずるも、之れ見當違ひの議論にして、假令事實誤解に出るものなるも「ホブソン」氏は前顯の如く蔣祈の記事を以て白色瓷器の意なりと解せるものなる故氏の
說は一貫せる說にして毫も矛盾する所なしと思ふ。(cf. Prof. Dr.円Zimmermann Chinesisches Porzellan; Bd. I〓Text, Anm. 369.)「ホブソン」氏の右の著書は西紀一九一五年の出版に係るを以て氏が最近如何なる說を抱くやは之を知るに由なし。然し氏は「ユーモルフオプロス·コレクシヨン」の解說中には紅定は柿天目なりと云ふ說あることを掲げ、昨年出版せられたる「アレキサンダー·コレクシヨン」解說中には只朦朧なると云ふ一語を以て之を形容し何等論ずることを避けたり。(Hobson: The Eumorfopoulos Collection Vol.Ⅲ,P·18;and Hobson, Rackham, King: Chinese Ceramics三Private Collections, T.O Le)由是觀之.氏の說は其後餘り進展し居らざるものの樣である。「ヘザリントン」氏は支那陶瓷蒐集家は河南天目の釉色赤褐色なるものを以て或は紅定にあらざるかと疑ふ者あるは陶說に定州の紅瓷及兎毫盞の記事あるを以て無理からぬ次第なるも、右の河南天目にして定州產の瓷器の如く精妙なる技巧を想起せしむるに足るが如き品は今日まで未だ一點も發見せられずと云ひて、暗に河南天目を以て紅定と考へ難き意を示せり。(A. Hetherington: The Early Ceramic Wares O) China, T.〓128.)「リユケル·エムデン」氏は類似品として朝鮮產の柿天目の圖を提示し、紅定なる者は恐(cf. Prof. Dr.円Zimmermann Chinesisches紅定なる者は恐らく「ホブソン」氏の云ふ如く不確實なる色彩記述に起因するものならんと云ふ。H O R〓cker=Embden: Chinesische Fr〓hkeramik,〓〓117, .- Anm. c.c.「チンメルマン」氏は前記「ホブソン」氏とは別の意味で蔣祈の記事を誤解せるものの如く紅定は紅玉とも比較せられ又屢々景德鎭の磁器とも比較せらるゝよりして見れば、紅定等は瓷質ならんと推定せり。(蔣祈の記事を斯くの如く解することの誤なることは「ホブソン」氏の誤解の條に既述する處によりて明かと思ふ)。而して氏は紅瓷が定州に於て產したることを否定せざるも、兎毫盞と同じく定州以外の地即ち建窯に於ても亦た宋代に之を產せりと爲し、「ボブソン」及「リユケル·エムデン」兩家の烏有說を難詰せり。(Zimmermann:op. CH S.91-92,〓Anm. 369)。西洋人の說は右の如くにして一方に鳥有說あるかと思へば他方には定州のみならず建窯にも之を產すと云ふ說あり、甚だ區々にして一定せざるが、然し何れも旣知の文獻の一部のみを採りて全部に及ばず、而かも其採用せる一部の文獻の解釋さえ之を誤れるは前陳の如し。之では其說く所粗漏杜撰の譏を免れ得まい。さて然らば定窯紅瓷に關して宋元時代の文獻に果して如何なるものがあるかと云ふに、H O
寡聞なる余の知つて居る限りに於て從來瓷學家によりて發見せられたものは只左の四事あるのみである。今記述せられたる事項の年代順に之を列記する。C北宋の仁宗皇帝の寵妃であつた張貴妃の紅瓷(邵氏聞見錄の記事)。(二)蘇東坡の試院煎茶詩に見ゆるもの、即ち文潞公の紅瓷。(三)周輝の〓波雜誌に見ゆるもの。(四〓蔣祈の陶略に見ゆるもの。是等の文獻は旣に普く人の知る處であつて何等珍らしいものは無い。つきて考究して見よう。以下少しく是等にC張貴妃の紅瓷(A)張貴妃邵氏聞見錄卷二に左の記事があつて、定州志、欽定古今圖書集成等にも引用せられて居る。仁宗一日幸張貴妃閣見定州紅瓷器帝堅作怪周校問曰安得此物妃以王拱辰所獻爲對帝怒曰甞戒定州志、欽定古今圖書集成等にも引用せられて居汝勿通臣僚饋遺不聽何也因以所持柱斧碎之妃愧謝久之乃己仁宗皇帝は北宋四代目の帝で其治世は天聖元年(西紀一〇二三年)より、明道、景祐、寳元、康定、慶曆、皇祐、至和等の多くの年號を經て嘉祐七年(西紀一〇六一一年)に至る三十九年間に亘つて居る。而して張貴妃の傳を見ると左の通りである。(宋史卷二百四十二)張貴妃河南永安人也祖頴進士第終建平令父堯封亦擧進士爲石州推官卒堯封兄堯佐補蜀官堯封妻錢氏求挈孤幼隨之官堯佐不收恤以道遠辭妃幼無依錢氏遂納于章惠皇后宮寢長得幸有盛寵妃巧慧多智數善承迎勢動中外慶曆元年封〓河郡君歲中爲才人遷修媛忽被疾曰妾姿薄不勝寵名願爲美人許之皇祐初進貴妃後五年薨年三十一仁宗哀悼之追册爲皇后謚溫成追封堯封〓河郡王謚景思而堯佐因緣僥倖致位通顯云仁宗の後宮は何十人又は何百人居たか今之を詳にせず、然し乍ら才人とか修媛とか美人とか云ふ者を除きて、皇后以外に妃と稱せらるゝ者は、張貴妃、苗貴妃、周貴妃、楊德妃及馮賢妃の五人に過ぎぬ。此中で楊と馮とは其死後、貴妃又は賢妃を追贈せられた者であるし、周貴妃は仁宗の崩後數十年(此人は初め張貴妃の養女であつて九十三才迄長生した)徽宗の朝に至りて貴妃の稱號を貰つたのであるし、苗貴妃も英宗が幼時宮中に保育せられ
て居る間、擁佑頗る恩有りと云ふ譯で、英宗が踐祚の後、其前勞に酬ゆる爲に貴妃に進めたのだ、即ち孰れも仁宗の崩後である。斯く數へてくると、仁宗も位に在り、自分も達者な間に貴妃となつた者は、仁宗の治世前後三十九年の間唯だ張貴妃一人あるのみである。加之至和元年春正月癸酉張氏薨するや仁宗は輟視朝七日禁京城樂一月、丁丑述册して皇后と爲し、溫成と賜謚せられたと本紀にある。又唐介の傳を見るに帝自至和後臨朝淵默そこで唐介が諫めたことが記してある。之は恐らく貴妃の死により快々として樂しまざりしものであらう。其寵幸せられたことは察するに足る次第である。されば「有盛寵」と云ふのは右の事情を能く十二分に諒察すべきである。而して妃も亦た實に「巧慧多智數善承迎勢動中外」とある通り極めて明敏な人で能く帝意を迎へ所謂飛ぶ鳥を落す勢があつたのてあらう。不幸にして比較的短命で、皇祐の初貴妃に進められてから僅か滿五年の後、(宋史卷十一本紀には皇祐元年の前年即ち慶曆八年の暮十二月丁卯に册美人張氏爲貴妃となつて居る)、年三十一で薨じたとある。故に本問題の仁宗が定州の紅瓷を破碎した事件は、皇祐元年(西紀一〇四九年)の初から皇祐五年(同一〇五三年)の暮までの間に張貴妃の閤(閨閣即ち「ブウドワール」である)で起つたものと一應見るべきである。(B)王拱辰さて問題の紅瓷は王拱辰が張貴妃に獻納したものであると、貴妃自身が仁宗皇帝に白狀して居るのであるが、此王拱辰なる者は果して何者ぞやと云ふことが次に問題となる譯である。そこで宋史列傳を少しく調べて見ると、卷三百十八に其傳が出て居る。之によると王拱辰は字は君既、開封成平の人で、元の名は拱壽と云ふた。年僅かに十九才にして進士第一に擧げらるゝと云ふのであるから、所謂神童の類であらうか、兎に角俊敏無比と云ふべきである。而して拱辰と云ふ名は此時仁宗から賜はつたものだと云ふから、其光榮、其得意想ふべしで實に華やかなる出世の「スタート」である。それから種々の官を經て慶曆元年翰林學士となつた。彼は哲宗即位の元祐元年頃七十四才で死んだとのことであるから、慶曆元年は二十九才位であつたと思ふ。此頃契丹の勢が仲々盛んであつて、動もすれば宋へ入寇せんとする氣色があり、恰かも翌慶曆二年には大軍を國境に集結し使者を宋に送りて地を割かんことを强請すると云ふ樣なことがあつて、其答辯には君臣頭を惱まし誰も名案を提示する者がなかつた。然るに拱
辰の獻謀其宜しきを得て流石の契丹も辭窮して侵略を思ひ止まつたと云ふ樣なことがあつて帝の御感斜めならざりしと云ふ。此邊までは彼の出世も先づ順當であつたが、之から後はどうも思ふ樣にゆかなかつたらしい。其原因としては第一に仁宗の仁君的政治は前漢の文帝と並び稱せられ、從つて其朝は有宋三百年間に於て最も人物の輩出した時代であつて此時代に出た第一流の人物例へば呂夷簡、富弼、韓琦、文彥博、司馬光等は何れも社稷の臣とか名臣とか云はれて名を竹帛に垂れた人である。其他杜衍、曾公亮、王安石、歐陽修范仲淹以下に至りては屈指に遑なき程である。されば此時代の神易家郡康節が聘を受けて屢出仕を命ぜられたが辭して遂に起たなかつた。其理由を後年息子の伯溫が尋ねたら「本朝、仁宗に至りて政化之美、人材之盛、朝廷之尊、極まれり矣。前或は未だ至らず後及ばざるものある也。天の命ずる所、偶然にあらず、吾出ると雖も何の益があらん。是れ爾の知る所にあらずや」と答へたと云ふ。(たセ書ニンニ氏お問(現象)斯る時代に出ては如何に少年狀元の才に書いてある子でも儕輩を拔いて進むことは容易でない。それから第二として才人の常として王拱辰も亦た重厚謹直の資質に於て聊か缺くる所があつたのではないかと思はれる。勿論自分の惠まれたる天禀と、君主の恩寵とを恃みにしたと云ふことも手傳つて居たのてあらう。又前記の如く濟々たる多士の中で出世に焦慮した結果もあらう、兎に角此頃から彼の言動は分に過ぎたものがあつたのは事實である。例へば矢張り慶曆中の事であるが、(此時拱辰は旣に御史中丞に拜されて居た)夏竦が出師して歸來、功無くして樞密使に除せられたのを彈劾して、「對によりて之を極論す、帝未だ省せずして遽かに起つ、拱辰前みて裾を引く、乃ち其說を納れ、竦遂に罷めらる」と云ふが如き、又勝宗諒の無爲無能を彈効した時にも「未だ聽さず、即ち家居して自ら貶せんことを求む、乃ち宗諒を岳州に徙す」とある如き。御史の職は彈劾糾察に在ること勿論であるし、且右の如き方法は古來支那では剛直の臣が君主を直諫する場合屢用ひられた處であつて珍しいことでは無いが、然し事に大小輕重あり此種のことは素より御史の彈劾の理由とするに足らんも.未だ以て直ちに國家存亡の危急と爲すに足らぬ。從つて是等の遣り方は孰れもやり過ぎである計りでなく、苟且にも君主を强要してまで我意を貫かんとする如きは臣節を辯ぜざるの詆を免れ得まい。又彼は後述の如く杜衍、富弼、范仲淹等當時要路の先輩の勢を殺かんが爲め杜衍の婿蘇舜欽以下其一派の者十數名を彈劾して罪に致し快哉を叫んだ。彼は斯る人物であつたから、因果は廻る小車の、後年御史趙抃の爲めに彈効せられて散々な目に遭つた。
此趙抃と云ふ人物が又珍らしい男で、殿中侍御史となつて其職を行ふに方り、「彈劾、權倖を避けず、聲稱凛然、京師目して鐵面御史と爲す」と云ふのだ。而かも此人は日々爲した事は其夜必ず衣冠を着け香を焚いて以て天に告げた、〓ぐべからざる如きことは敢て爲さずと云ふのであるから、先づ裃を着て夜眠ると云ふ樣な人であつた、それで居て自ら奉ずること極めて薄く、長厚〓脩、人其喜慍を見ず、平生貨業を治めず聲伎を蓄へず、兄弟の女十數人、他人の孤女二十餘人を嫁めにやり、其他孤獨貧窮の者等に德を施す事數ふるにたえずと云ふのであるから、全く以て模範的な人物であつた。宰相韓琦も感心して眞に世人の標表であると云ふた。此人に手ひどくやられたのであるから、王拱辰も全く助からぬ。拱辰の彈効せられた理由と云ふのは、第一に至和元年に命を奏じて契丹に使した。其時契丹に對する應對甚だ宜を得ず後患を貽したと云ふのが一つ。第二に此頃湖南省で眞珠に關する疑獄が起つた、然るに拱辰は悉く問題の眞珠を沒收して之を後宮に入れた、卽ち妃嬪等に獻じたと云ふのが一つ。此二罪併發である。(王拱辰の傳には至和三年復拜三司使聘契丹とあるが、本紀には至和は二年限りで三年は卽ち改元して嘉祐元年である、而して此年に王拱辰契丹に使する記事は見えない。然るに本紀至和元年九月の處に辛己三司使王拱辰報使契丹とあるから之は至和元年の事かと思ふ)。乃ち左遷せられて地方官かせぎを暫くやつて居る内、(右趙抃に彈劾せられたのは恐らく至和元年以後遠からざる時と思はれるから拱辰が四十五歲前後であらう)積年の功勞で段々出世して漸く吏部尙書に漕ぎ付け、神宗の即位卽ち熙寧元年、(此時拱辰五十六歲位である)、御卽位の恩典として僕射の榮官に轉ずる處であつた。然るに此僕射と云ふのは宋では重い官であつて宰相が任ぜらるゝものである、而して拱辰は未だ一度も宰相になつて居ないのであるから、順序でないと云ふので歐陽修に邪魔されて、僕射になり得ず但だ太子少保に遷つた。邵氏聞見錄によると歐陽修は王拱辰と同期の進士出身で競爭者であつた、而かも不思議の緣で兩人共に薛簡肅公の娘婿となつた。卽ち歐陽修、先づ姉娘を娶り、後(其夫人が死んだ爲であらうか)、再び其妹を娶つた、卽ち彼等は淺からぬ緣のある義兄弟である。然るに斯る邪魔をしたのは歐陽修が心中王拱辰を輕侮して居た爲である。又此兩人日頃黨派が異る爲だと云ふことだ。斯く義兄弟の歐陽修にまで妨害をされては王拱辰も亦た氣の毒な人物と云はねばならぬ。同時に歐陽修の人物も頗る疑はれる次第である。
歐陽修に云はしむれば種々理窟もあらうが、然し要するに歐の心中、王の榮達を疾むの邪心があつて此擧に及んだのは事實であらう。(邵氏聞見卷八參照)それから北院使、南院使、武安軍節度使と云ふ樣な官を經、此間に金方團帶を賜る等の事があつて、哲宗卽位卽ち元祐元年に、多年の功を以て檢校太師を加へられたが是年薨じた.年七十四、死する數年前に保甲と云ふ惡法があつて、(王安石の新法の一だ)、それが苛酷の爲に民之に苦しみ、往々去つて盗となると云ふ事があつたけれども誰も憚つて之を朝延に訴へる者が無かつた。然るに拱辰は老臣の國に報ずるのは此時だと云ふので敢然其害を申立てて帝を動かし漸く其害を少なからしむることを得た。是が彼の最後の御奉公であつた。薨ずるや開府儀同三司を贈られ懿恪と謚した、開府儀同三司と云ふのは從一品に當り位階としては最高である。又檢校太師は檢校官十九の最高である。(尤も檢校の官は宋では純然たる加衝だと云ふことだ。卽ち名譽の爲に加へらるゝもので實職は無い)。然し、彼は終に宰相には爲り得なかつたし、何國公とか何開國男とか云ふ爵(宋の爵は十二ある)を賜つた形迹はない、勳章は宋には上柱國以下十二あるが彼とて勳功があつたのであるから何か賜はつたと思ふが記して無いから分らぬ、尤も前に述べた金方團帶と云ふのが綬を加へられた樣のものかと思ふが、未だ究めない。(C)燈籠錦此王拱辰と云ふ人は兎角後宮に贈獻を爲して其歡心を得ようとする癖があることは前記眞珠疑獄の時の一件でも分る、然し乍ら後宮に贈獻を爲すことにつきては彼一人を責むるは酷である。例へば郡氏聞見錄には定窯紅瓷の次に左の如く記して居る。妃又甞侍上元宴於端門服所謂燈籠錦者上亦怪問妃曰文彥博以陛下眷妾故有此獻上終不樂後潞公入爲宰相臺官唐介言其過及燈籠錦事介雖以對上失禮遠謫潞公尋亦出判許州盖上兩罷之也或云燈籠錦者潞公夫人遺張貴妃公不知也唐公之章與梅聖兪書竄之詩過矣鳴呼仁宗寵遇貴妃冠於六宮其責以正禮尙如此可謂聖矣此一件は十八史略には「文彥博向守蜀以燈籠錦獻貴妃得執政」とあり、兪文豹の吹劍錄には「仁宗上元宴張貴妃服燈籠錦曰文彥博所獻蓋錦上織成燈籠也」とある。之によると燈籠の模樣を織出した錦であつたと見える。又宋史卷三百十三、文彥博の傳には「御史唐介効其在蜀日以奇錦結抜因之登用介旣貶彥博亦罷云々」とある。然し此事件を最も詳細に記
述せるは蓋し宋史卷三百十六唐介の傳である。此事件は王拱辰の紅瓷獻上に直接關係は無いが間接には重要なる關係があるから、冗長を厭はす唐介の傳より左に之を抄出する。介遂効宰相文彥博守蜀日造間金奇錦緣閹侍通宮抜以得執政今顯用堯佐益自固結請罷之而相富弼又言諫官吳奎表裏觀望語甚切直帝怒郤其奏不視且言將遠竄介徐讀畢曰臣忠憤所激鼎鑊不避何辭於謫帝急召執政示之曰介論事是其職至謂彥博由妃嬪致宰相此何言也進用家司豈應得預時彥博在前介責之曰彥博宜自省卽有之不可隱彥博拜謝不已帝怒益甚梁適叱介使下殿脩起居注蔡襄趨進救之貶春州別駕王擧正言以爲太重帝旋悟明日取其疏入改置英州而罷彥博相吳奎亦出又慮介或道死有殺直臣名命中使護之梅堯臣李師中皆賦詩激美由是直聲動天下士大夫稱眞御史必曰唐子方而不敢名數月起監郴州稅通判潭州知復州召爲殿中侍御史遣使賜告詣關下入對帝勞之曰卿遷謫以來未甞以私書至京師可謂不易所守矣介頓首謝言事益無所顧他日請日臣旣任言責言之不行將固爭爭之重以累陛下願得解職換工部員外郞直集賢院爲開封府判官出知揚州徒江東轉運使御史吳中復言介不宜久居外文彥博再當國奏介向所言誠中臣病願如中復言(以下略)之でみると當時の模樣は目に見る樣に分る、而して仁宗皇帝が名君であつた次第も、文而して仁宗皇帝が名君であつた次第も、文彥博が爲人、如才なくて其出世の偶然ならざりし譯も判然とするが、同時に此一件が仲々面倒な問題であつたことも分る、而して此事は後述するが王拱辰の贈獻に密接な關係ありと云はねばならぬ。此處で確めて置かねばならぬことは此彈劾事件の起つたのは何時頃かと云ふ時日の問題である。前記文彥博の傳によると「彥博亦罷爲觀文殿大學士知許州云々」とあつて次に「至和二年復以吏部尙書同中書門下平章事昭文館大學士與宣田弼同拜士大夫皆以得人爲慶語見富弼傳」とある。卽ち此時罷められて一旦出でて許州の知事になつたのが至和二年に富弼と兩人復活して又宰相の官に任ぜられたので、人々喜んだことを言ふのだ。而して本紀を見ると至和二年六月戊戌陳執中が罷められて文富兩人が之に代つたことが記せられてあるし宰輔表にも同じ事が出て居る。其前に文彥博が宰相を罷められたのは宰輔表に皇祐三年辛卯十一月庚子文彥博自吏部侍郞同平章事以行吏部尙書觀文殿學士出知許州とあるのが、それに當るし、又本紀には皇祐三年十月庚子文彥博罷となつて居る。孰れにせよ是れで此彈効一件の起つた時日は略ぼ明かであらう。而して宰輔表によると文彥博は益州(卽ち蜀の成都)の知事から慶曆七年帝都へ召還されて樞密副使に除せられ、同年更に參知政事となり、翌八
年には宰相の位に進んだのであるから、燈籠錦を献じたのは慶曆六七年頃のことである。文彥博は云ふ迄もなく宋朝三百年間に一二位を爭ふべき名臣中の名臣で、將相の任に在る事五十年、位勳人臣の榮を極め、遂には國老を以て目せられた人である。此人にして尙ほ出世の途に於て右の如きことありしとせば、是れ當時の風であつて、獨り王拱辰のみを責むべきではあるまい。唯だ其目的の奈邊に存するやは略之を察することを得るが、本問題の定窯紅瓷を張貴妃に献じたのは何か特に其頃欲求する次第でもあつたのか?之は多少の〓究を費さねばなるまい。そこで彼の行動を猶ほ少しく調べてみる。(1)蘇舜欽慶曆二三年頃から七八年に至る間に王拱辰は前にも述べた如く御史中丞の職に在りて頗る遣り過ぎたのであるから、之を憎む者も隨分多かりしことゝ思はれる。就中當時要路に居つた杜衍、范仲淹、富弼の輩には睨まれて居り、日頃反目して居つた。此處で少しく其ゆきさつを述ぶる必要がある。杜衍と云ふ人は宰相までなつた人であるが若い頃から苦心厲操尤篤於學と傳にあつて、所謂苦學力行したエライ人だ、それで治を爲すに謹密、威刑を以て吏を督せず然れども吏民も亦其〓整を憚ると云はれた、而も身を持すること〓介にして私產を殖せず、慶曆七年七十にして致仕したが其後の生活は狹小な陋屋に棲み、使傭人も少く粗服を着て居つた。死する前に其子を戒め極めて質素に葬むるべきを以てし、又遺疏を作つて國家百年の久計を述べたが、一語も私事に及ばなかつたと云ふ。是れ實に模範的な高潔なる人物であつた此人慶曆七年に七十歲と云ふのであるから王拱辰に比すれば卅五年の年長先輩で親子位の年齡の相違があることが分る。范仲淹は慷慨忠節の國士であり、富弼は人も知る宋の名臣として恐らく韓琦に勝るとも劣らざる有名な人である。今此に其傳を述べる要はあるまい。杜衍と云ふ人は前顯の如く謹密實直な人物を好んで賢士に薦引し而して僥倖を沮止したから小人多く悅ばずと傳にある。王拱辰一派の才子肌の所謂僥倖派とは根本的に合はなかつたらしい。而して此頃は杜衍、富弼、范仲淹の三人等が要路に居つて、心を一にし從來の政弊を改め政務の更新に努力して居つたが、王拱辰等の僥倖派は何とかして富范を排斥せんと欲し、あること無いこと牽强附會して益々二人の缺點を攻撃し帝をして此二人の政
務遂行を罷めしめんと焦慮したが、每度杜衍が此兩人の爲に辯護したから其目的を達することが出來なかつた。是れ杜衍は決して朋黨比周の辟論を立つるにあらずして、事實富范兩人等の爲に公平無私の正論を唱へたものであることは、杜衍平生の人物なり持論なりに徴して毫末も疑なき處である。然し乍ら此所に蘇舜欽と云ふ馬鹿者が出て來て杜衍の爲に實に氣の毒な事件が起つて王拱辰をして一時快哉を呼ばしむるに至つた。蘇舜欽は宋初の名臣、蘇易簡の孫である、故に其出身に於て名家の後裔と云ふ箔がある。少にして慷慨大志あり、狀貌怪偉、其人と爲りは磊落豪放で、古文歌詩に長じ、一時の豪俊多く之に從つて游ぶと云ふから、所謂豪傑肌の人であつた。此人の才能が范仲淹に認められて其推薦によりて集賢校理に召試せられ、進奏院を監して居つた。加之餘ほど范仲淹の氣に入つたと見えて、其推擧で當時の宰相杜衍の婿になつた。然るに其福落豪放な性質が崇つて、あらう事か自分の監督して居る進奏院の中で右班殿直の劉巽と云ふ相棒と二人で多くの賓客末社を集め妓樂を召して酒宴を開き、飮めよ歌へよの大亂痴氣を演じた、就中王益柔と云ふ者は(之も范仲淹の推薦せる人物だ)醉ふて傲歌を作ると記してあるから傍若無人の歌を作り、恐らく作つた計りでなく大聲を擧げて其歌をわめき立てたのであらう役所の中へ藝者を呼んで大酒盛をやつたと云ふ一事丈けでも官吏何とか云ふ規則の制裁を免れまい、況んや御苦勞にも其費用は役所の故紙を賣拂つて得た公金を以て支辨したと云ふのである。是では、如何に顯官の婿でも助からぬ。手ぐすね引いて事あれかしと待つて居た王拱辰は同僚の魯周詢、劉元瑜等を諷して共に之を擧勃した。此に於て事が六ケしくなり、遂に蘇舜欽は劉巽と共に盜と云ふ罪名で除名せられ都城を放逐せられて遠く吳中に寓居せざるを得ざるに至つた。同時に會合した者は皆知名の士、之が爲に罪を得て四方に逐出された者が十餘人あつたと云ふ。尤も杜衍の傳には妓樂が伎樂となつて居り、且此事は前例によりて進奏院で神を祭つたのであつて、伎樂を以つて來賓を樂ましたのだと書いてある、又蘇舜欽の傳を見ると、此成敗は世以て過薄卽ち過酷と爲したとあるが、然し王拱辰等が如何に機會を覗つて居ても、前例により神を祭ると云ふ丈けの事を爲したのなら之を彈劾するにも、爲樣が無い譯だ。由是觀之、杜衍等には誠に氣の毒だが事實、前例による祠神を口實にして前記の樣な事實があつたものであらう。此事件があると王拱辰は「自喜日吾一擧網盡矣」とあるから、今の言葉で云へば一網打盡にしてやつたと云ふて、頗る滿悅の體であつた。今の言葉で云へば一網打
此事件の起つたのは何時頃であらうか?杜衍の宰相になつたのは、宋史宰輔表によると慶曆四年の九月で、宰相を辭したのが翌五年の正月である。此間僅かに百日である。(何故に斯く早く辭したかにつきては或は前記小人等が之を悅ばざりしを察した爲めと云ひ、或は之に代つて宰相となつた買昌朝に排斥せられた爲だともある、恐らく右兩方共事實であらう)。而して蘇舜欽は傳によるに吳中に寓居、其後二年にして死んだ。擬年錄によれば其死んだのは慶曆八年で、年四十一とあるから問題の起つたのは其二年前なら慶暦六年頃であらう。さすれば杜衍の宰相辭職後少くとも一年以上乃至二年の後であり、岳父衍の爲には不幸中の幸であつたが。若し宰相在職中であつたら、勿論安閑として其職に留まることは出來なからうし、一層の苦痛であつたらうと思はれる。王拱辰の行動は斯くの如くであつたから、日頃反對派から睨まれて居たらうし、自分でも夫は萬々承知であつたらう。杜衍の傳に前にも述べたが「衍好薦引賢士而沮止僥倖小人多不悅」とある、其小人の內の首要なるものに數へられて居たと思はれる。從て日頃自分の安全と出世を計る爲には拔目なく立廻つて居たらうし、紅瓷献上以前から後宮へ種々献上を爲して居たかも知れない。(上)紅瓷献上王拱辰の慶曆六年頃迄の行動は右にて略ぼ明かとなつた、而して慶曆七年から至和元年前にも述べた契丹に使する迄の彼の行動は如何と云ふことが次に問題となる。此間に皇祐と云ふ年號卽ち定窯紅瓷を張貴妃に献じたと思はるゝ時代が存在して居る譯である。勿論前に述べた如く燈籠錦を文彥博が張妃に献じたのは慶曆六七年で張氏が貴妃に進められる一二年前であるから、紅瓷の場合も必ずしも張氏が貴妃に進められた後と斷定することは出來ない。邵氏聞見の書き方はそれほどまでに截然と時日を定むる丈けの力に乏しいものである、然し後に述ぶる事情によりて矢張り紅瓷進献の時日は皇祐二三年頃かと思はれる。傳によるに彼は此頃(慶曆七八年頃)富民鄭旭を擧ぐるに座して出でゝ鄭州に知たりとある富民鄭旭を擧ぐると云ふは何の事件か其詳を知り難いが、兎に角此問題に連座して地方官を勤めねばならぬことになり鄭州の知事になつた。次で遭、瀛井三州に徒り、數歲にして還り、學士承旨兼侍讀となる云々とある。此次に至和元年契丹に使したことが書いてある。そこで張貴妃に紅瓷を献じたのは此間であるが、果して地方官稼ぎをして居た間か、又は學士承旨となつて後か分らぬ。然し前にも記した通り文彥博が燈籠錦を献じたのは蜀(益州卽ち成都)に居た時であつて、其地の名產である錦卽ち所謂蜀紅の錦を献上したので
ある。王拱辰も田舍廻りをして失意の時代に其在任地又は其附近の名產である定州の紅瓷を献上したと云ふ樣なことがありはせぬか?そこで彼が地方官として轉々數年を費したと云ふ各地を一應調べて見ると左の如くである。鄭州、之は河南省の鄭州で、熙寧五年地方制度の變革ありし迄は此地方は鄭州と稱して居つたことは宋史地理志に明記してある。澶州、之は地理志によると河北路の開德府のことで、〓朝時代の地圖を見ると直隷省の開州とあるのがそれだ。瀛州.之も地理志によると河北路の河間府のことで、(〓朝の圖にも河間とある)、注意すべきは宋代の定州卽ち中山府に近接せる州であることである。〓州、之は山西省の太原府のことらしい。假に慶曆の七八年頃から地方廻りをしたと見て鄭州及澶州の知事を經て定州の近接地瀛州に至つたのは皇祐二三年頃ではあるまいか。而して彼が定州の紅瓷を得て之を張貴妃に献じたのは恐らく其瀛州の知事時代であると推定するのは必ずしも不當ではあるまい。此處で先づ二つの假說が成り立つと思ふ。皇祐三年の十月前後になれば前にも述べた通〓朝時代の地圖を見ると直隷省のり文彥博の燈籠錦の一件が頗る八ケましくなり、宰相を罷められた位であるから、王拱辰も迂濶に後宮に献上も出來ないから、無謀の冒險を思ひ止まつたらう、又貴妃も之を受取ることは出來まい。即ち紅瓷の贈献は其前だと云ふのが第一說。邵氏聞見に記するが如くば仁宗は張貴妃の閤にて紅瓷を見て王拱辰の献じたのを妃から聞きて怒つて甞て汝を戒めて決して臣僚の饋遺を通ずるなと申付けて置いたのに何故にコンナものを受取つたかと詰り怒つて自分の持て居られた柱斧を以て之を碎かれたと云ふのだ。何か前に贈献につきて重要なる問題が無かつたならば、仁宗は、イキナリ、こんなに激怒される譯は無い。之は恐らくこの少し前に燈籠錦の一件があつて間も無くの事であらう燈籠錦の一件では仁宗は仲々頭を惱まされ、怒つたり後悔したりされたことは前に唐介の傳を引て述べた通りである。されば此時に張貴妃に對し懇々戒められたものであらう。然るに張貴妃が其戒を聽かざりし故に帝の激怒を蒙つたと見るのが至當だと云ふのが第二說である。此兩說は何方も一理あると思ふ。そこで第三說として結局かうでは無いかと考へる。王拱辰の贈献は燈籠錦事件の發生前であつて、仁宗が紅瓷を碎いたのは燈籠錦事件の後だと
云ふのだ。此假說によれば種々の點が都合よく解釋出來ると思ふ。第一說の冐險と云ふ事も献者、被献者共に戒心前であつたし、第二說の仁宗の激怒も無理でなくなる。只貴妃は燈籠錦の時に何故に仁宗に實は紅瓷を王拱辰から受取つて居ると云はなかつたかと云ふ論も出ようが、如何に怜悧でも婦人のことである、今此處で理智的に嚴しく批判する樣に行動は出來まい。又何故にソレナラ詰られた時に是は戒められる前に受取つたものだと辯解せざりしやとの論も出やうが、斯る辯解は理論としては一應成立するかも知れないが、ソレナラ何故前に戒めた時に云はざりしやと第二の詰問が出るに極つて居る。且又ソンナ逃れ口上は俗に云ふ口答へであつて決して帝の怒を解く所以では無い。されば結局は謝罪せねばならぬ譯である。況んや臣下より貴妃に贈献した物は必ずしも燈籠錦及紅瓷の二點には限るまい。是等の事情を省るときは貴妃が初から愧謝久之乃己と云ふ態度を取つたのは恐らく最も賢明怜悧の策であつて、其如何に明敏貞淑な婦人であつたかと云ふことを立證するものであつて、帝寵を一身に萃めたのも偶然で無いと思ふ。そこで右の考察により紅瓷の贈献及破碎は皇祐三年頃に起つた事件として置く。以上、此事件に關係ある張貴妃王拱辰等の事歷並に當時是等の者が活動して居つた環境の一端と、此事件の起つた年代及其由來等につき考究の大要を略述した。斯くの如く長々と縷述した目的は要するに只茫然と邵氏聞見錄の簡單なる記事を讀んだ丈けで十分會得の出來ないと思はれる事實の眞相を、出來る丈け確然と明白に攫まんが爲に外ならない。而して上述した處によれば仁宗皇帝三十九年の治世の間に唯一の貴妃として盛寵を一身に萃め、飛ぶ鳥を落す勢のあつた張貴妃に、俊敏氣銳の王拱辰が杜衍、富弼、范仲淹の如き老巧の先輩上官を向ふに廻して散々葛籐の擧句.自分の出世榮達を冀ふ爲に贈献した紅瓷なるものが決して平凡なる品物で無く、當時に在りては頗る珍稀なる品であつたことは確かであらう。(一)邵氏聞見錄次に考察すべきは、邵氏聞見錄と云ふ書の文献としての價値如何である。此書の著者邵伯溫は易學の大家として有名なる邵康節の子であつて此書は紹興二年の自序がある。而して書中仁宗崩御のときに彼は七歲であつたと自記して居るから嘉祐元年の生れであることが分る。(擬年錄には嘉祐二年生るとある)嘉祐元年(西紀一〇五六年)-紹興二年(西紀一
一三二年)即ち彼が七十六歲の時の著述である。四庫提要によれば、伯溫藉邵子之〓猶及見元祐諸耆舊故於當時朝政具悉端委とあるが、事實父の邵康節は當時の名流富弼、司馬光、呂公著等と親交があつて恒に相從つて游ぶとあるし、伯溫自身は若い頃は常に此父に侍座して〓を受けて居た計りでなく。やがて官吏となつて直接社會の事相を見聞した。卽ち元祐中薦を以て大名の助〓を授け、潞州の長子縣尉に調せられ、夫れから主管耀州三白渠公事、知果州、提點成路刑獄等の官職に歷任した。而して紹聖の初め章惇が宰相と爲つたとき、惇甞て雍(康節卽伯溫の父)に師事した故を以て、伯溫を引用せんと欲したけれども、伯溫百計之を避けた。又後に主管耀州三白渠公事に除せられ、其任に在つた時、童貫が宣撫と爲つたと聞き、他州に出でゝ之を避けたと云ふ。蓋し是等は其家學から出た明哲保身の秘訣の現はれであらう。然し徽宗卽位、以日食求言、伯溫上書、言當復祖宗制度、辨宣仁誣謗、解元祐黨錮、分君子小人、戒勞民用兵、益爲小人所忌、とあるから正に言ふべきに方りて言ふことを避けなかつた丈けの氣節は之を有して居つたものと認め得る。彼には聞見錄の外河南集、及家學に關する易辨惑、觀物內外篇解、並に皇極系述、皇極經世序等の著述があつたと云ふ。要するに前記の如き環境なり體驗を有する著者が其聞見を記したものであるから隨筆としては尤も信用すべき價値あるものの一だと思ふ。尙ほ此書に關する四庫提要の所說を左に續記して參考に供する。是書成於紹興二年前十六卷記太祖以來故事而於王安石新法始末及一時同異之論載之尤詳其論洛蜀朔三黨相攻惜其各立門戶授小人以間又引程子之言以爲變法由於激成皆平心之論其記鐙籠錦事出文彥博之妻於事理較近其記韓富之隙由徹簾不由定策亦足以訂强至家傳之譌周必大跋呂献可墓誌謂是書頗多荒唐凡所書人及其歲月鮮不差誤殆好惡已甚之詞不盡然也十七卷多記雜事其洛陽永樂諸條皆寓麥秀黍離之感十八卷至二十卷皆記郡子之言行而殤女轉生黑猿感孕意欲神奇其父轉涉妖誣又記邵子之言謂老子得易之體孟子得易之用文中子以佛爲西方聖人亦不以爲非似乎附會至投壺一事益猥瑣不足紀葢亦擇焉不精者取其大旨可耳妖誣、荒唐、附會、猥瑣に渉るものゝ採るべからざるは勿論であるが、此書採るべき說も少くない、決して周必大の唱ふるが如きもので無いことは提要の謂ふ所が正しいと思ふ。而して定州紅瓷一條の如きも恐らく實說であらうと思ふ。尙ほ右提要の記述中邵子とある
は勿論著者伯溫の父邵康節を指したものである。(二)文潞公の紅瓷之は蘇東坡の試院煎茶詩中に見ゆるものである。普通は只だ「定州花瓷琢紅玉」と云ふ一句のみを引くのであるが、例陶錄卷六、定審の項)是れだけでは頗る物足りない、加之意味がよく分らぬ。又之に其前の句である「潞公前茶學西蜀」をつけるものもある、例陶說卷五)然し西蜀を學ぶとは何であるか?而して此句と後の紅瓷とは如何なる關係ありや等一層複雜にして困難なる問題が發生してくるのを免れ得ない。仲には琢紅玉は琢如玉の誤だと云ふ說もあるやうだ。然し蘇東坡詩集、唐宋詩醇等を見るに皆、琢紅玉となつて居るのであるから、確かな理由が無い限り漫然と誤謬だと云ふことは出來まい。之は矢張り紅玉であろうと思ふ。然し今此句の意義を窮めんとするには矢張り試院煎茶詩の全部を一應通覽する必要があると思ふから左に錄出する。蟹眼己過魚眼生颼颼欲作松風鳴蒙茸出磨細珠落眩轉遠〓飛雪輕銀餅潟湯誇第二未識古人煎茶意君不見昔時李生好客手自煎貴從活火發新泉又不見今時潞公煎茶學西蜀定州花瓷琢紅玉我今貧病常苦飢分無玉盛捧蛾眉且學公家作茗飮博爐石銚行相隨不用撑腸拄腹文字五千卷但願一〓常及睡足日高時蟹眼、魚眼、蒙茸、細珠、眩轉、飛雪、是等は東坡詩集の注解書を見れば皆夫々丁寧に說明がしてあつて殆んど疑を遺さないから今此處で彼是云ふ必要はあるまい。要するに是等は煎茶に際して水の沸騰する狀態又は茶末が湯に混淆せられて茶甌に注出せらるる有樣を形容せるものである。第二を誇ると云ふのは注解書を見ると種々の說があつて一定せぬ樣だ。例へば第二と云ふは水が第二であると云ふ意味、又は茶が第二であると云ふ意味だとの說がある。水は惠山泉を第二と爲す、又煎茶は兩浙が盛んで、越州の日注が第一、景祐より以來、洪州雙井の白芽が製作尤も精しく、遠く日注の上に出で、遂に草茶の第一となる。と云ふ樣などつ
ちともつかぬことを書いてある注解書もある。勿論陸羽の茶經以來喫茶の風が天下に風靡し、其結果として茶の品質の詮議が異常なる熱心と細心とを以て行はれ、唐から宋に至りて鬪茶、試茶と云ふことが一の風を成した。是は孰れも茶の品質の優劣を論評するを以て目的とするものに外ならない。卽ち右の注解にある如く其時代々々に應じて第一等の茶、第二等の茶と云ふ風に其品位を定めたものである。一而して之と同時に水の詮議が頗る八ケましくなつて四百餘州の水を一々試驗して其優劣を定むると云ふ樣なことも行はれた。勿論水が純粹なる〓〓〓でない限り、其中に溶けて居る鑛物質乃至夾雜物などの爲に茶の風味に種々の影響、關係を有するものであるから、茶の品位を試定する爲には當然水の詮議が必要である譯である。故に已に唐時代に於てさえ張又新の煎茶水記、蘇元明の湯品と云ふ樣な書があつて天下の川や泉の水を試驗したり、煮沸用の器具乃至燃料までも吟味して其優劣を論定した位である。されば此誇第二と云ふのを第二等の茶品又は水品を誇つたと解釋出來ぬことは無い。然し茶にしても水にしても第一を誇るので無いから切實でない。どうも此詩を讀む者の心にピツタリと來ない。加之第二泉と云はるる惠山泉と云ふのは成るほど無錫に在るのである而して此詩は凞寧五年八月十日の作で當時東坡は杭州通判の任に在り、是年科場試を監す、故に呈試官及試院前茶諸詩ありと云ふから、此時東坡は杭州に居たのだから無錫から杭州までは比較的近いとは云へる、眞逆に遼東の水を湖南湖北へ運ぶほどの遠距離では無い。然しそれにしても無錫から杭州までは百哩以上の距離はある、而して其間太湖及運河によりて水運の便はあるけれども、ワザワザ水を取りよせたとは思はれない。殊に此詩の後段には我今貧病常苦飢と云ふ身分である。故に如上の注解は問違つて居ると思ふ。管見によれば此誇第二はどうしても陸羽茶經卷下、五之煮の中にある左の一條を指したものであると考へる。其沸如魚目微有聲爲一沸緣邊如湧泉連珠爲二沸騰波鼓浪爲三沸已上水老不可食也此內の第二沸卽ち緣邊如湧泉連珠ものを指したのであろう。騰波鼓浪を三沸を爲す、已上は水老いて食すべからざる也とあるが、右一節の意味は第二沸を以て最も適度としたものであるか、卽ち已上とあるは三沸も其內に入りて不可であるとの意味か、或は又三沸までは可であつて、其上は不可であるとの意味か、分明でない樣であるが、之は明の顧元慶の茶譜にある左の解說が妥當である樣に思ふ。五之煮の中にある左の一條を指した
始則魚目散布微微有聲中則四邊泉湧纍纍連珠終則騰波鼓浪水氣全消謂之老湯之によると終卽ち第三沸は水氣全く消えて老湯となるのである。其水本來の味が消失して無くなる卽ち鮮新なる所以が無くなるから老湯と云ふのであろう。由是觀之第二沸が最も適當なる程度である譯だ。諸家の說も亦た斯くの如くである樣だ。然し今繁を厭ひて其詳は之を省略する。兎に角右の如く解して始めて第二を誇ると云ふ意味が明確に分るかと思ふ。而して次の句の未識古人煎水意と照應するし、且又後に述ぶる李生が活火に從つて新泉を發するを貴んだと云ふ句及潞公の煎茶が西蜀を學ぶと云ふ句とも相照應する譯である。尤も後世明以後淹茶の法が行はるるに至りては第四沸、第五沸の湯を用ゆると云ふことも工夫せらるるに至りたる樣であるが、北宋頃には未だ淹茶の法は發達せず、從つて第二沸を最も適度としたものである。次の二句、昔時李生好客手自煎、貴從活火發新泉と云ふのは、唐代に李約なる者があつて茶須緩火炙活火煎と云ふたことを指すのであつて、蒙史によれば炭火之有焰者を活火と謂ふとある。又東坡の汲江煎茶の詩に活水還須活火烹とあるのは是である。さて次は潞公前茶學西蜀の一條であるが、潞公は前に述べた文彥博で此頃は旣に多年高位高官に在りて威望赫々たるものがあつたが、燈籠錦の項に述べた如く慶曆七年頃四十一二歲の時に一時益州即ち蜀の成都に在勤して居たことがあつた。これで西蜀を學ぶの意味が一應判つた。即ち潞公は蜀に居たことがあるから西蜀風の煎茶法を學んで、其方法によりて茶を煎じて居るとの意である。然し西蜀風の煎茶法とは何ぞやと云ふことが次に問題となる。注解書にはそこまで說明したものは見當らない。一本には「潞公前茶の事は考ふる處なし」とある。然るに是は此東坡の試院煎茶の詩に對する弟子由即蘇轍の唱和の詩を讀めば自ら氷解するから左に之を錄出する。和子瞻煎茶年來懶病百不堪未廢飮食求芳甘煎茶舊法出西蜀水聲火候猶能暗相傳煎茶只煎水茶性仍存偏有味君不見聞中茶品天下高傾身事茶不知勞又不見北方俚人茗飮無不有鹽酪椒薑誇滿口
我今倦遊思故〓不學南方與北方銅鐺得火蚯蚓叫匙脚旋轉秋螢光何時茅詹歸去炙背讀文字遣兒折取枯竹女煎湯即ち之で見ると當時西蜀には煎茶の舊法と云ふのを尙ほ傳へて、水の沸騰する聲と火加減とをよく暗じて居た。其祕傳と云ふのは茶を煎るのに只だ水を煎るべし、斯くすれば茶の性分が仍ほ存して偏に味があると云ふのだ。是れ當時煎茶に際し動もすれば茶を前過ぐる弊あるが故に潞公がよく舊法によつて茶を煎るのを稱讃したものである。尙ほ舊法と云ふのは畢竟陸羽の茶經に記述せる法であつて文潞公が此舊法によつて茶を煎たと云ふことは元より嘗て蜀に在勤したからではあろうが然し是で其爲人がよく洗鍊せられたる高い趣味の持主であつたことが判ると思ふ。尙ほ蘇轍には文潞公から賜はつた茶を舅に分與した時に作つた左の七絕三首がある。詩の前書にある公擇なる者は轍の舅なることは別詩で分る。本詩に外家と云ふのも其故である。東坡の詩によく出てくる李公擇と云ふのが恐らく同人であるかと思ふ。以潞公所惠揀芽送公擇慶雲十六升龍餅披拂龍紋射牛斗國老元年密賜來外家英鑒似張雷赤嚢歳上雙龍壁想得天香隨御所曾見前朝盛事來延春閣道轉輕雷風爐小鼎不須催魚眼長隨蟹眼來深注寒泉收第一亦防楊腹瀑乾雷此處に少しく唐宋時代の煎茶の法を略記せんとす。是れ餘事に似たれども此事をよく理解するにあらざれば、東坡の煎茶の詩を了解出來ないと考へるからだ。唐以前の喫茶法は茶の葉を其まゝ煮て之を文字通りに喫食したものだ。即ち單に其煮汁を飮む計りでなく同時に煮た葉も之を食べたものであつた、恰かも野菜などを煮て食べると同じであつたとたしか茶經の序にも書いてあつたと覺えて居る。勿論之には鹽とか薑とか云ふ調味料を加へたものである。此風が宋に至りても北方に殘つて居て盛んに調味料を
用ひたことは前述蘇子由の詩にも「鹽酪椒薑誇滿口」とある通りだ。然るに陸羽の茶經頃になると喫茶の方法が變化して來た。然らば其方法は如何と云ふに勢製茶法から述べねばならぬ。製茶の法は先づ(一)茶の葉芽を採取したら之を蒸すのである、(二)適度に蒸せたら之を白に入れて搗くのである、(三)適度に搗けたら其硬泥狀の塊を鐵又は木製の型にて長方形又は花形に拔くのである、其大さは宣和北苑貢茶錄によれば大凡二寸內外より三寸內外であつた。(四)斯くして出來た長方形又は花形のものは簀などに並べてよく乾し上げるのである、(五)大凡乾せたら其中央に尖りたる錐刀で丸く穴をあけ之に竹の棒の樣なものを通して吊し更によく乾かしたる上之を焙じて貯藏するのである。茶を喫せんとする場合には右の貯藏せるものを取りて(一)先づ之を烈火に翳して炙るのである、之に用ゆる鐵製の火ばし又は「ピンセツト」樣の器具があつた樣だ、(二)適度に炙れると膨脹して蝦蟇狀を爲す、そこで紙の袋に之を容れて口を密閉して置く、之を煎るには紙の袋から取り出して藥〓を以て粉末狀と爲すのであるが、之に用ゆる藥〓は唐代に於ては大抵木製であつて、柑橘類の如き木を適當とした樣である、宋代になると鐵製又は銀製などを用ゐたと云ふことだ。而して粉末は唐代に於ては餘り細かくせざるを可とし細米粒狀と爲すとあるから米粒か、もう少し細かい位の粗粒と爲した、然るに宋代になると大體今日の沫茶の如く細かき粉末と爲した樣だ。古法では之を第二沸の湯中に投ずる譯だ。以上は極めて大略であるが今坐右に參考書が無いから詳き考證は之を省略するが右は曾で茶經以下大觀茶論茶譜、茶錄等々の諸書にて讀みたる處を綜合して述べたのであつて大體間違は無い積りである。東坡の時代頃は支那は上下共に茶に凝り固まつて居て、上等の茶を手に入れるのに非常に苦心したもので、從つて優等の茶は到底今日想像も及ばぬ高價のものであつた。而かも斯る優等品は勢、產額も產地も極めて局限せられて居たものであるから、悉皆貴顯、高位の人にさらわれて、普通の人はイクラ金を積んでも手に入らなかつた。今其最も極端なる一例を擧げると。歸田錄に曰く、慶曆中蔡君謨爲福建路轉運使始造小片龍茶以進其品絕精謂之小團凡二十餅重一斤其價値金二兩然金可有而茶不可得每因南郊致齋中書樞密院各賜一餅四人分之宮人往々縷金花其上蓋其貴重如此
今此記事によりて此茶の貴重なる程度を正確に認識せんとするには勿論北宋の中頃に於ける金一兩は現時例へば日本の何匁に當るか、其一斤は今の何匁になるか等を〓究した上で更に當時代の物價、例へば米價と云ふ樣な重要なる生活必要品の價を確かめた上で、是等を綜合して比較考量して見ねば判明せぬ譯である。然し之は余の未だ考究せぬ處であるから博雅の君子の示〓を俟つこととし、此處には只だ極めて貴重であつたこと丈けは確かであつたと云ふに止めて置く。歸田錄の右の記事は灑水燕談錄には次の如く出て居る。蔡君謨の獻上する此茶(所謂上品龍茶とある)は仁宗皇帝が尤も珍惜する所であつて宰相と雖も未だ嘗て容易に賜はらなかつた。惟だ郊禮致齋の夕に、(兩府即ち中書と樞密と)各々共に一餅を賜はつた、(合計二餅だ)。宮人が金を剪りて龍鳳の模樣を爲くり其上に貼付し、八人が(兩府四人づつ併せて八人だ)之を分けて蓄へ、以て奇玩と爲し、敢て自ら試みず。佳客あれば出して傳玩となす。歐陽文忠公云ふ、茶は物の至精と爲す而して小團は又た其精なる者也とある。文潞公は張妃の紅瓷の項にも述べた通り五十年間に亙りて高位高官に居り人臣の榮を極めた人であるし、定めて上等の茶を用ひ、且上等の器具を用ひて之を喫用したものであろう。而して此人啻に權勢の人である計りでなく、能く洗鍊せられたる高き趣味の人であつたと思はれることは前にも述べた通り、古法によつて茶を煎じたと云ふこと、及蘇子由に揀芽を贈つたのを子由が其舅に分與した時の詩等によつて略之を推察出來る。之を當時の權臣韓琦であつたと思ふ(今坐右に參考書が無いから確かなことは判らない)が蔡襄を訪れると蔡襄は何しろ當時赫々たる威望ある權臣の枉駕であるので非常な喜びで、最も祕藏する最上等の茶を出し饗應した。然るに韓琦は懷中から一服の散藥を取り出して、其茶で之をグツト飮んだ。之を見て居た蔡襄は茫然自失の體であつたと云ふ逸話と對比すべきである。(此逸話の人名は或は余の記憶の誤があるかも知れぬから豫め御斷りして置く)さて本問題の東坡の詩には次に定州花瓷琢紅玉とあるのだが、是は紅玉の樣に紅く美麗にして模樣のある瓷器を云ふたもので、次の玉盛云々の句から見ても無論茶〓であろう。即ち文潞公は茶を喫するのに定州紅瓷の〓即ち茶碗を用ひたものと解すべきだ。此句から後の部分の意味は要するに自分の樣な貧乏人で病み且飢えて居る者は到底、潞公の樣な立派な玉盌(即ち定窯紅瓷の盛を玉盛に譬へたのだ)を用ひたり又美人を蓄へて之をして茶を棒げしむるやうな結構な分限ではないが、それにも拘はらず尙ほ「ヱライ」方々
の眞似をして御茶を飮むが、然し其道具は塼爐石銚の樣な粗末極まるものを、何處でも持つて行つて用ゆると云ふのだ。此所に公家とあるのを一本に官舍のことだと注解してあるが、官舍では意味を爲さぬ。無論是は三公或は公卿と云ふやうな高位高官の「ヱライ」人達を指すもので、此處ては無論暗に潞公を指すのであろう。宋史職官志によれば、三師三公、宋は唐制を承けて太師太傅太保を以て三師と爲し、太尉司徒司空を三公と爲す、凡そ除授は則ち司徒より太保に遷り、太傅より太尉に遷る、太尉舊と三師の下に在り、唐より宋に至る重を加へ遂に太尉を以て太傅の上に置く云々とある。今之を順序に列べると次の如くなる。(1)太師(2)太尉(3)太傅(4)太保(5)太子太師(6)太子太傅(7)太子太保(8)司徒(9)太子少師一四四空(11)左僕射(12)太子少傅(13)右僕射(以下略)そこで若し宰相官僕射に至りて致仕する者其在位の久近を以て、或は司空司徒に任ずれば則ち太尉太傅等の官を拜す。太師の如きは則ち異數と爲す。趙普、開國の元勳を以てし何處でも持(5)太子太師一四四空てより、文彥博、累朝の者德を以て方に特に拜す焉。太傅王旦、司徒呂夷簡、各宰相に任ずること二十年なりと雖も、止だ太尉を以て致仕す云々とある。由是觀之、文彥博が如何に人臣の榮を極めたかゞ分る。尤も此人は長壽であつて紹聖四年(西紀一〇九七年)九十二歲で死んだとあるから、東坡の此詩を作りし凞寧五年は正に其死する前二十五年に當り其六十七歲の時だ。此前後には王安石が宰相として獨り政權を專らにし、文彥博等は直接政治には與つて居なかつた。然し彼は慶曆八年初めて宰相に任ぜられてから旣に此時二十四五年を經過して居るのであるから、其太師に任ぜられたのは尙ほ後のことかも知れないが、前記蘇轍の詩にある通り、所謂國老として其聲望今や赫々たるものがあつたと思ふ。此エライ潞國公が用ひ、東坡などの用ゆることを得ざりし定州の紅瓷である。博爐は瓦で出來て居る爐だ。石銚は石製の銚である。銚とは字書に燒器、釜之小而有柄有流者とあるから、茶を沸煎するに用ゆる急須、藥罐の類であろう。茶經にも鎮(即ち釜)は或は瓷製も石製もあり又銀や鐵にて造ると記してあるし、大觀茶論、煎錄等にも金銀又は瓷石にて作るとある。東坡の詩の終末の方にある撑膓拄腹、五千卷、但願一〓云々は前にある未識古人煎水意と照應して、此時王安石が試驗法を改正したことを嘲つたものだ
と云ふことだ、然し本問題に關係が無いから其說明は省く。補記煎茶の法に關しては蔡襄の茶錄、徽宗の大觀茶論によれば仁宗から徽宗頃にかけて既に今日の沫茶法が行はれて居たことは明かである。卽ち陸羽など唐代に行はれた如く茶の粉末を煮るのでなくて、一定量の茶末を茶碗の底に容れて之に熱湯を注ぐのである。而して蔡襄の茶錄によれば著者の時代卽ち仁宗頃には之を擊拂するに未だ茶筅を用ひず、成るべく重い金屬製の茶匙を用ひた。之が徽宗の大觀茶論になると茶筅を用ゆることが書いてある、卽ち今日の沫茶法と異らざる樣に變化したものである。而して此方法は點茶と稱して煎茶とは云はなかつた樣だ、本問題の試院煎茶は果して點茶であつたか煎茶であつたか分明でないが當時は恐らく煎茶から點茶に移る過渡時代であつたので潞公の煎茶は西蜀の古法によつたのだから煎茶であつたと思はれる、然し東坡が試院で行つたのは其詩題の如く果して煎茶であつたか又は點茶であつたかは疑問である。尙ほ本文中に記せる如く藥研にかけて粉末にせる團茶一個は一回に飮む分量ではなくて之を合子に入れて置き何回にも分用するのだ、爲念附記して置く。(三)〓波雜志に記せるもの周輝の著である〓波雜志に記せられてある定窯紅瓷に關する記事は從來諸書に散見するけれども、大抵省略して其一部分のみを揭ぐるものが多い樣だから、此所に同書中燒物に關する部分の全文を摘錄して置く。輝出疆時見燕中所用定器色瑩淨可愛近年所用乃宿泗近處所出非眞也饒州景德鎭陶器所自出於大觀間窯變色紅如朱砂謂榮惑躍度臨照而然物反常爲妖窯戶亟碎之時有玉牒防禦使仲機年八十餘居於饒得數種出以相似云比之定州紅瓷器色尤鮮明越上祕色器錢氏有國日供奉之物不得臣下用故日祕色又甞見北客言耀州黃浦鎭燒瓷名耀器白者爲上河朔用以分茶出窯一有破碎卽棄於河一夕化爲泥又汝窯宮中禁燒內有瑪瑙末爲油唯供御揀退方許出賣近尤難得(以上知不足齋本による)右の內定窯紅瓷に關する部分は率爾として之を讀めば極めて簡單明瞭であつて、別に考究の必要も無きが如くであるが、少しく仔細に點檢すると種々の問題が起つてくるであらう。先づ第一に仲機と云ふ人物は如何なる素性、經歷の人であるか。次に玉牒防禦使とは如何なる官職であるか。大觀年間景德鎭妖變とは何事であるか等々是等の內には調べて判ることもあれば、判らぬものもある。後者に至りては更に他日の考究に讓るか、然らざれば博雅の君子の示〓に俟つ外に致方なきは勿論である。先づ第一に仲機と云ふ者は如何なる人であるかと云ふに、餘り大した人物でも無いと見餘り大した人物でも無いと見
えて其經歷等少しも分らない。次に玉牒防禦使と云ふ官職は何であるかと云ふに、玉牒とは元來古封禪之文で玉牒を用ひて書し、之を方石の內に藏した。史記封禪書に「封廣丈二尺、高九尺、其下則有玉牒書」とあるのが夫れだ。又唐開元十三年に泰山に事ふることがあつて、玄宗皇帝が前世如何なる理由で玉牒を祕したかと問ふたら、賀知章が玉牒は意を天に通ずるのであるから、微密を尙ぶと答へた。帝曰く朕今民の爲に福を祈るのである、一も祕密に請ふものは無いと、乃ち玉牒を出して以て百僚に示したとある。然し玉牒の意味は獨り如上に止まらず、殊に宋以後は皇室の系譜を指して玉牒と云ふたらしい。宋史本紀大中祥符六年の條に宗正寺に詔して帝藉を以て玉牒を爲くるとあり、又九年には修玉牒の官を置いたとある。尙ほ宋朝の玉牒は一朝の大政事、大號令、大更革、大拜罷等は皆之を載せたものであつて、其體裁は世系と朝政と相對して錄記せられてあつたと云ふことだ。されば宋朝の玉牒なるものは明〓代の玉牒が專ら宗室の世系のみに詳かなるものと異つて居たものだ。又北宋時代には淳化六年始めて局を設けて官を置き詔して皇宋の玉牒を以て名と爲し、玉牒殿を建つとある。其後種々の變遷があつたが、南渡の後は紹興十二年に始めて玉牒所を建つとある。(職官志による)尙ほ玉牒と云ふものは何か、玉石に刻せるものの如く或は誤解せられるかも知らぬが其實は紙に書せるものであつて、決して玉や石では無い。只其紙は金模樣を附せる白羅紙と云ふ樣な上等の紙を用ひ其取扱は叮重を極めたことは勿論であつて、此事は宋の曾鞏の聞見近錄に詳記してある。それによると國書の嚴奉せらるること未だ玉牒の如き者はあらず。祖宗以來金花白羅紙、金花紅羅標、黃金の軸を用ゆ。神宗の時、詔して黄金の梵策を爲くる、軸大にして披閱し難きを以て也。予神宗に玉牒を進むるとき始めて此制を用ゆ。又黃金を以て匣を爲くる、鎻鑰皆黃金也、進め畢りて太廟の南、宗正寺玉牒殿に奉安す。予初め執政官に白して寺書を修せんことを乞ふ。司馬丞相、呂丞相よりして下、一人も此典制を知る者なし。皆曰く玉牒は玉簡を用ひて刊刻して册の如き者也と、其玉牒の典制をだに尙ほ悉く知らず、書の廢せらるる亦た宜なり矣とある。(尙ほ玉牒の沿革等同書、宋洪邁の隨筆、宋羅大經の鶴林玉露等參照)。防禦使の官は武官であつて唐代に初めて之を置き、其位は團練使の下に在り、大凡大郡要害之地は則ち之を置き以て軍事を治す、刺史之を兼ね、代宗位に即き諸州の防禦使は皆停めて刺史をして團練を兼ねしめた。然し宋代の防禦使なるものは虚街であつたとのこと
だ。即ち實職を有せざりしもので、云はゞ名譽職であつた。さて次に「時に玉牒防禦使仲機なるもの有り、年八十餘、饒に居りて數種を得たり」とある意味であるが、之は一寸考へると「此の時、即ち景德鎭窯に妖變のあつた時に仲機なるものがあつたが其年八十餘であつて饒州に居て數種を得た」と云ふ風に讀んで妖變のあつた時に仲機は旣に八十餘歲の高齡であり、而して恰かも饒に居たかの樣に見える。然し斯くの如く解するときは頗る不合理なこととなる。其譯は大觀年間(大觀の末年は四年で西紀一一一〇)から此書の著はされた紹熙三年·(西紀一一九二)までは八十二年ある、而して大觀の末に旣に八十餘歲ならば此の書の出來た紹熙三年には百六十餘歳となる、假に紹興の初(西紀一一三一年)に此事を〓波雜志の筆者周輝に語つたとしても尙ほ且つ百餘歲となる。而して假に紹興の初に周輝が二十歲とすれば此書を著はした紹熙三年は八十一歲の高齡となる。二十歲內外の若年で百歲以上の老翁から此話を聞いて夫を數十年の後に書いたとは普通では到底受取れない。加之周輝の生歿年は判然しないが「年八十餘」と書いたのは畢竟仲機が高齢者であることを表示した所以であつて他意なき譯だ。されば若し百歲にもなつて周輝に此事を語つたならば當然百歲の老翁であることを書かねばならぬと思ふ。そこで常理から判斷して此八十餘とあるのは周輝が此話を聞いた時又は此一條を書いた時の仲機の年齡であると見ねばなるまい。即ち此一條は筆者周輝の頭で混線して居た爲に斯る記述をしたのであらう。大觀年間景德鎭窯の窯變のことは支那古陶瓷〓究上の一大問題であつて、今日其眞相を說明するに足る資料が無い。或は有つても未だ誰も氣がつかぬのかも知れない。兎に角色紅如朱砂と云ふのであるから頗る美麗なる紅色又は赤色を呈して居たものであらう。次に「出以相似云」と云ふものは其取つて置いた紅色窯變の景德鎭の燒物を出して周輝に示して、さて之を比較形容して云ふのに云々と云ふ意味だ。以下、「比之定州紅瓷器色尤鮮明」とあるのは仲機の言を其まゝ記述したのであつて、文理上周輝自身の意見ではあり得ない。此一事は本問題の記事中最も注意せねばならぬことだと思ふ。さて定窯紅瓷に關する周輝の記述は右にて盡きて居る。即ち彼は仲機の言を其まゝ錄して居るのみであつて、之につきて自己の意見は一言も述べて居ない。此事實は畢竟何事を指示するものであらうか?管見によれば周輝は定窯紅瓷を見たことが無かつたことを最も雄辯に語つて居るものと考へる。周輝にして若し定窯紅瓷を見たことがあるならば、必ず
や此機會に於て、何とか一言附記せねばならぬと思ふ。例へば右の仲機の言を記せる後に「予視之眞然」とか「眞如其所言」とか書かれねばならぬ。殊に前にも摘錄せるが如く周煇は獨り定窯紅瓷のみならず、定窯白瓷、越州祕色器、耀窯、汝窯等に關しても記述して居り、陶瓷器に關して相當關心を有して居るのであるから、若し定窯紅瓷を一見する機會ありしならば、假令夫れが仲機の言を聞きたる後であつても何とか附記せらるべきは當然であらねばならぬ。此點につきては〓波雜志の記事は仁宗の仁君的政治を歎美するに當り偶然張貴妃の紅瓷に記及せる郡氏聞見錄、及び文潞公の古法による煎茶法を謳歌するに托して王安石の新試驗法を嘲り、之が爲に偶々潞公の紅瓷に叙及せる東坡の煎茶歌とは大に其趣を異にせるものであることを知らねばならぬ。右の如く周輝は此紅瓷に關する記事を書くまでは定窯紅瓷を觸目する機會を有せざりしものであるならば、次に起る問題は、然らば周輝は果して何時頃、換言すれば、大凡何年位の時に此記事を書いたかと云ふことである。四庫提要によれば〓波爲杭州城門之名紹興中輝寓其地因以名書とある。之で見ると恰かも紹興中に彼が杭州〓波門の傍に住居して居た頃に此書を書いた故に〓波雜志と名付けたかの如く思はれるが、之は果してどうであらうか? (因に右は初坐右にある上海出版の安本によつたが、爲念、東洋文庫所藏の殿版を借覽して之を確めた處、矢張り紹興中とあつた)然るに此〓波雜志の初に著者周輝の自序及友人の張貴謨の序がある。自序には「輝早侍先生長者與聆前言往行有可傳者歲晩遺忘十不二三暇日因筆之非曰著述長夏無所用心賢於博弈云爾時居都下〓波門目爲〓波雜志紹熙壬子六月淮海周輝識」張貴謨の序には「余故人周昭禮嗜學攻於文當世名公卿多折節下之余與昭禮定交今不翅二十年矣每一別再見喜其論議益該治文益工今老矣而志益壯云々今寓中都〓波門之南故因以名其集云紹熈癸丑春古括張貴謨序」とある。右の二序を見ると此書の成りしは紹熈年間であつて當時周輝は〓波門の傍に住んで居たことは明かである。而して書中には事實紹興以後の淳熈から紹熈に至る記事が散見して居るから、四庫提要が紹興中云々と云ふは紹熈中の誤であることは明白である。(紹興と紹熈では三十年も違ふから特記した次第である)。之と同時に右の二序によりて此書は周輝が晩年に至りて始めて執筆せるものであつて、隨筆の體裁ではあるけれども決して若い時、中年の時に書いたものが晩年の記述と混淆しては居ないと見て差支無い樣だ。即ち本問題の爲念、東洋文庫所藏の殿版を借覽して之を確めた處、矢
定窯紅瓷に關する記述も亦た紹熈頃周輝の晩年に至りて書かれたるものであつて、從つて彼は晩年に至るも定窯紅瓷を觸目する機會なかりしものと看做すことが出來ると思ふ。以上で定窯紅瓷に關する〓波雜志の記事につきての考究は一應完了せる譯だ。然し此書に關する四庫提要の所說には不可解の點が少くないから、左に開陳して博雅の君子の示〓を仰ぐ。四庫提要には此書の撰者周輝は邦彥の子だとある。周邦彥と云ふのは北宋末期の人で官吏としては知州位で終つたが、性來音樂の天才であつて北宋詞家の大宗と稱せられ其方面では仲々有名な人である。其傳は宋史卷四百四十四、列傳第二百三、文苑六の內に出て居る。之によると彼は字を美成と云ひ、錢塘の人であつて元豊の初京師に游び汴都の賦萬餘言を爲くり之を献じたのを初として終には順昌府の知事となり、處州に徒つて卒した、年六十六、宣奉大夫を贈くる云々とある。彼は何と云ふ年號の何年に生れて、何と云ふ年號の何年に卒したか、宋史の列傳では不明だ。然し元豊の初都に上りて萬餘言の賦を献じたとあるからには此時既に相當の年配に達して居たと見るのが至當では無からうか。殊に傳には其前に博く百家の書に渉るとある位である。然し大まけにまけて、元豊の初(元年は西紀一〇七八年に當る)に彼は二十歲で能く萬餘言の賦を爲り得たと假定しても其六十六歲で卒したのは西紀一一二四年即ち徽宗の宣和六年で無ければならぬ。然し事實二十歲で萬餘言の賦を爲くることも、況んや其以前に博く百家の書を涉獵することも普通では出來ないことであるから、六十六歲で死んだのは恐らく尙ほ數年前に溯るのでは無からうか。而して宣和の末に子の周輝が十歲と假定すれば其〓波雜志を書いた紹熈壬子即ち三年(西紀一一九二年)には七十七歲位となり、晩年の著と云ふことに符合して丁度工合が良い譯である。然るに一度〓波雜志の內容を見るときは、右四庫提要の所說を否定せざるを得ざる記述が.此所彼處に散見するのは何故であらうか?今其數例を擧げやう。本書卷三に「紹興丁已歲」(丁已は七年だ)車駕巡幸建康回蹕時先人主丹徒簿排辦新豊鎭頓物皆備御舟過止宣索生菜兩籃非所辦者官吏倉卒供進幸免關事前頓傳報生菜遂爲珍品物有時而貴世事奚不然又同書卷十にも紹興初先人爲丹徒簿云々とあるから、紹興一-七八年頃周輝の父は達者で丹徒の簿を勤めて居たことは明かである。而して前記宋史列傳にある通り六十六歲で
死んだと云ふことが事實とすれば紹興七年(西紀一一三七年)に六十六歳即ち其生れたのは西紀一〇七一年熈寧四年となり.元豊元年には漸く滿七歲だ。之れでは到底百家之書に渉り、遙々浙江省の錢塘から河南開封府の都へ上りて萬餘言の賦を爲くりて之を上ることは思ひもよらぬことだ。況んや同書卷九を見ると更に左の如き重要なる記事がある。煇自四十以後凡有行役雖數日程道路倥德之際亦有日記以先人晩苦重聽如幹蠱次叙旅泊淹速親舊安否書之特詳用代縷々之問記向年貨田句金不遂取塗三茅得新刊山圖而歸濡滯良久殊失倚門之望因思昔淵才久出其家日望其歸々止携一布囊人謂其間必珍貨也後數日會親戚啓囊乃歐陽公新修五代史稾數秩李廷珪墨一笏而己煇用此書於日記後先人爲之一笑自隆興癸未至紹熈辛亥恰一世伏書泫然右で見ると周輝の父の死んだのは隆興癸未(即ち元年西紀一一六三年)に相違無い樣だ。此時六十六歲なれば其生れたのは西紀一〇九七年即ち紹聖四年であつて、萬餘言の賦を献じた元豊の初から約二十年も後になる。言ふまでもなく不合理だ。不審は右に止まらない、同書卷六には曾祖侍紹聖經筵至政和五年以右文殿修撰知桂州云々とありて當時の權官蔡京の意に忤つて落職したことが書いてある。曾祖父が紹聖、政和の間に汴都に於て官吏として相當の地を占めて居たと云ふのに前記宋史列傳中周邦彥の傳には毫も之を記して居ないのも奇怪であるし(若し邦彥が輝の父なれば祖父に當る譯だ)、第一紹聖よりも更に十五六年も前(政和よりは卅三四年も前)に故〓から孫の邦彥が既に汴都に出でゝ萬餘言の賦を献じたと云ふのは如何にも時代が符合しない樣に思ふ。右等の次第で余は周輝が周邦彥の子だと云ふのは怪しいと思ふ。然し別に此時代同じ錢塘からの出身者に同名異人があるならば格別だ。因に鄭堂讀書記なども四庫提要の說其ままに邦彥の子なりと記して一言も疑を挿まない。(周邦彥が錢塘出身者なるは前にも記した通りで、輝も亦た錢塘出身なることは自記して居る)只だ四庫提要によれば是書之末有張斯中張訴陳晦楊寅張巖翼頤正徐似道等七跋皆同時人云々とある、是等の諸跋を見るを得ば或は邦彥の子と云ふ樣なことが書いてあるかも知れないが、余の見たる知不足齋本には是等の跋は殘念ながら之を缺いて居るし、四庫の原本である處の內府藏本は之を見ること能はざるは勿論、即今四庫さえも窺ふの便宜なきを以て止むを得ない。
尙ほ又、四庫提要には「又白稱甞至金國益不可解或隨出使者行也」とあるが、此記事の如きはこれこそ不可解であると云はねばならぬ。周輝が金國に至りたることは所謂別錄又は北轅錄の著がありて其〓末を詳述して居る。即ち此書によれば、周輝は詔待制敷文閣張子正假試戶部尙書の金國の生辰を賀する使節に任命せられたるに其隨行員の內に加はりて都門を辭して旅程に上りたるは淳熈丁酉四年正月七日であつて、金國に至り無事使命を果して歸國し、其家に還りたるは同年四月十六日で、是行程往返凡九十六日と明記して居る。而して此記事は〓波雜志の卷三に淳熈丙申從使節出疆回轅當三月中下旬とあるに符合するし、(因に北轅錄によれば都門を辭したのは前記の如く淳熈丁酉正月七日だが命を受けたのは前年即ち丙申十一月廿九日とある)同所に絕江渡淮過河越白溝風聲氣俗頓異寒瞑云々と云ふのも、卷五に使金國者冬月耳白即凍墮云々と凍傷の注意を述べ、輝出彊時以二月旦過淮云々と記せるも皆此旅行の一端を記したものである。之をしも益々不可解と云ふは四庫提要其ものの鼎の輕重を問はねばならぬ譯だ。此記事の(四〓蔣祈の陶略に見ゆるもの景德鎭陶錄卷六、鎭仿古窯の內、定窯の項に左の通り記してある。蔣記云景德鎭陶器有饒玉之稱視眞定紅瓷足相競則定器又有紅者云々藤江氏の譯本を見ると左の通り之を讀んで居る。蔣記ニ云ヘリ景德鎭ノ陶器ニ饒玉ノ稱アリ眞定ノ紅瓷ヲ視ルニ相競フニ足レバ則チ定器ニ又タ紅ノモノアルナリ云々右の如く訓讀しては原文の意味がよく分らぬと思ふ。云ふまでもなく「足相競」までが蔣記の原文であつて、「則定器」以下は陶錄著者の意見である。從つて「相競フニ足ルト」にて一旦句讀を切りて「則チ定器云々」と別に書き出さねば意味を爲さぬ。此に問題となるは視の字である。藤江氏は單に「視ルニ」と譯した。而して假名がついて居ないから何と讀ませるのか明確には斷言出來ないけれども、恐らく「見ルニ」と讀ますのであらうが然し斯く讀んでは十分に意味が徹底せぬと思ふ。勿論此場合蔣記の筆者即ち蔣祈なる者が定窯紅瓷の實物を實見したとの推定は此「視」と云ふ一字からは出て來ない。其次第は更に後段に述べん。順序として先づ考ふべきことは、右陶錄の記事は何に基きたるものなりやと云ふことで
ある。蓋し蔣祈の陶略なるものは恐らく初め浮梁縣志に輯錄せられたものであつて、其後に饒州府志に、更に近代に至りて江西通志等にも轉載せられたものであらう。而して「ブツシエル」氏は浮梁縣志に之を輯錄せるは臧廷鳳の編纂せる元志(至治二年編纂、元泰二年刊行)に始まると云ふも、「ペリオ」氏は恐らく明初の改版に初めて輯錄せられしものならんと云ふ。何れにせよ其後の縣志は改版每に其まゝ之を轉載し來りて〓代に逮びたるものなることは略ぼ明瞭の樣だ。〓Bnshcll:Oriental Ceramic Art. Section 30 pp, 99ー102. Paul Pelliot: Notes 117 l'histoire de EI C〓ramique chinoise. pp·39-40)蔣祈の陶略、詳しく云へば陶記略の內容は要するに當時(元代)景德鎭に於ける窯業の實情につき當業者の困苦を當局に訴へて施政の改善を請願せるものであつて元代窯業に關する資料極めて乏しき事實に省るときは相當重要なる資料であり且又興味深きものであることは言を俟たぬ。故に例の「ペール、ダントルコル」が康熈五十一年旣に浮梁縣志によりて之を讀みたるを初めとし其後西洋磁學家の注意を引き、遂に「ブツシエル」氏によりて殆んど其全譯を見るに至つた。浮梁縣志は道光頃の〓版があるにも拘はらす何故か稀少であると見へ予は未だ之を見るchinoise.ことを得ない。然し江西通志に轉載するところは恐らく之と全く同一であると思ふ。江西通志によると、本問題の定州紅瓷の部分は景德鎭陶錄に記述する處とは多少其趣を異にして左の如くである。(元蔣祈陶記略云)景德鎭陶昔三百餘座埏埴之器潔白不疵故鬻於他所皆有饒玉之稱其視眞定紅瓷龍泉靑祕相競奇矣云々而して右以下は前述せる如く景德鎭窯業の實情につき縷々訴ふる所あるのみであつて一言半句も定州紅瓷と相干與することなし。されば蔣祈は單に景德鎭の陶磁器につきて其美を誇示せんが爲に有名なる定州の紅瓷と龍泉の靑瓷とを引き來りしものに過ぎぬ。故に此一條から吾人が學び得る所は只だ定窯紅瓷が珍貴なる品として元代に於ても有名であつたと云ふ一事あるのみである。勿論之のみでは蔣祈が之を見たとも見ぬとも云へぬし、又龍泉の靑瓷は當時多く產出して居たとの理由を以て直ちに定州紅瓷も多く產出して居たとは云ふこと能はざる次第である。此に一言の要あるは前段に述べた「視」の字の解である。藤江氏譯の如く只「視ル」と譯すことは出來ないと思ふ。字書を見ると、「視」には大凡十種許りの意義がある。即ち瞻
察、示、看待、比、效〓納活、指等である。字書には一々例を擧げて說明してあるが今繁を厭ひて之を省略するけれども、其內で比と云ふ意義が即ち本問題の蔣祈の陶記にある「視」の意義だと考へるから此に其用例を擧示すると康凞字典には左の通り出て居る。〔左傳襄公二十七年〕季武子使謂叔孫以公命日視邾膝。注曰欲比小國。又辭源には同じ例を擧げて謂與之相比例也とある。井々博士の左氏會箋には「ナゾラヘヨ」と振假名がつけてある。勿論右の文例は命令法であるから若し普通の直說法ならば「ナゾラヘル」、「比スル」、「比例スル」、「比較スル」、である。即ち此場合には眞定の紅瓷、龍泉の靑瓷に比ぶるに奇を相競ふとの意味である。「ブツシエル」氏は之をCompareと譯して居るのは正しいと思ふ。尙ほ比較の意義に用ひてある視の字の用例を手近にある天工開物から左に擧出して置く刀磚之直視導磚稍溢一分。若煤炭窯視柴窯深欲倍之。(天工開物中卷陶埏第七卷より)尙ほ九五頁哥窯の末尾に引てある董其昌の文の内にも其例がある。是等の用例は比較の意義であつて「見る」とは違ふ。見たと云ふ事實を證することにはならぬ。要するに元代の蔣祈が定窯紅瓷を以上定窯紅瓷に關する旣知の文献四種につき〓究の大要を述べた。勿論此〓究は單に余の「ベスト」を盡したと云ふに止まるものであるから將來補正せらるべきものは或は尠なからざるべしと雖も、然し以上〓究の結果を綜合して二三の所見を此に開陳するは徒爾であるまいと思ふ。先づ第一に云ふべきは定州に於て北宋の中頃から末頃にかけて一種の紅瓷を產出したことは確かな事實であると見て差支あるまい。彼の烏有說の如きは採るに足らざる迂說であることは以上諸文献の解釋考察によりて明白である。然らば定窯紅瓷は果して如何なるものであつたかと云ふに此問題の解答は實物の破片一つさへ容易に發見すること能はざるが故に極めて困難である。屢說せる如く北宋當時旣に珍貴で王侯貴人の愛玩に供せられたものが今日容易に觸目の機會なきは寧ろ當然である。故に將來文潞公乃至北宋の王侯貴族等の墓からでも出土せざる限りは、先づ見ることを得
まい。右の如く定窯紅瓷は北宋時代極めて珍貴のものであつたが、何故に即ち如何なる理由で斯く珍貴であつたかと云ふことを次に考へて見ねばならぬ。先づ第一に張貴妃の紅瓷の場合を取つて見る。此場合には張貴妃が王拱辰から貰つた紅瓷は珍貴であつても此事實を以て直ちに定窯紅瓷なるものが悉く高價珍稀であつたと云ふ結論にならぬことは勿論である。例へば燈籠錦の場合でも分ることであるが、蜀は錦の產地として有名であるから、錦其ものは決して左まで珍貴ではあるまい。勿論品質に上中下種々あつて上等品は相田高價であつたらうが中下に至りては左まででもあるまい。文彥博が張貴妃に献上した燈籠錦は金を間へて織つたもので、只に材料が高價であるのみならず恐らく其織法の技巧に於ても特別飛切り上等のものでありしならん。之と同じ樣に定窯紅瓷其ものも左まで珍貴で無かつたかも知れぬ。少くとも邵氏聞見にある張貴妃の紅瓷に關する記事丈けでは當然解釋としては定窯紅瓷は悉く珍貴でありしとの結論は出て來ない。果して然らば張貴妃の紅瓷は何故に珍貴なりしやと云ふに陶瓷の性質として原料其ものに金銀珠玉を使用すると云ふ樣な場合は一寸考へられない。汝窯の場合に瑪瑙を釉とする何故に即ち如何なる理由でと云ふ樣な記述が古書にあるけれども、之は言ふまでもなく釉色が靑瑪瑙に似て居るから斯る妄說を生じたのであることは絮說の必要はあるまい。從つて張貴妃の紅瓷が珍貴なりし理由は別に之を求めぬばならぬ。先づ考へられ得べきことは陶瓷器其ものの價にあらずして之に附屬せる裝飾の爲に珍貴であると云ふことだ。例へば今日見る定窯の鉢皿の口緣に銅鑛即ち俗に云ふ覆輪が施してある。あの覆輪を金又は銀にて造り、而して之に花鳥、唐草其他精巧なる細工を施せる如き場合である。十六七乃至十八世紀頃に支那から西洋に渡りたる陶瓷器(多くは染付と赤繪である)が彼地に於て大に珍重せられ其時代西洋に於ける金銀細工の名工によりて之に精巧なる細工を施せる金銀の覆輪、臺蓋把手等を附けて珍藏せられた。其今日に殘存せるものが多々ありて特に此種のものを〓究せる著書もあることは人の知る處である。宋代に於ても銅鑲を施せる原品が今日旣に殘つて居るし、銅の代りに金銀を以てせるものも間々見受ける。尤も金銀の如きは剝ぎ取られ易きもの故今日存在する覆輪が必しも古いものだとは云へない、恐らく後世に品物を珍重するの餘り之に金又は銀の覆輪を施せるものなどの方が多いであらう。然し乍ら之を要するに五代乃至宋代に於て金銀を以て覆輪
は勿論其他の部分に精巧なる裝飾を施せるものが無かりしと斷言することは出來ない。否飜て文獻を檢ねれば帝王とか貴顯とか云ふ方々の使用せるものは恐らく大抵金銀を以て精巧なる裝飾を施せること恰かも前記十何世紀頃に西洋に於て支那產の陶瓷器を珍重せると同樣のものありしに似たり。今此種の文獻を二三錄出して置く。其一は陶說卷二、吳越祕色窯の條に引用せる王蜀報朱梁信物有金稜碗致語云金稜含寳碗之光祕色抱靑瓷之響とある金稜碗と云ふのがそれであると思ふ。竹泉譯本の如く之を金陵と誤つては意味が全然分らなくなる。金陵は云ふまでもなく南京の異名である、南京に寳碗の光を含むと云ふては意味を爲さぬと思ふ。其二は楓窓小牘に宋初吳越王錢俶が太宗皇帝に金銀飾の陶器十四萬餘點を献上した之が爲に遂に國初以來積むところ一に空しとある(尤も他に多數の珍品異寳を献上したのであつて陶瓷器は其一部分に過ぎない)其三は宋會要に記すところであつて宋初吳越王錢鏐、錢俶等が何回となく献上した物產珍品と云ふやうなものの內に金銀の裝飾を施せる陶瓷器のことが記述されてあつて前記楓窓小牘の記事を裏書して居る。(宋會要に見ゆる陶瓷器に關する記事につきては何れ其內稿を新にして書きたいと思ふ)。要するに當時帝王皇族乃至貴人の用に供せられた陶瓷器は右の如く金銀の裝飾を施せるものが少くなかりしは事實であらう。而して金銀の裝飾と云ふても今日吾人が銅の覆輪を見て想像するが如く單純なるもので無く恐らく相當に纎麗巧緻なるものありしことは漢代以後非常に發達して居た此方面の事例を一々此所に例示せずとも分明であると考へる。本問題の張貴妃の紅瓷の如きも恐らく精緻なる金銀の裝飾を施してあつたと見るのが至當であらう。果して然らば張貴妃の紅瓷は或は斯る附屬的の裝飾によりて異常に其價値を高められて居たと見る方が寧ろ至當であつて、瓷器其ものの價値は左まで大したもので無かりしものだとの論は之を立て得る餘地があることは認めねばなるまい。例へて云へば今日現存する相當作家の作つた燒物に金銀で精巧なる裝飾を施すが如き是れである。此點は邵氏聞見の記事のみでは必しも之を否定出來ないやうだ。然るに第二の東坡の試院煎茶詩にある文潞公の紅瓷になると頗る趣を異にして居る。即ち此場合には(一)紅瓷其ものを以て紅玉とか玉盛とか形容讃美して居る計りでなく、(二)到底東坡の如き貧乏役人の手の及ばざるものであると爲して居る。若し文潞公の紅瓷が金
銀の裝飾を施せるが爲に貴重でありしならば詩中に毫も其事實に敍及せずして單に瓷質のみを紅玉とか玉盛とか讃美する理なく、又金銀飾を爲さざる紅瓷を得來りて之を使用すれば可である、何を苦しんで甎爐石銚の如き粗品を用ひんやである。此所に茶碗は何を用ひたか詩中には記して無いが之は〓爐石銚に相當する如き粗品を茶〓に使用せることを言外に含ませたもので敍事の精確を主とする散文と違ひ詩であるから致方あるまい。又潞公の紅瓷に對して自分の〓爐石銚を提出して對照せしめたのであるから東坡にして假令安物にせよ紅瓷を用ひ得たならば此詩の妙味は半減すると思ふ、否右の如き事實があつたならば此詩は自から異つた風に作られねばならぬと思ふ。換言すれば東坡の此詩から判斷すれば定窯紅瓷が貴重なりしは決して之に附屬せる金銀飾の爲めではなく瓷器其ものが貴重であつたのであり、又定窯紅瓷には蜀錦の如く上中下種々の品質があつたのでは無くして唯一種の瓷器があつて夫れが悉皆貴重珍稀であつたことが略判斷がつくかと思ふ。此に繰返して注意すべきは東坡の此詩は熈寧五年(西紀一〇七二年)の作であるから、曾て述べた張貴妃に王拱辰が紅瓷を獻上した皇祐二三年頃(西紀一〇五〇年頃)から約廿一二年後であつて此頃には珍貴なる定窯紅瓷は確かに世の中に存在して居たのだ。次に〓波雜志に記述せられある定窯紅瓷は屢說せる如く著者周輝は相當陶瓷器に關して心を留め且七八十歲位まで長壽でありしにも拘はらず晩年に至るまで遂に之を實見する機會なかりしものと推定せられるから、定窯紅瓷は著者周輝の生榮した南宋初期には旣に殆んど世上に其跡を絕つたと云ふべきである。第四の蔣祈の陶記略に至りては只景德鎭瓷器の聲價を誇示せんが爲に定州の紅瓷を引き來りしに過ぎぬから、資料としての價値に乏しきは止むを得ざる處である。定窯紅瓷が當時宋の上流社會に異常なる愛顧を有したのは前陳の如く金銀裝飾の如き附加的の價値の爲めにあらずして、それ自身の價値の爲めであるならば何が斯くまで定窯紅瓷に愛着を感ぜしめたかと云ふに云ふまでもなく其紅色であらう。從來有名なる陶瓷器と云へば必ず白か靑かの系統に限られて居た。定窯、越窯、祕色窯、柴窯、汝窯等唐五代以降有名なる窯は悉く白にあらざれば靑、靑にあらざれば白であつた。其所へ突如として紅色の瓷器が現はれたのであるから一部の人士の愛着を得たことは當然である。就中張貴妃の如き婦人が之を喜んだのは無理からぬことであらう。然し乍ら凡そ人間社會に於て物が貴重である爲めには必ず珍稀でなければならぬ。如何如何
に利用價値が大でも又美麗であつても多數に存在しては平凡視せらるることは古今東西同じことである。北宋時代には紅色の瓷器が珍稀でありしことが定窯紅瓷の價値を高めた事實は之を否定すること能はずと考ふ。〓波雜志に記せる大觀年間景德鎭に於ける妖變の如き工人の無智によるとは云へ偶々以て赤色紅色等の瓷器に彼等の目が如何に慣らされて居なかつたかを看取出來ると思ふ。又是等の事實を綜合すると彼の宋均窯と稱せられたる紅色乃至紫色の出て居る燒物が北宋時代の所產なりと云ふ說は甚だ根據に乏しきものであることが分る。(因に宋均窯なるものは夫れ自體に關する文獻から論じても頗る怪しきものである、此事は大谷師も旣に其一端を論ぜられて居て筆者は同師の所論に大賛成であるが、今本編の終結を急ぐを以て他日機會を得て更めて所見を述べ度いと思ふ)。次に必然問題となるは定窯紅瓷の紅色は何による呈色であらうか?と云ふことだ。何しろ破片さえ見付からないのであるから全然推量の外はないのであるが凡そ現代に於て陶磁器の釉藥なり加彩なりの原料にして普通赤色又は紅色を呈せしむるに用ひらるゝものは鐵銅金の三種又は其各の化合物であらう。此內で金による呈色の如きは恐らく比較的近代の發見にかゝるものであつて宋代の如き時代には萬々未だ用ひられたことはあるまいと思バートン氏によれば金より得らるる加彩の紅色はカーミン、ローズ、ピンク、クリムソン及紫にして是等は悉く支那に於ては十八世紀に於て現出せるものてあつて其基幹原料は一種の金化合物で其發見者Andrias Cassiusの名をとりてカシアスの紫と稱せられる。此物質に關する報〓は西紀一六八四年又は一六八五年に公けにせられたるを以て最初とす。其後間もなく此物は紅色「ガラス」の製造に使用せられ、次で磁器の上繪付けに使用せられたるが、此處法は次で歐洲より支那に傳はり(多分「ジエスウヰツト」宣〓師の傳へたるものならんと云ふ)十八世紀に於て支那磁器加彩の主調を爲すに至れりと云ふ。以上は勿論近代に於ける此處法發見及傳播の由來であるが、夫れより數百年も以前に支那に於て此法が行はれたとは先づ考へられ得ないことであらう。そこで北宋時代定窯紅瓷に用ひられたる紅色の原料は酸化鐵であつたか、銅であつたかと云ふ問題になるのだが、これは仲々確然と解決することは六ケしいと思ふ。將來何かの機會によりて此問題に解決の鍵を授くることが必ず出てくるものと信ずるが今日吾人の有する知識の程度に於ては此問題に右か左かの斷案を下すことは未だ早過ぎるものと思ふ。以下何故に此の問題が斯く解決に難きかと云ふ理由を述べて置くのも決して徒爾ではある
まい。先づ初めに酸化鐵であるが此物は黄褐色から美麗なる赤紅色に至るまで種々樣々な赤色褐色系統の色を出すことは云ふまでもないことである。而かも原料が普偏的で至る所極めて容易に且安價に得られるから古くから用ひられ、彼の唐三彩の如きものにも頗る普通に用ひられて居る。然し是等初期のものは大低其色黃褐色であつて頗る美麗でない。處で問題は所謂宋の加彩と稱せらるるものに見る如き美麗なる赤紅色が發明せられたのは果して何時であらうかと云ふことである。是れ今日に於ては未だ確言すること難しと云はねばならぬ。一說によれば宋加彩は鉅鹿出土品中に之ありと云ふ。鉅鹿は人も知る如く北宋微宗皇帝の大觀年間に黄河の洪水の爲めに一夜の間に埋沒した地であつて近年に至り始めて一丈何尺も下から發掘せられたのであるから此所から出土するならば其北宋末前の所產たることは言を俟たない譯だ。(因に此地の丘上にある何とか云ふ寺に碑が立つて居て其碑文に大觀何年何月何日に黃河の洪水の爲に一夜の內に寺が埋沒したこと、依つて之を洪水の虞なき丘上に再建するに至りし因緣が書いてあつて、之から支那學者が其正確なる年月日を推知するを得た譯であるが今其論文が手元に無い。碑文には、たしか干支で出て居て而かも陰曆だから之を陽曆に推算してあつたと記憶する。尙ほ碑は寺の再建と同じで矢張り北宋時代の建立であつた)然しこれは所謂學術的の發掘で明白にされた事柄では無く只商賈の傳ふる所に過ぎないのであるから奈邊まで信用してよいのか實の處分らぬ。只近年支那から本邦に將來せられた宋加彩の盛の底に金の年號の書いてあるものがあつて(確か泰和何年とあつたと記憶する、又此種のものに關する奧田君の論文が國華に出て居たと記憶するが今坐右に無いから參照するを得ないのは殘念である)金即ち支那の南宋時代には確かに存在して居たものなることは議論の餘地は無いやうだ。そこで問題となるは此種の加彩が果して南宋時代、當時金に占有せられて居た北方の諸窯で發明或は創製せられたものであらうかと云ふことである。是等の加彩の盌は普通磁州窯の產と云はれて居るが、中には明白に他所の產と思はるるものもあるやうだ。然し乍ら何れにせよ殆んど大抵其北方の所產であることは略ぼ疑を容れる餘地なきが如し。果して然らば是等の地は當時旣に南宋の治を離れて居たるが故に其支配者であるところの金の文化によりて自然に創製せられたか又は北宋時代旣に存在したる技法が傳統的に金に於ても行はれて居たものであるかの二途を出ない譯だ。
筆者は未だ金の文化と云ふ問題を〓究したことが無いけれども當時臣視して居た南宋の風を學ぶ程度であつて別に取り立てゝ特異の秀拔なる文化を建設したとも思はれない。加之定窯の產地の如き金人の劫掠を免かれんが爲に陶工等が擧つて江南に移住したとの傳說があり、これ敢て獨り定窯のみに止まらず北地諸窯に共通の現象でありしなるべく軈て江南諸窯就中景德鎭窯業が元明以降頗る隆盛になつた重要原因の一とも云ふべき次第である北宋の滅亡と共に北地諸窯の運命は果してどうなつたか殆んど何事も知られて居ない現在に在りては何等的確なる議論を立つることを得ないけれども前記傳說と事態の推移とを併せて考ふるときは南宋時代に於ける北地諸窯の運命は少くとも著しき衰退を推察せざるを得ず、恐らく其大部分は殆んど知命的の打撃を蒙りたるにはあらざるか?此事につきては前記傳說の外に尙ほ南宋初期の著である〓波雜志に見出さるる當時定窯の場違ひ物の跋扈して眞正の定窯が稀少となりし記事をも參照せらるべきであろう。要するに斯る衰退否潰滅的運命に在りし南宋時代の北地諸窯に於て斯る洗鍊せられたる赤繪の技法が發明され創製されたとは考へられない。云ふまでもなく所謂赤繪と稱せらるる比較的鮮明なる赤紅色の上繪付けは其顏料の調製等には相當技術上の困難が伴ふものであつて今日出來合ひの繪の具を買求め來つて何でも拵へるのとは違ひ八百年の昔には一般の文化が發達して居ねば此種の發明は六ケしいと思ふ。彼の赤繪の發明?にて嘖々たる名聲を有する柿右衛門とか云ふ陶工に關する傳說の如きは夫れより更に五百年の後のことである。又他方宋加彩と稱する品物を仔細に檢査すると中には到底南宋即ち金の占有せる時代の產と思はれざるものも有り其作行乃至模樣から見て北宋時代に溯ると云ふを以て至當と認めらるる品も間々ある樣だ。以上の理由は何れも直截簡明では無いが然し大體上加彩而して其用ひてある鮮豔なる赤紅色が南宋時代の發明にあらずして北宋時代の絢爛華美の文化の創製なることを指示して居るのではあるまいか。若し果して然りとすれば我が定窯紅瓷なるものは或は加彩の先驅かも知れない。此位鮮麗な赤紅色ならば婦女子の愛着を引くに十分であろう。而して金の年號を有するものは其傳統を繼承するものであろう。飜て銅による赤紅呈色を考へる。此方は若し洋人等の唱ふる如く赤紅色の出て居る均窯なるものが北宋時代の所產であるならば、定窯にも亦た此種のもの之ありしと云ふて簡單に片付けることが出來る。然し前にも陳べた如く北宋代均窯(大谷師の唱ふる如く實は當
時均州釣州の名もないのだ)に斯る赤紅色のあるものが存在せりとは思はれない、且洋人等の說の基く所である明人の記述など果して奈邊まで信用出來るか餘りあてにならぬ。加之明人と雖も遵生八機などは決して宋代の均窯とは書いて居らないのだ。只均窯と書いて居るのであつて之を宋代と解するのは洋人の勝手であつて彼等は明人の記述其ものさへも決して正當に解して居ないのださて北宋代の均窯(實は汝窯の舊窯だと大谷師は云ふて居らるる樣であるが是れ實に卓見であると思ふ)に銅呈色の赤紅色が無い、或は極めて稀であるとすれば之を假りて定窯紅瓷を說明することは出來ない。然し乍ら銅呈色による赤紅色が定窯紅瓷の顏色であることは事理の上から見て相當の公算があるのでは無いかと思ふ。銅を釉藥中に容れて還元焰によりて之を燒き所謂釉裏紅なる鮮艶なる赤紅色を得る技術が巧妙に行はるゝには相當以上の困難を伴ふことは勿論であるが然し北宋代に於ては旣に支那の南北に亙りて還元焰を巧みに「コントロール」して空前絕後とも云ふべき立派な靑瓷を燒くことに成功して居るのである。即ち南方に於ては龍泉窯.北方に於ては舊新の汝窯が其代表的のものである。斯く宋代には銅による赤紅色を得る技術上の素地は旣に十二分に出來上つて居るのではあるまいか?若し假に何か偶然の機會に於て酸化銅の一片が靑瓷の釉に入る樣なことがあつてそれが器に掛けられて還元的に燒かれる樣なことがありとすれば紅色なり紫色なりを得ることは必ずしも絕無ではあるまい。之が酸化銅の仕業であることが分らねば妖變として恐れられるし、若し陶工が其由て來る所を覺れば祕傳ともなるのであろう。而して右に述ぶるが如く當時旣に十二分の素地が出來て居たならば誰か北宋時代定窯に斯る妖變が起らなかつたと斷言出來やう。旣に吾人は大觀年間景德鎭に於て一種の妖變が起つて全窯紅色となつたとの文獻を有して居る、而して此事實は同種の現象を以てするにあらざれば科學的には到底說明出來ないのだ。斯く考へ來れば定窯紅瓷が銅呈色の釉裏紅の一種であつたとの考も相當の公算ありと云はねばならぬ。(斯く云へば宋均窯の赤紅色の出て居るものも同理によりて北宋時代に之ありしならんとの論も出やうが、勿論絕無とは云へない、只假に之ありても極めて稀でありしならん。然るに今日宋均窯と稱するものを見るに何れも多少とも赤紅又は紫色の出て居ないものは殆んど稀である前にも述べたことと重複するが斯く普遍的に紅紫色を出す樣なことが北宋時代に行はれ居りしならば彼の大觀年間妖變など事々しく記述せらるる理なく〓波雜志の記述も殆んど意
味を爲さぬことになる次第だ。加之洋人等の貴重する是等の品物は其形狀等より察するに恐らく大抵元明の產らしく思はれる)。以上縷述するが如く定窯紅瓷なるものは酸化鐵による呈色なりしや、或は又銅若は亞酸化銅等による呈色なりしや、未だ之を判定すべき決定的の資料に乏しと云はざるを得ない故に筆者は今此に疑問として其疑問である理由を陳べて置く次第だ。最後に一言すべきは柿天目のことである。此ものは一說に定窯紅瓷だと云はれて居るが是れなど可なりの誤だと思ふ。赤紅と云ふ樣な立派な柿天目は筆者未だ見たことが無い。普通見る樣な品では婦人の愛着など到底引かれまい。況んや張貴妃に献上して其歡心を求むるなど思ひもよらぬことである。又これならば今も世上に澤山あるし、當時造るにしても恐らく極めて容易安價にイクラでも出來たろうと思ふ。即ち東坡の如き何も磚爐石銚など云ふて羨望せずとも、そこらの店で金十錢を投じて買つて來れば可なりだ。(斷はつて置くが之は八百年前の相場です、今は仲々高いでせう)。若し柿天目にして定窯紅瓷と何等かの關係ありとせねば恐らくそれは只其拙劣なる模造又は僞造品でありしことであろう。東坡の如き良心が麻痺して居ない者は勿論これで滿足出來なかつたのは當然だ。附記以上で甚だ不完全乍ら本稿を了ることとする。御覽の如く四回に亙り前後一年餘の長い時日を經て書いてゐるので前後重複せる所、辻褄の合はぬ所もあらん、宜しく御推讀を請ふ。支那陶磁小考大尾
9.5.29小考奧附支那陶磁版元著昭和九年五月三十日發行昭和九年五月十五日印刷印刷者發行者者電話日本橋九一九振替東京二六七三二東京市日本橋區通三ノ三寶貳圓五拾錢定雲舍價東京市京橋區木挽町一ノ十一川橋仁川堂印刷所川橋源三郞東京市日本橋區通三ノ三遠藤敏夫尾崎洵盛
9年日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
