
独学で国立医学部に合格した勉強法を全て公開【総論】
2022年6月追記
【ここからVol1】
皆さんこんにちは!
このページへアクセスいただきありがとうございます。
読んでくださる受験生には合格へのロードマップを、保護者や教育関係者にはぜひ指導の羅針盤として活用していただければ幸いです。
※非常に内容の濃いものになっております。
私は東京医科歯科大学医学部医学科への合格を、
浪人が決まったその日から戦略を定め、戦略通りに合格したものです。
この記事にアクセスいただきありがとうございます。恐らくは受験生そしてその保護者、又は教育関係者だと思います。
きっと多くの人がこの「東京医科歯科大に独学で合格した人間の勉強法」が気になっていると思います
私がこのnoteを書くにあたってある思いがありました。少し前置きが長いですが後悔させませんので読んでみてください。
自分の受験生時代も今も、塾や予備校が変わらず繁栄しています。
現代の受験社会ではそれらに通うことが当たり前の空気感が蔓延しています。まだそこで成績が上がっている受験生はいいのです。
しかし高いお金を払っても成績が伸びず自分は勉強が出来ないんだと勘違いをして、挙句の果てにうちの子供は勉強ができないと嘆いている親を見ていると悔しい気持ちでいっぱいになります。
なんで効率的な勉強についての勉強をせずに塾に行くのだろうと。
なぜこのような受験社会の風潮になってしまったのか。
塾や予備校が大学合格のための必要条件というのは本当だろうか。
このような疑問が高校3年生頃から私の頭の片隅にはありました。
☆結論:塾や予備校は必要ない
私の見解を書きます。
塾や予備校は質問対応を除いて全く必要ありません。
なぜなら授業形式の知識のインプットは余りにも効率が悪いからです。
「勉強=自分にない知識を増やす」には正しいやり方と間違ったやり方があります。これは誰にでも明白です。
しかし、効率的な勉強とそうでない勉強を正しく理解している人となると極端に少なくなります。
効率的な勉強は少ない時間で多くの知識を入れる勉強。
そうでない勉強は知識を入れられるが時間をかける勉強。
受験において圧倒的に有利なのは前者です。
【端的に言うと受験当日は「どれほど知識を入れてきたか」のみが問われます。】
なので知識を半年で入れようが3年かけて入れてこようが試験側は知ったこっちゃありません。
受験合格に必要な知識というのはあらかじめ合格者がやってきた問題集を見ればある程度分かります。
彼らと同じかそれ以上の知識を入れていけば合格を確信できます。
要はいかに効率的に知識を頭に入れられるか?
これが受験生の永遠のテーマでありこれ以外を考えてるのは話になりません。
この問題を自分で解決するために他人の意見を参考にしたりして自分で試行錯誤する必要があります。
なぜなら効率化を考えること=論理的思考力の養成となるからです。
他力本願ではいけません。
全て自分で考えることが大切です。
しかし今の時代はインターネットがあるので他人の考えや思考を知ることができ、少しでも自分の思考の構築の参考にすることだって可能です。
後々記述しますが私は「思考力」を「既存の知識を組み合わせて新しい知識を生み出すこと」だと定義しました。
だから何もない状態から考えるのではなく、このnoteや色々な合格者の成功体験を見てそれらのノウハウを自分の中にためてそれらをつなぎ合わせましょう。
それが自分だけの新たな勉強法になります。
私だって合格体験記やいろんな人の意見や経験を参考にして自分の持論を得るまでに至っています。
受験はビジネスです。顧客がいないと成り立ちません。
だから毎年かなりの広告費を出して「合格するなら〇〇塾」というキャッチフレーズで多くの現役生・浪人生を集客します。
しかしその予備校でやっていることが、効率化を最重要視しているかは甚だ疑問です。
☆このnoteを書くにあたって
私はこのnoteを書くにあたって「少しでも効率的に頭に知識を入れる自身の考え」を知ってもらいたいなと思っています。
受験時代に考察したことや大学で勉強した脳科学、哲学などの学問の分野に加え、受験じゃない分野でも成功している経営者の論理的思考などの実学の分野も合わせて様々な文献を参考にして自分の考えを構築しています。
受験だけに限らず、論理的思考力の高い人の頭の使い方などについても日々参考にしています。
もちろん、勉強のできる同級生や自身が高校生に直に教えるにあたって得られた経験からも良いフィードバックが得られました。
医学部の定期試験でも合格する人と不合格の人に別れるがその違いは何か?
高校生の中でも成績が燻る生徒と飛躍する生徒の違いは何か?
私は実学分野で大成功している人間ではないため、すべてが正しい意見だとは自身でも思っていません。
しかし少しでも読んでくれる人の「気づき」になればそれは嬉しいことです。
恐らく読んでくれている人の多くが受験生でしょう。
そういう人はチャンスです。
勉強法の勉強をメタ勉強と呼びますが、メタ勉強を受験時代に思考することは受験が終わってからの長い人生でも必ず役に立ちます。
もしこの記事を読んでくれる人の中には少し非効率な勉強法をしていたり周りの環境のせいで過度に受験勉強を捉えていたりする人もいると思います。
そういった方々が少しでも意識が変わり自分の本当の行きたい大学に行ける手助けになれば、文章の書き手としてホントにこんなに嬉しい事はありません。
「過去は変えれないけど、未来は変えられる」
私はこの言葉を本気で信じ続けています。
総論はVol.1〜3まであり全22章+付録3章に渡る予定で執筆していきます。
全部で10万字を軽く超えますがほどありますが少しずつ読み進めていただけたらと思います。
このVol.1では第1章〜第4章まで収録されています。
ところで一番初めに書くのが良かったのですが、区切りがいいのでここで大切なこと言わせてください。
noteにある総論3つ、各論5つの記事の中の全ての文章は、
【1年という制限時間の中で志望大学の合格最低点以上の知識を効率的に身につける】
ということのみを目的とした私の経験と思考から構成されています。
それ以外のことは一切考えていないのでこの目的と同じ目的の受験生は読む価値があります。
第1章
受験の本質とは

私は読者の周りの人と同様に、どうしたら合格するかを語るなどは今までしたことありません。する意味がないからです。
本来は気が引けるのです本当の意味で受験ハックを語り少しでも受験生の役に立てれば嬉しいと思いTwitterやnoteで情報発信しています。
〇〇ハックという言葉、虫唾が走るほど嫌いなんですが受験に関してはこのnoteに書かれている内容は本当にハックですので安心して読んで下さい。
私は高校生の頃、恐らく多くの受験生が抱いているように医学部受験となると
「自分は頭が良くないから。」
「地方だとやはり都会とは情報格差があるから。」
「医学部はほとんどが有名進学校出身で小さいころから神童と呼ばれている人しか行けないから。」
「凡人は多浪する覚悟で臨まないといけないのか。」
という考えが頭を埋め尽くしていました。
結局、現役時には地方の非医学部を受けてあえなく不合格。
浪人が決まった時、それはそれは落ち込みましたね。
ただ考えるきっかけになりました。
浪人することは確定したのだから1年間で医学部に、それも私立のギリギリでなくて国立のトップを目指してみようと。
当然無謀だと周りにも思われました。親にも無理だと思われていました。そこで親にどうして無理だと思うか聞いてみたら、私の頭を埋め尽くしていた先ほど挙げた理由がどんどん出てきました。
私はふと気付きました。
自分の持つ受験の仕組みについての知識はなんて浅かったのだと。
そこから合格の方法を考えて受験の本質に気づきました。
例えば、日本一難しい東大理三に入学するには
・有名中高一貫進学校卒
・小さいころから神童と呼ばれる
・他人と比べて目に見えて頭が良い
これらのような条件は入っていません。
合格条件は募集要項を参考にすると
一次試験、二次試験の得点が合わせて合格最低点より0.1点でも上
これのみです。
ちなみにすべての医学部および難関大学の合格条件はすべて同じです。
つまり「受験での成功」を考えるならば、上の条件以外のことを考えてもすべて無関係で時間の無駄です。
言葉では分かっていても実際に納得するのが難しい人も多いでしょうから、まずはこの変わらない事実を受け入れてください。
少し掘り下げると、受験とは入試当日に合格最低点より1点でも多く得点できるだけの知識があるならば誰でも合格できます。これは真実です。
受験のために4浪目でいざ本番を迎えた受験生も受験当日まで海外旅行していた受験生も入試当日に合格最低点を上回ればだれでも通ります。
今でしょ。でお馴染みの林修先生も現役時代は高3の夏で東大合格のための勉強は終わったからあとは遊んでいたと仰っていました。
先生は結局合格していますから、受験では成功者です。
ちなみに余談ですが、大人や塾関係者(講師やチューター)などの人々がいうことは受験生を心理的に惑わすことが多いのでまったく鵜呑みにする必要はありません。
例えば「倍率が高いから」とか「発想力もある程度必要だから」などは多くの受験生がストレスを抱えてしまうホントに良くない言葉です。
そんなことを平然と言うことを許してしまっている今の受験社会に対してとても悔しい気持ちになります。
倍率についてですが、その大学の入試の倍率が毎年1.1倍であろうと50倍であろうと各年の合格最低点を上回る勉強をしていれば、倍率などただの数字でまったく意味のない飾りです。
なぜなら例年通りの倍率ならば、合格最低点は大きく上下動しないからです。
私が入学してから数学科の教授に聞いたら毎年同じように点数が取れる難易度にしているそうです。
ということで、まず倍率うんぬん言う人は受験を勘違いしているので真面目に聞くべきではないです。
発想力についてですが、受験で発想力は必要ありません。これまじ大事。
受験当日に数学や物理でうんうん考えていたら時間切れでその科目は壊滅し、十中八九不合格でしょう。
そもそも受験で発想力を試すという概念自体が間違えています。詰め込み教育の日本では解き方を覚えてしまえば一発で、次にそれがきたら解ければいいだけです。
一番やってはいけないもっとも最悪なのは普段の勉強中から、発想力を鍛えるといって一題に20分も30分も時間を費やすことです。志望大学に向けての勉強は早く終わらしてしまいましょう。
また詳しく書きますがとにかくこれを受験の全てだと思ってください。
「一次試験、二次試験の得点が合わせて合格最低点より0.1点でも上」
これが合格するための唯一かつ絶対の条件です。
第2章 第1節
勉強計画の立て方(1) 志望大学を決める

この章では受験勉強を始める際に1番最初にしなければいけないことについて書いてあります。
一番最初ですよ。普段何気なく勉強してきて今日もなんとなく勉強しようとしている受験生は、今日は一旦勉強やめてこのことについて考えましょう。
遠くに行きたければ目的地も入れずにドライブするのはもう今日でやめましょう。
まず一番初めにしなければならないこと。
それは合格までの計画をたてることです。
それは絶対に具体的に立てなければいけません。
受験勉強の最初にしなければいけないことは英単語を暗記することでも化学式を覚えることでもありません。
そんなの計画を立てることに比べたら小事です。
「勉強計画」こそがあなたの受験結果を大きく左右するのは圧倒的に間違いありません。
この手順を踏まずにいくら勉強をしても合格は近づいてきません。
合格がどの方向にあるのか分からないのに歩き始めてもほぼたどり着かないのは当たり前ですよね。
先程言いましたが、この計画を立てずに受験勉強を始めるのは、遠いところへ車で向かいたいのにナビを入れずにいきなり走り出すようなものです。
走っても目的地に進んでる気配が感じられないので不安になります。
逆に合格への計画というナビがあれば必ず目的地につきます。
ナビの入れ方はこのnote全体を読めば確実に立てることができるようになります。
☆計画とは一体何なのか!?
計画を立てることは大事です。
この言葉は万人が納得する言葉です。
そしてあなたの身の回りにいる、心理的に上に立ちたいが具体的なアドバイスは何1つくれない教師や勝手な親戚も口にします。
少し考えてみましょう。
「計画」ってなんでしょう。
システム工学の世界では、「問題」を「理想と現実」とのギャップであると定義します。
かなり具体的に受験に置き換えてみましょう。
理想をハッキリいうと「志望校の合格最低点」です。
受験において理想とは合格です。
合格とはすなわち合格最低点です。
ここには判定や倍率などは一切入る余地のないことに注意してください。
現実をハッキリいうと「今の自分の知識で取れる志望校の点数」です。
受験において現実というと今の学力です。
今の学力とはすなわち今ある知識で得点できる点数です。
具体的に東大受験を例にとり数値化してみます。
合格最低点が315/550である理科I類において今時点で230/550だとします。
この場合は「理想」は「315」,「現実」は「230」,「問題」は「85」となります。
なんら難しいことはありません単なる足し算引き算です。
ここで「計画」についてもう一度考えてみましょう。
さっきの例にとると受験生は「計画」を立てて、「問題」である「85」を解決しようとします。
「計画」の仮の定義を立てるならばそれは
問題を解決するために当人が考えるプラン
です。
ここでもう少し深掘りしてみましょう。
上の定義じゃ親戚のおじさんの受験アドバイスとあまり変わりませんね。
新たに2つ考慮に入れなければなりません。
それは「時間」と「具体性」です。
受験だけに限らずあらゆる計画には「期限」つまり制限時間が存在します。
逆に考えると制限時間内に問題を解決しなければいけないから「計画」と初めて言えるのです。
例えば、とある経費削減の計画の中身を見たときに
・時期のバランスを見て慎重に経費を削減する
・無駄遣いをしないようにする
の2点がメインのポイントでした。
こんな中学生でも考え付くような稚拙な計画では経費など削減できませんね。
これの問題点はみなさんお気付きでしょう。
それは具体性に欠けることです。
自分の受験計画に具体的な言葉を入れていない人は気をつけましょう。それは逃げに他なりません。
具体的な計画というのは失敗したときに言い訳ができなくなります。曖昧な計画だと失敗しても原因が分かりませんから何となく外的要因、つまり自分のせいだけじゃないと心のどこかで安心して自分を保とうとできるのです。
しかし受験も含め社会に出て行くようになったら、
「どれだけ結果を出せるか」
「どれだけ人に影響を与えられる人物であるか」
が大切であり、
「自分がどれほど計画通りに物事を進められない悲観的な環境に身を置いているか」
は誰も見てないし知らないので自分の心の保身のために逃げるのはやめましょう。
結論を言います。「具体性」とは「数字」を入れることでその性質を持たせることが可能です。
「数字」を入れる最大の特徴は可視化できイメージすることができるという点です。
まとめると「計画」という言葉を正しく定義するならば
期日内に問題を解決するために当人が考える具体的なプラン
です。
定義というと抽象的な言葉になりがちですがもっと砕いていうと、
「受験当日までに合格最低点までに足りない点数を得点できるようにするために考える日単位ベース・問題集ベースで立てるプラン」
のことです。
余談ですが私が予備校の授業が嫌いな理由、は予備校の授業は合格までの道のりへの数値化ができないからです。
この問題集(200問)完璧にすれば大丈夫ですか?
という質問には答えられますが
この予備校の授業(50限分)完璧にすれば大丈夫ですか?
という質問には答えられません。
☆計画を立てる第一歩は志望校と学部を決めること
合格に向けて受験勉強に開始するにあたって具体的に最初にしなければならないことは志望校と学部を決めることです。
これは先ほどの計画でいうと「理想」を確定させることです。
「理想」を確定させると
・受験科目
・点数配分
・合格最低点
・各科目の問題の難易度
・各科目の問題の傾向
・センターで必要な点数
・例年の成功者のレビュー
が明確になります。
つまりゴールが見えるのですね。
ちなみに上に挙げた中で1番大切なものは合格最低点だということはもう言わなくてもいいですね。
ゴールを決めた後は先ほど説明した「計画」を立てます。
数値化した具体的な「計画」と必要量の「時間」はあなたを「理想」へと連れて行ってくれます。
時間だけあっても理想へと連れて行ってくれないことを理解してもらえれば十分です。
よく「努力は実る」なんて言いますね。
あれの半分は嘘です。
ダルビッシュ有は次のようなコメントを残しています。
「何も考えずに行っている努力は平気で裏切るよ。でも正しく努力したら必ず実る。」
これは完全にあっています。
ここで言っているのは先の計画を考えずにただがむしゃらに何かを頑張ってもそれは意味のない時間が過ぎることにもなりうるということです。
とても現実的で残酷だと思います。
だって誰しも努力すれば実ると思いたいじゃないですか。
でもこの考えの人って実は自分に甘くないですか?
1番大変な「頭を使う」ということをしていません。
「計画」を立てようと必死に頭を使おうとすらせず、ただ努力をして結果がいつか出ないかなと待っています。
待っていても結果は出ていません。自分で掴みに行きます。
結果が出ないと気づいたら方向性をシフトして、こんなに頑張っている自分を評価してくれと言わんばかりに周りに承認を求めてくる恥ずかしい人間へと成り下がるのがオチではないでしょうか。
そんな人にならないよう「計画」を立てるのがどれだけ大事か理解してください。
最初から完璧な計画なんて誰も立てられません。
私だって3月時点では年間の大まかな計画と4~5月の具体的な計画ぐらいしか立てられませんでした。
その途中でもちょっと変えた方がいい場合は何百回、何千回と軌道修正してました。
☆決まらない人は東大理3を第一志望にしよう
もし何も志望校が決まらないなら東大理3をおススメします。
なぜなら日本で一番難易度が高いからです。
もし受験勉強の途中で自分の人生の目標が決まった場合でも東大理3を目指して勉強する過程で身についた思考法は決して無駄ではなく、人生にとっても大きな意味があります。
でも人生の目標なんて一生かかっても探すようなものですから今のうちは気にしなくても大丈夫です。
オリンピック日本代表選手などを見ると我々は尊敬の眼差しで見ます。
彼らはその競技で日本を代表できるほどの技能をもち、大舞台で発揮できるメンタルを持っているからです。
勉強の世界で言うと理3に合格することはもしかしたら人々はオリンピック選手以上の尊敬の眼差しを向けてくれます。
それほどすごいことだと思います。
東大理3も他の大学の入試と同様に合格最低点を上回れば合格できるのに、メディアや妄想によって勝手にあなたを宇宙人レベルに頭がいいと思い込んでくれます。
私は医科歯科に合格するだけの計画を立て、それを徹頭徹尾実行したに過ぎませんが周りの人は勝手に「頭のいい人」として見てくれます。
日本の学歴社会では「頭のいい人→高学歴」ではなく「高学歴→頭のいい人」という構図を勝手に周りが判断してくれます。
私は今でも自分のことを思考力のある人間だとは思いません。
話を戻します。
先ほど説明した通りシステム工学の世界では問題を「理想と現実のギャップ」と定義しますが、これはそのまんま受験勉強に当てはまります。
そのギャップを埋めるべく問題集・参考書を使い知識をつけていくのですが志望校が定まっていないのであれば一番ギャップのある東大理3にしましょう。
ちょっとやそっとじゃ到底手の届かないレベルのところに設定するのが良いです。
なぜならそうすると自分をそこまで引き上げる過程で試行錯誤を繰り返すことになるので理想実現力が上がります。
これは人生にとってもプラスです。
試行錯誤というと勘違いされそうですが、これは悩みではなく常に自分の今の状態を客観的に見つめ、目標と現在位置間の距離を測ることを自然と考える癖をつけることです。
ただ今年から理転した人や中学レベルが怪しいという人はどうしてもイメージしづらいと思うので東大理1という目標でも大丈夫です。
第2章 第2節
勉強計画の立て方(2) 目標への計画を具体的に立てる

次は理想に向けての現実とのギャップを埋めるべくその計画を立てます。
受験に限らずいかなる場合でもそうですが計画というのはすべて逆算式で考えます。
数学でいうところの同値と似ているかもしれません。
身近な例を出します。
▪️明日朝9時から模試
明日朝9時の模試に間に合う
→家を8時40分に出れば間に合う
→8時に起きれば間に合う
→今夜目覚ましを8時にセットすれば間に合う
といった具合になります。
つまり今の時点で目覚ましを8時にセットすれば明日の朝9時の模試に間に合うことと同値となります。
受験については点数という最もはっきりした物差しのみで測るので今の自分の実力を知っているならば計画が立てやすいです。
次に受験当日から簡単に逆算の例を書きます。
具体例として東大を挙げていますが日本で一番の総合大学のため今後もちょくちょく例に取り上げます。自分の志望校が決まっている人はそこの大学の科目と合格最低点を頭で思い浮かべながら読んでください。
☆受験勉強での逆算式で考える具体的な計画
目標
この1年間(4月から2月末)で理3合格
計画
二次試験で300/440点を取る。
↓
国語:40/80 数学:60/120 物理:50/60 化学:50/60 英語:100/120
↓
▪️国語
点が取りやすい古文漢文を8月までに東大国語で30/40点取れるように仕上げる。
そこからは現代文などを定期的な過去問演習などで少し詰めていく。
8月までに東大古典を仕上げるにはまず4月5月でハイエンドの古文単語帳や漢文の構文の基礎、センターレベルの文章などが読める程度にはなっておく。
6月7月で問題演習をこなし東大レベルまで対応できるようにする。
8月は予備月でさらに問題演習にあてるか大丈夫なら今まで解いたものをより復習する。
▪️数学
年が明けてから25年分の過去問演習にあてたい。
12月までに新数学演習を2周したい。
新数学演習レベルの問題に触れても理解して吸収できるように9~11月で3~4冊の問題集を何週もして下積みを作りたい。
今のままではそれすら厳しいので4~8月の5ヶ月で青チャートと1対1対応をこなしていく。
▪️物理
センター終わりから過去問演習に切り替える。
12月からセンターにかけて難系の例題を仕上げる。
9~11月で重要問題集と名問の森のさらなる復習にあてる。
7~8月で名問の森を仕上げる。
今のままでは重要問題集も名問の森も解けないので4~5月は体系的に解説している参考書を読みまくり、簡単な例題を解きつつ良問の風で問題練習。
5月が過ぎても参考書は毎日一章読むなど理解できるまで読む。
▪️化学
年明けから過去問演習に切り替える。
8~12月で化学の新演習を仕上げる。
それまでには重要問題集を仕上げなければならない。
4月から照井式の無機理論有機の参考書を繰り返し読み、理解した分野から重問の問題演習に取り掛かる。
8月までに照井式の完璧理解と重問を仕上げる。
▪️英語
東大英語に見合う英単語帳・英熟語帳一冊を4月から取り掛かり出来るだけ早く、遅くても8月までには仕上げる。
リスニング教材を毎日使い、耳と脳を慣らし東大英語のリスニングで満点が取れるよう仕上げる。
英作文は駿台の基本300選を8月までに暗記する。
東大に対応した文法問題集を必要ならば9~12月の間で取り入れてすぐ終わらす。
長文は短いものから始め、徐々に長くする。
最低1000語以上の長文を1つ以上9月から毎日読む。
センター明けから過去問演習に切り替える。
ざっと簡単に書きましたが、こんな感じで合格できます。
予備校の授業など計画には一切入っていません。
毎日ずっとインプットを続けていきます。
数英理の問題集については私が使用した問題集も含めて別記事で紹介します。
哲学者デカルトの言葉に「困難は分割せよ」というものがあります。
理3合格というどこから手を着ければいいかわからない超難問も分割しまくると実行可能な問題にまでレベルを落とせます。
例えば化学においては「照井式の参考書を読み、理解出来たら一般的な問題演習で確認する」というところまでブレイクダウンできました。
☆合格までの計画を考えるときに注意すること
このようにあらゆるものを逆算して考えると今やるべきことが明確になってきます。
「今自分がやっていることは確実に合格へと続いている」
と確信できたら勉強効率はかなり変わります。
もし読んでくれている受験生の中で「今日は何しようかな」と漠然に考えている受験生がいるならばこれを参考に考えるきっかけになれば幸いです。
今日は何しようかなと考えているということは中期計画または長期計画が立てられていないために今やるべきことが分からないのです。
受験で合格するために計画を立てる際に注意しなければならないことがあります。
数学が東大模試クラスで5完以上できるすごい人は別に気にする必要はありません。
私のような凡才が考えなければならないのは数学の点数を最初に計上しないことです。
上の例では数学を2番目に書きましたが実際は最後に立てました。
入試で安定して高得点を取りやすい英語と理科で高い点数を設定し、国語で足を引っ張らない点数をまず決めます。それらを例年の合格最低点より20~30点ほど高く設定した目標ラインから引いて数学で何点取ればいいのか考えます。
この計算を行って数学で8割取らなきゃいけないような計算になると、それはうまく計画を立てられていません。
数学というのは
「入試までの準備で1番かける時間が多くなる科目」
でもあり
「入試本番で1番期待してはいけない科目」
でもあります。
理由はもちろん数学で本番でも高得点を取るのは半ば博打に近いものがあるからです。
「いやいや確固たる学力があればできるだろ」
と思うかもしれませんが、私にとっては英語と理科という集中的に練習を積めば高得点で安定する科目が隣にあってのでそれを見逃すわけにはいきませんでした。
逆にあまりいませんが、もし読んでいる人で数学がべらぼうにできるけど他の科目がてんでダメという人は適切に英語と理科で演習を積めば受験がかなり楽です。
☆計画をうまく立てる方法
「今日の夜は何をやろうかな」
「今週は数学だけやるぞ」
このような行き当たりばっかりの計画を立ててしまう人が中にはいると思います。
その人はまず短期計画が立てられていません。
短期計画が立てられていないとやる気が出ない時に自分に対して「今日はやる気が出ないからしょうがない」という言い訳をダメだとわかっていても作ってしまいます。
では短期計画が立てられない原因はなんでしょう?
それは中期計画と長期計画が立てられていないからです。
長期計画は
・合格最低点までどの科目で何点取る必要があるか
・それには各科目でどのレベルの問題集の中身を頭に入れておけばいいのか
ということを自分の志望に合わせて「具体的」に決めます。
中期計画は
・長期計画で決めた各問題集を何月までにだいたい終わらせればその先の問題集に取り組められるか
を「具体的」に月ベースで考えます。
実際にどれくらいで終わるかは問題集の場合、(その問題集の総問題数)=(1日のノルマ)×(日数)であるので必要な日数は簡単に求められます。
長期計画に基づいた中期計画を立てられればその計画の中身は「1日のノルマ」だらけで占められているので
「何をやれば良いか」という疑問は一切出てきません。
目の前の本を今日のノルマ分、理解して覚えることに全力を注げます。
それを淡々とこなせば自分の立てた「計画」があなたを合格まで引っ張っていってくれます。
第2章 第3節
勉強計画の実行 自分に言い訳して逃げることが1番損

前節で具体例として理3合格のための勉強計画の具体例を書きました。
あの計画通り進めばほぼ十中八九合格します。
あの計画には
外的要因はほとんど入っていないかつ、自分が実現可能な計画
だからです。
しかも受験において一番点数が崩れやすい数学の点数を低めに設定かつあの目標点数でも例年の合格最低点よりも20点近く高いため不測の事態にも対応しています。
☆完璧な計画でも完璧に遂行できる人なんていない!
「目標を立て、計画を立てたら、あとはその期間分だけ自分の時間を投資して達成する」
というプロセスの途中で絶対つまずくことがあります。
どうあがいても目標達成は厳しいと感じる苦しい時期も訪れるでしょう。なぜなら今の自分よりかなり高いレベルを設定したからです。
しかし重要なのはこういう時期です。
ここで
「理解が出来ない」
「一日丸々サボってしまってもう取り返せない」
「やる気が出ない」
「自分に見合うレベルでいいや」
これらのよくある感情を言い訳にして逃げて志望レベルを落とす受験生がよくいます。
非常にもったいないです。
計画を立てれた時点でほとんど成功は確約されているにもかかわらずです。
本田圭佑はロシア時代にインタビューでこのように答えていました。
「ある目標に対してそこまでの道筋を具体的に描けたら、それはもう既にそこにいる時点でそれは成功」
この言葉は私も感銘を受け、計画を立てる際にもそのまま当てはめ私は合格しました。つまり一浪して勉強を始める4月からではなく具体的な合格への道筋を見通せた3月の時点で合格していたも同然です。
実現可能な綿密な計画を立てたら後は適切に時間を投資するだけで自分が行きたいところまで自分を連れていってくれるのです。
本田圭佑はサッカーという、明らかに外的要因に大きく左右される競技でさえこの方法論を確信していました。
全く外的要因に左右されず計画を立てられる受験でこれができないわけがありません。
☆割りに合うと認識できればなんだって可能!
人間は不思議なもので割に合うと感じたら実は意外に自分の思っている以上のことできるという場面が多いんですよね。
1つ私の体験談を例として挙げます。
私は高3の2学期終わりから受験にかけて通学に時間のかかるという理由で地元で勉強しようと思い、近所の図書館で勉強することに決めていました。
そこまではいいのですが目標設定も勉強計画もあいまいなまま受験勉強時代を迎えてしまいやる気だけはあるのですがどうしても朝起きれない日々が続きました。
9時過ぎに起きてボケーっとテレビを見ながら朝食を食べ11時ごろから18時ぐらいまで図書館でダラダラと勉強していたに過ぎませんでした。
しかし浪人時代になるとその日の各科目のノルマを達成することのみがその日の最重要課題でした。
それのおかげか、遅起きもダラダラとテレビを観る行為もすべて割に合わないと頭が理解してくれたおかげで毎日6時には起きることが出来ました。
正直20歳ぐらいならば、5時間も寝れば頭は働くので大丈夫です。
だからいかに計画を立ててそこに時間を注ぎ込むことが自分に割に合うかを理解してください。
単にかっこいいでもいいですし地元を飛び出して都会に行くでもいいです。
実際自分が最初思っているよりはるかに上の大学に合格すると周りの思考力も自分と同じかそれ以上の人たちとの素晴らしい出会いが待っています。
「自分の設定したノルマをこなせばそれを間違いなく手に入れることができる」
これが最大のモチベーションです。
世間は努力して成功した人をかなり評価します。勝手に頭が良いとも思ってくれます。学歴というものが存在する社会では「頭が良い=良い大学を出ている」というより「良い大学を出ている=頭が良い」という風潮があり勝手に評価も上がります。
周りに公言して逃げ道を作るのも1つの手です。
私は身の程知らずだったので最初は周りからも絶対無理だと言われましたが、宣言したからには1日1日のノルマをこなして絶対合格して見返してやると決めました。
目標とするところに合格することが割に合うことを理解することは言い訳の心を抑える受験で必須の考え方です。
第3章
なぜ問題集で合格が確信できるのか

まず、受験に合格するには
自分が受ける年に合格最低点以上を確実に取らなければいけません。
浪人が決まった時、その現実にどう立ち向かい対処するかを考えていました。
私の完全な持論なんですけど、浪人が決まった時って
「これから合格実績の良い予備校に1年通って去年落ちたところ通ればいいなあ」
ではなく、
「1年間という制限時間の中で何が何でも合格最低点までのギャップを埋めるのにベストな勉強はどれか」
というマインドになるべきだと思います。
ギャップを埋めるためなら必要な問題集ならいくら高かろうが買い、予備校が必要なら死んでも予備校に行く、という様に何でもする覚悟でした。
考えた結果、答えはすぐ出ました。
予備校の授業は90分で4題しかやらない上にテキストに答えもついておらず、さらにはどの科目も家で解いてきた問題を授業中に解説するといった形式だったので時間対効果を考えるととても授業出る気にはなりませんでした。
予習+90分で4題は私には足りな過ぎました。
私は青チャレベルからやる必要性を感じていたのでどうしても時間が足らなくなります。
予備校に通わされているとお金払っているんだから行かなきゃ親不孝だと考える人がいるかもしれません。そうは思わないでください。ちゃんとその年に合格することが一番の親孝行です。
1番自分が受かる可能性の高い勉強法を選ぶのは当然です。
☆合格最低点までのギャップを埋める具体的な方法
この部分は何章にも渡る記事の中でもトップクラスに大事なところです。集中して読んでください。
まず第一に自分の志望校の合格体験記を見ます。
成功者をパクるのはガチ基本中の基本です。
そうすると、だいたい多くの人が同じような問題集を使っていたことが分かります。
例えば、
「物理は難系使っていました。例題だけです。」
「終わり間際には25ヵ年で演習していました。良かったです。」
「重要問題集2周しました。」
とかですね。
ここで、
「あぁ、この大学を受験する人たちはこのレベルの問題集までできるようにして受験当日、会場に向かったんだな。」
ということを実感して下さい。
合格者達がそのレベルの問題集を使っていたことは確かです。
しかしどの程度しっかりやっていたのか分かりません。
だから私は目標を
「最低でも合格者たちがやっていた一番レベルの高い問題集を何週もして全問似たような問題が出ても瞬殺できるレベルにする」
にしました。
少なくともこれなら彼らと同じぐらいの学力レベルにはなるからです。
とても簡単です。
上手くいった人の真似をすればいいだけです。
鉄緑生たちも鉄緑の先輩からおススメの問題集など聞いてそれを受験までに仕上げてきますから。
合格者たちが使っていた問題集を完璧にすることが目標ですが、そこには受験において大きなメリットが2つあります。
☆問題集を完璧にする2つのメリット
1つ目です。
市販の問題集の中で評価が良いものは、受験において頻出の問題を集めたorほかの受験生と差がつく、つまり知っているか知っていないかが重要な問題を集めています。
だからこれらを完璧にすると合格点は必ずとれます。
どの問題集にも載ってない様な問題しか出なかったら誰もまともな点が取れません。
20年ほど前の難関国立の理系の後期でごくまれに見ますが最近ではまず見ないので大丈夫です。
それと受験数学で8割以上取る必要は0です。
7割か最低でも6割取れば、得点が取りやすいかつ高得点で安定する物理化学英語で点を取れば合格です。
余裕で最低点超えることができます。
2つ目です。
受験本番での精神安定度が全然違います。
勉強をめっちゃしてるのに落ちましたっていう受験生は、
・勉強しているつもりが全然身に付いていない
・本番で緊張して頭が真っ白になっているか
どちらかです。
頻出問題集を含め、合格者がオススメとしている問題集の解法を全部頭に知識として入れて受験会場にいきますよね。
そうすると自分の見たことあるのはまず自分が必ずできる問題です。
全く見たことない問題(それでも途中まではできる)は、まぁどの問題集にも載ってないしみんなも分からないだろうなと確信できます。
問題集というのは全国の書店にあるので大手予備校の浪人生だけでなく、再受験生も宅浪も鉄緑生もみんな使います。
その最も汎用性の高いものである問題集を仕上げると、精神的に落ち着くことができます。
できる問題を確実に完答して分からない問題も途中まで答えれば十分な点数です。
しかも見たことある問題は何週もした問題なので時間をかけずに解くことができます。
☆受験での合格の目安は問題集で考えよう
自分の志望校の合格者たちが使っていた問題集を完璧に仕上げることは合格に直結します。
計画を立てるときには逆算で考えましょう。
最終的にそのレベルの問題集を使うための参考書や、中継の問題集などをそれぞれネットでレビューを見たり、書店でパラパラと見て決めましょう。
私は浪人が決まった3月の段階で決めて一気に買いました。思うようにいかないときもあったのでその都度その状況のレベルに最も適した薄い参考書や問題集で補完していきました。
目安としては10~11月から志望校レベルの問題集に入れるとかなりの2月までにかなりの演習量が確保できるといった感じです。
第4章
問題集を自力で解こうとしていると合格できません

いきなりすごいタイトルで驚かせてすいません。笑
これを実行出来るかどうかが、あなたが雑魚か優秀になれるかの分かれ道です。
皆さんは問題集買ってきた時どのような気持ちになりますか?
「この問題集を解けば、実力が上がるはず」
「しっかり解いて思考力を磨くぞ」
「友人も1ヶ月前に始めたし頑張って追いつくために1日5題解くぞ」
このような気持ちになる人はいませんか?
残念ながら彼らは問題集の意味を履き違え勉強の意味も履き違えています。
問題集を一から自力で解こうとしている人は危険です。
そういう人に限って「理想」の勉強法で問題集を解いています。
「理想」の勉強法とは、まず問題を見てノートや紙を用意して分からない問題があったら20分でも30分でも自力で考えます。
本番さながらに綺麗に解答を書き解説を読んで理解して復習するといった勉強方法です。
たしかにこの勉強法は解法が頭に定着する勉強法の1つでしょう。
自分の頭で能動的に考えているのですから同じ問題の解説を授業で聞いているだけとは大違いです。
ただこの勉強法は受験勉強ではやってはいけません。
☆時間のコストを考えたら到底解くなんて発想にならない!
圧倒的に時間がかかりすぎます。
綺麗に解答を書くというのは日々の勉強では全く必要ありません。
頭の中で再現出来れば本番では正確に書くことができます。
書いても覚えられないという人は覚えるときに頭の中で再現せず、手だけを動かしているから本番で再現できないのです。
1問に30分かけて理解するというのはあまりにも受験の頻出問題集のストックを自分の中にためる際には時間が足らないです。
最初から答えを見れば10分で1問終わらすことができます。
「頭の中で再現」ということを強く意識して解法を理解すれば、10分でも集中していない1時間以上の効果があります。
現時点で高校3年生や浪人している人は常に受験当日までの時間との戦いです。
少ない時間でより多くのことをインプットするためには、やはりいちいち紙に書いたり分からない問題を悩み続けることは意味がありません。
自分の持っていない知識を新たに身につけるためだけに問題集を使うので基本的に新しい見たことない問題は考えても解けないのは当然です。
だから答えを見ることを躊躇しないでください。
☆本当にそれを最後までやりきれますか?
最初から問題集を解くやり方では分からない問題が連続した時にやる気がそがれます。
3問連続でまったく分からない問題が続いた時に精神的にきついものがあります。
「あとこの3問に合わせて2時間近く自力で考えなければならない」
と潜在意識が働くと余計頭の回転も鈍くなり、結局何も新しい知識がつかない無駄な時間が流れてしまいます。
しかも分からない問題が続くと自分は頭が悪いと錯覚してしまい受験勉強自体にナイーブになってきがちです。
少し休憩が必要とか言って現実逃避を始めてしまうのも時間の無駄です。
分からない問題が3問続いたら
「よし。新しい知識が3つ以上も手に入る。なんとか45分以内に解答を再現できるよう集中しよう。」
と考えなければなりません。
また、自分の解ける問題ばかりの問題集を選ぶ人がいますが自分の出来ることばかりを続けても時間の無駄です。
3割ぐらいしか一瞬で分かる問題がないレベルの問題集を使うのが良いです。
8割だと時間の無駄です。自己満に近いです。
1割だと恐らくまず解答を理解できないでこれも時間の無駄です。
問題集を自力で解くのは時間の無駄がかなり生じてしまい効率が悪いので実は受験とはかなり相性の悪い勉強法です。
多くの受験生が問題集は
「解かなければいけないもの」
と勝手に思ってくれています。
問題集なんてただの本ですからどう使おうと勝手です。
受験本番では
「どれだけ解いてきたか」
よりも
「どれだけ知識があるか」
しか問われません。
少ない時間で多くの知識を入れましょう。
問題集は最初から答えを見てもいいことを合理的と思えると受験勉強が非常に楽になりますよ。
分からない問題が続いても何も思わなくなりますから。
逆に常に時間をかけて「思考力」とやらを鍛えている受験生が「1対1対応」や「重要問題集」の解法を全て覚えていると思いますか?いいえそんなことはありません。
彼らは思考力を鍛えれば、試験本番で未知の問題に対応できるかもという幻想を抱いているだけです。この勘違いのおかげで、今これを読んでいる貴方は勝ち組受験生になれます。
その未知の問題以前に、皆が使っている問題集に出てくる頻出問題に漏れがあり解けないような自体でもあったらその「思考力」を鍛えていると思っている受験生の合格可能性はほぼ0になります。
多くの受験生が使う頻出問題集に載っている問題で漏れがありそこが出題されれば周りの受験生に大きくアドバンテージを取られると思ってください。
逆にどの問題集にも載ってないような未知な問題が出たら捨てて構いません。
思考力を鍛え続けていれば、答案も書かなきゃいけない、緊張感もある、制限時間も迫っている試験本番で未知の問題を解けるとかいう妄想は一刻も早く捨てましょう。
もし皆さんの目標が「自分の行きたい大学に合格すること」であるのみならば。
以上、読んでいただきありがとうございました。
東京医科歯科大学 Yajima Yusuke
【ここからVol2】
【総論】Vol.2へアクセスいただきありがとうございます。
まだ読まれていない方は【総論】Vol.1を読んでからこの記事を読んでいただけるとより納得感が増すと思います。
この記事では第5章〜第14章までを収録しています。
Vol.1では合格するために本当に必要なこととそれを受験期間内に達成することに何が大切かを解説してきました。
Vol.1だけでも自分の「受験とはこうである」という固定概念が変わり、よりシンプルに合格に向けての道筋を考えられたと思います。
このVol.2の記事では「大学合格のために効率的に知識を入れる」というこうにさらに焦点を当てて多くの章を掲載しました。
特に「時間」という観点から受験勉強について着目しています。
受験勉強に制限時間がない人はいません。
みんな現役合格or今年で決めたいと思っているはずですし、そうでなきゃいけません。
私も1年の独学で東京医科歯科大学に合格できたのもこの「1年間」という与えられた時間をどう活用するかについて考え抜いた結果だと思っています。
もし高校生の時の勉強法のまま浪人していたら、到底1年では合格できず志望も下げていたと思います。
これを読んでくれた人が「時間」ということについて考えるきっかけになり、この1年で自分の行きたいところに余裕を持って行くことができ、受験勉強の道中も良き過程になる助けになれば、文章の書き手としてこんなに嬉しいことはありません。
noteにある総論3つ、各論5つの記事の中の全ての文章は、
【1年という制限時間の中で志望大学の合格最低点以上の知識を効率的に身につける】
ということのみを目的とした私の経験と思考から構成されています。
それ以外のことは一切考えていないのでこの目的と同じ目的の受験生は読む価値があります。
第5章
予備校に真面目に行くことが正しいと思ってる人は危険です

今の日本の受験社会を俯瞰してみると「予備校に通って授業を受ける」のがマジョリティとなっています。
多くの人が
・予備校は良いもの
・多くの合格者を出しているから通わなきゃいけないもの
と勘違いしています。
予備校の多くの合格体験記など見ていてあたかも予備校に通っている人だけが合格を勝ち取っていくようにさえ見えてきます。
大学受験は「合格最低点」というはっきりした数字によって合否が分けられているのでまずその事実はしっかりと強く認識したほうがいいです。
そんな事分かってると思うかもしれません。
極論を言うと、3年計画で医学部受験のために浪人してこようが受験前にどんだけ遊んでいようがそんな事は受験当日には一切聞かれません。
大学が試験当日に聞きたいのは手っ取り早く
「今日あなたは合格最低点より上の点数が取れるだけの知識を頭に入れて来た?」
という事だけです。
日本の受験システムはシンプルでいいですね。
予備校について勘違いしているみなさんだけがダメだというわけではありません。
予備校というのはビジネスですから電車にも雑誌にも莫大な広告費を払い生徒を顧客として必死に集めています。
その広告戦略で「予備校こそ合格への必要条件」と思わせるのは基本だと思います。
もし自分がシミュレーションで予備校の経営を任せられたら今以上に
「予備校に通うしか合格方法はない」
というメッセージをあの手この手で社会に浸透させようとするでしょう。
ここまで読んできた人は私の言いたいことがもう分かっていることでしょう。
私が言いたいことは
予備校というのは受験勉強では効率が悪い
という圧倒的な事実があるということです。
効率というのはコストパフォーマンスのことです。
かけるコスト(=時間)に対してパフォーマンス(=合格までに得られる知識量)が独学に比べてかなり悪いのです。
ここでコストのところに金銭的なことを書かなかった理由は、受験生にとって何よりも大切で貴重な財産は時間でありお金も大事ですがそれよりも何よりも最も大切な時間を強調するためです。
この章では
・予備校の授業はパフォーマンスが悪すぎる!
・パフォーマンスの悪さの具体例
・インプット量も無限ではなく各科目に終わりが存在する
について解説します。
予備校で習えることは全て本に書いてあります。予備校にいかなきゃ手に入らない知識などありません。
☆予備校の授業はパフォーマンスが悪すぎる!
塾の授業を真面目に受けていると合格が近づくと考えているとはっきり言って危険です。
なぜなら扱っている問題の量が圧倒的に少ないからです。
ある予備校の授業はどの科目も80分授業らしいですがその中で数学だったら大問を4つ扱います。
4つ目の大問になると難しい問題もありますから予備校教師も
「これは僕も解くのに時間かかった。センスが要るね。」
なんていう受験専門教師とは思えない発言をします。(体験談)
物理も化学も大体4つ程度の問題をたらたらと解説するだけです。
「今日授業でやったことを家に帰ったらよく復習する」
これがほとんどの予備校の先生やチューターのいつものセリフです。
しかも授業では予習を要求するという意味不明なことが起きます。
義務教育ですら先生の言う通りに勉強しなくても良いのに高校生以上が人の言うことを鵜呑みにしてその人の勉強法を遵守しなくても良いのです。
その人の言う通りではなくて、何が1番効率的に知識を入れられるかを考えてみればその人の勉強法を採用するかどうかは自分で判断できるようになります。
☆パフォーマンスの悪さの具体例
実際に数学の1回の授業を例にとって見ましょう。
・答えのついてないテキストで前夜に2時間で4題分予習する
・80分授業ではその大問4つ分しかやらない
・その日の夜か後日、授業内容しか復習しないならばその科目は2~3日で大問4つ分しか進捗がない
自分でも書いてて悲しくなりましたが、残念と言うかほとんど無念に近いような勉強です。
予備校のスタンスは
「うちの授業では問題演習及びその解説をするから、暗記事項はすませて置いてね」
というものですがここでも受験の本質とはかけ離れています。
受験に合格するにはインプット量を増やさなければなりません。
アウトプットなんて共通模試や大学別の実践模試でやれば十分です。
平日の何もない日からたらたら人の話聞いている時間はありません。
要は1日の勉強はすべてインプットのために使うためにあります。
アウトプットはー?なんて質問もありますがこのnoteで書いてある勉強法は毎日インプットの前に必ず頭だけで解法再生のアウトプットをしています。
紙にいちいち書いて勉強している人の何倍ものアウトプット量になるでしょう。
数学も物理の化学もすべてインプット量さえ増えれば必ず成績は上がります。
☆インプット量も無限ではなく各科目に終わりが存在する
先ほどの1つ予備校教師の入ったセンスという言葉についてです。
大前提ですがセンスなんて大学受験では必要ではありません。
数学でセンスが必要なんて言っているのは、例えると見たことのない英単語を人に見せて意味が分かるか聞いて分からないと言ったらセンスないねと言っているようなものです。
ただその人の言うセンスというのは「スペルの接頭辞や語尾を見て推測する」ということでしょうが英単語って覚えてしまえばもう終わりです。
次に見た時に即答出来たらそれで良いのです。
こんなことを言うと
「英単語なんて無限にあるからやっぱり本番に対応するためにもセンスを磨かないといけない。」
「数学も物理も化学もいくらでも難しい問題作れるのだからセンスが大切だ」
と反論してくる人もいるでしょうが大丈夫です。
受験には頻出問題+αという見えない上限が存在し、それを抑えて出来るようにすれば受験で落ちることはありません。
それを仕上げれば必ず合格最低点以上とることができます。
ここでいう+αとはその大学に特徴のある問題、分野です。
+αを例に出すと東大英語のリスニング、慶應義塾大学医学部の確率漸化式、慈恵医科大学の英文法問題などです。
しかしそれでも頻出問題を完璧にさえすれば十分合格できるレベルです。
言うなれば受験は頻出問題をいかにどれだけ完璧にしているかが問われています。
1秒でも早く問題集を使ってそれらを覚えなければなりません。
1つの科目につき80分で4題などと眠たいこと考えていてはいけません。
第6章
なぜ塾は繁栄しているのか!?その本当の理由とは・・・

今の受験社会を見てみると河合塾、駿台、代ゼミ、東進などの大手予備校をはじめとした日本全国かなりの塾が多くの受験生を集めていますね。
何年も潰れず世間に跋扈しているのを見ると経営的にうまくいってるんだなと感じます。
大手予備校の主催する模試によっては河合の全統模試のように模試だけで20万人弱の受験者がいるような模試さえあります。
昔と変わらず今もかなり塾・予備校は繁栄していますね。
ではなぜ繁栄しているのでしょう?
この章では
・受験はビジネス!お金が動いています
・なぜ予備校含めた受験産業が儲かるのか?
・予備校に時間を投資しようとしている人へ
について解説しています。
☆受験はビジネス!お金が動いています
現在受験生の皆さんはカジノゲームで言う子側つまりゲストです。
予備校は親側つまりカジノ側です。
私は浪人時代や合格後にプレイヤー側から席を立ちそのテーブルを客観的に見るような立場を取りました。
すると子側のプレイヤーとして座っているときは見えてこなかった様々なことが見えてきました。
まず塾や予備校にとって受験は完全にビジネスです。
法人化している以上、利益を出さなければいけません。
あれだけの職員、講師、広告宣伝費、各校舎維持費、その他雑費を差し引いてさらに利益が出ているからますます繁栄し猛威を振るうことが出来るのです。
あなたが支払う高いお金で職員は夜ご飯を食べているのです。
一般的な会社にとって多くの利益をだすには単純明快です。
それは
「少ないコストで得たものを高額でたくさんの人に売りつける」
ことです。
これが意味不明なツボやDVDという風に対象商品が変わると途端にマルチ商法をする人と認定され人間失格の烙印を押されます。
私は先ほどカジノで例えましたがカジノではお金とお金で交換が起きるマネーゲームです。
カジノ側もリスクを負います。
ツキが来てぼろ儲けされることだってあるでしょう。
しかしそれでもカジノが世界中で運営され続けている理由は利益が必ず出ているからです。
これは意外なことですがカジノの長期的な期待値は一番期待値の低いスロットでも95%の期待値があります。
ほぼほぼイーブンな状況にして、カジノがそこにあること事体で外資を誘致したり観光客を集めるのが目的ですのでそれはそれで経営戦略は理にかなっています。
しかし受験、特に予備校になると話は全く変わります。
予備校では紙に問題を刷って高値で売るという商法ですからリソースは事実上無限です。
模試もかなりのビジネスチャンスで一回の模試で8000円近くも利益を出せます。
長期休みの講座になると90分×5回で18000円とこれに関しては苦笑いすら起きません。
私のnoteを全て買っても13000円も行きません。
noteに合格できるノウハウが書かれていますが予備校は合格の仕方自体の的を得た答えはくれません。
私からすれば各予備校同士がグルになって行うぼったくり商法にしか思えませんでした。
☆なぜ予備校含めた受験産業は儲かるのか?
なぜ紙に問題印刷したらこんなに高値をつけて儲けることができるのでしょう。
その理由は
・予備校に通う本人または両親が受験において予備校以外に有益なものはないと思っている
・「情報を扱っているから」「情報に価値はあるから」と主張できる
というものでしょう。
情報というのは恐ろしいもので実態はないがお金を生み出せます。
私がnoteに載せている情報も家庭教師という案件なら1時間4000円前後のお金を発生させます。
予備校もその原理で高値をつけて何もかも売りつけてきますが本当のことは誰も言いません。
本当のことを言うと予備校に来なくなり利益が減るからです。
その本当のことというのは
「受験情報は予備校にのみあるのではなく、ネットで数分探せば合格者の軌跡を調べることが出来る。予備校が売りつけてきた、夏期講習の20(4題×5回)題18000円は書店に行けば200題1200円で手に入る」
という事実です。
受験は情報戦とかよく言いますが、戦いというよりは効率的に合格へと進める情報をいろいろ調べて自分の中に落とし込めばよいだけです。
予備校の問題もべらぼうに高値が付いていますが書店にいけば私を含め多くの合格者がこなしてきた良質な問題集がかなり手ごろな値段でずらりと並んでいます。
講座には喜んで入金するのに参考書となるとお金を出し渋る人がたまにいますがそういう人は何を得るためにお金使うかを全く理解できていません。
お金は使えばいいという訳ではないですが使うなら為になることに使いましょう。
医科歯科の最寄りの駅前で大手予備校の人が夏期講習のパンフレットを笑顔で配っていたのを見たことがあったのですが詐欺師にしか見えませんでした。彼ら自覚ないでしょうけど。
☆予備校に時間を投資しようとしている人へ
予備校のすべてを批判するわけではありませんがこれを読んでくれている人に言いたいことは
何もあなたまで予備校に課金することはないのですよ
ということですね。
予備校の良い所もたった1つだけあります。
それは個別に質問したらすぐに教えてくれることです。
授業などは受ける必要性は間違いなく0ですが分からないところを長時間かけて悩むよりすぐ人に聞いたほうがいい場合があります。
数学や物理で「なぜこの式が来るのか」「なぜ力はこの方向にかかるのか」などを素早く聞いて納得してすぐ自分の勉強に戻るのが重要です。
予備校に長く居続けると友達が出来、慣れが生じてきます。これは良くないことで自分の目的がぶれたり油断やスキが生じます。
noteをちゃんと読んでくれていたら合格するための問題集をちゃんと設定しているはずで、合格計画に友達や周りの環境は出てこないはずです。
頭は常に自分の目標達成のために集中して使うことを強く意識しましょう。
第7章
夏休みの受験勉強で夏期講習ほど恐ろしいものはありません
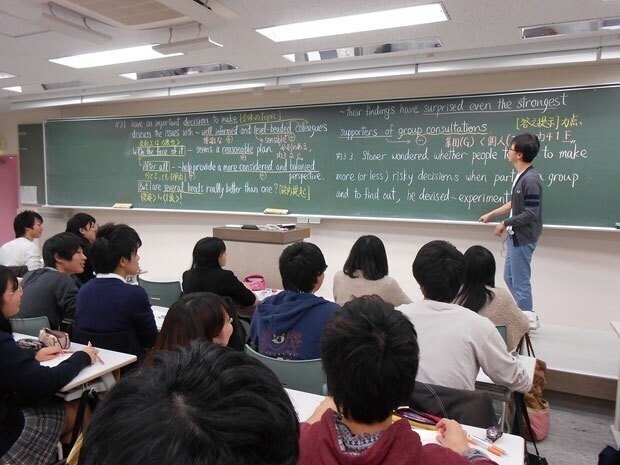
夏になると各大手予備校が大盛り上がりします。
それは「夏は天王山」とかいう非論理的なキャンペーンを打ち出し夏期講習という名の、得られるものに対して法外な値段を吹っ掛けるビジネスが面白いように上手くいくからです。
いきなり強い口調で話してしまいごめんなさい(笑)
ですがこのキャッチコピーよく考えてみるとおかしな話だということが分かります。
恐らくこの
「夏は天王山」
「夏を制すものは受験を制す」
などという言葉は大学進学予定者が多い非私立高校の現役高校生に向かっての言う場合にのみ適用です。
まず大学進学実績の良い中高一貫私立は先取りで授業が進みます。
そうすると早い時期で勉強が終わり高3ぐらいには正直学校に行く必要がなく独学しています。
現に灘や開成はそういったシステムで(もちろん公式の行事にはいくだろうが)自分の好きなように勉強方法を選択できる環境にあります。
しかし非私立の高校はこうは自由度がききません。
夏休みはあるだろうが終わったらまた学校です。
高校側も「夏=天王山=最も重要」という認識があるなら最初から9月からも夏休み状態にして生徒に好きに時間を使わせてやれよ、と思いますけどね。
学校に縛られず自由に勉強できる夏が最も大事だと言っておきながら、
「でも9月からはまた学校に来てね」
と言うのですから矛盾していますよね。
次は1番おかしな話です。
自分で好きに勉強していいはずの予備校の中でさえもこの言葉が横行しているのです!
この章では
・予備校生に対しての「夏は天王山」は明らかに筋違い!
・季節なんて本当は関係ない!
・学力アップは独学が最も早く効率的!
について解説しています。
私は塾が嫌いなんじゃなくて、もっと簡単に考えれば合格最低点を上回る知識を身につけることができるよということをもっと広めたいです。
予備校に1年間必死に通って予習復習欠かさずしてきたのに落ちてしまうと自分に絶望してしまうような受験生も中にはいるかもしれません。
実はそうじゃないんだよということをこのnoteを通じて実感してください。
☆予備校生に対しての「夏は天王山」は明らかに筋違い!
単刀直入にいって浪人生や進学校の高3には天王山とか関係ありません。
なぜなら彼らは「学校の授業」に時間を拘束されないので自分の好きなように勉強計画を立て好きなように勉強できるからです。
このような状況ですので予備校の浪人生を対象にした「夏は天王山」は意味が通りません。
このことを面談で平然と親御さんの前でもいってしまうチューターなど本当に残念でなりません。
おそらく彼らはそのことに気づいておらず、本当にその塾の講習が最もいいと思っているから勧めてくれるのでしょうが実際はそうではありません。
少し話変わりますが、何もわかってない人からのアドバイスほど自分の役に立たないものはありません。
その人のアドバイスが有益であるかを判断するコツは
・とにかく具体的で実現可能でコスパが良いか
・その内容と自分の今知る違う方法と照らし合わせてどちらが目的達成のために得るものが多いか
この2つを常に念頭に置いてその人のアドバイスを聞くようにすると自分でもだんだん良い選択ができるようになります。
話を戻します。
要は本当ではないことをあたかも本当のこととして嘘がまかり通っているのを見ると悔しい気持ちになります。
浪人生を対象にした大手予備校が
「夏こそ受験で最も重要」
「間違いない学力アップ」
と大きな広告をかかげ生徒の親から法外な金額をふんだくっている今の受験社会を見ると辟易してしまいます。
☆季節なんて本当は関係ない!
先ほど挙げた1つ目の「夏こそ受験で最も重要」という言葉はウソです。
受験の本質ではありません。
受験で最も重要なのは
受験当日に向けた今の自分にない知識をインプットするための毎日の勉強
です。
夏だけ気合を入れるとか夏だから前期の総復習をしようとか愚かなことはやめましょう。
まず気合ですが日々の勉強をインプットに専念すると頭を絶対に使い続けるので「覚える」という気合は自動的に入ります。
時間で測るのではなくノルマで測るのはnoteで散々言ってる通りです。
前期の総復習するのはいいですが夏の期間ごっそりインプットしない時期を作るのは自殺行為です。
大きな時間のロスです。
もっと言ってしまえば4月にやった問題を8月に総復習なんて忘れているに決まっています。
私を含めそんな昔のことを覚えている天才は中々いません。
復習は次の日、1週間後、1ヶ月後と短いスパンで何度もしましょう。
私の場合はある日の勉強時間が10時間だとしたら、4時間は復習、6時間はインプットに費やしていました。
☆学力アップは独学が最も早く効率的!
先ほど挙げた2つ目の「間違いなく学力アップ」についてですが、これはホントです。
なぜならやらないよりやる方が確かに学力はアップします。
しかしほとんどの詐欺まがいの文句です。
具体例を挙げましょう。
ある大手予備校の数学の夏期講習は90分×5回で17000円ほどです。
だいたい一回の授業で解説する大問は4つですからこの期間で20題分ですね。
しかし予備校の授業の恐ろしい所は生徒に予習を求めます。予備校のテキストには答えを付けると人が来なくなるので答えを付けていません。自分で解く力を養成する目的などといった意味不明の文言を並べてきて答えを予備校は渡してくれません。
次の日の数学の90分授業のために前日の晩にウンウン2時間唸ってやっと答え解けたとかいう生徒を見ているとかける言葉すら見つかりません。
次の日の授業中の90分はただボケっと答えがあっているか聞いているだけでこの間新しい知識は何ひとつ身に付きません。
もっといい方法があります。
こんなに時間とお金を無駄にして数学20題に17000円払うよりも書店で1500円払えば、数学の問題が200題載っている本が手に入ります。
どちらが自分にとって最善かは自分で考えてみてください。
一つ言えることは授業に出ればその問題が次の日に自動的にできるようになる魔法はこの世に存在しません。必ず受験当日までにその問題を頭を酷使して覚えなければなりません。
第8章
秋の受験勉強で合格のためにやるべき3つのこと

受験生にとって秋という季節は大切です。
具体的には9~11月を指します。
この時期での勉強へのアプローチで冬に入った段階での成熟度がまるで違います。
よく予備校や高校教師が
「夏を制するものが受験を制す」
などとよく考えてみれば非論理的な文句を垂れていますね。
私からしてみれば、年中時間は平等なのだから夏だけ本気でなく毎日のインプットこそが受験を制すと言いたいですね。
しかし、もし受験当日までの準備の中で1番点数を上げるのに必要な時期はどれかと聞かれたらそれは間違いなく秋と断言できます。
なぜなら
秋の時期に数学や理科の標準解法を頭に定着させ、典型問題が解けるようになるためのインプットをするから
です。
ここでいう標準解法とは、
理科なら「重要問題集」
数学なら「1対1対応の演習」「Focus Gold」「青チャート」
に乗っている問題の解法を指しています。
インプットする量が大幅に変わるわけではありません。
春も夏も秋もだいたい1日の勉強時間自体は大きく変わらないでしょう。
しかし春と夏は秋と冬の爆発に対する投資という側面があり、インプットしていることが点数としてダイレクトには反映されにくいのです。
コツコツ単語や熟語を覚えたり照井式や物理教室などの理解用の参考書をこなしている春や夏は秋以降の時期の勉強のための基盤の時期です。
この時期にしっかり長文を読みこなす知識や、重要問題集を理解できる下地が整ったらあとは秋から問題集の解法を覚えまくれば点数が大幅に上昇します。
今言ったことを自然にやっているのが
秋以降に成績を伸ばし現役合格する受験生
です。
この章では
・秋に数学や理科で目を咲かせよう!
・英語の長文は毎日必ず!
・センターは古典と社会だけは形にしておこう!
という3つに分けて説明します。
この章に書いてあることが分かれば秋以降の成績の伸びのカラクリが分かります。
☆秋に理科や数学で芽を咲かせよう!
夏までに化学や物理における理解用の参考書をある程度復読し、典型問題集に入れる下地ができているとします。
▪️化学の場合
化学は「重要問題集」に取り掛かりましょう。
全275題なので1日5~6題ずつこなしましょう。
そうすれば2ヶ月かからず終わります。
2周目からは1日10題ずつこなしてできる問題に印をつけておきましょう。
3周目からは印のついていないところだけ1日10題ずつこなしましょう。
1日5題だの10題だの量が多い気がしますが化学ではこれぐらい大丈夫です。
化学は物理とは違い、知識問題が半分弱あるので知識さえあれ解けば即答できる大問が多いです。
例としては、大問1個の中に(6)まであって(1)~(5)までが知識問題で(6)だけ計算問題と言った構成の大問も多いです。なので1日5~6題でも余裕でこなせます。
知識問題として問われて分からなかったところはまた繰り返し「照井式」を読み返しましょう。
しかも2周目からは問題復習する際にメモすら取る必要がありません。
問題と解答を同時に開いて目で見て復習するだけです。1回理解したかしかけた問題なのでかなり早くこなせます。
▪️物理の場合
物理は「重要問題集」か「名問の森」に取り掛かりましょう。
どちらも160題弱なので1日3題ずつこなしていきましょう。
物理の場合は化学と違い、知識のみを問う問題が出されないので初めて頻出問題集に取りかかる場合は1日3題ほどがいい目安です。
そうすると物理も2ヶ月かからず終わります。
2周目からは化学と同じ要領で復習する問題数を増やし、目だけでもう一度確認します。
化学も物理も他の人と差がつくのは、この目だけでもう一度頭の中で認識する復習です。
たいていこのレベルの問題集やったのに不合格という受験生の場合はたいてい1~2回解いて終わりです。
問題集は単なる本です。
解くことは目的ではなく1つの手段にすぎません。
本当の目的は載ってある問題の解法を完璧に覚え、反射で解けるようにすることです。
そこの認識を間違えないようにしてください。
▪️数学の場合
数学は「やさしい理系数学」「スタンダード演習Ⅲ」に取り掛かりましょう。
「1対1対応の演習」が終わっていることが大前提です。
やさしい理系数学の方は200題ぐらいありますがこの問題集の素晴らしいところは別解の豊富さです。
1題につき平均3弱の解法を示してくれるので読み物として非常にいいです。
とにかくこのレベルの数学の段階で大事なことは
自力で解ける解けないよりも、圧倒的な量の解法に触れて覚える
ことです。
90分でやさ理を6題するとしたら感覚では15分問題考える時間、後の75分は解答を読みまくって理解しまくることですね。
解答読むとき鉛筆とかいりませんからとにかく目で追って解法を認識しまくって頭に定着させてください。
「1対1」と「やさ理」が終わったら地方旧帝大以下なら数学でアドバンテージが取れるレベルになります。
ここから余裕があればさらに「スタンダード演習Ⅲ」に進みます。
理系大学でスタンダード演習をする余りにも大きい意味は数学の記事にも掲載されています。
なぜ「スタンダード演習1A2B」じゃないかというとその範囲はやさ理までで十分だからあえて1A2Bの問題集をまたする必要がないからです。
☆英語の長文は毎日必ず!
夏までで文法問題集、単語帳、熟語帳、英文解釈、英作暗記を一通り終えているとします。
つまり長文を精読できる下地がある程度は付いてきたとします。
基準でいうとセンター試験レベルの英文ならほぼ全て正確に訳せる状態です。
そうしたら毎日長文を2題、最低でも1題読みましょう。
今、私が長文を「解く」ではなく「読む」と言ったのには理由があります。
入試英語の長文問題で聞かれることなんて文章を訳せていれば誰でも解ける問題しかないからです。
試しに中2に長文と問題の全訳を渡して問題に答えさせたらほとんど満点を取るでしょう。大学入試レベルの英語の問題で日本のセンター現代文並みの読みの深さを問う大学なんか1つもありません。
全訳できれば勝ち確定です。
なぜ「解く」ではなく「読む」と言ったかというと
問題なんか解く時間がもったいないから読んで全訳を確認すればそれで十分
ということを強調したかったからです。
時間の節約にもなりますし、英文を読む敷居も下がるのではないでしょうか。
☆センターは古典と社会だけは形にしておこう!
上の書いた数学と理科と英語の内容をこなしていればあとはセンター対策となります。
理系科目で上の内容をこなしているにもかかわらず、しなければならないセンター対策は
・数1Aの図形
・英語の発音、アクセント
のみです。
理科は二次対策をしていたら自動的に満点近くまで行きます。私が医科歯科志望だったということもあるでしょうけど。
私は重要問題集をこなした後にセンターの問題を買ってきてたまに解いても
化学は毎回100、物理は毎回96か100でした。
センターの点数は別に96だろうが100だろうがそんなに神経質にならないように意識するといいです。
つまり上記2点が理系科目で別に覚えなきゃいけない項目です。
しかしその2つは年明けからでも間に合います。
問題は古典と社会です。
古典は単語と文法さえ頭に入れておけば、演習の際にそれらをもう一度認識できるのでこの時期にセンターレベルは満点でなくてもセンターレベルの問題自体には触れられるようにしておきましょう。
・単語は600語クラスのハイエンドのもの
・文法書はマドンナ古文、漢文ヤマのヤマ
を私は使っていました。
この時期はメインの科目が忙しいですから知識が夏までに入れておきましょう。
そしてメイン科目の休憩としてたまにセンター演習で十分です。
社会は4月から対策しましょう。
対策といっても書店で大量に並んでいる黄色い「〇〇が面白いほどよく取れる」シリーズ1冊で十分です。
地理選択の私は地図帳も見ながら読んでいましたが、日本史世界史選択の人は資料集を横に置いて読みましょう。
それを4月から何周も読みましょう。
1~2周ではダメです。
秋ぐらいまでに5周ぐらい読んでいると秋にはいきなり過去問を解いても9割近くいきます。
あらゆる勉強で「反復」というのは絶大な効果があります。
・反復の際には前の反復よりも明らかに少ない労力でこなせること
・頭への定着度が段違い
受験では理解したことを頭に定着させる反復が最も重要なことの1つです。
第9章
決して天才ではない!東大や医学部に現役合格する人たちの正体とは!?

東大や医学部には大体半分以上が現役合格です。
医学部の中でも都市圏の難関大になればなるほど現役合格の割合が高くなります。
医科歯科でも私の入学年度は65%以上が現役で、例年もそんなもんです。
私は一浪です。
高校生の頃は、高3の夏頃からはさすがに勉強しましたがそれまでは授業でもよく寝るし定期テスト前だけには一生懸命勉強するタイプでした。
高校生の時にも浪人している時にも現役合格できるやつらと何が違うのだろう?という疑問は常に私の中にあり、その理由を考えていました。
初めて思った瞬間は、
勉強量が違うだけ
と思っていましたが、もっとこう、具体的に要因を知りたかったのです。
浪人が終わる年明けごろからは何となく答えはでかかっていましたが大学に入学して確信に変わりました。
多くの現役合格してきた友人に具体的に話を聞いて「なるほどやはりそうか。」と確信し予想は間違っていませんでした。
この章では
・東大や医学部に現役合格する人たちの勉強パターン
・高3始まりまでに出来ておくべき数学と英語の基礎
・東大や医学部に現役合格するための他の科目の勉強法
について解説します。
現役合格する人たちの正体がつかめれば、今の自分に照らし合わせて合格への筋道も立てられるでしょう。
☆東大や医学部に現役合格する人たちの勉強パターン
東大や医学部に現役合格する人たちの特徴を端的に書きます。
それは
高3始まりまでに英語と数学を積み上げている人たち
です。
これは旧帝大以上の難関大になればなるほど当てはまり、現役合格の基盤といってもいいです。
難関大に現役合格する人で高3になるまで英語も数学も受験勉強を始めていなかったというのはごく少数です。
「いやいや、有名進学校で東大に現役合格した人の体験記には高3の6月の体育祭の後から勉強したら間に合いました。って書いてありますよ!」
と思う人もいるかもしれませんが、これ大体は違います。
この合格者たちは、自ら進んで問題集を足してやったり、国語や社会を自分だけでやり始めたのがこの時期というだけです。
この時期には数学や英語の基礎はたいていの進学校の生徒なら出来ています。
なぜなら鉄緑会や駿台の英語か数学または両方を、高校生の頃に部活を続けながらもこなしているからです。
彼らは数学や英語の基礎はできているので、あとは理科2科目と国語と社会で受験当日に点が取れるよう知識を入れるだけです。
理科の記事にも書いてありますが理科2つは両方合わせて6ヶ月あれば、
読み流し用の参考書
↓
理解して問題集
↓
典型問題の解法を暗記
↓
復習してメンテナンス
のサイクルを終わらせることができます。
実際に私もできました。
現役合格の人の多くは高3初期や夏から理科始める人も多いのです。
次にどの段階が数学と英語の基礎ができていると呼べるのかについて書きます。
1番いいのは実際の数学の入試問題にも手を出せて、二次の英語長文もばんばん読めるぐらいがいいのですが。
ここでは最低限これをできるようにしておくと、高3から非常にうまく他の科目にも力を入れられるという基準を示します。
☆高3始まりまでに出来ておくべき数学と英語の基礎
▪️数学
高3の始まりの時までに青チャートかFocus Goldなどの標準的な解法が網羅されている問題集1冊を一通り終えていることが目安です。
難関大ではなく地方国公立の場合は黄チャートでもいいです。
標準的な解法が身についていると1対1対応の演習を終わらせ、やさ理やスタンダード演習に移るのがスムーズで負担が減ります。
▪️英語
高3の始まりの時までに高2の時点で受けるセンター本試で150点以上が目安です。
私が高2の時に受けさせられた英語の本試は80点行きませんでした。残念です。
この時期に英語で測りたいのは文法問題でも単語でも熟語力でも英作力でもありません。
長文を読める下地があるかどうかです。
上記4つは知識として高3からでも全然間に合います。
ただその4つも不十分で英文読むのもほぼダメという状態なら高3の時に英語に多くの時間を割かなければなりません。
高1,2のときに理科にばかり力を入れていた人で現役で東大や国立医学部に合格した人は私の知る限りではごく少数です。
またデータ的に見ると入学偏差値が55前後で東大や国立医学部に多数の合格者を出す高校は高1,2のときに英数に力を入れています。
しかし入学偏差値が60を超えているのに東大や国立医学部の合格者が少ない高校は高1,2の頃からやたら理科に力を入れています。
何が言いたいかというと
高3になるまでは理科ではなく、英数に力を入れるべき
ということです。
理科は高3から始めても東大の入試で50/60は容易ですが
数学は青チャートも終わらしてないのなら60/120も怪しいです。
英語は全大学全問題そうですが長文読解ができたらかなり高得点が取れます。
実質、単語と熟語と文法問題の知識はより2次試験で出るレベルの長文読解の精度を上げるために必要なのです。
だから高2の時点では知識がそこまで要求されないセンターレベルの英文が読めるかどうかが大事なのです。
☆東大や医学部に現役合格するための他の科目の勉強法
高校生ははっきり言って忙しいです。
文化祭も体育祭もあるし昼休みには友達と校庭でサッカーしなければなりません。
そんな中現役合格してきた友人たちの体験談も交えて書きたいと思います。
▪️理科2科目
高3の夏に入るまでに頻出問題集に入れるまでの下地を作らなければなりません。
ここでいう頻出問題集とは、
物理なら「名問の森」か「重要問題集」
化学なら「重要問題集」
です。
ここでいう下地とは、
読み流し用の参考書で科目の全体を理解して問題に対応できるようにする
ということです。
その読み流し用の参考書ですが1冊で全て済むかつ分かりやすく、1冊で東大レベルまで対応しているとなると
物理なら「物理教室」
化学なら「照井式解法カードシリーズ」
です。
▪️国語と社会
古文と漢文は知識を入れてセンター演習だけで十分です。
単語帳や文法書、使い方などは国語の記事をみてください。
社会は「センター〇〇が面白いほど取れる本」を何回も読みまくってあとはセンター演習だけで十分です。
その本じゃ取れないという人いますが、読み返しが足りなさすぎます。
何回も読みましょう。
国語と社会の勉強ですが、普段は数学と英語と理科というメイン科目で忙しいです。これらの勉強の休憩がてらにやりましょう。
社会の本の通読は厳しいですが古文単語などは気分転換も兼ねてカフェでも覚えられます。
第10章
高校生が早い段階でしなければいけない科目はこれ!

高校1,2年生が現役で合格するためににやらなければいけない勉強とは何でしょうか?
それは数学と英語と断言できます。
高2の終わりまでに基礎を仕上げておくと高3での本格的な受験勉強が非常に楽になります。
理科や社会や国語など高3の1年間の間に余裕で間に合います。
理科を仕上げることのできずに現役時に不合格になった大抵の人はこのnoteに書いてある理科のコスパの良さと重要性に気づいていないかもしくは数学と英語に時間を取られすぎたパターンです。
受験において理科はたいへんコスパが良く数学に比べて圧倒的に解法暗記する量が少ないです。
扱うものも元素や物理現象など無味乾燥な数字ではないのでイメージが付きやすいので一度得点できるようになったらそこからは点数は下がりません。
大学の中には、数学100点と理科2つで200点という配点の大学すらあります。
受験当日では理科の仕上げ具合が合格への必要条件です。(十分条件ではありません)
覚える問題量の具体例を挙げると数学は1対1対応の6冊だけで350問以上あります。
しかし物理の名問の森は上・下で150問程度しかありません。
これだけ覚えれば東大の問題にも対応できるので理科におけるコストにおけるパフォーマンスは素晴らしいです。
この章では
・高校生がしておくべき数学について
・高校生がしておくべき英語について
について解説しています。
高校性を指導する立場にある方もこの基準を目安にしていくと良いです。
☆高校生がしておくべき数学について
結論から言うと数学で言う基礎とは
高2の終わりまでに青チャートやFocusなど高校数学を体系的に網羅している問題集の数3までを解いている状態
にすることです。
2年間で数学これだけやればいいのですから簡単です。なので高2の終わりまでに必ず出来るようにしてください。
これをしていると高3に入ってからはある程度インプットされた状態から3~4冊の軽めの頻出問題集でインプットをして過去問集を解くだけなので非常に楽になります。
その分理科に時間をかけることができ受験を大いに有利に進められます。
頻出問題集については数学の記事で紹介しています。
なぜ最初から頻出問題集ではいけないのかといいますと、これらは体系的な問題集ではなく頻出問題を集めたものだからです。
なので重要性は高いのですがまったくインプットしたストックがないと解答の意味が頭の中で繋がらず良い効果が生まれてきません。
青チャートで見たことのある解法なら解法を読んだときに、
「これは見たことあるから理解できる。そうかこれが頻出問題で特に重要なんだな。」
と認識できます。
私は1年間で青チャートからスタートして新数学演習まで行きました。
夏の終わりぐらいから頻出問題集に入りインプットのストックがあった秋の模試では成績がかなり上がりました。
☆高校生がしておくべき英語について
結論から言うと英語で言う基礎は単語・熟語・構文読解です。
この中で1番大事なのは構文読解です。
単語と熟語は構文読解をするための材料でしかありません。
ロイヤル英文法などの文法書を読むなど、はたから見るといかにも英語を根本から理解しようとしているように見えますね。
しかしこれ全くの無意味かつ非効率です。
自動車に乗るためにエンジンの仕組みについて理解する必要はありません。運転さえできれば卒検も難なく合格です。
「私はエンジンについてはずっと勉強してきたのにぃ」とか思っても誰も聞いてくれません。
大学受験で言う運転とは「長文読解ができる」ことです。
受験英語では長文の意味が取れるとかなりの高得点が狙えます。
ほとんどすべての大学の長文問題の英語の問題ではいろいろ聞き方は変えても結局は正しく訳せているかどうかしか聞きません。
そのためには長文を構成している単語と熟語の知識を積み上げていくことが必要不可欠です。
高3までの学校の授業で触れた文章は必ず全訳できるようにしておくことや構文読解専用の参考書を1冊仕上げるぐらいをしておきましょう。
英単語・英熟語・構文読解の参考書については英語の記事で紹介しています。
とりあえず英語の知識を早いうちから詰め込むというのは重要です。
暗記というのは頭を使うので高3になってからの解法暗記と並行してこれらをこなしていくには少しだけ大変です。
できないことではないですが早めにできるなら早めにできて悪いことなど一つもないです。
さらに英語は文系理系どちらともで必須科目であり、英語の配点は各教科の中で同率か一番高いことが多いです。
しかも文章読めればかなりの高得点が見込めるので読める人と読めない人では雲泥の差になります。
受験英語で高得点が取れると他の科目で余裕ができるので楽という側面もあります。
受験に時間的余裕のある高校生は今のうちに知識を詰め込んでおきましょう。
どうせ結局後でやることになるのですから。
第11章
「現役生が入試直前に伸びる」と言われる理由の正体

「現役生は入試直前まで伸びる」
こういう話を聞いたことありませんか。
最近の受験事情に疎い大人や現役高校生でも多くの人が知っている有名な言葉ですよね。
私もドラゴン桜などを見ていて何度も耳にしたことがあります。
実際にこれは本当によくある話です。現役生は秋から入試直前までに急激に伸びそのままの勢いで現役合格してしまう。
ではその理由は何でしょう。
・高校三年生の9月から翌年2月にかけては神様が一律で全国の高校生にくれた確変期間で、何を勉強しても直ちに頭に定着するから?
→そんなSF話はありませんね。
・現役生は浪人生と違って学年で結束してお互いに気持ちを支えあっているから?
→残念ながら学年で結束しても自身の知識は増えません。無敵の結束力で替え玉受験したら二度とそこを受験できないでしょう。
・やはり現役の高校生は現役で入りたいって気持ちがあるから集中して目の前の勉強に取り組んでいるのでは?
→現役生であろうが浪人生であろうが集中する人はしますし、しない人はしません。それに何より気持ちや集中といったことは直接的なこの現象の答えにはなり得ません。
もちろんいずれも的を得たものではありませんね。
この章では
・現役生が入試直前に伸びる理由とは
・現役生だから伸びるという言葉の本質
について解説します。
私の見解ですが多くの難関大現役合格者と現役不合格者を見てこの結論に至っています。
☆現役生が入試直前に伸びる理由とは
結論から言います。
それは間違いなく理科です。
現役生で入試直前まで成績が伸びるのは夏までに理科の理解用の参考書をこなした人です。
つまり頻出問題集に取り組める下地がある人です。
その人は秋以降に一気に問題集を進め受験に必要な典型的な解法を身につけるのです。
物理の重要問題集が150問、化学の重要問題集が270問ですから2か月もあればどちらも余裕で1週することができます。
秋から年末にかけて2~3周し年明けから過去問に取り掛かっても普通に合格までの点数が取れるような状態になります。
難関大を受ける場合でも、問題数が少ないかつややハイレベルな薄い問題集などで適宜補完していけばどんな入試理科でも高得点が狙えることは間違いありません。
逆に数学は長い時間をかけなければいけません。
なぜならシンプルに量が多く以前の内容が理解できていないとそれが理解できなくなるという積立式の教科だからです。
しかし理科では問題の大半は独立しているので、理解して覚えればすぐ身に付く問題が非常に多い科目です。
高校3年生の秋から冬の3ヶ月弱で典型問題を集めた問題集を1冊仕上げればモノにすることができる非常にオイシイ科目です。
さらに理科の配点は理系入試において大きく、一度高得点が取れるようになればそこからテストによって上下落することが少ないので
「理科を仕上げた」=「入試で一番点を取りやすい科目をモノにした」
ということに繋がり、それはすなわち合格最低点を越えるためにかなり重要です。
☆現役生だから伸びるという言葉の本質
多くの現役合格者は数学や英語をぼちぼち高2ぐらいから積み上げていくので、偏差値は一次関数的に上昇するグラフになるのはうなずけます。
しかし受験直前になると現役合格者は理科の問題集をだいたいみんな仕上げるので成績が曝上がりします。
これが現役生の成績グラフが指数関数的に上昇している理由です。
彼らは受験直前期だから死ぬ気で集中して数学の点数を100点あげたのではなく、元々ほとんど点が取れなかった理科で高得点が取れるようになっているのです。
つまりこれらのことから「現役生は受験直前期まで伸びる」というのは単なる現象であって本質ではないということが分かります。
彼らは単に理科に本腰を入れたのが高3からでだいたい秋から冬にたまたま問題集を仕上げる人が多いというだけです。
集中力が上がるから(もちろん受験期になると少しはモチベーションも上がるでしょうが)といった単純な理由ではありません。
高3はたまたま時期的に秋から冬にかけて解法を覚えますが、大学受験では別にその時期に覚えるという決まりはありません。
いつ覚えても問題集の内容は変わらないので早く覚えて悪いなんてことはまったくないです。
そういう人はごくまれにいる「受験勉強は夏で終わっちゃった」人の正体に繋がります。
いつ問題集の知識を覚えても一緒です。浪人しているから頭悪いとか思うのではく、とにかく理科の典型問題集を1冊完璧にして下さい。
頭が悪いから浪人するのではなく現役生でも理科を仕上げきれなかった人がまず浪人するし、大切なことは頭の良し悪しや思考力よりいかに受験当日に点を取るための必要な知識がストックされているかということです。
理科がいかに入試にとって大切かということですね。典型問題を覚えてない人はさっさ覚えてしまい受験当日に備えましょう。
第12章
参考書・問題集を中心とした独学の3つのメリットとデメリット
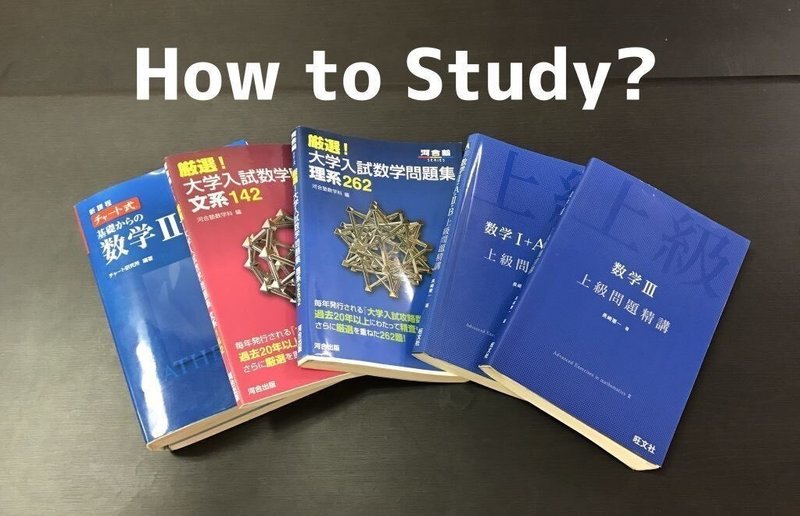
突然ですが受験においてあなたを最も直接的に合格に導いてくれるのは何でしょうか?
「高校の時の先生、予備校の人気講師、予備校のテキスト、予備校の模試、志望大学の過去問、勉強のできる友達」のうちどれだと思いますか?
残念ながら答えはこの中にはありません。
特に浪人生にいますが受験生の多くに見られるのは予備校の人気講師を崇拝して盲信してしまうことですね。
ここで考えなければならないことが2つあります。
1つ目です。
人気講師はその科目において他の講師より教えるのがうまいかもしれません。しかし受験当日にあなたの代わりにその問題を解いてくれるわけではありません。
崇拝していいことは何もありません。
人気講師の授業に大金を払って長時間受けるより効率的にその講師の言っていることを頭に入れる革命的な方法があります。
それはその人が出している本を買うことです。
2つ目です。
なぜその人が人気講師になったかということです。
教え方がうまく、口コミで評判が広まったのでしょうか。
違います。
予備校に個人として在籍するのは多浪を除けばせいぜい2年です。また下から新しい予備校生が生まれるサイクルです。
そんな短いタームで口コミだけでは人気が出ないことは少し考えればすぐわかります。
ではなぜか。
答えはその講師の書いた参考書・問題集が合格者から好評だったからです。
本が有名すぎて人が有名になるのです。
だから人気講師だからといって無条件にその人を盲信するのは誤りです。
崇拝するならその人の参考書・問題集の方を崇拝しましょう。
話を戻します。
冒頭部分の問題の答え合せをしましょう。
受験においてあなたを最も直接的に合格に導いてくれるのは「問題集」です。
この章では
・参考書・問題集を使った独学のメリット
・参考書・問題集を使った独学のデメリット
について解説します。
デメリットはこのnoteに書いてあることを実践すればなんてことないのですけどね。
☆参考書・問題集を使った独学のメリット
①自分で計画を立て、全て自分でペースを決められる
まず何よりも自分本位で勉強を進められます。
自分の目標とする大学の問題のレベルに対応した問題集を終わらせればその科目の受験勉強は終了です。
こんなことを書くと、
「いやあなたは一人で進められるからこんな勉強法を進めて来るのでしょう」
「私は誰か近くでサポートをしてくれないと勉強できない」
といった人も中にはいるでしょう。
化学の記事を読んでもらえればわかりますが私は化学を高3の夏までまともに授業すら聞いたことなく元素記号も最初の4つしか言えませんでした。
つまり0から参考書と問題集で独学しただけです。
頭がいいから、と思ったかもしれませんが最初から目標とする問題集どころか重要問題集すらも全く解けない状態だったので初学者からでも入れる参考書から始めました。
それでも医科歯科の化学で合格点が取れるくらいには準備できました。
そして何より参考書や問題集は受験生の頭を悩ませるために書かれた本ではありません。
合格するのに必要な知識を教えるために書かれた本です。
②圧倒的に時間を効率的に使える
このポイントがこそ私が1年間でどんな大学でも合格圏内に持っていけるなと確信できた要因です。
予備校の授業では数学も理科も90分授業で大問4つしか扱ってくれません。
しかも予習を前提としているので答えもついてないテキストの問題をウンウン前夜に考えなければなりません。
私からすれば時間が足りず何浪もしなければ目標の大学には受からない計算になります。
18~20の時期を大学受験専用の勉強に費やしたくありませんでした。
1年で受かるには最も時間をかけずに最も多くの知識を頭に入れる勉強法を採用する必要がありました。
受験勉強には目安となる終わりがありますのでそれに向かって毎日問題集を淡々と進めていくだけでしたが確実に合格に近づいて行きました。
予備校の授業の前提は
「家でアウトプットしてきたことを授業で答え合せをし、できなかった問題を家で復習する」
ことですがここには問題点があります。
授業90分+予習60分+復習30分の合計3時間でMAXでも4問分しか頭に新しいことが入ってはいません。
書いてて涙が出てきます。
これは私からすれば、効率的に合格まで近づきたくない人がする勉強だとさえ思えてしまいます。
③全くお金がかからない
予備校の授業や講習を受ける場合と問題集買って独学する場合で費用対効果を紙に書いてみてください。
5科目合わせても5万円かからないと思います。
3月にやる参考書と問題集決めてしまえばそれ以降受験にかかるお金は受験費ぐらいなものでしょう。
ちなみに模試は東大阪大などのその大学の形式に対応した模試があるならば、一年のうち一回は受けるべきです。
それも「問題を解かなきゃ」ってよりは形式や雰囲気に慣れるためだけです。
夏に解けなくても2月下旬に解ければ受験は大成功なので8月に解ける必要性はありません。
なぜみんな夏のOPで打ちひしがれるのでしょうか?私には分かりません。(笑)
模試の記事にも書きましたがどれだけ出来てもどれだけ出来なくても全く何も感じませんでした。どうせ2/25の試験の日には合格点が取れるのだから途中はどうでも良かったです。
そもそも模試というのは自分の現在地が分からない人間が受ける試験です。
私は医科歯科の合格者が使っていた問題集を2/25までに完璧に解法暗記する、という至上命題さえクリアすれば確実に合格できることに気づいていたため途中で受ける模試など何点でも良かったです。
秋の河合の記述模試では偏差値80ぐらい行きましたが「こんだけ覚えりゃそりゃそだろ。」とだけ思っていました。
☆参考書・問題集を使った独学のデメリット
①明確な計画を立てられなかったら続かない
この時期までに大体この参考書は終わらしておく、といった基本的な中期計画を立てられない人は無理です。
そういう人の特徴は朝起きて、今日はどの勉強しようかなという思考に至ります。
そういう人は受験に向いていないので無理にでも予備校に行って人気講師を崇拝しましょう。
こういうタイプは志望が高いほど必要な知識も多くなるので、時間もかかります。
私のシミュレーションでは「予備校のみかつ授業の内容は完璧に抑える」という条件で医科歯科医学部に合格するとなると、最低3年は必要な計算になりました。
②人と話していないと不安な人には精神的に辛い
よく女の子にいると思いますが受験期とは不安に陥るものです。
それはきっと、結局当日は自分人の力でなんとかしなければならないからだと思います。
実際、言葉を交わしての会話には内容が何であれリラクゼーション効果があると言われています。
会話をすることはいいことですがこの場合では相手が問題です。
同じ予備校や同じ立場の人間と話すのはやめましょう。
なぜなら自分の計画と相手の計画は違うためです。
絶対に話している際に相手の進捗状況が不意に見えてくることがあり、深層心理で自分と比べてしまうことが必ずあるからです。
「人は周りから無意識的にも必ず影響を受けて行動選択をしている」とはなかなかに的を得た表現だと思います。
少し難しく書きましたが具体例を挙げると、
「あの人はあの問題集はまだ終わってないのか」と心の中で思ってしまうと必ずその後に心に隙ができます。
なぜ影響を受けるのが悪いかというと、相手と自分の勉強計画は全く異なっておりあなたの勉強計画には普段話す友達の名前も出てこないはずだからです。
受験時代に同じ立場の人と話してもしょうがないので話さないと不安な人は親とか受験に関係ない人にしましょう。
第13章
大学受験での問題集の選び方と正しい使い方

受験時代に成績を上げて合格へと導いてくれたのは、予備校の教師でも親戚からの激励の言葉でもありませんでした。
問題集が最も直接的に合格へと導いてくれました。
塾や予備校が合格に導いてくれていると思っている人は是非この章を何回も読んでください。
塾や予備校と問題集は実は同じことを言っているのです。
それは「問題」だと言うことです。
各科目の大問一つ一つが受験当日に必要な知識を着実に積み上がっていくのです。この章を読むと大学受験とは何か?合格するとは何か?がクリアに見えてきます。
今回はそんな大学受験で合格に必須である問題集について実際に私がやっていた選び方と使い方を紹介します。
この章では
・なぜ問題集をそこまで信じるのか?
・合格できる問題集の選び方
・選んだ問題集の具体的な使い方・勉強法
について解説します。
☆なぜ問題集をそこまで信じるのか?
浪人が決まり(2/26)、これから1年間という時間が与えられた私は
「どうしたら1年間で例年の医科歯科の合格者たちと同じ知識を得られるだろうか」
とずっと考えていました。
となると当然やることは、合格体験記をまず見ますよね。
これは基本です。成功した人をパクるのは基本です。
合格体験記を見てみると2パターンに分かれます。
・予備校の授業の予習復習を真面目にやってきた系女子
・塾にも通っていたけど問題集自分で買ってやってたよ系男子
大体この2パターンに分かれます。
なぜ男女で分けたかというと完全に私の偏見です。(笑)
ここで予備校の授業とテキストの問題について考えましょう。
テキストに載っている問題の出所はなんだと思いますか。
それは各大学の毎年の過去問です。
駿台の先生が凄すぎて、駿台オリジナルの問題なんかまずこの世に1問もないことを理解してください。
そんな問題作ったとしても、入試に出てない問題をドヤ顔でテキストに乗せても解いただけ損です。時間の無駄です。出ないのですから。
つまり予備校界隈の問題の出所はすべて大学の過去問であることに注意してください。
次に問題集に載ってある問題について考えましょう。
こっちはもっと分かりやすいですね。
こちらも全問題、各大学の過去問です。
ある問題集のカバーに次の、
「出版社オリジナルの問題搭載!」
「過去問を分析し、頻度の高いものを激選!」
のキャッチコピーなら、間違いなく前者を考えた編集者は荷物をまとめてオフィスを出ることになるでしょう。
誰も買いたいと思わないからです。
つまり受験生が大学受験までに勉強するすべての科目のすべての問題の大元は大学の膨大な過去問であり、それらが分析されて自分たちの手に届いている。ということに気づきました。
だから私は1年という短い条件を鑑みて、問題集を一人でガリガリ進めることを選択したのです。
なにせ同じ時間で進められる問題量が段違いですから。
☆合格できる問題集の選び方
すごくシンプルです。
「自分に合う問題集」
ではなく
「結果の出せる問題集」
を選ぶのです。
受験生の段階なんてほとんどの人がその科目で理3に受かる知識はないのですからたいていの人が言う「自分には合わない」は単に内容が理解できてなくて本のせいにしようとしているだけです。
「重要問題集は私には合わない」なんて言っちゃう人は中々に合格に近づくのは難しいです。
結果の出せる問題集の探し方も簡単です。
ここでのポイントは何を持って結果の出せるというのが言えるかということです。
それは「合格者たちが数多く使っていた問題集」です。
ここでのポイントは、合格者たちはその問題集を使ったとは言っていますがどの程度使い込んだかは分からないということです。
ですので、その問題集に書いてある問題を全部できるようにしておけば少なくとも例年の合格者よりは上の知識が頭に入ります。
しかし注意点は例えば化学で合格者は皆「化学の新演習」を使ってた場合、いきなりそれに取り組むのは無謀なので繋ぎの問題集を探しましょう。
それはたいていが標準的な問題集です。
たいていと言うかほぼ100%ですね。
数学なら「1対1対応の演習」
化学物理なら「重要問題集」
です。
他にも結構多くの合格者が聞いたことがないような問題集をやっていたらそれも必ずチェックしましょう。
その大学の傾向(=出やすい分野がある)に沿った良い問題集のはずです。
次に実際に今の自分の学力と照らし合わせてやるべきふさわしい問題集かどうかを判断するポイントを説明します。
それは問題集の存在意義から考えてみましょう。
問題集とは自分に足りない知識をそこから得るためだけに存在しています。
だから、パッと書店で手に取り8割以上わかる問題集など自分にとってはなんの価値もありません。
ベストなのは3割分かるけど7割は分からない問題集です。
逆に1割も分からない問題集など買って周りの受験生を威圧するのも時間と金の無駄なのでやめましょう。
☆選んだ問題集の具体的な使い方・勉強法
問題集買ってきたときに「この問題集解きまくるぞー!」とか考えている受験生は全然違います。
問題集とは解くためではなく、自分に足りない知識を頭に定着させるために存在しています。
1対1や重問のように標準的な問題集なんて知ってたいら解けるし知らないと解けないものばかりです。
標準的なレベルなのに知らない問題を考えている時間ほど無駄な時間はありません。
私は問題文見たら全部答えをすぐ見ていました。
大体5分で問われていることと解法の流れを理解し、10分で暗記していました。
そうやって覚えまくりましょう。問題集はその中身を覚えたら終了ですから、どう使おうと使い方は自由です。
すぐ答え見てたら本番解けないよ〜と言う人が私の周りにはたくさんいて私に解法暗記だけに専念するのをやめさせようとした人がいましたが、練習でできることは本番でもできます。
本番ではたいてい聞き方を変えてきますが、問題集を何周もしてその問題を覚えるとこういう聞き方ではこれが結局聞きたいんだな。と頭が理解してくれます。
このやり方を批判する人は所詮、紙に書いて問題解いてるから時間足りなくて本番までに1~2周しかしてこなかった人たちばかりです。
だから今私のやり方で解法暗記やっている人も自信を持って大丈夫です。
私は1浪ですが、現役で京都大学の医学部に合格した知り合いは化学の新演習を13周したそうです。
私は8周ぐらいしました。
しかし時間的には真面目に解いてた人の1~2周分です。
人間1~2周で本の中身が分かる人なんてほとんどいないことを覚えておいてください。
何周も同じものを認識しまくってやっと頭に定着させるのです。
受験当日では知っているか知らないかのみが問われるので、3周以上してはいけないルールなんて存在しないのでぜひ何周もしましょう。
第14章
模試を受けることが正しいと思っている人は危険です

夏から秋にかけては数か月後の受験当日に向けて日々インプットに時間を費やさなければならない時期です。
どの科目も完成していない状況で受験リミットを1年とするならば、夏までが理解用の参考書だったり青チャートなどの基本問題集だったりに時間を費やします。
つまり秋からの自分の志望校レベルの問題集をこなしていくための準備期間、橋渡し期間です。
例えば東北大学医学部に合格するには化学の場合、今まで合格した人たちは化学の最後の問題集が「化学の新演習」であることが判明したとします。
有名なデカルトの言葉に「困難は分割せよ」というものがあります。
東北大医学部に入学するという困難な問題を、
(化学の場合)東北医合格=新演習を仕上げる
というレベルまで分割することがまずできます。
この分解を繰り返すと受験勉強初期の段階では、自分でもかなりこなしやすい〇〇が良くわかるシリーズなどのレベルの理解用の参考書まで逆算的に変換することができます。
次にこの大学受験当日までの準備の過程で多くの模試がどのような影響を及ぼすかを説明します。
この章では
・なぜ模試をたくさん受けようとする人が危険なのか?
・模試を受けると1番大切な「時間」が奪われる
・模試は塾のビジネスであることを理解しよう
について解説していきます。
私が受験生時代に感じた世間にはびこる予備校神話の嘘についても本質的に説明しています。
☆なぜ模試をたくさん受けようとする人が危険なのか?
なぜ秋の時期に多く模試をたくさん受けることが正しいと思っている人が危険なのかを説明します。
秋は先ほどの説明通り、志望校に沿った問題集の解法暗記にこそ時間を投資しなければいけません。
模試には本番さながらの模擬の試験を体験できる代わりにその分弊害も存在します。
それはあなたにとって大切な時間がかなり取られてしまうことです。
大手予備校の記述模試やマーク模試や大学別模試は朝から夕方過ぎまで時間を取られます。
さらに東大実戦になれば2日間も受験体験に時間を取られてしまいます。
しかも大抵の場合、模試を受けた日の夜は復習などで気持ちが切り替えられず日々行っているインプットが疎かになってしまいます。
最悪の場合は次の日まで復習に時間をかけてしまったり、単なる体験である模試で成績が振るわなかったからといってせっかく立てた勉強方針を変更してしまい、本屋で今の自分に見合わない問題集を購入してしまうなどの場合もあります。
受験の模擬体験なんて1回か2回すれば十分です。
試食コーナーに一定時間空けて何回も来る客なんてこいつどうしたって思いますよね。
マーク模試なんか全科目を1日で済ます上にそんなに時間をかけたのに得るものがほとんどありません。
時間対効果が全く見られないので受けなくていいです。
センター演習なら自分の机でしましょう。
大学別の模試は一回だけ受けることをおススメします。
内容的にどんなもんか確認するのも大切です。
しかし1番大事なのはその志望校の各科目の制限時間とそれに伴う各大問に対する時間配分などを体験できることです。
実際に普段からシミュレーションしていてもやはり1回自分で体験してみると、試験後により具体的にイメージすることができます。
私は夏の東大模試を試しに1回受けましたが成績的には合格には程遠かったです。夏の私には東大レベルの問題難しすぎましたし2日目に行ってしまったことを本当に後悔します。ブッチすれば良かったと。
東大レベルの問題が出来なくても一切不安などはありませんでした。
夏で基本は習得したのでこれからそれよりも上の汎用性の高い問題集を覚えまくれば知識量が曝上がりすると確信していたからです。
☆模試を受けると1番大切な「時間」が奪われる
模試が1年間で時間の大きなロスに繋がる簡単なシミュレーションをしてみます。
条件として「東大志望の浪人生」で模試のその日は夜も解説読んだり鬱になったりする設定でその日の新しい知識のインプットは0とします。
マーク模試 × 3
記述模試 × 3
東大模試 × 2(実質4)
受験制限期間を300日とすると10/300で3%以上もインプットできない日があります。
結構小さい数字って思うかもしれませんが時間にすると240時間無駄にしています。
人生の内1/3は寝ているとすると実質160時間もの時間を無駄にしています。
160時間もあれば物理の重要問題集が150問ですから1問1時間かけても重要問題集が終わる計算になります。
物理選択者なら必ずこなさなければならない重問を他の人が模試に行っている間に理論上は一通り終えることができてしまうのです。
最近の受験生の中にはほかの予備校の模試まで受けてみたり有名講師だからといってわざわざ時間をかけて移動して90分ただお話を聞いて帰ってくるだけの受験生がいますが、彼らは大学受験で合格する気もなく暇人なのでしょう。
☆模試は塾のビジネスであることを理解しよう
模試を受けて知識が増えるなんてことないので無鉄砲に模試を受験の大事な時期に受けるのはやめましょう。
必要最小限で大丈夫です。
こんな当たり前のことをなんで教えてくれないのかと言うと、予備校側の気持ちになってみれば分かります。
問題さえ誰か担当に作成させれば原価5円もしない紙代のみで受験生1人当たり7000~8000円もぼったくれるかなりオイシイ商売なのです。
予備校としてはかなりのビジネスチャンスです。さらに判定や倍率などという、良く考えてみれば受験と全く関係のない要素を広く一般に定着させることで模試を神格化させ「模試をしっかり受けることは正しいこと」という認識を広めることに成功しています。
そのため判定を気にしてまた模試を受けに行くサイクルが出来上がるのです。
チューターなども、
模試をあなたに受けさせて何とか利益を上げるために虎視眈々と面談している切れ者チューターか
模試の受験に対する有用性をまったく思考したこともなく、心の底から勧めているアホチューター
しか基本的にはいないと思ってください。
まぁほぼ99%後者です。
私が受験生にアドバイスするなら、
「模試なんか一回で十分だから早くその問題集を覚えてしまいなさい」
と言います。
以上、読んでいただきありがとうございました。
東京医科歯科大学 Yajima Yusuke
【ここからVol3】

【総論】Vol.3へアクセスしていただきありがとうございます。
まだ読まれていない方は【総論】Vol.1を読んでからこの記事を読んでいただけるとより納得感が増すと思います。
この記事では第15章〜第22章+付録3章を収録しています。
Vol.1では「受験合格に必要な考え方」
Vol.2では「Vol.1を達成するために必要な考え方」
について主に解説してきました。
この2つの記事を読んでもまだ「いやそれは分かるんだけどイマイチ納得できないなぁ」と思う受験生もいると思います。
それは「自分が思っている受験の常識」に縛られているからです。
周りの環境から察した事や自分の経験等から、「受験とはこのようなものである」という固定観念がまだ拭えてない可能性もあります。
受験勉強を客観点に捉えて1年の独学で行きたい大学の合格できた私が気づいたたくさんの誤った固定概念を1つずつ解説して行きます。
読んでくれた人が自分の受験への解釈がより良いものへと変わり日々の勉強に役立てて合格への道のりもクリアな状態でいられる助けになれば、文章の書き手としてこれほど嬉しいことはありません。
noteにある総論3つ、各論5つの記事の中の全ての文章は、
【1年という制限時間の中で志望大学の合格最低点以上の知識を効率的に身につける】
ということのみを目的とした私の経験と思考から構成されています。
断定口調だったり主張が強い部分もありますがこのたった1つの目的を達成するための意見として自分の中に落とし込んでいただければ文章の書き手として幸いです。
第15章
受験勉強は有限で各科目に終わりが存在します

みなさんの中には受験が無限に続くゴールの見えないものと思っている人はいませんか?
確かに毎年の東大の問題を見ると、
「入試問題ってのはいくらでも難しくできて自分には上限が見えずただ下の方あたりで苦しくもがいている」
ように感じてしまう場面もあります。
しかしこれらは単なる思い込みです。
自分で受験を苦しくしてしまっています。
受験は無限に見えて有限です。
各科目で終わりが存在します。
なぜなら入試問題というのは無限に存在しますが聞き方を変えているだけで出る問題の中身は大して変わらないからです。
その理由を実際に問題を作る側の気持ちに立って見るとわかります。
この章では
・教授が問題を作る時に考えること
・理系科目の頻出問題とは!?
・合格までの距離を見極めよう!
について詳しく解説していきます。
大学受験を自分で苦しいものと認知してしまっていては受かる大学も受かりません。
☆教授が問題を作る時に考えること
数学を例にとって考えてみましょう。
まず文科省が決めた指導要綱を逸脱した問題は入試問題として出すことが出来ません。
だから要綱を逸脱せずに高校数学の範囲で生徒の理解力を試す問題を出したいと各大学の数学科の教授たちは思います。
自分が本気を出せばだれも解けないような問題を作ることは造作もないが、指導要綱に逸脱しない範囲でそれらを練りに練ります。
だから多くの大学で被ったような問題が出題されてしまうのです。
また違う大学や過去に出された問題を参考にして問題を作ることももちろんあります。
聞いた話ですが東大の数学の問題というのは各大学の教授たちも毎年参考にしているらしくそこから作問のヒントを得たりしているようです。
つまりこれらのことから、
入試問題として出される問題には頻出のものがありそれを抑えてしまえばほとんどの入試問題で高得点が取れる
という確固たる事実が存在します。
☆理系科目の頻出問題とは!?
これらの頻出問題はどこにあるのでしょうか?
数学なら「1対1対応の演習」
化学なら「重要問題集」
物理なら「名問の森」「重要問題集」
などに眠っています。宝の山です。出版社の方に足向けて寝れません。
それらの問題集は過去の膨大な各大学の入試問題を分析しどの大学でも出されているような頻出問題をかき集めた本です。
だからそれらの問題集を仕上げることは受験合格にかなり直結します。
なぜならあなたが受けるであろう大学の問題では必ずそれらの問題集に載っている解法と同じかそれに準じた問題が数多く出題されるからです。
「万が一出なかったらどうするの?」という質問に対しても一定の答えがあります。
それは「まずどの大学でもそんな年見たことないし、万が一そうであっても受験会場の生徒はほとんどできないから安心していい」です。
大手予備校の授業でしか触れられないような問題があると勘違いする受験生もいます。
それらの問題ももれなくすべて問題集に載っていると断言できます。
なぜなら問題集に載ってないような問題を予備校のテキストに載せようとすると管理部の人から
「こんな効果の薄い問題は載せられない、もっと汎用性のある問題を載せろ」
と言われます。
つまりは頻出問題集に載っているような問題です。
☆合格までの距離を見極めよう!
受験は有限で勉強に終わりが存在します。
時間に余裕があれば早い段階でさっさと終わらしてしまって自分の趣味に没頭しても自動車学校に通い始めても全く問題ありません。
たまに過去問で演習するぐらいで大丈夫になります。
合格するのですから。
東進の林修先生は高3の8月で東大受験のための勉強は終わってしまったのであとは適当に遊んでいたとTVで話していましたね。
理3本(理3合格者約40人の合格体験記)を見ても一定数、こういった受験勉強で合格している人がいます。
人間終わりが見えるとやる気も集中力も上がります。
例えば駅からとある場所まで歩いていく際に方向だけ知っていて距離が分からない場合、初回にその場所に行くときはあとどれくらいかの距離感も掴めないので精神的にも長く感じます。
しかし2回目以降はその場所までの距離感を頭で分かっているので、1回目の闇雲に歩いているときより確実に精神的に楽です。
なぜならあとどれくらいで到着するか分かっているからです。
「とりあえずこの問題集みんなやってるしやるか」
と適当にではなく、
「この問題集をやればこの科目の受験勉強は終わる。」
と確信を持って取り組むと問題集への取り組む際の集中力もモチベーションも大きく上昇します。
終わりが見えなくて悩んでいる受験生はひとまずがむしゃらに取り組むことをやめ、合格までの距離を自分の中でつかむことをしましょう。
第16章
受験における思考力とはこれです、これ以外は全て嘘です

「しっかり考えて思考力を鍛えることが大切。」
「難関大の数学では思考力がものをいう。」
「スティーブ・ジョブスなどのIT革命を起こした人物も皆思考力が高い。」
恐ろしい文章ですよほんと。
世間にはこういった文章があふれかえっています。
思考力という言葉自体、多くの人がその定義を自分でもち統一性がないように思えます。
受験においても「思考力」「発想力」「センス」などという、本人自体が厳密にそれが何なのか分かっていない言葉を連発して18前後の高校生たちを困らせます。
私の周りにもいました。「数学は思考力が大切だからねえ」というやつに限って数学の点数が悪かったりします。
私は学問としての「数学」は全くできるようになる自信がありませんが「受験数学」なら誰にも負けないという自信で2/25を迎えることができました。
この章では
・思考力とは何だろう
・思考力を数学の例で考えてみよう
・思考力とは既存の知識から新しい知識を生む力だ!
について解説していきます。
これを読めば、受験において思考力は必要ないんだと確信して合格へとアプローチできます。
noteにある記事を読めるぐらいの読解力があれば大丈夫です。
☆思考力とは何だろう
思考力とはいったい何なのでしょうか。
私もそれについて考えている時期がありました。
受験では
「普段から1時間1人でじっくり考えなんとか既存の知識から答えに辿り着く」
ことを思考力とみなしがちです。
しかしこれは少し考えると受験数学の本質ではありません。
本番で解ければなんだっていいのです。
数学の試験は長くて180分で、多いと6題もの問題を解かなければいけません。
ですから本番でウンウンうなっている時間は多くないのです。
受験に思考力は必要ありません。
必要なのは知識です。
難しい問題が解けないのは思考力がないからじゃないです。
知識不足なだけです。
単に知識不足の受験生が「自分には思考力がない」と勝手にネガティブになってしまうことがよくあります。
ここでさっきの「」内の文章を見るとポイントがありますね。
それは
「なんとか既存の知識から答えに辿り着く」
というところです。
☆思考力を数学の例で考えてみよう
数学で言うと、A,B,C,D,E,F…という数多くの青チャレベルの基本の解法の知識が前提として身に付いているとします。
そこである大問ではBとFの解法を組み合わせれば解ける問題となっています。
ここで先ほどから言う思考力のある人というのは、
「この問題、最初は絶対Bを使うのは分かるんだよな。あとはどの組み合わせだろう、、、今知っている解法で繋がるのはないかな。」
という思考回路に至ります。
こうしていろんな組み合わせを頭の中でシミュレーションしてBの後にFを組み合わせると気づくと問題が解けるわけです。
ちなみにここでABCの3つまでしか解法の知識がない人はその問題は絶対に解けません。
要は知識不足の人です。
青チャレベルもカバーできてないのに難問を理解しようとするのは無理です。
解答を読んでも自分の中で腑に落ちないので効率が悪いです。
この例で言いたいのは人間はその範囲の知識がゼロだとその知識に既存の知識からアクセスすることは不可能ということです。
1時間かけて考え込む必要なく、その問題を習得できる簡単な方法があります。
それは答えを先に見ることです。
「こういう問題はB→Fと繋げて解くんだ。」と認識すれば良いのです。
この問題で得たい知識はBとFの間にある「→」です。
1時間かけても、5分で答え見てもここで得た知識は同じです。
受験本番に出たらどちらの勉強法の人も瞬殺できるでしょう。
ここでやはり気になるのは、本番で知らないっぽい問題が出たら常に自分で「→」を考えて体得してる人が有利なんじゃないの?ということですね。
心配することはありません。
まず場合の数的に言うと、すべての解法同士に繋がりがあるわけではありません。
つまり入試で良く出る矢印は決まっています。
ある程度の頻出問題集からはたくさんの頻出の→が出てきます。
それを効率的に覚えていきましょう。
受験本番では大問も多く、知っている問題といえども書く量が多いので1問に時間を多くかけられません。
しかも常に時間をかけている受験生が5~10分で考えてその場で解法を思いつく学生の方が少ないです。
以上を踏まえた上であえて話しますが、
まず受験数学で満点を取る必要はありません。
ぱっと試験問題見て6問中3問で解法が浮かぶ問題だったら受験数学は大成功です。
確実に合格できます。
なぜならあれほど範囲が多い数学の中で3つも完答できる問題があるぐらい演習を積んだのですから。
物理と化学は勝手が違います。
これらは範囲も狭く、一通り学習すれば高得点で安定するので取れて当たり前です。
☆思考力とは既存の知識から新しい知識を生む力だ!
スティーブ・ジョブスやビル・ゲイツが単に思考力だけで何もない所から新しいものを創造したと思いますか。
彼らは根っからのコンピュータオタクで、寝食を忘れるぐらいコンピュータに熱中していたそうです。
つまり彼らもコンピュータに関して膨大な知識を持っていました。
そういう下地があってこそ既存の知識を組み合わせ新しい知識を生み出したのです。
「思考力とは」という問題に対しては、
「知識が豊富にある人が既存の知識を組み合わせて新たな知識を作れること」
であると私は考えています。
そのためには大量の知識が必要です。
受験に必要なのは今の自分が持ってない知識です。
思考力ではありません。
それに思考力自体については私も脳科学者ではないので高める方法は分かりません。ただ脳トレをしてれば東大に受かる訳じゃないことは私の思考力でも分かります。
たくさんの知識があれば問題は余裕で解けます。
知識がない状態では何も生まれません。
知識があると、問題を見た際に勝手に頭がつなげてくれるレベルの問題も多いです。
このnoteに書いてあることを理解できるぐらいの理解力があれば、思考力が十分にあると考えて大丈夫です。
第17章
そもそもやる気と受験勉強を結びつけること自体が大間違い!

受験生の皆さんはモチベーションの維持や勉強に対するやる気をどのように捉えていますか?
「今日は調子がいい」
「もっとできるな今日は」
「いやなんか気分が乗らない」
こういった感情に対してどのように考えそしてどのように日々の勉強に打ち込むべきかの私の考えを書きます。
この章では
・勉強をやる気と結びつけるな!
・絶対に「時間」で測るな、絶対に「ノルマ」で測れ!
・絶対に「時間」で測ってはいけない理由
について解説します。
やる気とモチベーションについては沢山の質問を受けるのでまとめました。
☆勉強をやる気と結びつけるな!
皆さんの多くは
「やる気がある→勉強する」
の構図ではありませんか。
この構図の問題点はなんだと思います?
それはやる気がないときは勉強ができないではありません。
問題はもっと根深いです。
あの構図の本当の問題点は「やる気」というものに自分の勉強のペースを握られてしまっていることです。
「やる気」にペースを握られてしまっているからやる気が出ないときに勉強ができないのです。
もっと本質に迫ると「やる気」という、なんだか自分の意思ではコントロールできないと自分が認識しているものを言い訳にして深層心理で「勉強ができない」と頭が認識してしまうのです。
頭が認識しなければ実際に行動できないのは皆さんご存知だと思います。
何だかややこしい話ですが、私は心理学を学びこれらのことをはっきりと認識しました。
「やる気」についてですがその要因を見ると、
・動機付け
・睡眠時間
・体調
・環境による心理的変化
・摂取する食物
など挙げればきりがありません。
これらを徹底した自己管理でコントロールして年中やる気が出ている人なんて見たことありませんし非現実的です。
もともとやる気なんていつも出るわけじゃないのが普通です。
徹底した自己管理よりもっと簡単な方法があります。
それは「やる気」と勉強を結びつけるのをやめることです。
別に受験勉強でなかったら、やる気が出ない日には家に閉じこもりひたすら寝たりひたすらYoutubeを見ても構いません。
しかし勉強になると「やる気」に左右されてはかないません。
「やる気」は勉強から一旦離して考えましょう。
では次に具体的に受験に対する勉強への考え方についてみていきます。
☆絶対に「時間」で測るな、絶対に「ノルマ」で測れ!
高校生などまだ目標に対する勉強法が分かっていない生徒に限って
「何時間勉強したらいいですか?」
「先生は1日何時間ぐらい勉強していましたか?」
「数学土日で10時間しました。頑張ったと思いません?」
といった質問をしてくるのですが、彼らは勉強とは何か全く分かっていません。
勉強とは自分の現在地と目標までのギャップを埋めるための知識を入れることです。
決して時間をかければいいってもんじゃありません。
少し強い言葉を使うといくら頑張っても結果が出なきゃ誰も見向きもしてくれません。
結果が出なくてもみんなが見てくれるのは黄色いTシャツ着て24時間走る偽善的な番組だけです。
1日の勉強は「時間」ではなく「ノルマ」で測りましょう。
ノルマには「大きなノルマ」と「小さなノルマ」があります。
「大きなノルマ」とは受験当日までに対していつまでに〇〇の問題集、そして次はいつまでに△△の問題集といった感じに日単位ではなく、もっと大きな枠組みでみます。
反対に「小さなノルマ」とは1日の中で、今日は1対1対応を5題、英作文10例文、名問の森を4題といった感じに各科目の今日やる具体的な問題数でみていきます。
早い話、今日のノルマが4時間で終わればその日の勉強は午前で終了です。逆に12時間かかっても終わらないようなノルマにしてはいけません。
これは志望の高さでも変わってきます。
一般式にして例えると、
今ある知識が100、第1志望の合格最低点の知識が3700だとすると、1年間でだいたい1日100の知識を入れればいい計算になります。
しかし第1志望の合格最低点の知識が1900だとすると、1年間でだいたい1日50の知識を入れればいい計算になりますね。
私の場合は志望を医科歯科と、かなり高く設定したのでその日の午前中にノルマが終わるような日は1日もありませんでした。
あと余談ですが、よく質問で1日何時間勉強していたかよく聞かれますが正確に測ったことないので分かりません。
しかし1日15時間など現実的に毎日続けることが難しい計画ではありませんでした。
計画というのは現実可能性がなければただの「理想」へとなりさがるので。
☆絶対に「時間」で測ってはいけない理由
理由が2つあります。
1つ目は1日の勉強を時間で測っていては知識量が測れないのです。
同じ90分の勉強でも4題なのか9題なのかは分かりません。
ちなみにこの具体的な数字は予備校の数学の授業を例えに取りました。
話を戻します。
時間で測っていては知識量が測れませんがノルマで測っていたら知識量が測れます。
知識量で測れるということは目標までの進み具合を具体的に頭の中で測れるということです。
知識量で測らず、ただ闇雲に時間で測っていては「こんなに頑張っているのに受かる気がしない」という精神状態になるのは誰でも想像できます。
マラソン選手は42.195kmが事前に皆分かっていてそれを想定して練習をするから本番でうまくペース配分できているのです。距離も分からなければ練習法やペースも定まりません。
2つ目は時間で測っていたら
時間さえ経てば今日の勉強が終わるな嬉しいなの精神
になってしまいます。
ここまではっきり意識はしないでしょうが皆さんは親に無理やり塾に通わされている悪ガキではありません。
そんな考えでは、新しい知識など定着する訳ないって誰でも本当はわかっていると思います。
目標まで自分を連れていってくれるのは、新しい知識です。
時間ではありません。
時間が経てば解決するという言葉は特別な人間関係を除けば、嘘です。
このことを良く理解しておきましょう。
第18章
大学受験でやる気を無理に出そうとしても続く訳がありません

「受験勉強ではやる気を出して必死に勉強すれば志望校に合格する」
こんな言葉をよく聞きませんか。
恐らく受験生に対するアドバイスで最も頻繁に聞く言葉の1つでしょう。
なぜならこれは単なる正論で親戚の中卒の叔父さんでも言えるレベルで浅い言葉で誰でも言えるからです。
これは「戦争をやめれば世界は平和だ」レベルのアドバイスです。
じゃあどうしたら戦争をやめるシステム作りをするのか、そこに焦点を当てて議論しなければなりません。
まぁ大抵の叔父さんは大事なそこについて聞くとはぐらかすか俺は知らないと走って逃げるでしょう。
このnoteと並行してツイッターでも情報発信しています。
「〇〇がたった一ヶ月で〇〇大に逆転合格」系のアカウントを覗いてみると
・輝かしい未来を想像すると自然とやる気がでてくる
・やりきらないから、後悔する
・午前中に数学、寝る前に暗記科目
・参考書を大切にし、自分だけの参考書を作ろう
などの素晴らしいお言葉で埋め尽くされていましたが、ほかにも計算ミスの重要性を説いたり、論理力を鍛える重要性を説いたりしています。
しかしこれらのアドバイスは残念ながら直接的なアドバイスとはなりません。
この章では
・やる気には2種類ある!
・内なる「やる気」を出すために
について解説しています。
20年も生きていない人間はやる気についてよくわかっていません。行動心理学的要素を踏まえた論理ですので受験生を指導する立場にある方も是非ご一読を。
☆「やる気」には2種類ある!
やる気には内なるやる気と外から動機付けされるやる気の2種類があります。
この章の最初のアドバイスを受験生が聞いても
「それはただの正論でやる気が出ないから困っているんだよ」と思うだけです。
私も高校生時代はそうでした。
学校の教員に直接相談したことはないのですが、よく彼らが言っていたのは
「受験は団体戦」
「オープンキャンパスに行って自分がそこにいる姿をイメージしろ」
「やる気と根性さえあれば同じ志望校を目指すやつらに食らいつけるぞ」
などの残念ながら一つとして腑に落ちないものばかりでした。
まず、
「受験が団体戦=学年の雰囲気が大事」
ですが、これは違います。
学年中の「勉強」の雰囲気にのまれてやる気が出るということなのでしょう。
これって割と害が多いのを知っていますか。
学年中が受験を無理に強大なものと勝手に想像しているので多くの受験生が確信を持ってやる気を見出せていません。
そんな重苦しい雰囲気の中を形成する1人にあなたがわざわざなる必要はありません。
やる気というのは周りから与えられるものではなく内なる自分から出てくるべきです。
なぜなら外の環境から与えられたやる気は確実に長続きしないからです。
例えば、親から無理に行かされている塾とかですね。
内なる自分から出るやる気は必ず長続きしさらに目標に近づくにつれ増大します。
これらの2種類のやる気の決定的な違いは自分がその行動について確信をもって行っているかどうかです。
だから単に「やる気を出せ」というアドバイスはアドバイスに見えて1mmも役立ちません。
「やる気と根性」を出す具体的な考え方を、高校の教員には生徒に教えてあげてほしいものです。
この内なるやる気が出る時というのは
今自分の頭の中にある次にするべきであろう行動が自分にとって得か、
受験に当てはめて言うと、自分にとって最大限の効果を得られるつまり合格へ近づいている
と確信している時です。
確信が持てない行動には無意識の内に頭の中で次に考えている行動の必要性を感じなくなりやる気も集中力もなくなります。
例えばあるサイトに掲載されている特別キャンペーンのボタンをクリックすれば10万円が確実に手に入ることをあなたは事前に知っていたとします。
もしそのサイトが全文英文で書かれていて応募フォームやいろいろな選択画面が何回も出てきたとしてもそれでもあなたはあきらめず、辞書使って何が何でもそのボタンのあるページまでたどり着くでしょう。
しかしなんでもないサイトでこのリンクから飛んだ先のサイトで必ず10万円が手に入りますよと書いてあった場合、リンクから一旦は飛ぶでしょうけど英語だらけのページが出てきたとき、あなたは面倒くさくなってそのページを閉じるでしょう。
この例では前者は事前に確信を持ちましたが、後者はネット上のみの情報なので上手く確信が持てませんでした。
なので英文を訳すモチベーションは生まれませんでした。
もう1つの具体例として私の体験談を書きます。
浪人時代にはすでに合格を確信していたし、立てた計画を実行するだけでしたが量が多く5時ごろには毎日起きていました。
必要性を頭で認識していたので自然に目も覚めます。
少なくとも9時以降に起きた日は4月から2月までで一日もありませんでした。
しかし大学に入って特にやることもなくなった当初は一限が9時からでしたが重要性を確信できず10時以降に起きる日も多くなってしまいました。
良いことではありませんけどね!!
☆内なる「やる気」を出すために
大学受験では内なるやる気を出すために次の行動に確信を持つことが大切です。
そのためには「この計画を実行しさえすれば、合格へ間違いなく繋がると確信する」という計画をまず受験勉強の初めに立てることが重要です。
もう一度言いますがここが重要です。
なぜなら、船出前に航路設計図を立てるようなものだからです。
勉強計画をまずはしっかり立てること、これはビジネスにおける最初の投資のようなもので後から大きな見返りを期待できます。
第19章
頭のいい人になるには (1) 誤解と迷信、そして本質

突然ですが「頭がいい」「頭の良さ」とはなんでしょうか。
受験時代このことについてよく考えていました。典型問題を暗記するだけで受験に受かってしまうのですから「頭の良さ」は受験にいらないことになってしまいます。
ならば本当に「頭の良さ」とは何なのか?一年かけて考える時間がありました。
世間で言われている「頭がいい」という言葉の使われ方は100人いれば100通りの答えがあるでしょう。
なぜなら「頭がいい」ということについてきちんと議論する機会など日常ではあまりないからです。
そのために偏見にもとづく誤った認識もしばしば見られます。
この章では誤解や迷信に対する私の見解を書きます。
よくありがちなのが、
「東大だから頭がいい」
「医学部だから頭がいい」
「学歴があるから頭がいい」
「頭の良さは遺伝だ」
「育った環境だ」
「そもそも脳のつくりが違う」
などです。
私の見解ではこれらはいずれも本質ではありません。
この章では
・頭の良さは学歴では分からない
・頭の良さは遺伝では決まらない
・脳のつくりで頭の良さは決まらない
についてまず解説して行きます。
☆頭の良さは学歴では分からない
まず学歴があるから頭がいいではありません。
大学生になってから目的意識を失い堕落する人も多く単に彼らは受験当日に
「合格最低点より上の点数を取るだけの学力があった」
だけで、それと
「頭の良さ」
はイコールではありません。
少し考えてみれば分かります。
「頭がいいから医学部に合格した」は分かりますが
「医学部だから頭がいい」は成り立ちません。
「おいしいクッキー」というパッケージを見ただけでそのクッキーをおいしいと思う人がどのくらいいるでしょうか?
普通食べてから判断しますよね。
「学歴があるから頭がいい」はパッケージ見ただけでおいしいクッキーと決めつけるのと同じです。
よくテレビで「頭でっかちの東大生は使えない!」ということを議題にした討論番組はありますね。
テレビ的にその構図が受けるのもあるでしょうけど、もし東大卒で使えない人が本当にいるならそれは典型的なここでいう「頭の良さ」はないけど解法の知識だけはあったタイプの人です。
☆頭の良さは遺伝では決まらない
私の小学校の時の先生は「頭の良さは遺伝でだいたい決まる」と言っていました。
頭の良さという曖昧な定義の問題に対してこういった抽象的で実際に目で見て確かめることのできない答えは、一つの意見のようで答えではありません。
はっきりいえば単なる逃げです。
これが全くの真実なら人の知能は生まれた時に決まってしまい、自分で変えることは多少できても最初から素質のある人にはかなわないということになります。
確かに一卵性双生児の研究によって人間の知能の5割は遺伝によって決まるという結果が出ています。
しかしこれには大きな落とし穴が2つあります。
1つ目は「知能とは何か?」という問いに対しはっきりとした定義がないのです。
知能の指標とされるIQテストは、与えられた文字や図形から数学的な規則性を見出すことです。
しかし数学的な素養のみが人間の思考力の指標なんて有りえません。
IQが並でペーパーテストなど全然できなくても社会で活躍している人はごまんといます。
逆にIQは高いのに職場に馴染めないという人も多くいます。
ですので相関関係がはっきり出ているのかは微妙なところです。
2つ目はテストで測れない「頭の良さ」もあるということです。
自分の知っている語彙や表現や経験則から、その場の空気に応じて的を得た表現で笑いを取る芸人の頭の良さは机の上では測れません。
また株取引やギャンブルにおける勝負師の感的なものも実際に測るのは難しいです。
学力はなくても組織作りに長け経営者として社会で活躍する人も沢山います。
話を戻します。
遺伝という存在は絶対的なものではありません。
生物や医学の知識がある人ならわかると思いますが、体の中では常に遺伝子の異常が起きています。
常に一個人の中で突然変異が起こり、その細胞は体の中の免疫細胞によって正常に除去されるから正常な健康状態でいられるのです。
しかも父親と母親の染色体同士も交配する時に交差という現象が起き、子遺伝子の多様性につながります。
ですのでそっくりそのまま遺伝するなんてありえないのです。
だから遺伝のせいで自分の頭が悪いなんていうのは完全にお門違いの認識です。
次の章で、私の考える頭の良さの定義を具体的に説明しますがそれは遺伝とは全く関係ありません。
それについて適切に努力すれば頭は良くなります。
☆頭の良さは環境では決まらない
まず環境は外的要因であって内的要因ではありません。
今この章を目で読むことを含め、自分の生きていく上でとるあらゆる全ての行動は、
「外的要因の影響を受けはするものの最終決定は全て内的要因」つまりは自分の意思で決まります。
外からの影響を受けていると自分では自覚していても、その行動を選択しているのは世界中の誰でもないあなた自身です。
これはアドラー心理学の考え方ですが、アドラー心理学は意思決定の外敵要因を否定し内的要因に焦点を当てる考え方です。
また外的要因についてですが高学歴学生の親は高学歴という相関関係は明らかに存在します。
その答えは「教育にかけるお金」です。
高学歴の親は小さい頃から塾に通わせ有名進学校に進ませ、周りが勉強する環境を子供に与えます。
それが自分たちもそうであったように学歴のいい大学に合格できる簡単な方法だと認識しているからです。
それでも彼らの頭がいいかというと全くそこに相関はありません。
非効率的な時間の使い方をしている人など大勢いますし大学に合格した時点で大抵の人間は勉強や新たに知識を身につける行動をやめるので、いわゆる「頭の悪い」方向へと向かって行きます。
生まれ育った環境で頭の良さが決まるほど単純ではありません。
☆脳のつくりで頭の良さは決まらない
脳科学を勉強すると分かりますが脳のつくりはまず万人共通です。
先天的な病気や事故などの特例を除きますが、私のいう「頭の良さ」は脳のつくりでは決まりません。
脳を物質としてみると大脳を構成する200億のニューロン(神経細胞)は大きさも数も人によって大差ありません。
脳が働く時にはこれらのニューロンに電気信号が走りますが、発生の仕組み、電動速度は皆同じです。
いわゆる「脳トレ」的なやつがありますが私は全く嫌いですね。
脳を鍛えるだけでいきなり高校レベルの数学ができるようになるとも思えませんし、いきなり翌日の会議で素晴らしいアイデアを出しまくることもできません。
勉強や仕事に効果的とは到底思えません。
「脳トレ」をやめる思考過程を踏むことこそが脳を鍛えた何よりの証でしょう。
☆全ては本人次第
色々「頭の良さ」について私の見解を述べました。
要は何が言いたいかというと、頭の良さとは
「周りの外的要因のせいにするのではなく、自分で変えられるもの」
つまり自分に注目してどうしたら頭をもっとよくできるかについて考えましょう。
具体的な話は次の章で。
第20章
頭のいい人になるには (2) 頭の良さの定義とは

「あいつは頭がいいからね…」
「医学部だから頭よくて羨ましいな〜」
「いや俺は頭悪いから無理だよ」
こういう言葉を日常的に耳にしますね。
しかしこの人たちの中で具体的に「頭の良さ」が何かわかっている人がいるでしょうか。おそらくいません。
よく考えるとこれは不思議な現象で、誰もその言葉の定義がわからないのに平然と会話で使っているのです。
意味のよくわからない言葉って普通使わないじゃないですか。(笑)
なのに「頭がいい」の話題になるとみんなこの言葉を使って会話します。
ちなみに私は高校生の頃は全く頭の良さについて考えたこともなかったので、自分より定期テストの順位が上の人はもれなく全員頭がいいと決めつけていました。
今振り返ると当時の思考回路自体が賢くないですね。
この章では
・「頭の良さ」の捉え方
・「頭の良さ」の定義
・問題設定と問題解決の具体例
・受験における問題設定と問題解決の能力
について解説します。
皆さんが何となく分かっている事を、この章を読んで言葉として再認知してください。
☆「頭の良さ」の捉え方
頭の良さなんて人によって捉え方が違い、その捉え方によってなんとでも定義できてしまうものです。
例えば暗記力、計算力、空間認知能力、論理的思考力など全て「頭の良さ」の一部ではありますが、これで全てでもありません。
暗記しかできない人は、マニュアル人間になることがあるし、計算力だけあってもそこに社会性や論理的思考力が足りてなかったら有能な人とは見られません。
それならば「頭の良さ」なんて考えても答えなんか出ないので不毛なのでしょうか。
もちろんそんなことはありません。
大事なのは机上だけでなく人生通じてあらゆる場面に共通する「頭の良さ」とは何かを考えることです。
いかなる状況下においても適応される頭の良さの定義について私の見解を次に書きます。
☆「頭の良さ」の定義
ズバリ、頭の良さとは「問題設定と問題解決の能力」です。
このnoteは「受験の本質とは何か」について説明しています。
その中でも私の思考の根本となるのはこの定義です。
問題設定と問題解決の能力とは
その名の通り自分が何をしなければいけないかを客観的に見極め(=問題設定)、それを確実に達成できうる計画を立てて実行する(=問題解決)能力
のことです。
この能力があれば、大学に合格した後も卒業した後も確実にあらゆる場面で結果を出すことができます。
こんな感じで難しそうな漢字が並ぶとなんだか難しく見えてきてとっつきづらそうですが、全然そんなことはありません。
実は皆さんは既にこの定義をはっきりと意識してないけれど実行できているのです。
☆問題設定と問題解決の具体例
実際に皆さんも問題設定と問題解決を普段からしているという実感を具体例とともに認識して行きましょう。
①明日朝9時に友達と遊びに行く場合
(問題設定)
8時55分に待ち合わせ場所に着く
(問題解決)
待ち合わせ場所まで30分かかるので家を8時20分に出よう。
↓
支度に40分かかるので7時40分に起きよう。
↓
毎朝一回で起きられず10分ぐらい布団から出られないので7時30分に目覚ましをかけとこう。
つまりこの目的を達成するには「7時半に目覚ましをかける」ことを今すれば大丈夫という風に思考します。
結構みんな当たり前にやりますよね。
②1週間後に定期テストを控えている場合
(問題設定)
各科目60点以上取ろう
(問題解決)
数学と英語と化学はもうとれるから勉強しなくていいや。
国語は先生が出すって言ったところを完璧にすれば6割はいく計算だな。
物理は範囲が指定されているけど授業聞いておらず意味がわからん。
↓
2日前に国語のワークを始める
物理は最初の3日で教科書読んでその後テスト前までは友達にその範囲を聞く
この目的を達成するために今やるべきことは「物理の教科書の範囲の1/3分読む」だけです。
これも当たり前ですね。
③気になるあの子と付き合いたい場合
(問題設定)
あの子と付き合う
(問題解決)
今ラインすらしていない
↓
入学当初から接点があるわけでもなく急に何もなく近づいたら逆に不自然
↓
その子は毎年秋にある文化祭の実行委員をしているから俺もそこに入って「実行委員」という肩書きを持って自然と近づこう
↓
友達に副実行委員長がいるのでそいつを何でもいいから説得して今年から実行委員に入れてもらおう
この目的を達成するために今やることは「友達の説得」です。
決して「直接ラインを聞く」ことではありません。
恋愛については気質も関係してくるのでいきなり告白とかいうので成功する人もいるかもしれませんね。
今3つほど簡単に具体例を挙げましたが、こんな感じのことは実際に紙に矢印書いて考えなくても皆さん頭のなかで日々やっていることと大差ありません。
このnoteは一応受験noteなので次に受験について問題設定と問題解決について書きます。
補足としては、今3つ挙げたうちの最初2つと受験に関しては極めて成功率が高いです。
なぜならほぼ全ての行程で登場人物は自分だけであり、自分は自分の意思でコントロールできるため計画が頓挫する可能性が低いからです。
恋愛についてはどうしても相手がいてこそのことなので計画通りことが運ぶかはわかりませんが
それでも何も考えず行動するよりはいいのではないかと思います。
☆受験における問題設定と問題解決の能力
受験における目的とは全員が「合格」のはずです。
不合格になりたいのであれば受験当日まで待機しておけば目的達成です。
受験というのはこの思考法がもろに適応できる場面です。
なぜなら「受験」という大きな問題を解決するために教科レベルから分野レベルに至るまで細かく細分化して考えなければならないからです。
その思考の過程は今後絶対にあなたの人生に大きくプラスとなります。
東大受験を例に受験における問題設定と問題解決を見ていきます。
(問題設定)
合格する
(問題解決)
合格最低点より上をとれば受かる
↓
二次で300/440とればどの年でも間違いなく最低点を上回る
↓
英語と理科は本番の運に左右されず、今までためてきた知識量が顕著に反映される科目なのでどちらも100/120。
国語は40点文の古文漢文はレベルも高くなく、一定量勉強すれば点が取れるが現代文は高得点が取れそうもないので40/80。
数学は300-240で60点取ればいい。
半分ならセンスとか当たり外れ関係なく典型問題を体得しまくれば取れる。
受験で考える際には、合格最低点より少し高めの点数を設定します。
そこから理科、英語、(東大の場合は国語も)をこの順に想定点数を引いていき、最後に数学で何点取ればいいかを算出します。
「まず数学で何点取って〜」の話ではありません。なぜならば数学は実力と本番が比例しないことがあるからです。
それは苦手分野だったり本番に対する緊張もあるでしょう。
しかし数学で点が乱高下する1番の原因は「解法の流れは同じでも聞き方が違う」ことです。
聞き方が違うと初めて見る問題に見えてしまい誰でも焦るのです。
だから自分が取らなければいけない点数を想定するときには数学は最後にすることを強くオススメします。
第21章
成績が上がる人と上がらない人の決定的な違い

突然ですが本番までの受験勉強で最も危惧しなければならないことがあります。
それが何かわかりますか?
「使う時期が適切でない参考書や問題集を使う」
「和訳や解答を整理して書く」
「模試を受けることに奔走する」
このnoteではこれらのことをマジで意味ないからやめとけと口すっぱく言っています。
これらは実は単なる現象で本質ではありません。
これらに共通することは時間という最も大切な財産をかけているのに目標到達に自分を連れて行ってくれない行為だということです。
これは大問題です。
今あげた3つ以外にも自分の生活を振り返り自分を合格というゴールまで送ってくれない行為をしている人がいたら反省し二度としないようにしましょう。
この章では
・成績が上がる人と上がらない人の決定的な違い
・時間についてもっとよく考えよう
について解説していきます。
皆さんには限られた時間があります。
5浪できるなら何も言いませんが、ほとんどの人が現役合格もしくは今年で決めたいと考えているはずです。
ぜひしっかり読んで自分の勉強法を見直してみてください。
☆成績が上がる人と上がらない人の決定的な違い
受験勉強の中盤以降になると一学期や前期にやってきた勉強に対して同じように「勉強している」といっても成績が上がる人と上がらない人が出てきます。
この人たちの違いって何なのでしょうか。
模試の後で
前者は普通に解けて
後者は「あれだったか。見たことあるのに。」
となります。
厳しいことを言うと結果だけ見れば、
問題ができた人
問題ができなかった人
という構図ですから受験で言うと合格と不合格になります。
実をいうとこの2人の言う同じ「勉強」には実際にやっていることに大きな違いがあります。
同じなのは漢字だけです。
成績が上がる人の言う「勉強」とは
問題を解く
↓
分からなかったら迷わず答えを見る
↓
解答の論理を理解する
↓
理解して覚える
↓
頭の中だけで答案を再現する
成績が上がる人はこの正しい流れの勉強が実践できている人です。
一方成績が上がらない人の言う「勉強」とは
問題を解く
↓
長時間考え込む
↓
解説を見て納得して終わり
という流れが「勉強」だと思っていたり、
問題を解く
↓
分からず解説を見る
↓
理解しようとせず解答を丸暗記しようとする(一番最悪)
という流れが「勉強」だと思ってしまっています。
受験で頻出である必須問題集を使って正しく勉強しているはずなのに成績が上がらない人は一つ一つの問題に対するアプローチに原因があります。
「じっくり考えろ」などとよく言ったものですが受験とは関係ありません。
受験勉強では2時間考えて分からない問題も5分で答え見て10分で論理を覚えてしまえばそれで終わりです。
いかに受験当日までに自分の中にこなした問題のストックがあるかが重要です。
このストックは2時間かけたとか、このストックには丸1日かかったとか非効率の極みです。
その原因を取り除いて成績の上がるアプローチをすれば必ず成績が上がります。
今この成績の上がらない勉強法をしてしまっていた人は今日から正しい方に変えましょう。
☆「時間」についてもっとよく考えよう
上述したように問題に対するアプローチの違いにより1問1問に大した時間の差がなくても積み重なって大きな違いとなります。
成績の上がらない勉強法をしている人は今すぐ勉強をやめたほうがいいです。勉強向いていません。
正直に本音を言うと勉強しているのに結果が出ないのならば、勉強してないのと同じです。
友達と遊んでたほうが有意義な時間となります。
少し時間について考えてみましょう。
こいつ意識高いな〜なんて思われるかもしれません。
でもこれは大切なことなので集中して読んでください。
時間というのは皆に平等に与えられています。受験生の1時間も年金暮らしでヒルナンデス!を見るのが日課のお婆さんの1時間も同じです。
ここで考えなければいけないのは、時間に価値をつけられるのは本人の行動次第ということです。
1時間かけて数学の1問かけて解けなかった残念な受験生も1時間かけて4題解法暗記した受験生も同じく「勉強した」と言い、同じ「1時間」が流れています。
受験にはもちろん1年ないし2年の制限時間が存在します。
「俺には制限時間なんてない。何浪でもできるんだ。」という人は別に構いません。何年でも頑張ってください。
バカだなとは思いますがせっかくnoteを読んでくれている人の好感度を下げないためにもいちお応援してますと言っておきます。
制限時間がある中で時間の価値を最大化することを考えるのは基本であり必須です。
これが俗にいう「勉強の質を上げる」という言葉で世間では使われます。
「勉強の質を上げる」なんていうと本人が頑張ってその1問から多くのことを学び取らなければならないかのような印象を受けますが全然違います。
ていうか「質を上げる」の意味を正確に理解してこの言葉を使っている人の方が少ないでしょう。
正しくいうならば
「勉強をする際にかける時間の質を上げる」
です。
このことをしっかり意識して受験当日への準備を進めていきましょう。
第22章
有名講師の授業を受けることが正しいことではありません
受験生の中には顔と名前が一致する予備校教師を知っているという人がいるかもしれません。
おそらくその人は有名な人で多くの受験生もあなた同様に知っているでしょう。
駿台講師の伊藤和夫さんや竹岡広信さんなど英語の予備校教師としては顔も名前も有名なのではないでしょうか。
私も受験生時代はその2人を含め何人か知っていました。
書店の学参コーナーで問題集を適当に見ていると、その人の本をたまたま手に取る機会がありそこで知りました。
実はこのことは後で解説する「人気講師へのなり方」へのヒントにもなります。
タイトルは強烈ですが今回はなぜ予備校の人気講師による授業を受けたいと思っている人が受験勉強では危ないかを解説していきたいと思います。
この章では
・なぜ人気講師になるのか?
・予備校の人気講師=最高の授業ではない!
・受験で必要なのはインプット!
について解説していきます。
ただ有名講師の授業はきっと有用なのではないかという気持ち、分からなくもないです。
17前後の人間ははっきりと自分の物差しを持っている人は少ないためよく考えず風評で自分の行動を選択しがちなのはある種自然なことでもあります。
☆なぜ人気講師になるのか?
なぜ予備校教師が人気講師になるか分かりますか?
授業が素晴らしく生徒から大変好評で口コミで広がって知名度が全国区になったのでしょうか。
最もらしい理由で予備校「講師」がいかにも有名になりそうですね。
しかしこれは違います。
中に入るかもしれませんが私のいる限りでは1人もいません。
予備校業界では受験生はたいてい1年か2年いたらすぐその生徒はいなくなりまた新しい受験生が入ってきます。
そんな短いタームの中で口コミだけで一気に全国区の予備校教師になるなんて現実的ではないことは少し考えれば分かります。
例外としてはCMでキャッチーなフレーズが浸透して人気になる国語教師ぐらいでしょう。
では口コミで有名になるのでないとなると人気が出る理由は何でしょう。
それは書いた本が好評で売れすぎて、著者として名前の載ってある人が有名になるからです。
予備校教師の授業がすごすぎて人気が出るのではありません。
その人が書いた本がその人を人気にさせるのです。
人が先ではありません。本が先です。
☆予備校の人気講師=最高の授業ではない!
人気の問題集を作っている予備校教師というとさぞ分かりやすい授業を展開してくれるかと思ってしまいます。
しかしこれはすべての場合に当てはまる場合ではありません。
なぜならその人が自分の頭の中にあることを紙に起こして体系的に説明する能力があることが人前で分かりやすく話す能力も高いということイコールではないからです。
実際に受けたことはありませんが物理の「物理教室」「名問の森」を書いた浜島先生は授業はそこまで分かりやすくないそうです。
本は素晴らしいですが、本が素晴らしいからといって期待して授業を遠征してまで受けにいった生徒は失望したことでしょう。
最高の本を書いてなくても高校教師の中には物理が苦手な女の子に分かりやすく何かに例えて説明するのが上手い先生だっているはずです。
その予備校教師の言いたいことつまり受験に必要なことを、自分の頭の中に知識としていれたい場合は授業を受けるよりももっと画期的な方法があります。
それはその人の書いた本を何回も繰り返し読むことです。
受験で合格のために必要なことは全て本の中に書いてあります。
本には絶対載っていなくてある教師の授業を受けないと合格できないような情報などただの1つもないので安心してください。
予備校教師の授業があなたを合格に導く訳ではないことを理解してください。
問題の解法をどれだけ自分で覚えるかが大切です。
人気講師の授業をもし受けるなら、その科目もだいぶ合格レベルの問題集が仕上がってきて「この授業でさらに成績を上げるぞ」というスタンスではなくて「あんなにいい本を書いた人は実際の授業ではどんなことを言うのだろう」というスタンスで軽い気持ちでたまに授業を受けるぐらいなら大丈夫です。
月から金までびっちり予備校の授業が入っているようだととても効率的だとは思えません。
☆受験で必要なのはインプット!
何回も言うように受験で結果を左右するのはインプット量です。
受験でのインプットはすべて参考書・問題集で事足ります。なぜなら受験に必要なことはすべて本に書いてあるからです。
人気講師のその科目の分かりやすい説明はすべてもれなくその本の中に詰まっています。
ですからわざわざ大量の時間をかけてその人気講師のお言葉を聞く必要はありません。
授業で90分間聞いているだけでは時間がもったいないです。
90分で4つの大問の解説を聞くより自分で6問の解法を暗記した方がはるかに効率的です。
言っていることが同じなら本の方が何倍もいいです。
人から話を聞くだけでは頭への定着率が全然違います。みんな無意識の内に深層心理で楽をしたいと思っているから授業や人気講師にすがってしまうのです。
はっきり言ってインプットはそんなに甘くありません。
インプットに必要なのはボーっと何回も書いて勉強するフリや授業中スキがあれば集中を切らすことではありません。
インプットに必要なことは「頭を使い理解して、理解したら覚える」。これに尽きます。
そのためだけに本を使います。
本は喋らないので自分から能動的に頭を使って理解せざるを得なくなります。
参考書には
「大事なところが視覚的に強調されている」
「何回繰り返し読んでもいい」
といった利点もあります。
そもそも人気講師の授業を一回聞いてそれを理解して覚えているなんて人は予備校に通う羽目にならず現役で合格しているはずです。
物事は必ず反復しなければ頭に定着しないので1回で覚えられるなんて思わないでください。私は受験に必ず必要な問題集なら1000周でもする覚悟でした。そうしたら受かるのですからこれほどシンプルなことはありません。
まとめますが、最も短時間かつ大量にインプットをするためには理解用の参考書を何週も読んで理解して、問題演習で答えとその理由を何回も理解して覚える、を繰り返すことです。
付録第1章
防衛医科大学を受験する時によく考えなければいけないこと

秋になると医学部受験する人は防衛医科大学医学部の話題が出てきますね。
現役生や浪人生でも受ける人は多いでしょう。
一次の学力試験が10月下旬ということもあり腕試しという名目で受験する生徒の方が多いです。
この章では防衛医科大学を受験する人に向けてその受験は本当はどんな意味を持つのか、そして受験全体に向けてかなり大切なメッセージを込めて書いています。
私が書いている章ははっきり言って全てが重要です。
受験時代、一年かけて独学のみで医科歯科に合格した勉強法を紹介するために記事作成しています。
この記事でもそうですが、各記事では一段落は受験に対する大切な考え方(この考え方さえ身につけば受験の正体が見え合格することへの不安が一切なくなる)を記載していますのでほとんど全ての記事を閲覧することを強く勧めます。
他の勉強法などを紹介する記事等ありますが日本でもトップクラスに核をついているとの自負があります。
バランスうんぬん等、煙に巻いた説明が死ぬほど嫌いですので必ず具体的に何をすれば良いかを全力で文章にしています。
それでは防衛医科大学の受験についてのあれこれを紹介していきます。
☆防衛医科大学の難易度
防衛医科大学の難易度は70前後あり偏差値だけなら東大理科1類2類といい勝負です。
問題が違うので一概には言えませんが一次の筆記試験のレベルは国公立の医学部の中でもトップレベルだということは間違いありません。
理科3類に合格する受験生ならほとんど受かりますが千葉大や医科歯科大を合格する生徒の中には不合格の生徒もいます。
現役生の多くが受けますが10月の段階でこのレベルの問題を解けというのは少し酷かもしれません。
高2ぐらいから本格的に勉強しているそのまま理3に合格する人が受ける場合と高3から始めて千葉や医科歯科には結局受かるけど防医を受ける人の場合では理科において実力差が顕著になって現れますので合否に大きく関わってきます。
多くの進学校の生徒が受験料無料ということもあって受験するのでしょう。
ちなみに私は受けていません。受ける意味すら見出せませんでした。次に詳しく書きます。
☆防衛医科大学を受験する理由を1回考えよう
しかしここで本当に考えなければいけないのは「防衛医科大学に行く可能性はありますか」ということです。
どれほど頭が良くても自分のいける大学は一つだけです。
受験では自分の行く可能性のある大学に一つでも受かれば他の国立や滑り止めの私立にいくら落ちようとその人の受験は大成功です。
防衛医科大学の医学部は学力的な腕試しで受けただけで、もし自分の第一志望の医学部に落ちて防衛医科大だけ受かっていたとしても合格を蹴って浪人すると考えている受験生は受験するのをやめるべきです。
自分の行く可能性のない大学など極論を言えば、受験する意味も、合格するために対策する時間や会場に移動する時間もはっきり言って全て無駄です。
腕試しうんぬんの議論を頭に浮かべるかもしれませんがはっきり言って勉強とは何かを理解できていません。
自分の最も行きたい大学に確実に受かるようにインプットを続ける方が効率的です。
しかもその合格までのインプットの計画の目標達成時期を2月ごろに設定している場合、10月で学力の腕試しなどうまくいかないことの方が多いです。
☆受験では何校も併願すると危険!?
「どこでもいいから医学部に」という理由で私立医を何校も受けたり途中で志望校を変えたりする人がいますがあまりいいとは思えません。
私立医の場合は傾向がはっきりしているところがあります。
しかしそういうところは大抵その医学部専用の知識がいるために他の大学受験問題に対して汎用性がなく何校も受けるのは合格に向けて頭に入れなければならない知識が量的に増えて行きます。
例えば
・一般的な単語帳に乗っていない医療単語を新たに覚えなければならない
・化学生物で知識レベルで専門的な内容まで覚えなければならない
などですね。
国公立が第一志望だとしても受験の途中でうまくいかないからといって志望校を下手に落とすと実は不利な点もあるのです。
国公立大の問題は標準レベルの頻出問題が数多く出題されるために市販の問題集を覚えれば基本どこでも対応できます。
しかしやはりそれぞれの大学で配点・各科目の微妙な難易度の差異・頻出分野が少しずつ違います。
なので勉強計画をその都度軌道修正しなければなりませんが「この大学の方が偏差値が低いから」などという理由でいちいち軌道修正するのは時間が余りにもったいないです。むしろ合格までの計画が立てられていないから迷走するのです。
しかもそれに慣れてどんどん志望を落とし自己嫌悪に至る可能性だってありますのでオススメしません。
実際には偏差値が1か2程度低いといって志望大学を変更するより元から決めた勉強計画を進めて行く方が第一志望に合格しやすいものです。
そもそも偏差値の数値で受験の難易度が決まってはいないということを理解してください。
受験の本質とは合格最低点より上ならば合格ですから。
倍率が毎年100倍だろうが今までE判定しかとってこなかろうが受験当日に合格最低点を上回れるだけの知識があれば文句なく合格です。
大事なのは第一志望の大学の入試問題が解けるためだけの知識です。
このnoteで何回も口すっぱく言っています。これが本質で全ての科目の全ての記事はこれをゴールに書いています。
偏差値ではありません。
偏差値の細かい数値で自分の行く末を支配されないように今言ったことをしっかり念頭に置いてインプットを続けて行きましょう。
付録第2章
親の年収で学歴が変わるのには相関関係がある

この章はお子さんがいる方に是非よく読んでいただきたいです。
「親の年収と子供の年収は比例する」なんて都市伝説のように思われますがこれ中々相関関係あります。
しかもはっきりと理由があります。
それは教育にかけるお金と親による学歴の重要性の認識です。
まず最終学歴が年収の多少に関わってくるのは厚労省のデータからも明らかです。東大卒が年収いくら、早慶卒が年収いくら、なんていう大学別のデータも出ています。大学別にまで出す必要性はわかりませんが大卒と高卒では年収にかなりの開きがあります。
親の年収で子供の最終学歴がある程度決まるというのは本当です。
少し具体例をあげて見ていきましょう。
☆親に学歴がない場合(特に地方に多い)
日本の特徴として大企業の本社、政治機関などはすべて東京及び大都市圏にあります。
そこに勤める人たちはある程度学歴がある人たちが多く必然的に都会に高学歴の人が、地方に低学歴の人が多くなります。
本社に勤める人は頭脳職ですが地方の下請け会社などで働く場合にはそれほど学歴は必要ありません。
地元の国立大を出てればいい方です。
親に学歴がないと学歴の重要性が理解できていません。
だから子供を小学生の段階で塾に通わせたり、県内の進学校を受験させようという思考に親がいたりません。
小学生ぐらいの段階の子供は自我があっても自分で自分の人生について理解できる段階ではないです。
なので親が方向性を与えてあげないと子供は地元の小学生たちとまったく同じ価値観になります。
「人は無意識の内に環境に左右される」とはよく言ったもので、
勉強ができる=かっこ悪い
悪ぶって遊ぶ=かっこいい
という価値観が子供に確立されてしまったら、その子供にどんなに才能があったとしてもその時点でその子は潰されてしまいます。
するとどうなるか。
才能があったとしても親と同じようなレベルの学歴、人生を歩むようになります。
例として地方の人は地方で生まれたら生涯地元に残って地元に貢献することが正しいという風潮がありますから親がそうだと子供も影響を受けてそういった選択をしてしまうのです。
都会に出ることが必ずしも良いことばかりとは限りませんが確実に良いことがあります。
それは人との出会いです。
資格の勉強や知識のインプットは全国どこにいても本とインターネット環境があれば誰でもできますが都会には出会いがあります。
自分がすべき勉強を頑張りながら人との出会いというチャンスにも恵まれています。
ある決まった職業にとらわれない、人生でいろんな事業に手を出してみたい、何するか決まってないが独立して挑戦したいという動機で都会に出てくるのも素晴らしいと思います。
話を戻します。
子供を自分よりもいい学歴の大学に行かせてあげたいと思うならば子供を塾に行かせて中学受験をさせることです。
まず塾に入り勉強ができることはかっこ悪いことじゃなくてむしろ褒められる、という環境を子供に与えるべきです。
そうすることで子供は自然と勉強ができるような子達とつるむようになり、悪ぶっているだけのグループからは離れていきます。
☆親に学歴がある場合(首都圏に多い)
先ほどの説明通り学歴のある親は学歴の重要性を理解しているので子供にも将来のことを考えて早いうちから中学受験をさせます。
なぜなら子供は環境に左右されながら成長するので頭のいい子たちがいる学校に入りさえすれば、頭がいいことは素晴らしいという価値観を持って成長することを親は知っているからです。
言うなれば、教育を周りの環境に任せているのですね。
これは全然間違ったことではありません。中学ぐらいまでは子供は自分や人生のことなど自分では判断できないことが多いので親が指針を与えてあげることが大切です。
しかし大学受験する段階になったらもう親のしてやれることはありません。
自分で考えて自分で第一志望に合格するしかありません。
この段階になってまで親が子供を半ば強制的に塾に通わせているのは、ただの過保護ではっきり言って子供の邪魔にしかなりません。
経済的な支援は大切ですが高校生になったら放っておきましょう。
余談ですが、地方で生まれて親に学歴がある場合お母さんと息子2人で中学受験のために上京し6年間子供を都内進学校に通わせながら2人暮らし、というパターンも多いです。
それぐらい学歴のある親は教育の重要性を理解しています。
付録第3章
難関医学部に受かる8割はただ環境に恵まれただけ!?これが地方との教育格差!

東大医学部・京大医学部やその他旧帝医学部に受かる人は中学生ごろから学力0から確固たる意志を持って受験勉強を始め合格を勝ち取ったわけではありません。
これはみなさんの周りを見てみればすぐに気づけます。
地元出身で同じように地元の公立かちょっと頭のいい私立にいる同級生の中で「俺は東大理3に受かるのが目標でその為に努力し続けるんだ!」と言って実際に理3合格までこぎつけた人はいますか?
少なくとも私の周りには1人もいませんでした。
医学部に行きたいなんて言っている同級生すらいなかったですね。
もしそんなことを口にするような同級生がいたとしてもそれは完全に親の影響です。
そのぐらいの年代の子供が圧倒的な自我で目標を医学部に定めたわけではありません。
実は、東大医学部や京大医学部、その他旧帝大の医学部に合格する受験生は頭が良くて入れたわけではありません。
もちろん入試当日に合格できるだけの学力があっことは間違いないですがだからと言って元から才能があったわけではありません。
その答えは環境に恵まれていただけなのです。
具体的にいうと10~12歳までに偶然教育環境が良かっただけです。
☆難関医学部に合格する人の鉄板パターン
まず環境に恵まれた人という問いの答えを先に言います。
それは都市圏の有名中高一貫私立高校に中学受験で入ってくる人です。
まず彼らの親は教育熱心かつ裕福なことが多いです。
その理由はもちろん裕福であることと教育熱心であることに相関関係が見られることは前章で説明した通りです。
小学校からSAPIX、早稲田アカデミー、日能研などの塾に通わせ中学で進学校に通わせます。
そんな中で大学受験を意識している小学生なんかいません。
とりあえず中学に入学したら親の教育としての第一段階終了です。
私は今第一段階が終了と説明しましたが、私の持論としてはこれが第一段階でもあり最終段階でもあると思っています。
あとは子供を育てるのは親→環境へと変わるのが正しい教育だと信じているからです。
高校生にもなって親が子供の勉強に首を突っ込んでいる話を聞くと歯がゆい気持ちになります。
第一段階終了時点で既に高校生になってから大学受験を意識するようになる人とは大きな学力的隔たりが生まれます。
そういう高校生の中には1年や2年じゃ埋められない差となります。
中学校に無事合格した後からの続きです。
有名進学校に入学して中3や高校生ぐらいから鉄緑に通い始めたら、そこからとてつもない量の問題をこなします。
彼らは高2の終わりや高3になると自然に難関医学部を第一志望にしても問題なく受かってしまう下地が出来上がっているのです。
周りの講師も受験を数年前に終えたばかりの受験エキスパートだらけであり受験の成功者だらけでもあるので受験の最新傾向を教えてもらうことができるのです。
彼らは最初から環境に恵まれていただけなのです。
都会に住んでいて親が教育熱心で塾に行かせてもらえて、周りもみんな東大・医学部に行くから自分も周りと同じことしてればそれ相応の所に行けてしまうというのが地方受験生と都会受験生の教育格差の真実というやつです。
私は鉄緑会の存在を初めて知ったのが高校卒業時でその実態を知ったのが医科歯科入学後でした。
私が浪人しているときに在籍だけしていた予備校のチューターも知りませんでした。
チューターの頭の中には駿台と河合塾のどちらが優れているかしかありませんでした。
今回話したのは事実です。
しかしこれらは受験生が志望校を諦めなければならない理由にはまったくなりえません。
理由はのちに後述しますがそれが1番伝えたいことでもあります。
☆鉄緑会という漫画の世界のような塾をご存知ですか!?
「鉄壁」という単語帳が有名です。
地方の書店にも置いていますし一度は聞いたことがある人が多いかもしれません。
この「鉄壁」は東京と関西にしかない「鉄緑会」から出版されている本です。
この塾こそまさに地方と首都圏(関西)の受験生の学力差を生む大きな原因の1つです。
ていうかほぼこの塾の影響です。
初めて聞く人もいるでしょうから簡単に鉄緑会について説明します。
この塾は塾が指定した超有名校(開成、筑駒、麻布、桜蔭、etc)の生徒は顔パスで入塾できます。
それ以外の中・高校は入塾テストをしなければ入れない超エリート塾です。
また関西にも鉄緑会があります。ここには灘生や関西有名校の生徒がたくさんいます。
この塾は高校年代における上から成績上位のうち90%以上が在籍しているような塾です。
誇張しているわけではなくリアルにそうです。
あなたが今受験生だとしたら今年の受験界で学力高い順トップ100を見ると80人以上は鉄緑生でしょう。
この塾は簡単に言うと東京大学専門塾です。
鉄緑会の名前も東大医学部の「鉄門」と東大法学部の「緑会」を合わせた塾名です。
講師は現役の理3か文1の学生もしくはその卒業者のみです。
次に実績を見てみましょう。
進学別に見ると現役の理3合格だけで見ると6割強なので恐らく1浪も合わせると8割程度の理3生が鉄緑会出身ということです。
これって恐ろしくないですか?
日本の受験に携わる多くの人は理3生のことを「宇宙人」「人外の天才」などと勝手に評価してくれますがその実態はたった1つの塾の出身者が8割を占めているのです。
試しに書店で「理3本」を手にとって見てください。
理3本は今年の理3の合格者40人にどんなプロフィールでどんな勉強をしてきたかを合格者自身に書いてもらったものを集めた本です。
その中身を見るとほとんどの人が鉄緑会に通っていることがわかります。
ほかにも東大他類、医科歯科、筑波医、千葉医、慶応医などの上位私立医には非常にたくさんの鉄緑生がいます。
次に実態を見てみましょう。
私は鉄緑出身ではないのですが医科歯科の同期に鉄緑出身者がいたので実際に話を聞いたことを要約して説明します。
この意見は貴重です。
なぜならホームページなどでは分からない実際に起きているリアルな実態が文面として情報源から手に入れられるのですから。
簡単に箇条書きします。
▪️とてつもなく宿題を出す塾として有名で、実際にそう
▪️受験期になると大きくA,B,Cの3クラスに分かれて、その中でもA1,A2などと分かれている
▪️Aクラスが1番良く、特にA1クラスに数学か英語で在籍している人は全員理3に合格する力がある
▪️例えば英語Bクラス、数学Bクラスでも筑波、千葉、医科歯科には普通に通る学力
▪️だいたいみんな中3から数学や英語などに通い始め、高校入ったら理科も取り始める人が殆ど
▪️みんな(特に男子は)中3ぐらいまでは勉強せずただ通っている状態だが高1、高2になると一変して鉄緑の勉強に集中する
▪️「Aクラスに入るにはしっかり宿題をやっておけばいい?」という私の質問に「そんなことしたらAどころじゃなく、間違いなく理3余裕で入れるよ(笑)」と返された。
質問については友人の主観も入っていますが、大抵鉄緑出身者はこのことを言います。
こんな漫画に書いてあるような塾が実際に存在するんだなと私は大学に入ってからとても驚きました。
しかし実際怖いのはその塾ではなくその塾を一切知らなかった私を含め地方の受験が大多数であることです。
東大模試とかの成績優秀者で「兵庫」出身者は全員灘の鉄緑生と思って差し支えないでしょう。
☆しかし合否を決めるのは...
総論の最後の段落としてだけでなく私の受験に対する考え方のまとめとして締めくくります。
読んでくれている皆さん、本当にありがとうございます。後少しです。
難関大に医学部に受かる人の鉄板パターンや鉄緑会の存在を知った人は今どういう気持ちですか?
「こんな事実があるなら自分は地方出身だし今もう高校生になっちゃってるし手遅れだ」
なんて思っている人がいると思います。
しかしこれらのことは受験当日には関係ありません。
誰がいつどこで何をどのように「今まで」してきたかは大学入試では1mmも問われません。
大学入試で問われるのは「今」どれほどの知識を頭に入れてきた状態で会場までやってきたのかということだけです。
高校中退の不良でも大検として東大の二次試験で300点とったらその瞬間に「中卒→理3生」と肩書きが変わります。
合格するために1番必要なものは他にあります。
違います。1番ではありません。唯一です。これしか必要ではないです。
それは合格最低点以上の知識です。
受験生の中で倍率や判定などの受験当日に何も役立たないものに思考の邪魔をされている人は今すぐ考えを改めましょう。
「そんなことはわかってる」と心の中で反論している人も判定をちょっとでも気にして気を揉んでいるようではまだ足りません。
私はこの考え方が完全に身についていたので、
▪️模試の日→時間の無駄なので極力受けませんよ?
▪️倍率6倍かぁ高いなぁ→例年の倍率はどうでもいいから合格最低点のみに焦点を
▪️ノートに自分の考えをアウトプット→知っていることを紙に書いてどうするねん
▪️予備校の授業を大切に→予備校の授業で合格を絶対に確信できるの?
という行動の選択や思考をしていました。
これを真似しろと言っている訳ではありません。
これらの根底としてあることはいかに時間の価値を高め受験当日までに足りない知識をインプットしていくかという考えが元になっており、このことをしっかり意識すればあれらのような思考になります。
まずはこのマインドをもって日々の勉強に臨んでください。
そして行きたい大学に無事合格される事を願っております。
以上、読んで頂きありがとうございました。
東京医科歯科大学 Yajima Yusuke
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
