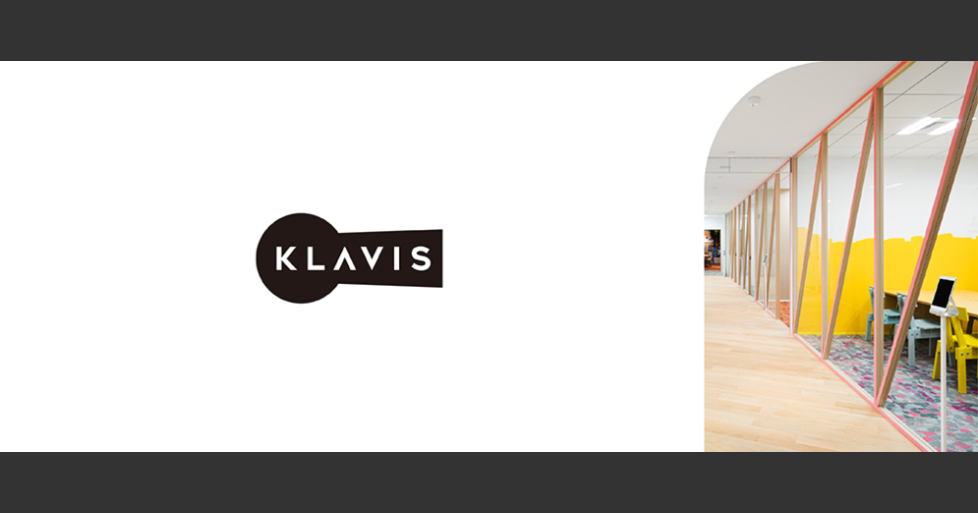来期に向けて”組織の力”さらに高めるべく開発チーム合宿を開催しました!!
みなさんこんにちは!クラビスの佐藤です。
先日クラビスでは1dayの開発合宿を開催しました!
そこで今回は、合宿の内容とその模様を大公開いたします。ぜひ最後までご覧ください!
開催背景
今回の開発合宿は10月13日、箱根にて1日を通して行いました。
普段のオフィスとは異なるロケーションで、かつその後の懇親会で希望者が宿泊することに楽しみを感じてもらえるような場所という条件で、人事部が選定しました。(ここだけの話ですが、軽井沢との2択で迷ったので次回は軽井沢かもしれません。)
そんな、ロケーションを重視した研修場所は三菱地所さんが運営する、「WORK×ation Site 箱根湯本」です。

さて、この開発合宿の目的は”チームビルディング”です。クラビスは現在もリモートワークがメインとなっています。開発チーム単位では当然ながら日常的に連携が発生し、関係ができています。一方で、プロダクトカットのチームになっているため業務が自チームで完結できてしまい、チームを横断したコミュニケーションが少ない状態でした。
そのため、プロジェクト進行の最適化だけでなく、チームを超えて異なる知見を持つメンバーが意見交換や相談できる環境をつくっていくことが次のステージへ向けた一つの課題でした。これまでも月次の全社会議である All Hands をはじめ、定期的なオンラインでの懇親会などチームを超えたコミュニケーションが生まれるような施策も行ってきました。オフラインで顔を合わせながら双方向でのコミュニケーションが起きる経験をともにすることで、効率的にこの課題を解決できると考えました。
合宿のコンテンツ
開発組織のチームワークを醸成することを目的とした本合宿ですが、当日のみ”やった感”を得られるものでは意味がないと考えています。そこで、自分たちの今の組織状態を理解し、今後の組織をより良くするきっかけとなるコンテンツとなるよう意識しました。

チームビルディング研修
マネーフォワードで研修を担当されている方に講師として来ていただき、チームビルディング研修を実施しました。
実は、クラビスの現メンバー全体でチームビルディングについて学ぶのは初めてでした。そのため、講師の方から投げられる議題に対して様々なアイディアが飛び交います。
まずは「いいチーム」とは何かについて議論がありました。踏まえて、組織を成功に導く考え方を知り、まずは”関係の質”を重視した行動を取っていくことの重要性を理解しました。
とはいえ、理解と実践は難しいものです。続くコンテンツではヘリウムリング(複数名が人差し指を出し、その上にフラフープを置いて、地面にフラフープを置くアクティビティです)を行いました。比較的有名なアクティビティですので、今この記事をお読みの方にも体験されたことがある方がいらっしゃるかもしれません。

さて、私たちが実際に行った結果はというと・・・全然下がりませんでした。最初のトライではほとんど下がることがなく持ち時間を消費してしまい、各チーム頭を抱える状態に。続くトライでは、意見の活性化、起点となる人物の選定など、様々なアイディアが飛び交い、成功に近づいていきました。
そんな、活発な行動のあとはリフレクションです。良かったところ、悪かったところ、普段の仕事と似ているところを振り返りながら、”楽しかった”で終わらないように進行していきます。
午前中はこうしたアクティビティと議論、振り返りを通して、理論を肌で感じながら進んでいきました。特に、チームの成長ステージ(タックマンモデル)の共通理解を通して、グループからチームへと組織を移行する重要性、難しさ、そして現在の立ち位置を学べたのではと感じています。
コミュニケーション研修
お弁当を囲んで和気藹々とお昼を済ませた後は、午後の研修です。
午後は、私たち人事部が用意したコミュニケーション研修です。
まずは座学+ディスカッション、次にゲームを通した実践、最後に再度ディスカッションと3部構成で進んで行きました。
座学ではコミュニケーションのフレームワークを共通理解し、持ち帰ってもらえるよう進行していきました。クラビスで取り入れたのはアサーティブコミュニケーションという、相手を尊重しながらも、自分の意見を伝え切ろうという手法です。実際のアサーティブコミュニケーションには様々な書籍や外部研修などがありますが、その中でも基礎となる姿勢、伝え方、聞き方に重点を置いて、座学とディスカッションを進めました。

自分はどんな伝え方をしていたか、どんな聞き方をしていたかを振り返り、よく話せる人は聞く力と姿勢を、話すことが苦手な人はまず伝えてみることを、それぞれ理解できたのではないでしょうか。
今回の合宿では、一過性、つまり合宿だけで終えるのではなく、普段の業務に活かしてもらうことを重視していますので、座学だけでなく、体で覚えられるような体験も重視しています。今回、コミュニケーションのあり方を見直し、体験してもらうきっかけとして、コンセンサスゲーム(与えられた課題について、チームで協力しながら、合意形成を目指すゲームのこと)を行いました。いくつかメジャーなものがあるのですが、その中で今回はNASAゲームという”惑星に不時着した宇宙飛行士は手持ちのアイテムをどんな優先順位で保持すればいいか”を議論するゲームを実施しました。
ゲームでは、15のアイテムの優先順位を
・個人でつける(理由も必ず)
・チームでつける(多数決ではなく理由を理解し合い、議論して決める)
・実際のNASAの回答と照らし合わせる
といった流れで進むのですが、ただ、4チームがそれぞれ動いて結論を出すだけでは盛り上がりにかけてしまいます(何もなくても楽しんでもらえたとは思いますが)。そこで、今回はNASAの回答と差分が一番少ないチームにちょっとした賞品を用意し、議論が実績につながる体験もしていただきました!
普段考えないテーマでの議論でしたので、選んだ理由が現実的であったり、独創的であったり、異なる考えの意見が活発に飛び交っていたことが印象的でした。

さて、研修最後のコンテンツはディスカッションの時間です。実業務に付帯するチームに分かれ”理想的な開発体験”というテーマで議論してもらいました。
技術者としての経験値、レベルだけでなく、年齢など様々な人財が所属しているクラビスですので、そもそも”理想的な開発体験”から連想されるイメージは多様でした。まずはコンセンサスゲーム同様、先に個人の考えを固めてもらい、その後チームのディスカッションです。”理想的な開発体験”をチームで定義しないまま、個人の考えを順番に発表していったため、様々な価値観と理想が出揃います。どうやってチームとして一つの理想を固めるのか、それぞれ頭を悩ませていました。
そして、およそ1時間弱のディスカッションを通してでた結論を全体で発表し、午後の研修のコンテンツは締めくくられました。各チームが明日からの開発に活かすための現実的な一歩目と中長期的な理想を掲げ研修は終えました。
全体を通して、今日1日だけのものとしないというテーマが伝わっていたこともあり、より実務と照らし合わせながら進んだ本合宿。後日談ですが、あるチームではコミュニケーション用の新たなチャンネルをつくったり、別のチームではコミュニケーションの頻度や品質を見直すなど、成果に近づくきっかけになったようです。

今回、開発組織の取り組みについて、記事にさせていただきました。クラビスがどのように組織の状態に向き合い、そして、どんな形でワークしているのか少しでも伝われば幸いです。
クラビスは、一人ひとりの成長と向き合い新しい学びを後押しする環境があります。
ここまで読んでいただいて、少しでも話を聞いてみたい、もっと働く人の顔をみてみたいという方はぜひ一度カジュアル面談をしませんか?
ご応募お待ちしております。
▼カジュアルに面談で話を聞いてみたいという方はこちらからエントリーください
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?