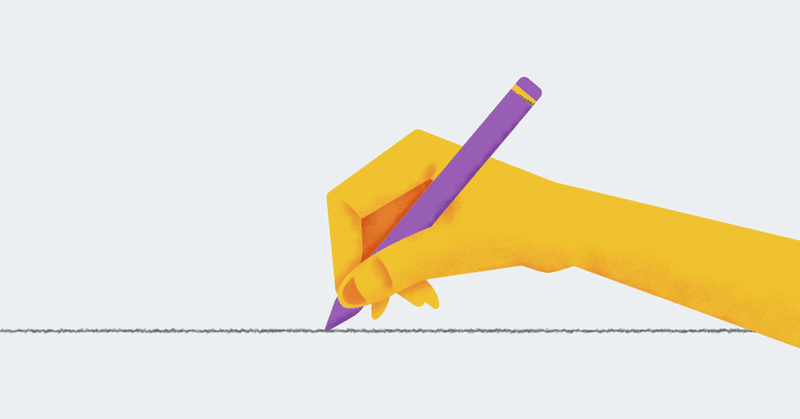
修士論文の書き方:執筆中に気づいたことをふり返る
このnoteでは,私が2015年に所属研究室の合宿の際に「修士論文ができるまで」というタイトルで行ったプレゼンテーションをシェアしたいと思います.
修士論文執筆を振り返る
今回のnoteは(発表当時,D2であったころから)修士論文の作成過程を振り返って,今後の研究生活の向上を図ることが目的です.私の修士論文は「教育達成の階層間格差における下降回避仮説の検討」というタイトルで,のちに学会雑誌に掲載され(毛塚 2013),さらにありがたいことに学会賞をいただくまでになりました(毛塚 2017).修士論文執筆中に気づいたことを,個人的な経験と絡めてお話できればと思います.
なお,このnoteでは論文の内容には踏み込みません.もし,内容を知りたい方は論文をぜひ読んでください.
今回のnoteで書かれていることは,あくまで個人的な経験ですので,読者のみなさんに適用できるかはわかりませんが,みなさんの参考になれば幸いです.
修論ができるまで
混沌のM1
私の修論までの道のりを順を追って説明しましょう.まずはM1の時代からです.当時,考えていた最大の「やりたいこと」は「数学を社会科学に応用したい,数理モデルを使って何かしたい」ということでした.数理社会学を志し,数学科から社会学の研究をする環境にやってきた私は,とにかく「数理モデルで何かしたい」しか頭にありませんでした.
そうした中で,ぼんやりと対象を考えていきます.当時は文化社会学に関心があったので,P. ブルデューの文化的再生産論の話(Bourdieu 1979=1990, Bourdieu and Passeron 1970=1991)とかを読んで,何かこの理論の一部を数理モデルで議論できないか,といったことを考えていました.
分析対象すらぼんやりしていた修士研究はうまくいきません.テーマを2, 3回変え,いろんな分野を見歩きした結果,あまり実りのない1年となりました.
対象を定めたM1の終わりごろ
M1の終わりごろに,分析対象を「教育の階層間格差」に絞ることにしました.理由は,もちろんM1の間に読んでいた本『再生産』(Bourdieu and Persron 1970=1991)に面白さを感じたのもありますが,相対リスク回避仮説という数理モデルベースの理論枠組み(Breen and Goldhorpe 1997)に出会ったこともあります.
そして,「教育の格差」という現象の理解に軸足を置き始めたのもこの時期でした.それまで,「分析手法(数理モデル)をいかに使うか」が軸足にあったのですが,それを対象への理解に軸足を置きなおすことにしたのです.
そこからの行動は迅速でした.関連論文・書籍をかたっぱしから読み漁り,どのような議論・研究がなされているかを把握しました.また,手持ちのデータや公的統計で実際にどうなっているのか,確認したりもしました.
そうすると,いくつか「できそうなこと」が見えてきます.たとえば「この説明,なんかしっくりこないな」とか「こういう指標を使えばもっとズバッと言えそうだなぁ」とか「なんだ、か先行研究の結果がまちまちだなぁ,、別の要因を検討すべきかもなぁ」とかそういう「穴」が見つかってきます.この穴のどれかを埋めるだけでも,修論としては大成功かな,と考え始めました.
とりあえずモデルを作ってみたM2前期
そこで,まずは手を動かすことにしました.私の場合は,数理モデルを作って分析することでした.ほかの仮説(学歴下降回避仮説,吉川 2006)を組み込んだモデルを作り,分析をしました.合計4つのモデルを作って,それぞれのモデルからどのような帰結(専門用語ではインプリケーション)が得られるのか,分析をしました.
モデルをふるいにかけたM2後期
4つのモデルを立てただけでは終われません.一定程度,説得力のあるモデルたちの中から,どのモデルが現実に対して適合的か,明らかにしないといけません.そのために,数理モデルの帰結と社会調査データを見比べて,更なる分析を行いました.
以上のM2の時に行った分析をまとめたものが修士論文を形作りました.なので,実質的な分析はM2に凝縮されていることになります.M1はインプットの時間であったといえば聞こえがいいですが,結局のところ右往左往しているだけでした.
何がダメだったか/よかったか
手法より対象,前提よりゴール
私がM1の時に迷ったのは「数理モデル」に軸足を置いていたからです.そうなると,何をすればいいかが定まることはありません.ゴールがないからです.
一方で「対象」に軸足を置くと「この現象のメカニズムを(部分的にでも)明らかにする」とか,「この問題の実態を明らかにする」というように,ゴールが明確になります.そうなると,自分が何を示せばいいか明確ですし,結果もわかりやすく,理解もされやすくなります.
このゴールを定めることにはもう一つ良い副作用があります.それは,本来ゴールが明確でないと使えない言葉の乱用を防ぐことができることです.たとえば「改善する/最適化する/よりよくする」という言葉は,ゴールが定まっていなければ「良い」が定義できないので,ゴールがない限り使うことはできません.
あるいは,先行研究の手法が「不十分である/適していない」といった言葉も,先行研究とゴールが違うので当然と言えば当然です.先行研究において「管見の限り見当たらない/十分な蓄積はない」といった言葉は,ゴールは同じだけど違う分野の研究を拾えていない可能性を無視しています(たいてい,別の分野で別の言葉で似たような研究がやられているものです).言い換えると,ゴールへの別ルートの探索を怠っているわけです.
シンプルなスタートから,必要最小限の複雑性を確保する
社会学の理論は,たいていすごく複雑です.私が読んでいたブルデューの本も例外ではありません.当時の私はその理論を,そのまま理論化しようという無茶な野望を抱いていました.ほかの分野でも同じだと思いますが,最初から複雑にしすぎると,ブラックボックスしかできません.そうなると,何がメインかわかりづらいし,異なる水準の議論(個人と集団,概念と測定,記述と規範などなど)が混在しやすくなります.
それならば,最初はシンプルなモデル・理論・説明・アイディアをいくつか考えて,そのふるまいを確認するところから始めると,見通しが良くなります.スタートはとにかくシンプルにして,それでうまくいかなければ徐々に足していく形にしていくことで,自分の理屈を混乱することなく,ブラックボックス化することもなく理解することができます.
複数の理論・モデル・予測の立て方が,同じぐらい有効性を持つことが往々にしてあります.そこで初めて「ふるい」にかける必要があります.その時には,「ふるい」の基準を明確にしておきましょう.よりシンプルなものを選ぶのか(倹約性),より安定的なものか(頑健性),よりデータに適合的なものか(適合度指標),理論と整合的なものか(整合性),さまざまな基準から自分で選び取らなければなりません.
やってみるべきこと
ここからは,修論を書き終えてわかったやるべきこと/やった方がいいことをまとめます.
まずは実際どうなっているか確認する
自分が扱おうとしている対象・事象について,実態を把握することから始めましょう.全体の傾向としてどうなっているのか,確認しましょう.たとえば,データベースをあたってみて,傾向を確認することができます.データベースには以下のものがあります.
・e-Stat (政府統計のポータルサイト)
・World Bank Open Data(世界銀行のデータベース)
・OECD.stat (OECDに関するデータベース)
あるいは,入門として新書にあたるのもよいかもしれません.この点は別の記事で触れましたね.
とりあえず手を動かすといいことある……かも
いろいろ理屈をこねるのも重要ですが,なにはともあれまず手を動かしてみることで見通しが良くなることがあります.統計分析ならとりあえず分析してみる,数理モデルなら作ってみる,シミュレーションなら組んでみる,質的調査なら人に聞いてみる.一回簡単に手を動かすと,改善点,コツ,罠,先行研究の理屈などなど,いろいろなことが見えてきます.
"Done is better than perfect."という言葉があります.Facebook創始者のマーク・ザッカーバーグ氏の言葉と言われています.この意味は「完璧よりもひとまず完成させることが大事である」ということです.いったん何かを作り上げ,そのあとに徐々に改善していく姿勢の重要性を説いています.この精神は研究においても当てはまります.とりあえず,一回手を動かすことで,完璧へ一歩一歩近づいていくことになります.
(ちなみに,Facebookは以前映画『ソーシャル・ネットワーク』を取り上げましたね)
自分の研究を人に話してみる
自分にとって面白いと思っているポイントは,他人にとってどうでもいいことかもしれません.その逆もしかり,ほかの人が何を面白がるかはわかりません.わたしも指導教員との対話から,自分の研究の意外な「面白いポイント」を見出すことができました.
また,人に話すことで,何を説明すべきか,どのような説明をすれば「かゆいところに手が届くのか」がわかります.修論の質も向上するので,積極的に話してみましょう.
以上,私の修士論文執筆からのふりかえりでした.みなさんの助けになればなによりです.
参考文献
Bourdieu,Pierre, 1979, La distinction : Critique sociale du judgement. , Paris:Minuit. (=1990, 石井洋二郎訳『ディスタンクシオン――社会的判断力批判I,II』藤原書店.)
Bourdieu,Pierre and J.C.Passeron, 1970, La reproduction , Paris:Minuit. ( =1991, 宮島喬訳『再生産――教育・社会・文化』藤原書店.)
Breen,Richard and John H. Goldthorpe, 1997, ”Explaining Educational Differentials:Toward a Formal Rational Action Theory,” Rationality and Society, 9(3):275-305.
吉川徹, 2006, 『学歴と格差・不平等――成熟する日本型学歴社会』東京大学出版会.
毛塚和宏, 2013, 「教育達成の階層間格差における下降回避仮説の検討」修士論文, 東北大学大学院文学研究科提出.
毛塚和宏, 2017, 「数理モデルと実証分析の協働」『理論と方法』 32(1):3-12.
