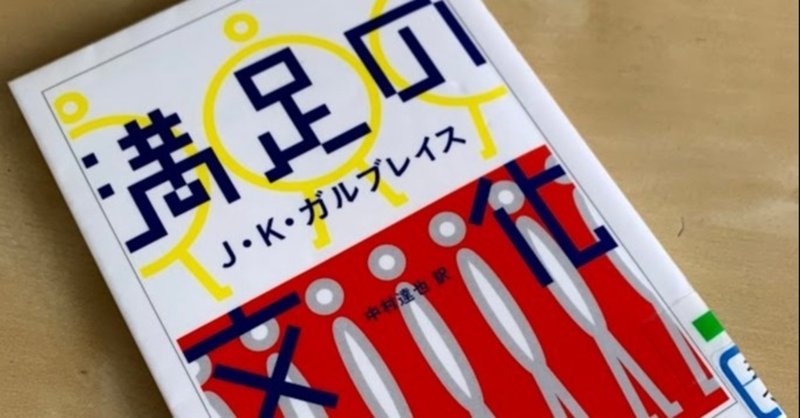
J・K・ガルブレイス「満足の文化」~「馬にカラス麦を十分与えればそのおこぼれを雀が食べる」
6月の末にリクルートワークス研究所が主催するオンラインセミナー「コロナは働く人の意識をどう変えたか」に参加した。神戸大学大学院経営学研究科の服部泰宏准教授が最後のコメントの中でJ・K・ガルブレイスの「満足の文化」に触れていたので興味をもち早速本書を読んでみた。
本書は自己満足の感情、すなわち「満足の文化(the culture of contentment)」を支える人々(「満足せる人」)がアメリカにおいて支配的な政治的影響力を持つようになった経緯を論じている。
まず「満足せる人」は長い時間をかけて問題を解決するよりも、とりあえずは何もしない方を好む。彼らは引き続き満足を得ることを正当化してくれる大義名分を生み出し、長期的福利は考えず当座の平安と満足に精力的に反応する。大義名分とは社会的援助や扶助は「恵まれていない人」をダメにするとか「選択の自由」、「意思の自由」、「公的活動の賢明な視覚化」等をいう。
デモクラシーのもと社会を支配するのはこれら「満足せる人」であり、「恵まれていない人」はデモクラシーに参加していない。とかく「恵まれていない人」は「満足せる人」の階層にその原因がある問題をも政治家のせいにし批判するが、政治家は単に自分を擁立した選挙民の充実な代理人に過ぎず、本当に責められるべきなのは「満足せる人」だという。
ガルブレイスは、「仕事」についても辛らつだ。仕事は人によっては「無味乾燥で、苦痛に満ちた品位のないもの」である一方、人によっては「楽しく、社会的な評価が高く、経済的な報酬もおおいもの」であり、これが「現代のペテン」だと指摘する。
現代社会は中間所得層の「満足せる人」へのシフトを促したが、依然「無味乾燥で、苦痛に満ちた品位のない」仕事はなくならず、これらの労働力を埋め合わせするために、農場で働いていた南部の黒人はデトロイト自動車産業で働くようになり、さらには移民への依存度が高まり「恵まれていない人」として新たに社会に組み込まれる。これら「恵まれていない人」は経済向上を期待しながらも実際に統計では経済的な立場は低下している。つまり一般労働者と高所得者層の所得格差はますます広がっている。
「満足せる人」の一部になった中位の所得者層は高所得者層への増税に同意しない。これは万人に対する増税から身を守るための「連帯」による。また経済政策が金融政策に依存するのは、財政政策は財源確保のために「満足せる人」への課税強化につながるからである。「満足せる人」は所詮税金とは「恵まれた人が支払いそうでない人が受け取る」ものだと信じており、増税で自らの負担が増えることを拒む。
トルストイは「多数者の側に身を置くことほど楽なことはない」という。大脳作用による思考とそこから生じる意見や行為ほど、仕事上の対人関係を損ない当初の計画を覆し、時には自分自身に苦痛を与えるものはない。ガルブレイスは大企業の経営層はとかく官僚批判をするが、彼らもすでに動脈硬化をおこしており官僚と何ら変わるものではない、という。大組織では「組織の方針を受け入れ自己の考えを放棄してしまう人々にこそ報酬が与えられる」と言う。
経済学についても、「満足せる人」におあつらえ向きの理論が続出した、と辛らつだ。ジョージギルダー、ラッファー曲線、マレー博士などが「サプライサイド・エコノミクス」の理論的支柱となり、「馬にカラス麦を十分与えればそのおこぼれを雀が食べる」という考えを支援した。
満足の時代の二つの脅威は「軍事活動」と「下層階級の反乱」だというが、彼はその効果も限定的だとみている。伝統的に共和党は「満足せる人」層の忠実な代理人だが、民主党といえども「満足せる人」を意識せざるを得ず、空虚な理念は述べても実際に富裕層への増税には及び腰になりがちだという。
目下のところ米国は新型コロナウイルスの感染者数拡大がとまらない中、更なる脅威であるBlack Lives Matter(以下BLM)の問題に直面している。その意味ではまさにガルブレイスが予測した「下層階級の反乱」が起きているわけだ。これに対してトランプ大統領は「法と公正」を縦に断固とした態度を示そうと躍起だ。
Netflixで「13th」というドキュメンタリー映画が公開されているが(2020年7月3日現在YouTubeで限定無料公開中)、この映画はBLM運動を理解する上で大変参考になる。
南北制度で終わりを告げた奴隷制度の後に次々と生まれる”Convict Leasing"や”Jim Crow"などの代替人種差別システム。その中でも最も今の状況を加速化したのは"Law and Order(まさにトランプが言う「法と公正」!)"や”War on Drugs"の名を借りた共和・民主両党間の刑事罰徹底競争と”Minimum Sentencing"や”Three Strikes"などの連邦法州法改正から生まれた大量の受刑者数増大だった。そして成長する巨大産業としての刑務所ビジネスに群がるビジネス界と政界。これらはガルブレイスがいう「満足の文化」の大義名分そのものだ。
最後にガルブレイスは将来の予測をするが「残念ながらハッピーエンドではない結論を述べなければならない」と最終章の「レクイエム」でいう。
果たしてBLMは新型コロナウイルスによる経済破壊と相まって悲観的だったガルブレイスを驚かすような社会変革に進展していくのか。そして来る大統領選はどうなるのか。それらの結果は移民問題はまだ顕著で無いものの、所得格差が拡がる日本社会にどのような影響を及ぼしていくのか。こういった疑問を考察する上で本書は絶好の参考書だといえよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
