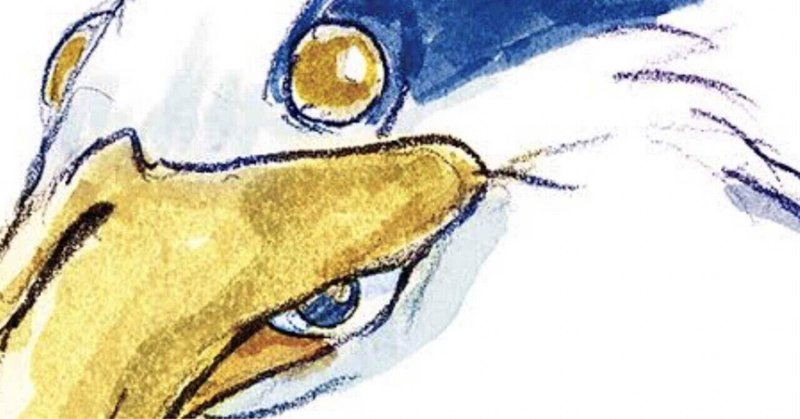
"君たちはどう生きるか"を工芸職人の立場から読み解く
宮崎駿最後の監督作品と言われた「風立ちぬ」から10年、まさかの新作「君たちはどう生きるか」が公開されました。
SNSで口コミを覗くと、頭を悩ませている人しか見受けられない状況。
私は数日後に大切な仕事が控えているので、変な悩みで頭を支配されてしまったら困るなぁと見にいくかどうか大変迷いましたが、気になって逆に何も手につかなくなってしまったので公開2日目の7月15日(土)に観に行ってきました。
結論から言うと、観に行って本当に良かったです。
でもこれはあくまでも私の感想です。観る人の置かれている境遇などによって、感想は全く違うものになると思います。今の私にとってはものすごく辛くもあり、清々しくもあり、そして揺さぶられる最高の作品でした。
個人的な解釈のうえでですが、私にとっては今作がこれまでのジブリ作品の中で最も衝撃をうけ、生涯心に残り続けるものとなりそうです。
以下、少し内容を含むことを書きますが、ストーリーのネタバレには影響しないかと思います。なぜなら、この作品はストーリー自体に重点を置いたものではない(と私は思っている)ので。でも、できれば映画を観てから読んで欲しいです。以下にあげていく描写を思い出しながら読んでいただけたらと思います。
でも、観る前の方にもこれだけは言っておきたいです。
"ストーリーに囚われるな。宮崎アニメーションをどっぷりと体感せよ!"
序盤: 注目のアニメーション
この作品は、主人公マヒトの抱く"感覚的なところ"を、まるでスーパースローカメラでとらえて分析したように細かく描写しています。
"音"と"間"にも気を配り、とても効果的に作られていたと思います。宮崎アニメーションのASMRの塊と言っても良いです。
これは作品の特に前半部分に集中しており、ストーリーに期待していた人は眠くなってしまったかもしれません。(始まって早々にイビキが聞こえました。)
ですが、アニメーションの表現方法に関心のある人にとっては終始目と耳が釘付けになるものだったのでは思います。
たとえば覚えている限りでも…
・焦ったときに下駄がうまく脱げない描写
・災害で混乱する群衆の中を、掻き乱された心境で無我夢中で走る歪んだ描写
・人力車からの乗り降りの際の荷台の浮き沈みの描写
・大きな鳥が翼を広げて風のない中をスーーっと滑るように飛んでいく描写
・夜に部屋から抜け出して、階段の上から父の帰りを待っているときの間と描写
・"吸いのみ"から水を飲む間と描写
・身近なもので武器を作っていくときの静かなワクワク感が伝わる描写
・土に埋もれた狭い入り口を無理やり通ろうとしていろいろ頭や顔にくっついてしまうけれどそれどころではない心境で気にしない描写
・魚を捌いていてハラワタを傷つけてしまい、おさまっていた中身がモモッと溢れてくるときの描写
・眠っているマヒトを木彫りのおばあちゃん人形が守っている様子と、それをまたいでゆっくり外に出るときの描写
・わらわらが息を吸って膨らんで、いちどしぼんでまた息を吸って浮遊に再挑戦するときの描写
などなど…あげるときりがありません。
どのシーンも好きでとても良く覚えています。
しかし、これらの描写は単にリアルを追求したものとはまた少し違います。
上にあげた描写の感覚を、現実の中で少し違う形ではあれ体験したことのある人にとっては、それらをとてもリアルに思い出させられたのではないでしょうか。また、過去に体験したことがなかったとしても、まるで体験した感覚として身体に残ってしまうような特殊なリアルさがあったと感じます。私はここに宮﨑アニメーションの骨頂というか、凄さを感じました。今回宮﨑さんが作品でやりたかったことのひとつが、これらの表現だったと思います。
先ほどは"マヒトの感覚にフォーカスして…"と書きましたが、描写からマヒトの心情を表すというよりは、宮﨑さんが表現したいことをマヒトにさせたといったほうが正しいかもしれません。
ストーリーの流れとアニメーションのこだわりを両立させようとすると、余分な描写や細かすぎる描写はストーリーに集中できなくなって流れやテンポを妨げてしまいます。しかしアニメーションとしては、作れば作るほどこだわりやアイデアが出てきてしまうものです。
これまでたくさんの作品を手掛けてきて、ストーリーのために削ったり妥協せざるを得なかった表現方法や、あとになってから、もっとこうすることもできたよなぁと湧き上がってきた表現方法がたくさんあっただろうと思います。それらを形にして放出せずに終えることは、アニメーターとしては死んでも死に切れないでしょう。
したい表現を妥協しないで表現したものを、なんとか形にしたい。それを実行したものが、今作ではないかと私は感じています。
だから、この作品は宮﨑さんの夢の中のようであり、ストーリーに削られない宮﨑アニメーションの原石でありもあり、磨きあげられた宮﨑さん独特の技術手法であり、そして彼の走馬灯のようなものになっているのではと考えます。
SNSを見ると、"これまでのジブリ作品からいろんな要素を抜き出して繋げたオマージュ作品だ"という意見を多く見かけました。しかしこれはオマージュではなく、"宮﨑アニメーション要素を突き詰めた集合体"なのだと感じています。
中盤: ストーリーの難解さについて
中盤あたり、次々と変わる場面で、あのときのあれはどういう意味だったのだろうかと頭を悩ませている人が多いようです。考察もさまざまあるようですが、この映画ほど考察はその人次第なのだと感じた映画はかつてありません。
突然現れては、特に主人公の行動を大きく左右するわけでもなく去っていく事象。本来映画という作品においては珍しい作りなのかもしれない。でも、そんなことは人生において日常茶飯事なことです。自分の目の前で起こる出来事は、ただ過ぎ去るものもあれば、何かしらの布石や影響を置いて去っていくものもある。生涯ずーーっと付いてまわるものになることもある。その人がどんな問題に向き合っているか次第で、その影響は大小色形は全くもってさまざまです。
この映画の場面についても、今のはなんだったんだろうと思う人もいれば、それな、とストンと受け入れられる人もいる。これは他人の考察を読んで、なるほどと思える映画ではありません。自分が観て感じたことが全てな映画です。似た境遇の人とは、共感できる部分が多いかもしれませんが。
今作の、一見繋がりの薄いように思われる各場面は、宮﨑さんが生涯で経験してきた中で大きな影響をうけてきた事象を抽象的に描き出したものかもしれないと思っています。それを全てが繋がった物語として誰よりもよく捉えているのは、もちろん宮崎さん自身だけです。この映画は宮﨑さんの、客観的ではなく、内面的な部分のドキュメンタリー映画だと私は思っています。ですから、宮﨑さんと少しでも似た境遇にある人は、きっと所々で、違和感なくすうっと受け入れられる部分があったのではないでしょうか。
最初に私は「この作品はストーリー自体に重点を置いたものではない」と書いたのは、この作品を理解するにはストーリーではなく、そこから個々が何を感じるか次第なのだろうということです。
終盤: 込められた想い
終盤、大叔父様という人物が出てきて、主人公マヒトと重要な話をします。この大叔父様というのは宮崎駿本人でしょう。
宮崎駿は今作で、これまで心残りだった自分のアニメーションを突き詰めて表現しました。内面も表現しました。本当はまだまだアイデアは湧くし、わくわくするようなストーリーをつけて世に出したいのでしょうけれど。でも彼は、自分に残された時間はもう、そう長くはないことを知っています。
"悪意のない石を用意した"という言葉が出てきますが、それは今作のことかもしれません。(石は意思とも捉えられるかもしれません。)
宮崎駿が純粋に自らの仕事と内面を掘り下げ、そのエッセンスだけを集めたものということです。
伝統工芸などの手仕事に置き換えたら、
これまで自分が見つけ磨いてきた素材の活かし方や技術。そして想いを純粋に書き留めたものです。
私はこの瞬間、胸が熱くなりました。
大叔父様の想いは、結局最後は横槍を入れられてうやむやになり、完全に大叔父の知らないところとなってしまいます。でも現実世界もそんなものです。どんなに準備してきても、結局どうなるのかは誰にも分からないのです。
あとを生きていく人たちは、先人の知恵を基礎にして自分らしく磨いていき、そして先人を超えていくのか。
はたまた、それらには全く触れずに新しいものを作り出していくのか。
もちろん、先人の知恵が全てではありません。何が正しいのかは誰にも分からないし、強制もできません。
あくまでも、自分はこういう仕事をした。こう生きた。自己満足かもしれないけれど、最後に純粋にそのエッセンスだけを置いていく。あとは、これからを生きていく人たちに委ねる。
だからこその、
君たちはどう生きるか。
なのだと。
それが、宮崎駿の最後のあがきだとか、まとまりがなくストーリーもよく分からない作品だと言われようが、私は今作が、彼がいま表現すべきもの、そのものだったと思っています。
宣伝をしなかったのも、奇をてらった戦略だとか、宣伝しようのない内容だからとかいろいろ意見が飛んでいますが、どんな酷評が飛び交っても、見る意思のある人観られれば、届くべき人に届けば…という想いがあったのではと思っています。
最後に
この映画は、人によってはアニメーションは満喫できるけど難解な映画かもしれません。全てがすうっと入ってきて、救われるような、一生ものの映画となるかもしれません。数十年後に貴方の境遇が変われば、また全く違う感覚で入ってくるかもしれません。そんな映画です。だから、今は難解だと思っても、それで良いのです。きっとまた、改めて観たいと思うときがきたら観れば良いのです。
私は今、後継者問題に悩んでいます。少なからず、宮﨑さんの想いがすうっと入っていた部分が多々あります。この作品に今出会えて、本当によかったです。この映画を作ろうと思い実現させた宮﨑さん、そして支えたスタッフの皆さんにとても、とても感謝しています。
自分は最後に何を突き詰めるのだろうか。
それをどう残すのだろうか。
さて、大きな課題を残されたわけですが、私は今とても清々しいです。数日後に控えた大切な仕事にも、新たな気持ちで集中できそうです。
追記
マヒトは大叔父様が用意した石を受け取りませんでしたが、いつのまにか、大叔父様の世界のそのへんに転がっていた真っ白い小石をひとつ、自分の現実世界へ持ってきていました。これは宮崎駿の小さな希望の表れかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
