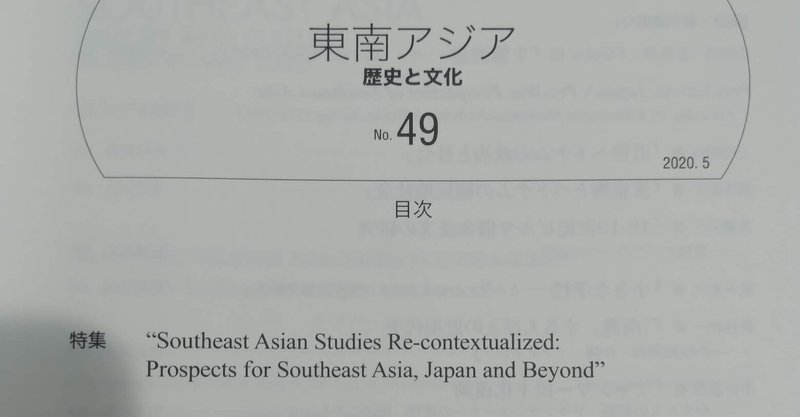
シンガポール国立大での東南アジア研究とInter-ASIAN Studies
日本の東南アジア学会の学術雑誌「東南アジア 歴史と文化」の49巻(2020年)に今後の東南アジア研究のあり方・方向性についての特集があった。飯島 明子による特集の説明、トンチャイ・ウィニッチャクンによるアジア域内における東南アジア研究の現在についての概説的な論文の他に3本の各論的な論文(ベトナム、シンガポール、インドネシア)が収録されている。
個人的にとても関心を持った論文がGoh Beng-Lanの"Inter-Asia and Southeast Asian Studies at the National University of Singapore: A Personal Evaluation"という論文だ。そもそも、私自身シンガポール国立大出身で、そのままそこで勤務していることもあるけれど、東南アジア研究とInter-Asian Studiesの両方の参与しつつ2者の緊張関係について自覚的だということもある。
Inter-Asian Studiesや地域研究が何かを理解するには、その略史を理解する必要がある。そもそも第二次大戦後、アメリカ合衆国の世界戦略が変化するなかで、それぞれの地域(東アジア、南アジア、東南アジア、中東、ラテンアメリカなど)を理解しようとする地域研究(Area studies)というジャンルが形成された。もちろん、政府からの投資付きで。例えば、東アジアは、共産化した中国、分断された朝鮮半島、そして新たに「西側」に加わった日本という国々の国民性、域内の緊張関係、文化的な共通性、近代化の問題などを理解することに主眼が置かれた。アメリカの冷戦的な戦略の中で、日本は近代化や民主化の優等生と認識され、その成功の秘訣が探られる。西側と敵対するに至った中国は「失敗例」として、「なぜ西洋や日本のような近代化を遂げないのか」といった問いをかけられることとなる。中国が近代化に成功している現在でも、「なぜ中国は西洋のようにならないのか」のようなパラダイムからの研究が圧倒的に多いという点では、20世紀の研究の功罪が今も続いている。
東南アジアは、インドネシアやベトナムなど、アメリカとソ連の代理戦争の舞台として、住民たちの国民性や異なるグループの研究が注目をあびることとなった。ナショナリズムと左翼運動の研究が多かったのは、こういう経緯がある。日本の読者たちの所謂「一般常識」のようなものも、このようなアメリカ主導の知識生産の影響を強く受けていると思う。
Inter-Asian (Cultural) Studiesというのは、冷戦崩壊後の1990年代以降、上記のアメリカ主導の地域研究、そして均一的な概念や理論を異なる地域に一律で適用してしまいがちなグローバル研究の批判の中で出てきた考え方だ。「地域」というものをアメリカの行政・戦略が恣意的に作り出したものとして退け、しかし方法としてはアジアの文化間の比較を多用することで、新たな知識を作り出そうとする運動。理論的には、文化の分析を通して権力関係にメスを入れるカルチュラル・スタディーズに依拠している人が多い。Inter-Asian Studiesという概念については、中国語では「際亜」という訳が定着しているけれど、日本には定着してる訳語が無い。(多分、多くの人は「域内のアジア研究」で済ましている。)
実は、今回の論文の著者であるGoh Beng-Lan(以後GBL)は、私がシンガポール国立大の修士課程に入った頃、東南アジア研究学科の学科長だった。彼女は、東南アジア地域研究側の論者として、Inter-Asian Studiesの論者たちから激しい攻撃にさらされていた。というのも、Inter-Asian Studiesの論者たちは、基本的に「東南アジア研究」の破棄を主張していたから。それで、一時期はGBLもやや過剰な守りに入ったり、東南アジア研究について悲観的になっていた時期もあったと思う。今回の論文では、Inter-Asian Studiesの貢献をある程度評価しつつ、その弱点をより古い東南アジア研究が補填できるという主張をしており、シンガポール国立大内部でのディベートについてうまく紹介している。
両方に関与している私だけれど、現時点での見解としては、東南アジア研究は維持しなければならないと思う。特にシンガポール国立大では。
まず、政治的・実際的な理由がある。Global StudiesやInter-Asian Studiesは、「地域」の正当性を奪おうとしている。彼らに言わせれば、「これらの地域がアメリカによって政治的理由で作られたから」ということになる。
けれど、Global StudiesやInter-Asian Studiesにも政治的アジェンダがあるわけだ。例えば、ASEANは、東南アジア地域共通の利益の保護を目指す組織で、特定の問題(例えばミャンマーの人権や災害の対処など)については、先進国以上に影響力を持っている。このような地域共同体を解体させることに成功すれば、残るのは比較的に弱い東南アジアの国家だけ、ということになる。そうすると、先進国の政治家や資本家たちは、より強気に交渉し、説得しやすい相手ばかり、ということになる。具体的に言うと、かつてのフィリピンや、現在の東ティモールみたいに、新植民地主義的な状況になりえる。
日本の読者にわかりやすい例をあげると、第二次大戦中、日本は「大東亜共栄圏研究」を推進していた。これは概念に正当性を与えるためでもあったし、構成国に対する日本の立場や政策を確立するためでもあった。Global Studiesは多国籍企業の利害に合致するし、Inter-Asian Studiesもインドや中国など、アジアの大国の関心にある程度合致していく可能性が高いといえる。既に確立しているASEANに知的正当性を与えていくことは、東南アジアの地域的利益を守ることにつながる。
2つ目もやや政治的だけれど、「東南アジア」という概念が既に東南アジア域内の主体にかなり広く支持されており、組織化・行政化・ビジネス化されているという点がある。域内の人々が支持している時点で、研究者にとっては研究する理由になる。(つまり、かつてのオリエンタリズムと違って、ある程度は研究者と研究対象の両方から支持されているということになる。)
シンガポールは非公式の「アジアの首都」なわけだから、シンガポール国立大の決断というのは、東南アジアだけでなく、隣接する地域の大学の動向も影響する可能性が高い。なので、これからも、「地域研究の学科はつぶしていいんじゃない?」という同僚はたくさんいると思うけれど、シンガポール国立大はアジア研究を維持しなければいけない。
よろしければサポートお願いします。活動費にします。困窮したらうちの子供達の生活費になります。
