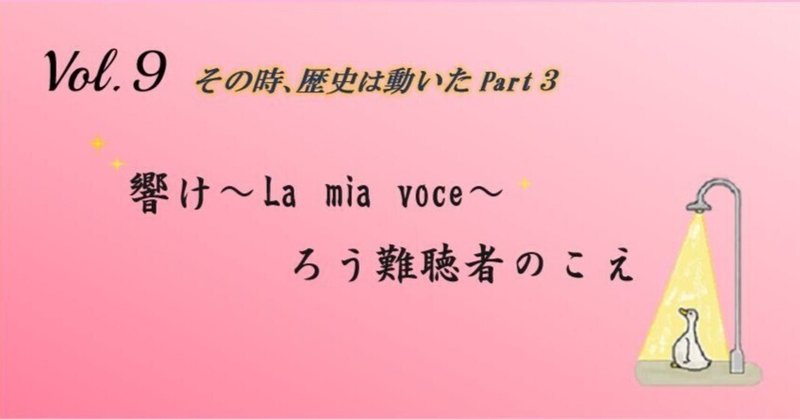
Vol.9 その時 歴史は動いた!Part3 「口話〜発語編」
【響け ~La mia voce~】ご覧いただき、ありがとうございます。
多くの皆さまに、興味・関心を持っていただけること、心より嬉しく思います。今後も引き続き、よろしくお願いいたします。
その時、歴史は動いた!
オトナになってから入った「大学」で知った、衝撃の事実について、いくつかのトピックを立ててお送りします。
Part3は、「発語(発音・発声)」「言葉」についてです。
(私自身は、ろう学校に通ったこともなければ、専門機関にて熱心な口話教育を受けた経験もありません。“口話”それ自体に賛否両論があることは承知で書いています)
手話、口話、音声を使う人…など、聴覚障害者のコミュニケーション方法は、個々によって様々であることは、これまでに幾度なく、お伝えしてきました。
一般的に聞こえる赤ちゃんは、生後4か月以降になると大人の声・言葉を聞いて「あー」「うー」などの言葉(喃語)を話し始めます。そして、成長に伴って「まんま」「ブーブー」など意味のある一語文を話したり、「これ、ちょうだい」などの二語文を使い 自分の思いを言葉で伝えたりします。
人間の「ことば」が発達するために必要な条件として、以下の項目が挙げられます。
【ことばが発達するために必要なこと】
①言葉を聞き分ける『聴力』が発達していること。
②言われたことが理解できる『知能』が発達していること。
③発声するための『運動機能』が発達していること。
④子どもに「話したい」という『欲求』があること。
https://x.gd/jKGnM(参照2024-1-10)
また、「ことば」の発達は、一定の決まった順序で進むと言われ、年齢に応じた発達段階があります(年齢区分は文献によって多少の差があります)。
【おおよその構音完成(獲得)時期】
2歳代:母音、パ行、バ行、マ行、ヤ行、タ行(ツを除く)、ダ行(ヅを除く)
3歳代:カ行、ガ行
4歳代:ナ行、ハ行、ワ行
5歳代:サ行
6歳代:ザ行、ツ、ラ行
一般的に子どもは、身近な大人の声や言葉を聞いて、模倣することにより言葉を身に着けていきます。
時々「食べる」を「ぱでる」等と発音する幼児に出会いますが、適切な発音ができなくても、身体的な成長発達に伴い、いつの間にか「食べる」と言えるようになっていた、なんてことがあるかと思います。
そして、「正しい言葉」だけでなく、音や息づかい、音色、抑揚などを感じ取る力を身に着けていきます。
しかし、私のように先天性聴覚障害児の場合には少々異なります。
生まれたときから、聞こえない・聞こえにくいことが当たり前で、自分が話す音声も聞こえにくい、聞こえない場合には、聴覚的フィードバックが困難なため、発音にも影響を与えると言われています。
「自分は、補聴器や人工内耳を使って聞こえる」と言う方であっても、
明らかに聴覚に障害のない方の「聞こえ方」とは異なります。
つまり、聴覚に障害があると、外部から適切に「言葉」が入らないために、「発声」「話すこと」に何かしらの影響が生じるといわれています。
*学童期以降に難聴・失聴した中途失聴者、あるいは「日本語」
の発語が身についた後に失聴した場合は、日本語の文法や話
し言葉が、ある程度理解できる場合が多い。
「聞こえない人」と言えば、それを補う方法として「手話」をイメージされる方もいるかもしれません。
しかし、つい数十年ほど前の日本では、「手話」が禁止され、聞こえる人と同じように声を出してコミュニケーションができるようにと「熱心な口話教育」が施されていました。
聴力障害のある子どもの“9割”は、聴覚に障害のない親から生まれてきます。
金澤貴之: 日本にあるもう1つの言語 ―日本手話とろう文化
https://x.gd/OeH3W(参照2024.1.10)
そのためでしょうか…
「聞こえる」社会の中で生きていくのに困らないように、
聞こえる人の口を読み取って口で言葉が話せるように、
と1930年代から急速に口話教育が広まっていきました。
NHK情報サイト ハートネット 手話と口話-ろう教育130年の模索-
https://x.gd/hnYHd (参照2024.1.20)
「ろう児の幸せ」を願って施行された教育法でしたが、口話法の「技術」ばかりが強要されるようになり、次第に教育的視点を失っていきました。
そのうえ、聴力の程度に関わらず 一律に同じ教育 がなされるようになりました。
現在では、「聴力の程度」によって口話教育の成果が異なることが明らかになっています。
ですが、当時は口話ができないことは、本人の「努力」や「能力」に問題があるとされてきました。
年配のろう者に話を伺うと、上手く発音できないと定規で手を叩かれたり、怒鳴られたり、虐待に近いことをされるということが、つい最近まであったそうです。
今は、昔ほど厳格な発音指導はされなくなったと言われていますが、
「聞こえない・聞こえにくい耳」で聞き取った言葉を、筋肉・身体の発達が未熟な聴覚障害児に模倣させて、子どもの能力それ自体を判断するなんて…
おまけに「文字」の学習をしていない幼児に、音や言葉の「正しさ」ばかりを求めて読話・発音をさせても、聞こえる人同様に「発音・発声」できないことを想像できなかったのだろうか…、本当に心が痛みます。
そのような歴史的背景もあり、「発音」「発語」することに対して抵抗のあるろう者、話せるけどあえて「声をださない」ろう者も少なからずいます。
私は軽度難聴でしたが、難聴が発覚した時期が遅く、周りも聞こえる家族に囲まれて育ったので、ふつーに音声を使って、ふつーにコミュニケーションをとってきました。
しかし、小学校に入ると、なぜか自分の話し方を真似される、「なんて言っているの?」と聞き返される、自分の言いたいことが伝わらない、ということがありました。
それらが度重なり、思春期になるにつれ「自分の声」や「話すこと」に嫌気が増し、大人になっても「発音」や「自分の声」に対するコンプレックスがありました。
しかし、大学生になった時、初めて声の「魅力」に出会い、自分のコミュニケーションの課題や数々の衝撃事実を知ったことで、少しずつ抵抗感が薄れていきました。
今は、音声に対する「拒絶感」はありませんが、コンプレックスが払拭できたかといえば、嘘になるかもしれません。
だから、今も話すためのトレーニングを続けています。
そのお陰なのか?! 講演に行くと、
「発音きれいですね。全然、ヘンじゃないですよ」
「発音練習は、どのようにされたんですか?」
と、訊ねられることがあります。その質問をする方は、言語療法士さんや教員、親などで、つまりは「聞こえる方」ばかりです。
何事も、できないよりか、できた方がいいのかもしれません。
そして、今なお続く「手話」VS「口話」の教育論争。
ここでは、教育方針に対する過激な論争はせず、声を出してコミュニケーションしている私の体験談を交えた “私の意見” をお伝えします。(私の主観に基づきます)
◎良いところ
① 身体の筋肉や口の筋肉が鍛えられる
一般的に多くの方が「声」を使ったコミュニケーション方法を使っています。「話す」「発声」することに意識を向けてトレーニングをすると、いかに自分が「声」「言葉」に気を使って話せていないか、ということがよく分かります。声を鍛えることは、口や舌の運動にもなり、口呼吸の改善 や 咀嚼・嚥下の機能を高めます。また、顔の筋肉を動かすことで、お肌の美容 と 健康 にも役立ちます!
②コミュニケーション手段が増える
聴覚活用ができる人であれば、「読話・口話」が出来ることで、日本語を母語とする人、聞こえる人と音声を使ってコミュニケーションをとれるようになります。筆談よりも音声の方が早く伝えられる、文字の読み書きが難しい方ともコミュニケーションが取れる、良さがあるでしょう。
③手話にない語句・表現が伝えられる
手話は、とても良い伝達手段ではあるけど、手話で表現できない日本語(用語・語句)がたくさんあります。その場合、書いたり、指文字や口話で伝えたり、簡単な言葉に置き換えて意味を伝えたりします。口話ができると、手話にはない「語彙」を筆談と共に伝えられる良さがあります。
④声を出すとスッキリする、歌が歌える
聴覚障害者の中には、カラオケに行き、声を使って歌を歌うことが好きな方もいます。声を出すとスッキリするし、カラオケだと発音を気にせず歌えて、楽しいようです。(手話でも歌が歌える!という意見については、また別の機会に…)
聴覚障害者が「声」を出すこと、口話をすることの利点は、他にもあるかもしれません。
しかし…
聴覚障害者が「音声」を使って話せるようになっても、
聞こえる人たちと同じように出来ない、「越えられない壁(不自然さ)」があります。そして、時々「社会の視線」に胸が チクッ と痛くなるようなことがあるのです。
教育者、言語指導をする方、保護者の方に、少し考えていただけると嬉しいです。
◎音声で話せても困ること…
◆練習じゃなくて「訓練」!!! ~相当なエネルギーを要する
聴覚障害の程度にもよりますが、聴覚障害者が、目には見えない音声というものを耳で聞いて模倣するためには、聴覚以外の「感覚」も総動員して、繰り返し身体に覚えさせる必要があります。
声・音を出すだけ ならともかく、聞こえる人に伝わる 「日本語」 を話せるようになるためには、練習というより「訓練」に近いものがあります。
例え、聴覚活用ができたとしても、聞こえる人たちのように、自分で自分の声・音・言葉を聞いて「微調整」「修正」がすることが難しいので、「正しい音」「正しい言葉」で 発音 ができている という 判断は、他者(親、先生、友だちなど)がすることになります。
自分で調整するには、自分の中に「正しい」という判断軸が必要になります。しかし、それが直ぐに得られないのです。
「正しい感覚」が、自分の中にないと、常に他人の顔色を気にしなければいけないし、例え上手く発音できたとしても、他人の耳に頼らなければならないのです。他者の耳を借りて「正しさ」を身体で覚える。
その「正しさ」が、直ぐに身につくわけもなく、上手くできても家に帰るとできなくなっていることもあります。
また、幼少期であれば、専門機関で理論に則った 発音練習 をしてくれるけど、それをいつまで続けるのか?
トレーニングを長期的・定期的にすることに、当人が価値を見出せるか?
当事者の意欲、必要性の程度によっても、得られる結果が異なる気がします。
そして、話せても、問題なく聞こえる人のようにはならないので、積み重ねるというより、何だか、同じところをグルグル回っているような感じがするのです。
おまけに、トレーニングを止めた途端に発音が崩れだす…という悲しい現実があります。
「正解」「ゴール」が見えない中で続ける意味、価値、時間…
私は、地域(一般社会)の学校で先生をしているので、「声」を使って伝達をする必要があります。自分で「必要だ」と思うからトレーニングを続けているのですが、なぜか時々、虚しくなることがあるのです。
◆音声を使うと、聞こえにくいこと・聞こえないことを忘れらてしまう
発音・発語の明瞭度・程度には、個人差があり、重度の聴覚障害者でも「発音」が得意な人もいます。発音明瞭度が高いと、発語の明瞭度も上がり、話したことが周囲の人に伝わりやすいことから、その聴覚障害児者の「学力」や「言語力」も高いと思われがちです。
しかし、「発音明瞭度の高さ」と「読み書きの力」ましてや「学力」は、必ずしも 比例する わけではなく、話せるけど必要な日本語力が十分に身についていない人もいます。
また、音声でやり取りをしていると、なぜか聞こえにくいことを忘れられてしまうことが多々あります。(補聴器が、そう見えるようにしてくれているんだけどな…)
その他に、聴覚障害者は「上手く話せない」というイメージが強い方に対して明瞭な発音で話すと、聞こえない・聞こえにくいことを疑われたり、
話せるのだから電話ができるだろう?等と、勝手に判断されたりする事例もあるようです。
◆「正しい発音・言葉」で話しても…日本語が通じない
聴覚障害児の発音・発語指導には、
「聴覚障害児が話し言葉を通して、国語の的確な 音韻表象 を確立し、国語の習得を図るために欠かせないものであるとともに、話し言葉の明瞭性を高め、イントネーション等にも留意した話し方ができるようにするために行われる」、という目的があります。
私には、日本人相手に、日本語を話しているのに、自分の話す日本語が通じないという体験が、これまでに幾度もありました。
「日本語が通じない」というより、自分の思いが「伝わらない」というのが適切かもしれません。その理由が、大人になっても よく分かりませんでした。
例えば、友だちに何かをしてもらって「ありがとう」「嬉しい」などの一言を伝えても「本当に嬉しいと思っているの?」と問われ、返事に困るという経験が何度もありました。
「ありがとう」「嬉しい」と思っているから、それを言葉で伝えているのに、なぜそのようなことを言われないといけないのか?と、疑問に思いながらも、当時は気にしないようにやり過ごしていました。
この原因を、大学に入ってから知ることになったのですが、
結論を言うと「発語のプロミネンス」に問題があったように思います。
「聞こえている人たち」は、同じ言葉を使っているときでも、その時々によって言葉の「間」やイントネーション、音の高さを意識的・無意識に変化させて使っているようです。
言葉は、言語による意味を伝えるとともに、「言い方」によってその言葉の持つ意味が大きく変わります。つまり、正しい発音・音で「言葉」を話しても、伝えたい意味を表す技法を用いて言葉を発しなければ、単なる「言葉」という物体を発しただけで、意図しない意味を持った言葉、お粗末な言葉になってしまうのです。
だから、明瞭度の高い、きれいな発音で言葉が話せたとしても、それが相手に適切な思いを持った言葉として「伝える」「伝わる」ためには、別の力が必要になるのです。
◆日本語を話しても、何かしら残る違和感…「先生は、外国人なの?」
大学生時代に、小学校の学習支援ボランティアに行っていた時の話です。
この小学校は、全校児童700人程度で、学力も高く、帰国子女や外国にルーツのある児童も多数在籍する学校でした。
学習支援に入るクラスでは、毎回、自己紹介と共に難聴のこと、補聴器についての説明をしていました。もちろん音声を使って。
ある時、3年生の学級で自己紹介を終えた後、一人の男の子が、私に「ハロー」と言いながら手を振ってきたのです。私も「ハロー」と言い、手を振り返すと、彼は私のもとに数歩寄ってきて「先生は、外国人なの?」「日本語 話せるの?」と問いかけてきたのです。
「どこから どう見ても 東洋人の容姿だし、自己紹介も日本語でしたじゃん!」と思いながらも、「日本人だよ。日本語 話してるでしょ」と伝えると「ふぅーん」と言い、教室から出ていったのです。
また、1年生のクラスで同じように自己紹介を行い、教室の後ろの掲示物を見ていたことがありました。すると、一人の可愛らしい女の子が「先生の声、可愛いねー」と話しかけてきました。
「1年生で、私の声に反応するのは初めてだ」と思い、「声、変だったかな?」と尋ねてみたのです。すると、間髪入れずに「うん」と頷くと同時に「ハーフみたいで可愛いよ」と言ったのです。なるほど、ハーフね!
そこから私は、自己紹介の時に「聴覚障害者と聴者のハーフです」と伝えています。
方言による言葉の差異は別にして、自分では聞こえる人と同じように日本語を話しているつもりだけど、何かしら違和感があるようです…
低学年には指摘されるけど、高学年は触れてこない「声」そのものに対する違和感。
「聞こえる人」たちは、成長するにつれ、言葉と共に「声」を聴いているような気がします。
◆話し方を真似される
X(旧:Twitter)で、こんな記事が話題になっていました。
「殺意が芽生えた瞬間」その7 pic.twitter.com/gh2UO8RI4a
— しろやぎ秋吾 (@siroyagishugo) January 7, 2024
私も、似たようなことをされたことが、何度もあります。
昔は嫌だったけど、今は「変だから、また真似してるな」と言う感じで慣れてしまいました。人によっては、傷つく人もいるようですが、人はバカにするつもりはなくても、好きな人や特徴がある人の真似をしたくなるようです。
◆場に合わせて声の音量調整ができない
「聞こえる人」たちは、オトナになるにつれ、TPOに合わせた話し方、声の大きさを自分で判断して、身に着けていくことができます。
しかし、聞こえにくいと、自分の声の大きさが自分で分からないため、その場に適しているのか不安になることがあります。補聴器を使っていても、補聴器は「自分の声」がよく聞こえるように作られているため、聞こえる人たちが耳にする音量と自分に聞こえる音量が同じでない可能性があるのです。だから、公共の場や内緒話で声が大きくなったり、時に小さくて聞こえなかったりすることがあります。
私は、自分の声の大きさがよく分からないので、話す前に「後ろの方、私の声聞こえますか?」と尋ねてから話すようにしています。
◆音声のテクニックが、やたらに難しい!
私だけかもしれませんが、いわゆる音声化のテクニック(音の高低、ピークをつける 等)と、イントネーションをつけて話すことが難しいのです。
例えば、「買った?」という言葉で、疑問・断定のイントネーションをつけるとなると、「買った」「勝った」「飼った」「カッター」等、同じ言葉でアクセントの異なる言葉と混同してしまい、どの位置の言葉(文字)をどのように、どの程度、変化させたら良いのかわからなくなってしまいます。
また、話し言葉は、歌(楽譜)のように高さの基準がないので、はじめの言葉の高さを自分でどのように作ったらよいのか、どこに合わせて声を出したらいいのかわからないのです。おまけに声=音は、目に見えないし…
さらに、同じ言葉の前後に他の語句・言葉がつくと高さが変化するタイプの言葉(例「音楽」と「音楽家」)を言うことが苦手です。
そんなことを考えながら話すと疲れてしまうので、気にしないようにしていますが…
◆「腹から声を出しなさい!」と言われても…
声を出すことが怖くて、縮こまっていた時代によく言われた言葉です。
これは「丹田」という場所を意識して 声を出せ という意味なのですが、当時は理解ができませんでした。「声が出るのは口だよ!」と思いながら、お腹に力を入れても声は出ないし、何をどのようにしたら良いのか分からず、よく泣いていました(笑)。
◆正しい知識を持った上でトレーニングすること
何事においても、「努力」することは美徳とされ、正しい「知識」で、正しい「方向・方法」で、十分な量がなされた場合において効果を発揮します。しかし、間違えた知識・方法で続けたドリョクは、反対に弊害になることがあります。本人はガンバッタよと言いたいのですが…
私は、病院で1~2回、発音の検査と「口型をつけて話す練習」をしたことがあるくらいで、本格的な口話教育というものを受けたことがありません。
うまく話せるようにと、自分で本を買い、口を大きく動かし、はっきり話せるように練習していました。それが「正しい」と思って。
しかし…、大学に入学してすぐ「あ・い・う・え・お」と過度に母音の口型をつけて話すことの弊害を知ったのです。
「えぇぇぇぇぇ、今までに使った時間を返して!」と、心底叫んだことは一生忘れません(笑)。
無理に声を出して喉を傷める聴覚障害者もいるので、口話をする方は、声を出すための 正しいトレーニング方法を知っておくことも必要だと思います。
*興味・関心のある方は、こちらをご覧ください。
『史センセイの声トレ道場』(トレーニング動画)
https://www.youtube.com/@prof.ayakororin/videos
ネットで学ぶ発音教室
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所及び独立行政法人理化学研究所
https://forum.nise.go.jp/kotoba/htdocs/
◆「聴覚障害者」という立場
聴覚障害者が、「きれいな発音」で話せることを学校で褒められ、読話・口話に自信をもって社会に出たけど、聞こえる人には通じなかった、困ったと…いう事例があります。
聴覚障害者の発音・言葉が、聞こえる人たちに伝わるのは、この人は「聴覚障害者」という立場が明確にされているからだと思います。
「ツタワル」というより、聞こえる人たちに「読み取ってもらっている」から、「コトバ」が伝わるという方が 正しいかもしれません。
私が “難聴" を自己開示していない時期は、自分の発音が伝わらないことがありました。
「聴覚障害」があることを伝えなければ、ただの「発音が悪い人」、「変な話し方をする人」だと思われたり、果ては「外国人ではないか」と思われたりして、日本語を話しても伝わらず、トラブルもたくさんありました。
だから、聴覚障害者が声を使ってコミュニケーションをする時には、「言葉を話せても聞こえる人のようにならない」こと、聞こえる人は言葉(文字)だけを読み取って生きているわけではないこと、「聴覚障害者」「聞こえにくいこと」という立場が前提条件として周知されているからこそ発音が「ツタワル」ということを、聴覚障害者自身が自覚しておく必要があると思います。
◆要らない!「伝えたい気持ちがあれば伝わる」という慰め
「音声で話すことも、手話も、両方とも中途半端だから自信がない…」と伝えると、言われるこの言葉。これは、聞こえない人からも、聞こえる人からも言われるのです。
「伝えたいと思う気持ちがあれば伝わる」「心は伝わる」と言われるたびに、「心?気持ち?とはなんぞや??ダイレクトに伝わらないから、苦労しているんだよ!!」と言いたいのです。
………伝わりません。
まとめ的に…
私は「音声」が嫌いなわけではありません。どちらかと言えば「好き?」です。
近年、早期に人工内耳を装着することで「聞こえて、話せる」聴覚障害児が増加し、それに伴って教育の在り方が議論されるようになってきました。
「聞こえて、話せる」それ事態が悪いことではないけれど、少し考えてほしいのです。
手話に抵抗がある、読話・話すこと押し付ける聞こる方に、
そして、「聞こえているから、話せるから大丈夫。手話はいらない」という聴覚障害当事者の方に。
「音声」で話せても「困ること」がある現実を…
今回は、ここで終わり!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
《引用・参考文献》
1)文部科学省 (2020), 聴覚障害教育の手引 令和2年3月.
2)深澤茂俊 (2016). 聴覚障害児・者のコミュニケーション方法ー手話・口話論争と障害の克服ー,神戸親和女子大学福祉臨床学科紀要 ,13, 15-29.
3)澁谷智子 (2005). 声の規範「ろうの声」に対する聴者の反応から, 社会学評論, 56 巻 2 号, 435-451.
4)渡邊史 (2022). 日常にある道具を用いた実践歌唱指導の提案 ~「具体性ある歌唱指導」のために, 滋賀大学教育実践研究論集 , P79-87.
