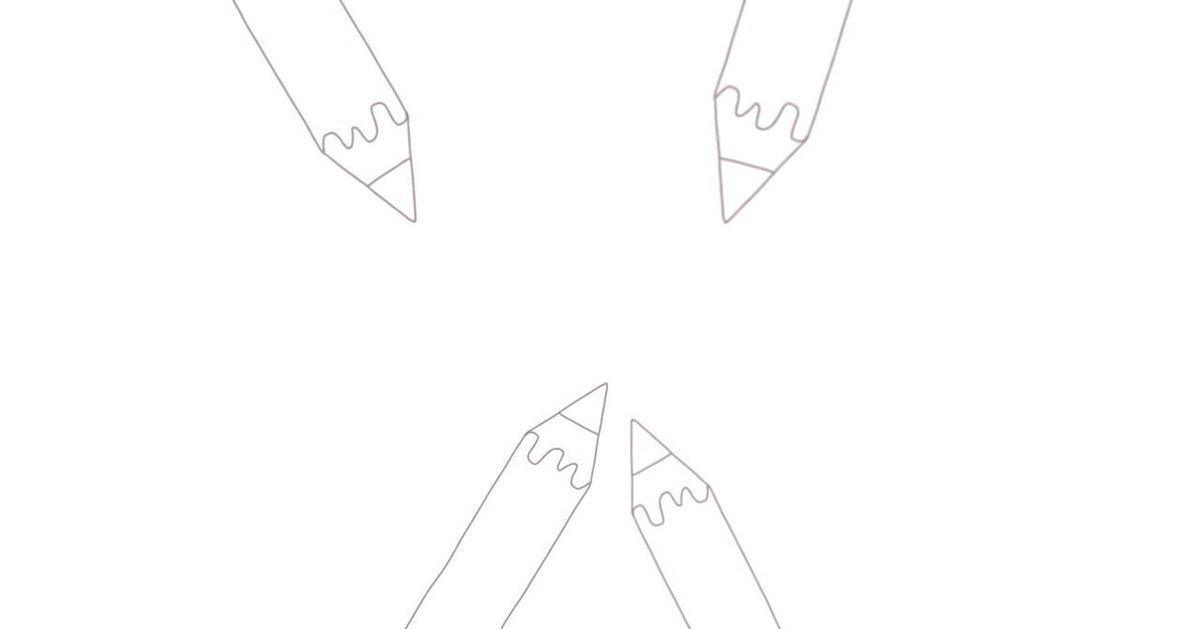
第2回目の授業研究
先々週や先週は、校内研究の事前授業とその事後検討、あゆみ、研究員の課題、学校公開と保護者会は4度目の緊急事態宣言で中止になったが、土曜授業といった、なかなか色々ある2週間だった。
やっと体力的にも精神的にも少し余裕ができた感じで、久々のnoteの記事に手を出せた。
さて、7月6日(火)は本校の第2回授業研究だった。
授業実践は3年生だった。超多忙な時期に引き受けてくれたことに、ただただ感謝の思いしかなく、研究主任としてはもちろん、同じ中学年ブロックとしてという思いで、一緒に色々話しながら授業を考えた。3年生の先生方も大変な中にも関わらずとても前向きに、授業について、教材について様々お話しして下さった。改めて、子どもの学びを中心にしてあーだこーだ言い合うのっていいな〜。と感じた。
今回、講師でご来校くださったのは、昨年度も大変お世話になった、
NPO法人授業づくりネットワーク理事長の石川 晋先生だ。
3年生4クラスの授業をご覧いただいて、研究協議会へ。
今回は、一応緊急事態宣言が明けていた頃だったため、年度当初計画していたRoundstudyを取り入れた協議会を実施した。協議会の大まかな流れは以下の通り。
1.授業終了後、すぐに協議会会場へ。
2.授業者が集まるまでの10分間で、各グループRound1のテーマ「各担任の授業参観の視点を中心に思ったこと考えたこと」を話し合う。
3.校長挨拶と講師紹介
4.授業者自評
5.グループリーダー以外は別のグループに移動。Round2「グループリーダーの説明を受けて思ったこと考えたこと」を話し合う。
6.元のグループに戻り、Round3「良かった点、改善点、質問」を話し合い、整理して短冊に書き、どんどん貼り出していく。
7.ファシリテーターが参観者の意見と授業者をつないでいく。
8.指導講評
9.閉会
といった感じの流れ。
Roundstudyは、昨年度は石川先生が全ての流れをご自身で進めて下さったため、今回、校内だけでやるのは初めて。もちろんファシリテーター役は私。
職員のみなさんが前向きなため、Round1から熱心な対話が生まれていた。ありがたい限りだ。
校長挨拶と講師紹介、授業者自評の後、Round2に入る。この時点で時間が多少ずれ込んだため、短時間だったがRound2もグループリーダーを中心に活発な話し合いが始まる。3年生の先生方に、ご自分のクラスのグループに気軽に入ってよいと伝えて入ってもらった。この時点で授業者と参観者がかなりフラットで気軽なやりとりがあった。その様子がとても嬉しかった。
「先生たちってすごいな〜」と感心して各グループを回っていた。
Round3は、本当に時間がなかったため、2つほどの話題で終わってしまったが、それまでの話し合いがとても活発だったので、ひとまず良かったかなと思った。ただ授業者と参観者が気軽にフラットに話している場をうまく生かせたらな〜と思った。また、ファシリテーターとして、各グループが話し合っているときの、自身の立ち回りがいまいちのように感じた。改善していきたい。
さ〜、いよいよ石川先生のご講評に。
今回は、「鉛筆対談」というものを進行していただいた。
これは、柳内達雄さんが昭和27年に実践されたものだそうだ。
これがまた、超アナログで、今「ICT」やら「GIGAスクール構想」やら言われている中だからこそか、人と人の接触、筆談的で、人と人との何とも言えない間があり、とても温かい人間的な空気を感じた。
書き終えたら、二人が自分の書いた部分を読み上げ、会話しているように発表する。必ず文末には「とてもすてきな授業でしたね!!」と入っていて、そこは2人で声を揃えて発表する。またこれがよいのだ。自然と笑いが起こる。
石川先生は、「どうでしたか。鉛筆対談。書いている間、何を書こうかなとか、相手が書いている途中、何を書いているのかなってちょっと覗いたりして、何とも言えない、アナログだからこそのよさがありますよね。なかなかこういった雰囲気って、ICTでは難しい。」と。
研究の目的はICTではないのだが、どうしても目的に傾きがちな点に、スッと鉛筆対談を通して、本来人が集まる学校という場の大切なものを思い出させて下さった、そんなことを感じた。
石川先生は、続いて次のような項目を立ててお話を進めて下さった。
1.とにかく役立ちそうなものを集めてみましょう
2.板書から考え直そう
3.知識に至るのではなく、知識をスタートにしよう
4.既存の授業のパッケージにはめ込む形を緩めたい
5.ツールの交通整理をしたい
「1.とにかく役立ちそうなものを集めてみましょう」について、1990年代後半に起こった「学級崩壊」についてのお話から、授業づくりネットワークの当時代表をされていた上條晴夫さん(現東北福祉大学)が仰ったことで、当時の教育状況は「湿地」に例えたというお話をされた。
湿地では授業成立にすぐにはたどり着けないことから、当時は、役に立ちそうなものをとにかくたくさん集めたという例から、では、今はどうか。というお話へ。今の教育状況は、流動化もしくは液状化しているのではないかと。
こういった教育状況を、ICTはどのような切り札となれるのか。切り札となる最適解を見つけるためには、やはりとにかく役立ちそうなものを集めることだとお話しされた。
「2.板書から考え直そう」については、板書≒ノート指導を手放していくというお話があった。板書のお話では、電子黒板を使っていても、結局教師は黒板の前にいるし、板書まですることもある。アイランド型(班毎にまとまって座る形)をしていても、やっぱり教師は黒板の前から離れられない。そういったこれまでの授業スタイルの縛りをほどかなければいけないと。
また、ノートのあり方については、東井義雄先生の『村を育てる学力』(明治図書,1957年)をご紹介され、「学習帳(ノート)機能の分類」を引かれた。私個人的に、校内研究という場で東井先生のお話が出てくることが嬉しかった。そういったかつての教育実践家のお話って、なかなかして下さる方は少ないから。
ちなみに、東井先生があげている分類は次の通り。
(1)練習帳的機能
(2)備忘録的機能
(3)整理保存の機能
(4)探究的機能
この中で、デバイスというものは何を引き受けるかという問いを出された。
私は、「整理保存くらいかな〜」と考えた。
石川先生のお考えは、「探究的機能」と「整理保存の機能」だとお話しされた。
ただ「整理保存の機能」について、ポートフォリオ的に残していくという点では、やはりアナログ的なノートもしくはプリントをファイルするといったことが良いというお話をされていた。
石川先生は、記録を残すということが大事なのではなく、残したものを取りに行き、ペラペラペラと見返しながら目的の記録にたどり着くという、自分の身体で学ぶ“行為”が大切だとお話しされ、本当にそうだなと思った。
しかも、ペラペラと探していれば、目的としていたページ以外での適した情報が得られる可能性だってあるなと思った。
デジタルかアナログか、しっかり見極める必要を感じた。
「3.知識に至るのではなく、知識をスタートにしよう」については、総合的な学習の時間、合科学習についてのお話へと進んだ。
ある教科の知識に至るためのではなくて、様々な教科の知識をスタートにしながら、合科的に学びを展開できるのは、ICTの強みだと。
そこで、「4.既存の授業のパッケージにはめ込む形を緩めたい」の話へとつなながり、ある教科の中で、だるま落としのようにどこかのパッケージでICT使いましたは、ICTを活用したとは言えない。そういった考え方を緩めていかないといけない。だから、合科的なダイナミックな活用をしていかないと、ICTの強みは出せないのではないかと。
ここもまた、確かにな〜と感じた。ある教科の中で、どう使おうかという話になりやすい。ICTを使っていくと腹を決めたら、ダイナミックな活用でなければならないんだと感じた。
「5.ツールの交通整理をしたい」については、3年生の授業のあるクラスの授業風景を出して、大型モニター、教科書、ノート、端末、ホワイトボードと教師が引き出しとしてもっているアイテムを全部使っていたことについて、情報量の多さは、やはり学習を進みにくくしてしまうお話があった。石川先生は、このお話の際、とても明るく笑いながらお話しくださった。と書くと、誤解されそうだが、石川先生のこういった自然で思い切り明るく笑ってお話しくださるところが、私はとても大切だなと思っている。「ありとあらゆるものを出しすぎで子どもが混乱してしましますね!」というような“ご指導”ではなく、笑顔で「◯◯先生の授業は、個人的にとっても好きですね(笑)。自分も◯◯先生のような授業って好きだったから。すごく良かった!それと、きっと◯◯先生はいろんなことを学んで来られたんだよね。こんないっぱいのツールが出てるくらいだから。」と、本当に温かいお話のされ方だなと感じた。
また、この情報の多さというのは、前回の校内研究で講師でご来校された蓑手 章吾先生がパソコン画面を開かせたままでの教師の説明を「認知負荷」というお話がつながっているのかもな〜と聞いていた。
協議会の時間のもちかたが昨年度と変わってしまい、昨年度よりも石川先生のお時間が少なくなってしまったため、大変申し訳ない中だったが、それでもとても大切な部分をお教えくださり、校内のこれからの学びとなった。
協議会終了後、石川先生はご多用な中にもかかわらず、校長室で3年生の先生方、そして、9月に授業を控えている5年生の先生方ともじっくりお話下さった。
先ほども書いたが、石川先生は、ご講評の時に、面白いとお感じなられた場面について、思いっ切り笑ってくださる。誤解を招かないように言っておくと、決して人を馬鹿にするとか、嘲笑ということでは全くない。
石川先生のそういった温かく自然な笑い、場を温めてくださる。様々なお話に加え、そういったお振る舞いにも石川先生は魅力があるのだな〜と感じた。
最後に、石川先生を最寄り駅までお送りさせていただいている際、
「昨年度に比べて、見違えるように職員のみなさんが研修に前向きになったね。」とお話くださり。
「そうですか!?私、そういった変化に全然気付けてません。」
「いや、そりゃ当事者だからだよ。いい雰囲気だったよ。今日は楽しませてもらいました。」
ありがたいお言葉だった。みなさんのそういった変化に私は支えられているんだな〜と感じた。これからも、校内のために、職員同士の学びのために微力ながらも努めていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
