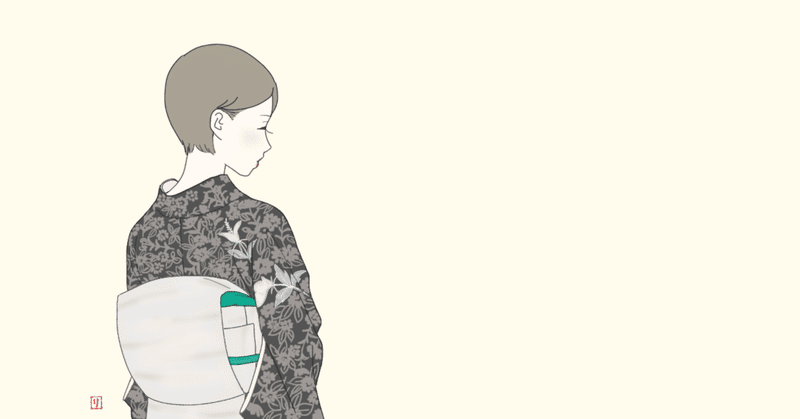
きものお手入れ上手への道②
前回はコチラ
さて、着物を大事に使うコツはわかったけれど
お次は保管方法について
これもただ夏物、冬物と衣替えしていた洋服の頃より
湿気と紫外線に気を付けるようになりました
着物を着ると、どうやっても避けては通れない、『お手入れ』
それ以前に
着物、どうやって保管していますか?
気をつける点は
紫外線を通さず、湿度の低い場所に保管する事
これに尽きます
・日向より日陰
・湿気のこもる床下より床上(高いところ)
・桐タンスがあればいい着物はその中に(湿度調節してくれます)
・和紙の文庫紙もある程度は湿度調節してくれます
・風呂敷で包むのも紫外線予防に
うちの場合、優先度で保存方法が変わります
①着るスパンの長い着物(訪問着、留袖、色無地など)、勝負服
陽の当らない部屋のアルミラック上段へ
年一で文庫紙の点検をします(文庫紙にシミのある場合は交換)
②年一で袖を通す着物(小紋、紬、木綿、ウールなど)
取り出しやすいプラケースへ(湿気と紫外線に注意)
シーズンオフ品は文庫紙の中に入れてアルミラックor風呂敷かけておく
③着る予定のない着物
趣味や年代が合わなくてお蔵入りしている着物。あります。
もう派手で着れないね~、や、今着るにはちょっと地味すぎ、手持ちの帯と合わない。。。など
生かせるその日が来るまでは~と文庫紙に入れたまま大風呂敷でひとまとめしてます
カビてしまってはいけないので、床には置かない(湿気がありますので)あと、ウールも一緒にしません
保管はこんな感じ
では管理は?っていうと
よく言われる虫干し
あんまり気張ってやっていません。^^;
というのも、着物って使っているうちは文庫紙の出し入れや、汚れ落とし云々で空気が通るので
特にこの日!と決めて気張って着物を干さなくても着物の状態は悪くならないのです
着る、脱ぐ、畳む、点検、きちんと保存する
が出来ていればそこまでシミを気にする事もないし
着ている時に気になる汚れがあればすぐに手入れするので
ワードローブとして稼働しているうちはそんなに気にしなくても大丈夫
なので①なら文庫紙を開けて空気をとおす&よれよれの文庫紙交換
②なら衣替えがそのまま虫干しの代わり
③は何があるかな~と風呂敷広げる(年1ぐらい?)だけ
虫干しが必要な着物は
・文庫紙を開く機会が全然なくて湿気が籠ってそうな着物
(特に梅雨時期を過ぎた頃の衣類は湿気を帯びてる事が多いので
どうかな?と見ておいた方がいいです)
や
・一度カビた着物、もともとシミや汚れのある着物
・こんな着物あったっけ?って思い出せない着物w
不思議なもので、こういう着物こそ、いざ、着ようとすると妙なシミが浮いて足り、着れなかったり
私はそれを「着物が拗ねた」と言ってます(笑
いざって時拗ねられないように、そこそこ御機嫌はとっておきたいところです~
衣類って湿気と紫外線(と、たまに虫)さえ気を付けておけばけっこう長持ちするもんです。
木綿着物の寿命は5年ぐらいで見積もっているのですが、実際に自分が使ってみた所、どれも10年以上は使えているので(最初の保多織は12年選手、おくみに穴が開いたので引退させました)お手入れと他の衣類との繰り回し、洗濯の頻度とかで変わるのかな
次回
お手入れで絶対やってはいけないこと
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
