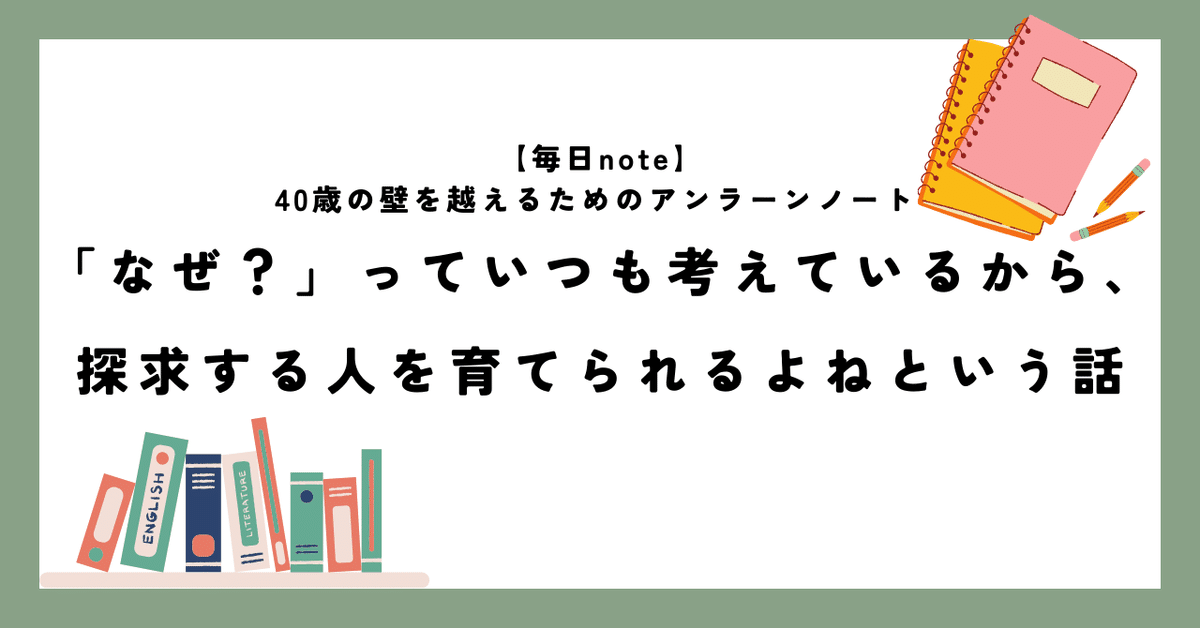
「なぜ?」っていつも考えているから、探求する人を育てられるよねという話
今日は自分の考え方というよりは、人を育てるという観点から考えてみたいと思います。
僕は常々、教育において、他者を育てる過程で「自分の頭で考える人」をどのようにして育てるかということを考えています。
この答えの一つとして、自分の頭で考える人を育てるためには、教える側が探求することを実践していることが不可欠だということです。
学ばない大人も学んでいる?
大人は学ばないとよく言われますが、学びの違いはあれど、日々、人は学んでいると思います。毎日書いているメールだって、相手やシチュエーションが変われば一通書くのに何時間もかけてしまうこともあるし、突如振られた書類仕事は今までのテンプレートが使えない種類のものだったりで、対応するのに新たな学びを必要としてます。このように多くの大人は学んでいないわけではなくて、日々の業務を通じて学んでいますが、これは必ずしも深い探究心からくる学びではありません。
教える側の探究心が必要
学生や大学院生の指導にあたる上では、業務に対応する学びよりも、「なぜ?」と探究する学びや研究を実践していることが求められると思います。
教員が知っている事実を喋りまくって学生に伝える。これでは、学生は考えることをやめてしまいそうですね。知識を自分で作っていこうとする姿勢を学生が身につけるためには、教える側もわからないことを知ろうとして知識を作っていこうとしていることを見せるのがいいと考えています。
何が知りたいのか?を考えることの大切さ
僕が研究室の大学院生に対して実践している方法は、彼らに「何が知りたくてこの研究をやっているの?」と質問することです。多くの場合、彼らは結果については話せますが、その結果がなぜ重要なのか、どのような新たな問いを提起するのかという深い考察が欠けていることがあります。この質問を通じて、単に結果を得ることではなく、その結果から何を学び、次にどのような問いを立てるべきかを考えることを促そうとしています。
その質問をしているときには僕の中でも明確な答えは持っておらず、大学院生と議論して一緒に考えていこうと思っています。この対話を通じて、何を知りたいのかに注目して、わからないを考えること。この知識を生み出す過程を体験させることが、自分の頭で考える学びにつながると信じています。
教える側の探究心が自分の頭で考える人を育てる
今日の世界では、「たくさん知っている」ことの価値は相対的に低下しています。代わりに、未知の問題に対して「なぜ?」と問い続け、自らの力で答えを見つけ出そうとする力が重視されています。教える人が探求心を持ち、わからないことに挑む姿勢を示すことで、学ぶ人にとって大きな刺激となり、自分の頭で考える力を育てることができます。
なので僕は何が知りたいのかに忠実になって、研究し、論文を書き続けています。この姿勢を持って学生と対話していくことで、探究心を持った人を育てることにつながっていくと信じています。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
