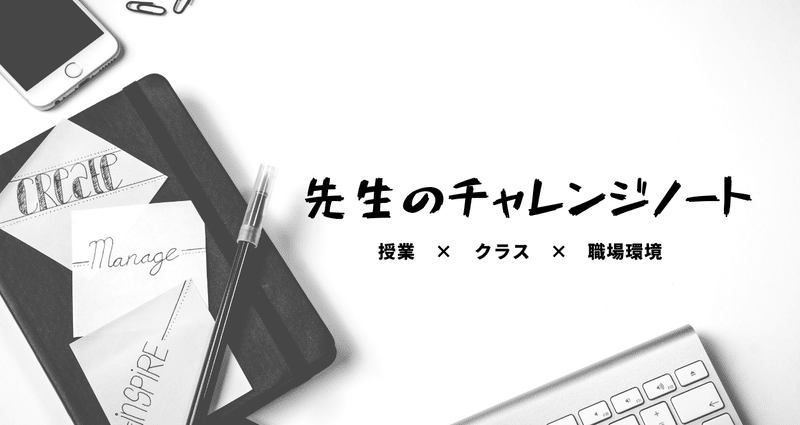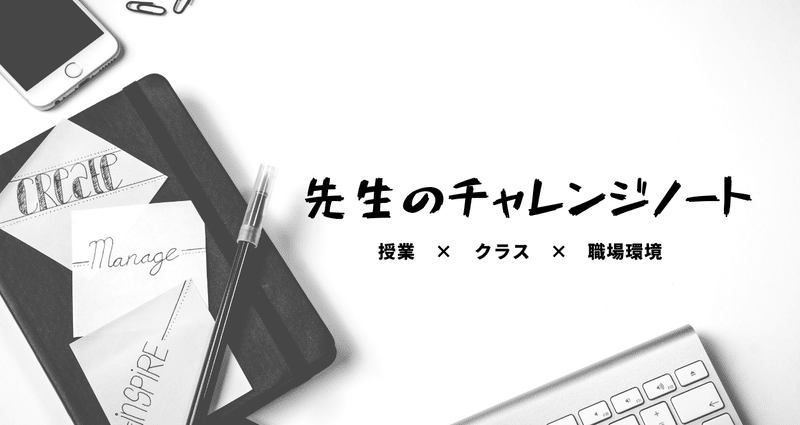生徒指導〜「できない」を自分で表現できない
教員の日常茶飯事の中に、未提出や忘れ物の指導があります。そこで最近目立つようになったのは、生徒自身で忘れてしまった、できなかったと言えないということです。
約束を破ったら気まずいことを知っているそういう子と対話をすると、「忘れちゃいました〜てへ!」みたいなことはあまりなくて、「すみませんでしたしゅん」ということがほとんどです。中には泣き出す子もいます。最近思うのは、子どもながらに約束を破ったら気まずいことを知っているし、いけないことだという感覚があるんだなということ。
「