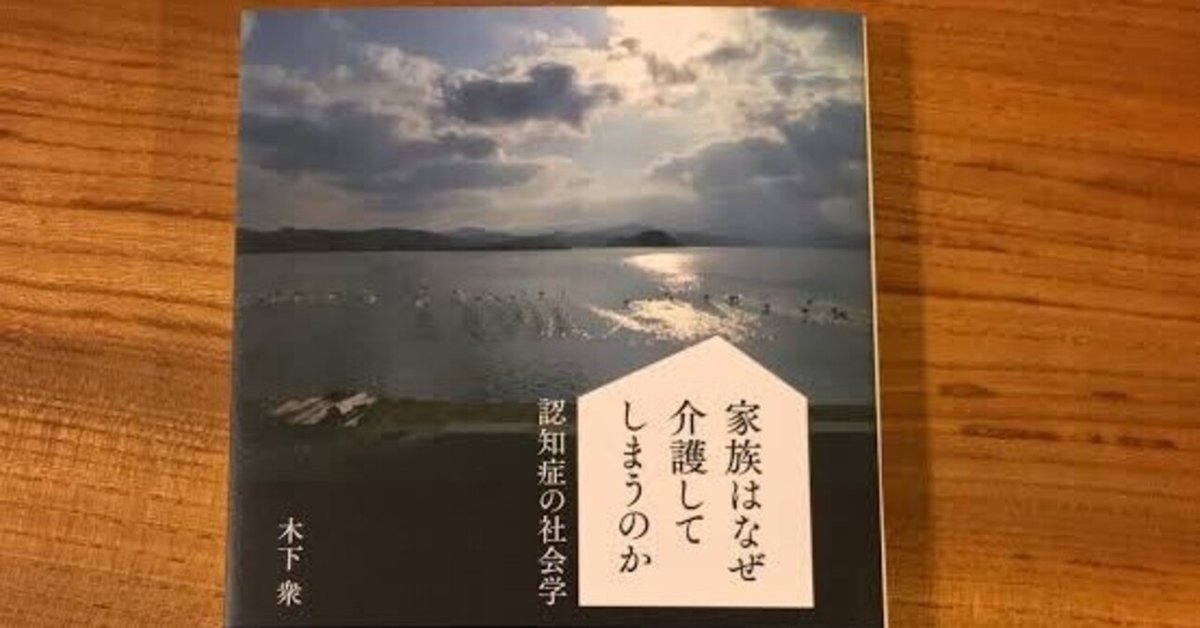
慶應大学助教 木下衆先生インタビュー 認知症ー介護者と要介護者の関係の捉え直しに向けて(前編)

今回のインタビューに関して、私は認知症の親介護を日常とするものとして、ずっと「認知症介護家族」の研究をされている方の話を聞きたい、と思ってきました。現状では施設等で認知症を介護する介護職の人、あるいは介護家族に対する認知症の啓発、傾向などについて段階ごとの対応方法のありようを伝える本はたくさん出ていますが、その理想の介護に向けての家族側などの大変さに着目した本や研究がなかなか見つからないなと思っていたなか、「介護家族」にピントを当てる木下先生の本に出会い、随分救われたものです。家族は認知症当事者を良く知るからこそ、悩み、憤り、そして対応を反省する流れに身を浸す傾向があると思います。また現在においては認知症者の人生の歩みや性格に合わせた介護が求められる時代でもあり、介護者はそれを理解するゆえにこそ、新たな悩みがまた生じる。そこに答えはすぐ出ませんが、そのような形で悩む時代であるからこそ、感情に溺れず方向性を進める(社会的資源を本人のために積極的に活用するなど)のではないか?そのような角度を軸として新たな知見を知りたく、木下先生にさまざまにお話を伺いました。
事情があり、インタビューから半年以上経ってしまいましたが、今回はお話の前半を掲載します。
最も脆弱な人たちの間に宿る強い倫理観
杉本 木下先生が書かれた『家族はなぜ介護してしまうのか』(世界思想社:2019)。大変共感を持って拝読しました。私も母親の認知症介護を始めて5年目に入りましたが、なかなか悩ましいものです。認知症になり始めの頃から一緒に暮らしていて、今の認知症症状は中程度。はたから見て認知症だとわかるところまで来てるんですけど、認知症に対しては「どう対応したらいいか」という本はよく見かけますけれども、実際は看る側の戸惑いというものがたくさんあるわけです。そこに届くもの、特に専門的に研究された本などなかなか見つからない中で、先生の本は介護している家族、その介護家族分析の本ということで、自分の問題ともフイットして、とてもありがたかったということがあり、ぜひお話を伺いたいと思ったところなんです。
もう一つは、認知症を看ている家族というのはいまどんどん増えていると思いますので、看ていてたいへん悩ましく、どういうふうにかかわったら良いのかということで悩んでいるご家族の人もとても多いと思います。ですので、わかりやすい部分と、深掘りした部分と、贅沢なようですが(笑)。お話を伺えればと思います。
木下 ありがとうございます。まずこの本は元々は社会学の博士論文という形で書いて、それを出版したわけですけれども、出版社や編集の人とずっと話してたのは、介護家族の方にも届くようなものを書きたいねということで、そこはかなり議論したところです。学術論文として見たとき、今はインターネットで検索すれば元になった論文がタダで読めたりするわけで、本にしてまとめたときに付加価値をできるだけつけなくてはいけないことは意識しました。やはり一つの物語というか、ストーリーとして、介護家族の方に届けていく。もちろん社会学という専門的な分野の研究ではあるんですけれども、最終的には実際に介護しているかたに届くものにしたいと思ってやっているので、おっしゃったように、例えば5年やってきたご自分の経験と照らし合わせながら「なるほど」と思っていただけるものを目指していたつもりはあります。ですからいま自分自身の問題としてフイットしたと言っていただけると、著者としても嬉しく、出版社もとても喜ぶんじゃないかと光栄に思っています。
もちろん、私自身わかりやすくということは考えたんですけれども、同時に専門的な議論の水準は落としたくないことでもありまして。
杉本 そうですよね。
木下 専門的な議論の水準を保ったままどうわかりやすくしていくのか。どう両立させるかということが、いまの時代の専門書に求められることじゃないか。介護の経験で言えば、実際に介護されている人たちのほうが経験を積んでおられて、それぞれの思いであるとか、知識をお持ちなわけですから、そういう人たちが読んで「そうだな」と思っていただけるものを届けようと思った時、こちらもけして手は抜けないし、いわば学術的なわかりにくい言葉で誤魔化して書くとすぐ見透かされると思うんです。だからきちんとここまでなら言えるということを、できるだけわかりやすく書く。高度な面もわかりやすく書くことによって、介護家族のかたとかにも「ああ、これは納得できる」というふうに評価してもらえる。そういうものになるんじゃないかと思っていました。
杉本 そうですよね。うちも日常はある程度落ち着いてはきてるんですけど、最初の頃、特に2020年の2月ですね。コロナが始まった頃はコロナ自体誰も経験してない事態だったですし、北海道は一足早くコロナ患者さんがまとまって出たこともあって、この時点で仮に感染してしまって、「流行病」で亡くなったりするのはあまりにもつらいと思って、2月下旬からデイサービスを4ヶ月近く休ませたら、案の定、認知症が増悪してしまいました。そのころがいちばんしんどかったですね。前提知識がなくて、日々悩みながら格闘していたというか。全体像が見えなかったんです。例えば先生がご自身の本のなかで紹介された*小澤勲(おざわいさお)さんというかたも知りませんでした。そのような先駆者の人の本などにも出会って、やっと介護している自分の辿っている方向性はこうなんだというふうにわかるところがあり、心の落ち着きが少し持てて、やっぱり「病気は病気なんだ」と納得できて、今までの母親の非連続性のようなものによる悩ましさに少し踏ん切りつきつつあるかもしれないのが、この本に出会って以降の感覚です。そのこともあって、少し最近落ち着いている感じがします。
木下 杉本さんが数年介護してきて、「もしこの流行病で亡くなったら」と悩んだと仰りましたけど、私の調査協力者でリモート面会をされている方も、なぜリモート面会を続けるかというと、ここまで頑張ってきていた母の状態を何とか維持させたいからという言い方をされるんです。だから介護されているかた、杉本さんであれ、多くの家族のかたがやっぱり認知症の人が頑張ってきたと思っていて、それをこのコロナ禍で台無しにはしたくないとなんとか踏ん張っておられるのが、もう二年。非常に苦しい状況かなと思われますけれども、一方でケアが必要な他者のために頑張るという、そういう強い思いがあって、そこは人間の善意というか、人間の強い部分だと思うんですよね。それが最も脆弱な人たちの間で強い倫理観というか、強い思いというものが出てくる。それはやはり大事なことというか、一つの人間の在り方というか、姿なんだろうなというのはお話を伺っていて、とても思うところですね。
杉本 それはまさに先生の本にも書かれている「なぜ介護してしまうのか」という部分とか、「道徳性の上昇」みたいな話として書かれていますけど、あえてモラリステックに生きていきたいとか、自分は善意的に生きて行きたいから家族を徹底的に看ますというよりも、やはり流れに「巻き込まれる」というのが正直な所でしょうか。ウチは幸いそんなにアグレッシブな問題行動がなくて、元々性格が温厚な人なので、いわば僕自身が悩ましいところで完結しているというか、だんだん自分の中にほっとけない気持ちが定着して時間が経てば、ふと「自分自身がいつまでも看ていることで、逆に自分の人生はどうなるんだろう?」と思うんですが、同時に“哀れ“というか。そんな感じもしますからね。やはりどうしても看れるところまでは看ていきたいという気持ちになります。
当事者を中心に置く新しい認知症ケア
杉本 それでは本に則してお話を伺えればと思うんですけど、まず認知症の「新しい認知症ケア」について。例えば2000年の介護保険以前の時代との間で、画期というか、変化があると思うんです。そこはやはり介護保険の存在が大きくて、介護をするのは家族だというものから、介護そのものを社会で支えていくという前提で始まった制度ですけど、「なるほど」と思ったのはやっぱり認知症に対する考え方の変化ですね。介護保険の導入で、専門職の人も、あるいは介護する側も認識が変化してきたという、そういう啓蒙的な流れができたと思うんです。その「新しい認知症ケア」へ変化して行く流れに至る経緯みたいなものを教えていただけないでしょうか。
木下 ぼくが本のなかで用いている「新しい認知症ケア」という言葉は元々*井口高志さんというかたの『新しい認知症ケア時代の臨床社会学』、副題は「認知症介護を生きる」という本で、いわば専門用語として出てきた概念なんですよね。
一つは小澤勲さんに代表されるような精神科医療、あるいは介護関係のさまざまな先駆的な動きが主流になっていく。こうして認知症がどんなに進行しても“その人を中心に置く“などという試みは、それこそ人類史上初めてだと思うんですよね。通じる言葉がなかなか喋れなくなってくる。記憶も曖昧になってきたりする。それでもその人にはその人らしさが残っているんだということを中心におきながら、その人のライフヒストリーを大切にしながらケアをすれば必ず何か残っていくし、保たれていくんだ。そしてそれがより良いケアなんだ。その価値観や実践。井口高志さんも整理されていますけれど、宅老所であるとか、精神医療の場であるとか、いろんなところで起きてきた動きが2000年代くらいに一つの主流となって結実していく。
もう一つはおっしゃられた制度的文脈がありまして、新しい認知症ケアという介護現場での理念や実践を支えていくものとして2000年代に介護保険制度がうまく乗っかってスタートしたということは言えるんじゃないかと思います。それまでも自治体レベル、あるいは今でいう「認知症の人と家族の会」、かつての「呆け老人を抱える家族の会」ですね。自治体レベルあるいは自助グループレベルで様々なサポートをやってきたということはあるんですけれども、それをいわば国家単位で、しかもそれを社会保険制度を使って支えていくということができあがった時、その制度の変化と臨床の変化がうまく重なり、特に認知症ケアにおいて大きな変化が生じたことは一つの大きな見立てになるかなと思うんです。いつも紹介するんですけど、「呆け老人を抱える家族の会」、いまの「認知症の人と家族の会」が編集した『ぼけ老人を抱えて』という本がありまして、これが1982年に初版が出てるんですけれども、要は当時の介護家族の方の体験談を集めてるんですよね。そうすると本当に文字通り助けがない。困っても助けてくれる人がいない。行政の人に相談しても仕方がない。介護は家族がすべきものというのが厳然としてあって、それにのらざるを得ない。ぼくは介護保険制度ができていちばん大きな変化というのは、「家族介護の姿を変えた」ことだろうと思うんです。つまり80年代とかであれば家族介護と言えば文字通り「家族だけ」が「家庭の中で」すべきものとされていた。ところがいまの家族介護は家の中に専門職がやってきたり、あるいは家の外に通わせたり、いろんな援助の方法で専門職とやり取りしながら進めるというふうになっている。もちろん主な介護者が家族であるというのは統計的に見てもいまだに多くて、6割くらいなんですけども。ただ主な介護者が家族だったにせよ、家族が全てを抱え込んでいるわけではない。
杉本 そうですね。
木下 2020年代に私たちが生きているわけですけれども、私たちは公的サービスが一切関与せずに家族が全てを抱え込む、そんな家族介護は「そうあるべき」というふうにもはや捉えないと思うんですよね。少なくとも何がケアのあるべき姿かみたいな規範レベルの変化というものは、介護保険ができてからの20年くらいで変化が着実に進んできたんじゃないかと。自分の家の中だけで“全部やりなさい“みたいな話とは議論の前提が根本的に異なっている。ここは一つ重要なことかなと思っています。
次のページへ→ 1 2
*小沢勲ー 1938年生まれ。京都大学医学部卒業。京都府立洛南病院勤務、同病院副院長、老人保健施設桃源の郷施設長、種智院大学教授、種智院大学客員教授を歴任し、2008年死去。
著書に、『痴呆老人からみた世界』(岩崎学術出版社)、『痴呆を生きるということ』『認知症とは何か』(洋泉社)など多数。
*井口高志ー 975年山梨県生まれ。奈良女子大学生活環境科学系准教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(社会学)。主著に『認知症家族介護を生きる――新しい認知症ケア時代の臨床社会学』(東信堂、2007)、最近の論考に、「閉じること/開くことをめぐる問い――家族介護を問題化する〈まなざし〉の変化を素材として」『支援vol.3』(生活書院、2013)ーシノドスより
この記事が参加している募集
よろしければサポートお願いします。サポート費はクリエイターの活動費として活用させていただきます!
