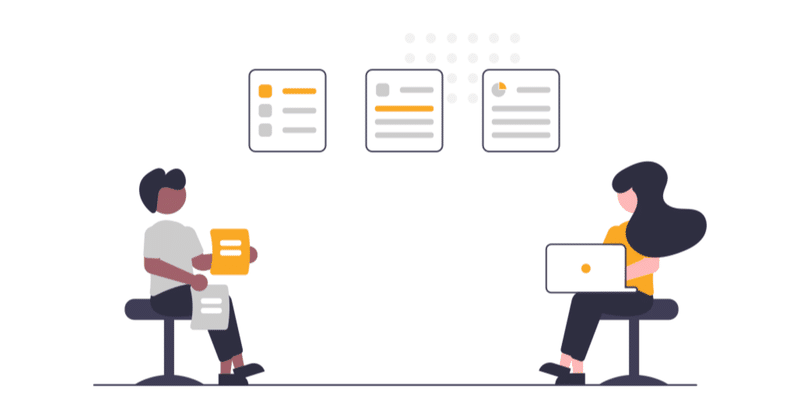
上司との1on1がカギだった。あなたの“燃え尽き症候群”を防ぐコツ
あなたにもこんな経験はないでしょうか?
・「タスクの締め切りが近いのに、やる気どころか危機感も湧いてこない」
・「今まで頑張っていた仕事の意味がなんだか分からなくなってきた」
・「自分にはもっとできることがあるのに、上司からは雑務ばかり押し付けられている気がする」
少しでも身に覚えがあるのなら、それ、“燃え尽き症候群(バーンアウト)”かもしれません。
実は“燃え尽き症候群”は誰にとっても起こりうる意外と身近な症状で、名前を知っている方も多いことでしょう。
しかし、あなたはなぜ燃え尽き症候群が起こるか答えられるでしょうか?
それだけではなく、対処するには上司をはじめとした身近な人とのコミュニケーションが重要とされていることもあまり知られていません。
そこで今回は“燃え尽き症候群”とその対処法についてまとめてみました。
「自分が好きで始めたはずの仕事が何だか面白くない・・・」
この記事が、そんなお悩みを抱えた方の一助になれば幸いです。
1. 燃え尽き症候群とは?
そもそも燃え尽き症候群とは、「仕事や学業に没頭していた人が、心身の疲労から急激に意欲を失い、社会に適応できなくなってしまう症状」を指します。
参考:厚生労働省 e-ヘルスネット「バーンアウトシンドローム」
世界保健機関(WHO)の最新の国際疾病分類(ICD-11)では「職場における慢性的なストレスが適切に管理されなかったことに起因する症候群」と定義されており、あくまで病気ではなく職場で起こる一つの現象と解釈されています。
またその特徴としては、下記のような症状が挙げられます。
・エネルギーの枯渇感や疲労感がある
・自分の仕事に対し心理的な距離感を感じたり、否定的な感情が増大する
・業務効率の低下
燃え尽き症候群は個人のパフォーマンスを阻害することはもちろん、企業にとってもマイナスの影響が大きいため、臨時休暇を付与するなど、各社が大がかりな対策に乗り出しています。
米国・Kronos社とFuture Workplace社が行った調査によると、人事担当者の95%が、「社員の燃え尽き症候群が労働力の維持に大きな影響を与えている」と認識しています。
つまり燃え尽き症候群が、“社員個人だけでなく、企業にもさまざまな問題を引き起こす可能性がある事象”として広く認識されるようになってきていると言えるでしょう。
77%の社員が現在の職場で燃え尽き症候群を経験している

デロイト社の調査によると、77%の社員が現在の仕事で燃え尽き症候群を経験していることがわかりました。
しかもそのうち51%は、一度以上仕事に燃え尽きたと感じたことがあり、84%は仕事に情熱を持てないと答えています。
そう。燃え尽き症候群はただ認知されているだけでなく、非常に一般的かつ誰しもが直面する可能性のある症状なのです。
また、indeed社の調査によれば、67%の社員が「コロナ禍で燃え尽き症候群が悪化した」と答えるなど、自覚症状を持つ人々は増加し続けています。
これはリモートワークにおけるコミュニケーション不足や、オン・オフの切り替えの難しさによる過重労働などが一因となっていると考えられるでしょう。
以下、参考記事になります↓
さて、これだけ多くの方が悩んでいる燃え尽き症候群。そもそもなぜ発生してしまうのでしょうか?
2. なぜ燃え尽き症候群が発生するのか
燃え尽き症候群は徐々に発生するため、多くの人は自分が燃え尽き症候群になり始めていても気づかないまま、仕事を続けていることもあります。
では、じわじわと社員を精神的に追い詰める主な要因とは何でしょうか。
燃え尽き症候群は、社員個人ではコントロールが難しい事象が原因で、自身の期待と現実にギャップが生じる時に発生しやすいとされています。
例えば燃え尽き症候群の原因としては、一般的に以下のような要因が挙げられます。
・膨大な仕事量
・長時間の労働と残業、それに見合わない報酬
・競争的で心理的な安全性が無い雰囲気
・病欠や休暇を充分に取れない状態
・劣悪な仕事環境
つまり燃え尽き症候群は、従業員にとって過度なストレスがかかる(=自身の理想とギャップがある)働き方の中で発生しやすいと言えるのです。
この中には上司が過度に残業を強いるような直接的な要因もあれば、残業を賞賛するような雰囲気を組織が作ってしまうなど間接的な要因もありますが、あなたの働き方に問題はありませんか?
自覚はなくても、一度客観視して振り返ってみると良いでしょう。
いずれにしても、燃え尽き症候群がどのようにして起こるのかを知ることが、症状に対処していくうえでは非常に重要です。
3. 燃え尽き症候群に気づくには
とは言え、燃え尽き症候群の兆候は本人でも気づけないことがあるくらいですから、周囲の人間が気づくことはなおさら難しいでしょう。
冒頭でも述べたようにWHOでは、燃え尽き症候群を、「職場における慢性的なストレス状態」と定義しています。
この状態は、心身ともにさまざまな問題を引き起こす可能性があります。
特に些細な異変に気づいてくれる人が少ないリモートワーク下においては、少しでも自分の体からのサインを認識し、自分の状態に気づけるようになることが重要です。
以下の代表的な兆候の中で、自分に当てはまるものがあれば燃え尽き症候群を疑うと良いかもしれません。
・肉体的、精神的な疲労感
・集中力の低下
・イライラする、落ち着きがない
・孤立感
・エネルギーと熱意の欠如
・眠れない、朝起きられないといった睡眠障害
・うつ症状
このように燃え尽き症候群は、仕事と生活のバランスを崩すだけでなく、個人の健康にも深刻な影響を及ぼします。
そして燃え尽き症候群の最大の問題は、「原因を取り除かない限り時間が経っても自然に治ることはない」ということです。
4. 燃え尽き症候群への対処法
では、燃え尽き症候群になってしまった場合、どのように対処するべきなのでしょうか?
まず大事なことは、何が自分のストレスの原因となっているかを把握し、適切に取り除くことです。
今の仕事において、「何が自分にとってストレスか」、「それをどうやったら解決できそうか」を考えてみてください。
最初に多くの人が思い浮かべる対処法は、転職や異動で労働環境を変化させることでしょう。
実際にGALLUP社の調査では、“燃え尽き症候群を自覚している社員は、そうでない社員と比較して2.6倍も転職を検討している”というデータも出ているなど、「転職こそが燃え尽き症候群の解決法だ」と認識している人が多いと言えます。
またマイクロソフト社の調査でも、調査対象となった労働者の40%が転職を検討している(2021年時点)という結果が出ており、やはり転職が世界的なトレンドとなっていることが分かります。
しかし、転職は一つのきっかけとなり得ますが、実は根本的な解決方法とは言えません。
なぜならば、ほとんどの場合、あなたに仕事の指示をするのも、あなたの業務量を調整するのも、“会社”ではなく“上司”が行うことだからです。
つまり、転職をしたからと言っても上司とのコミュニケーションが取れていなければ、燃え尽き症候群はどんな職場でも起こりうるものなのです。
上司とのオープンなコミュニケーションが燃え尽き症候群を防ぐ

そこで重要になってくるのが、1on1。
上司とのオープンなコミュニケーションである1on1を通して、上司に悩みを吐き出せる状態を作り、最適な業務量や内容、目標を調整していくことが燃え尽き症候群の有効な対処法です。
1on1の理解を深めたい方はこちら↓
ただ、中には「会社で1on1は行われているけど、上司にオープンに話せる状態ではない」、「些細な兆候だけで声をかけていいものか」と悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、具体的にどんなステップを踏めば効果的な1on1を実践でき、燃え尽き症候群に対処できるかをご紹介していきます。
---
ステップその1:自己内省を行い、原因を追求する
具体的なアクションを行う前に、自分がなぜ燃え尽き症候群になっているのかを正確に理解することが大切です。
ストレスの原因となっている仕事上の人間関係や、無駄だと感じている業務はないでしょうか。
与えられた仕事に忙殺されていたり、上司に良い印象を与えようと無理をして頑張りすぎていたりはいないでしょうか。
自分が心地よく働けている状態(=ゴール)を考えながら、そこに至るまでの課題を認識してみましょう。
ステップその2:同僚に相談し、客観的に自分の置かれている状況を把握する
内容や関係性によっては、いきなり上司に相談することが憚られる場合もあるかもしれません。
そんな時は友人や信頼できる同僚に、自分のストレスや置かれている状況を伝えてみましょう。
客観的な意見を得ることで、責任の所在やストレスの度合いをより正確に測ることができます。
ここで、同僚から見た新たな視点や考え方を得られることもあるかもしれません。
ステップその3:自分のありたい姿と、そこに至るまでのプロセスを整理する
自己内省に基づいて、自分の燃え尽きを克服するために必要だと思われる事柄を2~4つ挙げ、実現可能な解決策を考えてみましょう。
ワークライフバランスをとることが最優先事項であれば、勤務時間を短くしたり、自分にとってのオン・オフを明確にすることが重要です。
また、ストレスを軽減したいのであれば、納期を後ろ倒しできるタスクがないか、自分とチームメンバーが協力して仕事をすることで仕事量を減らせないかなど検討してみましょう。
ステップその4:上司にオープンに相談する
上司に相談する準備ができたら、自分が燃え尽き症候群の影響を感じていることを率直に話します。
身体的、精神的に自覚がある症状を伝え、ステップ3で考えた要求とその解決策をいくつか挙げてみましょう。
もちろんただ自分の要求を伝えて終わるわけではなく、より自分の業務を効率的に行う方法がないか、より簡単に成果を挙げられる方法がないかについては聞いてみると良いかもしれません。
もし話し合いの中で仕事を休む必要があると感じたら、迷わずその意思を伝えましょう。燃え尽き症候群に対処するうえでは、休息は非常に重要です。
ステップその5:最悪の場合に備える
ここまでの取り組みで、恐らく多くの上司は何らかの対処を取るでしょう。
ただし、ここまでしても仕事量を調整してくれなかったり、休暇の申請に応じてくれなかったりと、何もしてくれない上司もいるかも知れません。
そんな時には、①さらに階層が上の上司に直接相談する、②別の組織への異動を直談判する、③転職活動を行う
など、最悪の場合に備えたプランを用意しておきましょう。
もし既に心や精神に不調をきたしている場合は、無理せずカウンセリングなどを行うことも一手です。
オープンなコミュニケーションで上司と調整を図っていくことは非常に重要ですが、最終的には自分が自分の人生をコントロールしているという自覚を忘れないようにしましょう。
---
いかがでしたでしょうか?
社員の燃え尽き症候群は、国内外を問わず様々な職場で問題となっていることもあり、悩んでいるのは決してあなただけではないはず。
何はともあれ、まずは相談することが大事です。
上記のステップで伝えれば、上司はきっと適切な業務量やポジション、キャリアを提案してくれるでしょう。
あなたが少しでも燃え尽き症候群の兆候を感じているのであれば、心と体の健康、そしてあなたの人生のために、一度立ち止まって考える時間を設けてみることをおすすめします。
あなたの仕事は誰かが代わってくれるかもしれませんが、あなたの人生を代わってくれる人はいないということを忘れずに。
・・・
ハイマネージャー
OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。
Twitterでも、リモートワークやマネジメントに関する知見を日々発信しています。ぜひフォローお願いします!


