
人事の豆知識】人材プログラムモデル(PPM)についてを解説、契約社員は入れるべき?
今日、成功している組織は、タイプの違う多様な働き手から構成されています。
そしてそのチームの中には、部署外から派遣されたメンバーもいれば、多種多様な経験や経歴をもつ人々、プロジェクトベースの契約社員であるフリーランサー/個人事業主(IC)もいます。
組織というものは、従業員の書類上の分類がどうであれ、全員を大切なチームメンバーとして尊重するのが理想です。
健康保険や労災保険といった福祉を受けられる正社員がいる一方で、1099従業員と呼ばれる契約社員も、やはりチームの一員であることに変わりはありません。
一体感ある組織文化を醸成し、従業員の満足度と就業意欲を高めるべく尽力している人事担当者が、契約社員をPeople Program Models(PPM/人材プログラムモデル)に加えようとするなら、いくつもの特殊な配慮を要します。
そこで今回は、PPMとは何かや契約社員をPPMに含めることがなぜ重要か、そしてそれを効果的に行うにはどうすればよいかについて、詳細を以下にまとめます!
▼人材育成においても重要な、1on1への理解を深めたい方はこちら⇩
▼人材育成においても重要な、OKRへの理解を深めたい方はこちら⇩
そもそも、人材プログラムモデル(PPM)とは?

PPMとは、企業が従業員と情報の交換・収集を行う様々な方法であり、これによって社員から最高のパフォーマンスを引き出すことができます。
PPMを構成するのは、3つの主要な要素です。
すなわち、目標設定の意思統一・従業員の職場経験に関する情報収集・パフォーマンス管理になります。
しかしPPMとは、組織がただチェックボックスを埋めれば終わりという作業ではなく、むしろ常に現在進行形のプロセスであって、年間通じて何度も見直し、必要な改善や調整を検討し続けなければならないものです。
このような観点から、前述の3つのカテゴリの実践例を以下に示します。
PPMの要素①|目標設定の意思統一
社員とマネージャーとの間で、四半期ごとに目標設定を行います。
PPMの要素②|社員の職場経験に関する情報収集
定期的な就業意欲および満足度調査を行います。
匿名で収集された従業員の意見は、組織の行動計画を策定する管理職にとって、貴重な自己申告データとなります。
PPMの要素③|パフォーマンス管理
一定の評価期間を設け、パフォーマンスに基づくフィードバックと、従業員の業績により総合評価を行います。
マネージャー側も社員側も、型どおりのパフォーマンス評価だけではなく、1対1の気軽なチェックイン・ミーティングなどの場で、今後を見据えた対話を行いやすくします。
時代と共に変わる契約社員の企業貢献性
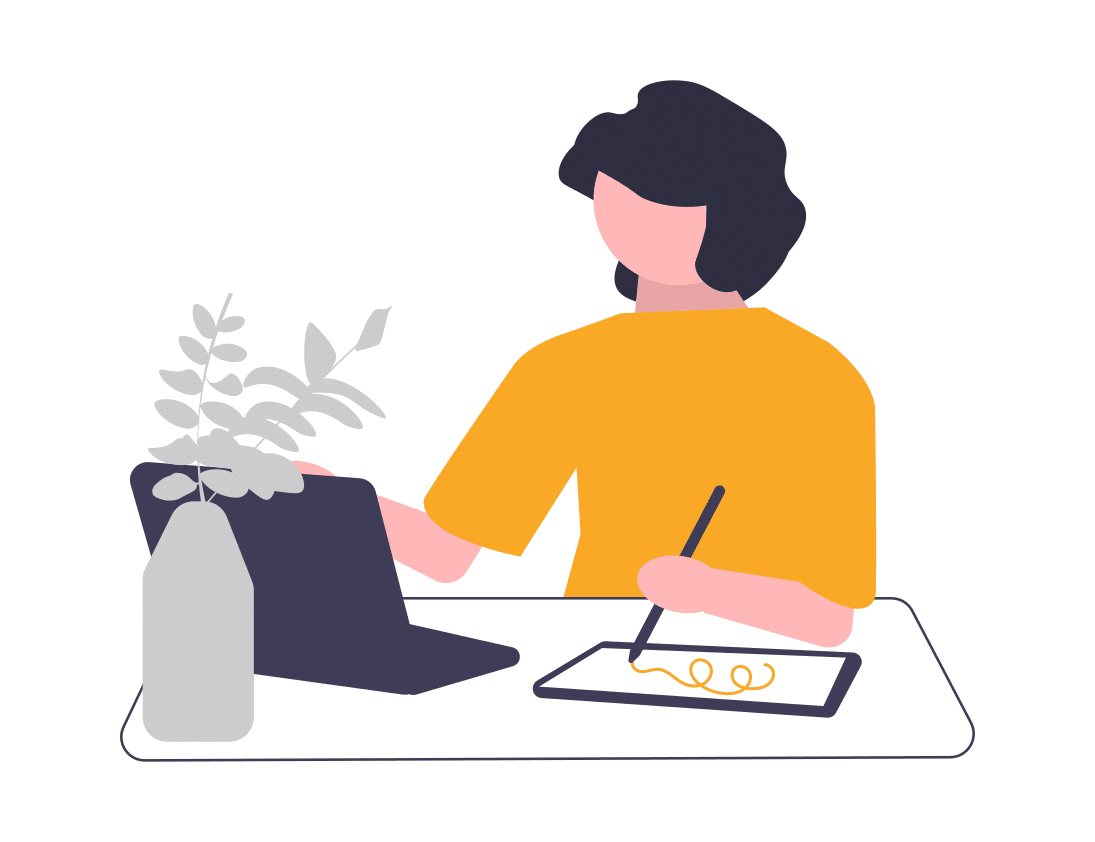
ここ20年の間に、契約社員の数は驚くほど増加してきました。
ギャラップ社による2019年の調査によれば、契約社員もしくは自営業者として働く成人の数は、2000年から2016年の間に850万人も増加しています。
一定の契約期間に社内の決まった業務を行う者から、プロジェクトベースの業務を複数の企業で兼任する者まで、契約社員は陰に陽に、さまざまな形で企業に貢献しています。
と、ラティス社のコンサルティング・サービス部長であるジュリア・マーキッシュ氏は語ります。
会社『で』働くのか、会社『と』働くのか、どんな形にせよ、働き手は企業文化に影響を与えます。そして、企業文化とは、時とともに多様化する行動様式や規範に他ならないのです
正社員と契約社員の間には、税制・法制上の重要な区別があります。
とはいえ、違いといえばそのくらいのものです。
プロとして、一個人として、意義ある仕事に時間と労力を注ぎ、企業に利益をもたらしていることに変わりはありません。
氏は続けて言います。
どうすれば素晴らしい仕事を奨励できるか、そして全体を総合的に高められるのか―それこそPPMの精神ですが―を考えるなら、企業文化や成果、目標達成に貢献している人物は、誰であろうと称賛を受け、成長の恩恵を受けるべきなのです
インクルーシヴかつ人材中心の考えに立てば、契約社員も組織のPPMに加えるべきです。
それどころか、企業が前進を続けるためには、それが現実的に必須条件となっていくでしょう。
従業員の一翼をになう契約社員は、今後とも比重を増していくと予想されます。
そして、正社員と契約社員で別々のPPMを適用することは、成長企業にとってサステナブルと言えません。
契約社員をPPMに加える方法

自営業者であって正社員ではないという法的立場にある以上、契約社員を誤って分類することは避けなくてはなりません。
とはいえ、人事チームがそうした個々人をPPM内に、適切に位置づけることも不可能ではないです。
そのためにはどうすればよいか、前述の3つの主要カテゴリそれぞれについて、以下に提案します。
方法①|目標設定の意思統一
目標設定によって、従業員の業務と企業全体の使命との関連性が、明確になります。
目標設定を、期待値設定やフィードバックのやり取り、勤務評定などの枠組みとして使用している企業は多いです。
パフォーマンス管理の中でも、型どおりのパフォーマンス評価という手法は契約社員向きではないですが、組織と個人との関係を強化する上で、目標設定は効果的なやり方として推奨できます。
マーキッシュ氏は言います。
企業が何を目指しているのか、また、その目標達成のために契約社員がなぜ、どのように貢献できるのかを、(契約社員に対して)明示することは、さらに重要だとさえ言えます
氏によれば、契約社員は企業の使命、価値観、文化といった情報に、日常的に触れることが少ないです。
例えば全体会議や、こういった話題がよく議論される場に加わることがまれだからです。
組織がこうした情報を契約社員に伝達する接点も限られます。
だからこそ、適切な情報源や、社内の相談相手を通じて企業目標を理解できれば、契約社員はさらに企業に貢献できる立場にあります。
方法②|職場経験に関する情報収集
社員調査は、社内コミュニケーションの満足度から、特定の役割に対する意欲の度合いに至るまで、さまざまな尺度として使われる。契約社員を満足度/就業意欲の調査対象に加えることは、彼らをPPMに加える適切かつ効果的な方法です。
ただしその際、現実的な配慮を要することに留意しなければなりません。
まず第1に、調査に対しては「社員(の)」と入れず、単に「就業意欲調査」や「満足度調査」などのタイトルをつけるべきです。
これはただ言葉のあやに見えるかもしれませんが、契約社員にとっては違いがあります。
契約社員は正社員ではなく、この区別は雇用法規関係のさまざまな意味を持ちます。
調査のタイトルをシンプルかつインクルーシヴにすることで、全員に対する敬意を示すことができます。
第2に、全回答は従業員の分類によらず集計されるとはいえ、匿名性を留めつつ最終的には正社員と契約社員の回答を、判別できるようにしておくべきです。
収集データを正しく評価し、解釈し、質問に対する回答の意味をはっきりさせるためであります。
例えば、正社員福祉の満足度といった質問に対して契約社員が回答しても、データとして不適切でしょう。
方法③|パフォーマンス管理
契約社員をパフォーマンス管理の対象とすることは、かつてはタブーでした。
従業員の分類を誤れば法的な問題が発生するので、1099従業員(契約社員)をパフォーマンス管理プログラムに加えることに対しては、強硬な反対派も多いです。
しかしこうした考え方は、パフォーマンス管理とパフォーマンス評価を混同したものです。
契約社員は確かに、型どおりのパフォーマンス評価の対象になるべきではないですが、彼らを全体的なパフォーマンス管理プログラムの一部とすることは有益で、そのための効果的な方法もあります。
私たちは目的のはっきりしたパフォーマンス管理を推奨しています。そこには継続的なフィードバック、マネージャーとの信頼関係、従業員個人の自己啓発プランなど、より広範囲な行動やプロセスが含まれます。どんな業務を担当しているか、契約社員かそうでないかを問わず、万人向けのものです
と、マーキッシュ氏は述べています。
従業員に関して言えば、年間レビューや中間レビューではなく、異なる手法のパフォーマンス管理、たとえば定期的なチェックイン・ミーティングや、日常的な称賛の言葉がけを通して、継続的フィードバックを習慣化するというような方法が適切でしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
本記事が、PPMへの理解や契約社員のマネジメントに悩む方に取って参考になっていれば幸いです。
ハイマネージャーの提供する、6つのお役立ち資料はこちら
・・・
ハイマネージャー
OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。







