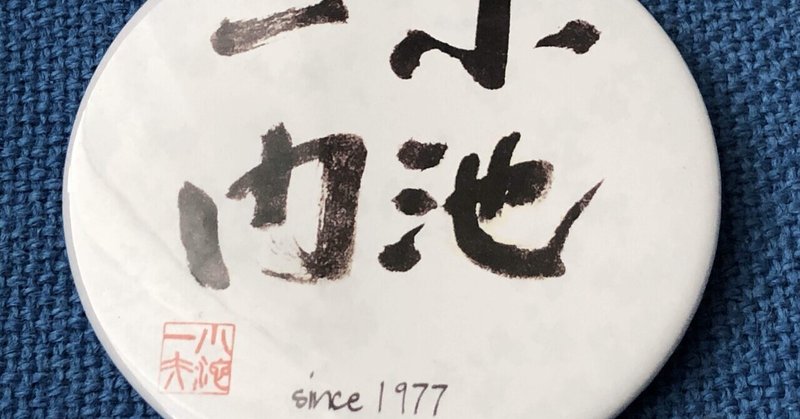
"キャラクターを起てろ!"劇画村塾第4期生 第3章〈2〉
<麻雀ができもしないのに麻雀劇画の連載を引き受ける〜小池一夫先生と石ノ森章太郎先生の言葉、そして狩撫麻礼先輩のラスタな説教>
相変わらず都立大学の安アパートで悪戦苦闘を続けていたが、ある日突然、
「『コミック劇画村塾』、残念ながら休刊!」
という話が飛び込んできた。
「え! マジ? なんてこった……」
大好きな作品も掲載されていたし、何よりも自分がデビューした雑誌だけに、ひじょうに残念だったが、”休刊”というやつはその当時もよくある話だったので、致し方なかった。
必然的に自分が原作を担当している『危(ヤバ)めのヴィーナ』も終了することになってしまった。
それでも単行本一冊分も書かせてもらったのだから、まったくのド素人から始めたデビュー作としては、幸運なほうだった。(すぐには単行本化されなかったが、後年、スタジオ・シップから社名変更になった小池書院より刊行された。ありがたい話です)
しかし……。
またしても無職に逆戻りである。
その頃には映画館のバイトも止めていたので、どうしようかと思った。
そこへ救いの手を差しのべてくださったのが、劇画村塾事務局のSさんと、小池先生のマネージャーのOさんだった。
「梶君、麻雀できる?」
SさんとOさんに訊かれた。
「それが……ぜんぜんできないんですよ」
正直に答えた。
大学生といえば麻雀、という風潮がまだ残っていた時代だったが、どういうわけか自分の周囲には麻雀をやる友人達がいなかった。そのせいもあって、牌に触ったことくらいはあったが、麻雀そのものは、ほとんどやったことがなかった。
ちなみに、麻雀劇画の名作を何本も書かれているだけあって、なおかつ若い頃はプロの雀士として食われていただけのことはあって、小池先生の麻雀の腕前は超一流だった。
一度、そのテクニックを見せてもらったことがあるが、牌の山の中から指先の感触だけで、望んだ牌を的確に取り出したり、手の甲の上で自在に牌を移動させたり、掌の内側に牌を隠してすり替えたりと、まるで手品を見るような指捌きだった。
そんな小池先生の薫陶もあってかどうか、マネージャーや社員の人達も、麻雀の腕ではかなりの猛者が揃っていた。
「まあ、できなくても何とかなるか」
Sさんが言い、
「麻雀シーンは専門のプロが作ってくれるから大丈夫だと思いますよ」
と、マネージャーのOさん。
「麻雀漫画の連載を、うちの伊賀一洋さんと組んでやってみない?」
「本当ですか!」
想像もしていなかったオファーだった。
完全無職の身にとっては、もちろん断ることなどできない。一も二もなく引き受けることにした。麻雀のことなど、何も知らないというのに……。
同時に、小池先生からも、
「原作者というのは、得手不得手はあるだろうが、勉強してでも、どんなジャンルでも書けないといけない」
と言われていたし、小学生時代から大ファンだった石ノ森章太郎先生も、
「好奇心のおもむくままに、どんな仕事でも面白がって受ける」
と、公言されていた。
二大巨頭のその言葉が頭にあったことも確かだ。
(ちなみに、小池一夫先生の師匠はさいとう・たかを先生、さいとう先生と石ノ森先生は兄弟みたいに仲が良かった関係から、小池先生にとって石ノ森先生は、いわゆる「"叔父貴"にあたるンだ」とよく聞かされていた)
Oさんが話してくれた通り、麻雀漫画の闘牌シーンは、作品の要となるため、プロの雀士の方が作ったり、監修していることがほとんどだった。
自分は、キャラクターとストーリーを担当すればいいということになった。
当時、スタジオ・シップに所属されていた漫画家の伊賀さんとは、夏合宿でちょっと顔を合わせた程度の中だったが、まったく知らないという仲でもない。
伊賀さんはバイク乗りだったので、大型バイクの後ろに乗せてもらって、さっそく竹書房の『近代麻雀オリジナル』編集部まで、二人で打ち合わせに出向いたことを覚えている。
そこで始めることになったのが、麻雀漫画『キャッシュハンター』である。
この作品に関しては、とにかく生活費がかかっていたので、食うために懸命にやった記憶が残っている。
同時に、なんとも贅沢な話だが、デビュー作と同じく、原稿料をもらいながら、原作修行を続けさせてもらっていたようなものだ。
まだまだ綱渡り状態ではあったが、何とかギリギリ、原稿料だけで食っていけるようにはなった。
ちょうどその頃だったと思うのだが……。
劇画村塾十周年記念のパーティで知り合った、たなか亜希夫先輩から飲みに誘われるようになった。
偶然にも、お互いのアパートが近かったということもある。
さらに、自分とほぼ同い年の本沢たつや氏(後に漫画家としてデビューし、狩撫先輩ともコンビを組む)がアシスタントでいて、ちょうどクッションのような役割も果たしてくれた。
たなか先輩は、まぎれもない天才漫画家だった。
たなか先輩のアパートに遊びに行って、ちょっとその仕事ぶりを見ただけでも、はっきりと分かった。
下書きもコマ割りもほとんどせず、いきなり、あのクオリティの漫画を描き出すのだ。
だが、御本人は、超然としているわけでもなく、偉ぶるわけでもなく、実にフランクに後輩の自分にも接してくれた。
二人とも、プロレスや格闘技が大好きという点でも話が合った。
本沢氏もまじえて、食事に行ったり呑みに行ったりの交友が始まった。
このあたりから、都立大学をベースにした、書いて、飲んで、食って、歌っての日々が続いていくことになる。
そのうち、たなか先輩が狩撫先輩と組んで、『週刊漫画サンデー』で連載を始めるという話が持ち上がった。
(おお! あの時実現しなかったゴールデンコンビがついに実現するのか!)
劇画村塾十周年記念パーティの夜の打ち合わせが思い出された。
両先輩の一ファンとしては、これは期待せずにはおれないニュースだった。
タイトルは『ルーズボイルド』と、いかにも狩撫先輩らしいタイトルだ。
たなか先輩の作画のペースを考えて、週刊連載ではなく、月一のシリーズ連載ではなかったかと思う。
そんなわけで、たなか先輩のところに遊びに行くと、たまに狩撫先輩が打ち合わせで来ていることがあった。
そんな時は、相応の覚悟を決める必要があった。
たなか先輩との打ち合わせが終わると、今度は自分に対して、ひとしきり説教が始まるからである。
今から考えると、先輩としてかなり貴重なアドバイスを次々としてくれていたのだが、ただの青二才でしかなかった当時の自分は、
(狩撫先輩のことはめちゃくちゃ尊敬してるけど、このくどい説教癖だけは何とかならないのかなあ……)
と、ひたすら嵐が通り過ぎるのを待っているだけだった。
場合によっては、たなか先輩のアパートの中だけでは終わらず、そのまま下北沢のスナックまで拉致されて、そこでも延々と説教が続くことがあった。
その場合は、必ずカラオケを歌わされた。そして、
「おまえの歌にはソウルがない。そんなことじゃ、いい原作は書けないぞ」
決まり文句で怒られ、さらに狩撫先輩の歌唱を聴いて解散、となるのが常だった。
狩撫先輩の歌は、言うだけあってプロのソウルシンガー顔負けの上手さだった。
歌い終わると、
「こういうふうに原作を書け」
そう言われるのだが、
(それってどんな風にだよ……)
ニュアンスは分からなくもないが、実際的にはまったく理解できないのだった。
そんな中で、またもや麻雀漫画の原作の依頼が舞い込んで来て、さらに続けて……!
〈続く〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
